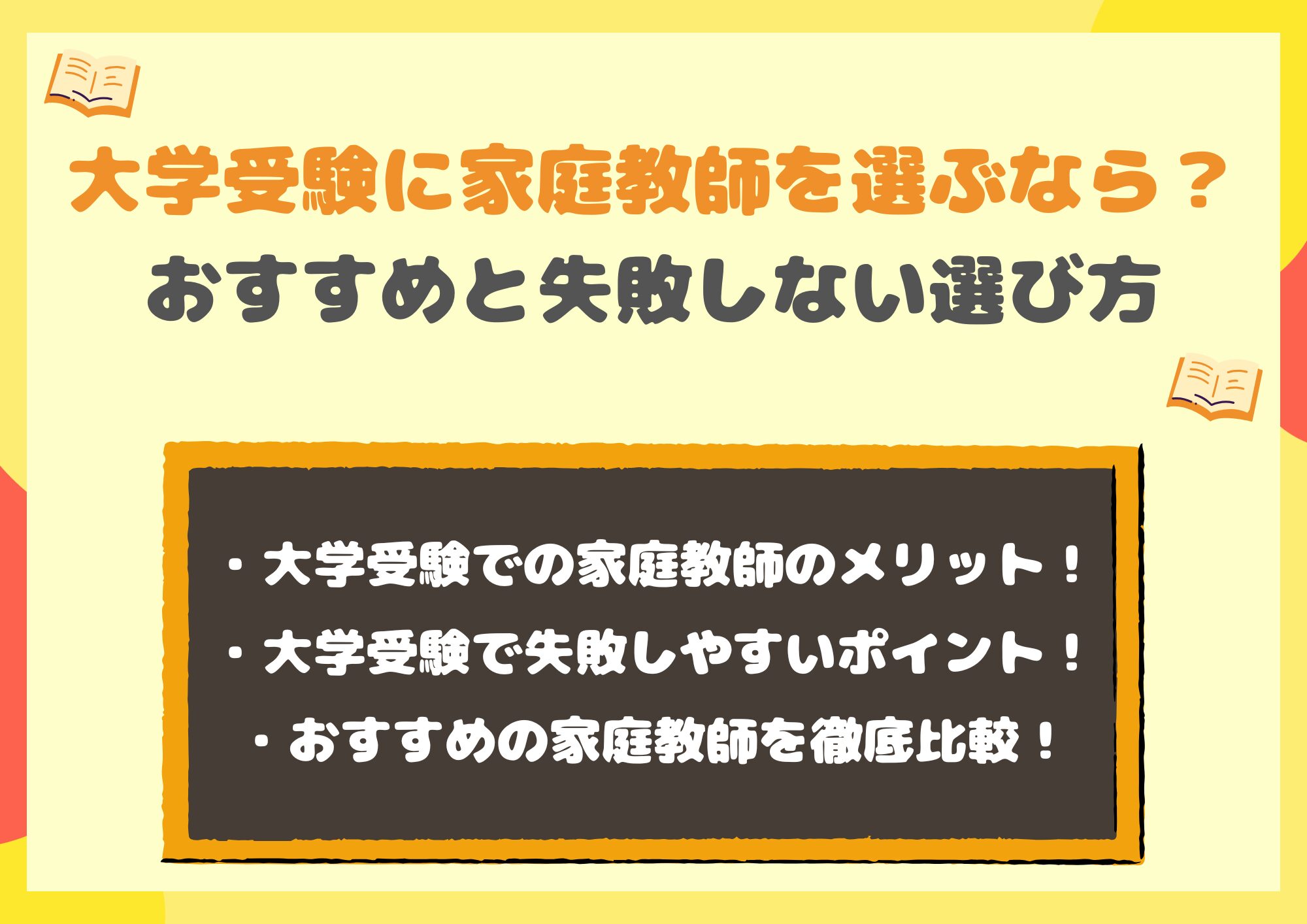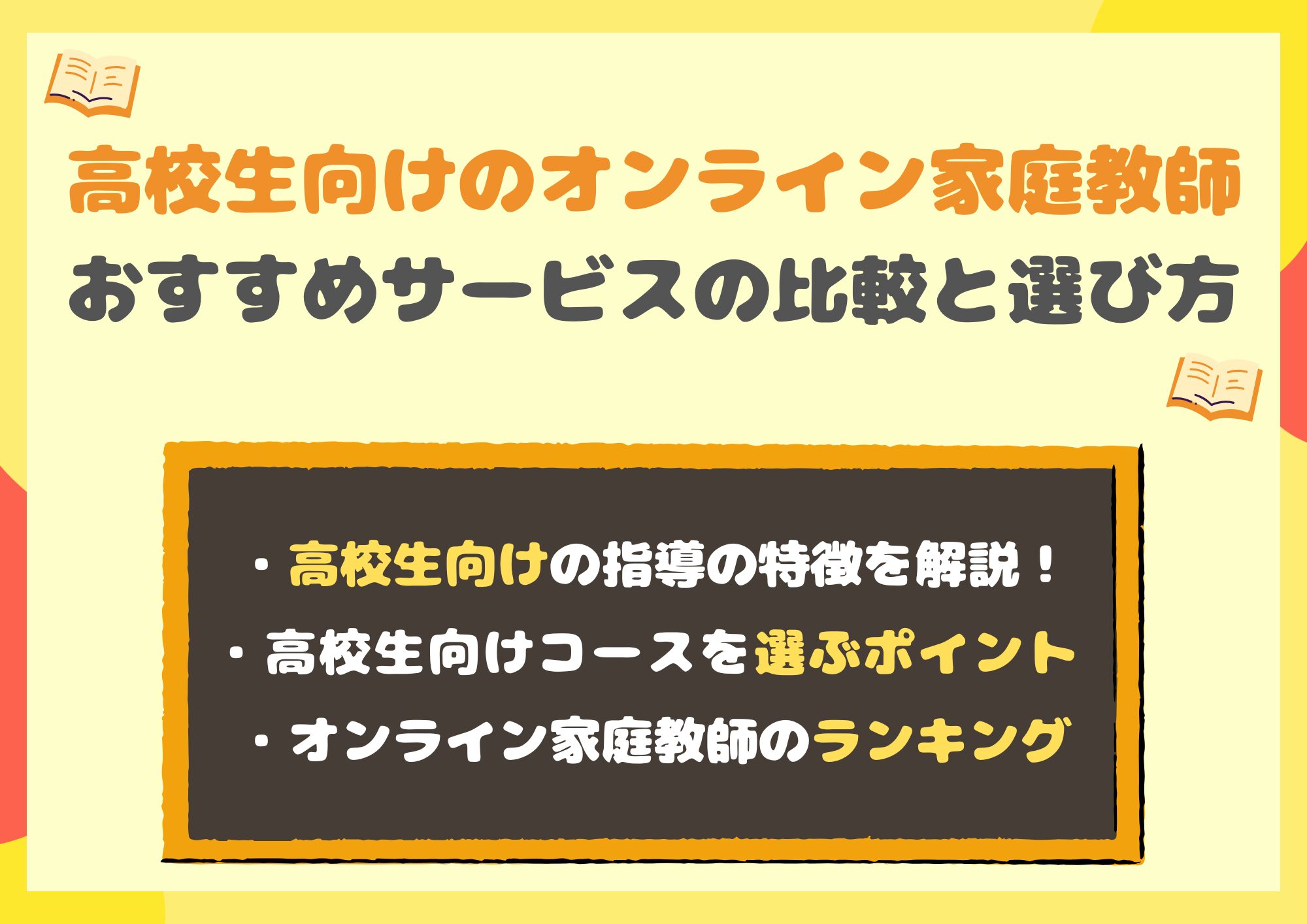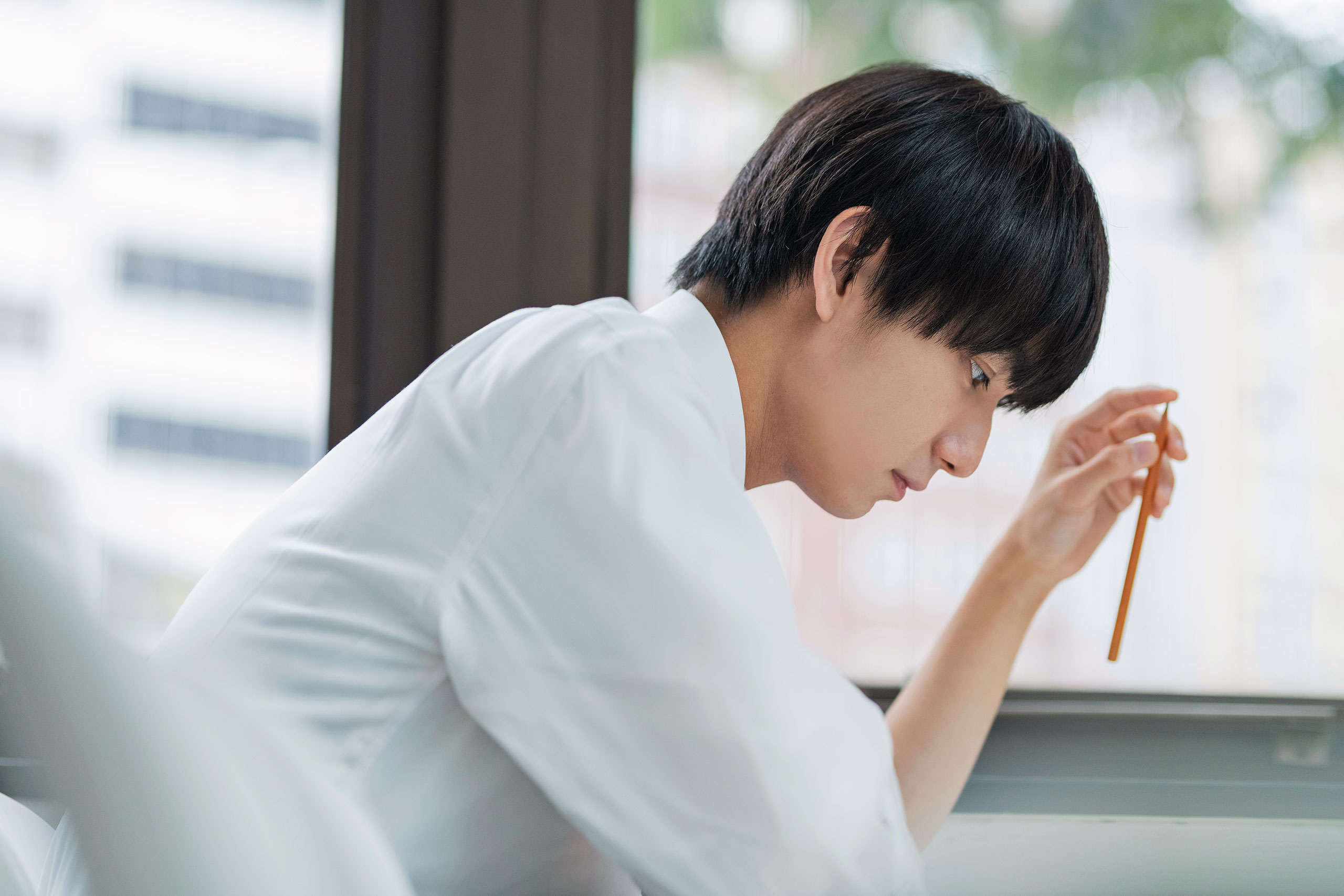- 高
高校生の不登校はやばい?親が今すぐできる対策と家庭教師活用法
2025.07.04

高校生のお子さんが不登校になると「本当にやばいのでは」と強い不安を抱えるご家庭は少なくありません。
実際、学年進級や進路選択への影響、将来の選択肢など心配ごとが次々と浮かんできますが、不登校は決して特別な問題ではありません。
全国では毎年約6.9万人(68,770人)の高校生が不登校になっており、多様なサポート制度と学び直しの選択肢が整っています。
本記事では「やばい」と感じる不安の正体を客観データや最新制度とともに解き明かし、今すぐ始められる具体的な行動と家庭教師サービスの活用方法まで、順を追って詳しく解説します。
目次
高校生の不登校がやばいと感じる理由と現状データ

高校生の不登校に直面した親御さんの多くは「このまま進級できないのでは」「進学や就職に大きな影響が出るのでは」といった危機感を抱えています。
背景には、不登校が中学生のとき以上に進路へ直結するタイミングで起きやすいという現実があります。
令和5年度の文部科学省統計では、高校不登校生は全国で68,770人、1,000人あたり23.5人と過去最多を更新しています。
これは決して珍しい出来事ではなく、社会全体で取り組むべき課題となっています。ここからは、なぜ「やばい」と感じるのか、その根拠をデータとともに明らかにします。
高校生の不登校の最新統計は増加傾向
- 高校生の不登校は年々増加傾向。
- 環境変化や人間関係が複雑に影響。
- 長期欠席が進路に直結しやすい。
近年、高校生の不登校は全国的に増加傾向にあります。
文部科学省の調査によると、2023年度には高校生不登校者数が68,770人に達し、前年よりも8,195人増加しています。
特に高校1年生の4月~5月や、進級・進学を控えたタイミングで増加が目立ち、これは環境変化や人間関係、学力不安など様々な要因が複合的に影響していることが要因です。
また、全体の約半数が「1か月以上の長期欠席」に該当し、学年末の進級判定や出席日数の不足が進路選択に直結しやすくなっています。こうしたデータを冷静に把握することで、不登校は「特別な出来事」ではなく、誰にでも起こりうる社会的な課題であると再認識できるでしょう。
不登校の「やばい」と言われる進級・進路への影響
- 出席日数不足や単位未取得で進級が厳しくなる。
- 補講や救済制度も各校で整備。
- 焦らず学校や担当者と相談を。
高校生が不登校になると、進級や卒業の可否、さらには大学進学や就職など将来への影響が強く懸念されます。
学校の多くは「出席日数不足」「単位未取得」により進級や卒業判定に厳しい基準を設けており、長期欠席が続くことで「留年」「自主退学」のリスクが現実味を帯びてきます。
しかし一方で、学校ごとに柔軟な対応や補講制度を設けているケースも増えており、すぐに将来が閉ざされるわけではありません。
親御さんが焦りすぎず、まずは担任や学年主任と現状を共有し、出席・単位の扱いや救済措置を丁寧に確認することが重要です。進路面での「やばい」を回避する具体策も必ず存在します。
高校生の不登校がもたらす精神面と生活面へのリスク
- 昼夜逆転や体調不良の悪循環。
- 孤立感・自己肯定感の低下。
- 家族や専門家との連携が重要。
不登校は単に「学校へ行けない」だけの問題ではなく、お子さん本人の心身や家庭環境にも大きな影響を及ぼします。
毎日が不規則になることで昼夜逆転や体調不良、自己肯定感の低下や孤立感が強まるなど、精神面・生活面での悪循環に陥りやすい状況が生まれます。
特に高校生は思春期のまっただ中にあり、「友人からの孤立」「家族との関係悪化」「将来への絶望感」など、精神的なリスクが深刻化しやすいタイミングです。
大人が危機感だけで動くと逆効果になる場合もあるため、まずは専門家やサポート機関と連携し、子どもの状況に合わせた対応を取ることが大切です。
高校生の不登校は本当に人生にとってやばいのか?
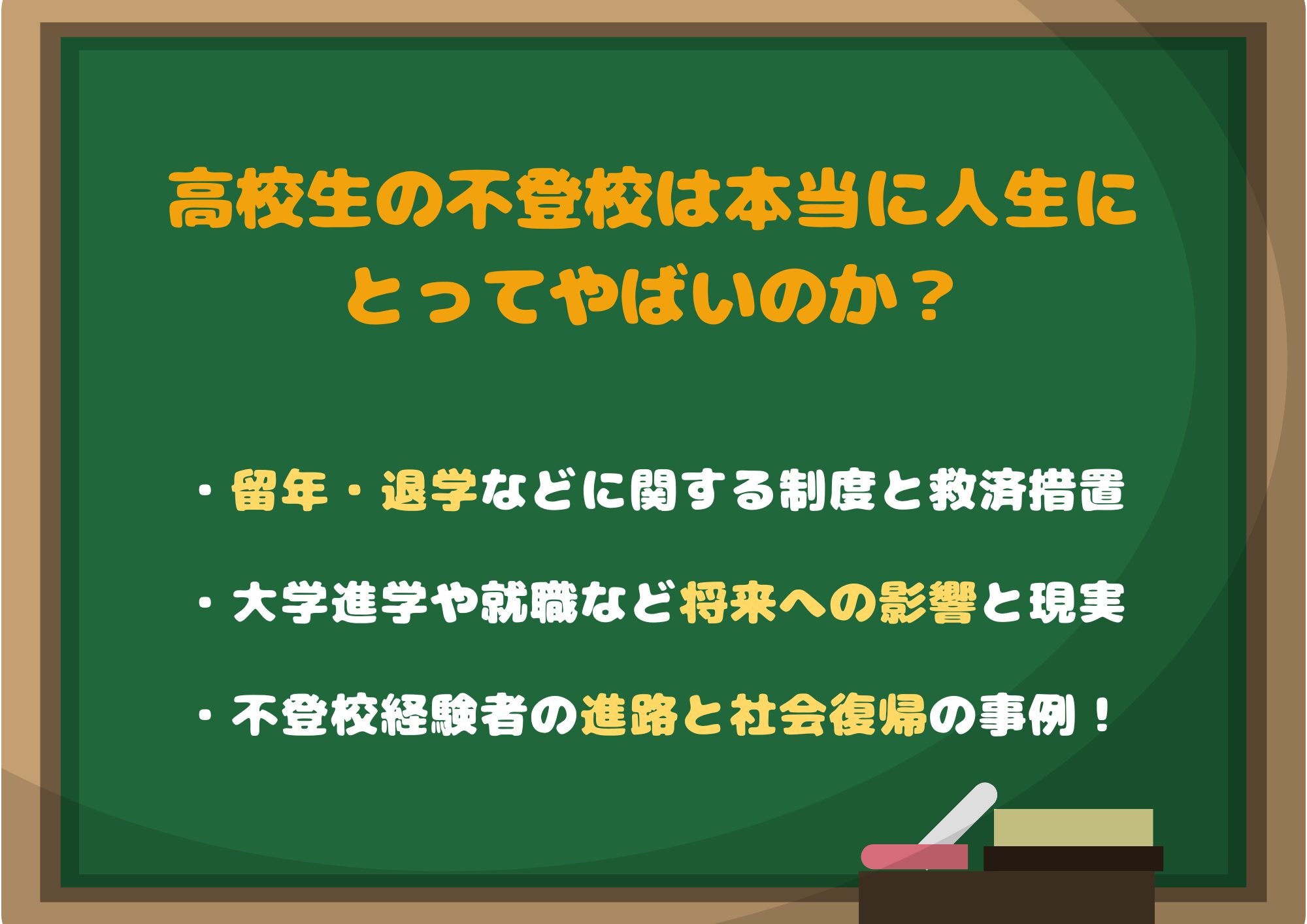
「高校生で不登校になったらもう人生が終わりなのか」と絶望してしまうご家庭もありますが、実際には救済制度や新しい学びのルートが多様化し、選択肢は大きく広がっています。
不登校は決して「人生の終わり」ではなく、正しい情報と支援を活用すれば希望ある未来を切り開くことができます。
ここでは、現在の制度や将来への影響、そして不登校を経験した先輩たちの進路事例まで、リアルな現実を解説します。
留年・退学・高卒資格取得に関する最新制度と救済措置
- 補講や追試で単位取得が可能な場合も。
- 通信制・サポート校への転校も選択肢。
- 高卒認定試験で進学資格を得られる。
高校生の不登校が長期化すると「このままでは留年や退学になってしまうのでは」と心配されますが、実際にはさまざまな救済制度が用意されています。
例えば、出席日数不足や単位未取得に対しては補講・追試・レポート提出などでカバーできる場合が増えてきました。
また、通信制高校やサポート校への転校・編入、高卒認定試験の利用など、従来とは異なる方法で高卒資格を得ることも現実的な選択肢です。
教育委員会や学校の進路指導担当者と相談しながら、柔軟なルートを探すことで「やばい状況」を大きく回避できます。
大学進学や就職など将来への影響と現実
- 高卒認定で大学・専門受験が可能。
- 通信制高校卒業で進学・就職も可能。
- 就職活動でも経験が強みに変わる。
「不登校だったら大学進学や就職ができないのでは」と将来を悲観してしまうケースも多いですが、現在は多様な進路制度が整備されています。
たとえば高卒認定試験の合格者は大学や専門学校を受験でき、通信制高校やサポート校で卒業資格を得た上で進学・就職する生徒も増えています。
就職活動でも「不登校=マイナス評価」という時代ではなくなり、履歴書の書き方や自己PR次第でポジティブな経験に変えるサポート体制も広がっています。
進学や就職の窓口は一つではなく、不登校を乗り越えた経験が「強み」になることも十分にありえます。
不登校経験者のリアルな進路と社会復帰事例
- 通信制・高卒認定から進学・就職。
- ITやクリエイティブ分野で活躍も。
- 「再スタートできる社会」になりつつある。
実際に不登校を経験した先輩たちの中には、通信制高校や高卒認定試験を経て大学へ進学し、充実した学生生活を送る人や、資格取得後に専門職へ就いた人も多くいます。
また、不登校をきっかけに自分の適性を見つけ、ITやデザイン、クリエイティブな分野で活躍している若者も目立ちます。
大切なのは「一度立ち止まっても、そこから再スタートできる社会」になっているということです。
不登校を経た人のインタビューや体験談から学び、自分やお子さんに合った道を柔軟に模索しましょう。
高校生の不登校を早期に見極めるチェックリストとセルフ診断
不登校が深刻化する前に、親子で現状を正しく見極めることが何よりも大切です。
「やばいサイン」を早期にキャッチし、適切な対応を取ることで、長期化や悪循環を防ぐことができます。
見逃しがちな兆候や家庭でできるセルフ診断の方法を知っておくと、より安心して一歩踏み出せます。
「やばい」サインを見逃さないためのチェックポイント
- 体調不良・昼夜逆転など生活リズムの乱れ。
- 友人・家族との会話減少、孤立感。
- 2週間以上続いたら専門機関へ相談。
不登校の兆候は突然現れるものではなく、徐々に現れてくる小さな変化の積み重ねです。
たとえば「朝になると強い頭痛や腹痛を訴える」「生活リズムが乱れ、昼夜逆転が続く」「スマホやゲームへの依存が強くなった」「友人や家族との会話が減った」などが目安となります。
こうした変化が2週間以上続く場合は、学校や専門機関への早めの相談を検討してください。
親御さんだけで抱え込まず、第三者の視点を取り入れることが早期解決の近道となります。
親子でできるセルフ診断と初期対応
- 対話で今の気持ちを共有する。
- 責めず、気持ちを受け止める姿勢。
- 悩みや体調を整理し、外部の支援も活用。
お子さんの変化に気付いたとき、親子で「今どう感じているか」「何が一番つらいか」を確認し合う対話を持つことが大切です。
責めたり焦らせたりするのではなく、まずは「学校に行かない選択も間違いではない」と気持ちを受け止めてあげましょう。
そのうえで体調や気分、悩みを書き出してみたり、メンタルチェック表を活用したりすることで、冷静に現状を整理できます。
セルフ診断とあわせて、地域の相談窓口やスクールカウンセラーへの連絡も検討し、早期サポートにつなげていきましょう。
高校生の不登校に対する具体的な選択肢とサポート制度
高校生が不登校になったとき、選択肢は「学校をやめるか残るか」だけではありません。
在籍校の支援・通信制高校・高卒認定試験・家庭教師・オンライン学習など、多様な制度やサービスを組み合わせて前向きな再スタートを切ることができます。
ここでは、それぞれの選択肢と具体的なサポート内容について分かりやすく紹介します。
在籍校・担任・スクールカウンセラーによるサポート
- 担任やカウンセラーとの連携が重要。
- 補講・特別課題・柔軟な出席認定がある。
- 個別に合わせた支援策が増えている。
不登校の悩みを抱えた際、まず頼れるのが在籍高校の担任や学年主任、スクールカウンセラーの存在です。
最近は学校現場でも不登校支援の体制強化が進み、定期的な面談・リモート課題提出・校内カウンセリングなど個別に合わせた支援策が用意されています。
単位取得の補講や特別課題、柔軟な出席認定など、学校ごとに多彩な救済措置があります。
まずは「現状を正確に伝えること」から始め、遠慮なく担任やスクールカウンセラーに現状と希望を相談しましょう。
通信制高校やサポート校への転校・編入という選択
- 全国に通信制高校200校以上。
- レポートやオンライン授業で柔軟に学べる。
- サポート校との併用で個別指導も充実。
近年、通信制高校やサポート校の人気は年々高まり、不登校経験のある生徒も安心して学べる環境が整っています。
全国には200校以上の通信制高校があり、レポート提出やオンライン授業が中心のため、体調や生活リズムに合わせて学習可能です。
サポート校を併用すれば、個別指導や進路相談、同世代との交流も充実しています。
実際に「転校して再スタートを切れた」「通信制で高卒資格を取得して大学進学できた」といった事例も多く、無理のない形で将来につなげられる柔軟な選択肢です。
高卒認定試験やフリースクールなど多様なルート
- 高卒認定で進学・就職の道を確保。
- フリースクールで社会性や生活力を養う。
- 「もう一つの道」として柔軟に検討。
「高校卒業資格」だけにこだわらず、高卒認定試験(旧大検)やフリースクールを活用して進学・就職を目指す道も注目されています。
高卒認定試験は年2回実施され、合格すれば大学や専門学校を受験できる権利が得られます。
フリースクールでは、学習だけでなく生活リズムや社会性を身につける多彩なプログラムが用意されており、不登校の子どもたちの「安心できる居場所」となっています。
こうしたルートも、今の自分に一番合った「もう一つの道」として検討できます。
家庭教師やオンライン学習の活用方法と効果
- 個別指導で学び直しやすい。
- 発達障害やメンタル配慮指導も可能。
- オンライン対応なら全国どこでもOK。
自宅で学習を継続したい場合や、学び直しへのモチベーションを高めたいときは家庭教師やオンライン家庭教師の利用が有効です。
家庭教師なら個別の状況に合わせて、無理なくペースを調整しながら基礎から丁寧に指導が受けられます。
特に「家庭教師のランナー」は、不登校や反抗期のお子さんへのサポート体制が業界でも上位レベルと評され、発達障害やメンタル面に配慮した指導も受けられるため安心です。
またオンライン型なら全国どこからでも希望する先生を選ぶことができ、時間や場所を選ばず効率的に学習習慣を取り戻せます。自宅学習が続かない、集団塾が合わないと感じたら、マンツーマン指導の家庭教師サービスはとても心強い味方になります。
高校生の不登校におすすめの家庭教師サービス比較
「自宅学習をサポートしたい」「勉強の遅れを取り戻したい」と考えたとき、どの家庭教師サービスを選べばよいか迷うご家庭は多いはずです。
不登校サポート・柔軟な学習ペース・親身なフォロー体制という観点から、代表的なサービスを比較紹介します。
不登校対応で最もおすすめな「家庭教師のランナー」

- 22年以上の実績を持つ大手グループ。
- 不登校・発達障害など専門サポートが充実。
- 兄弟同時指導・高額教材販売なしで安心。
家庭教師のランナーは「勉強が苦手な子専門」として22年以上の実績を持つ大手グループです。
特に不登校や反抗期、発達障害の子どもたちへの専門サポートが充実しており、一人ひとりの個性や心理的背景に寄り添ったオーダーメイド指導が特徴です。
指導料は小・中学生1コマ30分900円、高校生1コマ30分1,000円(いずれも税込)。
月額目安は指導回数や学年により異なるが、週1回60分指導の場合で約7,200円~。兄弟同時指導でも追加料金なし、高額テキスト販売も一切ありません。
オンライン対応・訪問対応のどちらも選べるので、全国どこでも利用でき、LINEでの相談や進路支援も万全。
親御さんからの満足度も非常に高く、「勉強だけでなくメンタル面もケアしてくれた」といった口コミが多く寄せられています。
学校復帰や進級・卒業を目指すご家庭には特におすすめのサービスです。
高校生不登校に強い家庭教師のトライの特徴

- 全国33万人超の講師ネットワーク。
- 不登校対応の専用カリキュラムあり。
- 講師交代が無料・オンライン指導も充実。
家庭教師のトライは全国33万人超の講師ネットワークを持ち、業界最大手の信頼感があります。
不登校・学習遅れ対応の専用カリキュラムを用意しており、専任教育プランナーが保護者と教師をつなぐ万全の体制です。
授業料は月18,000円~ですが、相性が合わなければ何度でも無料で講師交代できる点も安心です。
オンライン対応も充実しており、地方や離島でもトライの質の高い指導が受けられます。長年の受験ノウハウや都道府県ごとの進路データも強みとなっています。
学研の家庭教師のサポート内容

- 教育大手「学研」のノウハウが強み。
- 大学生からプロ講師まで幅広い指導陣。
- オンライン指導・進路相談も充実。
学研の家庭教師は、教育大手「学研グループ」が長年培ってきたノウハウを活かし、不登校や学習に不安を抱える高校生にも手厚いサポートを提供しています。
大学生からプロ講師まで幅広い講師が在籍しており、一人ひとりの性格や学習ペースに合わせた個別指導が強みです。
オンライン指導にも対応し、家庭と本部が連携した進路相談やメンタル面のフォローにも定評があります。
また、教科の枠にとらわれない柔軟なカリキュラム提案も特徴で、「勉強に自信が持てない」「生活リズムが崩れてしまった」など多様な課題に対して丁寧に寄り添ってくれます。
家庭教師サクシードによる不登校支援の取り組み

- 上場企業運営の安心感。
- 講師指名制・定期面談で個別サポート。
- 入会金・教材費不要、生活改善アドバイスも。
家庭教師サクシードは、上場企業が運営する安心感と講師の質の高さが特徴です。
不登校支援では、体験授業からそのまま正式指導に入れる「講師指名制」や、保護者との定期面談、きめ細かな学習計画サポートが評価されています。
入会金や教材費がかからず、オンラインでも対面でも同水準のサポート体制を整え、進路相談や生活習慣改善のアドバイスも受けられます。
「初めて家庭教師を利用する」「自宅学習が不安」という家庭でも始めやすいのが魅力です。
オンライン家庭教師Wamの強みと活用法

- 全国どこでも低価格で受講可能。
- 東大生など高学歴講師が多数在籍。
- 生活リズムの再構築や追加授業にも対応。
オンライン家庭教師Wamは、全国どこからでも低価格でマンツーマン指導が受けられるサービスです。
独自のオンラインシステムにより、板書共有やリアルタイム質問など教室同等のクオリティで指導を実現しています。
東大生など高学歴講師が多数在籍し、苦手科目の克服や生活リズムの再構築をサポートしてくれるのが大きな特徴です。
部活や通院、体調に合わせて時間調整がしやすく、「登校できない間だけ利用したい」「必要なときだけ追加授業したい」といったニーズにも柔軟に対応しています。
親が知っておきたい高校生不登校のサポート窓口と相談先
不登校の悩みを一人で抱える必要はありません。
公的機関や専門の相談窓口、民間のコミュニティを活用することで、情報やサポートを得られるだけでなく、親自身の孤立感や不安も和らげることができます。
どこに相談すればよいか、主な相談先を知っておくだけでも心の負担が大きく軽くなります。
自治体・教育委員会・相談窓口の活用方法
- 自治体や教育委員会に専門相談窓口あり。
- 電話・窓口・オンライン相談が利用可能。
- 進路・家庭・メンタル面まで幅広く対応。
各自治体や都道府県の教育委員会には、不登校や学習困難の相談窓口が設けられています。
電話や窓口面談、オンライン相談など複数の方法があり、専門の相談員が対応してくれます。
「子ども相談室」「教育相談センター」など名称は地域ごとに異なりますが、進路や家庭環境、メンタル面のサポートまで幅広く相談可能です。
地域によっては保健師やスクールカウンセラーとの連携体制も強化されているため、早めに利用してみることをおすすめします。
民間団体やオンラインコミュニティの利用方法
- NPOや一般社団法人などの支援団体が充実。
- オンライン掲示板やLINEグループも活用。
- 悩みを分かち合い安心感が生まれる。
公的機関以外にも、NPOや一般社団法人など民間団体によるサポートやオンラインコミュニティが全国各地に増えています。
同じ悩みを持つ保護者や先輩ママ・パパとつながれるオンライン掲示板、LINEグループ、Zoom相談会なども活用できます。
「ひとりじゃない」と感じられるだけで心理的な安心感が生まれ、家庭での対応にもゆとりが生まれます。
民間の不登校専門相談や家庭教師サービスの無料カウンセリングを利用するのも有効です。
カウンセリングやメンタルサポートのポイント
- 臨床心理士や公認心理師のサポートを活用。
- 学校・自治体・外部クリニックが選択肢。
- 「話すだけで気持ちが軽くなった」などの効果も。
お子さんの心のケアや家族関係の改善には、臨床心理士や公認心理師など専門家によるカウンセリングが大きな助けになります。
自治体や学校の無料カウンセリングだけでなく、必要に応じて外部クリニックやオンラインカウンセリングも選択肢に加えましょう。
「話すだけで気持ちが軽くなった」「第三者の意見で前向きになれた」という保護者の声も多く、メンタルケアを遠慮なく活用することが大切です。
家族全体でサポートし合う姿勢を大切にし、孤立を防ぐことが解決への第一歩となります。
高校生の不登校で「やばい」と悩む親が今すぐできる3つの行動
お子さんの不登校に直面し「何をどうすればいいかわからない」と感じている親御さんは少なくありません。
ですが、今すぐ始められる行動を一歩ずつ積み重ねることで、状況を大きく変えることができます。
家庭でできるコミュニケーションの見直しからプロへの相談、学習サポートの導入まで、すぐ行動できる具体策を紹介します。
家庭内コミュニケーションの見直し
- 安心できる家庭環境づくりが大切。
- 無理に解決を急がず寄り添う声かけを。
- 家族で過ごす時間がヒントになることも。
まず大切なのは、焦りや怒りをお子さんにぶつけず「安心できる家庭環境」を作ることです。
「今日はどうだった?」「つらいときは休んでいいよ」など、無理に解決を急がず寄り添う声かけを意識しましょう。
お子さん自身が「家族は味方」と思えることが、次の一歩を踏み出す原動力になります。
家族で一緒に過ごす時間や、ちょっとした雑談の中からヒントが見つかることも多いものです。
プロに相談して現状を整理する
- 親だけで抱え込まず第三者に相談。
- 教育相談窓口・スクールカウンセラーなどを活用。
- 相談することで新たな視点が得られる。
親だけで抱え込まず、学校や自治体、専門家など第三者に早めに相談しましょう。
スクールカウンセラーや教育委員会の相談窓口、民間の家庭教師サービスの無料カウンセリングも気軽に活用できます。
誰かに話すだけでも不安やモヤモヤが整理され、新たな視点や具体的なアドバイスが得られることが多いです。
「どこに相談すればよいかわからない」という場合は、まず自治体の教育相談窓口からスタートしてみてください。
すぐに始められる学習サポートの導入
- 自宅学習のペースづくりで自信回復。
- 家庭教師やオンライン指導で柔軟に対応。
- メンタル面への配慮指導も安心。
学校に戻ることだけが「正解」ではありません。
自宅で学習のペースをつくることで、お子さんの自信回復や将来の選択肢が広がります。
家庭教師やオンライン家庭教師を活用すれば、子どもの状況に合わせて柔軟に学習を再開でき、生活リズムの立て直しや苦手克服も目指せます。
特に「家庭教師のランナー」なら、発達障害やメンタル面に特化したカウンセラーが在籍し、無理なく学び直しができるので安心です。
高校生の不登校やばい状況についてまとめ
- 高校生の不登校は全国で約6.9万人と決して珍しくない。
- 進級や進路への不安はあるが、補講・通信制高校・高卒認定など多様な救済策が用意されている。
- 家庭教師やオンライン学習、公的・民間の相談窓口の活用で新しい学び直しの道を切り拓ける。
- 大切なのは、焦らず一歩ずつできることから始めること。
- 家庭や社会の支援制度を活用して前向きな再スタートが可能。
高校生の不登校は「やばい」と感じる場面が多いものですが、社会全体で支援制度や選択肢が大きく拡がっています。
今は在籍校や通信制高校、高卒認定試験、家庭教師やオンライン学習など、一人ひとりに合った多様な学び直しのルートが用意されています。
大切なのは、「取り返しがつかない」ではなく「今すぐ動けば、未来はいくらでも切り拓ける」という事実です。
家庭内のコミュニケーションを見直し、必要に応じて第三者やプロの力を借りながら、一歩ずつできることから始めてみてください。
家庭教師のランナーをはじめとした学習サポートサービスや、公的・民間の相談窓口も遠慮なく活用しましょう。
親御さん自身も決して孤立せず、悩みや不安を分かち合いながら、お子さんと一緒に「前に進む選択」を見つけていくことが大切です。