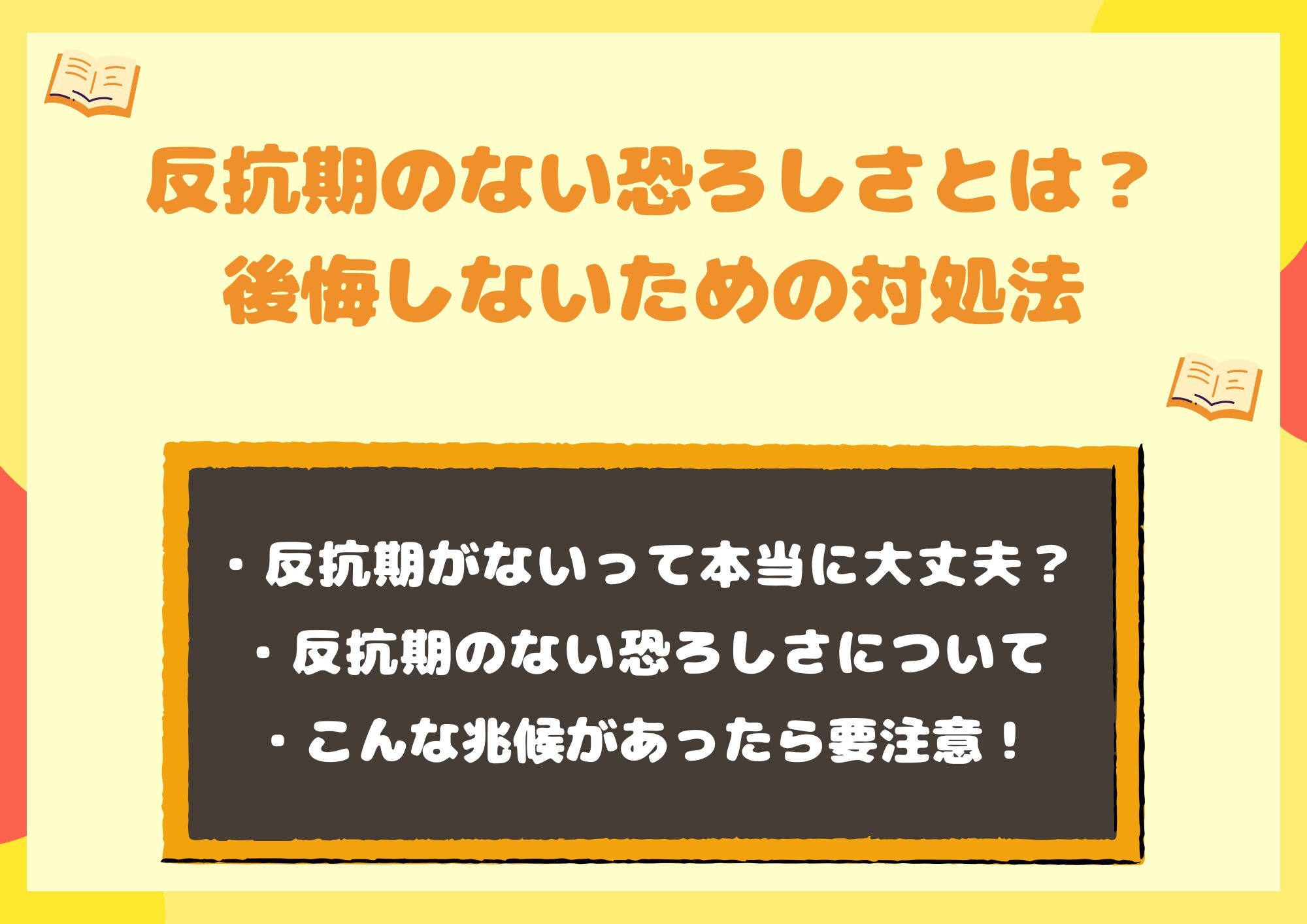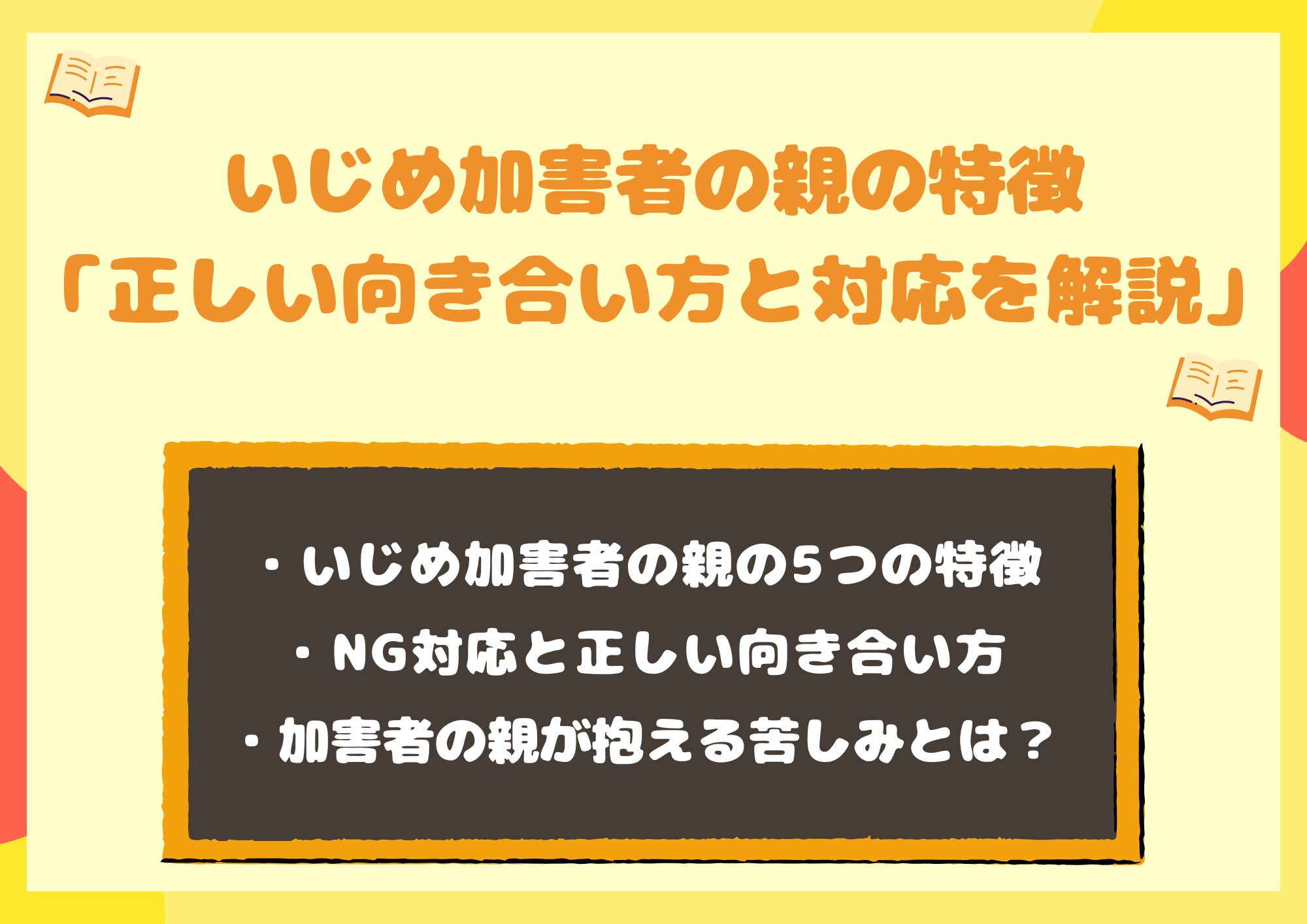- 中
私立高校無償化はずるい?不公平と言われる4つの理由と2026年改正
2025.11.08

私立高校の無償化について「ずるい」「不公平だ」という声を耳にして、複雑な気持ちになっていませんか?
この記事では、なぜそう言われるのか、制度の仕組みから2026年度の改正内容まで分かりやすく整理してお伝えします。
読み終わる頃には、ご家庭の状況に合わせた判断ができるようになりますので、ぜひ最後までお付き合いくださいね。
目次
私立高校無償化が「ずるい」と言われるのはなぜ?
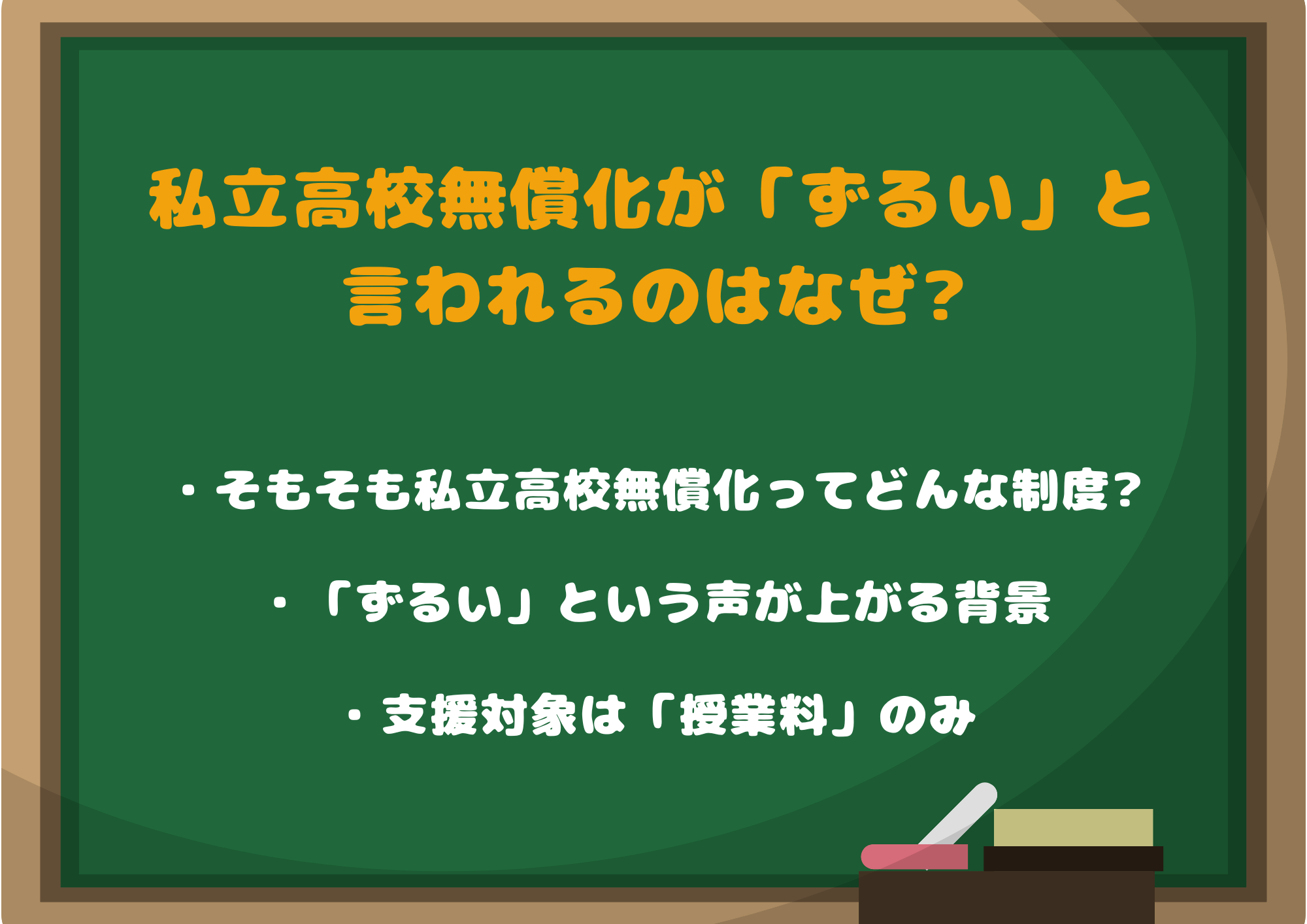
- 制度設計の構造的な問題が「ずるい」という声を生んでいる
- 所得制限の設定方法や地域間の格差が主な要因
- 「無償化」という呼び方による誤解も大きい
私立高校無償化に対して「ずるい」という声が上がる背景には、制度設計そのものに潜む構造的な問題があります。
単なる個人の不満ではなく、所得制限の設定方法や地域間の格差、制度の呼び方による誤解など、複数の要因が絡み合っているんです。
まずは制度の基本と「ずるい」と言われる背景を整理していきましょう。
そもそも私立高校無償化ってどんな制度?
- 正式名称は「高等学校等就学支援金制度」
- 2010年度にスタートし段階的に拡充されてきた
- 支援対象は「授業料」のみで入学金や施設費は対象外
私立高校無償化とは、正式には「高等学校等就学支援金制度」と呼ばれる国の支援制度です。
家庭の経済状況に関わらず、すべての子どもが高校教育を受けられるよう、授業料の一部または全部を国が支援するものなんです。
2010年度のスタート当初は公立高校の授業料が無償化され、私立高校には年額約12万円の支援が行われていました。その後、2020年には年収約590万円未満(目安)の世帯への支援が拡充され、2025年度には「高校生等臨時支援金」が創設されました。
そして2026年度からは所得制限が撤廃され、支給上限額も年額45万7,200円に引き上げられる予定です。
ただし、この支援はあくまで「授業料」が対象で、入学金や施設費、教科書代などは対象外なので注意が必要です。
「ずるい」という声が上がる4つの理由
- 年収910万円(目安)という所得制限による「崖」の存在
- 東京都と他の自治体との大きな支援額の差
- 「無償化」という言葉が生む誤解と実際の負担
- 公立高校を選んだ家庭が感じる不公平感
「ずるい」という声が上がる背景には、主に4つの構造的な要因があります。
1つ目は、年収約910万円(目安)という所得制限による「崖」の存在です。なお、実際の判定は年収ではなく住民税の課税標準額等をもとに計算されます。2024年度までは、この基準を超えると支援が受けられなくなっていました。
2つ目は、地域による支援額の大きな差です。東京都は独自に所得制限を撤廃して手厚い支援を行っていますが、他の多くの自治体では国の制度だけに頼っているため、住んでいる場所で受けられる支援に格差が生まれています。
3つ目は、「無償化」という言葉が生む誤解です。実際には授業料のみが対象で、入学金や施設費などで初年度に数十万円の負担が発生するケースが多いんです。
そして4つ目は、公立高校を選んだ家庭からの「なぜ私立だけ優遇されるのか」という声。これらの要因が重なり合って、多くの方が「不公平だ」「ずるい」と感じる状況が生まれているんですね。
私立高校無償化が不公平と感じられる具体的な理由
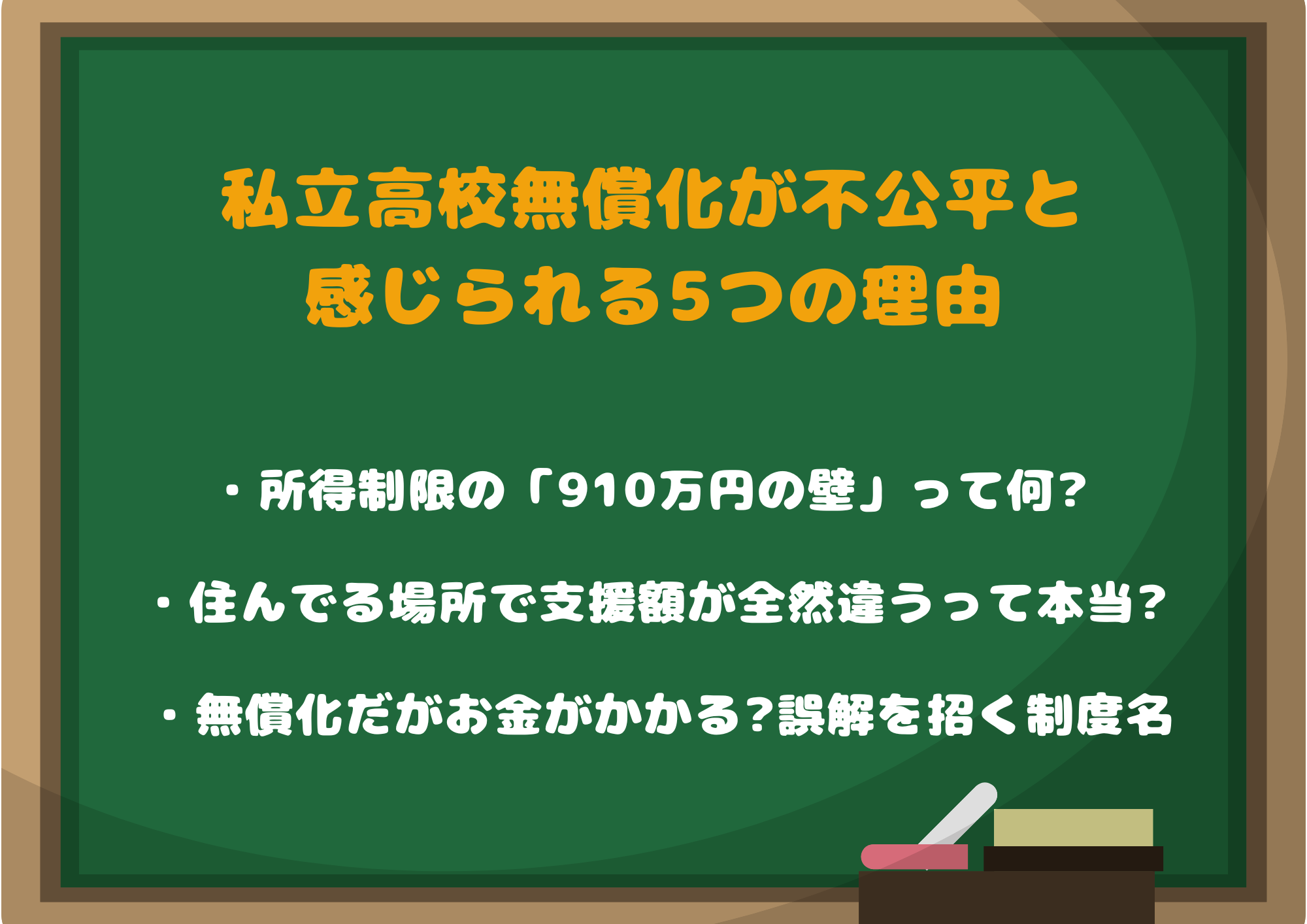
- 所得制限の「910万円の壁」で支援の有無が大きく変わる
- 住んでいる都道府県によって支援額が著しく異なる
- 「無償化」という呼称と実際の負担にギャップがある
ここからは、特に多くの方が「ずるい」と感じる理由について具体的に見ていきましょう。
制度の仕組みを正しく理解することで、お子さんの進路選択に役立てていただければと思います。
所得制限の「910万円の壁」が生む問題
- 年収がちょっと超えるだけで支援額が大きく変わっていた
- 2025年度は臨時措置で全世帯に基準額を支給
所得制限の「910万円の壁」とは、世帯年収約910万円(目安)を境に支援の有無が大きく変わる仕組みのことです。
2024年度までの制度では、この基準を超えると支援が受けられなくなっていました。例えば年収900万円(目安)の家庭は年額11万8,800円の支援を受けられますが、基準を超えると支援がゼロになる状況だったんです。
収入が少し増えただけで、逆に負担が増えるという矛盾が生じていました。
2025年度は臨時措置として、年収約910万円以上の世帯にも年額11万8,800円相当の支援が行われています。ただし、私立高校向けの加算部分は従来どおり所得による差があります。
2026年度からは所得制限が撤廃されるため、この「910万円の壁」問題は解消される見込みです。
住んでる場所で支援額がこんなに違う!
- 東京都は所得制限なしで手厚い支援を実施
- 他の地域は国の制度が基本で支援額に大きな開き
私立高校無償化の支援額は、住んでいる都道府県によって大きく異なります。
東京都は2024年度から、都独自の制度で所得制限を完全に撤廃しました。国の支援金と都の助成金を合わせた上限額は年度ごとに設定されており、令和6年度は48万4,000円となっています。これは都内私立高校の平均授業料をほぼカバーする金額です。
一方、東京都以外の多くの地域では、国の制度が基本となります。大阪府や神奈川県も独自の上乗せ支援を行っていますが、東京都ほどの手厚さはありません。
大阪府は国に対して、私学助成は本来国が責任を持つべきであり、自治体の財政力によって地域間格差が生じるのは問題だとする意見書を提出しています。
同じ日本に住んでいるのに、引っ越し先によって支援額が大きく変わるというのは、確かに不公平に感じますよね。
「無償化」なのにお金がかかる?
- 支援対象は授業料のみ
- 入学金・施設費・教材費などは自己負担
「無償化」という言葉から、多くの方が「お金がかからない」と誤解しがちです。
高等学校等就学支援金制度の支援対象は、厳密には「授業料」だけなんです。入学金、施設整備費、教科書代、制服代、修学旅行費などは一切含まれません。
東京都の令和7年度調査によると、都内私立高校(全日制)の初年度納付金の平均は約98.7万円。その内訳は、授業料約50万円、入学金約25.4万円、施設費約3.6万円、その他約19.7万円となっています。
都の上限額まで支援を受けても、入学金や施設費等で数十万円の自己負担が必要になることが多いんです。
学校によって金額には幅がありますので、志望校の費用を事前に確認しておきましょう。
公立高校を選んだ人が感じる不公平感
- 節約のために公立を選んだのに私立の方が得だった?
- 努力して公立に入った人の複雑な心境
私立高校への支援が手厚くなる一方で、公立高校を選んだ家庭からは不満の声も上がっています。
家計を考えて公立高校を選択した家庭にとって、私立高校の支援拡充は複雑な心境を生みます。特に東京都のように授業料負担が大きく軽減される地域では、「無理して公立に入れる必要はなかった」と感じる保護者もいるんです。
また、受験勉強を頑張って公立高校に合格した生徒や保護者にとっても、私立への支援拡充は釈然としない面があります。「頑張って公立に入ったのに、私立に行った方が選択肢が広がったかもしれない」という思いを抱く方もいるでしょう。
この感情は、制度そのものへの不信感につながることもあります。
2026年度からの制度改正|所得制限撤廃で何が変わる?
- 2026年度から所得制限が完全撤廃される
- 私立高校への支給上限額が45万7,200円に引き上げ
- それでも残る課題がある
2026年度からは、私立高校無償化の制度が大きく変わります。
自民党、公明党、日本維新の会の3党合意により、所得制限の撤廃と支給上限額の引き上げが決定しました。具体的な変更内容と残される課題について解説します。
所得制限撤廃と支援額引き上げの内容
- 全世帯が支援対象に
- 支給上限額は年額45万7,200円に
2026年度からは、世帯年収に関係なくすべての家庭が支援対象になります。
これまで年収約910万円(目安)以上の世帯は支援対象外でしたが(2025年度は臨時措置あり)、2026年度からは所得制限が撤廃され、どの世帯でも授業料支援を受けられるようになります。
さらに、私立高校への支給上限額も現在の39万6,000円から45万7,200円に引き上げられる予定です。この金額は私立高校の授業料の全国平均相当額で、授業料が全国平均以下の私立高校であれば、実質的に授業料の自己負担が大きく軽減される計算です。
東京都が先行して実施してきた「所得制限なしモデル」が、全国に広がる形になりますね。
それでも残る3つの課題
- 授業料以外の費用は依然として自己負担
- 授業料が全国平均を超える学校は差額負担が発生
- 財源確保の問題
所得制限の撤廃は大きな前進ですが、すべての問題が解決するわけではありません。
まず、支援の対象はあくまで「授業料」のみという点は変わりません。入学金、施設費、教科書代、制服代などは引き続き自己負担となるため、初年度には数十万円の費用が必要です。
また、授業料が全国平均の45万7,200円を超える学校に通う場合は、差額分が自己負担となります。
さらに、高所得者層まで含めて全世帯に支援を行うことで、追加財源が必要になります。報道によると、2026年度は4,000〜6,000億円規模の予算が見込まれています。
制度が拡充されても「完全無償」にはならないことを理解した上で、お子さんの進路を考えることが大切です。
実際にいくらもらえる?所得別・地域別の支援額
- 所得別に受けられる支援額が異なる
- 都道府県独自の上乗せ支援も存在する
ここからは、具体的な支援額について詳しく見ていきましょう。
お子さんの進路を考える上で、自分の家庭がどれくらいの支援を受けられるかを把握しておくことは重要です。
所得別の支援額一覧
- 年収590万円未満(目安)なら最大39万6,000円(2025年度まで)
- 年収590〜910万円未満(目安)は11万8,800円
- 2026年度からは全世帯で最大45万7,200円
支援額は世帯年収によって大きく異なります。なお、実際の判定は年収ではなく住民税の課税標準額等をもとに計算されます。
2025年度までの制度では、世帯年収が約590万円未満(目安)の家庭は最大年額39万6,000円、年収約590万円から910万円未満(目安)の家庭は年額11万8,800円が支給されます。
2025年度に創設された「高校生等臨時支援金」により、年収910万円以上(目安)の世帯にも年額11万8,800円相当が支給されるようになりました。
2026年度からは所得制限が撤廃され、全世帯で年額45万7,200円を上限に支援が受けられる予定です。
私立高校の授業料が年間50万円程度であれば、自己負担は約4〜5万円程度まで軽減される計算になります。
都道府県独自の上乗せ支援
- 東京都は所得制限なしで手厚い支援
- 大阪府・神奈川県なども独自支援あり
多くの都道府県が国の制度に加えて独自の上乗せ支援を実施しています。
東京都は全国で最も手厚い支援を行っており、2024年度から所得制限を完全撤廃。国の支援金と都の助成金を合わせた上限額は、令和6年度で48万4,000円となっています(上限額は年度ごとに設定)。
大阪府は2024年度から段階的に所得制限を撤廃しており、2026年度には全学年で無償化される予定です。神奈川県は年収約750万円未満(目安)の世帯に、国と県の支援を合わせて最大46万8,000円を支給しています。
各自治体の財政状況によって支援内容に差があるため、お住まいの地域の最新情報を確認することをおすすめします。なお、自治体の上乗せ支援には保護者・生徒の居住要件があることが多い点にご注意ください。
申請漏れに注意!知っておきたい制度のポイント
- 申請しないと支援は受けられない
- 教科書代や制服代は対象外
私立高校無償化の制度には、知らないと損をするポイントがあります。特に注意すべき点を詳しく解説していきます。
申請しないと支援は受けられない!
- 入学時と毎年の更新時に申請が必要
- 申請漏れを防ぐポイント
私立高校無償化の支援を受けるには、必ず申請手続きが必要です。
申請は入学時と毎年の更新時に、在学する学校を通じて行います。時期は学校の案内に従ってください(原則、申請月から支給開始となります)。多くの場合、オンライン申請システム「e-Shien」を利用します。
申請漏れを防ぐために、学校からの案内プリントは必ず保管し、申請期限をカレンダーに書き込んでおきましょう。
新入生の場合、申請が遅れると申請月以降しか支給されないため、入学時の申請を逃すと大きな損失になります。
在校生も毎年の届出を忘れると、以降の支給がストップしてしまうので注意が必要です。
授業料以外の費用はどうなる?
- 無償化の対象外になる費用一覧
- 奨学給付金など別の支援制度も活用しよう
「無償化」と聞いて、すべての費用が無料になると思っている方も多いのではないでしょうか。
高等学校等就学支援金の対象は授業料のみで、それ以外の費用は基本的に自己負担です。入学金、施設整備費、教育充実費、教科書代、副教材費、制服代、体操服代、上履き、通学鞄、修学旅行費、部活動費など、実に多くの費用が対象外なんです。
ただし、授業料以外の費用についても別の支援制度が用意されています。「高校生等奨学給付金」は、住民税非課税世帯や生活保護受給世帯を対象に、教科書代や教材費、修学旅行費などを支援する制度です。
年額で数万円から十数万円の給付が受けられる場合があるので、該当する方はぜひ活用してください。
私立高校無償化についてよくある質問
- 通学する地域と住んでる地域、どっちの制度が適用される?
- 共働きの場合、所得はどう計算するの?
- 年度途中で転校したらどうなる?
- 私立高校と公立高校、結局どちらを選ぶべき?
私立高校無償化の制度について、多くの方から寄せられる質問をまとめました。
通学する地域と住んでる地域、どっちの制度が適用される?
国の就学支援金は、学校の所在地に関係なく対象になります。
一方、都道府県独自の上乗せ支援には、保護者・生徒が都道府県内に在住しているなどの居住要件があることが多いです。
例えば神奈川県に住んでいて東京都の私立高校に通う場合、国の就学支援金は受けられますが、東京都独自の上乗せ助成は受けられません。逆に神奈川県の独自制度があれば、そちらを利用することになります。詳しくは、お住まいの自治体と学校に確認してください。
共働きの場合、所得はどう計算するの?
共働きの場合は、夫婦の所得を合算して判定します。
具体的には、両親の「課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額」を合計した金額で判定されるんです。年収ではなく課税標準額で計算するため、控除が多い家庭は実際の年収より低く判定される場合があります。
マイナンバーを使って申請すれば、自動的に計算されるので安心です。
年度途中で転校したらどうなる?
年度途中で転校した場合でも、引き続き支援を受けることができます。
ただし転校先の学校で改めて申請手続きが必要です。転校のタイミングによって支援額が月割り計算される場合もあるので、詳細は転校先の学校に確認しましょう。
また引っ越しによって住民票の都道府県が変わった場合、その自治体の独自支援制度に切り替わることがあります。
私立高校と公立高校、結局どちらを選ぶべき?
どちらが正解ということはなく、お子さんの希望や学力、ご家庭の状況に合わせて選ぶことが大切です。
私立高校は独自のカリキュラムや設備、部活動などの特色があり、2026年度からは無償化も進みます。一方、公立高校は授業料が安く、地域に根ざした教育が受けられるメリットがあります。
大切なのは、お子さんがどんな高校生活を送りたいか、将来どんな進路を考えているかを一緒に話し合うことです。学力面で不安がある場合は、早めの対策で選択肢を広げることもできます。
お子さんの学習面でお悩みがある場合は、「勉強しない中学生の末路は?理由や親ができるサポートも解説」も参考にしてみてください。
私立高校進学に向けて今から始める学力対策
- 私立高校の入試は早めの対策が重要
- 内申点対策と入試対策の両立がカギ
- 家庭教師を活用した効率的な受験準備
私立高校の無償化制度を理解したところで、次に考えたいのが学力対策です。
制度がどれだけ充実しても、お子さんが志望校に合格できなければ意味がありません。ここでは、私立高校進学に向けて今から始められる学力対策についてお伝えします。
早めの対策で広がる選択肢
私立高校の入試は、学校によって出題傾向や難易度が大きく異なります。
公立高校と比べて独自問題を出す学校も多く、早めの対策が合格への近道です。特に内申点対策は中学1年生から始めることで、3年間トータルでの評価を高められます。
ランナーでは2024年、第一志望校への合格率97.5%を達成しました。無償化で選択肢が広がった今こそ、早めの対策がお子さんの可能性を広げます。
内申点の重要性については、「内申点どこから高い?中学生が知っておくべき評価基準と成績アップの方法」で詳しく解説しています。お子さんの現在の成績と照らし合わせながら、早めの対策を始めてみてはいかがでしょうか。
家庭教師で効率的に高校受験対策を始めよう
高校受験を控えたお子さんにとって、内申点対策と学力向上の両立は大きな課題です。
塾では集団授業が中心となるため、お子さん一人ひとりの苦手分野に合わせた対策が難しいこともあります。その点、家庭教師なら学校の進度や定期テストの傾向に合わせて、オーダーメイドの指導が可能です。
特に私立高校の独自入試対策では、志望校に合わせた個別指導が大きな効果を発揮します。
家庭教師のランナーでは、これまで30,034人のお子さんを指導してきました。その中には「無償化で私立も視野に入ったけど、学力が心配」というご家庭も多くいらっしゃいます。
高校受験対策に特化した「中学生コース」では、勉強が苦手なお子さんでも、一人ひとりのペースに合わせた指導で着実に力をつけていけます。受験勉強に必要な時間の目安は「高校受験に向けた勉強時間はどれくらい必要?」を参考にしてください。
お子さんの高校進学でお悩みの方へ
私立高校への進学を検討しているけれど、学力面で不安がある方も多いのではないでしょうか。
教育費を心配されているご家庭も多いと思いますが、ランナーは1コマ30分900円〜と、続けやすい料金設定にしています。
高校受験対策の家庭教師選びについては「高校受験対策におすすめな家庭教師の比較」も参考になります。また、家庭教師の費用が気になる方は「中学生の家庭教師の相場はいくらくらい?」をご覧ください。
私立高校無償化と「ずるい」論争についてまとめ
- ・「ずるい」という感情の背景には4つの構造的問題がある
- ・2026年度から所得制限撤廃、支給上限45万7,200円に引き上げ
- ・「無償化」でも入学金・施設費等で数十万円の負担が必要
- ・制度を正しく理解し申請漏れに注意することが大切
ここまで私立高校無償化の制度と、「ずるい」と言われる理由について詳しく見てきました。
「ずるい」という感情の背景には、年収910万円(目安)という所得制限の壁、東京都とその他の地域の支援額の格差、「無償化」という呼び方と実態のギャップ、そして公立高校を選んだ家庭の不公平感という4つの構造的な問題がありました。
2026年度からは所得制限が撤廃され、支給上限額も45万7,200円に引き上げられる予定です。これにより、世帯年収に関係なくすべての家庭が支援を受けられるようになり、「910万円の壁」問題は解消される見込みです。
ただし「無償化」という言葉から受けるイメージと実態には大きな差があることを忘れてはいけません。支援の対象は授業料のみで、入学金や施設費などで初年度に数十万円の負担が発生するケースが多いんです。
私立高校への進学を検討している方は、制度の内容を正しく理解し、実際にかかる費用を事前にしっかり確認することが大切です。また申請漏れがないよう、学校からの案内をよく読んで期限内に手続きを行いましょう。
お子さんの高校進学に向けて、学力面でのサポートが必要な方は、ぜひ家庭教師のランナーにご相談ください。90分の無料体験レッスンで、お子さんに合った勉強のやり方を一緒に見つけていきましょう。