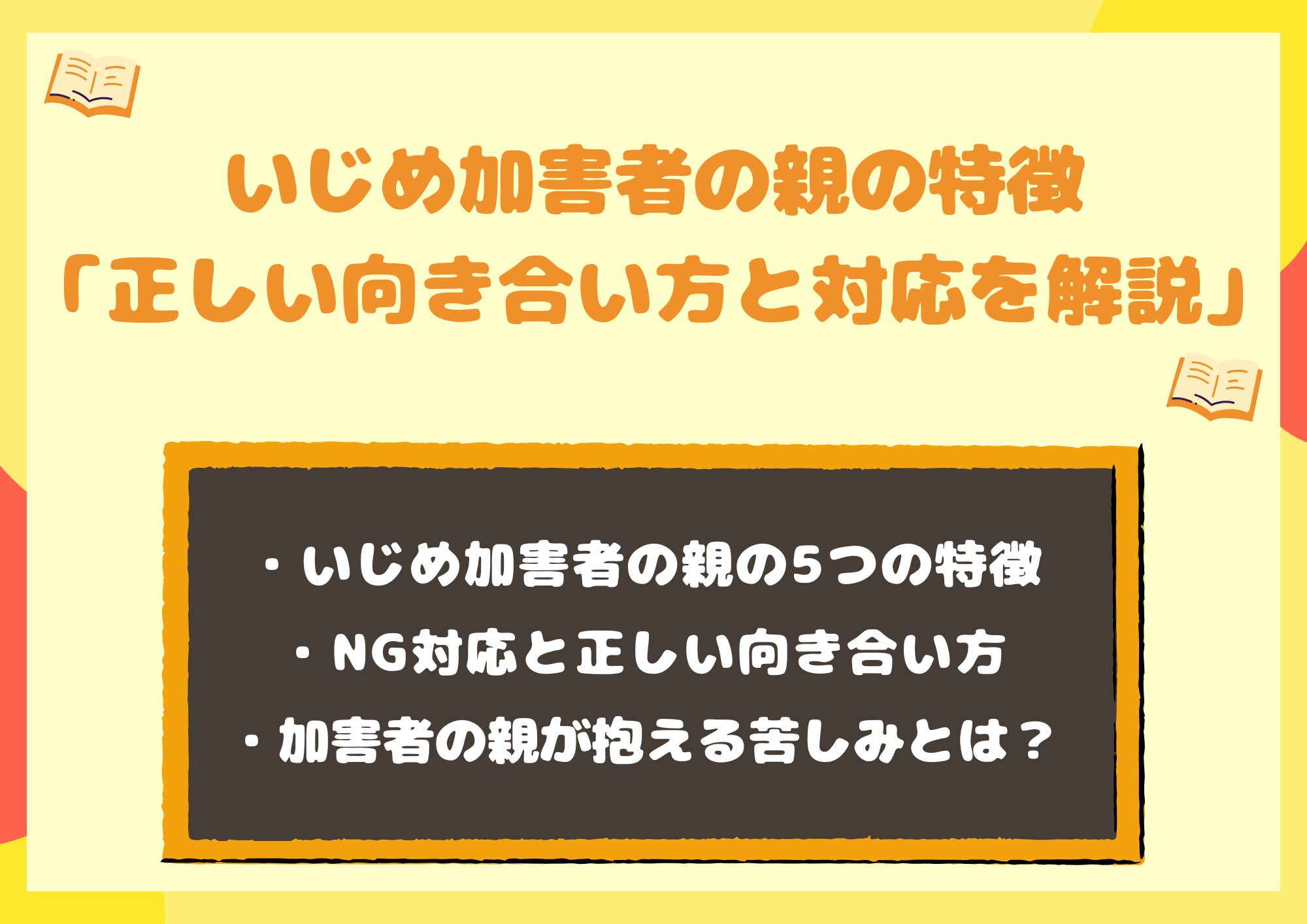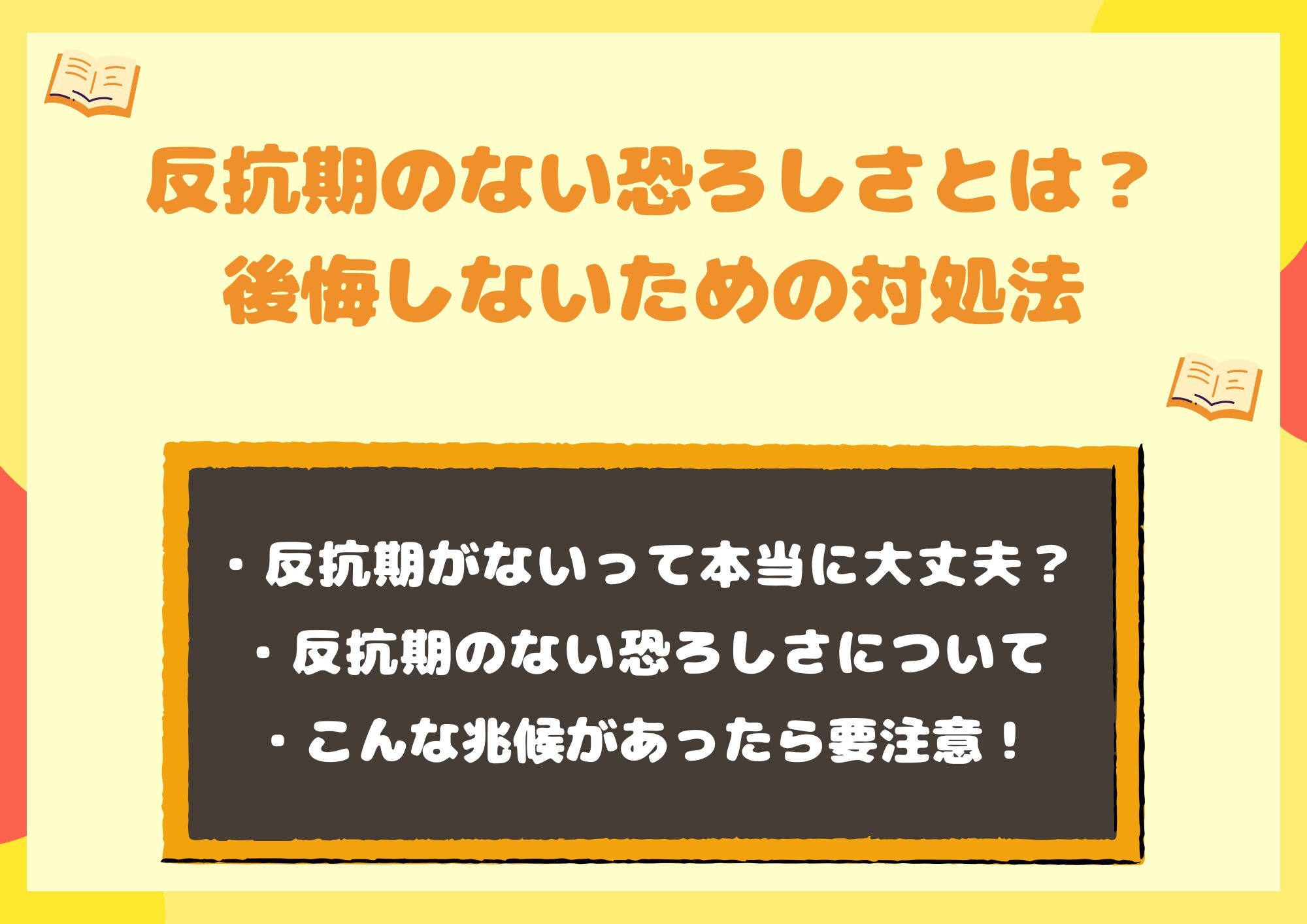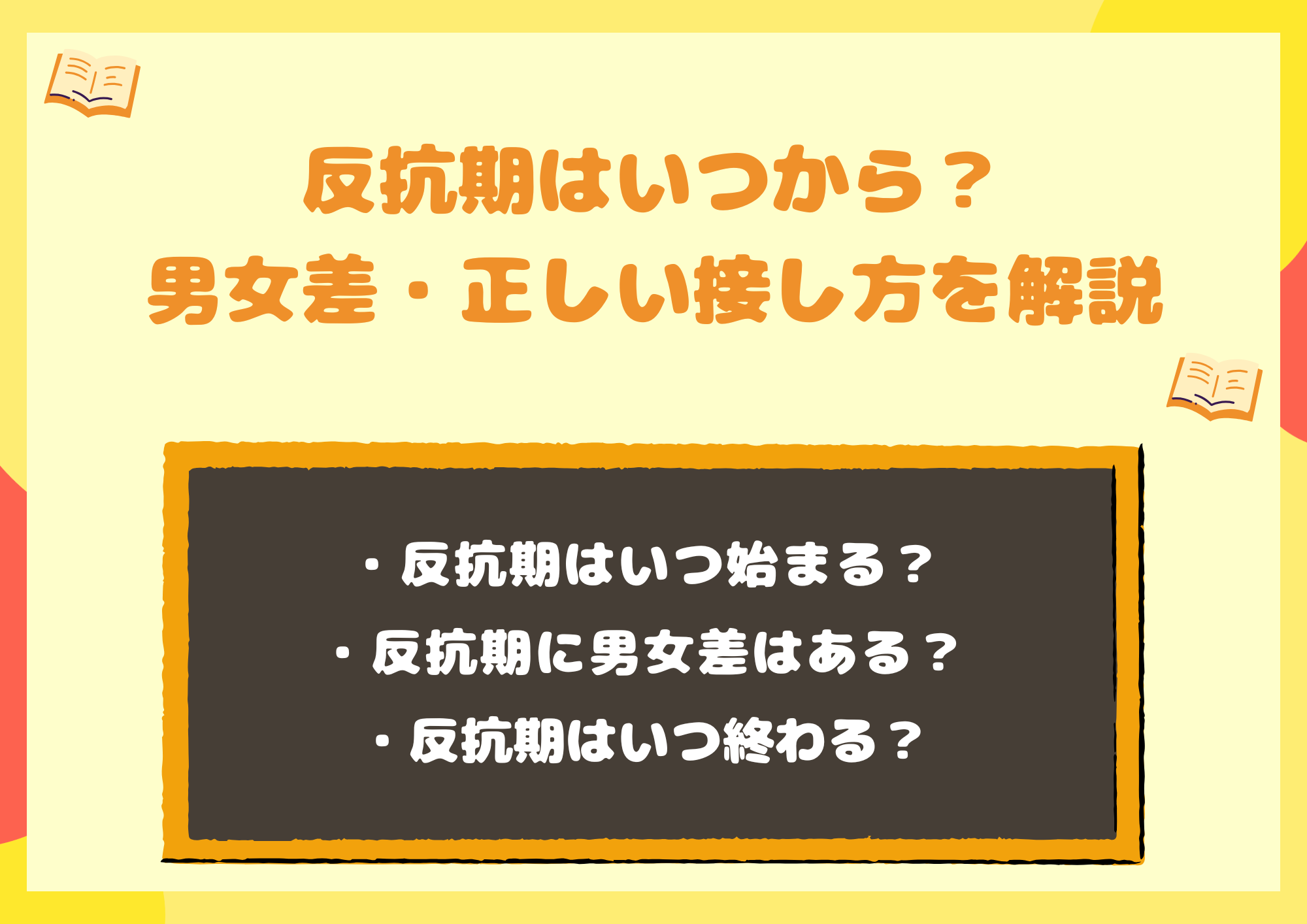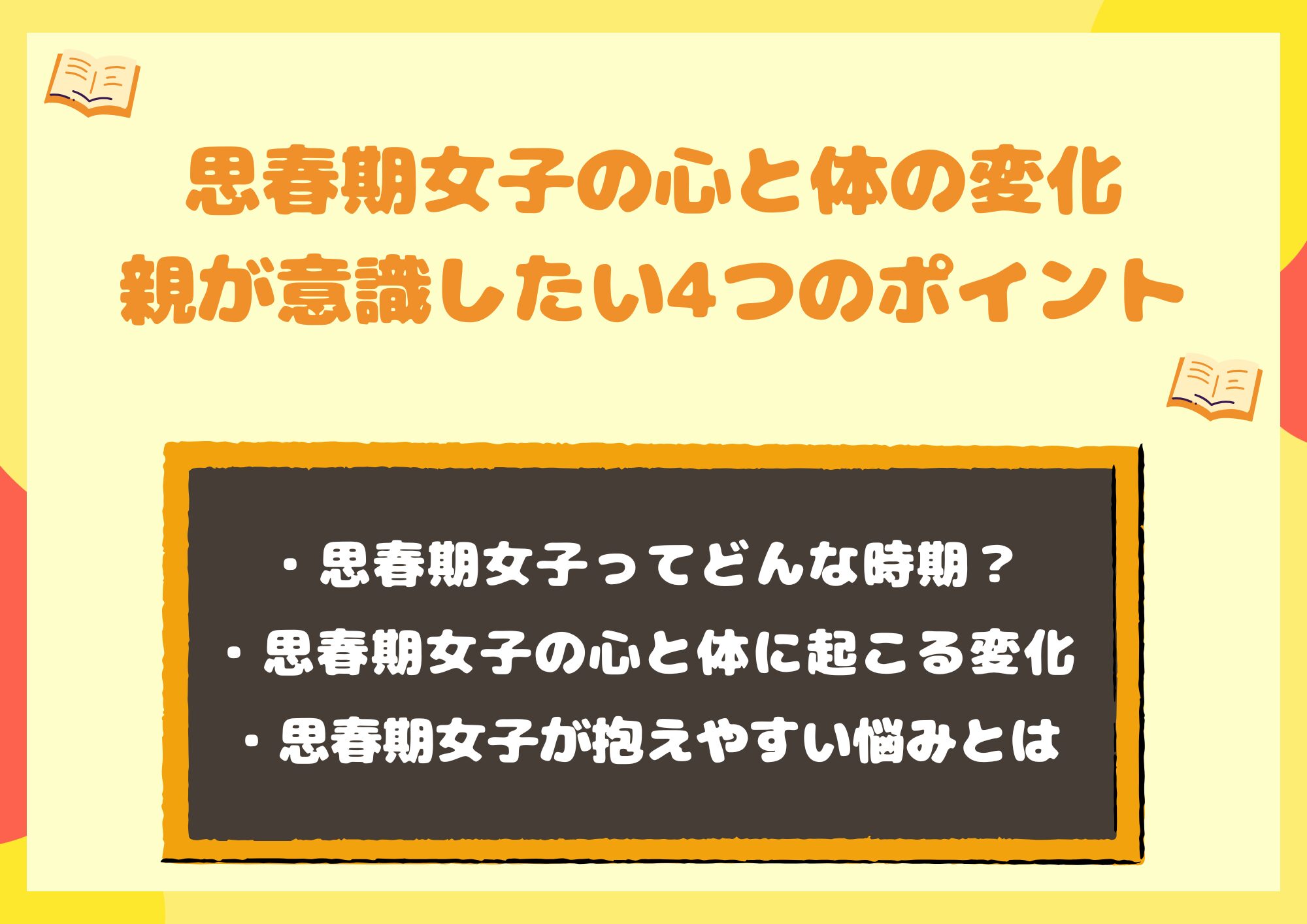- 中
- 勉強法
内申点どこから高い?結論オール4以上|3万人指導のプロが解説
2025.11.08
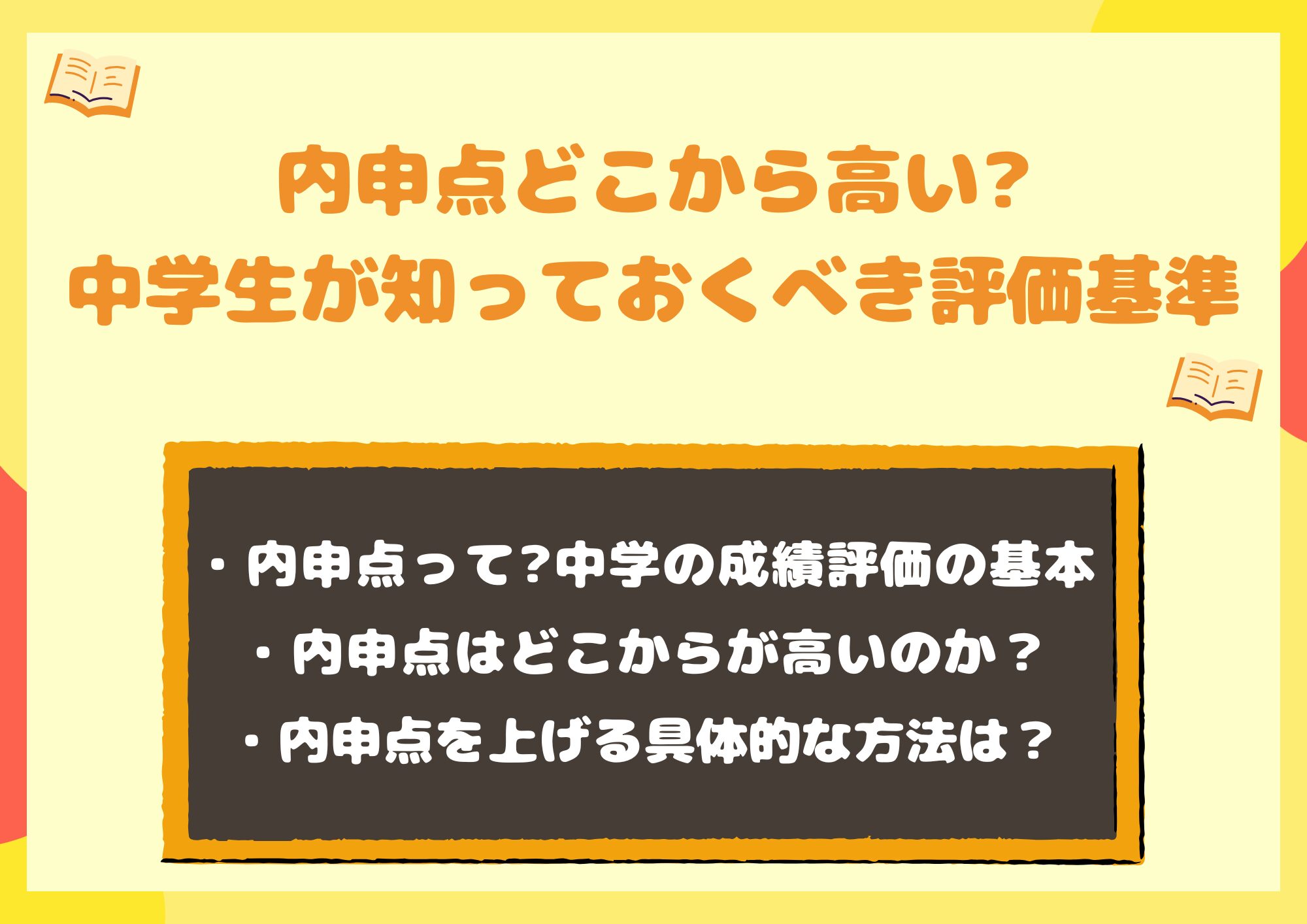
「うちの子の内申点、高いのかな?低いのかな?」「オール3って普通なの?」
中学生のお子さんを持つ保護者の方なら、一度は気になったことがあるのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、内申点は「オール4以上」なら高いと言えます。
この記事では、内申点の具体的な基準から、都道府県別の違い、効果的な成績アップの方法まで詳しく解説します。
私たちランナーは30,034人のお子さんを指導してきましたが、その経験から「今からでも内申点は上げられる」ということをお伝えしたいと思います。実際に2024年の第一志望合格率は97.5%という結果を出しており、内申点対策と学力向上の両立をサポートしてきました。
お子さんの内申点が思うように伸びない、どう対策すればいいか分からないとお悩みでしたら、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
なお、中学生の成績がなかなか上がらないとお悩みの方は「成績が上がらない中学生の原因と対策」もあわせてご覧ください。
目次
内申点って何?中学生の成績評価の基本を知ろう
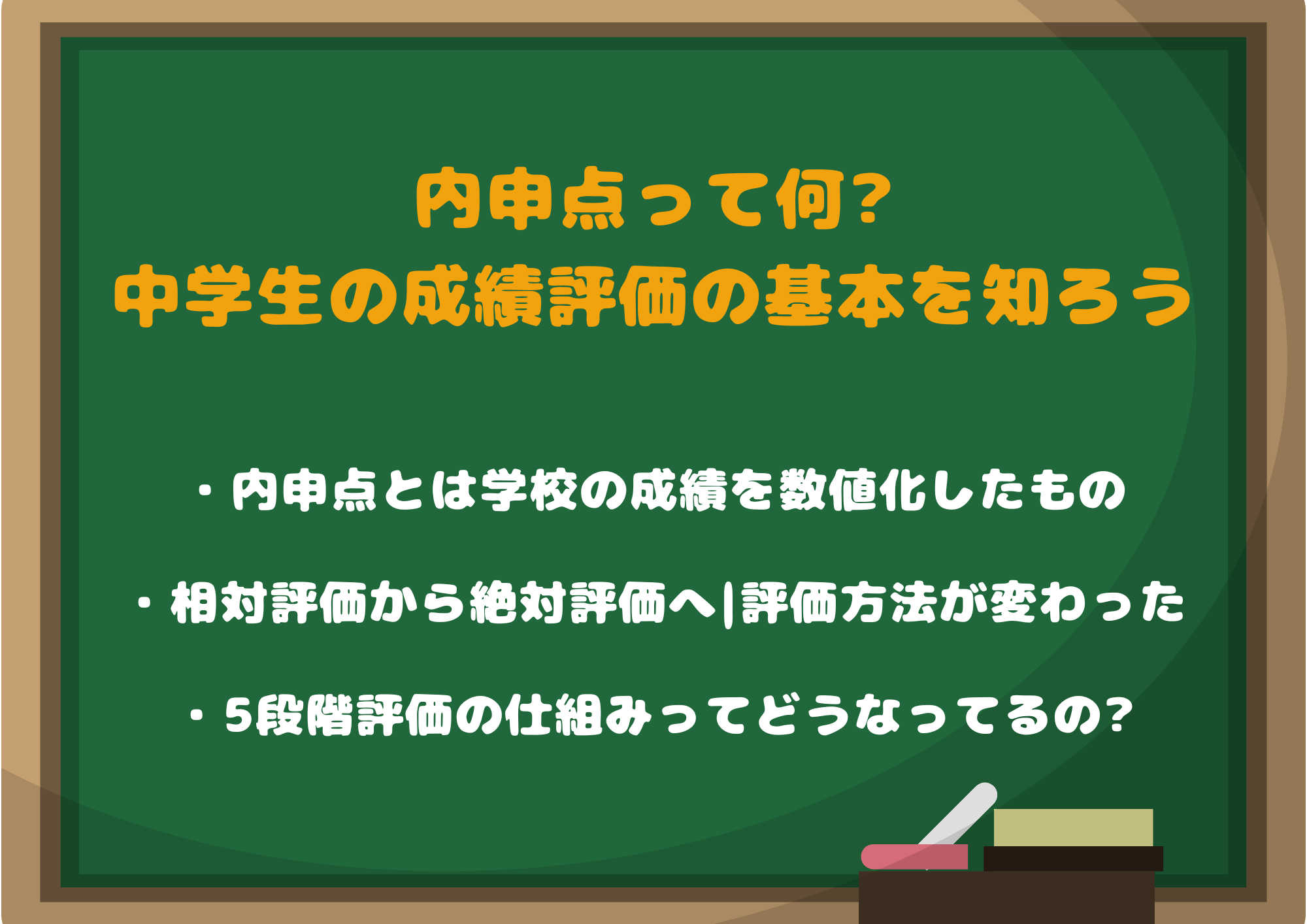
- 内申点とは学校の成績を数値化したもので、9教科の5段階評価を合計したもの
- かつての相対評価から現在は絶対評価に変わり、努力次第で誰でも高評価を目指せる
- 5段階評価は「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3観点で決定
内申点は高校受験において合否を左右する重要な要素です。
しかし、その仕組みを正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。まずは内申点の基本的な定義と、評価方法の変遷について見ていきましょう。
内申点とは学校の成績を数値化したもの
- 通知表の5段階評価(1から5)が基本で、9教科の評定を合計したもの
- 定期テストだけでなく授業態度や提出物も含めて総合的に評価される
- 日々の学校生活での取り組みが高校受験の結果に直結する仕組み
内申点とは、中学校での日々の学習成果を数値化した成績のことです。
具体的には通知表に記載される5段階評価(1から5)が基本となり、9教科の評定を合計したものが内申点として高校入試に使われます。
定期テストの点数だけで決まるわけではなく、授業態度や提出物なども含めて総合的に評価されるんです。多くの都道府県では、内申点と当日の学力試験の得点を組み合わせて合否を判定します。
つまり、日々の学校生活での取り組みが高校受験の結果に直結する仕組みになっています。だからこそ、中学1年生の早い段階から内申点を意識した学習習慣を身につけることが大切なんです。
相対評価から絶対評価へ|評価方法が変わった!
- かつては順位で評定が決まる相対評価だった
- 現在は学習目標への到達度で判断する絶対評価に変更
- 理論上はクラス全員が「5」を取ることも可能に
かつての中学校では「相対評価」という方法が採用されていました。
これはクラスや学年の中での順位によって評定が決まる仕組みで、「5」をもらえるのは上位7%までといった具合に決められていたんです。
しかし現在は「絶対評価」に変わり、定められた学習目標に到達しているかどうかで判断されるようになりました。クラスの他の生徒と比較されるのではなく、自分自身が目標をクリアできているかが重要になったわけです。
この変更により、理論上はクラス全員が「5」を取ることも可能になりました。お子さん一人ひとりの努力が正当に評価される、より公平な制度と言えるでしょう。
つまり、正しい方法で努力すれば、誰でも内申点を上げられるチャンスがあるということです。
5段階評価の仕組みってどうなってるの?
- 1から5の5段階で評価され、「5」は極めて優れている、「3」は目標達成の最低ライン
- 3つの観点別評価を総合して各教科の担当教師が決定
- 定期テストの点数だけでなく提出物や授業態度も評価される
中学校の成績は1から5までの5段階で評価されます。
一般的に「5」は極めて優れている、「4」は優れている、「3」は目標達成の最低ライン、「2」はやや努力が必要、「1」は大いに努力が必要という意味合いです。
この評定は後ほど詳しく説明する「観点別評価」という3つの視点での評価を総合して、各教科の担当教師が決定します。定期テストで高得点を取っていても、提出物を出していなかったり授業態度に問題があったりすると「5」はもらえません。
逆に言えば、テストの点数が少し低くても他の要素でカバーできる可能性があるということです。この仕組みを理解することが、内申点アップの第一歩になります。
内申点はどこから「高い」って言えるの?【結論:オール4以上】
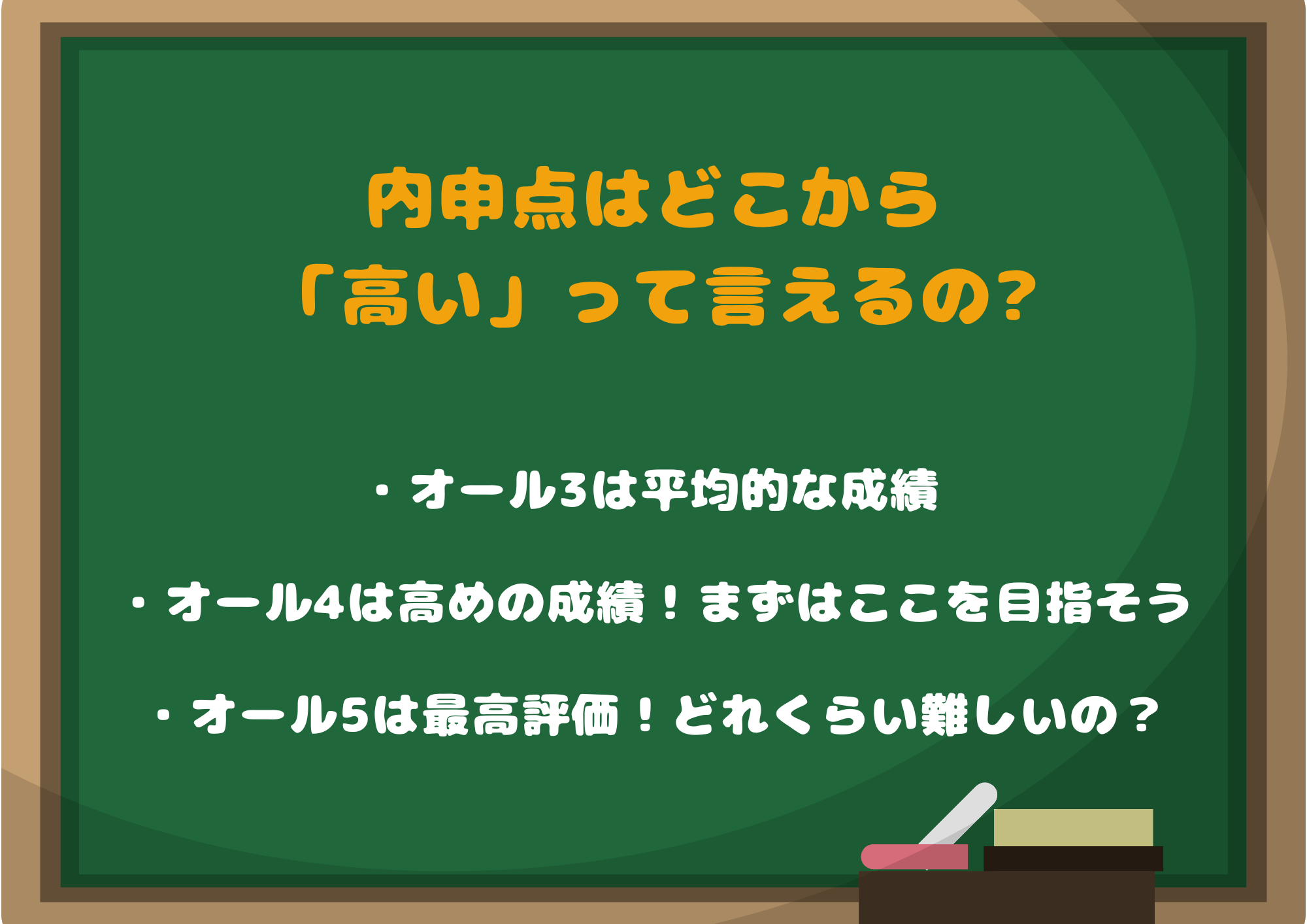
- オール3(合計27点)は「平均」ではなく「やや下」の水準
- オール4(合計36点)は高めの成績で進学校を狙える水準
- オール5(合計45点)は最高評価で学年でもごく一部の生徒に限られる
内申点の数値を見ても、それが高いのか低いのか判断に迷う方も多いでしょう。
ここでは具体的な数値を示しながら、内申点の評価基準について解説していきます。お子さんの現在地を把握し、目標設定の参考にしてくださいね。
オール3は「平均」ではなく「やや下」
- 9教科すべてで評定3を取ると合計27点
- 絶対評価では「3」は目標達成の最低ラインという位置づけ
- 上位の高校を目指すならオール4以上が必要
9教科すべてで評定3を取った場合、合計は27点となります。
「オール3なら平均的」と思われがちですが、実は絶対評価の制度では「3」は目標達成の最低ラインという位置づけです。つまり「普通」というより「やや下」と考えた方が正確かもしれません。
公立高校の普通レベルの学校であれば目指せる水準ですが、上位の高校を狙うなら、ここからもう一段階上を目指す必要があります。
オール3を基準として、どの教科をどれだけ伸ばせるかが受験戦略の鍵になるんです。お子さんがオール3前後の場合は、まず得意教科から4を目指していくのがおすすめです。
オール4なら高めの成績!まずはここを目指そう
- 9教科すべてで評定4を取ると合計36点で高めの成績
- 進学校と呼ばれる上位の公立高校を狙える水準
- 得意教科で5を取りながら苦手教科を4に保つ戦略も有効
9教科すべてで評定4を取ると合計36点となり、これは高めの成績と言えます。
オール4(36点)があれば、多くの地域で進学校と呼ばれる上位の公立高校を狙える水準です。実際には全教科で4を取るのは難しいので、得意教科で5を取りながら苦手教科を4に保つという戦略も有効でしょう。
内申点が36点あれば、当日の学力試験で多少失敗しても合格できる可能性が高まります。
中学1年生から計画的に学習を進め、まずはこのオール4を目標にすることをおすすめします。私たちランナーでも、まずはオール4を目標に設定し、そこから一歩ずつ積み上げていく指導を行っています。
オール5は最高評価!どれくらい難しいの?
- 9教科すべてで評定5を取ると合計45点で最高評価
- 学年でもごく一部の生徒に限られる難易度
- 定期テスト、提出物、授業態度のすべてで高い水準が求められる
9教科すべてで評定5を取ると合計45点となり、これは最高評価です。
オール5を達成できるのは、学年でもごく一部の生徒に限られます。定期テストで常に高得点を取るのはもちろん、提出物を完璧に仕上げ、授業中も積極的に参加する必要があります。
特に実技教科(音楽・美術・保健体育・技術家庭)で5を取るには、作品の質や実技の技能も求められるため、簡単ではありません。
オール5があれば、地域のトップレベルの公立高校や難関私立高校への合格が現実的になります。ただし無理にオール5を目指してお子さんを追い詰めるのではなく、得意分野を伸ばしながらバランスよく評定を上げていく姿勢が大切です。
内申点の平均ってどれくらい?気になる数字
- 内申点の平均値は一般的に27点前後(オール3相当)
- 教科ごとにばらつきがあるのが普通
- 志望する高校が求める内申点の水準を把握することが大切
内申点の平均値は地域や学校によって多少の差がありますが、一般的には27点前後(オール3相当)とされています。
実際には2から4の間に多くの生徒が分布し、完全なオール3の生徒ばかりではありません。得意な数学と英語で4を取り、苦手な実技教科で2を取るといったように、教科ごとにばらつきがあるのが普通です。
大切なのは平均と比較することではなく、志望する高校が求める内申点の水準を把握することです。
各高校の合格者の内申点平均は、学校説明会や塾などで情報を得ることができます。目標とする高校の水準を知ることで、どの教科をどれだけ頑張るべきかが見えてくるはずです。
内申点を上げるために何をすればいい?【30,034人の指導実績から分かったこと】
- 定期テストで高得点を取ることが「知識・技能」の評価に直結
- 提出物は丁寧に仕上げて期限内に出すことが「主体性」の評価につながる
- 授業態度や参加姿勢も内申点を決める重要な要素
- 実技教科は主要5教科と同じく重要で、努力次第で評定を上げやすい
私たちランナーは30,034人のお子さんを指導してきましたが、内申点アップに成功した多くのご家庭に共通するポイントがあります。
ここでは具体的な対策方法を4つの観点から解説します。どれも特別なことではなく、正しい方法を知って継続することが大切なんです。
中学生の勉強法について詳しく知りたい方は「中学生の効果的な勉強法」もあわせてご覧ください。
定期テストで点数を取ることが基本中の基本
- 定期テストの結果は「知識・技能」の評価観点に直結
- 年4〜5回実施されるテストの一回一回が内申点に影響
- テスト2週間前からの計画的な学習と繰り返し演習が効果的
内申点を上げる最も基本的な方法は、定期テストで高得点を取ることです。
定期テストの結果は「知識・技能」という評価観点に直結し、評定を決める大きな要素となります。中間テストと期末テストは年に合計4回から5回実施されますが、この一回一回が内申点に影響するんです。
テスト2週間前からは計画的に学習を進め、学校のワークを繰り返し解いて理解を深めることが効果的でしょう。
実際に私たちランナーでも「定期テスト対策を始めて3ヶ月で内申点が3→4にアップした」というケースを数多く見てきました。定期テストは内申点アップの最も確実な方法なので、一回一回を大切にしていきましょう。
定期テスト対策について詳しく知りたい方は「中学生の勉強法」もご覧ください。
提出物は期限内に完璧な状態で出そう
- 提出物は「主体的に学習に取り組む態度」の観点で評価される
- 丁寧に仕上げて期限内に出すことが高評価につながる
- 間違えた問題を赤ペンで直し、解説を書き加える工夫が効果的
提出物の管理は、多くの生徒が軽視しがちですが内申点に大きく影響します。
宿題やワーク、レポートなどの提出物は「主体的に学習に取り組む態度」という観点で評価されるんです。ただ提出すれば良いわけではなく、丁寧に仕上げて期限内に出すことが高評価につながります。
特にワークは、間違えた問題を赤ペンで直し、なぜ間違えたのか自分なりの解説を書き加えると良いでしょう。このような工夫は「自ら学習を調整している」姿勢として評価され、評定アップに直結します。
私たちランナーでも「提出物の管理を親子で始めたら、内申点が上がりました」という声を多くいただいています。提出期限をカレンダーに書き込んだり、週末にまとめて進める習慣をつけたりすることで、提出忘れを防げるはずです。
授業態度も評価されるって知ってた?
- 授業中の態度や参加姿勢は「主体性」の観点で評価される
- 積極的な発言は学習意欲の表れとして評価される
- 発言が苦手でも真剣に授業を聞く姿勢やノートを丁寧に取る姿勢で評価される
授業中の態度や参加姿勢も、内申点を決める重要な要素です。
これは「主体的に学習に取り組む態度」という観点で評価され、ノートの取り方や発言の頻度などが見られています。授業中に積極的に手を挙げて発言することは、学習意欲の表れとして評価されます。
ただし発言が苦手なお子さんでも、真剣に授業を聞く姿勢やノートを丁寧に取る姿勢を示すことで評価されるので安心してください。
グループワークでは協力的に取り組み、他の生徒の意見もしっかり聞く態度が大切です。分からないことがあれば授業後に質問に行く姿勢も、学習意欲の表れとして評価対象となります。
実技教科も手を抜いちゃダメ!2倍換算される地域もある
- 実技4教科は内申点では主要5教科と同じく重要
- 東京都では実技4教科の評定が2倍に換算される
- 日々の練習や努力が評価につながり、努力次第で評定を上げやすい
音楽・美術・保健体育・技術家庭の4教科は、しばしば「副教科」と呼ばれますが、内申点では主要5教科と同じく重要です。
特に東京都では実技4教科の評定が2倍に換算されるため、むしろ主要5教科より重要度が高いとも言えます。数学で5を取っても5点ですが、音楽で5を取ると10点として計算されるんです。
音楽では楽器演奏や歌唱のテストがあり、日々の練習が評価につながります。美術では作品の完成度だけでなく、制作過程での工夫や努力も評価対象です。
保健体育は運動能力だけでなく、ルールの理解や協力的な態度、安全への配慮なども見られています。技術家庭では作品の精度や、レポートの内容、実習への取り組み方が評価されます。
実技教科は努力次第で評定を上げやすい科目なので、ぜひ前向きに取り組んでみてください。
ここまで内申点を上げる4つのポイントをお伝えしてきました。「うちの子に合った具体的な対策を知りたい」という方は、ぜひ無料体験レッスンでご相談ください。お子さんの状況に合わせた学習プランをご提案します。
新しい評価基準「観点別評価」って何?
- 「知識・技能」は定期テストの点数や実技の出来栄えで評価
- 「思考・判断・表現」は記述問題やレポート作成で評価
- 「主体的に学習に取り組む態度」は提出物や授業態度で評価
2021年度から中学校で本格的に導入された新しい評価方法について、詳しく見ていきましょう。
この観点別評価の仕組みを理解することが、効果的な内申点アップの鍵となります。それぞれの観点で何が評価されるのかを知っておけば、対策も立てやすくなりますよ。
知識・技能の評価ってどうつくの?
- 定期テストの点数や小テストの結果で評価される
- 実技教科では実技の出来栄えが評価対象
- 基礎的な学習内容の理解と定着が求められる
「知識・技能」は3つの観点のうち最も分かりやすい評価項目です。
主に定期テストの点数や小テストの結果、実技教科では実技の出来栄えなどで評価されます。数学なら計算問題が正確に解けるか、英語なら単語や文法を覚えているかといった基礎的な学力が対象です。
実技教科では、音楽の楽器演奏や体育の実技試験などがこの観点に含まれます。この観点で高評価を得るには、基礎的な学習内容をしっかり理解し定着させることが必要です。
日々の復習を欠かさず、分からないところをそのままにしないことが大切ですね。
思考・判断・表現力も見られてる
- 知識を活用して考える力を評価する観点
- 記述問題、グループディスカッション、レポート作成で評価
- 「なぜそうなるのか」を考える習慣が効果的
「思考・判断・表現」は、知識を活用して考える力を評価する観点です。
定期テストの記述問題や、授業中のグループディスカッション、レポート作成などで評価されます。単に知識を暗記しているだけでなく、それを使って問題を解決したり自分の考えを表現したりする力が求められるんです。
例えば理科なら実験結果から考察を導き出す力、社会なら歴史的な出来事の背景を考える力などが該当します。
この観点で評価を上げるには、日頃から「なぜそうなるのか」を考える習慣をつけることが効果的です。暗記だけでなく、理解を深める学習を心がけましょう。
主体的に学習に取り組む態度が重要って本当?
- 粘り強く課題に取り組む姿勢を見せることが重要
- 自分で学習を調整できる能力が評価される
- 提出物の工夫や授業後の質問なども評価対象
「主体的に学習に取り組む態度」は、新しい評価基準で最も注目されている観点です。
この観点は単に授業中に手を挙げることだけを指すのではなく、学習に対する姿勢全体を評価します。具体的には、粘り強く課題に取り組む姿勢と、自分で学習を調整する能力の2つの側面から評価されるんです。
粘り強く取り組む姿勢を見せよう
粘り強い取り組みとは、難しい問題や課題に直面しても諦めずに努力を続ける姿勢のことです。
例えば、一度解けなかった問題を何度も挑戦して解き直したり、作品制作で試行錯誤を重ねたりする行動が該当します。教師はこうした姿勢を、提出物の修正跡や授業中の取り組み方から判断しています。
自分で学習を調整できるかがポイント
学習の調整とは、自分の理解度を把握し、必要に応じて学習方法を工夫する能力のことです。
例えば、苦手な単元を重点的に復習したり、効果的なノートの取り方を自分なりに工夫したりすることが該当します。間違えた問題になぜ間違えたかを書き込んだり、授業後に質問に行ったりする行動も、この観点で評価されるポイントです。
都道府県で違う!内申点の計算方法を確認しよう
- 東京都は中3のみが対象で実技4教科が2倍に換算される
- 神奈川県は中2・中3が対象で中3の評定が2倍
- 埼玉県は中1から全て対象で3年間の蓄積が重視される
- 大阪府は中1から対象だが中3の比重が全体の6割を占める
内申点の計算方法は全国一律ではなく、各都道府県が独自に定めています。
この違いを知らずに対策を進めると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があるので注意が必要です。お住まいの地域の制度を確認しておきましょう。
東京都は中3の成績だけが対象
- 中学3年生の成績のみが内申点として使われる
- 5教科はそのまま、実技4教科は2倍に換算される
- 中1・中2の成績は入試に影響しない
東京都の公立高校入試では、中学3年生の成績のみが内申点として使われます。
つまり中学1年と2年の成績は、内申点には一切影響しないということです。また、5教科の評定はそのまま使われますが、実技4教科の評定は2倍に換算されます。
この制度により、実技教科の重要性が非常に高くなっています。中1・中2で成績が振るわなかった生徒にとっては、中3から挽回のチャンスがあると言えるでしょう。
ただし、中3で急に頑張るのは大変なので、中1・中2のうちから学習習慣を身につけておくことをおすすめします。
神奈川県は中2・中3が対象で中3が2倍
- 中学2年と中学3年の成績が内申点として使われる
- 9教科すべてが対象で主要5教科と実技4教科は同じ扱い
- 中学3年の評定合計は2倍して計算される
神奈川県の公立高校入試では、中学2年と中学3年の成績が内申点として使われます。
9教科すべてが対象となり、主要5教科と実技4教科の区別なく同じ扱いです。ただし中学3年の評定合計は2倍して計算されるため、中3の比重が高くなっています。
計算式は「中2の評定合計(45点満点)+中3の評定合計×2(90点満点)=135点満点」となります。中2から内申点が始まるので、中2の1学期から気を抜けない制度と言えるでしょう。
また神奈川県には、内申点の代わりに観点別評価(主体的に学習に取り組む態度)を用いて、学力検査等と合わせて選考する「第2次選考」という枠もあります。
埼玉県は中1から全部対象!早めの対策が必須
- 中学1年・2年・3年の3年間すべての成績が内申点として使われる
- 中学に入学した瞬間から高校受験が始まっている
- 早い段階から学習習慣を身につけることが必要
埼玉県の公立高校入試では、中学1年・2年・3年の3年間すべての成績が内申点として使われます。
つまり中学に入学した瞬間から、すでに高校受験が始まっているということです。中1でつまずいてしまうと、その影響が3年間残り続けることになります。
早い段階から学習習慣を身につけ、定期テストや提出物をしっかり管理することが必要でしょう。埼玉県にお住まいの方は、特に中1の段階から内申点への意識を高く持つことが大切です。
私たちランナーでも、埼玉県のお子さんには中1からの対策を強くおすすめしています。
大阪府は中3の比重が特に大きい
- 中学1年・2年・3年の3年間すべてが対象
- 中1と中2の評定は2倍、中3の評定は6倍して計算
- 中3の比重が全体の6割を占め、大逆転が可能な設計
大阪府の公立高校入試では、中学1年・2年・3年の3年間すべてが対象となります。
ただし学年ごとの比重が大きく異なり、中1と中2の評定は2倍、中3の評定は6倍して計算されます。計算式は「中1の評定合計×2+中2の評定合計×2+中3の評定合計×6」となるため、中3の比重が全体の6割を占めます。
この制度により、中1・中2で多少成績が振るわなくても、中3で頑張れば大きく挽回できる可能性があるんです。逆に中3で油断すると、これまでの努力が水の泡になってしまう危険性もあります。
内申点が取りにくいお子さんへのサポート
- 発達障害・学習障害のお子さんには特性に合わせた対策が効果的
- 不登校でも出席扱い制度の活用など具体的な方法がある
- 一人ひとりの状況に合わせたサポートが内申点アップの鍵
内申点の仕組みは分かっても、「うちの子には難しいかもしれない」と感じている保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、内申点が取りにくいお子さんへの具体的なサポート方法についてお伝えします。お子さん一人ひとりに合った対策を見つけることが大切です。
発達障害・学習障害のお子さんの内申点対策
- 特性を理解した上での対策が効果的
- 学校との連携で合理的配慮を受けられる場合もある
- 専門知識を持つ指導者のサポートが心強い
発達障害や学習障害のあるお子さんにとって、内申点を上げることは一般的な対策だけでは難しい場合があります。
例えば、提出物の管理が苦手だったり、授業中に集中し続けることが難しかったりするケースも少なくありません。大切なのは、お子さんの特性を理解した上で、一人ひとりに合った対策を立てることです。
学校との連携により、テスト時間の延長や別室受験などの合理的配慮を受けられる場合もあります。また、視覚的なスケジュール管理や、タスクを細かく分けて達成感を得やすくする工夫なども効果的です。
私たちランナーには発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフが在籍しており、お子さん一人ひとりの特性に合わせた対策をご提案しています。専門的な知識を持つスタッフが、保護者の方と一緒にお子さんに合った学習方法を見つけていきます。
発達障害のお子さんの高校受験について詳しく知りたい方は「発達障害のお子さんの高校受験対策」もあわせてご覧ください。また、発達障害のお子さんへのサポートについては発達障害サポートコースのページでも詳しくご紹介しています。
不登校でも内申点をつける方法はある
- 不登校でも内申点がつく方法はいくつかある
- ICT等を活用した学習による「出席扱い」制度が利用できる
- 当日点重視の入試制度を利用する選択肢もある
「不登校だから内申点はつかない」と諦めていませんか?
実は不登校のお子さんでも、内申点をつける方法はいくつかあります。例えば、ICT等を活用した自宅学習が一定の条件を満たせば「出席扱い」となる制度があります。文部科学省のガイドラインに基づき、学校と相談しながら進めることで、自宅での学習を出席としてカウントしてもらえる可能性があるんです。
また、内申点が低くても当日の学力検査を重視する入試制度を利用するという選択肢もあります。神奈川県の「第2次選考」のように、内申点をほとんど使わない枠を設けている地域もあるんです。
私たちランナーは不登校のお子さんへのサポート実績があり、出席扱い制度の活用など具体的なサポートを行っています。お子さんの状況に合わせて、どのような選択肢があるのかを一緒に考えていきます。
不登校のお子さんの高校受験について詳しく知りたい方は「不登校からの高校受験対策」もあわせてご覧ください。また、不登校のお子さんへのサポートについては不登校サポートコースのページでも詳しくご紹介しています。
内申点対策におすすめの家庭教師3選
- 家庭教師なら定期テスト対策から提出物管理まで総合的にサポート
- 一人ひとりの状況に合わせたオーダーメイドの指導が可能
- 塾と違って通学時間がなく、効率的に学習できる
内申点を効果的に上げるには、定期テスト対策だけでなく提出物管理や学習習慣の確立が必要です。
家庭教師なら一人ひとりの状況に合わせて、これらを総合的にサポートできます。ここでは、内申点対策に力を入れている家庭教師サービスを3つご紹介します。
家庭教師のランナー|勉強が苦手な子専門のマンツーマン指導

- 30,034人の指導実績、2024年の第一志望合格率は97.5%
- 月額料金は小中学生で1コマ30分900円とリーズナブル
- 発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフ在籍
- 不登校のお子さんへのサポート実績あり
- 兄弟や友達と2人同時受講で2人目以降の料金が半額以下
家庭教師のランナーは、勉強が苦手な小中高生専門の家庭教師サービスです。
30,034人の指導実績があり、2024年の第一志望合格率は97.5%という高い実績があります。この合格率は、内申点対策と学力向上を両立させた結果です。
内申点対策は長期戦になりがち。だからこそ、1コマ30分900円という続けやすい料金設定で、無理なく対策を続けられるようにしています。実際には月々15,000円から25,000円ほどで受講されているご家庭が多く、塾の個別指導と比べて無理なく続けられると好評です。
さらに兄弟や友達と2人同時に受けると、2人目以降の料金が半額以下になるユニークな制度もあります。発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフが在籍しており、発達障害や不登校のお子さんにも特化したサポート体制が整っています。
90分の無料体験レッスンでは、お子さんに合った勉強のやり方を提案し、講師との相性を確認してから契約を決められます。無理な勧誘は一切ありませんので、お気軽にお試しください。
家庭教師のトライ|業界最大手の安心サポート体制

- 全国33万人以上の登録教師から相性の良い教師を選べる
- 専任の教育プランナーによるきめ細かいサポート
- 30年以上の実績と豊富な受験情報の蓄積
家庭教師のトライは業界最大手で、全国33万人以上の登録教師から相性の良い教師を選べます。
専任の教育プランナーが家庭と教師をつなぎ、きめ細かいオーダーメイドカリキュラムで指導を行います。1時間あたりの授業料は4,620円からで、週1回60分なら月額約18,000円前後から利用可能です。
30年以上の実績があり、各都道府県の受験情報が豊富に蓄積されているため、地域に合わせた受験対策ができます。講師は学力や人間性など厳しい基準で採用されており、万が一相性が合わない場合は無料で何度でも交代できます。
学研の家庭教師|大手ならではの充実したフォロー

- 教育大手の学研グループが運営する安心感のあるサービス
- 厳選された大学生からプロ講師まで約12万人の教師が登録
- 高額教材の販売は行わず、市販教材や学校の教科書で指導
学研の家庭教師は、教育大手の学研グループが運営する安心感のあるサービスです。
厳選された大学生からプロ講師まで約12万人の教師が登録されており、お子さんの学年や目的に応じて最適な教師を紹介します。指導料は1時間あたり3,190円からで、週1回60分なら月約12,760円から利用できます。
高額教材の販売は行っておらず、市販教材や学校の教科書で指導を進めるため追加費用の心配がありません。中学受験から高校・大学受験まで幅広い入試対策実績があり、教師と本部の連携による情報提供や進路相談なども充実しています。
内申点についてよくある質問に答えます
- 部活動は調査書に記載されるが、評定そのものを覆すほどの力はない
- 内申点が低くても学力検査で高得点を取れば合格の可能性は十分にある
- 塾と家庭教師のどちらが良いかはお子さんの性格や学習状況による
内申点について多くの保護者や生徒が疑問に思うポイントを、Q&A形式で解説します。
部活動は内申点に影響するの?
- 部活動や委員会活動は調査書に記載され高校側に伝わる
- 一部の高校では加点されたり同点の場合の参考にされたりする
- 部活動の実績が評定(1から5)を覆すほどの力はない
部活動や委員会活動は、調査書に記載され高校側に伝わります。
一部の高校では、特定の部活動実績に対して加点されたり、同点の場合の参考にされたりすることがあります。ただし、部活動の実績が評定(1から5)そのものを覆すほどの力はありません。
例えば部活を頑張ったからといって、評定3が4になるわけではないんです。まずは各教科で良い評定を取ることが最優先で、部活動はあくまで「ボーナス点」と考えるのが適切です。
部活動と勉強の両立に悩んでいるお子さんも多いですが、限られた時間の中で効率よく学習することが大切ですね。
内申点が低くても高校に合格できる?
- 多くの都道府県では内申点と学力検査の得点を合わせて判定
- 一般的に学力検査の方が重視される傾向がある
- 神奈川県のように内申点を使わない選考枠がある地域もある
内申点が低くても、合格の可能性は十分にあります。
多くの都道府県では、内申点と当日の学力検査の得点を合わせて合否を判定します。一般的な比率は内申点と学力検査が「7対3」や「6対4」程度で、学力検査の方が重視される傾向があります。
つまり内申点が多少低くても、当日のテストで高得点を取れば十分に合格できるということです。また神奈川県のように、内申点をほとんど使わない「第2次選考」という枠を設けている地域もあります。
内申点が思うように取れなかった場合は、志望校を再検討するか、学力検査で高得点を狙う戦略に切り替えることも選択肢の一つです。諦める必要はありません。
塾と家庭教師どっちがいい?迷ったら
- 塾は集団授業で周りの生徒と切磋琢磨しながら学べる
- 家庭教師は完全マンツーマンで一人ひとりのペースに合わせた指導が可能
- お子さんの性格や目標、ライフスタイルに合わせて最適な選択を
塾と家庭教師のどちらが良いかは、お子さんの性格や学習状況によって異なります。
塾は集団授業が中心で、周りの生徒と切磋琢磨しながら学べる環境が魅力です。競争心が強く、仲間と一緒に頑張れるタイプのお子さんには塾が向いているでしょう。
一方、家庭教師は完全マンツーマンで、一人ひとりのペースに合わせた指導が可能です。人前で質問するのが苦手な子や、特定の科目だけ集中的に対策したい場合は家庭教師がおすすめです。
また塾は通学の時間が必要ですが、家庭教師は自宅で受けられるため時間の節約になります。お子さんの性格や目標、ライフスタイルに合わせて、最適な選択をすることが大切です。
まとめ|内申点はどこから高い?
- ・内申点は「オール4以上」なら高いと言え、進学校を狙える水準
- ・オール3は「平均」ではなく「やや下」という認識が正確
- ・内申点の計算方法は都道府県によって大きく異なるため、お住まいの地域の制度を把握することが重要
- ・定期テスト、提出物、授業態度の3つをバランスよく対策することが内申点アップの鍵
- ・実技教科は地域によっては2倍換算されるなど戦略的に極めて重要
内申点は「オール4以上」なら高いと言え、多くの地域で進学校を狙える水準です。オール3は「平均」ではなく「やや下」という認識が正確なので、まずはオール4を目標に対策を進めましょう。
内申点はテストの点数だけでなく、提出物や授業態度も大きく影響するため、バランスよく対策することが大切です。また、都道府県によって計算方法が異なるので、お住まいの地域の制度を確認しておきましょう。
私たちランナーは30,034人の指導実績があり、お子さん一人ひとりに合わせた内申点対策をサポートしています。「うちの子に合った対策方法を知りたい」という方は、ぜひ90分の無料体験レッスンをお試しください。
無理な勧誘は一切ありませんので、お気軽にどうぞ。