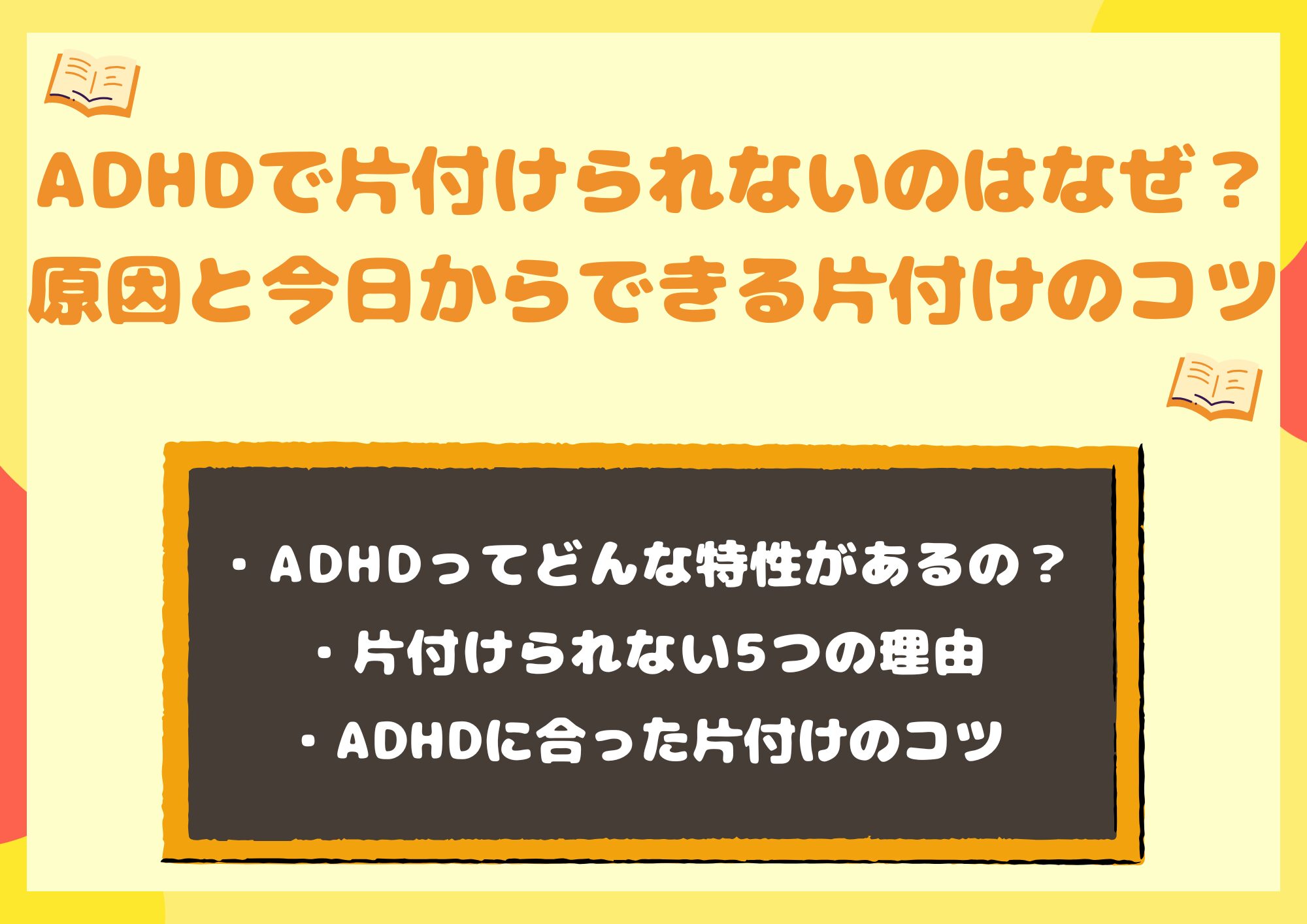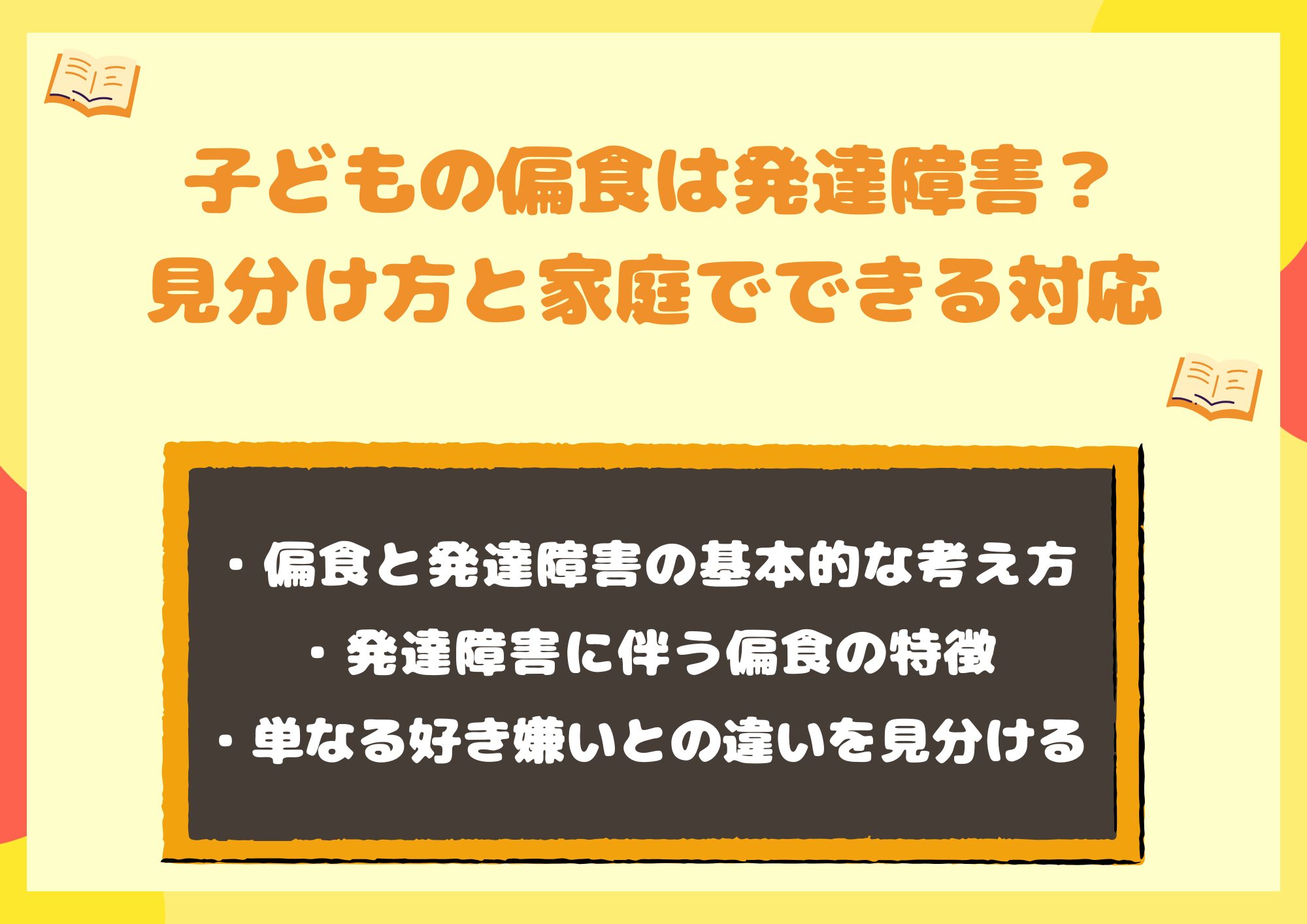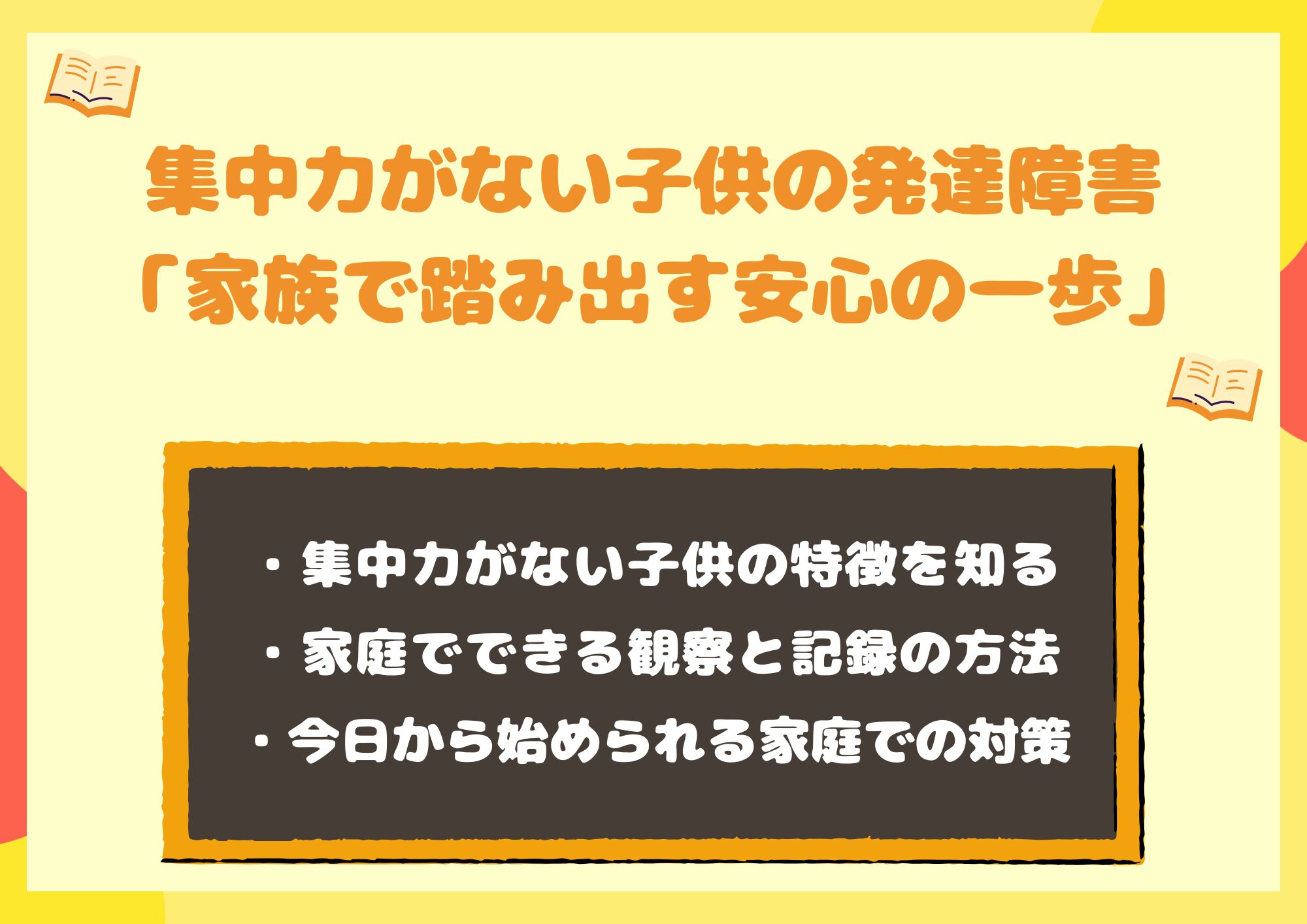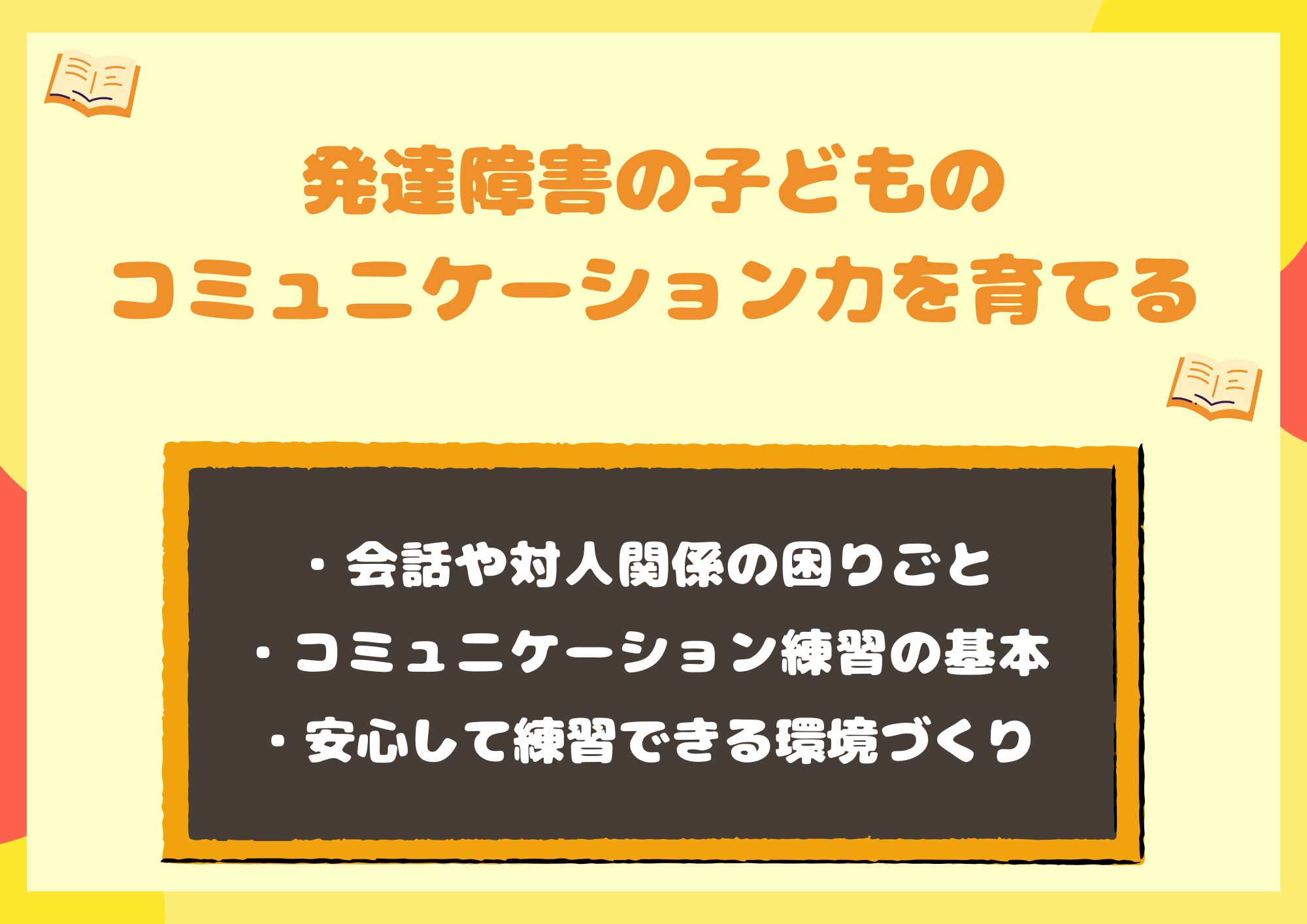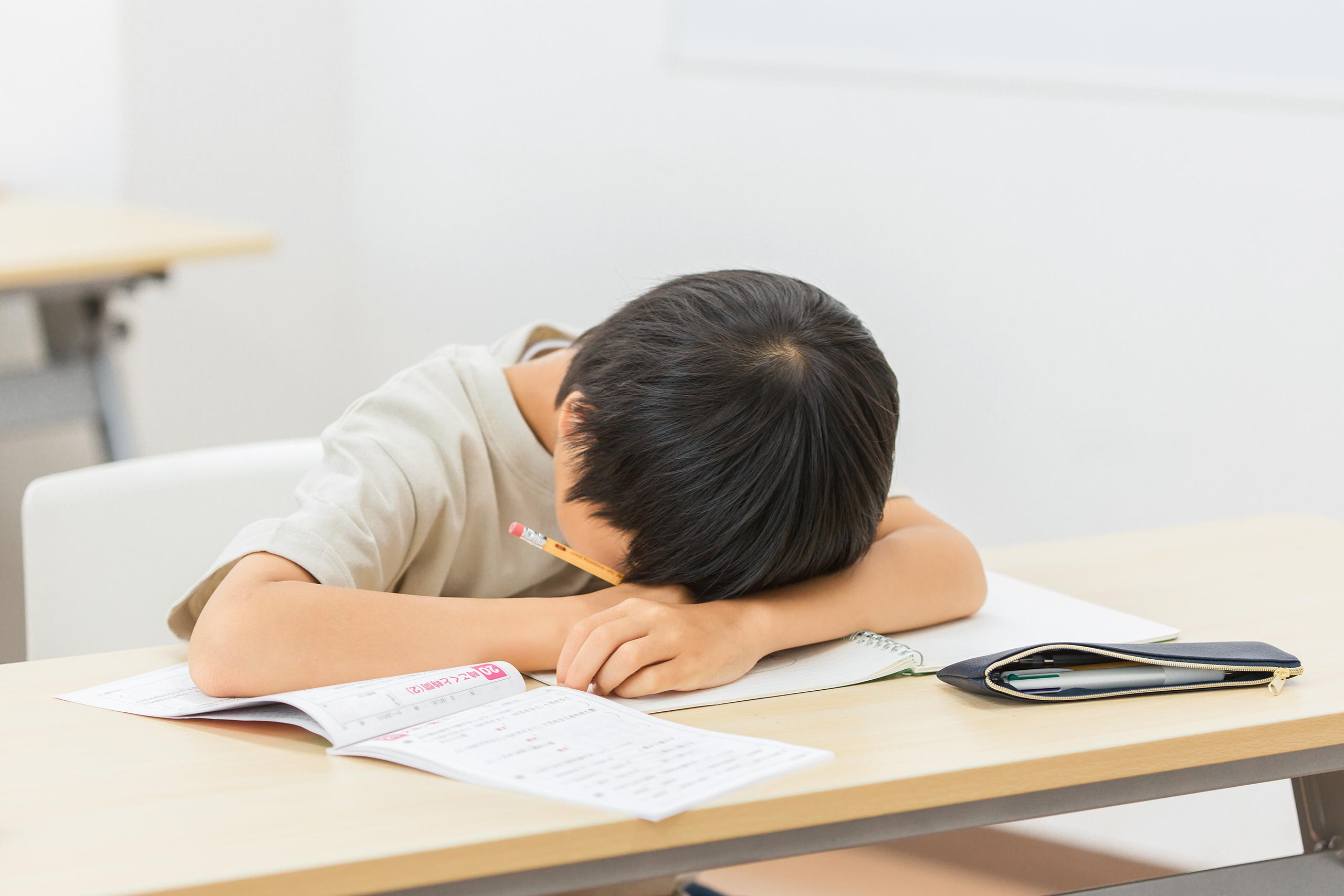- 発達障害向けの家庭教師
時間を守れない子供は発達障害?今すぐできる支援方法のまとめ
2025.09.27
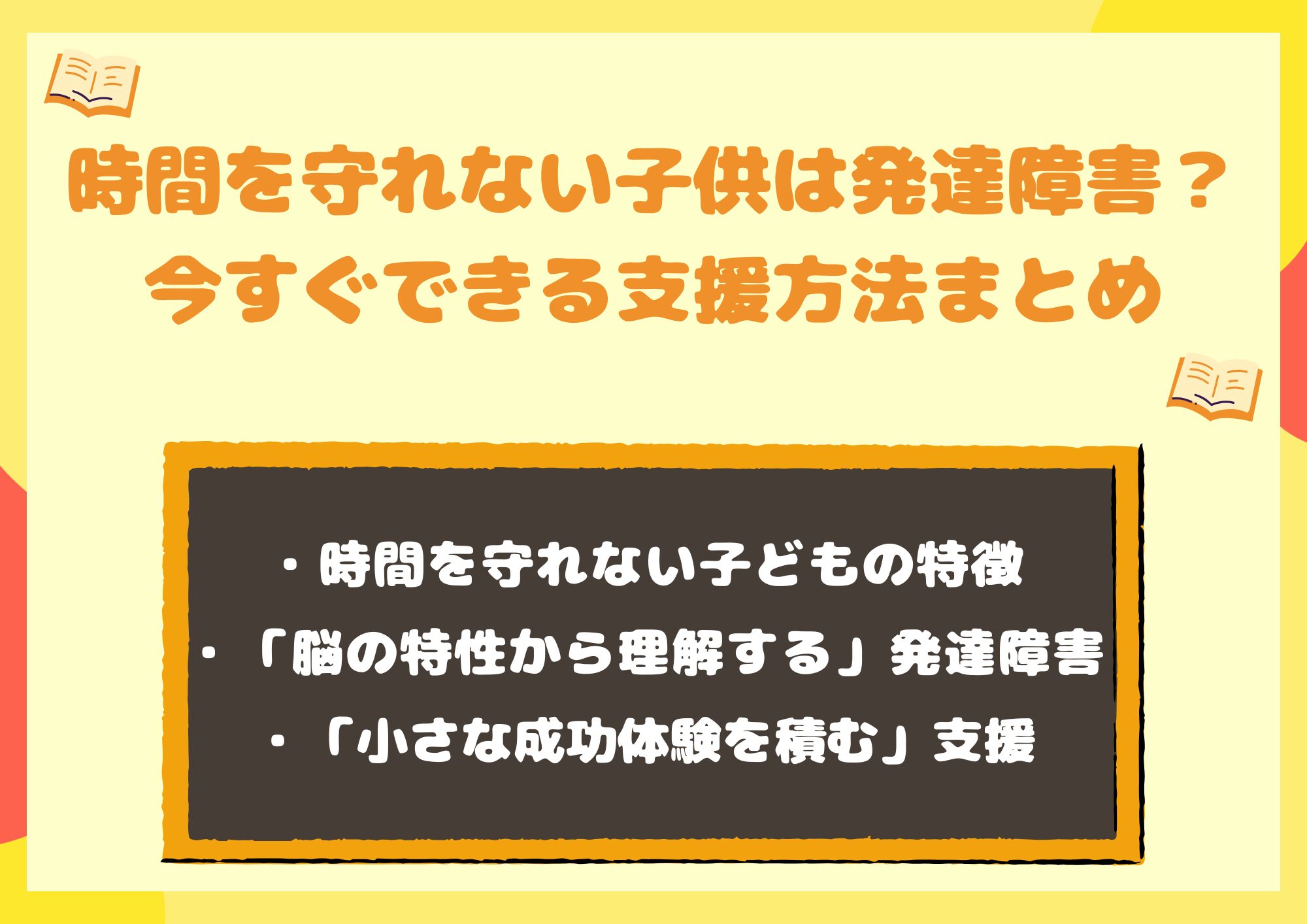
「朝の準備に1時間以上かかる」「約束の時間になっても動き出さない」「何度言っても行動が遅い」そんな悩みを抱えていませんか。
時間を守れない子どもの背景に発達障害の特性があるかもしれないと感じたとき、多くの親御さんは「叱り続ける自分」と「できない子ども」の間で心が引き裂かれるような思いをされています。
この記事では、発達障害で時間が守れない子どもへの具体的な支援方法と、家庭だけでは難しいと感じたときに頼れる家庭教師サービスまで、今日から実践できる内容をお伝えします。
お子さんの「できた!」を増やし、親子で笑顔になれる方法を一緒に見つけていきましょう。
目次
- 発達障害で時間を守れない子どもによく見られる特徴と家庭での困りごと
- なぜ守れないのか「脳の特性から理解する」発達障害と時間感覚の関係
- 今日から始められる「小さな成功体験を積む」具体的な支援方法
- 家庭で無理なく続けられる「習慣化のポイント」と親の心構え
- 学校や専門機関との連携で「より良い環境を作る」ための実践例
- 専門的なサポートを検討する「判断基準」と相談先の選び方
- 発達障害の子どもに寄り添う「おすすめ家庭教師サービス」徹底比較
- 家庭教師のランナー「不登校や環境変化が苦手な子への配慮」が充実
- 家庭教師のトライ「マンツーマンで子どものペースに合わせた」指導体制
- 学研の家庭教師「長年の指導実績に基づく」発達障害への対応力
- 家庭教師のサクシード「柔軟な対応で子どもの特性に寄り添う」指導方針
- 家庭教師ファースト「低価格でも手厚いサポート」を実現する仕組み
- 家庭教師のノーバス「個別カリキュラムで子どもに合わせた」学習計画
- 家庭教師のあすなろ「子どもの自信を育てる」独自の指導メソッド
- 家庭教師学参「プロ講師による専門性の高い」発達支援指導
- オンライン家庭教師Wam「送迎不要で続けやすい」オンライン学習環境
- オンライン家庭教師トウコベ「東大生が寄り添う」個別サポート体制
- オンライン家庭教師マナリンク「プロ講師が子どもの特性を理解した」指導法
- まとめ「一歩ずつ前進する」ための支援と家庭教師活用のポイント
発達障害で時間を守れない子どもによく見られる特徴と家庭での困りごと
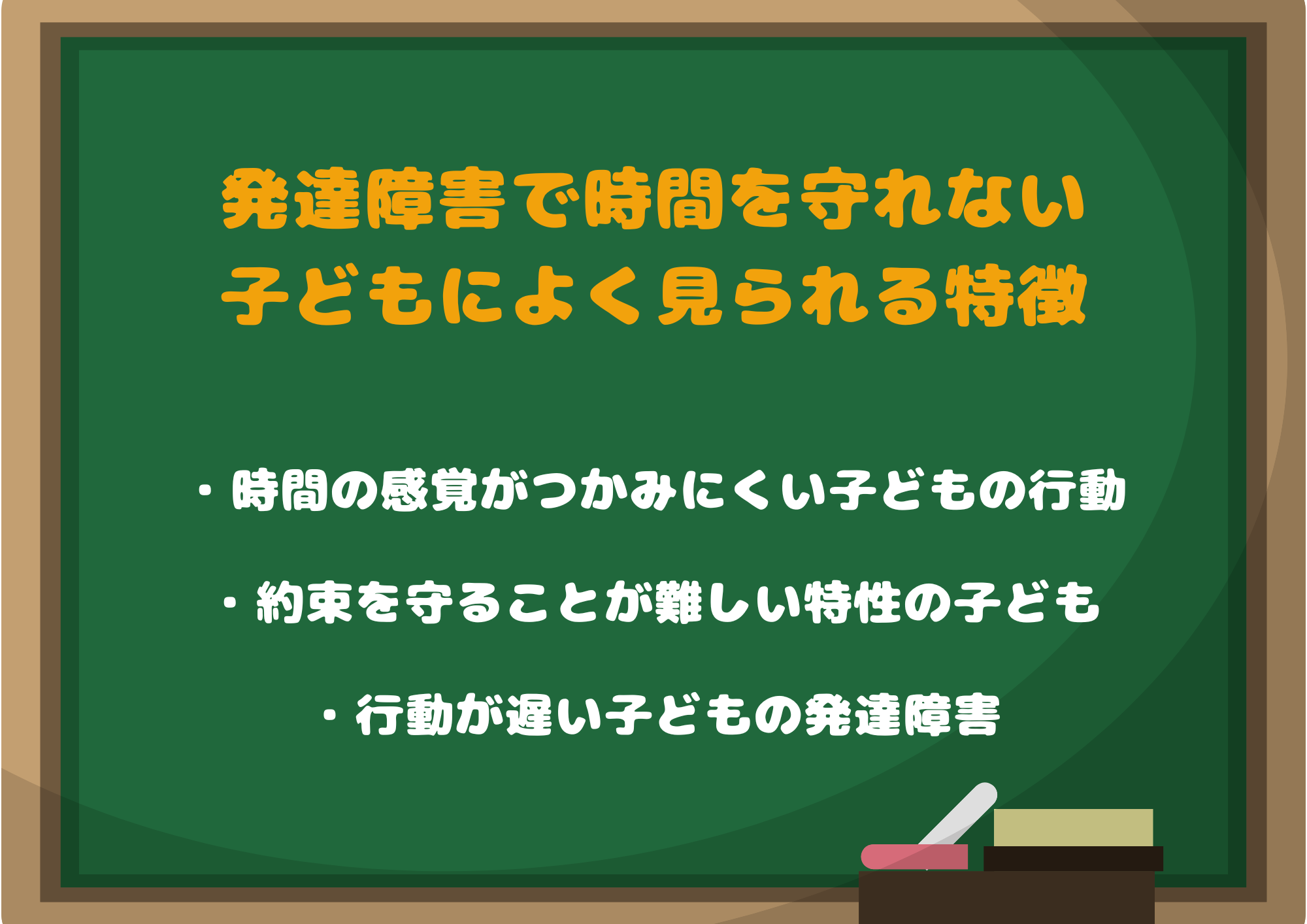
時間を守ることが難しい子どもの発達障害には、ADHDや自閉スペクトラム症(ASD)などがあり、それぞれの特性によって時間感覚の捉え方が異なることがあります。
「うちの子は本当に発達障害なの?」と迷われている方も、まずはお子さんの行動パターンを観察してみることから始めてみましょう。発達障害の診断がなくても、特性を理解することで適切なサポートが可能になる場合があります。
時間の感覚がつかみにくい子どもに多い行動パターンとその理由
- 「あと5分」の体感的理解が難しく、時間の流れを意識しながら行動することが苦手
- 実行機能の特性により「わざと遅い」のではなく脳の働き方の違いが影響
- 今やっていることから次の行動への切り替えに時間がかかる
発達障害の子どもは「あと5分」と言われても、その5分がどのくらいの長さなのか体感的に理解することが苦手な場合があります。
例えば、朝の準備で「着替えに30分、朝食に40分」というように、一つ一つの行動に時間がかかりすぎてしまうのは、時間の流れを意識しながら行動することが難しいためかもしれません。これは「わざと遅い」のではなく、実行機能の特性が影響する場合があります。
また、「今やっていることから次の行動に切り替える」ことも苦手なため、遊びから勉強への移行、テレビから着替えへの切り替えなどで時間がかかることがあります。
約束を守ることが難しい特性のある子どもに見られるサイン
- 覚えているけれど実行できないパターンと約束自体を忘れてしまうパターンがある
- 実行機能やワーキングメモリの課題が影響している可能性
- 目の前の楽しいことに気を取られて約束を後回しにしてしまう
約束を守ることが難しい子どもの発達障害では、「覚えているけれど実行できない」パターンと「そもそも約束自体を忘れてしまう」パターンがあることが指摘されています。
前者は実行機能の課題で、頭では分かっていても体が動かない状態かもしれません。後者はワーキングメモリ(作業記憶)の課題で、新しい情報が入ってくると以前の約束が記憶から抜け落ちてしまうことがあります。
「宿題をやってから遊ぶ」という約束をしても、目の前の楽しいことに気を取られて約束を後回しにしてしまうことも、発達障害の子どもに見られることがあるサインです。
行動が遅い子どもの発達障害で気づきやすい日常の場面
- 朝の支度、入浴、食事の場面で行動の遅さが顕著に現れる
- 過集中や注意散漫が原因となることがある
- 靴下を履くのに10分以上かかるなど日常動作に時間がかかる
行動が遅い子どもの発達障害は、特に朝の支度や入浴、食事の場面で顕著に現れることがあります。
一つのことに集中しすぎて次の行動に移れない状態(いわゆる”過集中”)や、逆に注意が散漫で一つのことに取り組み続けることが難しい状態が原因となることがあります。
例えば、靴下を履くのに10分以上かかったり、歯磨きの途中で手が止まることがあったりする様子が見られたら、発達障害の可能性を考慮してサポート方法を検討する時期かもしれません。
なぜ守れないのか「脳の特性から理解する」発達障害と時間感覚の関係
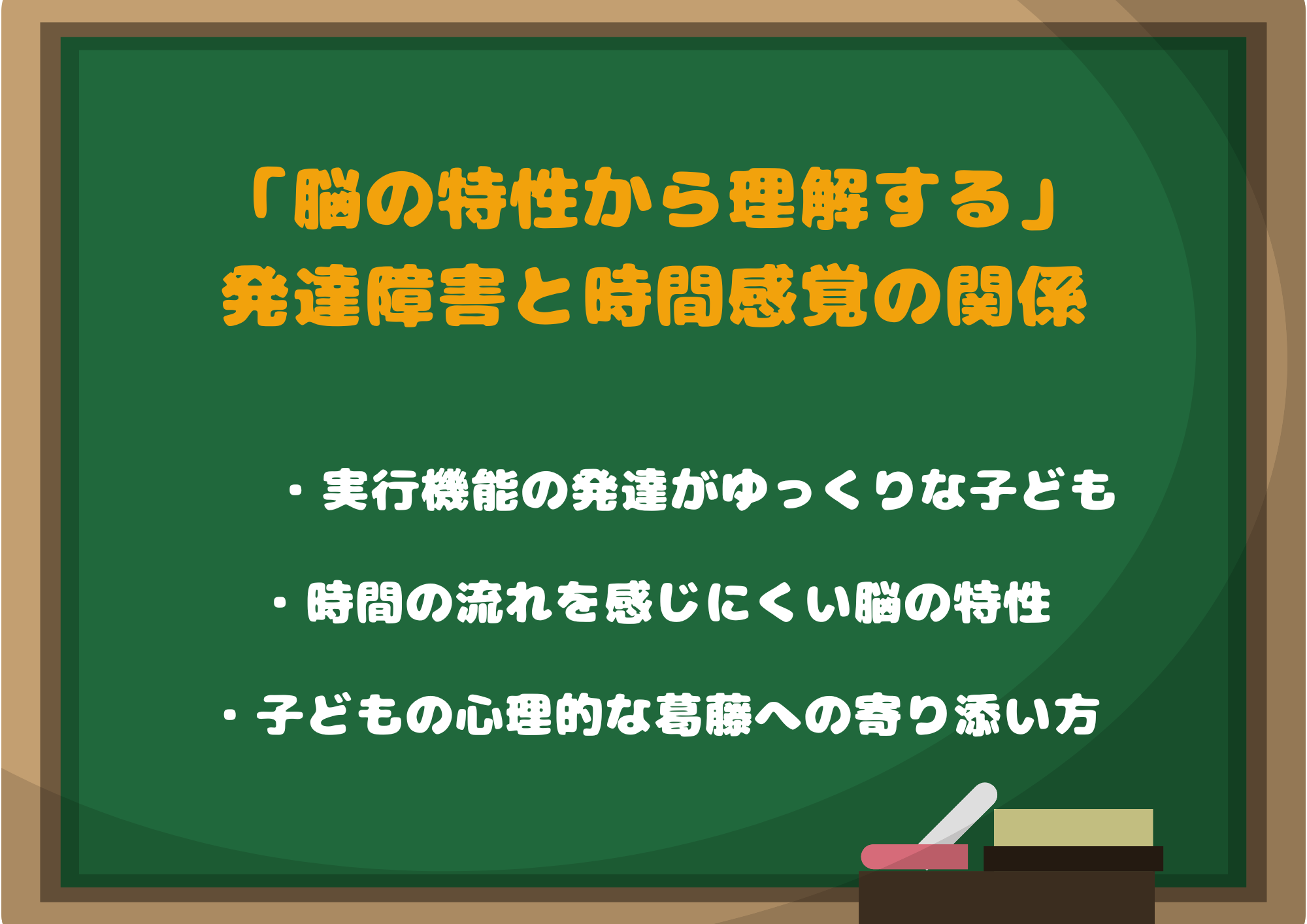
発達障害で時間が守れない背景には、脳の機能的な特性が関わっている可能性があります。
これを理解することで、「怠けている」「やる気がない」という見方から、「脳の働き方が違うだけ」という視点に変わることがあります。親御さん自身の心の負担も軽くなり、お子さんとの関係も改善していく場合があります。
実行機能の発達がゆっくりな子どもへの理解と接し方
- 実行機能(計画、優先順位、時間管理など)の発達がゆっくり
- 「一度に一つずつ」「具体的に」「視覚的に」伝えることが効果的
- 行動を細かく分けて指示することで動きやすくなる
実行機能とは、計画を立てる、優先順位をつける、時間を管理する、感情をコントロールするなど、目標に向かって行動を調整する脳の働きのことです。
発達障害の子どもは、この実行機能の発達がゆっくりな場合があり、「やらなければいけないことは分かっているのに、どこから手をつけていいか分からない」という状態になりやすいことがあります。接し方のポイントは、「一度に一つずつ」「具体的に」「視覚的に」伝えることが効果的とされています。
「部屋を片付けなさい」ではなく、「まずおもちゃを箱に入れよう」というように、行動を細かく分けて指示することで、子どもは動きやすくなる場合があります。
時間の流れを感じにくい脳の特性への配慮ポイント
- 時間の流れを体感的に捉えることが苦手
- 「今」に集中しすぎて「過去」や「未来」を意識することが難しい
- 時間を「見える化」することで意識しやすくなる
発達障害の子どもの中には、時間の流れを体感的に捉えることが苦手な子が多いことが指摘されています。
これは脳の働き方の違いが関与すると指摘されることがあり、「今」に集中しすぎて「過去」や「未来」を意識することが難しいためかもしれません。そのため、「あと10分で出発」と言われても、その10分がどのくらいの長さなのか実感できないことがあります。
配慮のポイントは、時間を「見える化」することです。
アナログ時計の針の動きや、タイマーの減っていく様子など、視覚的に時間の経過が分かるツールを活用することで、子どもも時間を意識しやすくなることがあります。
約束を守りたいのに守れない子どもの心理的な葛藤への寄り添い方
- 本当は約束を守りたいと思っているが脳の特性により行動できない
- 否定的な感情を抱えやすく自己肯定感が下がりやすい
- 「守ろうとしたこと」を認め、次の方法を一緒に考える姿勢が大切
発達障害の子どもも、本当は約束を守りたいと思っていることが多いです。
しかし、脳の特性により思うように行動できず、「また怒られた」「自分はダメな子」という否定的な感情を抱えやすくなることがあります。この心理的な葛藤に寄り添うことが、子どもの自己肯定感を守る上で重要とされています。
「守れなかったこと」を責めるのではなく、「守ろうとしたこと」を認め、「次はどうすればうまくいくか」を一緒に考える姿勢が大切です。失敗を成長の機会と捉え、スモールステップで成功体験を積み重ねていくことが推奨されています。
今日から始められる「小さな成功体験を積む」具体的な支援方法
発達障害で時間を守れない子どもへの支援は、特別な道具や専門知識がなくても、家庭で今すぐ始められることがあります。
大切なのは、子どもの特性に合わせて環境を整え、「できた!」という成功体験を少しずつ増やしていくことです。ここでは、多くの家庭で効果があったとされる具体的な方法をご紹介します。
視覚的なスケジュール表で行動を「見える化」するコツ
- 朝の準備を順番に並べて写真やイラストで表示する
- 完了した項目にシールを貼ることでモチベーション向上
- 100円ショップの材料で簡単に作成可能
視覚的なスケジュール表は、時間を守ることが難しい子どもにとって有効な支援ツールになることがあります。
朝の準備なら「起床→着替え→朝食→歯磨き→持ち物チェック」というように、行動を順番に並べて、写真やイラストで表示します。100円ショップのホワイトボードとマグネットシートで簡単に作ることができます。
完了した項目にシールを貼ったり、マグネットを移動させたりすることで、「やった感」が目に見えて、子どものモチベーション向上につながることがあります。
最初は親が一緒に確認しながら進め、慣れてきたら子どもが自分でチェックできるようにしていくとよいでしょう。
アナログタイマーを使った「あと何分」がわかる時間管理術
- 視覚的なタイマーで時間の経過を直感的に把握
- デジタル表示より赤い部分が減っていく様子の方が理解しやすい
- 短い時間(5分程度)から始めて徐々に延ばす
デジタル表示の「10:00」という数字よりも、アナログタイマーの赤い部分が減っていく様子の方が、発達障害の子どもには理解しやすい場合があります。
視覚的なタイマーを使えば、「赤いところがなくなったら片付け終了」というように、時間の経過を直感的に把握できることがあります。キッチンタイマーでも代用可能ですが、音が鳴る前に「あと5分だよ」「あと1分」と声かけすることで、急な終了による混乱を防げる場合があります。
最初は短い時間(5分程度)から始めて、徐々に時間を延ばしていくのがコツです。
行動が遅い子どもの発達障害に効果的な声かけと環境調整
- 「早くして」ではなく具体的な行動を伝える
- 前日の夜に翌日の準備をして朝の行動をスムーズに
- 動線上に視覚的な手がかりを配置する
行動が遅い子どもへの声かけは、「早くして」ではなく「○○をしよう」と具体的な行動を伝えることが効果的とされています。
また、環境調整も重要で、例えば着替えなら、前日の夜に翌日の服を準備し、上下セットで椅子に置いておくと、朝の行動がスムーズになることがあります。ランドセルの横に持ち物チェックリストを貼る、玄関に「今日の予定カード」を置くなど、動線上に視覚的な手がかりを配置することも効果的な場合があります。
テレビやゲームなど、気を散らすものは朝の準備が終わるまで見えない場所に置くなど、物理的な環境を整えることで、子どもが集中しやすくなることがあります。
手順を細かく分けて「できた」を増やす段階的アプローチ
- 大きな目標を小さなステップに分解して達成感を味わいやすくする
- 各ステップができたらすぐに「できたね!」と認める
- 最初は1つずつ、徐々にステップをつなげていく
大きな目標を小さなステップに分解することで、発達障害の子どもも達成感を味わいやすくなることがあります。
例えば「宿題をする」という目標なら、「①机の上を片付ける」「②教科書を開く」「③鉛筆を持つ」「④1問目を読む」というように、細かく分けます。各ステップができたら、すぐに「できたね!」と認めることが重要です。
最初は1つのステップごとに休憩を入れても構いません。
徐々にステップをつなげていき、最終的に一連の流れで行動できるようになることを目指します。
家庭で無理なく続けられる「習慣化のポイント」と親の心構え
支援方法を知っていても、毎日続けることは簡単ではありません。
親御さん自身が無理をしてしまうと、かえって親子関係がギクシャクしてしまうこともあります。ここでは、家庭で無理なく支援を続けるためのポイントと、親御さん自身の心のケアについてお話しします。
毎日のルーティンに組み込む仕組み化の実例
- 既存の生活リズムに新しい支援方法を組み込む
- 家族全員で取り組む「家族ルーティン」にする
- 夕食後の10分間を「明日の準備タイム」に設定するなど
新しい支援方法を「特別なこと」として始めるのではなく、既存の生活リズムに組み込むことが継続の秘訣とされています。
例えば、朝食後の歯磨きタイムに「持ち物チェック」を組み合わせる、お風呂上がりに「明日の準備タイム」を設定するなど、既にある習慣に新しい要素を追加していきます。家族全員で取り組む「家族ルーティン」にすることで、子どもも「みんなでやること」として受け入れやすくなる場合があります。
例えば、夕食後の10分間を「明日の準備タイム」として、親も一緒に翌日の準備をする時間にすれば、子どもも自然に参加できることがあります。
親が自分を責めずに済む「特性理解」という考え方
- 発達障害は脳の機能的な特性であり育て方が原因ではない
- 「なぜできないの」から「どうすればできるか」への視点転換
- 完璧を求めず小さな進歩を喜び合える関係を築く
「私の育て方が悪かったのかも」と自分を責める親御さんは少なくありません。
しかし、発達障害は脳の機能的な特性であり、育て方が原因ではないとされています。むしろ、特性を理解して適切な支援をすることで、子どもは成長していく可能性があります。
「うちの子は時間の感覚が育ちにくい特性がある」と理解することで、「なぜできないの」という苛立ちから、「どうすればできるようになるか」という建設的な視点に変わることがあります。
完璧を求めず、小さな進歩を喜び合える関係を築いていくことが大切です。
小さな変化を見逃さない「記録の取り方」と振り返り方法
- 「今日できたこと」を短く記録することで成長の軌跡が見える
- スマートフォンのメモ機能で1日1行でも効果的
- 週末の家族での振り返りで子どもの自己肯定感向上
日々の小さな変化は、意識しないと見逃してしまいがちです。
簡単な記録表を作って、「今日できたこと」「工夫したこと」「子どもの反応」を短く記入するだけで、成長の軌跡が見えてくることがあります。スマートフォンのメモ機能や、カレンダーアプリを使って、1日1行でも構いません。
週末に家族で振り返りの時間を作り、「今週頑張ったこと」を共有することで、子どもの自己肯定感向上につながることがあります。
記録を見返すことで、親御さん自身も「前進している」ことを実感でき、支援を続けるモチベーションにつながる場合があります。
学校や専門機関との連携で「より良い環境を作る」ための実践例
家庭での支援と同じくらい大切なのが、学校や専門機関との連携です。
子どもが過ごす時間の多くを占める学校での配慮があれば、子どもの困り感は軽減される場合があります。ここでは、スムーズな連携のための具体的な方法をご紹介します。
担任の先生への相談文例と「配慮をお願いする」ときの伝え方
- 批判や要求ではなく「協力のお願い」というスタンスで伝える
- 家庭での工夫と成果を具体的に示す
- 実現可能な範囲での配慮をお願いする
学校への相談は、批判や要求ではなく「協力のお願い」というスタンスで伝えることが大切です。
以下のような文例を参考にしてみてください。
「いつもお世話になっております。○○の時間管理について、ご相談があります。家庭では視覚的なタイマーを使って改善が見られているので、可能であれば学校でも似たような支援をお願いできないでしょうか」
具体的な配慮例として、「板書を写す時間を少し長めに取っていただく」「提出物の締切を視覚的に示していただく」など、実現可能な範囲でお願いすることがポイントです。
面談の際は、家庭での工夫と成果を写真や記録で示すと、先生も理解しやすくなることがあります。
地域の相談窓口や療育センターを活用するタイミングと準備
- 家庭と学校の両方で困り感がある場合が活用の目安
- 3か月以上同じ課題が続いている場合も検討時期
- 「いつから」「どんな場面で」「頻度」を具体的にメモしておく
地域の発達相談窓口や療育センターは、診断の有無に関わらず相談できる場所が多くあります。
活用のタイミングは、「家庭と学校の両方で困り感がある」「3か月以上同じ課題が続いている」「親子関係に影響が出始めている」などが目安とされています。相談前の準備として、子どもの困りごとを具体的にメモしておくことをお勧めします。
「いつから」「どんな場面で」「どのくらいの頻度で」という情報があると、専門家も適切なアドバイスをしやすくなる場合があります。
専門的なサポートを検討する「判断基準」と相談先の選び方
家庭や学校での支援だけでは限界を感じたとき、専門的なサポートを検討する時期かもしれません。
受診や相談のタイミングに「早すぎる」ということはないとされています。早期の適切な支援が、子どもの将来に良い影響をもたらす可能性があります。
家庭だけでは難しいと感じたときの受診タイミングの目安
- 毎日同じことで注意している、学校からも同様の指摘がある
- 親子関係が悪化している、子ども自身が困っている
- 3つ以上当てはまる場合は専門機関への相談を検討
受診を検討する目安として、以下のような状況が3つ以上当てはまる場合は、専門機関への相談を検討してもよいかもしれません。
「毎日同じことで注意している」「学校からも同様の指摘を受けている」「兄弟姉妹や同年齢の子と比べて明らかに差がある」「親子関係が悪化している」「子ども自身が困っている様子がある」「学習面でも遅れが目立ち始めた」
診断を受けることが目的ではなく、子どもに合った支援方法を見つけることが大切です。困りごとが続く場合は、医療機関や支援機関への相談を検討することをお勧めします。
医療機関や療育サービスを利用する際の「事前準備」
- 妊娠中や出生時の様子、発達の経過を整理
- 現在の困りごとの具体例、学校での様子を準備
- 公的サービスと民間サービスの特徴を理解して選択
医療機関を受診する際は、以下の情報を整理しておくとスムーズです。
「妊娠中や出生時の様子」「発達の経過(首すわり、歩き始めなど)」「現在の困りごとの具体例」「学校での様子(通知表や連絡帳のコピー)」
これらの情報は、母子手帳を見返したり、家族で話し合ったりして準備しましょう。
療育サービス利用時の心構えと期待値の設定
療育は「治療」ではなく「発達を促す支援」とされています。
即効性を期待するのではなく、長期的な視点で子どもの成長を見守ることが大切です。療育で学んだことを家庭でも実践し、一貫した支援を続けることで、効果が期待できる場合があります。
費用や通院頻度についての確認ポイント
療育サービスには、自治体が運営する公的なものと、民間のものがあります。
公的サービスは費用が安い反面、待機期間が長いことがあります。民間サービスは費用が高めですが、すぐに利用開始できることが多いです。
通院頻度や送迎の負担も考慮して、家族で無理なく続けられる選択をしましょう。
発達障害の子どもに寄り添う「おすすめ家庭教師サービス」徹底比較
時間を守ることが難しい、約束を守ることが難しい、行動が遅いといった発達障害の特性を持つ子どもには、個別対応できる家庭教師が効果的な場合があります。
学校や塾では難しい「その子のペースに合わせる」指導が可能で、自宅という安心できる環境で学習できます。ここでは、発達障害の子どもへの対応実績があるとされる家庭教師サービスを詳しくご紹介します。
家庭教師のランナー「不登校や環境変化が苦手な子への配慮」が充実

- 長年の運営実績と発達障害への理解を持つスタッフ体制
- 教材販売を前提としない方針で月謝のみの明朗会計
- オンライン指導対応で環境の変化が苦手な子どもも安心
家庭教師のランナーは、長年の運営実績があり、「勉強が苦手な子専門」として発達障害や不登校の子どもへの指導に力を入れています。
発達障害への理解を持つスタッフが担当する体制を整え、子どもの特性を理解した上で適した先生をマッチングする仕組みがあります。
月謝は学年・回数等で異なり、教材販売を前提としない方針を案内しています。兄弟同時指導に割引が設定される場合があり、発達障害の兄弟を持つ家庭にも利用されています。
オンライン指導にも対応しており、環境の変化が苦手な子どもでも、慣れた自宅の環境で学習できます。
ランナーの無料体験はこちら!家庭教師のトライ「マンツーマンで子どものペースに合わせた」指導体制

- 全国規模で多様な講師が在籍し経験豊富な先生を選べる
- 専任の教育プランナーが子どもの特性を把握してカリキュラム作成
- 講師交代に応じる運用で人見知りの強い子どもも始めやすい
全国規模で展開する家庭教師のトライは、多様な講師が在籍し、発達障害の子どもに対応できる経験豊富な先生を選べる仕組みがあります。
専任の教育プランナーが家庭と教師の間に入り、子どもの特性や学習状況を把握した上で、カリキュラムを作成します。料金は地域・条件により異なります。
講師交代に応じてもらえる運用があるので、発達障害で人見知りが強い子どもでも始めやすいかもしれません。
学研の家庭教師「長年の指導実績に基づく」発達障害への対応力

- 教育大手グループのノウハウを生かした個別指導
- 子どもの特性に合わせた先生選定と研修体制
- オンライン指導対応で全国どこからでも受講可能
教育大手の学研グループが運営する家庭教師サービスは、グループの教育ノウハウを生かした個別指導を提供しています。
多様な講師が在籍し、子どもの特性に合わせて先生を選定し、研修を受けた指導を提供する体制があります。料金は学年・地域・回数などの条件で異なります。
学研ブランドの信頼性と、本部スタッフによるサポート体制が特徴です。オンライン指導にも対応し、全国どこからでも指導を受けることができます。
家庭教師のサクシード「柔軟な対応で子どもの特性に寄り添う」指導方針

- 体験担当が継続担当となる運用で初回から安心
- 1回の授業で複数科目指導可能で集中力に配慮
- 上場企業運営の安心感と柔軟な対応力
上場企業が運営する家庭教師のサクシードは、多数の教師が在籍し、発達障害の子どもへの指導経験がある先生が在籍しています。
体験担当が継続担当となる運用がある場合があり、初回から子どもが安心して授業を受けられる仕組みがあり、発達障害で環境の変化が苦手な子どもにも適している場合があります。
料金はプランにより異なり、入会時費用の取り扱いもプランによって異なる場合があります。1回の授業で複数科目を指導可能なので、集中力の持続が難しい子どもでも効率的に学習できることがあります。
家庭教師ファースト「低価格でも手厚いサポート」を実現する仕組み

- 比較的低価格な料金設定で始めやすい
- 実際の担当講師で無料体験が可能
- 不登校支援プランで心理面のサポートも期待
家庭教師ファーストは、比較的低価格な料金設定で、発達障害の子どもへの対応も行っています。
実際に担当する先生で無料体験を行える場合があり、子どもとの相性を確認してから始められることがあります。不登校支援に対応するプランが用意される場合があり、学習面だけでなく心理面のサポートも期待できるかもしれません。
料金体系や費用項目はプランによって異なります。
家庭教師のノーバス「個別カリキュラムで子どもに合わせた」学習計画

- 個別指導塾も運営する豊富な指導ノウハウ
- 教師と学習プランナーのダブル体制でサポート
- オンライン指導サービスで対面同様の指導を提供
関東・東海地方で展開する家庭教師のノーバスは、個別指導塾も運営しているため、発達障害の子どもへの指導ノウハウがあります。
教師と学習プランナーのダブル体制で、子どもの特性に合わせたカリキュラムを作成する仕組みがあります。料金は条件により異なります。
オンライン指導サービスも提供しており、対面と同様の指導を自宅で受けられる場合があります。
家庭教師のあすなろ「子どもの自信を育てる」独自の指導メソッド
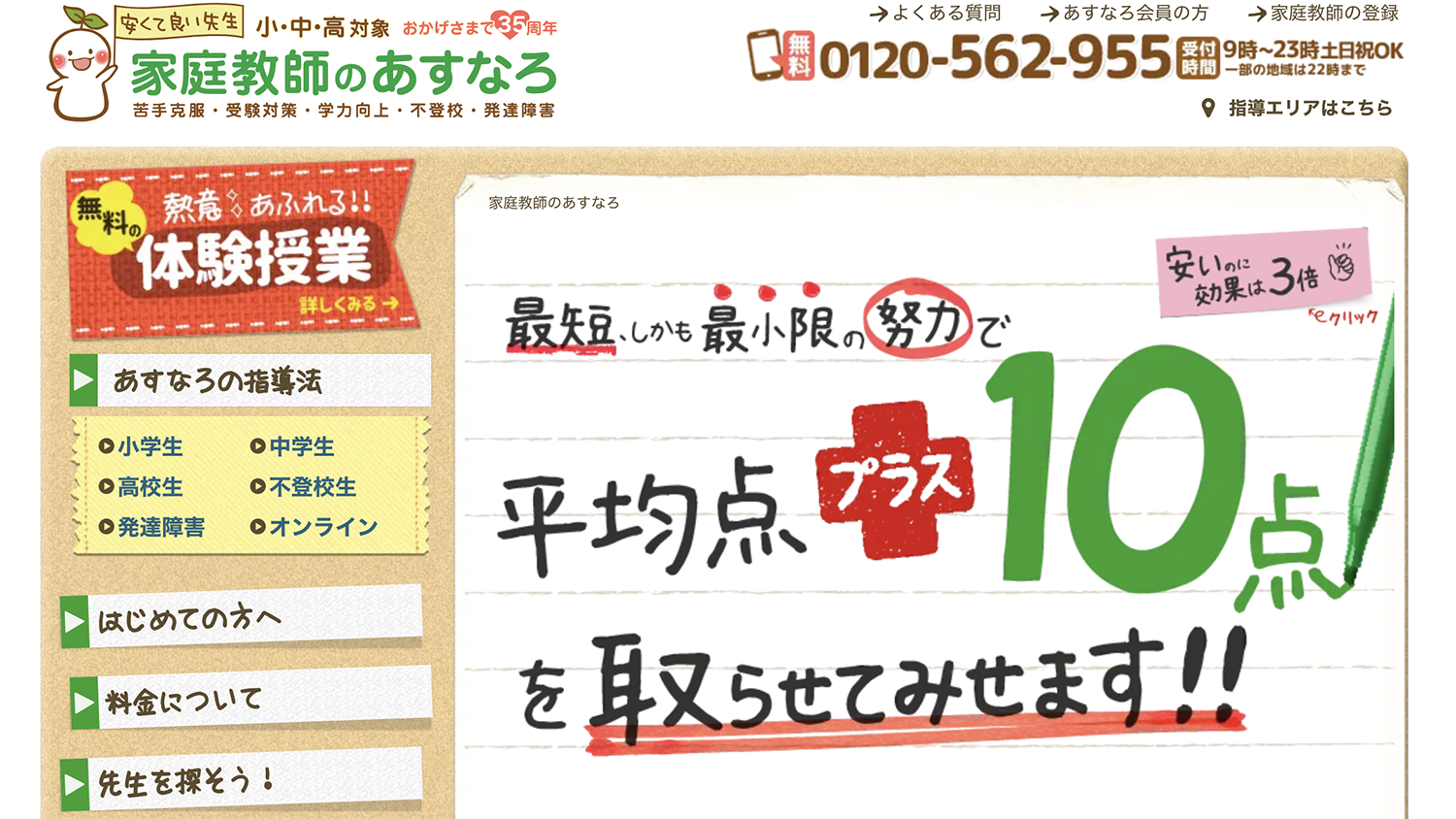
- 勉強が苦手な子専門で心理面のケアを重視
- 大学生中心の若い先生で親近感のある指導
- 連絡ツールで授業外でも学習相談が可能
「勉強が苦手な子専門」を長年続けている家庭教師のあすなろは、発達障害で自信を失いがちな子どもの心理面をケアする指導を行っています。
大学生中心の若い先生が多く、親近感のある指導で子どものやる気を引き出す工夫をしています。連絡ツールで学習相談ができる仕組みがある場合があり、時間を守ることが難しい子どもの「今やりたい」気持ちにも対応できることがあります。
料金は学年やプランにより異なり、基礎固めを重視した指導方針で、学習の土台を築くサポートを行います。
家庭教師学参「プロ講師による専門性の高い」発達支援指導

- プロ講師中心の専門性の高い指導
- 無料体験で相性確認後に契約可能
- 授業回数や時間の柔軟な調整が可能
長年の運営実績を持つ家庭教師学参は、プロ講師中心の指導を掲げています。
発達障害の子どもへの指導経験がある講師を選べる場合があり、無料体験で相性を確認してから契約できることがあります。料金は講師やプランにより異なります。
部活や習い事に合わせて授業回数や時間を調整できる場合があるため、時間管理が苦手な子どもでも無理なく続けられることがあります。
オンライン家庭教師Wam「送迎不要で続けやすい」オンライン学習環境

- オンライン専門の独自開発システムで集中しやすい環境
- 送迎不要で時間管理が苦手な子どもも受講しやすい
- 幅広いバックグラウンドの講師が在籍
オンライン専門の家庭教師Wamは、独自開発のシステムで、発達障害の子どもでも集中しやすい学習環境を提供する場合があります。
画面共有や双方向のやり取りに最適化されたシステムで、対面授業と同様の指導を目指しています。料金は学年やプランにより異なります。
送迎の負担もなく、時間を守ることが苦手な子どもでも自宅から受講できます。幅広いバックグラウンドの講師が在籍し、子どもの特性を理解した指導を行うことがあります。
オンライン家庭教師トウコベ「東大生が寄り添う」個別サポート体制
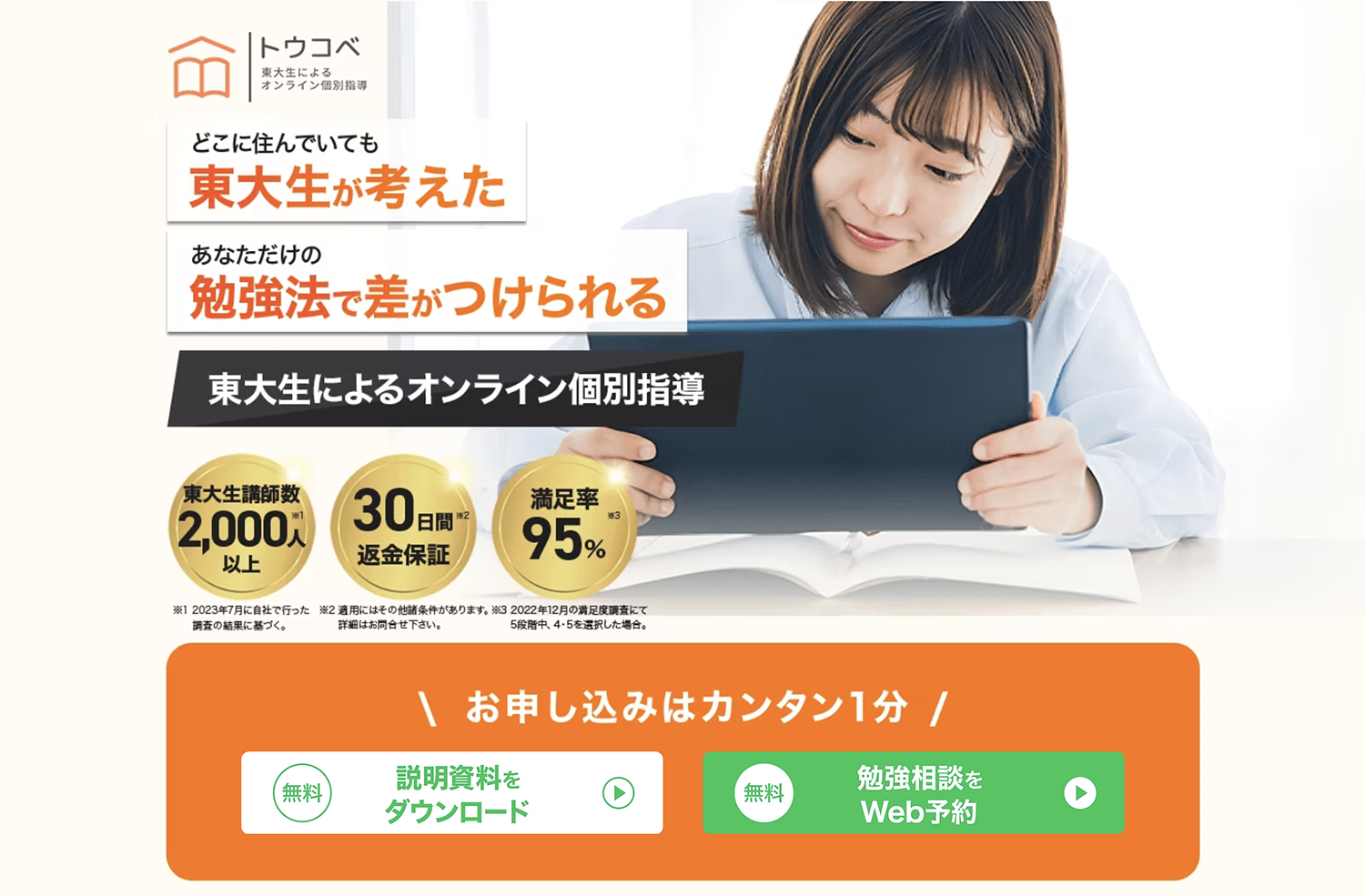
- 学生講師中心で子どもの特性に合わせた指導
- トライアル条件で新しい環境が苦手な子どもも試しやすい
- 効率的な学習方法をカスタマイズして提供
学生講師中心の個別指導を行うトウコベは、多数の講師が在籍し、発達障害の子どもにも対応しています。
効率的な学習方法を、子どもの特性に合わせてカスタマイズして指導する場合があります。トライアル条件が設けられる場合があり、発達障害で新しい環境になじみにくい子どもでも、試すことができる仕組みがあります。
料金は条件により異なり、利用者の評価に関する案内がある場合があります。
オンライン家庭教師マナリンク「プロ講師が子どもの特性を理解した」指導法
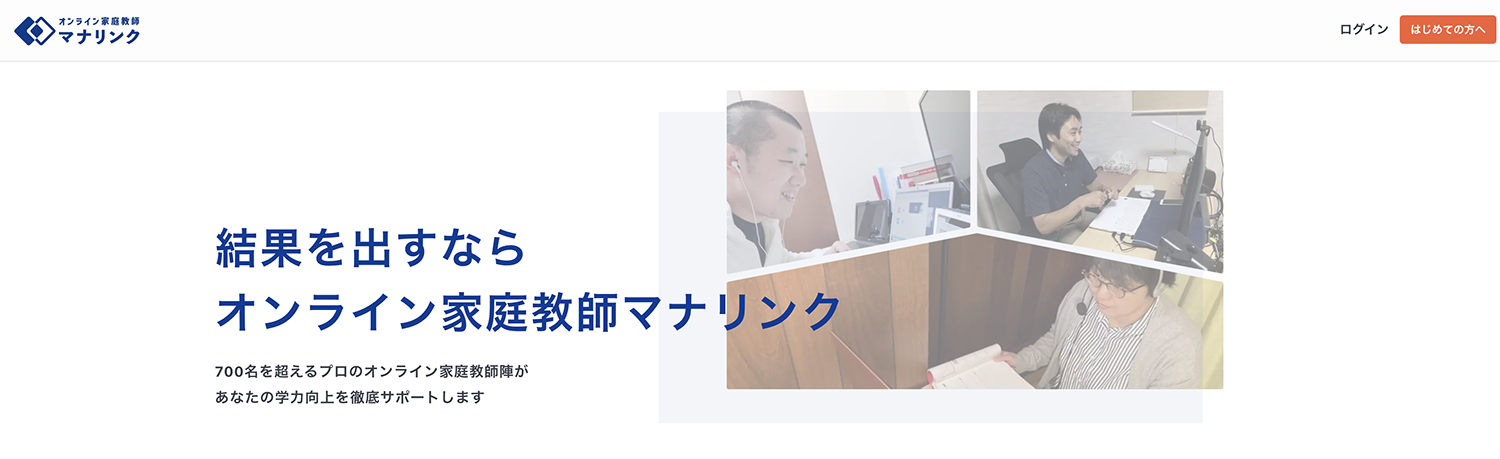
- 社会人講師中心で講師を自分で選べるシステム
- 講師のプロフィールや指導動画で事前確認可能
- 専用アプリで授業外でも質問や相談が可能
主に社会人講師が多いマナリンクは、発達障害の子どもへの指導経験がある先生を自分で選べるシステムがあります。
サイト上で講師のプロフィールや指導動画を確認でき、子どもの特性に合った先生を見つけやすくなっています。料金や費用項目は講師・プランにより異なります。
専用アプリで講師と直接やり取りでき、授業外でも質問や相談ができる場合があるため、約束を守ることが難しい子どもの「今聞きたい」にも対応可能な場合があります。
まとめ「一歩ずつ前進する」ための支援と家庭教師活用のポイント
- ・発達障害の特性は脳の機能的な違いによるもので「怠け」ではない
- ・視覚的なスケジュール表やタイマーの活用で時間管理をサポート
- ・小さな「できた」を積み重ねて親子で一緒に成長していく
- ・学校や専門機関との連携で子どもの困り感を軽減
- ・家庭教師サービスは個別対応で子どものペースに合わせた指導が可能
- ・各家庭の条件に合った支援方法と指導形態を選ぶことが大切
時間を守ることが難しい、約束を守ることが難しい、行動が遅いといった発達障害の特性は、決して「怠けている」わけではなく、脳の機能的な違いによる場合があります。
この記事でお伝えした視覚的なスケジュール表やアナログタイマーの活用、手順の細分化といった具体的な支援方法は、今日からでも始められます。
大切なのは、完璧を求めず、小さな「できた」を積み重ねながら、親子で一緒に成長していくことです。
家庭での支援だけでは限界を感じたときは、学校との連携や専門機関への相談も視野に入れましょう。特に家庭教師サービスは、子どもの特性に合わせた個別指導が可能で、自宅という安心できる環境で学習を進められるメリットがあります。
家庭教師のランナーなら、発達障害への理解を持つスタッフによるサポートを受けられる場合があり、長年の運営実績に基づいた指導が期待できます。
お子さんの特性を理解し、適切な支援を続けることで、前進していける可能性があります。焦らず、比べず、その子のペースで一歩ずつ進んでいきましょう。
各家庭教師サービスの最新情報を確認し、ご家庭の条件に合う指導形態を選ぶことをお勧めします。
ランナーの無料体験はこちら!