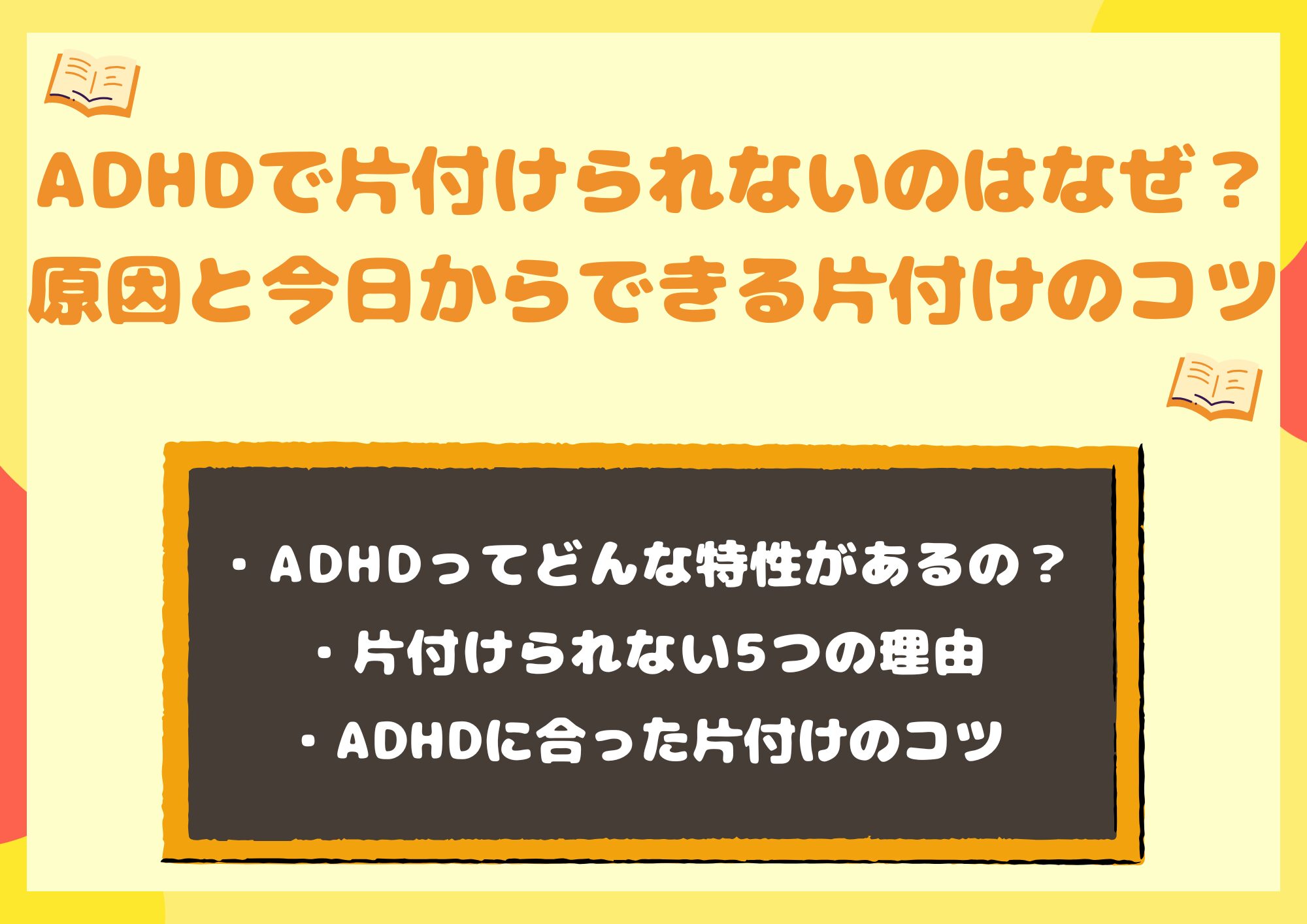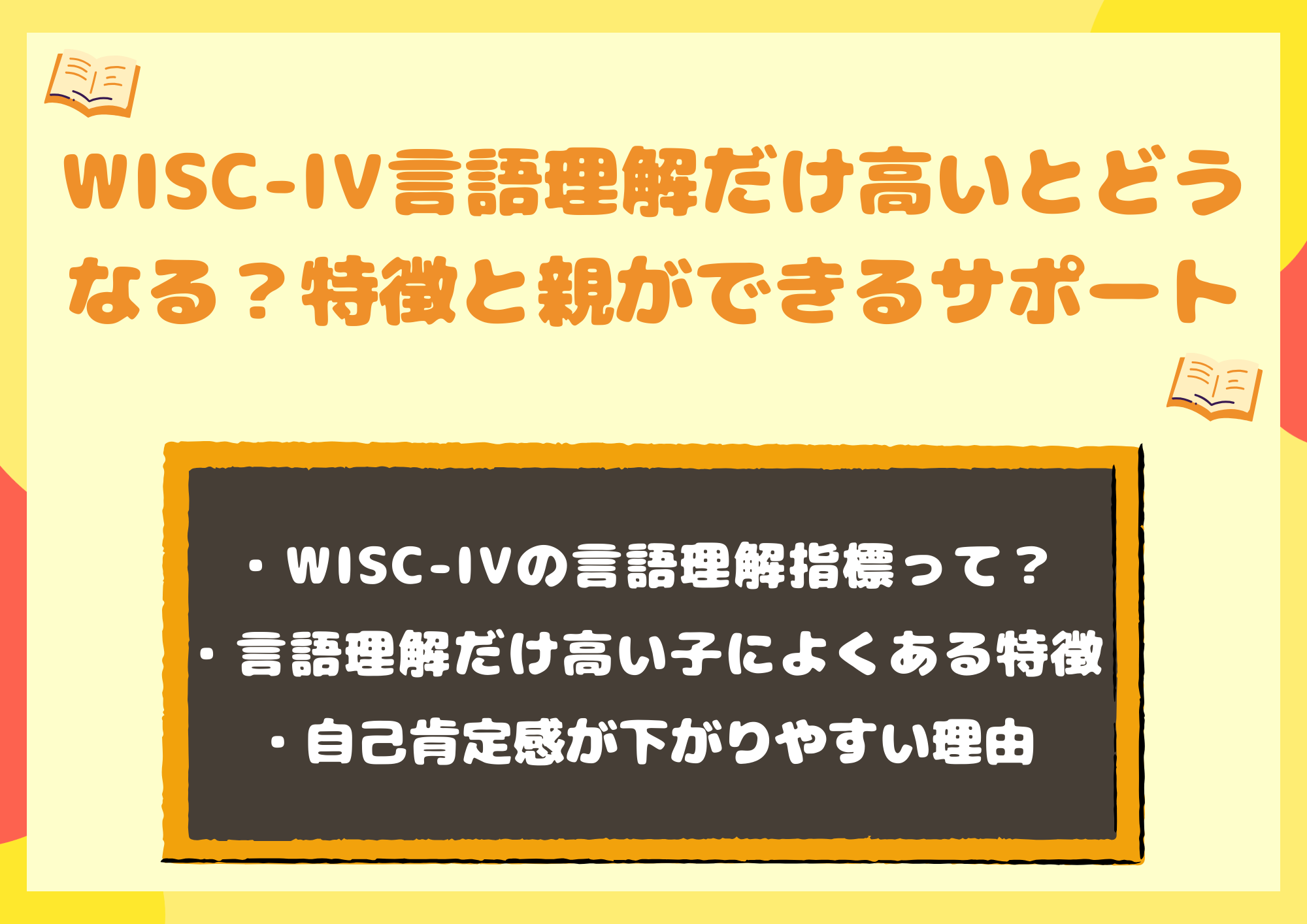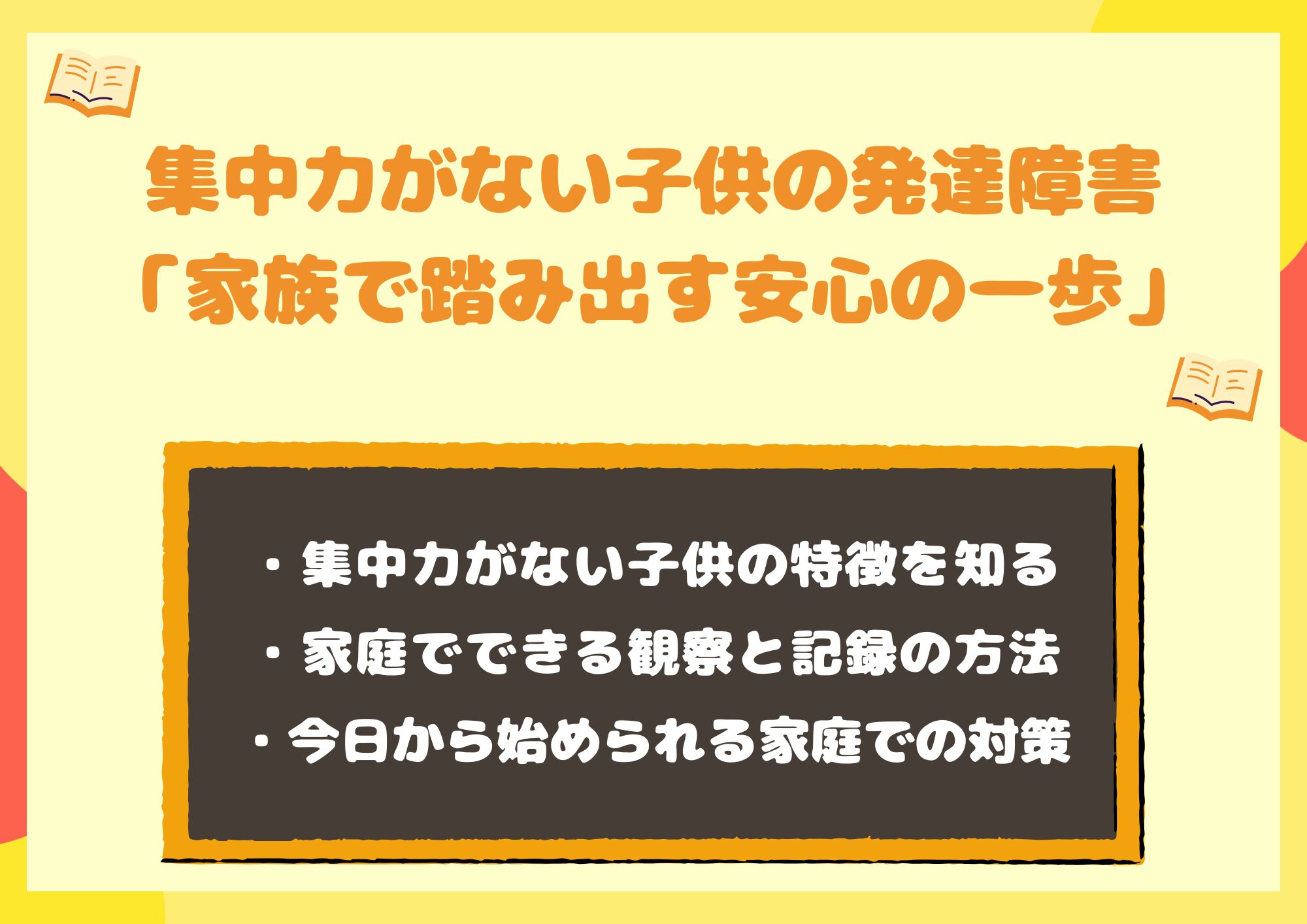- 発達障害向けの家庭教師
忘れ物の多い子どもと発達障害の関係「安心して始められる家庭での工夫」
2025.09.27
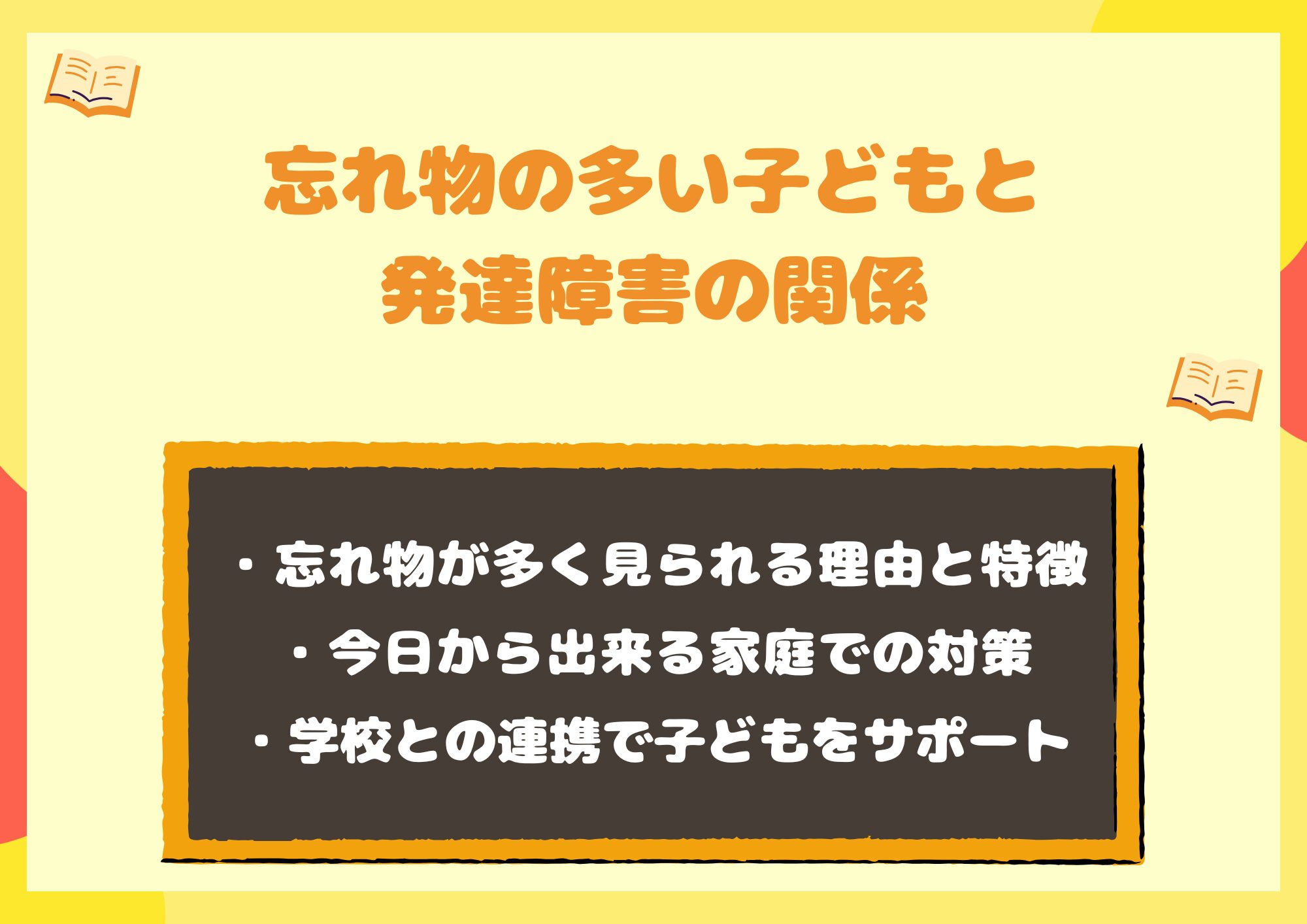
毎朝、お子さんの忘れ物チェックに追われて疲れていませんか。
連絡帳や宿題、体操服など、学校から「また忘れ物がありました」という連絡を受けるたびに、叱ってしまう自分に罪悪感を感じている保護者も多いのではないでしょうか。
実は、子どもの忘れ物が多いことと発達障害には深い関係があり、叱るだけでは解決しないケースもたくさんあります。
大切なのは、お子さんの特性を理解し、忘れ物を防ぐ「仕組み」を家庭に作ることです。
この記事では、発達障害のある子どもの忘れ物対策や片付けられない子どもへの具体的な対策方法を、今日から実践できる形でお伝えします。
家庭教師のランナーでは、発達特性に配慮した個別指導で、お子さんの「できた!」という成功体験を積み重ねるサポートを行っています。
ランナーの無料体験はこちら!目次
発達障害のある子どもに忘れ物が多く見られる理由と特徴を理解する
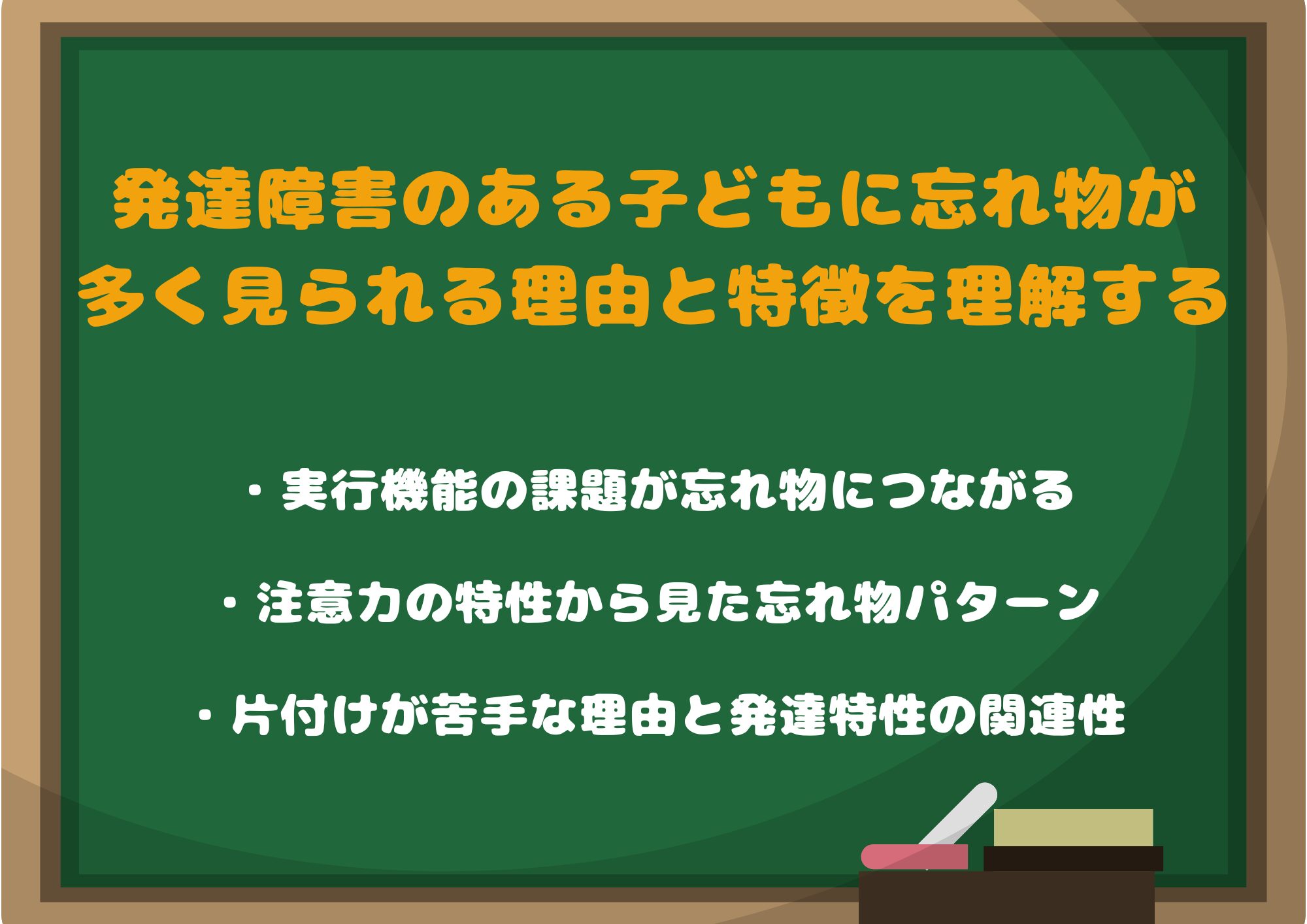
発達障害のある子どもに忘れ物が多いのは、決して「だらしない」や「やる気がない」からではありません。
脳の実行機能という、計画を立てたり、優先順位をつけたり、記憶を保持したりする働きに特性が影響する場合があります。ADHDやASDなどの発達障害では、この実行機能の働き方が定型発達の子どもとは異なることが研究で示唆されています。
お子さんが忘れ物をしてしまうのは、努力不足ではなく、脳の特性によるものであることも少なくありません。
実行機能の課題が忘れ物につながるメカニズムを知る
- 実行機能は計画・優先順位・記憶保持などの脳の働き
- 発達障害では準備から持参までの一連の流れが困難な場合がある
- ワーキングメモリの個人差により情報が失念しやすくなることも
実行機能とは、目標に向かって計画的に行動するための脳の司令塔のような働きです。
発達障害のある子どもは、この機能に課題があるため、「明日の持ち物を確認する」「準備した物を覚えておく」「朝、持っていく」という一連の流れがうまくできないことがあります。例えば、前日に準備をしても、朝になると別のことに気を取られてしまい、準備した物を忘れてしまうことがよくあります。
ワーキングメモリという一時的に情報を保持する機能の容量や働きの個人差により、「体操服を持っていく」という情報が、朝食を食べている間に失念しやすくなることがあります。
このメカニズムを理解することで、単に「気をつけなさい」と言うだけでは解決しないことが分かります。
注意力の特性から見た忘れ物パターンの把握方法
- 選択的注意と持続的注意の2つの特性が影響
- 必要な情報より興味のあるものに注意が向きやすい
- 1週間の記録で曜日別の忘れ物パターンを発見できる
発達障害のある子どもの注意力には、「選択的注意」と「持続的注意」という2つの特性があります。
選択的注意の課題があると、必要な情報とそうでない情報を区別することが難しく、大切な持ち物よりも興味のあるものに注意が向いてしまうことがあります。持続的注意の課題では、準備の途中で集中が切れてしまい、最後まで完了できないことがあります。
お子さんの忘れ物パターンを1週間記録してみると、「月曜日の体育の日に多い」「金曜日の図工の準備が苦手」など、特定の傾向が見えてきます。
パターンが分かれば、その日だけ特別な対策を取ることで、忘れ物を大幅に減らすことができます。
片付けが苦手な理由と発達特性の関連性を理解する
- 空間認知や分類の苦手さが片付けの困難に関連
- 「使ったら戻す」の行動連鎖の自動化が難しい
- 感覚過敏により片付け自体がストレスになる場合も
発達障害のある子どもが片付けられないのは、空間認知や分類の苦手さが関連する場合があります。
物の定位置を決めても、視覚的に「どこに何を置くか」をイメージすることが難しく、結果的に物が散乱してしまうことがあります。また、「使ったら戻す」という行動の連鎖を自動化することも苦手で、意識的に努力しても続けることが困難な場合があります。
さらに、感覚過敏がある場合は、物の手触りや見た目に強く反応してしまい、片付けること自体がストレスになることもあります。
これらの特性を理解した上で、視覚的な支援や動線の工夫をすることで、片付けのハードルを下げることができます。
家庭で気づける発達特性のサインと観察ポイント
- 時間感覚のズレや複数指示の処理困難などが特徴
- 朝の支度中に注意がそれやすい行動パターン
- 「いつ・どんな状況で・どのような行動」を記録することが重要
発達特性のサインは、日常生活の中で観察することができます。
忘れ物以外にも、時間感覚のズレを訴える子もいたり、「複数の指示を同時に処理できない」「予定の変更にパニックになる」などの特徴が見られることがあります。朝の支度では、着替えの途中でおもちゃに気を取られたり、歯磨きを忘れたりすることも多いです。
観察のポイントは、「いつ」「どんな状況で」「どのような行動が見られるか」を具体的に記録することです。
この記録は、学校との連携や専門機関への相談の際にも役立つ貴重な情報となります。
今日から始められる家庭での忘れ物対策「小さな成功体験を積み重ねる」
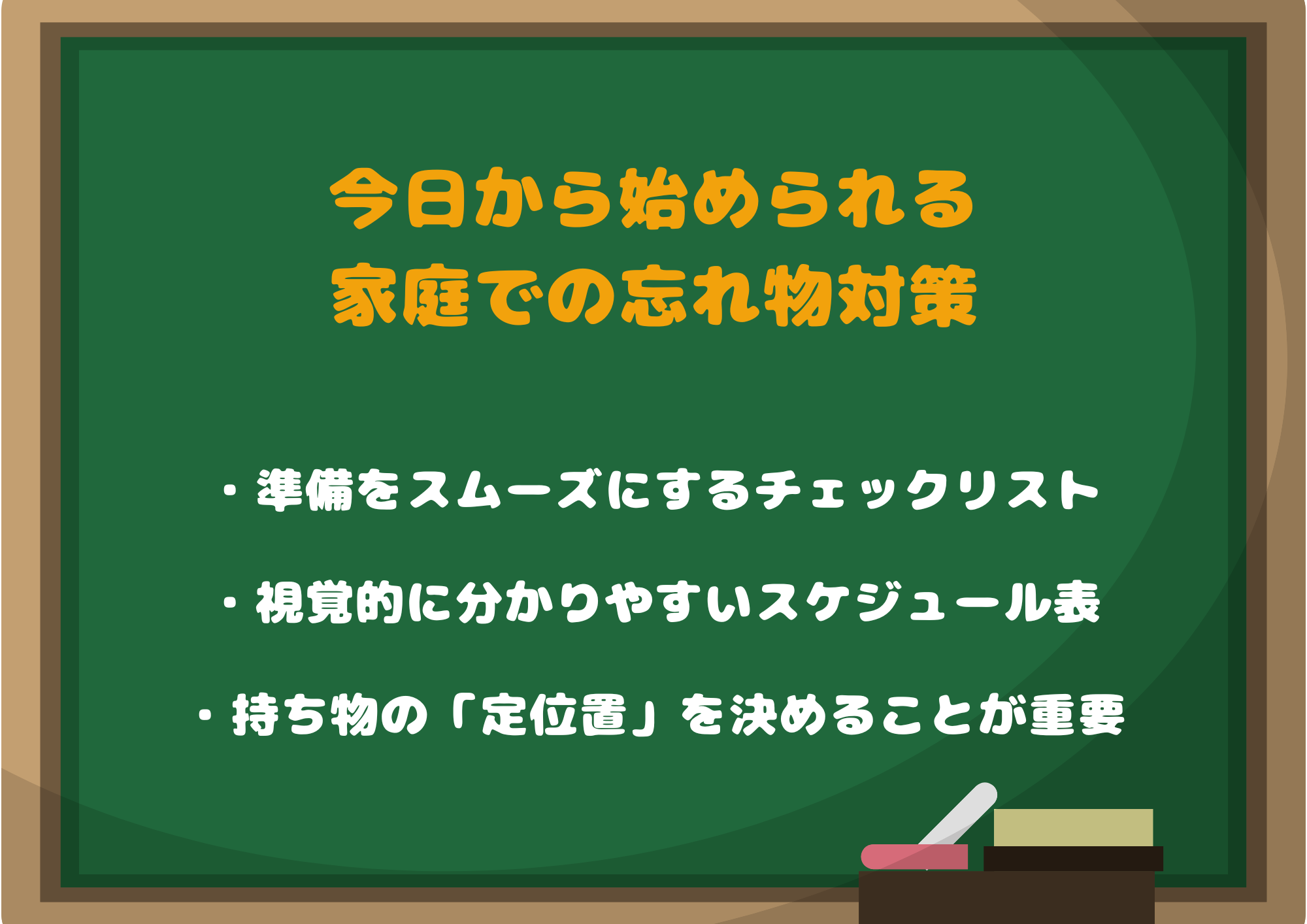
忘れ物を減らすために、今夜から実践できる具体的な方法をご紹介します。
大切なのは、完璧を求めず、お子さんが「できた!」と感じられる小さな成功体験を積み重ねることです。最初は保護者のサポートが必要ですが、徐々に自立できるよう、段階的に進めていきましょう。
まずは1つの方法から始めて、お子さんの反応を見ながら調整していくことが成功の秘訣です。
朝の準備をスムーズにするチェックリストの作り方と活用法
- イラストや写真を使った視覚的に分かりやすいチェックリスト
- 玄関の目立つ場所に貼って最終確認場所として定着
- 項目は7つまでに絞り、達成感を味わえる工夫を
チェックリストは、忘れ物対策の基本中の基本ですが、発達障害のある子ども向けには特別な工夫が必要です。
文字だけでなく、イラストや写真を使って視覚的に分かりやすくすることが重要です。例えば、「体操服」という文字の横に体操服の写真を貼ることで、瞬時に理解できるようになります。
チェックリストは玄関の目立つ場所に貼り、出発前の最終確認場所として定着させます。
項目は多くても7つまでに絞り、優先順位の高いものから並べます。チェックする際は、実際にペンで印をつけたり、シールを貼ったりすることで、達成感を味わえるようにしましょう。
曜日別チェックリストの作成手順
月曜日から金曜日まで、それぞれの曜日に必要な持ち物は異なります。
曜日ごとに色分けしたチェックリストを作成し、前日の夜に翌日のリストを玄関に貼り替える習慣をつけましょう。色分けすることで、お子さんも「今日は青の日だ」と視覚的に認識しやすくなります。
イラスト付きチェックリストのテンプレート活用
インターネット上には、無料でダウンロードできるイラスト付きチェックリストのテンプレートがたくさんあります。
お子さんの好きなキャラクターを使ったオリジナルのチェックリストを作ることで、楽しみながら確認する習慣が身につきます。ラミネート加工をすれば、ホワイトボードマーカーで何度も使えて経済的です。著作権・利用規約の確認も忘れずに行いましょう。
視覚的に分かりやすいスケジュール表で見通しを立てる方法
- 1週間の時間割と習い事、家族予定を含めた全体像を表示
- 特別な持ち物が必要な日は赤い星印で視覚的に強調
- 生活リズムに合わせて親子で確認する習慣づくり
発達障害のある子どもにとって、「見通しが立つ」ことは安心感につながります。
1週間のスケジュールを大きな表にして、リビングの壁に貼りましょう。時間割だけでなく、習い事や家族の予定も含めて、全体像が見えるようにします。特別な持ち物が必要な日は、赤い星印をつけるなど、視覚的に目立つようにします。
スケジュール表を生活リズムに合う頻度で親子で確認する時間を作ることで、明日の準備が習慣化されます。
変更があった場合は、すぐに書き換えて、お子さんに説明することも大切です。
持ち物の定位置を決めて動線をシンプルにする工夫
- 玄関近くに「学校セット置き場」を設置
- フックやカゴで一目で分かる収納システム
- 朝の動線上に必要な物を配置して忘れ物を防ぐ
忘れ物を防ぐには、持ち物の「定位置」を決めることが重要です。
玄関の近くに「学校セット置き場」を作り、ランドセル、帽子、上履き袋などをまとめて置けるようにします。フックやカゴを使って、一目で何がどこにあるか分かるようにしましょう。
動線は極力シンプルにし、朝起きてから玄関を出るまでの経路上に必要な物を配置します。
例えば、洗面所にハンカチとティッシュを置き、歯磨きのついでにポケットに入れられるようにすると、忘れにくくなります。
タイマーを使った時間感覚のサポート方法
- 視覚的タイマーで「あと何分」を一目で把握
- 各活動に時間を設定して行動の切り替えをスムーズに
- 余裕を持った時間設定から始めて徐々に調整
発達障害のある子どもは、時間の感覚を掴むことが苦手な場合があります。
視覚的タイマー(Time Timer等)を使うと、「あと何分」が一目で分かり、行動の切り替えがスムーズになります。朝の支度は「着替え5分」「朝食15分」「歯磨き3分」など、各活動に時間を設定し、タイマーで管理します。
最初は余裕を持った時間設定にし、できたら褒めることで、時間を意識する習慣が身につきます。
タイマーが鳴ったら次の行動に移るというルールを決めることで、だらだらと時間を使うことを防げます。
片付けられない子どもへの対策と環境づくりのポイント
片付けが苦手な発達障害のある子どもには、「片付けやすい環境」を整えることが何より大切です。
完璧を求めず、まずは「使ったものを元に戻す」という基本から始めましょう。環境を整えることで、お子さんの負担を減らし、片付けの成功体験を増やすことができます。
片付けを習慣化するための最初の一歩の踏み出し方
- 5分で終わる範囲から始める小さな一歩
- 成功したら必ず褒めて「片付けると気持ちいい」感覚を育てる
- 最初の2週間は保護者が一緒に行い、体で覚える
片付けの習慣化は、小さな一歩から始めます。
まず、片付ける範囲を限定し、「机の上だけ」「おもちゃ箱だけ」など、5分で終わる範囲から始めましょう。成功したら必ず褒めて、「片付けると気持ちいい」という感覚を育てます。
最初の2週間は保護者が一緒に片付けを行い、やり方を体で覚えてもらうことが大切です。
慣れてきたら、少しずつ範囲を広げていき、最終的には部屋全体を片付けられるようにしていきます。
スモールステップで進める片付けプログラム
1週目は「使ったペンを筆箱に戻す」、2週目は「教科書を本棚に戻す」というように、段階的に目標を上げていきます。
各ステップをクリアしたら、カレンダーにシールを貼るなど、視覚的に成果が分かるようにします。1ヶ月続いたら、お子さんの好きなご褒美を用意することで、モチベーションを保つことができます。
親子で一緒に取り組む片付けタイムの設定
毎日決まった時間に「片付けタイム」を設定し、親子で一緒に片付ける習慣を作ります。
夕食前の10分間など、生活リズムに組み込みやすい時間を選びましょう。音楽をかけながら楽しく片付けることで、苦手意識を軽減できます。
収納場所を一つに決めてラベルで分かりやすくする方法
- 物の収納場所を必ず一つに決めて変更しない
- ラベルや写真で中身を分かりやすく表示
- 透明な収納ケースと色分けで整理しやすく
物の収納場所は、必ず一つに決めて、変更しないことが鉄則です。
収納ボックスには、中身が分かるようにラベルを貼ります。文字が読めない年齢の場合は、写真やイラストを使いましょう。
透明な収納ケースを使えば、中身が見えるため、より分かりやすくなります。
ラベルは大きく、はっきりとした文字で書き、お子さんの目線の高さに貼ることがポイントです。色分けも効果的で、「算数は青」「国語は赤」など、教科ごとに色を決めると整理しやすくなります。
5分間の片付けタイムで達成感を味わう仕組みづくり
- 5分間という短時間で区切りゲーム感覚で楽しく
- キッチンタイマーで時間を管理
- 定期的に物を見直し、使わないものは処分
長時間の片付けは集中力が続かないため、5分間という短時間で区切ります。
キッチンタイマーを5分にセットし、「よーい、スタート!」で片付けを始めます。ゲーム感覚で取り組むことで、楽しみながら片付けができます。
5分で片付けられる量に物を減らすことも大切です。
おもちゃや学用品は定期的に見直し、使わないものは思い切って処分することで、片付けのハードルを下げることができます。
学校との連携で子どもをサポートする方法「安心して相談できる関係づくり」
学校との連携は、発達障害のある子どもの忘れ物対策において欠かせません。担任の先生と協力することで、家庭と学校の両方から子どもをサポートできます。
遠慮せずに相談することが、お子さんのためになることを忘れないでください。発達特性への理解が広がってきています。
担任への伝え方と連絡帳の活用例
- 具体的な事実を数値を含めて説明
- 家庭での取り組みも併せて連絡帳に記載
- 先生からのアドバイスを実践し結果を報告
担任の先生への相談は、具体的な事実を伝えることから始めます。
「忘れ物が週に3回以上あります」「準備に30分以上かかります」など、数値を含めて説明すると理解してもらいやすくなります。
連絡帳には、「本日○○を忘れてしまいました。家庭でもチェックリストを使って対策していますが、学校でもお声がけいただけると助かります」と、家庭での取り組みも併せて伝えます。
先生からのアドバイスは素直に受け止め、実践した結果を報告することで、良好な関係が築けます。
定期的な情報交換を続けることで、お子さんに最適な支援方法が見つかります。
面談で合理的配慮を相談するときの準備と伝え方
- 困りごとと希望する配慮内容を事前にメモ
- 具体的な要望を明確に伝える
- 医療機関の診断書があれば持参
個別面談では、合理的配慮について具体的に相談することができます。
事前に、お子さんの困りごとと希望する配慮内容をメモにまとめておきましょう。例えば、「朝の会で持ち物チェックの時間を設けてほしい」「忘れ物をしても叱らず、個別に声をかけてほしい」など、具体的な要望を伝えます。
医療機関の診断書がある場合は持参し、専門家の意見も交えて相談すると説得力が増します。
学校側も、できる範囲で配慮してくれることが多いため、遠慮せずに相談することが大切です。
専門機関への相談を検討するタイミングと選び方
- 日常生活に著しい支障がある場合は相談を検討
- 自治体の相談窓口、発達支援センター、児童精神科などが相談先
- これまでの記録や学校情報を持参するとスムーズ
家庭や学校での対策を続けても改善が見られない場合は、専門機関への相談を検討します。
相談のタイミングは、「日常生活に著しい支障がある」「本人が強く困っている」「二次障害の兆候がある」といった場合です。相談先は、お住まいの自治体の相談窓口、地域の発達支援センター、児童精神科、教育相談センターなどがあります。
初回相談では、これまでの記録や学校からの情報を持参すると、スムーズに相談が進みます。
専門機関では、より専門的なアセスメントや支援方法の提案を受けることができます。
発達特性に寄り添う家庭教師サービスの選び方とポイント
発達障害のある子どもには、個別対応ができる家庭教師が効果的です。
集団授業では見落とされがちな個々の特性に合わせた指導が受けられ、学習面だけでなく、生活習慣の改善もサポートしてもらえます。
家庭教師選びのポイントは、発達特性への理解があり、柔軟に対応してくれるサービスを選ぶことです。
特に、忘れ物対策や片付けの習慣づけまでトータルでサポートしてくれる家庭教師なら、保護者の負担も軽減されます。
家庭教師のランナーが提供する発達特性への配慮と支援内容

- 発達障害コミュニケーション指導者が在籍
- 講師数約14万人で相性の良い先生を見つけやすい
- 兄弟同時指導なら2人目以降の料金が半額以下
家庭教師のランナーは、発達障害や不登校の子どもに特化した支援体制を整えています。
発達障害コミュニケーション指導者が在籍し、お子さん一人ひとりの特性に合わせたオーダーメイド指導を行っています。忘れ物が多い子どもには、学習指導と並行して、チェックリストの作成や時間管理のサポートも行います。
講師数は約14万人で、お子さんと相性の良い先生を見つけやすいのが特徴です。
料金体系は1コマ(30分)小中学生900円・高校生1000円というシンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。兄弟同時指導なら2人目以降の料金が半額以下になる特別プランもあります。
学力向上だけでなく、自己肯定感を育み、「自分にもできる」という自信を取り戻すきっかけづくりもサポートします。
ランナーの無料体験はこちら!家庭教師のトライで受けられる個別対応プランの特徴

- 全国33万人以上の登録教師から最適な教師を選定
- 専任の教育プランナーが学習計画を立案
- 相性が合わない場合は無料で教師交代可能
家庭教師のトライは、業界大手として豊富な実績を持っています。
専任の教育プランナーが、発達特性を持つ子どもの学習計画を立て、定期的にフォローします。全国33万人以上の登録教師から、お子さんに最適な教師を選定し、相性が合わない場合は無料で交代可能です。
トライ式学習法により、忘れ物対策を含めた生活習慣の改善もサポートします。
オンライン指導にも対応しており、全国どこからでも質の高い指導を受けることができます。
学研の家庭教師による発達特性を理解した指導方法

- 学研グループが運営する安心のサービス
- 視覚的な教材を活用した分かりやすい指導
- オンラインは全国対応、対面は提供エリアあり
学研の家庭教師は、教育大手の学研グループが運営する安心のサービスです。
専門研修等を受けた教師による指導例があり、特性に応じた指導方法を実践しています。視覚的な教材を活用し、忘れ物が多い子どもにも分かりやすい指導を心がけています。
学研ブランドの信頼性により、学校との連携もスムーズに行えるケースもあります。
オンラインは全国対応。対面は提供エリアがあり、詳細は公式サイトで確認できます。
家庭教師のサクシードが実践する片付け支援を含めた学習サポート

- 上場企業が運営する信頼性の高いサービス
- 13万人以上の教師から発達特性に理解のある教師を選択
- 体験授業の先生がそのまま正式担当になる安心感
家庭教師のサクシードは、上場企業(株式会社サクシード)が運営する信頼性の高いサービスです。
13万人以上の教師が在籍し、発達特性に理解のある教師を選ぶことができます。片付けが苦手な子どもには、整理整頓の方法から教え、学習環境の改善もサポートします。
入会金無料で、料金は学年やコースにより異なりますので、最新の公式料金をご確認ください。体験授業を担当した先生がそのまま正式担当になるため、お子さんも安心して学習を始められます。
家庭教師ファーストの忘れ物改善につながる個別指導

- 忘れ物改善プログラムを用意
- 実際の担当教師による無料体験授業
- 不登校支援コースで学習面と生活面をサポート
家庭教師ファーストは、発達障害のある子どもへの指導経験が豊富です。
忘れ物改善プログラムを用意し、チェックリストの活用法や時間管理のコツを丁寧に指導します。実際に担当する先生による無料体験授業があるため、相性を確認してから始められます。
料金例として小学生60分×月4回:9,240円〜(コースにより変動)。不登校支援コースもあり、学習面と生活面の両方をサポートします。
家庭教師のノーバスによる学習面と生活面の両面サポート

- 発達障害に詳しい専門スタッフが在籍
- 独自の管理シートで忘れ物対策を実施
- プロ家庭教師コースで専門的な支援も可能
家庭教師のノーバスは、関東中心に展開する家庭教師センターです。
発達障害に詳しい専門スタッフが在籍し、学習面だけでなく生活面のサポートも充実しています。忘れ物対策として、独自の管理シートを使った指導を行い、保護者との連携も密に取ります。
プロ家庭教師コースもあり、より専門的な支援を受けることができます。対面校舎は主に関東圏で、オンラインは広域対応しています。
家庭教師のあすなろが提供する片付けも含めた総合支援
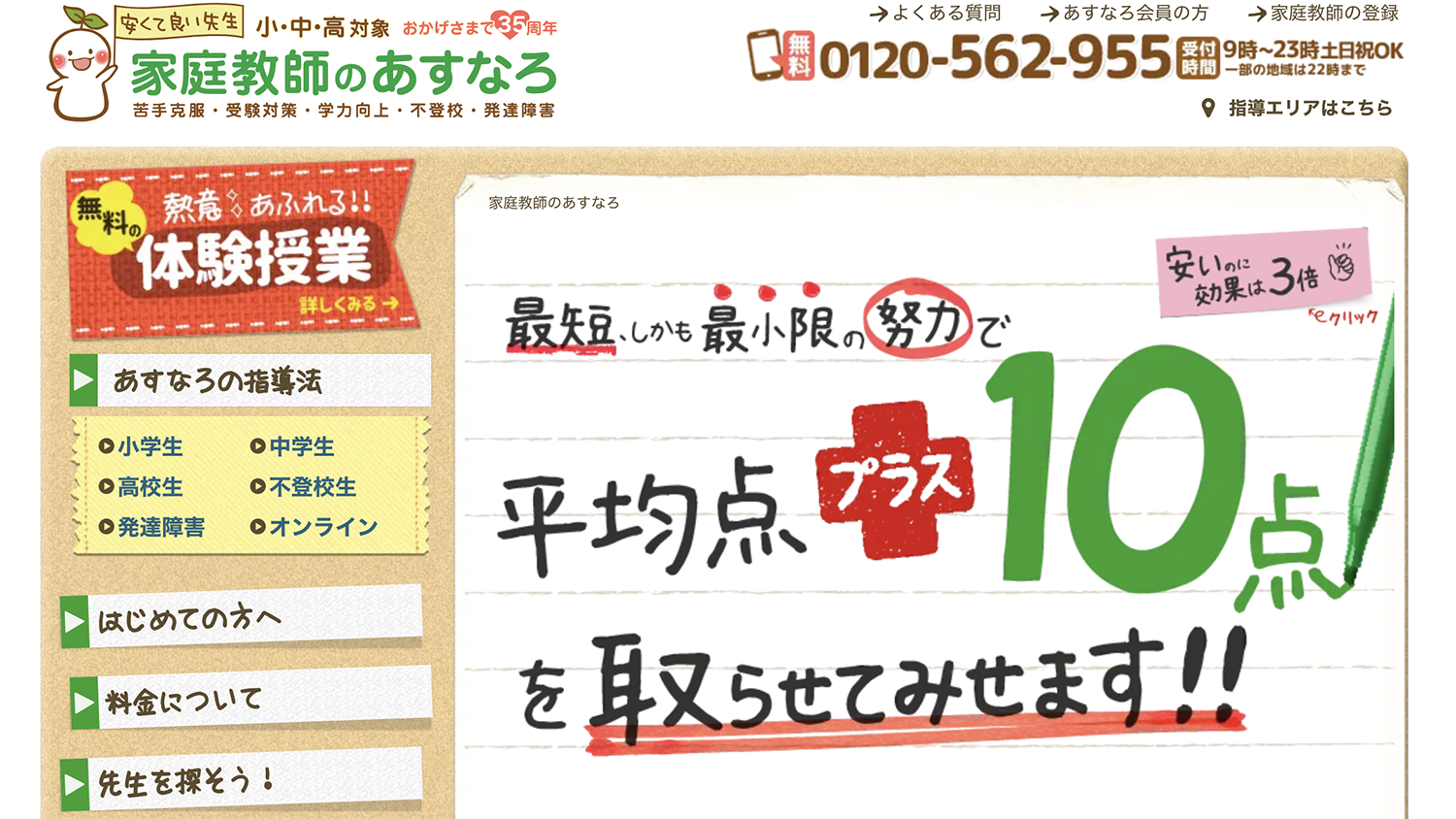
- 「勉強が苦手な子専門」として長年の実績
- 親しみやすい大学生教師による実践的サポート
- LINEでいつでも質問できる「お悩みお助け隊」サービス
家庭教師のあすなろは、「勉強が苦手な子専門」として長年の実績があります。
発達障害のある子どもの特性を理解した大学生教師が、親しみやすい指導を行います。片付けが苦手な子どもには、一緒に片付ける時間を設けるなど、実践的なサポートを提供します。
LINEでいつでも質問できる「お悩みお助け隊」サービスもあり、授業以外でもサポートを受けられます。コース・地域で料金は変動します。
家庭教師学参のプロ講師による発達特性に合わせた指導

- 40年以上の歴史を持つプロ家庭教師専門サービス
- 講師指名制で相性を確認してから契約
- 学習計画・行動面の支援を含む指導
家庭教師学参は、40年以上の歴史を持つプロ家庭教師専門のサービスです。
発達障害に精通したプロ講師が、お子さんの特性に合わせた完全オーダーメイドの指導を行います。忘れ物対策では、学習計画・行動面の支援を含む指導例があります。
講師指名制で、無料体験授業で相性を確認してから契約できます。入会金22,000円+教務費16,500円、指導料は1時間4,400円〜(講師ランクで変動)。料金の詳細については、公式情報をご確認ください。
オンライン家庭教師Wamで受けられる発達特性への配慮

- 独自開発の専用システムで効率的な指導
- 視覚的な教材や双方向のやり取りを重視
- 東京大学などの有名大学の現役学生が在籍
オンライン家庭教師Wamは、独自開発の専用システムで効率的な指導を実現しています。
発達障害のある子ども向けに、視覚的な教材や双方向のやり取りを重視した授業を提供します。忘れ物チェックの時間を授業に組み込むなど、生活習慣の改善もサポートします。
料金例として小1〜3:週1回40分・月4回で4,900円〜。学年・コースで変動します。東京大学などの有名大学の現役学生が教師として在籍し、全国どこからでも受講可能です。
オンライン家庭教師トウコベ(東大家庭教師友の会)の個別対応
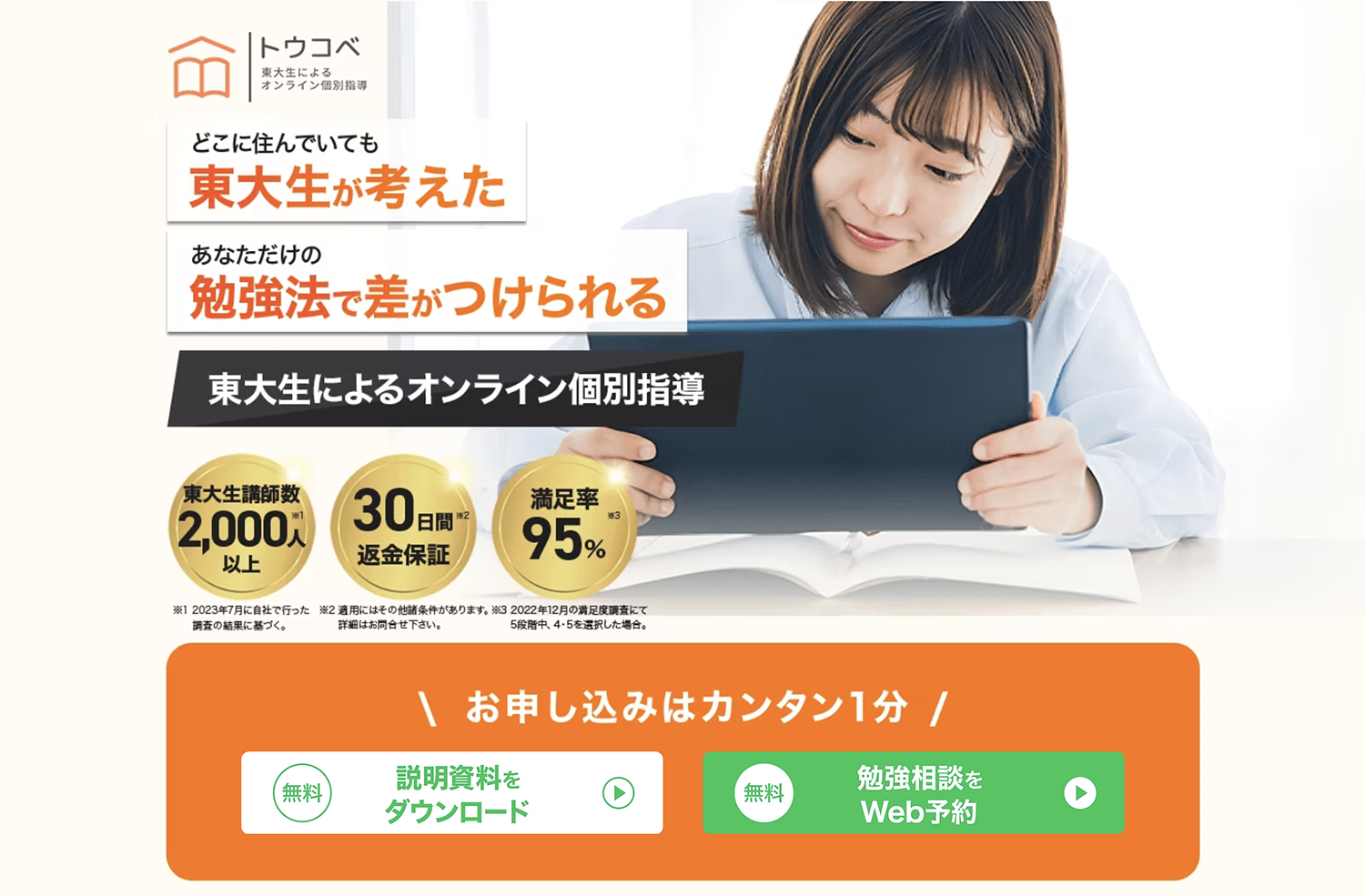
- 東京大学の現役学生による専門指導
- 30日間の全額返金保証で安心スタート
- 満足度95%(公称)の高評価
オンライン家庭教師トウコベは、東京大学の現役学生による指導が受けられるサービスです。
発達特性を持つ子どもへの理解も深く、効率的な学習方法と共に、忘れ物対策などの生活スキルも指導します。東大生ならではの学習ノウハウを活かし、お子さんの可能性を最大限に引き出します。
30日間の全額返金保証があるため、安心して始めることができます。満足度95%という高い評価を得ています。
オンライン家庭教師マナリンクのプロ講師による専門的支援
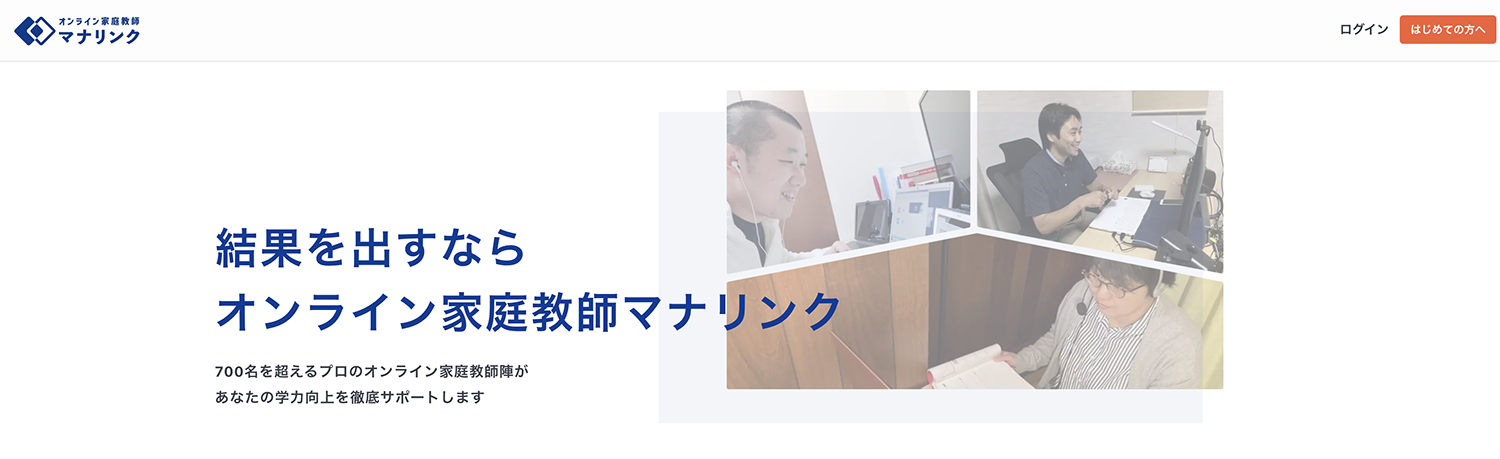
- 100%社会人のプロ講師が在籍
- 講師のプロフィールや動画を見て選択可能
- 専用アプリで気軽に質問や相談ができる
オンライン家庭教師マナリンクは、100%社会人のプロ講師が在籍するサービスです。
発達障害の専門知識を持つ教師も多く、忘れ物が多い子どもや片付けられない子どもへの対策を熟知しています。講師のプロフィールや動画を見て、自分で先生を選べるのが特徴です。
専用アプリで気軽に質問や相談ができ、きめ細かなサポートを受けられます。
忘れ物が多い子どもの発達障害対策で大切にしたいことのまとめ
- ・発達特性を理解し、叱るだけでなく環境と支援を整える
- ・チェックリストやタイマーなど視覚的ツールを活用
- ・家庭・学校・専門機関が連携してサポート体制を構築
- ・小さな成功体験を積み重ね、自己肯定感を高める
- ・家庭教師などの個別支援で学習面と生活面をトータルサポート
発達障害のある子どもの忘れ物対策は、一朝一夕にはいきません。
しかし、お子さんの特性を理解し、適切な環境と支援を整えることで、改善が期待できます。大切なのは、完璧を求めず、小さな成功体験を積み重ねることです。
「今日は忘れ物が1つ減った」「片付けに5分かかったのが3分になった」といった小さな変化を見逃さず、しっかりと褒めてあげてください。
お子さんが自信を持って学校生活を送れるよう、家庭・学校・専門機関が連携してサポートすることが何より重要です。
家庭教師のランナーでは、発達特性に配慮した個別指導で、お子さんの「できる」を増やすお手伝いをしています。忘れ物対策だけでなく、学習面でのつまずきも丁寧にサポートし、お子さんの自己肯定感を高めていきます。
保護者も一人で抱え込まず、周りのサポートを上手に活用してください。
お子さんのペースに合わせて、焦らず一歩ずつ前進していけば、きっと良い方向に向かっていきます。今日から始められる対策を一つずつ実践し、お子さんの笑顔が増える毎日を作っていきましょう。各社の最新情報を確認のうえ、ご家庭に合う支援を選択してください。
ランナーの無料体験はこちら!