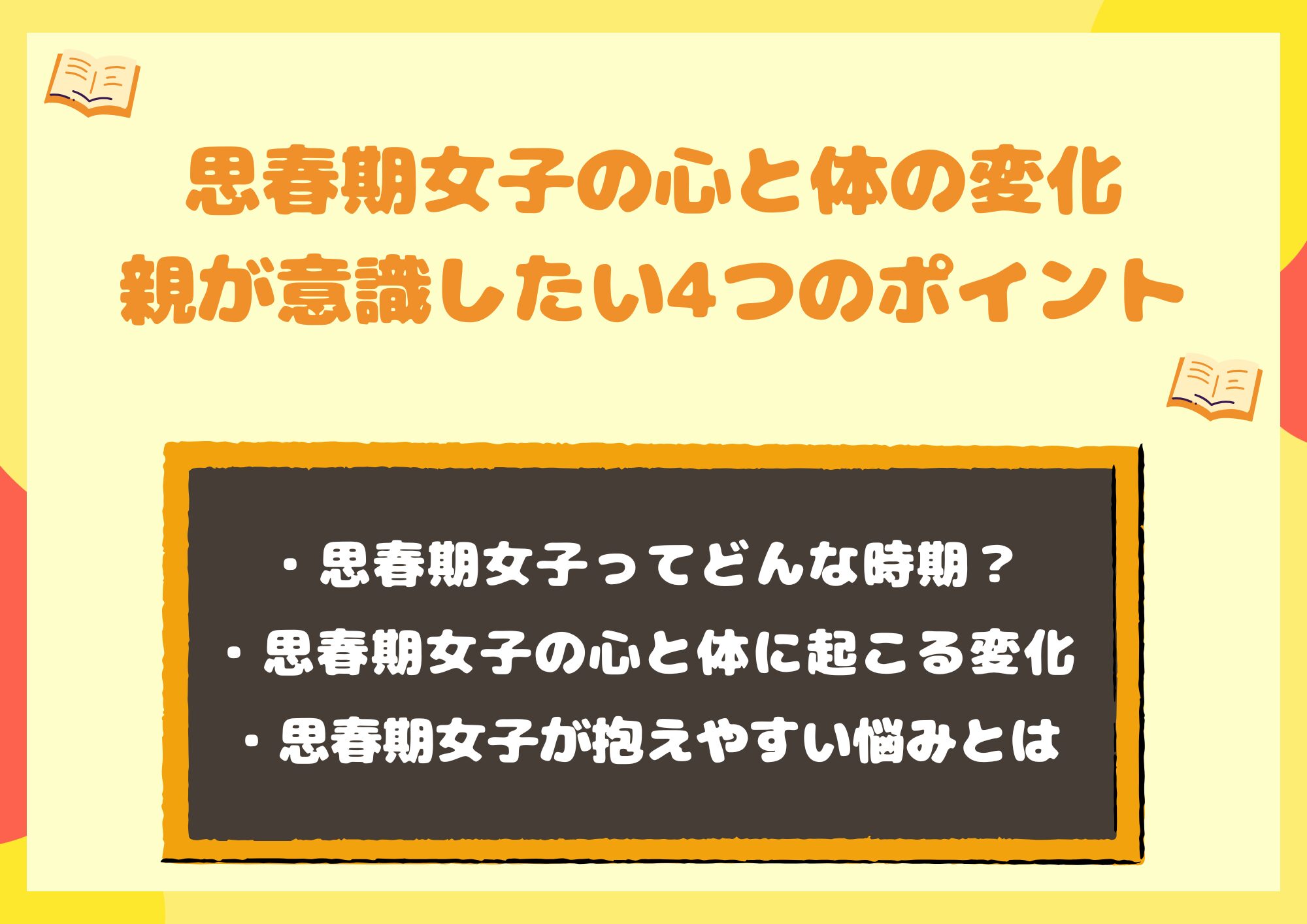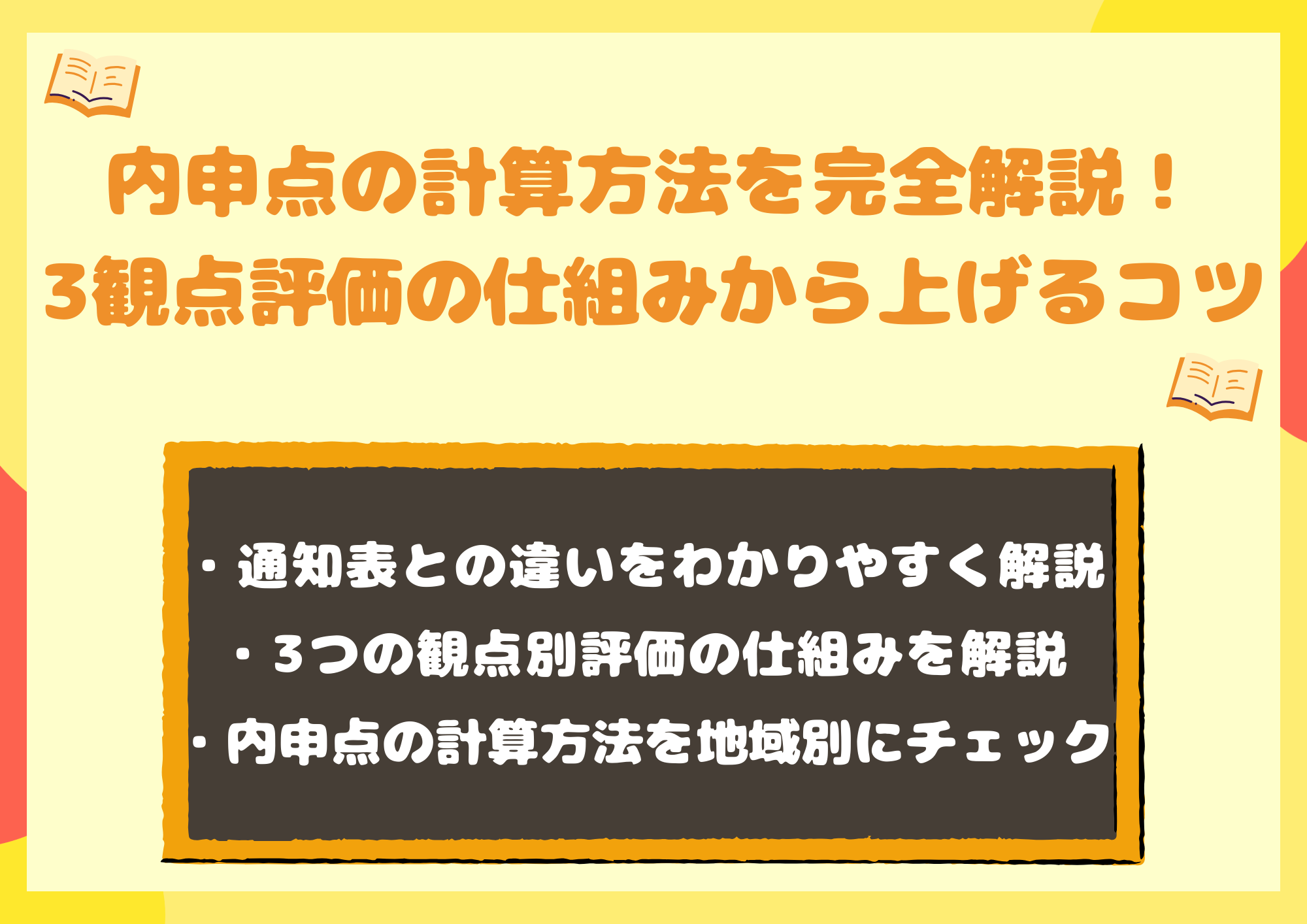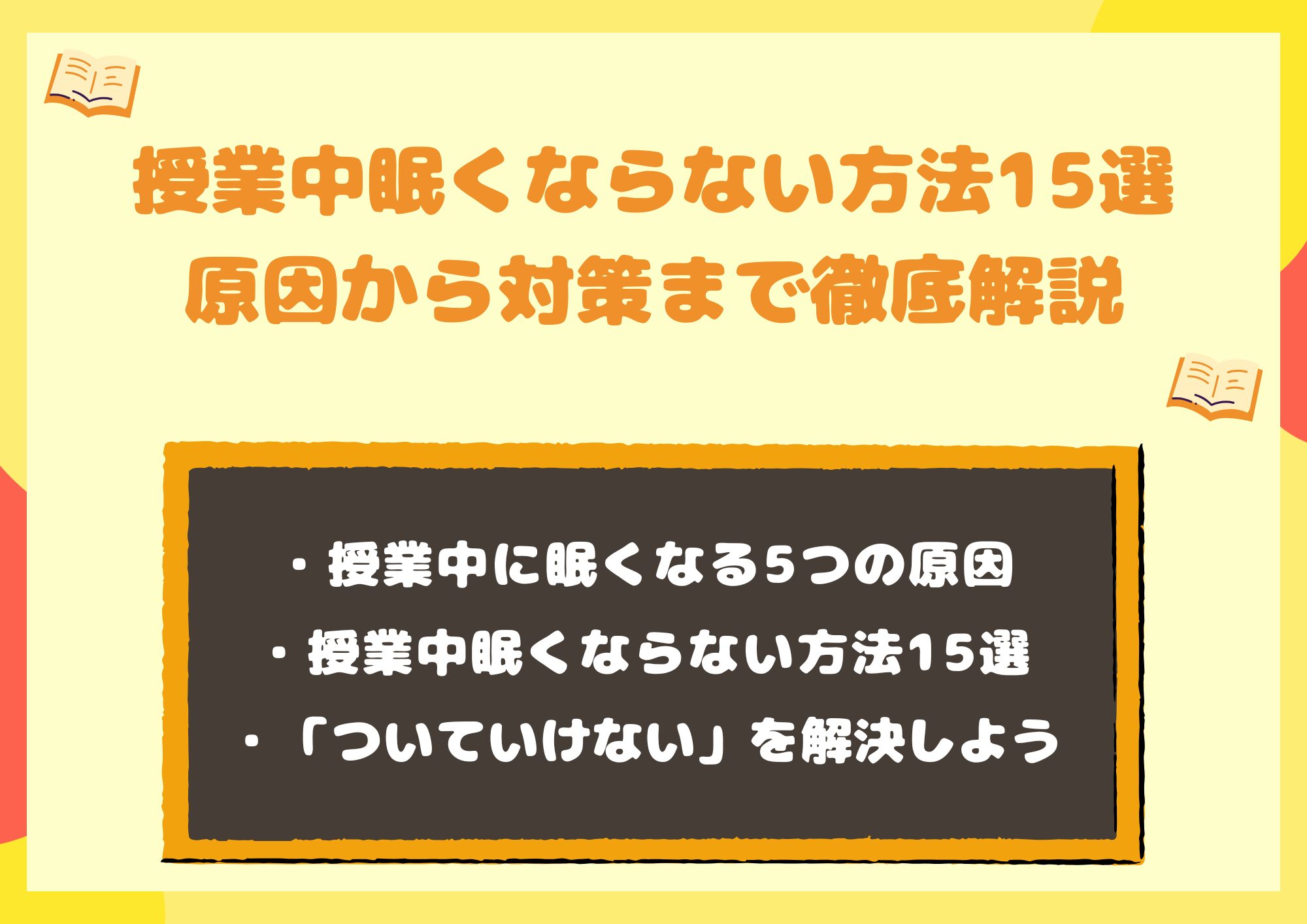- 中
勉強しない中学生の末路は?理由や親ができるサポートも解説
2025.01.08

中学生が勉強しない状況に悩む保護者は多いかもしれません。放置すると学力低下だけでなく、将来の選択肢にも影響を及ぼす可能性があります。この記事では、勉強しない理由や保護者ができるサポート方法について解説します。
目次
勉強しない中学生の末路は?ほっとくとどうなる?

授業についていけなくなってしまう
勉強をしない状態が続くと、授業で新しい内容を理解できなくなり、徐々に遅れが生じてしまいます。この遅れが積み重なると、苦手意識が強まるだけでなく、「自分は勉強ができない」という思い込みが生まれることもあります。その結果、授業への集中力が低下し、さらにわからない部分が増えてしまいます。最終的には、勉強そのものを諦めてしまうケースも少なくありません。
受験が上手くいかなくなる可能性が高まる
中学生にとって受験は将来を左右する重要な節目です。しかし、勉強をしないままでは必要な学力が身につかず、志望校への合格が難しくなります。特に基礎的な内容が定着していないと応用問題にも対応できず、点数が伸びない原因になります。また、準備不足による失敗は自信喪失につながり、その後の進路選択にも影響を及ぼす可能性があります。
努力をしなくなる癖がついてしまう
勉強をしない習慣が続くと、「やらなくても何とかなる」という考えが定着してしまいます。このような癖がつくと、困難な状況に直面しても努力しない姿勢が身についてしまい、将来の目標達成に必要な忍耐力や主体性を欠く可能性があります。特に中学生の時期は習慣が形成されやすいため、このまま放置すると悪影響が長期的に続く恐れがあります。
中学生が勉強しないのはなぜ?よくある理由を7つ紹介

中学生が勉強しない理由1.勉強に苦手意識を持っている
勉強に苦手意識を持つ中学生は、「わからない」「できない」という経験が積み重なり、やる気を失っていることが多いです。この苦手意識は、結果だけを重視した環境や、学び方が合わないことから生まれるケースもあります。自分に合った方法を見つけられるよう寄り添うことが、解消への鍵となります。
中学生が勉強しない理由2.スマホやゲームなど興味のあることが増えるから
中学生になると、スマホやゲームへの関心が急激に高まります。これらは即座に楽しさを得られるため、勉強よりも優先されやすい傾向があります。さらに、ゲームやSNSで得られる達成感や刺激が強いほど、勉強のように成果が出るまで時間がかかるものに対する忍耐力が失われることもあります。
中学生が勉強しない理由3.人間関係に疲れている
中学生の時期は人間関係が複雑になり、精神的な負担を抱えることが少なくありません。友人との関係がうまくいかなかったり、部活動でのプレッシャーを感じたりする中で、心が疲れてしまうことがあります。このような状況では、勉強よりも心の安定を優先するため、学習意欲が低下してしまうこともあります。
中学生が勉強しない理由4.反抗期によるもの
反抗期は自分の意見を主張したくなる時期であり、勉強を後回しにする行動もその一環といえます。この時期は「どうして勉強しなければいけないのか」を自分なりに考えようとする一方で、親や教師の意見を受け入れる余裕がなくなることがあります。そのため、勉強への取り組みよりも、自分を理解してほしいという思いが優先される傾向があります。
中学生が勉強しない理由5.勉強の仕方がわからない
中学生が勉強しない理由として、「勉強の仕方がわからない」というケースもよく見られます。ただ机に向かうだけでは成果が出にくく、効率的なやり方を知らないままではやる気を失うこともあります。また、学習計画を立てたり、具体的な目標を設定したりする経験が乏しいため、どこから手をつけて良いのかわからず、そのまま手が止まってしまうこともあります。
中学生が勉強しない理由6.成績が低下している
成績が低下すると、中学生は「自分にはできない」という思い込みを持ちやすくなります。その結果、勉強すること自体に意味を見いだせなくなり、学習意欲を失ってしまう場合があります。また、点数が低いと親や教師からの叱責を恐れて、さらに勉強から逃げるようになることもあります。こうした状況では、失敗を受け入れながら少しずつ自信を取り戻すサポートが必要です。
中学生が勉強しない理由7.親から勉強しなさいと言われるから
親から「勉強しなさい」と言われ続けると、中学生は「自分のペースを乱された」と感じることがあります。その結果、ストレスや反発心が生まれ、かえって勉強から離れてしまうことがあります。また、「やらされている」と感じると、自分から進んで取り組む気持ちが育ちにくくなります。お子さんが自分で考えて行動できる環境を整えることが大切です。
勉強しない中学生のやる気を引き出す!親ができるサポート方法をご紹介

勉強に適した環境を作ってあげる
勉強に集中できる環境を整えることは、学習意欲を高めるための基本です。静かで整理されたスペースを用意するだけでなく、お子さん自身が「ここなら集中できる」と思える場所を一緒に考えることがポイントです。また、リビングや共有スペースを利用する場合は、親が適度な距離を保ちながら見守ることで、安心感を与えつつ勉強に向き合いやすい雰囲気を作ることができます。
勉強する目的や目標を一緒に考えてみる
勉強に前向きに取り組むには、目的や目標を明確にすることが大切です。志望校の名前を具体的に挙げたり、将来なりたい職業について話し合ったりすることで、「何のために勉強するのか」を実感しやすくなります。また、「次のテストで5点アップを目指す」など、達成しやすい目標を小さく設定することで、自信を持てる経験を積むことができます。
適した声掛けを行う・しっかりと褒める
中学生にとって、保護者からの声掛けは学習意欲に大きく影響します。「どうして勉強しないの?」と問い詰めるのではなく、「頑張っているところを見て安心したよ」など、努力を認める言葉がけが効果的です。また、結果よりも過程を評価し、「よく工夫して取り組んでいるね」といった具体的な褒め方をすることで、自信とやる気を引き出しやすくなります。
親も一緒に勉強する
お子さんに勉強の大切さを伝えるには、保護者自身がその姿勢を示すことが大切です。例えば、横で静かに本を読んだり、調べものをしたりするだけでも、「学ぶことは特別ではなく自然なこと」というメッセージを伝えられます。一緒に取り組むというより、学ぶ雰囲気を共有することが、勉強への意欲につながる場合もあります。
中学生が勉強しない時のNGな接し方は?

勉強しない時に命令口調や脅し口調で声かけをする
「早く勉強しなさい!」と強く言われると、中学生は「自分のことを理解してもらえていない」と感じることがあります。こうした言葉は、反発心を生みやすく、勉強そのものに対する意欲を奪ってしまうこともあります。大切なのは、お子さんが話しやすい雰囲気を作りながら、「どうしたら進めやすいかな?」と自然にサポートする姿勢を見せることです。
親が決めた目標を押し付ける
中学生は、自分で考え決める経験を積むことで成長していきます。そのため、親が一方的に目標を押し付けると、「自分の意見が無視されている」と感じて反発心が生まれることがあります。特に、達成が難しい高い目標を設定されると、やる気を失うだけでなく、諦めの気持ちが強まることもあります。お子さんが主体的に目標を考えられるよう、保護者はサポート役に回ることが大切です。
他人と比較してしまう
中学生は、自分と他人を比べられると、「自分はダメなんだ」という気持ちにとらわれやすくなります。他人と比較する言葉は、お子さんのやる気を削ぐだけでなく、劣等感を生む原因にもなります。保護者が注目すべきなのは、お子さん自身のペースや取り組みです。他人ではなく、過去の自分と比べてどう成長したのかを一緒に確認することが、やる気につながります。
勉強しない中学生には家庭教師が効果的!

家庭教師は、中学生が勉強に前向きになるための効果的なサポート方法です。一対一の指導で、お子さんの理解度や性格に合わせた指導が可能なだけでなく、苦手意識を克服し、自信を育てることも期待できます。自宅で指導を受けられるため、リラックスした環境で学べる点も大きな魅力です。
勉強しない中学生の末路についてまとめ

中学生が勉強しない状態を放置すると、学力低下だけでなく、自信喪失や将来の選択肢の狭まりといった問題が生じる可能性があります。勉強しない理由を理解し、適切なサポートをすることで、お子さんのやる気を引き出すことができます。家庭教師などの外部サポートを活用するのも効果的な方法です。お子さんの未来のために、今できるサポートを始めてみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者
マインズ株式会社
本部
大島 あずさ
教育現場を志していたところ、家庭教師という仕事に出会い、「1対1での指導の素晴らしさ」に惹かれ、気がつけば10年になっています。勉強が苦手な子にももちろんですが、「理解することの楽しさ」を一人でも多くのお子さんに伝えるために日々努力しています。
# 経歴
家庭教師歴10年。家庭教師として仕事をしながら教師へのサポート業務も行いつつ、マインズ株式会社に入社。現在はマインズ株式会社本部に所属し、コンテンツ作成やサービス向上のためのコンテンツ制作に勤しんでいる。
# 得意領域
- 学習支援コンテンツ制作
- 勉強が苦手な子へのアプローチ