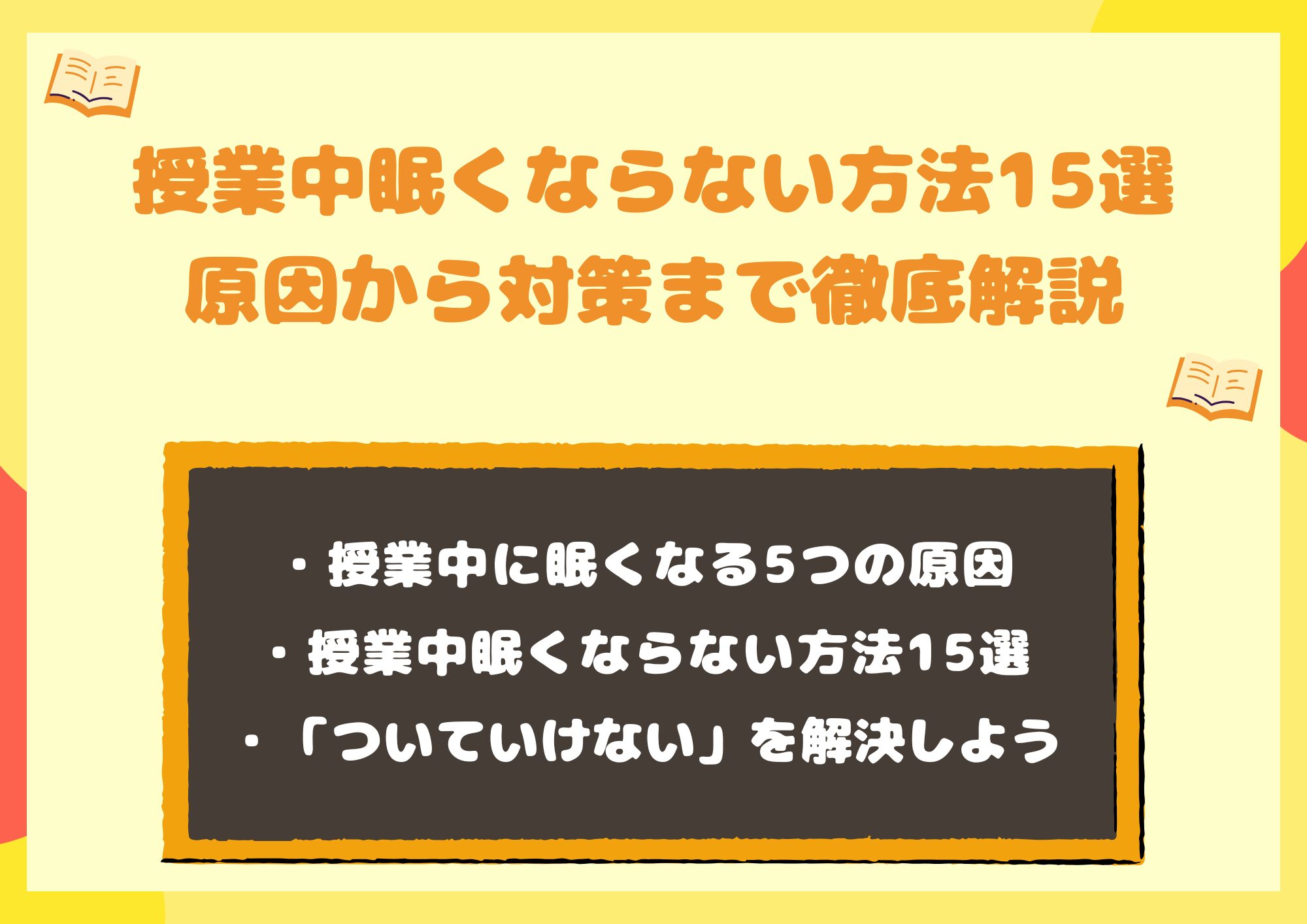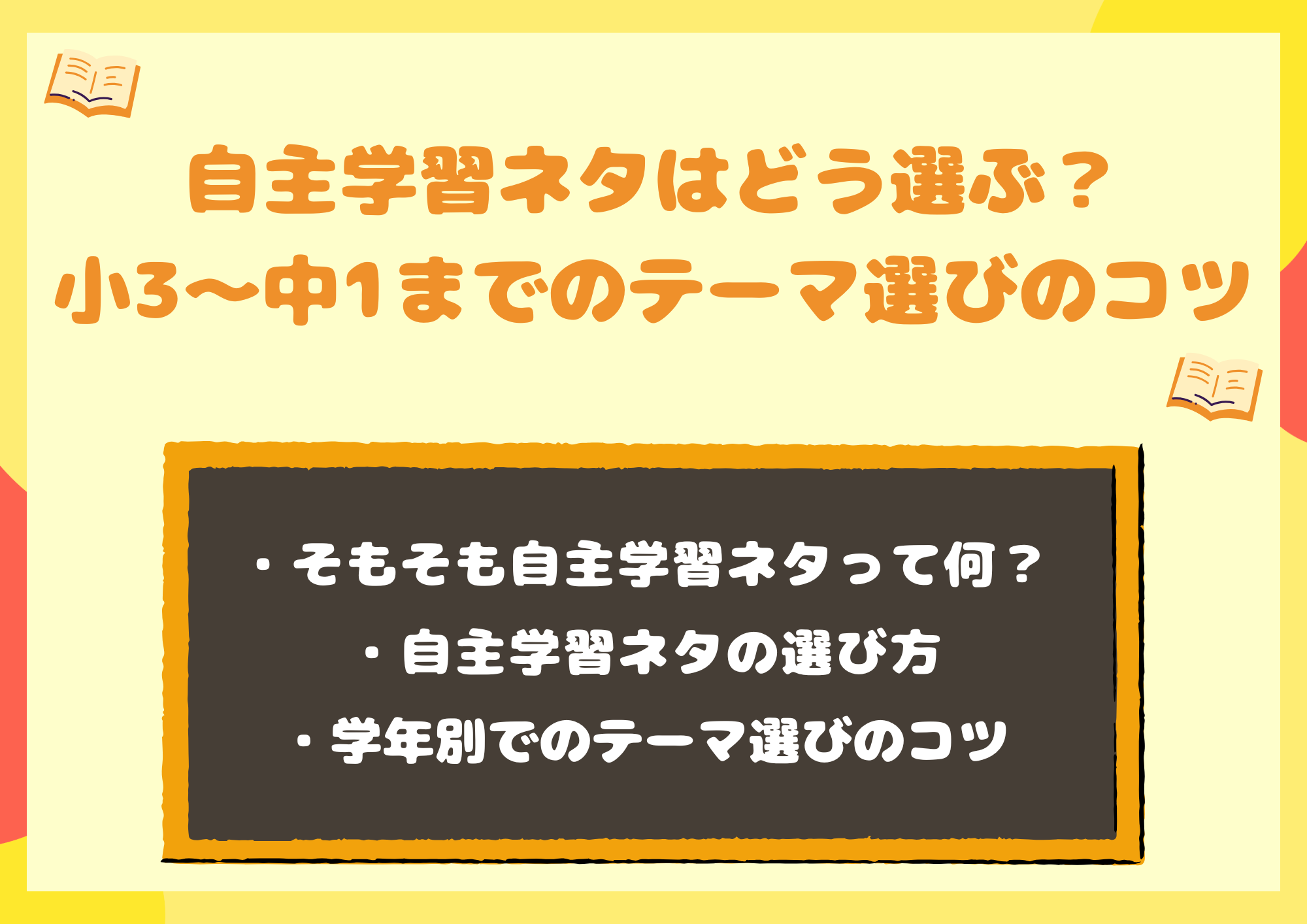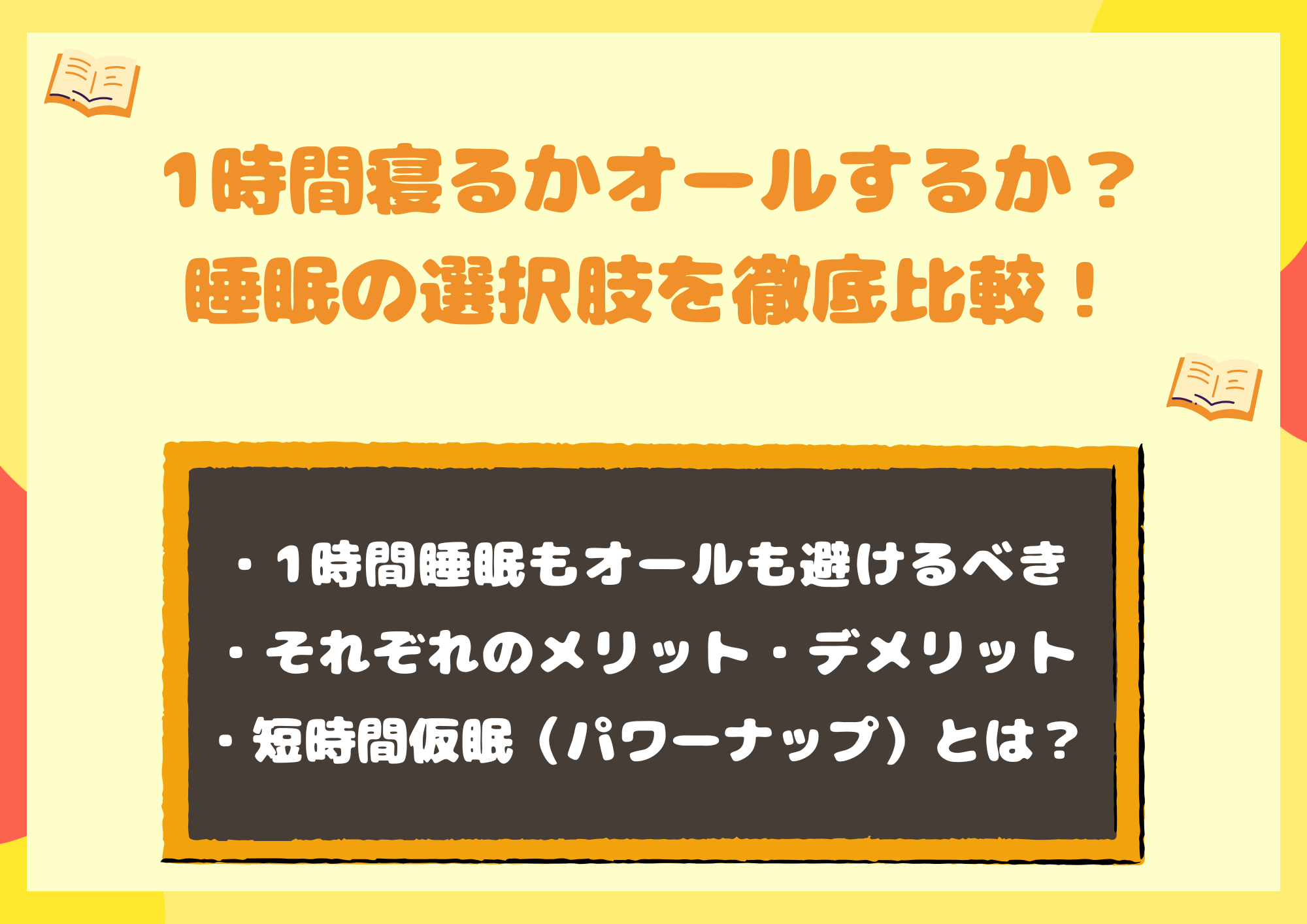- 勉強法
勉強のやる気が出ない原因6つと今すぐ試せる解決法7選
2025.10.28
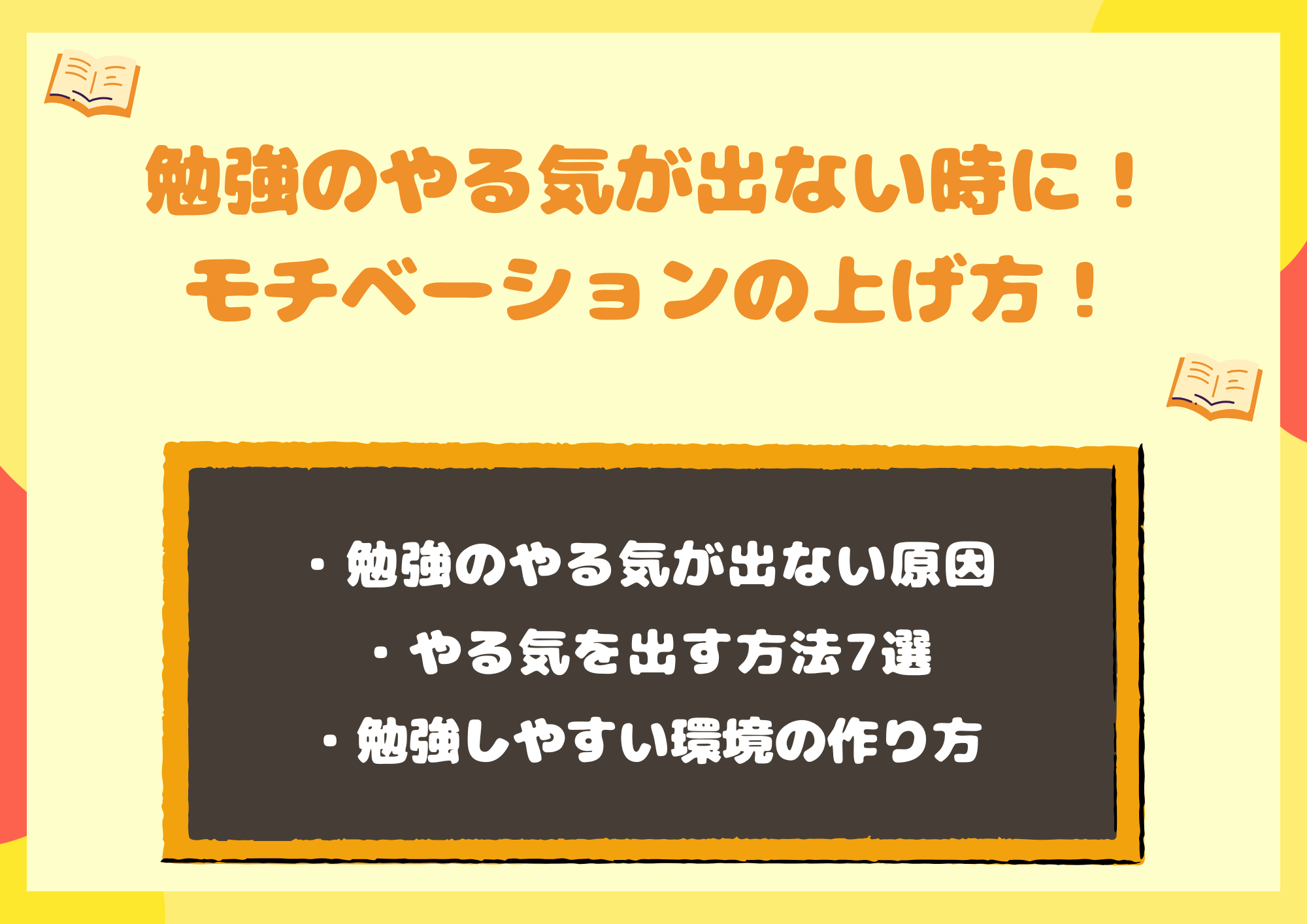
テスト前なのに机に向かえない、教科書を開いても頭に入ってこない。そんな「勉強のやる気が出ない」という悩みは、実は多くの学生が抱えている自然な感情なんです。
この記事では、やる気が出ない原因を詳しく分析し、今すぐ実践できる具体的な解決法をご紹介します。
最後まで読んでいただければ、きっとあなたに合った解決法が見つかるはずです。
目次
勉強のやる気が出ないのはあなただけじゃない!
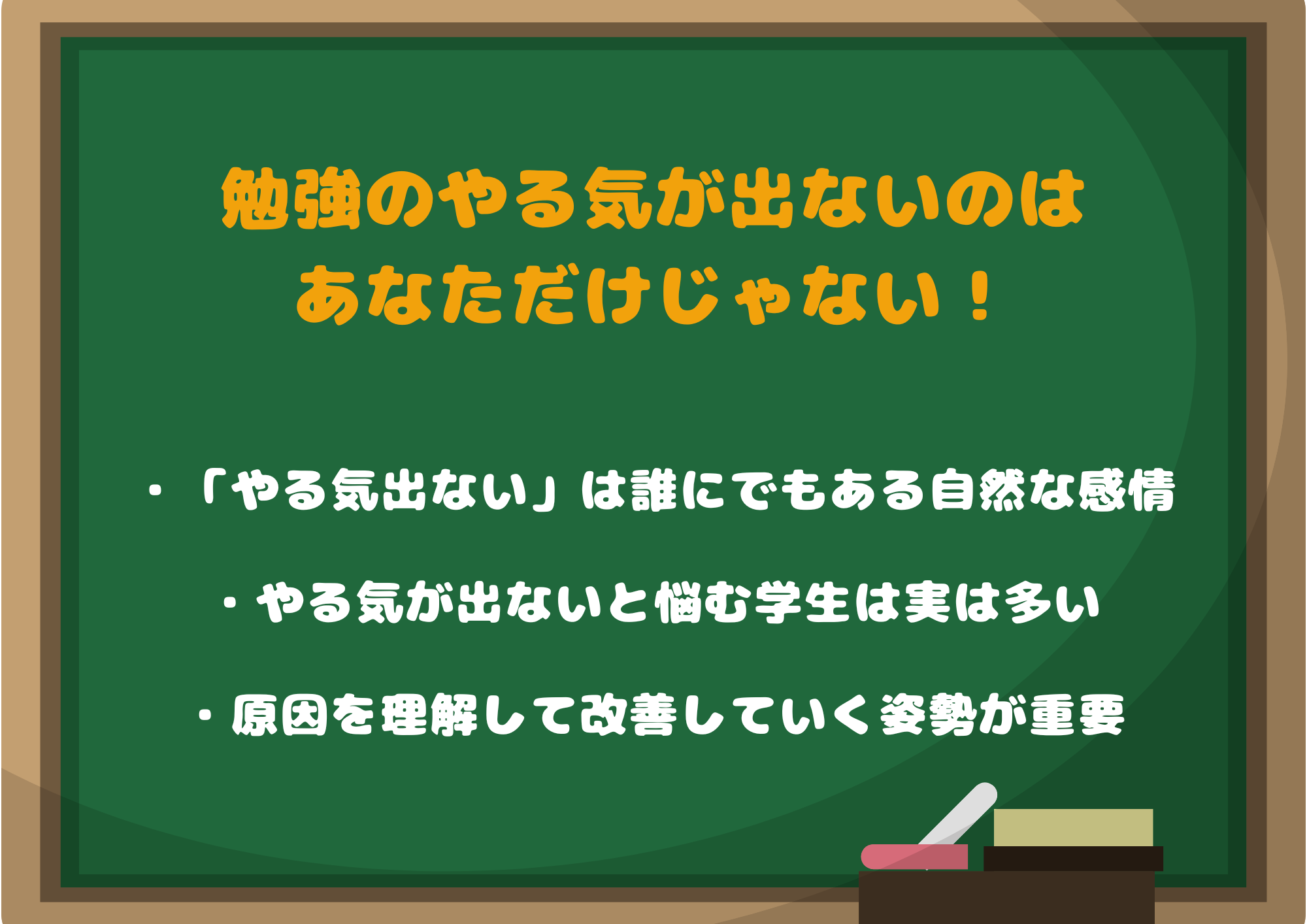
- やる気が出ないのは誰にでもある自然な心理反応
- 多くの学生が同じ悩みを抱えている
- 心理的欲求が満たされていないサイン
「自分だけがダメなのかも」と落ち込んでいませんか。
実は、勉強のやる気が出ないという悩みは、驚くほど多くの学生が経験している普通のことなんです。
「やる気出ない」は誰にでもある自然な感情
- 動機づけの低下は人間の本能的な反応
- 自律性・有能感・関係性の欲求が満たされないと意欲低下
- 思春期には特に自分で決めたいという欲求が強まる
やる気が出ないという感覚は、心理学では動機づけの低下として説明されます。
脳は常にエネルギーを節約しようとする性質があり、勉強という活動が「楽しくない」「意味がわからない」と感じると、自然とその活動を避けようとするんです。心理学の自己決定理論によれば、人間には自律性、有能感、関係性という三つの基本的な欲求があります。
これらの欲求が満たされないと、どんなに頑張ろうと思っても意欲が湧いてこないんですね。特に思春期には自分で決めたいという気持ちが強くなり、「勉強しなさい」と言われるとかえって反発したくなるのも自然な心理反応です。
やる気が出ないと悩む学生は実は多い
- 成績の良い生徒でも意欲低下は起こる
- 学年や成績に関係なく誰にでも起こりうる現象
- 原因を理解して適切に対処することが大切
あなたと同じように、多くの学生が勉強のやる気について悩んでいます。
成績の良い生徒でさえ、時期によっては意欲が低下することがあるんです。学習意欲の低下は、学年や成績に関係なく誰にでも起こりうる現象で、受験生の間でもプレッシャーから逃れたくて勉強を避けてしまうケースは珍しくありません。
大切なのは、この状態を認めて適切に対処することです。多くの先輩たちも同じ壁にぶつかり、それを乗り越えて目標を達成してきました。あなたも必ず解決策が見つかりますから、安心してくださいね。
勉強のやる気が出ない原因って何?
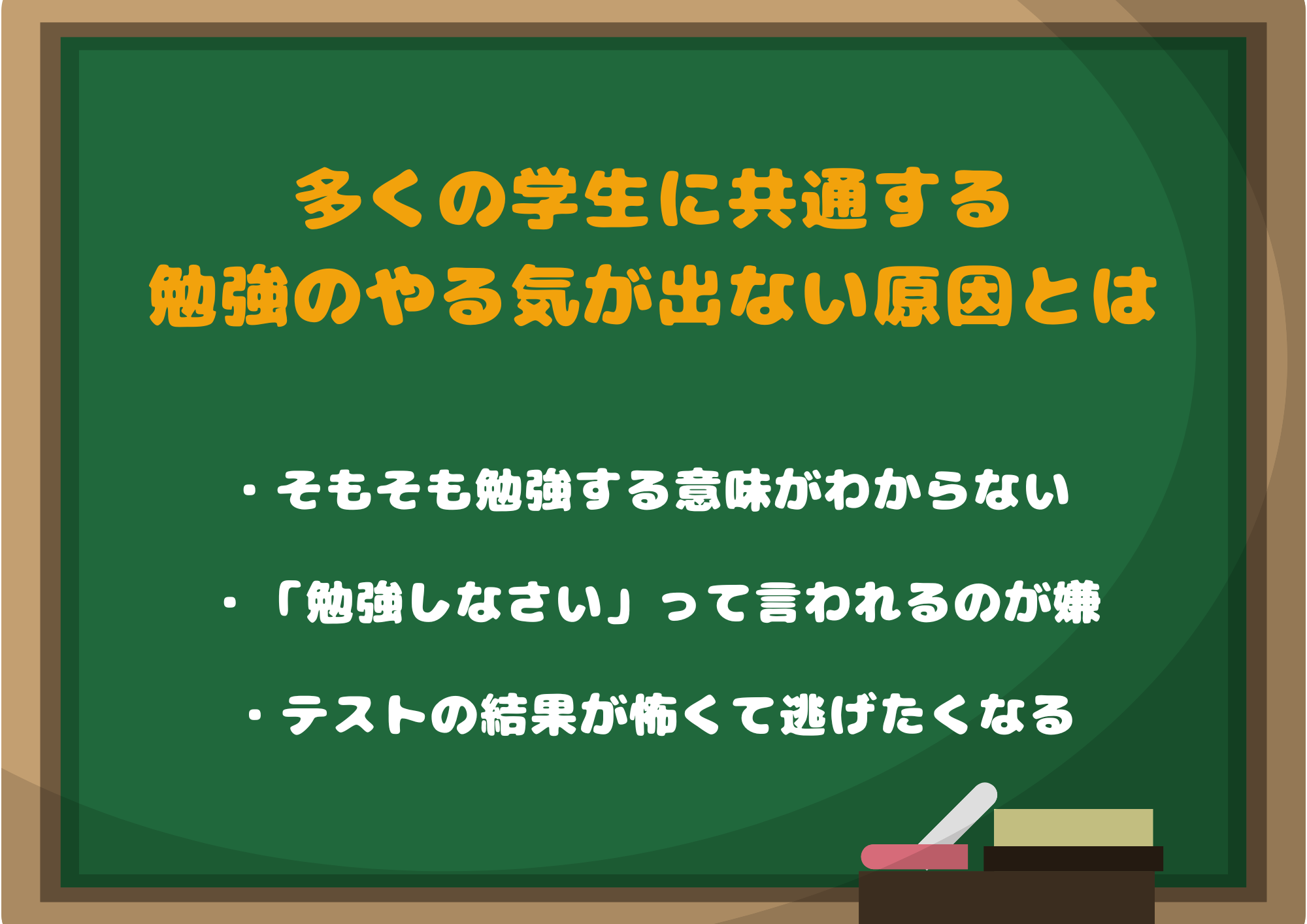
- 勉強する意味がわからない
- 内容が難しすぎてついていけない
- 「勉強しなさい」と言われるのが嫌
- テスト結果への不安やスマホの誘惑
私たちランナーはこれまで30,034人のお子さんを指導してきました。
その経験から見えてきたのは、やる気が出ない原因は一人ひとり違うということ。「私たちランナーが指導してきた30,034人のお子さんの中にも、最初は『やる気が全然出ない』と言っていた子がたくさんいました。でも、原因を見つけて正しいアプローチをすることで、多くのお子さんが自分から勉強するようになっています。」ここでは、多くのお子さんに共通する原因をご紹介しますね。
そもそも勉強する意味がわからない
- 目的が見えないと内発的動機づけが生まれない
- 学習内容と将来の目標を結びつけることが重要
- 自律性の欲求が阻害されている状態
「なんでこんなこと勉強しなきゃいけないの?」という疑問は、やる気を失う最も根本的な原因の一つです。
目的が見えないまま努力を続けるのは、誰にとっても困難なことなんです。数学の公式や歴史の年号が自分の将来にどう役立つのか実感できないと、勉強は苦痛な作業になってしまいます。
学習内容と自分の興味や将来の目標を結びつけることが、意欲を取り戻す鍵になります。例えば、医者になりたいなら生物や化学の知識が直接役立ちますし、プログラマーを目指すなら数学的思考力は必須のスキルです。
勉強嫌いなお子さんへの向き合い方については、「勉強が嫌いな子の特徴と対処法」でさらに詳しく解説しています。
勉強が難しすぎてついていけない
- 有能感が損なわれて無力感を覚える
- 基礎知識の欠如が理解困難の原因に
- つまずいた箇所まで戻って学び直すことが大切
内容が難しすぎると感じると、脳は無力感を覚えて学習を避けるようになります。
特に、基礎知識が欠けたまま次の単元に進むと、理解できない部分がどんどん積み重なっていきます。小学校の分数でつまずいたまま中学の数学に進むと、ストレスが高まる悪循環に陥るんです。
この問題を解決するには、つまずいた箇所まで戻って基礎から学び直すことが大切です。恥ずかしいと思わずに、わからないところを質問する勇気を持ちましょう。
お子さんのやる気を引き出す具体的な方法については、「中学生のやる気を出させる方法」でさらに詳しく解説しています。
「勉強しなさい」って言われるのが嫌
- 心理的リアクタンスで反発したくなる
- 自律性の欲求が阻害される
- 自分で決めたという感覚が必要
親や先生から「勉強しなさい」と繰り返し言われると、かえってやる気を失うことがあります。
これは心理学で「心理的リアクタンス」と呼ばれる現象なんです。人間には自分で決めたいという自律性の欲求があり、特に思春期にはこの欲求が非常に強くなります。命令されると、自分の自由が奪われたと感じて、意図的に反対の行動を取りたくなるんですね。
「やらされている」という感覚は、内発的な動機づけを完全に破壊してしまいます。本当のやる気を引き出すには、自分で決めたという感覚が必要です。
テストの結果が怖くて逃げたくなる
- 過度な不安が学習回避を引き起こす
- 自己防衛的な心理メカニズム
- 失敗を学びの機会として捉え直すことが重要
試験に対する過度な不安は、逆説的に学習回避を引き起こすことがあります。
「勉強しなかったから点数が悪くても仕方ない」という言い訳を無意識に準備することで、自尊心を守ろうとするんです。本気で頑張って失敗するよりも、最初から頑張らない方が傷つかないと脳が判断するんですね。
失敗を恐れる気持ちは誰にでもあります。大切なのは、失敗を学びの機会として捉え直すことです。完璧を求めずに、少しずつ改善していく姿勢を持ちましょう。
スマホやゲームの誘惑に勝てない
- 集中力を阻害する最大の要因
- 脳が本能的に新しい刺激に反応
- 物理的に距離を取ることが効果的
スマートフォンは、現代の学生にとって集中力を阻害する最大の要因です。
脳は新しい刺激を求めるように設計されており、勉強という単調な活動よりも、次々と変化するスマホの情報の方が脳にとって魅力的に感じられてしまうんですね。「ちょっとだけ見るつもり」が、気づいたら何時間も経っていたという経験は誰にでもあるはずです。
スマホは手元にあるだけで、集中力を著しく低下させることが研究でわかっています。勉強中は物理的に別の部屋に置くなど、距離を取ることが効果的です。
睡眠不足で頭が働かない
- 認知機能に絶対必要な要素
- 前頭前野の機能を直接的に損なう
- 深夜のスマホ使用が主な原因
十分な睡眠は、集中力や記憶力といった認知機能にとって絶対に必要な要素です。
睡眠不足は前頭前野の機能を直接的に損ない、やる気も集中力も低下させます。多くの学生の睡眠不足の原因は、深夜のスマホ使用です。夜遅くまでSNSやゲームをしていると、翌日の脳のパフォーマンスが大幅に下がってしまいます。
7〜8時間の睡眠を確保することは、勉強時間を増やすよりも優先すべき重要事項です。質の良い睡眠こそが、学習効率を最大化する土台になります。
今すぐ実践できる!やる気を出す方法7選
- まずは5分だけやってみる
- 好きな科目から始める・小さな目標を設定する
- ご褒美・友達・場所・文房具で工夫する
ここからは、心理学や脳科学の知見に基づいた、すぐに試せる具体的な方法をご紹介します。
自分に合いそうなものから、気軽に試してみてくださいね。
まずは5分だけやってみる作戦
- 行動のハードルを下げる効果
- 始めた行動を続けやすい脳の性質を利用
- 完璧主義の人に特に効果的
「5分だけ勉強する」という小さな目標から始めると、行動のハードルがぐっと下がります。
脳は一度始めた行動を続けやすい性質を持っており、最初の一歩が最も困難で、動き始めれば意外と続けられることが多いんですね。簡単な問題を1問だけ解く、教科書を1ページだけ読むといった、本当に小さな目標を設定しましょう。
5分経ってもやる気が出なければ、無理せず休憩してもOKです。でも多くの場合、始めてしまえば自然と続けられるものなんです。小さな成功体験の積み重ねが、やる気を育てていきます。
好きな科目から始めてみよう
- 楽しめる内容で脳をポジティブな状態に
- 有能感を感じられる活動から始める
- 良い気分が次の科目にも持ち越される
苦手な科目から始めると、最初からストレスを感じてしまいます。
好きな科目や得意な科目から取り組むことで、勢いをつけることができるんです。楽しめる内容で学習を始めると脳がポジティブな状態になり、この良い気分が次の科目にも持ち越されやすくなります。
数学が好きなら計算問題から、歴史が好きなら好きな時代から。楽しいと思える入口から勉強の世界に入っていくことが、継続の秘訣です。
小さな目標を設定して達成感を味わう
- 毎日達成できる具体的な目標を立てる
- 小さな達成感が自己効力感を高める
- 目標を紙に書いて見える場所に貼る
「試験に合格する」という大きな目標だけでは、日々のやる気を維持するのは難しいものです。
「今日は英単語を10個覚える」「数学の問題集を3ページ進める」といった具体的で測定可能な目標を立てましょう。達成したら、自分を褒めてあげることも忘れずに。
小さな達成感の積み重ねが、脳に成功体験として記録されていきます。目標は紙に書いて見える場所に貼ると、さらに効果的です。
勉強後のご褒美を用意する
- 外発的動機づけとして有効
- 脳が報酬を期待すると前向きになる
- ご褒美は勉強を終えてからというルールを守る
勉強の完了に対して報酬を設定することは、特に内発的な興味が湧きにくい科目で有効な方法です。
ご褒美は、好きなお菓子を食べる、ゲームを30分する、好きな動画を見るなど、自分が本当に楽しみにできるものを選びましょう。ただし、ご褒美は勉強を終えてからというルールを守ることが重要です。
脳は報酬を期待すると、その活動に対して前向きになります。「これが終われば好きなことができる」という見通しが、頑張る原動力になるんですね。
友達と一緒に勉強してみる
- 関係性という心理的欲求を満たす
- 教え合うことで理解が深まる
- メリハリをつけることが大切
一人では続かない勉強も、友達と一緒なら頑張れることがあります。
友達と勉強することで、わからないところを教え合ったり、励まし合ったりできます。他人に説明することで、自分の理解も深まるという効果もあるんですね。
ただし、おしゃべりに夢中になって勉強が進まないのでは意味がありません。時間を決めて集中する、休憩時間だけ会話するなど、メリハリをつけることが大切です。頑張っている人が周りにいる環境は、自然とやる気を引き出してくれるものです。
場所を変えて気分転換する
- 環境を変えて脳に新鮮な刺激を与える
- 図書館は静かで勉強に適した雰囲気
- カフェの適度な環境音が集中力を高めることも
いつも同じ場所で勉強していると、マンネリ化してやる気が出なくなることがあります。
図書館、カフェ、学校の自習室など、自宅以外の場所で勉強してみましょう。場所を変えるだけで、不思議と集中できることがあります。図書館は静かで勉強に適した雰囲気があり、カフェは適度な環境音があって一部の研究ではこれが集中力を高める可能性が示されています。
環境を変えることで、気持ちもリフレッシュできますね。
お気に入りの文房具を使ってテンションを上げる
- 好きな道具で勉強時間が楽しくなる
- 勉強を始めるきっかけになる
- 形から入ることは決して悪いことではない
新しいノートやペンを使うと、なんだかワクワクしませんか。
書き心地の良いペン、デザインが気に入ったノート、機能的な付箋やマーカー。自分が使っていて楽しい道具を揃えることで、勉強時間が少し楽しくなるんです。
道具を変えただけで学力が上がるわけではありませんが、「この新しいノートに綺麗にまとめたい」という気持ちが勉強を始めるきっかけになることがあります。形から入ることは決して悪いことではありません。
集中力が続かない時の対処法
- ポモドーロ・テクニックで時間管理
- 科目を切り替えてリフレッシュ
- 15分の仮眠で脳をリセット
やる気はあるのに集中が続かないという悩みも多いですよね。
ここでは、集中力を維持するための科学的に効果が認められている方法をご紹介します。
ポモドーロ・テクニックで時間管理
- 25分勉強+5分休憩のサイクル
- タイマーを使って集中時間を見える化
- 燃え尽きを防ぐ効果がある
ポモドーロ・テクニックは、25分間集中して勉強し、その後5分間休憩するというサイクルを繰り返す時間管理法です。
人間の集中力は一般的に25〜60分程度しか持続しないことがわかっています。無理に長時間続けるよりも、短い集中と休憩を繰り返す方が結果的に効率が良いんですね。このサイクルを4回繰り返したら、15〜30分の長めの休憩を取りましょう。
タイマーを使う際は、スマホではなく物理的なタイマーがおすすめです。時間が視覚化されることで、「あと○分頑張ればいい」という見通しが立ち、集中を維持しやすくなります。最初は25分が長く感じるかもしれませんが、15分から始めて徐々に時間を延ばしていくのも良い方法です。
科目を切り替えてリフレッシュ
- 使う脳の領域を変えてリフレッシュ
- 暗記に飽きたら計算問題に挑戦
- 得意科目と苦手科目を交互にやってみる
同じ科目や同じタイプの学習を続けていると、脳が疲れて集中力が低下します。
英単語の暗記に疲れたら、数学の計算問題に切り替えてみましょう。使う脳の領域が異なるため、リフレッシュ効果があります。読む活動から書く活動へ、インプットからアウトプットへと活動のタイプを変えることで、新鮮な気持ちで取り組めます。
また、得意科目と苦手科目を交互に配置することで、バランスよく学習を進められます。得意科目で達成感を得ることで、次の苦手科目にも前向きに取り組む原動力になりますよ。
15分の仮眠で脳をリセット
- 午後2時から3時頃がベストタイミング
- 15〜20分以内に抑えることが重要
- 寝すぎると逆効果になる
どうしても眠くて集中できない時は、短時間の仮眠が効果的です。
仮眠に最適な時間帯は午後2時から3時頃で、この時間帯は人間の体内リズムで自然と眠気が強まる時間なんです。15〜20分程度の短い仮眠は、脳をリフレッシュさせ、午後の集中力を大幅に向上させます。
仮眠は必ず15〜20分以内に抑えることが重要です。30分以上眠ってしまうと深い睡眠に入り、起きた後にかえって眠気や倦怠感が残ります。アラームを必ずセットして、寝過ごさないようにしましょう。
勉強しやすい環境の作り方
- 机の上を片付けて視覚的ノイズを減らす
- スマホは別の部屋に置く
- 照明と室温を調整する
どんなにやる気があっても、環境が整っていないと集中は続きません。
物理的な環境を最適化することで、学習効率は大きく変わるんです。
机の上を片付けるだけで集中力アップ
- 視覚的ノイズが脳のエネルギーを消費
- 勉強に関係ないものを排除
- シンプルな環境が集中力を引き出す
散らかった机は視覚的なノイズを生み出し、脳はそれを無視するために貴重なエネルギーを消費します。
勉強に関係ないものは、すべて机の上から排除しましょう。スマホ、漫画、ゲーム機など、誘惑の元になるものは特に注意が必要です。必要な教材や文房具だけを手の届く範囲に置き、それ以外は引き出しや棚にしまいます。
シンプルな環境が、脳の集中力を最大限に引き出してくれるんですね。勉強前の5分間を片付けの時間に充てることで、気持ちも整理できて一石二鳥です。
スマホは別の部屋に置こう
- 視界に入るだけで集中力が低下
- 物理的に距離を取ることが最も効果的
- 緊急の連絡は家族に伝えておく
スマホが視界に入るだけで、集中力は大幅に低下することが研究で明らかになっています。
別の部屋に置く、引き出しにしまう、保護者に預けるなど、簡単には手に取れない状況を作りましょう。机の上に裏返して置くだけでは、効果は薄いんです。
どうしても心配な場合は、家族に「何かあったら呼んで」と伝えておけば安心です。スマホから離れることが、集中への最短ルートなんです。
照明と室温を調整してみる
- 昼光色が集中力を高める
- 快適な室温は21〜25度
- 換気で二酸化炭素濃度を下げる
環境の感覚的な要素は、集中力に決定的な影響を与えます。
照明は、青白い昼光色が集中力を高める効果があります。ただし長時間使うと疲れやすいので、夜遅くまで勉強する場合は暖色系の光の方が目に優しいですね。室温は21〜25度が快適とされています。
換気も忘れずに。部屋の空気がこもると二酸化炭素濃度が上がり、頭がぼーっとしてきます。1時間に1回は窓を開けて、新鮮な空気を取り入れることが大切です。
図書館やカフェで勉強する選択肢
- 図書館は静寂と学習に適した雰囲気を無料で提供
- カフェは適度な環境音で集中力アップの可能性
- 自分に合った場所を見つけることが大切
自宅の環境がどうしても勉強に適さない場合、外部の場所を活用するのも良い方法です。
図書館は静寂と学習に適した雰囲気を無料で提供してくれる、学生にとって最高の環境です。周りも勉強している人ばかりなので、自然と集中できます。ただし人気の図書館は席が埋まりやすく、試験期間には座れないこともあります。
カフェは適度な環境音があり、完全な静寂よりも少し音がある方が落ち着く人に向いています。勉強する内容や自分の性格に合わせて、上手に活用しましょう。
勉強習慣をつけるための工夫
- 毎日同じ時間に勉強を始める
- 勉強前のルーティンを作る
- 勉強記録をつけて可視化する
- 完璧主義をやめて60点を目指す
一時的にやる気を出すだけでなく、持続的に勉強を続けられる習慣を作ることが大切です。
ここでは、習慣化のための具体的な方法をご紹介します。
毎日同じ時間に勉強を始める
- 脳は繰り返しのパターンを好む
- 習慣化されれば自然と勉強モードに
- 柔軟性を持ちながら基本リズムを守る
脳は繰り返しのパターンを好みます。
毎日同じ時間に勉強を始めることで、その時間になると自然と勉強モードに入りやすくなるんです。「夕食後の7時から」「学校から帰ってきたらすぐ」など、具体的な時間を決めましょう。
習慣になれば、いちいち「やるか、やらないか」と悩む必要がなくなります。歯磨きのように、当たり前の行動として勉強ができるようになるんですね。ただし体調が悪い時は無理をしないことも大切です。
勉強前のルーティンを作る
- 脳に「集中する時間」の合図を送る
- 学習モードへの移行を自動化
- 簡単で短時間のルーティンから始める
一貫した学習前の儀式を作ることで、脳に「これから集中する時間だ」という合図を送ることができます。
例えば、「コップ一杯の水を飲む」「机の上を整理する」「計算問題を5問解く」といった簡単な行動をルーティンとして決めましょう。毎回同じ行動を繰り返すことが重要です。
このルーティンは、スポーツ選手が試合前に行う準備運動と同じような効果があります。続けるうちに、このルーティンをするだけで自然と集中できるようになりますよ。
勉強記録をつけて可視化する
- 達成感を得られる
- 学習ペースを客観的に把握
- 学習パターンの分析ができる
自分がどれだけ勉強したかを記録することで、達成感を得られるとともに、学習のペースを客観的に把握できます。
ノートに日付と勉強時間を書く、カレンダーに印をつける、アプリで記録するなど、方法は何でも構いません。大切なのは、続けやすい方法を選ぶことです。
記録を見返すと、自分が積み重ねてきた努力が目に見えて分かります。どの時間帯に集中できているか、どの科目にどれくらい時間を使っているかなど、学習パターンの分析もできますよ。
完璧主義をやめて60点を目指す
- 完璧を求めすぎると学習が停滞
- 繰り返し学習で徐々に完成度を高める
- 気楽な姿勢が学習継続の秘訣
完璧を求めすぎると、かえって学習が停滞してしまいます。
教材を一言一句すべて覚えてからでないと次に進めないという姿勢は、認知的な過負荷を招き、燃え尽き症候群につながります。重要なポイントを押さえたら、どんどん先に進むことが大切です。
一度で完璧を目指すのではなく、何度も繰り返すことで徐々に完成度を高めていく方が、結果的に効率が良いんです。「とりあえずやってみる」という気楽な姿勢が、学習を継続する秘訣です。
モチベーションを維持するコツ
- 将来の目標と今の勉強を結びつける
- 成功体験を積み重ねて自信をつける
- 偉人の名言や勉強アプリを活用する
やる気を出すだけでなく、それを長期的に維持することが成功の鍵です。
ここでは、モチベーションを保つための心理的な戦略をご紹介します。
将来の目標と今の勉強を結びつける
- 最も強力な内発的動機づけ
- 具体的な職業や目標と関連付ける
- 目標を紙に書いて貼る
目の前の勉強が自分の将来とどう繋がっているかを理解することで、学習に意味を見出すことができます。
「医者になりたいから生物を学ぶ」「プログラマーになりたいから数学が必要」というように、夢と学習を直接結びつけましょう。抽象的な「将来のため」ではなく、具体的な職業や目標と関連付けることが重要です。
目標を紙に書いて机に貼っておくと、やる気が出ない時の良いリマインダーになります。「なぜ今頑張っているのか」を常に意識することで、モチベーションを維持できます。
成功体験を積み重ねて自信をつける
- 自己効力感を育てる
- 確実に達成できる目標から始める
- 成功の瞬間を記録する
小さな成功体験の積み重ねが、「自分はできる」という自己効力感を育てます。
最初は本当に簡単な目標から始めましょう。「英単語を5個覚える」「問題集を1ページ解く」など、確実に達成できる目標を設定します。達成したら、自分を褒めることを忘れずに。
テストで良い点を取った時、難しい問題が解けた時、そういった成功の瞬間を記録しておきましょう。自信を失いかけた時に見返すことで、再び立ち上がる力をもらえます。
偉人の名言から刺激をもらう
- 困難に直面した時の心理的支え
- 心に響く名言を見つける
- 机の前に貼ったりスマホの壁紙に設定
歴史上の偉人やアスリート、成功者の言葉は、困難に直面した時の強力な心理的支えになります。
例えば、トーマス・エジソンの「成功は1%のひらめきと99%の努力である」という言葉は、努力の大切さを教えてくれます。イチローの「やってみてダメだとわかったことと、はじめからダメだと言われたことは、違います」という言葉は、挑戦する勇気をくれますね。
自分の心に響く名言を見つけたら、机の前に貼ったりスマホの壁紙に設定したりしましょう。やる気が出ない時に目にすることで、気持ちを奮い立たせることができます。
勉強アプリを活用して楽しく学ぶ
- ゲーム感覚で学べる工夫
- 学習記録の自動化と可視化
- 補助的なツールとして上手に活用
テクノロジーを味方につけることで、勉強をより効率的で楽しいものにできます。
英単語学習アプリではクイズ形式で楽しく暗記でき、数学アプリでは間違えた問題を自動で記録してくれます。学習記録を自動でつけてくれるアプリも便利で、グラフで進捗が可視化されるため達成感を得やすくなります。
ただし、アプリに頼りすぎて基本的な学習がおろそかにならないよう注意が必要です。アプリは補助的なツールとして、上手に活用しましょう。
生活習慣を見直してやる気アップ
- 7〜8時間の睡眠を確保
- 朝ごはんで脳にエネルギー補給
- 適度な運動で集中力を高める
勉強のやる気は、日々の生活習慣に大きく影響されます。
身体と脳の健康を整えることが、学習意欲の土台になるんです。
7〜8時間の睡眠を確保しよう
- 認知機能に絶対必要な要素
- 睡眠中に記憶が定着
- 就寝1時間前にはデジタル機器から離れる
十分な睡眠は、集中力、記憶力、やる気といったすべての認知機能にとって絶対に必要な要素です。
睡眠中に脳は、その日学んだ情報を整理して記憶に定着させています。睡眠不足だと、せっかく勉強した内容が頭に残りにくくなるんですね。
疲れた状態で長時間勉強するよりも、しっかり寝て短時間集中する方が、はるかに効率が良いんです。就寝1時間前にはデジタル機器から離れ、リラックスする時間を作りましょう。
朝ごはんを食べて脳にエネルギー補給
- 脳の主な燃料はブドウ糖
- バランスよく栄養を摂取
- 勉強中の間食も上手に活用
脳はエネルギーを大量に消費する器官で、その主な燃料はブドウ糖です。
朝食を抜くと、午前中の集中力が大幅に低下してしまいます。忙しくても、バナナ一本とヨーグルト、おにぎりと味噌汁など、簡単なものでも構いません。何も食べないよりは、少しでも口にする方が断然良いです。
勉強中の間食も上手に活用しましょう。ナッツやドライフルーツなど、血糖値が緩やかに上がる食べ物がおすすめです。
適度な運動で集中力を高める
- 脳への血流を改善
- 軽い運動で十分効果あり
- 気分転換とストレス解消にも
定期的な運動は、脳への血流を改善し、記憶力や集中力を高める効果があることが科学的に証明されています。
激しい運動をする必要はありません。軽いジョギング、ウォーキング、ストレッチなど、気持ちよく体を動かせる程度で十分です。週に2〜3回、30分程度を目安に取り組みましょう。
1時間に1回は立ち上がって、軽く体を動かすことをおすすめします。2〜5分程度の短い運動でも、頭をリフレッシュさせる効果があるんです。
親ができるサポートとは?
- 「勉強しなさい」は逆効果の可能性
- 学習環境を整える
- 努力を褒める・一緒に目標を立てる
保護者の方の関わり方は、お子さんの学習意欲に大きな影響を与えます。
ここでは、効果的なサポート方法をご紹介します。お子さんが勉強しないことでお悩みの方は、「子どもが勉強しない時の対処法」も参考にしてみてくださいね。
「勉強しなさい」は逆効果かも
- 自律性を脅かし反発を招く
- 内発的動機づけは育たない
- 子どもの主体性を尊重する声かけを
「勉強しなさい」という命令は、特に思春期の子どもにとって逆効果になることが多いんです。
心理学では、これを心理的リアクタンスと呼びます。自分で決めたいという欲求が強い時期に命令されると、わざと反対の行動を取りたくなるのが人間の心理なんですね。
「勉強しなさい」と言えば言うほど、子どもは勉強を「親のためにやらされるもの」と認識してしまいます。命令するのではなく、「今日は何を勉強する予定?」「何か手伝えることある?」と、子どもの主体性を尊重する声かけを心がけましょう。
勉強しやすい環境を整える
- 物理的な環境づくり
- スマホを預かる協力体制
- 規則正しい生活のサポート
保護者の方ができる最も効果的なサポートの一つが、学習に適した環境を整えることです。
机の上を片付けるのを手伝ったり、適切な照明を用意したり、勉強中は家族がテレビの音量を下げるなど、物理的な環境づくりが大切です。また、勉強時間中はスマホを預かるという協力体制を築くのも効果的です。
規則正しい生活リズムをサポートすることも重要です。早寝早起きを促し、バランスの良い食事を用意することで、子どもの脳が最高のパフォーマンスを発揮できる土台を作ってあげましょう。
結果より努力を褒めてあげる
- プロセスに注目して褒める
- 成長思考を育てる
- 具体的な行動を認める
テストの点数だけを評価するのではなく、プロセスに注目して褒めることが大切です。
結果だけを褒めると、子どもは失敗を恐れるようになります。一方、努力を褒められると、結果に関係なく頑張ること自体に価値があると学びます。失敗しても「次はどう工夫しよう」と前向きに考えられるようになるんです。
「今日も集中して勉強していたね」「苦手な科目にも挑戦している姿が素晴らしいよ」といった、具体的な行動を認める言葉をかけてあげましょう。
一緒に目標を立ててあげる
- 子どもと一緒に考える
- 短期的な目標も設定
- 定期的な振り返りの時間を作る
目標設定を手伝うことは、効果的なサポート方法です。
「どんな高校に行きたい?」「将来はどんなことをしてみたい?」と、まず子ども自身の希望を聞きましょう。その上で、その目標を達成するために何が必要かを一緒に考えていきます。
大きな目標だけでなく、短期的な目標も設定しましょう。「今週は数学の問題集を10ページ進める」など、具体的で達成可能な目標が良いですね。定期的に振り返りの時間を作り、達成できたことを一緒に喜び、できなかったことは改善策を考えましょう。
どうしてもやる気が出ない時は専門家に相談
- 持続的で重篤な症状は要注意
- うつ症状や発達障害の可能性
- 専門家への相談が大切
一時的な意欲の低下は誰にでもありますが、症状が長期間続き、日常生活に支障をきたす場合は、専門家の助けが必要かもしれません。
こんな症状があったら要注意
- 持続的な気分の落ち込み
- 興味の喪失と疲労感
- 身体症状(朝起きられない等)
単なる「やる気が出ない」を超えて、以下のような症状が数週間以上続く場合は注意が必要です。
持続的な気分の落ち込み、あらゆることへの興味の喪失、食欲や睡眠の著しい変化などが挙げられます。疲労感が常にある、無価値感や罪悪感に苛まれる、以前は簡単にできたことができなくなった、といった症状も要注意です。
朝起きられない、立ちくらみ、頭痛、動悸といった身体症状が午前中に強く出る場合は、起立性調節障害の可能性も考えられます。これは自律神経の機能不全で、決して怠けているわけではありません。
うつ症状や発達障害の可能性
- 受験うつの特徴
- ADHDは生まれつきの脳の特性
- 周囲からの誤解が問題を悪化させる
受験うつは、単なる気分の落ち込み以上の深刻な状態です。
集中困難、意欲の低下、自己評価の著しい低下などが特徴で、学業だけでなく日常生活全体に影響を与えます。ADHDは不注意や多動性・衝動性の持続的なパターンを特徴とする神経発達症で、適切な診断と支援があれば学習方法を工夫することで能力を発揮できます。
ランナーには発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフが在籍しています。注意が続きにくい、こだわりが強いといった特性があるお子さんへの対応経験も豊富です。発達障害のお子さんへの学習サポートについては、「発達障害の子に合った家庭教師の選び方」で詳しく解説しています。
専門医や心理カウンセラーへの相談
- 症状の持続期間・重篤度・広範性が指標
- 正確な診断で適切な治療を
- 早期支援が重要
症状が持続する場合、重篤な場合、学校や家庭生活に著しい支障がある場合は、迷わず専門家に相談しましょう。
小児科、精神科、心療内科などが相談先になります。正確な診断を受けることで、適切な治療や支援を受けられるようになります。ADHDには薬物療法や行動療法、環境調整が有効で、うつ病には心理療法や薬物療法が効果を示します。
早期に適切な支援を受けることで、学習への意欲を取り戻し、本来の能力を発揮できるようになります。不登校傾向のあるお子さんの学習については、「不登校の子が勉強しない時の対処法」も参考にしてみてください。
家庭教師という選択肢もある
- 自分一人では難しい場合の選択肢
- プロの指導であなたのペースに合わせた学習が可能
- やる気を引き出す専門的なサポート
自分一人では勉強のやる気を出すのが難しい、学習方法がわからないという場合、家庭教師のサポートを受けることも効果的な選択肢です。
プロの指導で、あなたのペースに合わせた学習が可能になります。
家庭教師のランナー|やる気を引き出す指導が得意

- 勉強が苦手な小中高生専門で21年の実績
- 講師数・指導実績が国内最大級(講師14万人)
- 兄弟同時指導で2人目以降の月々の料金が半額以下
- 発達障害や不登校の子供にも対応
家庭教師のランナーは、勉強が苦手な小中高生専門を掲げる家庭教師グループです。
創業21年の実績があり、一人ひとりの個性に合わせたオーダーメイド指導を行っています。反抗的な子や無気力な子でも「わかる楽しさ」を感じてもらい自信につなげる指導理念を持っています。2024年の第一志望合格率は97.5%。勉強が苦手だったお子さんも、正しいサポートで成果を出しています。
料金は比較的リーズナブルで、小・中学生は1コマ30分あたり900円です。週1回60分で月約12,000円から利用できます。兄弟や友達と2人で同時に受けると、2人目以降の月々の料金が半額以下になります。
家庭教師のトライ|完全マンツーマンでモチベーション管理

- 業界最大手で全国33万人以上の登録教師
- 専任の教育プランナーが家庭と教師をつなぐ
- トライ式学習法による個別指導
- 30年以上の実績と受験情報の蓄積
家庭教師のトライは業界最大手で、全国33万人以上の登録教師から相性の良い教師を選べます。
完全マンツーマン指導で「トライ式学習法」という独自メソッドを採用し、きめ細かいオーダーメイドカリキュラムで指導します。専任の教育プランナーが家庭と教師をつなぐサポートを行うんです。
1時間あたりの授業料は4,620円(税込)からが目安です。週1回60分の場合、月額換算で約18,000円前後から利用できます。講師は万が一相性が合わない場合は無料で何度でも交代可能です。
家庭教師のあすなろ|勉強嫌いな子専門の親身な指導
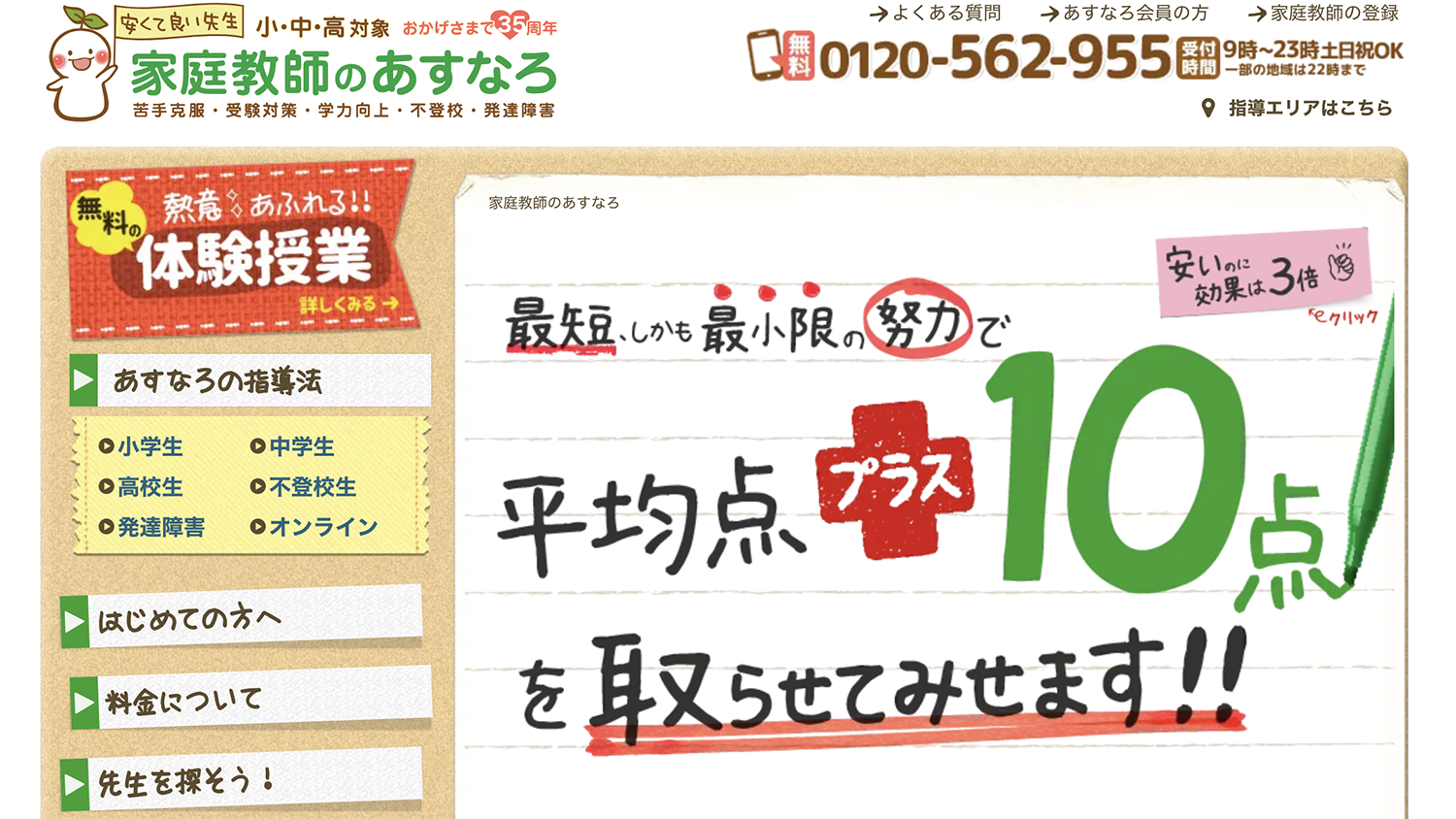
- 勉強が苦手な子専門で35年以上の実績
- 大学生中心の親近感のある指導
- 料金の安さと親しみやすさで人気
- LINEでいつでも質問できる無料サポート
家庭教師のあすなろは、「勉強が苦手な子専門」を掲げ、大学生中心の若い先生が親近感のある指導をしてくれます。
35年以上の運営実績があり、関東を中心に東北・関西・九州など全国各地に展開しています。基礎固めに重点を置いた指導方針が特徴です。
料金の安さと親しみやすい指導で人気があり、小学生・中学生は月16,000円程度から利用できます。LINEでいつでも質問できる無料サポート「お悩みお助け隊」があり、授業の無い日でも質問が可能です。
勉強やる気出ない時のまとめ
- ・やる気が出ないのは性格の問題ではなく、心理的欲求が満たされていないサイン
- ・原因は多様で、学習の意味の不明確さ、難易度、命令による反発、不安、誘惑、睡眠不足など
- ・5分ルール、好きな科目から始める、小さな目標設定など今すぐ試せる方法がある
- ・ポモドーロ・テクニックや科目の切り替えで集中力を維持できる
- ・環境整備、睡眠、栄養、運動といった生活習慣の見直しが土台
- ・保護者は命令ではなくサポーターとして環境を整え、努力を褒めることが大切
- ・長期間の重篤な症状は専門家への相談が必要
- ・家庭教師のサポートも効果的な選択肢の一つ
勉強のやる気が出ないという悩みは、決してあなただけのものではありません。
多くの学生が同じ壁にぶつかり、それを乗り越えてきたんです。やる気が出ない原因は、心理的な要因、環境的な問題、生活習慣の乱れなど、様々な要素が複雑に絡み合っています。自分に当てはまる原因を見つけることが、解決への第一歩です。
今すぐ試せる方法として、5分ルールや好きな科目から始めること、小さな目標設定、ポモドーロ・テクニックなどをご紹介しました。環境を整え、生活習慣を見直すことも、やる気を取り戻す重要な要素です。
保護者の方は、命令ではなくサポーターとして子どもを支えることが大切です。結果よりプロセスを褒め、一緒に目標を立てる姿勢が、子どもの自律性と意欲を育てます。症状が長期間続く場合は、専門家への相談を検討しましょう。
家庭教師のサポートも効果的な選択肢の一つです。自分に合った方法を見つけて、一歩ずつ前に進んでいきましょう。あなたなら必ずできます!