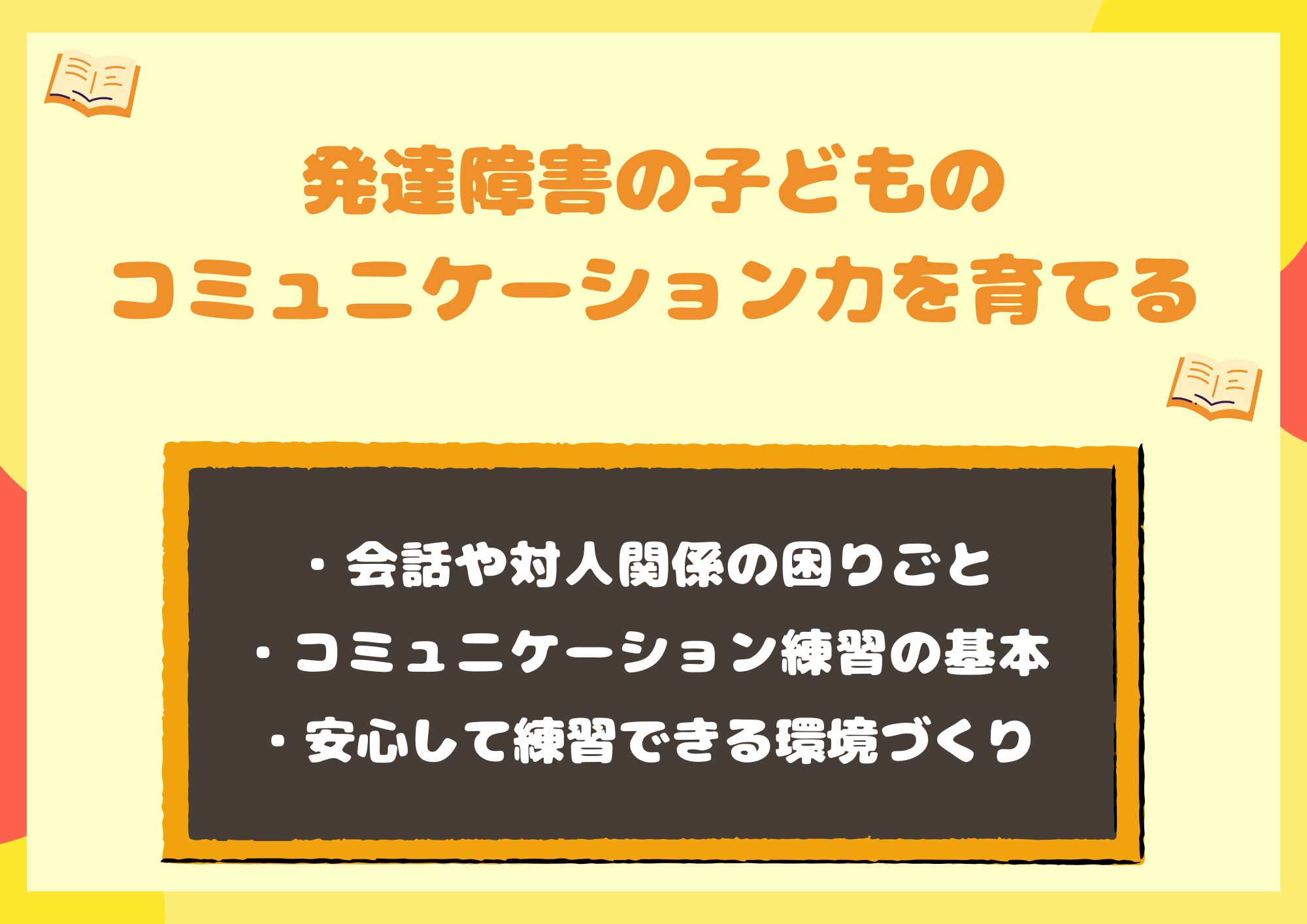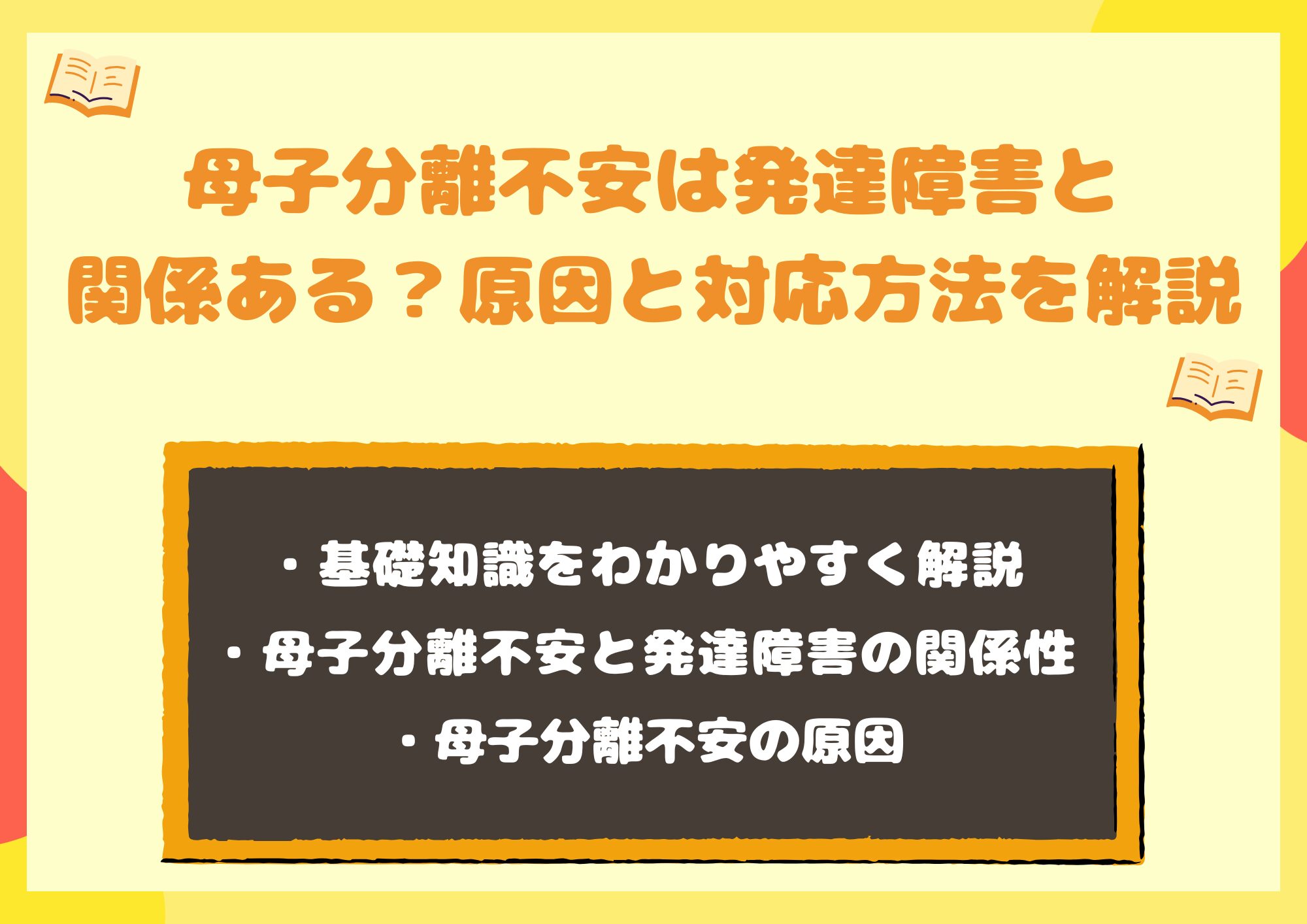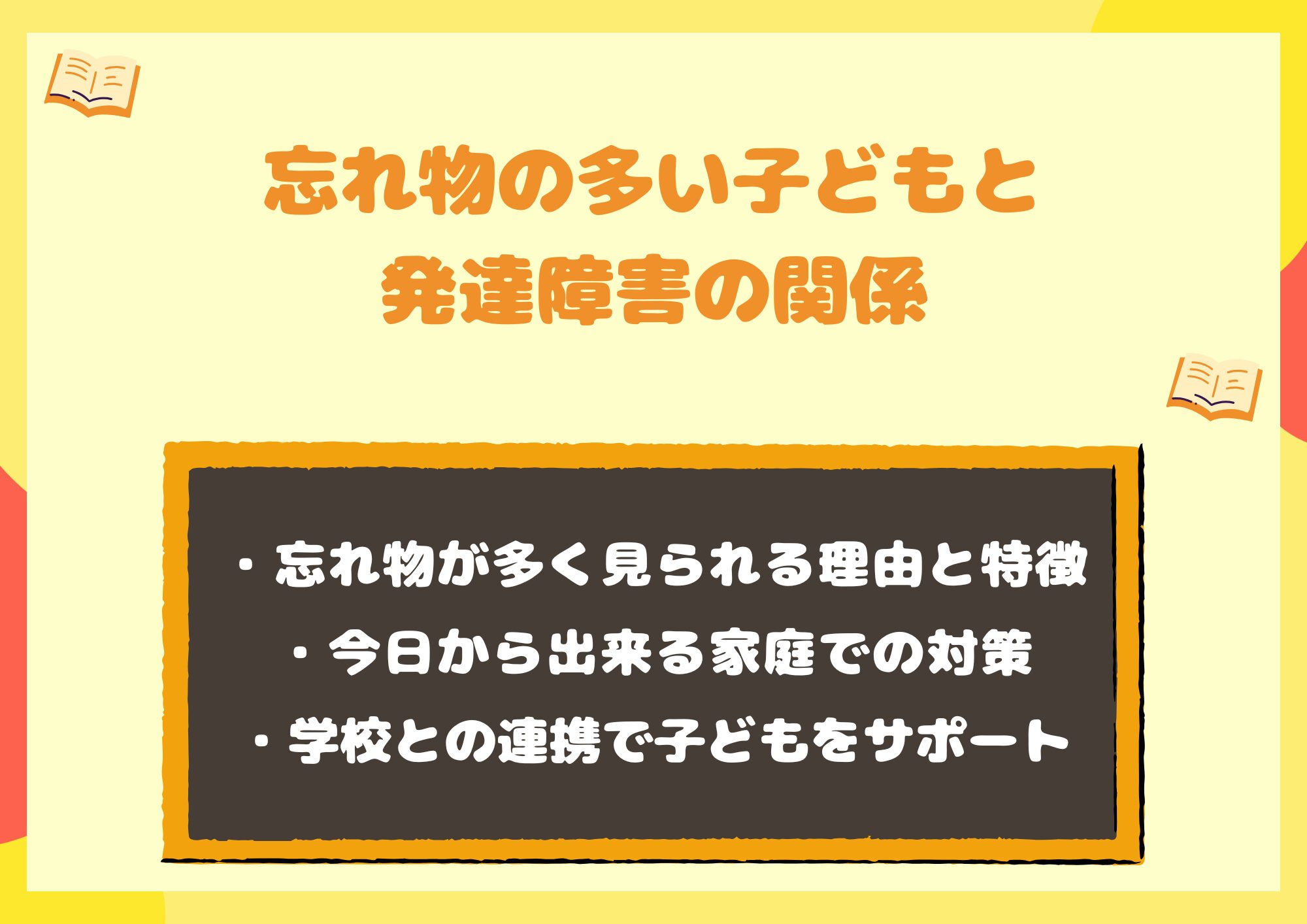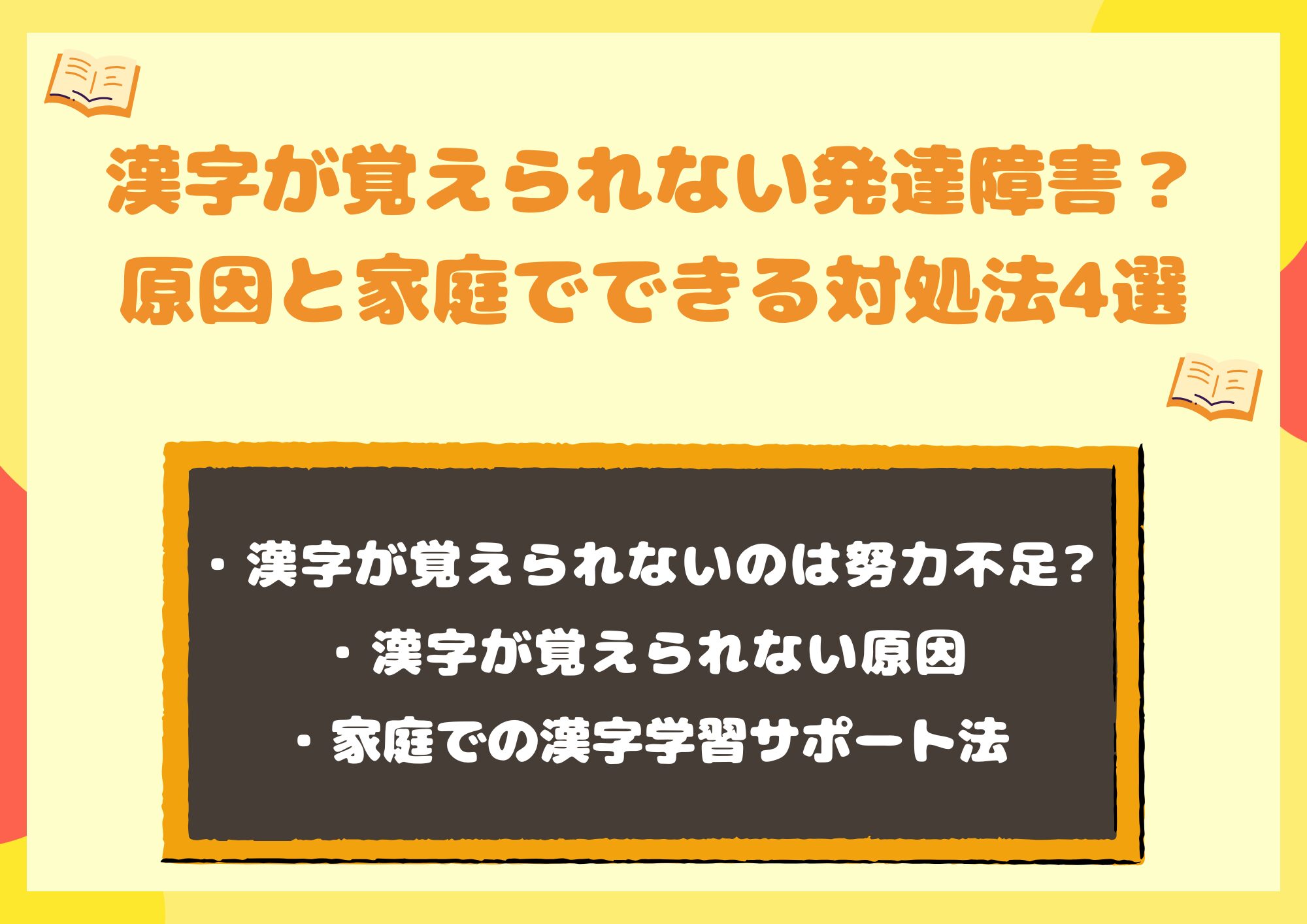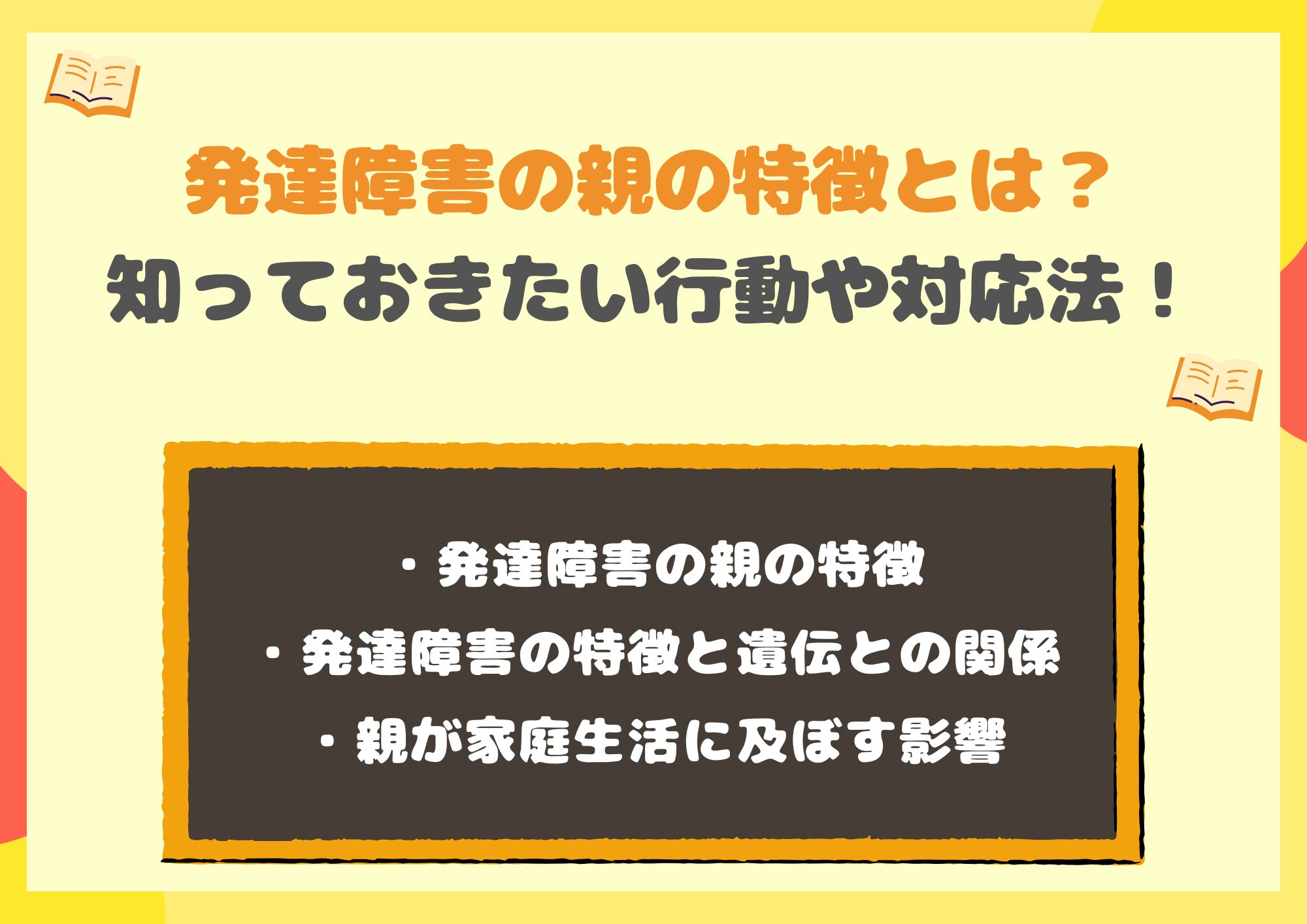- 発達障害向けの家庭教師
理解力がない子供の発達障害|今すぐできる支援方法と家庭教師選び
2025.09.25
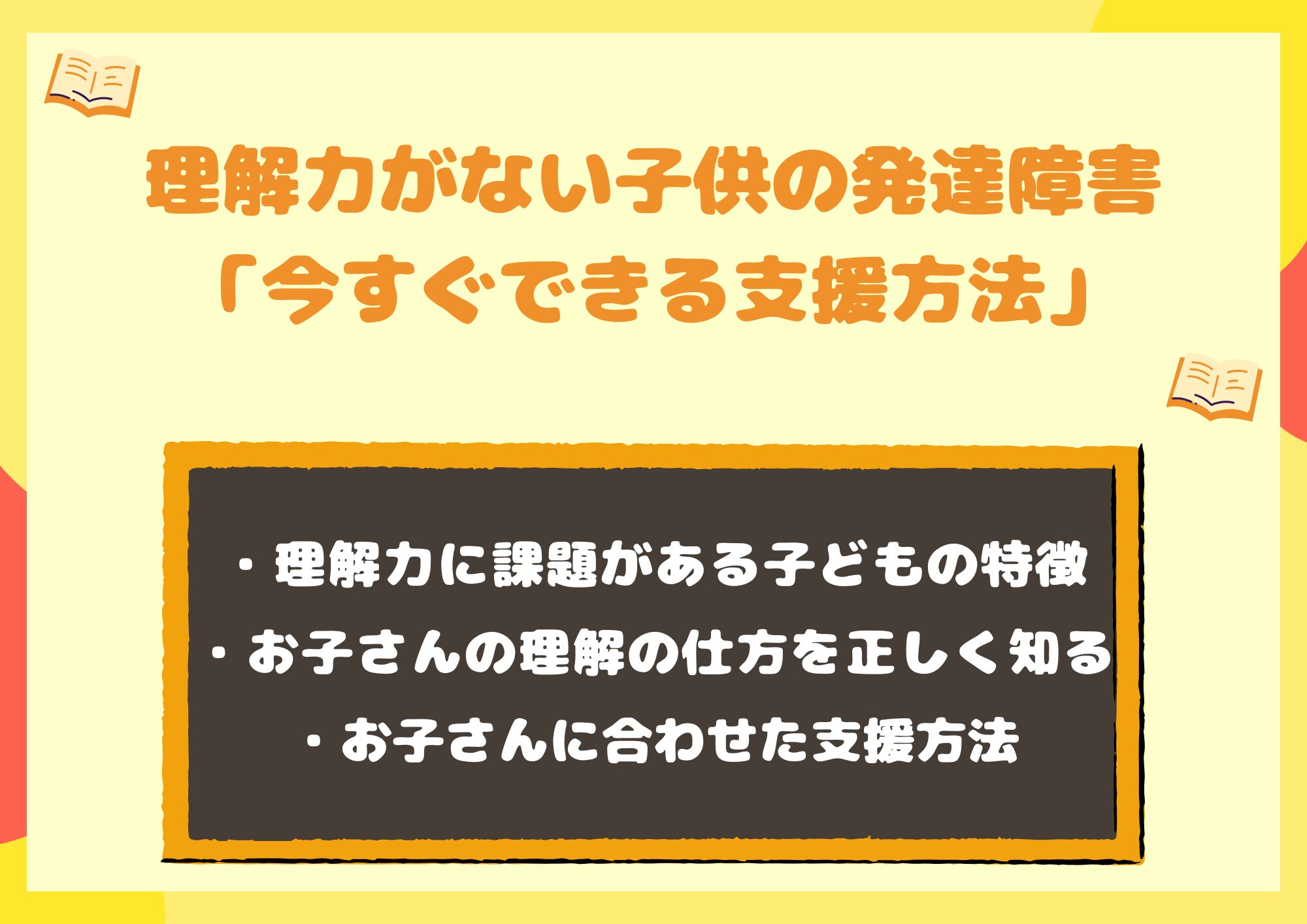
お子さんが発達障害で理解力に課題を抱えていると感じたとき、「何度説明しても伝わらない」「指示が通らない」という場面に直面して、親御さんは大きな不安を抱えているのではないでしょうか。
しかし、お子さんが理解できないのは決して「能力が低い」からではありません。
情報の受け取り方や処理の仕方が他の子と異なるだけで、その子に合った方法を見つければ理解が進みやすくなります。
この記事では、発達障害で理解力に課題がある子どもの特徴を正しく理解し、今日から家庭で実践できる具体的な支援方法、学校との連携のコツ、そしてお子さんに寄り添ってくれる家庭教師サービスの選び方まで、2025年最新の情報をもとに詳しく解説します。
目次
- 発達障害で理解力に課題がある子どもの特徴と「小さなサインに気づく」ポイント
- お子さんの理解の仕方を正しく知るための「基礎知識と誤解を解く」視点
- 今日から家庭で始められる「お子さんに合わせた」支援方法
- 発達障害のお子さんに寄り添う家庭教師サービス「選び方と特徴の比較」
- 家庭教師のランナーが選ばれる「きめ細かい対応と親身なサポート」の実績
- 家庭教師のトライの「個別最適化されたカリキュラム」で進める学習支援
- 学研の家庭教師が提供する「安心の実績と専門性」を活かした指導
- 家庭教師のサクシードで実現する「費用対効果の高い」マンツーマン指導
- 家庭教師ファーストの「体験から始められる」安心のスタート
- 家庭教師のノーバスが関東・東海で培った「豊富な支援実績」
- 家庭教師のあすなろが専門とする「勉強が苦手な子への寄り添い」指導
- 家庭教師学参のプロ講師による「専門性の高い個別対応」
- オンライン家庭教師Wamで実現する「送迎不要の低価格」サポート
- オンライン家庭教師トウコベの「東大生による丁寧な」オンライン指導
- オンライン家庭教師マナリンクの「経験豊富なプロ講師」によるサポート
- 学校との連携を進めて「一貫した支援を作る」実践的な方法
- 専門機関へ発達障害の相談を検討する時の「準備と心構え」
- お子さんの成長を見守る「長期的なサポート計画」の立て方
- 聞く力に課題があるお子さんへの「効果的な対応策」
- 発達障害で理解力に課題がある子どもについて「大切なポイント」のまとめ
発達障害で理解力に課題がある子どもの特徴と「小さなサインに気づく」ポイント
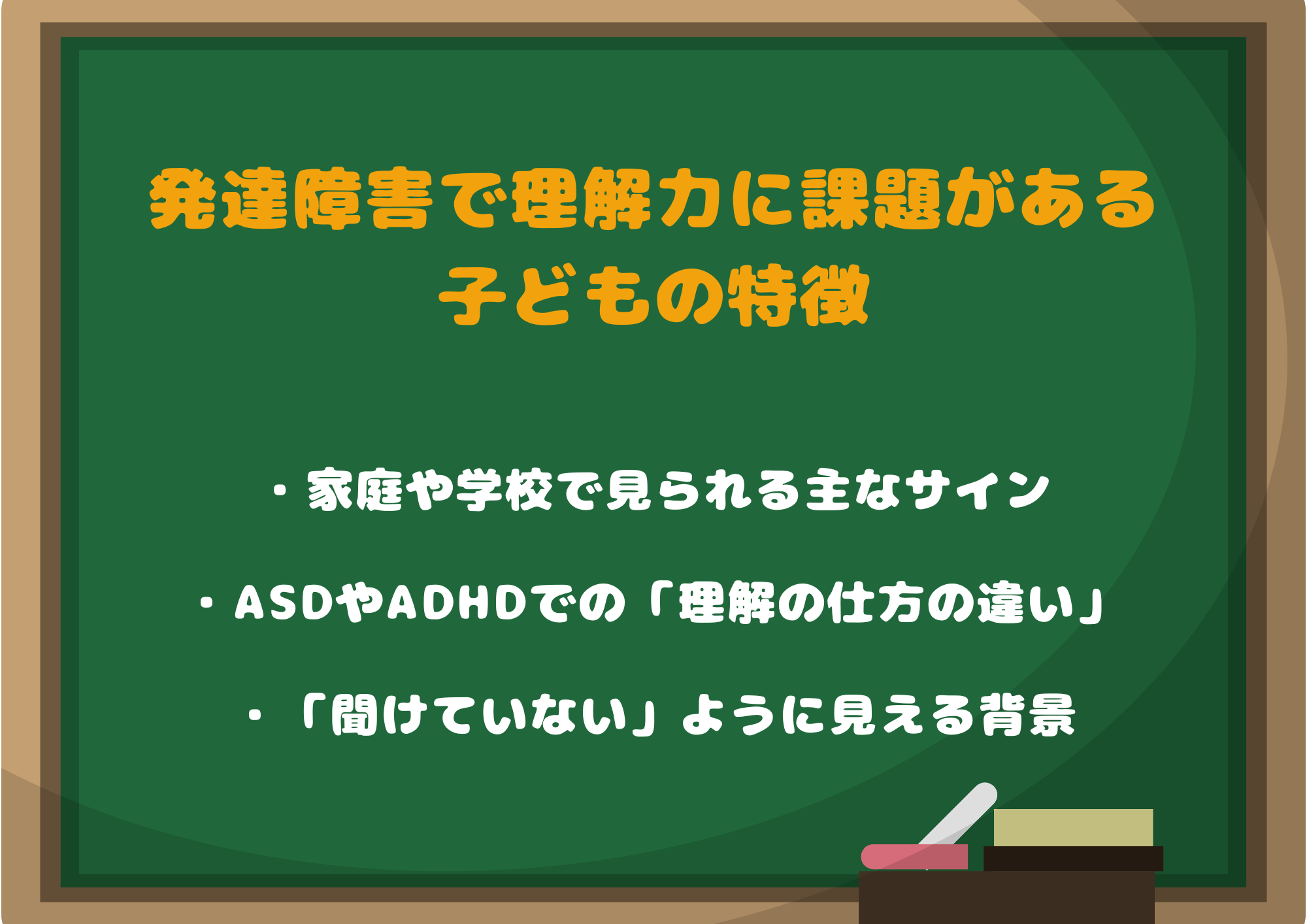
発達障害のある子どもの理解力の課題は、実は日常生活の中にたくさんのサインとして現れています。
例えば、「宿題のやり方を何度説明しても覚えられない」「先生の指示を聞いているようで聞いていない」といった場面で、親御さんは「うちの子は理解力がないのでは」と心配になることがあります。
しかし、これらのサインは発達障害の特性による情報処理の違いから生じている可能性が高く、適切な支援により改善が見込めるケースが多いです。
家庭や学校で見られる主なサインと「今すぐできる」チェック方法
- 口頭での指示が理解しにくい、複数の指示を同時に処理できない、抽象的な説明が苦手などの特徴がある
- 1週間の記録で「理解できた説明の手がかり」「環境音の有無」「指示の長さ」「反応までの待機時間」をチェック
- 時間帯や状況、説明方法をメモすることでお子さんの理解パターンが見えてくる
発達障害で理解力に課題がある子どもによく見られるサインには、口頭での指示が理解しにくい、複数の指示を同時に処理できない、抽象的な説明が苦手といった特徴があります。
家庭では宿題に取り組む際に「何から始めればいいか分からない」と固まってしまったり、学校では「黒板を写すのが遅い」「授業についていけない」といった困りごとが表れることが多いです。
親御さんができるチェック方法として、まず1週間お子さんの「理解できた説明の手がかり」「環境音の有無」「指示の長さ」「反応までの待機時間」を具体的に記録してみてください。時間帯や状況、どんな説明方法なら理解できたかをメモすることで、お子さんの理解パターンが見えてきます。
ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如多動症)などの特性別に見る「理解の仕方の違い」
- ASDは言葉を文字通りに受け取る傾向があり、比喩や暗黙の了解が理解しにくい
- ADHDは注意が散漫になりやすく、長い説明を最後まで聞くことが難しい
- LDは文字の認識や計算など特定の学習領域に困難が生じる
ASD(自閉スペクトラム症)の特性がある子どもは、言葉を文字通りに受け取る傾向があり、比喩や暗黙の了解が理解しにくいことがあります。
一方、ADHD(注意欠如多動症)の特性がある子どもは、注意が散漫になりやすく、長い説明を最後まで聞くことが難しい場合があります。LD(学習障害)の特性では、文字の認識や計算など特定の学習領域に困難が生じます。
それぞれの特性に応じて、視覚手がかり、短文での指示、具体例の提示などが有効な例として挙げられます。
家庭教師のランナーでは、こうした特性を理解した専門スタッフが、お子さん一人ひとりに合った学習方法を提案しています。
話を「聞けていない」ように見える背景と主な要因
- 「聞いていない」のではなく「聞こえているけど処理できない」状態であることが多い
- 聴覚過敏、ワーキングメモリの課題、言語理解の困難など様々な理由が背景にある
- 一文ずつ区切る、要点を視覚化する、復唱で確認するなどの対応が効果的
お子さんが話を聞けていないように見える場合、実は「聞いていない」のではなく「聞こえているけど処理できない」状態であることが多いです。
聴覚過敏で周囲の音が気になって集中できない、ワーキングメモリの課題で聞いた内容をすぐに忘れてしまう、言語理解の困難で話の内容が理解できないなど、様々な理由が背景にあります。
ワーキングメモリに課題がある場合は、一文ずつ区切って伝える、要点を付箋やカードで視覚化する、復唱で確認するといった対応が効果的です。お子さんが話を聞けないときは、まず環境を整え(静かな場所に移動する)、視覚的な手がかりを使い(メモや図を見せる)、短く区切って伝えることで、理解しやすくなります。
お子さんの理解の仕方を正しく知るための「基礎知識と誤解を解く」視点
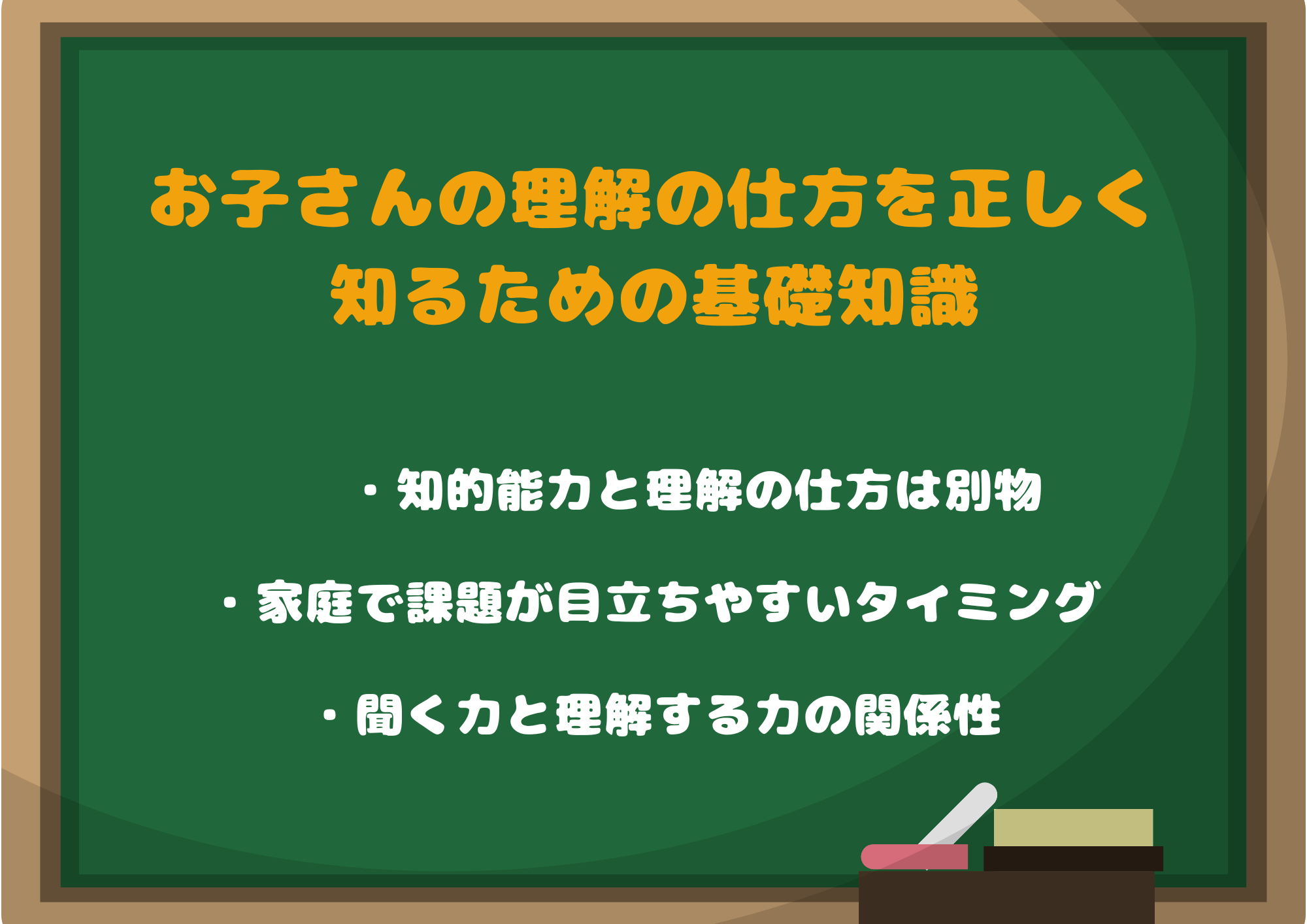
発達障害がある子どもの理解力について、多くの誤解が存在します。「理解力がない」という言葉は、実は正確ではありません。
正しくは「理解の仕方が異なる」「理解するために必要な支援が違う」ということです。お子さんの本当の力を引き出すためには、まず親御さんがこの違いを理解することから始まります。
知的能力と理解の仕方は別物という「大切な気づき」
- 知的能力自体は正常範囲内であることが多い
- 情報の入力方法や処理過程に特性があるだけ
- お子さんに合った「理解のルート」を見つけることが大切
発達障害で理解力に課題がある子どもでも、知的能力自体は正常範囲内であることが多いです。つまり、理解できないのは「頭が悪い」からではなく、情報の入力方法や処理過程に特性があるだけです。
例えば、耳から入る情報は苦手でも、目で見る情報なら理解できる子どもがいます。また、一度に多くの情報を処理するのは苦手でも、一つずつ順番に説明すれば理解が大きく進む例もあります。
大切なのは、お子さんに合った「理解のルート」を見つけることです。
家庭で課題が目立ちやすいタイミングと「見逃しがちな成長」
- 小学校入学後や学年が上がるタイミングで特性が顕在化しやすい
- 抽象度が上がる学年(小2〜3年)で困りごとが目立ちやすい傾向
- 「5分長く集中できた」などの小さな変化が大きな成長への第一歩
発達障害の特性は、小学校入学後や学年が上がるタイミングで顕在化しやすくなります。特に抽象度が上がる学年(例:小2〜3年)で困りごとが目立ちやすい傾向があります。
学習内容が抽象的になり、複数の概念を同時に理解する必要が出てくるためです。しかし、親御さんが見逃しがちなのは、お子さんの小さな成長です。
「今日は5分長く集中できた」「視覚的な説明なら理解できた」といった小さな変化こそが、大きな成長への第一歩です。家庭教師のランナーでは、こうした小さな成長を見逃さず、しっかりと評価し、お子さんの自信につなげる指導を心がけています。
聞く力と理解する力の関係性から分かる「支援の手がかり」
- 聞く力には「音を認識する力」「注意を向ける力」「記憶する力」が含まれる
- 注意を向ける力が弱い場合は名前を呼んでから話すなどの工夫が有効
- つまずきポイントを特定することで効果的な支援方法が見えてくる
聞く力と理解する力は密接に関連しています。聞く力には「音を認識する力」「注意を向ける力」「記憶する力」が含まれ、これらのどこかにつまずきがあると、理解まで至りません。
例えば、注意を向ける力が弱い場合は、話し始める前に名前を呼んで注意を引く、アイコンタクトを取ってから話すといった工夫が有効です。記憶する力が弱い場合は、重要なポイントを紙に書きながら説明する、何度も繰り返し確認するといった支援が必要です。
お子さんの「つまずきポイント」を特定することで、効果的な支援方法が見えてきます。
今日から家庭で始められる「お子さんに合わせた」支援方法
発達障害で理解力に課題がある子どもへの支援は、特別な道具や専門知識がなくても、今日からすぐに始められます。
大切なのは、お子さんの特性を理解し、その子に合った方法を見つけることです。ここでは、多くの家庭で効果が実証されている具体的な支援方法をご紹介します。
指示が伝わりやすくなる声かけの工夫と「成功体験を増やす」対応例
- 要点を3ステップに分けて提示することが基本
- 完了したら必ず褒めて成功体験を積み重ねる
- やることをカード化、砂時計で時間の見える化など視覚的手がかりを併用
発達障害がある子どもへの指示は、要点を3ステップに分けて提示することが基本です。
例えば複数の指示を一度に伝えるのではなく、「宿題アプリで『次の1問』を提示→終えたら『OKサイン』を一緒に確認→次のステップへ」という流れで進めます。
完了したら必ず褒めて、次の指示に移ることで、お子さんは「できた」という成功体験を積み重ねられます。また、視覚的な手がかりを併用することも効果的です。
やることをカード化して、終わったら裏返す、砂時計を使って時間の経過を見える化するなど、お子さんが理解しやすい方法を探してみてください。
学習でつまずいた時の「一緒に乗り越える」サポート方法
- 叱責は負担になりやすいので短い休憩を挟んでから再開する
- 問題を小さく分解し、できる部分から始める
- 文章問題は一文ずつ読み、図や絵で視覚化する段階的アプローチが有効
宿題や勉強でつまずいたとき、叱責は負担になりやすいので、短い休憩を挟んでから再開する手順を用意することが大切です。
まず深呼吸をして、「どこが分からないか一緒に探そう」という姿勢で接します。
問題を小さく分解し、できる部分から始めることで、お子さんの自信を保ちながら学習を進められます。例えば、文章問題が苦手な場合は、まず問題文を一文ずつ読み、分からない言葉を説明し、図や絵を描いて視覚化するといった段階的なアプローチが有効です。
家庭教師のランナーの先生たちは、こうした段階的な指導法を身につけており、お子さんのペースに合わせて丁寧にサポートします。
日々の変化を記録するシートの活用で「小さな成長を見つける」コツ
- 「今日できたこと」「工夫したこと」「次に試したいこと」を記録
- 「学習前後の気分」「所要時間」「使用した支援ツール」も追加すると効果的
- 具体的な記録は学校の先生や専門機関への相談時にも貴重な資料となる
発達障害で理解力に課題がある子どもの成長は、日々の小さな変化の積み重ねです。記録シートを活用することで、親御さんもお子さん自身も成長を実感できます。
記録する内容は「今日できたこと」「工夫したこと」「次に試したいこと」に加え、「学習前後の気分」「所要時間」「使用した支援ツール」も追加すると効果的です。例えば「3コマ漫画形式の説明で算数の問題が解けた」「タイマーを使って15分集中が続いた」といった具体的な記録を残すことで、お子さんに合った学習方法が明確になります。
この記録は、学校の先生や専門機関への相談時にも貴重な資料となります。
発達障害のお子さんに寄り添う家庭教師サービス「選び方と特徴の比較」
発達障害で理解力に課題がある子どもにとって、一人ひとりに合わせた個別指導は非常に効果的です。
2025年現在、多くの家庭教師サービスが発達障害のお子さんへの支援に力を入れています。
ここでは、特におすすめのサービスを詳しくご紹介します。各サービスの特徴を理解し、お子さんに最適な選択をしていただければ幸いです。
家庭教師のランナーが選ばれる「きめ細かい対応と親身なサポート」の実績

- 創業20年以上の実績と発達障害コミュニケーション指導者が在籍
- カウンセリングから先生選定まで妥協なく、定期的なフォロー体制も充実
- 兄弟同時指導の割引制度あり
家庭教師のランナーは、創業20年以上の実績を持ち、「勉強が苦手な子専門」として発達障害のお子さんへの支援に特に力を入れています。
発達障害コミュニケーション指導者が在籍し、お子さんの特性を深く理解した上で、最適な先生をマッチングします。
カウンセリングから先生選定まで妥協なく行い、定期的に様子を伺う連絡をくださるなど、本部のサポート体制が充実しています。兄弟同時指導の割引制度もあり、経済的な面でも安心です。
高額な教材販売もなく、教科書など持参のテキストで学習を進めていけます。まずは無料体験レッスンでお子さまの「できた!」という達成感と、保護者様の安心感を同時に実感してください。
家庭教師のトライの「個別最適化されたカリキュラム」で進める学習支援

- 豊富な登録教師数から発達障害の理解がある先生を選定可能
- 専任教育プランナーによるオーダーメイドカリキュラム作成
- トライ式学習法で視覚的な説明や段階的な学習を重視
業界最大手の家庭教師のトライは、豊富な登録教師数から発達障害の理解がある先生を選定できます。
専任の教育プランナーが家庭と教師をつなぎ、お子さんの特性に合わせたオーダーメイドカリキュラムを作成します。
トライ式学習法という独自メソッドは、理解力に課題がある子どもにも効果的で、視覚的な説明や段階的な学習を重視しています。万が一相性が合わない場合の教師交代も可能です(契約プラン・地域により条件が異なる場合があります)。
学研の家庭教師が提供する「安心の実績と専門性」を活かした指導

- 教育大手の学研グループが運営、発達障害への理解と支援ノウハウが豊富
- 視覚的に理解しやすい教材の活用例や学習プログラムの提案が可能
- 大手企業ならではの研修体制で教師の質も高い
教育大手の学研グループが運営する家庭教師サービスは、発達障害への理解と支援ノウハウが豊富です。
多数の登録教師の中から、発達障害の知識を持つ教師を厳選して派遣します。
学研の教材開発力を活かし、視覚的に理解しやすい教材の活用例や、お子さんの特性に合わせた学習プログラムの提案が可能です。大手企業ならではの研修体制により、教師の質も高く、保護者への情報提供や進路相談などのサポート面でも定評があります。
家庭教師のサクシードで実現する「費用対効果の高い」マンツーマン指導

- 上場企業運営で13万人以上の教師が在籍
- 入会金無料(一部コース)、小学生補習コース1時間3,080円〜
- 講師指名に対応、1回の授業で複数科目指導も可能
上場企業が運営する家庭教師のサクシードは、13万人以上の教師が在籍し、発達障害に理解のある先生も多数います。
入会金無料(一部コース)、小学生補習コースの最安単価の一例として1時間3,080円からという良心的な料金設定があります(コース・地域により異なります)。
講師指名に対応(要相談)しており、体験授業でお子さんとの相性を確認できます。1回の授業で複数科目を指導できるため、集中力に課題があるお子さんでも、柔軟に対応してもらえます。
家庭教師ファーストの「体験から始められる」安心のスタート

- 実際に担当となる先生で無料体験が可能
- 60分×月4回で9,240円〜の料金設定
- 不登校支援コースもあり、営業スタッフではなく担当教師が体験指導
家庭教師ファーストは、実際に担当となる先生で無料体験ができるため、発達障害のお子さんでも安心して始められます。
60分×月4回で9,240円〜(補習コースの一例、地域・学年により変動)という料金設定で、質の高い指導を提供しています。
不登校支援コースもあり、発達障害で学校に行けないお子さんへの対応経験も豊富です。営業スタッフではなく担当教師自身が体験指導を行うため、お子さんの緊張も和らぎやすく、そのまま継続できる利点があります。
家庭教師のノーバスが関東・東海で培った「豊富な支援実績」

- 主に関東中心の地域密着型サポート
- 個別指導塾も運営、発達障害への指導ノウハウが蓄積
- 教師と学習プランナーのダブル体制で継続的サポート
主に関東を中心に展開する家庭教師のノーバスは、地域密着型の丁寧なサポートが特徴です。
個別指導塾も運営しているため、発達障害のお子さんへの指導ノウハウが蓄積されています。
教師採用基準が厳格で、発達障害への理解度も選考ポイントとなっているため、質の高い指導が期待できます。教師と学習プランナーのダブル体制により、お子さんの特性に合わせた学習計画を立て、継続的にサポートしてもらえます。
家庭教師のあすなろが専門とする「勉強が苦手な子への寄り添い」指導
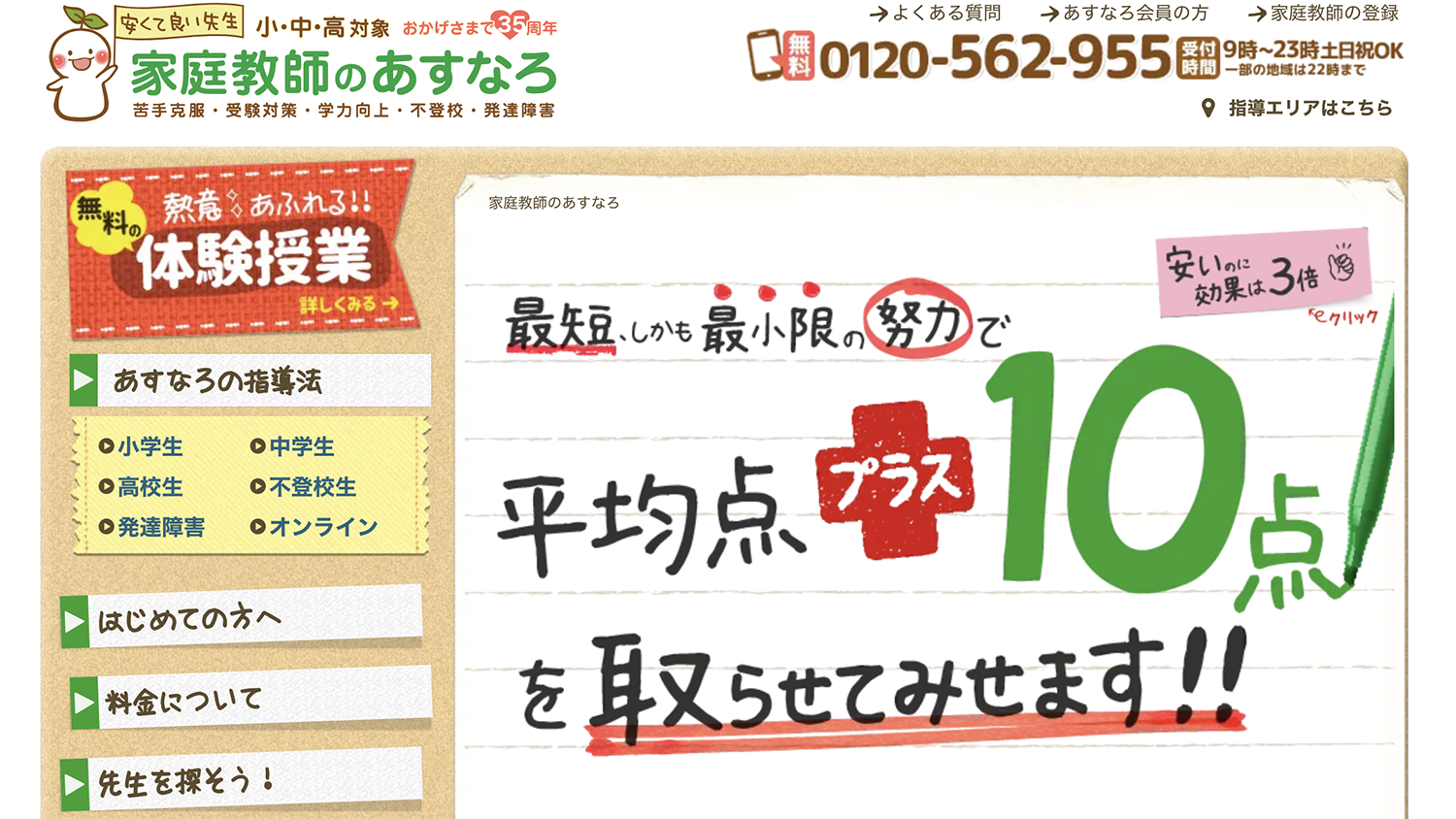
- 「勉強が苦手な子専門」を30年以上継続
- 大学生中心の若い先生による親しみやすい指導
- LINE質問対応サービス「お悩みお助け隊」で授業外でも質問可能
「勉強が苦手な子専門」を30年以上続けている家庭教師のあすなろは、発達障害で理解力に課題がある子どもへの支援経験が豊富です。
大学生中心の若い先生が多く、お兄さん・お姉さん的な存在として親しみやすい指導をしてくれます。
LINEを使った質問対応サービス「お悩みお助け隊」により、授業がない日でも質問できるため、理解が定着しやすいです。月16,000円程度からという料金設定で、家計への負担も少なく続けやすいサービスです。
家庭教師学参のプロ講師による「専門性の高い個別対応」

- 40年以上の実績、プロ講師による専門性の高い指導
- 講師指名制で無料体験後に正式契約可能
- 授業回数を柔軟に調整でき、疲れやすいお子さんでも無理なく継続
40年以上の実績を持つ家庭教師学参は、プロ講師による専門性の高い指導が特徴です。
発達障害の知識を持つ経験豊富な講師が多数在籍し、お子さんの特性を深く理解した上で指導します。
講師指名制により、無料体験で相性を確認してから正式契約できます。部活や習い事の都合に合わせて授業回数を柔軟に調整できるため、発達障害で疲れやすいお子さんでも無理なく続けられます。
オンライン家庭教師Wamで実現する「送迎不要の低価格」サポート

- オンライン専門で40分・週1回月4,900円〜の低価格
- 独自開発の専用システムで視覚的に理解しやすい授業
- 送迎不要で自宅で安心して学習可能
オンライン専門の家庭教師Wamは、40分・週1回(月4回)の小1〜3年コースの一例で月4,900円〜という料金設定で、質の高い個別指導を提供しています(時間・コース・学年により異なります)。
独自開発の専用システムにより、発達障害で理解力に課題がある子どもでも、画面上で視覚的に理解しやすい授業を受けられます。
東京大学など有名大学の学生講師が、お子さんの特性に合わせて丁寧に指導します。送迎の必要がなく、自宅で安心して学習できるため、環境の変化が苦手なお子さんにも最適です。
オンライン家庭教師トウコベの「東大生による丁寧な」オンライン指導
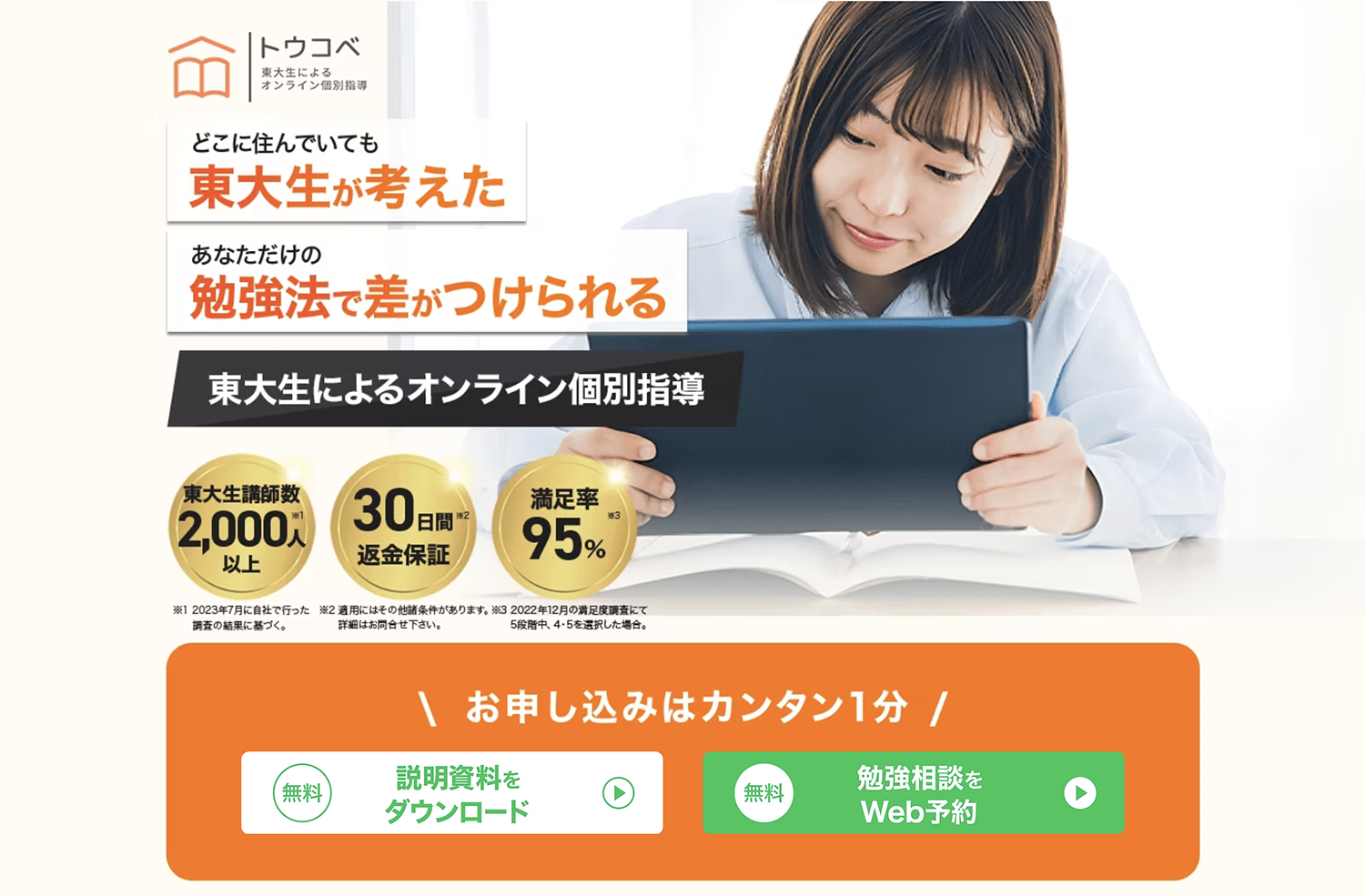
- 東大生講師による高い学力と指導力
- 30日間の全額返金保証あり(条件は要確認)
- 講師交代も自由で最適な先生が見つかるまでサポート
東大生講師によるオンライン指導のトウコベは、高い学力と指導力を兼ね備えた講師陣が魅力です。
発達障害のお子さんへの理解も深く、論理的で分かりやすい説明により、理解力に課題がある子どもでも着実に学力を伸ばせます。
30日間の全額返金保証があり(実施有無・適用条件は時期により変動のため要確認)、お子さんに合うか不安な場合でも安心して始められます。講師交代も自由なので、お子さんに最適な先生が見つかるまでサポートしてもらえます。
オンライン家庭教師マナリンクの「経験豊富なプロ講師」によるサポート
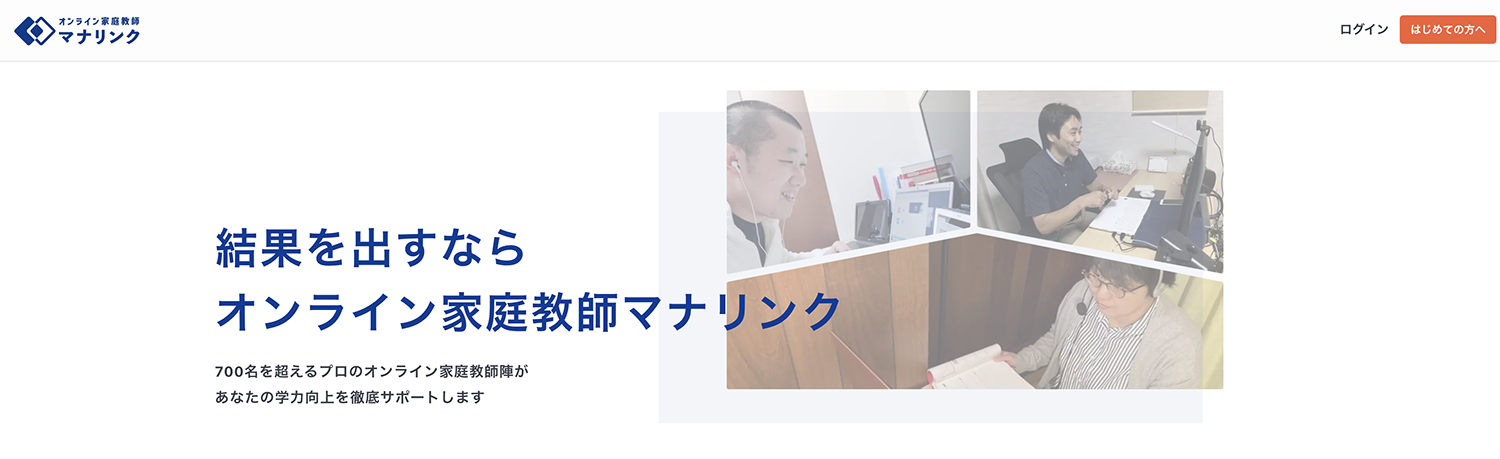
- 100%社会人講師で発達障害への専門知識を持つプロ講師が多数
- サイト上で講師プロフィールや動画を見て選べる
- 専用アプリで気軽に質問や相談が可能
100%社会人講師のマナリンクは、発達障害への専門知識を持つプロ講師が多数登録しています。
サイト上で講師のプロフィールや動画を見て、お子さんに合った先生を選べるため、ミスマッチが少ないです。
専用アプリで気軽に質問や相談ができ、集中が続きにくいお子さんでも、短時間の質問対応で理解を深められます。入会金が必要ですが、必要な時に必要な分だけ受講できる柔軟性があります。
学校との連携を進めて「一貫した支援を作る」実践的な方法
発達障害で理解力に課題がある子どもへの支援は、家庭だけでなく学校との連携が不可欠です。
家庭と学校で一貫した支援を行うことで、お子さんは安心して学習に取り組めるようになります。ここでは、学校との効果的な連携方法について、具体的にご説明します。
家庭と学校で支援を共有するための「効果的な伝え方」
- 診断名だけでなく具体的な困りごとと効果的だった支援方法をセットで伝える
- 家庭での成功事例を共有し、学校でも同じ方法を試してもらう
- 定期的に連絡帳や面談で情報交換を行い、成長を共有
学校の先生に発達障害の特性を伝える際は、「診断名」だけでなく「具体的な困りごと」と「効果的だった支援方法」をセットで伝えることが大切です。
例えば「口頭での長い説明より、要点を3つに整理して板書していただけると理解しやすいです」といった具体的なお願いをすることで、先生も対応しやすくなります。
また、家庭での成功事例を共有することで、学校でも同じ方法を試してもらえる可能性が高まります。定期的に連絡帳や面談を通じて情報交換を行い、お子さんの成長を共有することも重要です。
担任やコーディネーターへの連絡で使える「具体的な文例とコツ」
- 感情的にならず事実ベースで伝えることがポイント
- 具体的な困りごとと家庭での対応例を明確に伝える
- 特別支援教育コーディネーターとの積極的な連携を推奨
担任の先生への連絡では、感情的にならず事実ベースで伝えることがポイントです。
「いつもお世話になっております。○○(子どもの名前)の学習面でご相談があります。算数の文章問題で、問題文を一度に理解することが難しいようです。家では、問題を段階的に分解し、要点を図解すると理解できました。もし可能でしたら、授業でも要点の図解や段階的な説明を取り入れていただけると助かります」といった具体的な文例を参考にしてください。
特別支援教育コーディネーターがいる場合は、より専門的な相談ができるため、積極的に連携を取ることをおすすめします。
合理的配慮の申請手順と「準備しておくと良い」書類リスト
- 担任やコーディネーターに相談し、個別の教育支援計画を作成
- 医師の診断書、発達検査結果、家庭での支援記録、通知表を準備
- 座席配置、テスト時間延長、別室受験、ICT機器使用許可などの具体的配慮
合理的配慮は、発達障害のあるお子さんが他の子と同じように学習できるよう、学校に求められる配慮です(学校や自治体により運用が異なるため、手続きは学校のガイドラインに従ってください)。
申請には、まず担任やコーディネーターに相談し、個別の教育支援計画を作成してもらいます。
準備しておくと良い書類として、医師の診断書(ある場合)、発達検査の結果、家庭での支援記録、これまでの通知表などがあります。具体的な配慮内容としては、座席の配置(黒板の近く、窓際を避ける)、テストの時間延長、別室受験、ICT機器の使用許可などが挙げられます。
専門機関へ発達障害の相談を検討する時の「準備と心構え」
発達障害で理解力に課題がある子どもについて、専門機関への相談を考えている親御さんも多いでしょう。相談することは決して「弱さ」ではなく、お子さんのより良い成長のための大切な一歩です。
ここでは、相談先の選び方から準備まで、安心して相談できるようサポートします。
小児科や発達外来を選ぶ際の「安心できる基準」と予約のコツ
- 発達障害の診療経験が豊富で心理検査ができる体制があること
- 継続的なフォローが可能な医療機関を選ぶ
- 予約は数週間〜数か月待ちもあるため早めの連絡が大切
発達障害の相談先として、まず地域の小児科や発達外来があります。
選ぶ際の基準として、発達障害の診療経験が豊富であること、心理検査ができる体制があること、継続的なフォローが可能であることを確認してください。
予約は数週間〜数か月待ちの場合もあるため、早めに連絡することが大切です。初診時は時間をかけて話を聞いてくれる医療機関を選ぶことで、お子さんも親御さんも安心して相談できます。
発達障害の相談時に持参すると役立つ「記録と持ち物」
- 母子手帳、成長記録、連絡帳、通知表、お子さんの作品を持参
- 困りごと発生の前・最中・後の行動記録が特に重要
- お子さんが落ち着けるお気に入りのおもちゃや本も忘れずに
専門機関への相談時は、お子さんの様子を正確に伝えるための準備が大切です。
持参すると良いものとして、母子手帳、成長記録、園や学校からの連絡帳、通知表、お子さんの作品(絵や文字)があります。
特に重要なのは「困りごと発生の前・最中・後の行動記録」です。「いつ、どこで、どんな状況で、どのような困りごとがあったか」そして「その前後でどんな変化があったか」を具体的に記録したメモは、医師の診断に役立ちます。
また、お子さんが落ち着けるお気に入りのおもちゃや本を持参することも忘れずに。
保護者の不安に寄り添いながら「二次障害を防ぐ」ための視点
- 周囲の理解不足による二次障害(不安症、うつ、不登校など)のリスク
- お子さんの特性を理解し、適切な支援を早期に始めることが重要
- 保護者も一人で抱え込まず、支援団体や同じ悩みを持つ保護者と交流
発達障害で理解力に課題がある子どもは、周囲の理解不足により自信を失い、二次障害(不安症、うつ、不登校など)を起こすリスクがあります。
これを防ぐためには、お子さんの特性を理解し、適切な支援を早期に始めることが重要です。親御さん自身も一人で抱え込まず、専門機関や支援団体、同じ悩みを持つ保護者との交流を通じて、心の支えを得ることが大切です。
家庭教師のランナーでは、保護者の方の相談にも親身に対応し、お子さんと家族全体をサポートする体制を整えています。
お子さんの成長を見守る「長期的なサポート計画」の立て方
発達障害で理解力に課題がある子どもの成長は、短期間で劇的に変わるものではありません。長期的な視点でサポート計画を立て、小さな成功を積み重ねることで、お子さんは着実に成長していきます。
ここでは、継続的な支援のポイントをお伝えします。
現状把握から環境調整までの「ステップごとの進め方」
- 得意なこと、苦手なこと、興味関心を整理し優先順位をつける
- 学習環境の整備と生活リズムの安定化を図る
- 学期ごとに振り返りを行い、計画を柔軟に修正
長期的なサポート計画は、まず現状把握から始まります。お子さんの得意なこと、苦手なこと、興味関心を整理し、優先順位をつけて取り組む課題を決めます。
次に環境調整として、学習環境の整備(静かな場所の確保、視覚的な支援ツールの準備)、生活リズムの安定化を図ります。学期ごと、または8〜12週ごとに振り返りを行い、成長した点と新たな課題を確認しながら、計画を柔軟に修正していくことが大切です。
成果指標として、課題着手までの時間短縮や復唱での正答率向上などを設定すると効果的です。
自己肯定感を育むために大切な「日々の関わり方」
- 「できた」ことを認め、具体的に褒める
- 小さな成長を見逃さず自信を持てるようにする
- 得意なことで成功体験を積み、苦手なことへの挑戦意欲を育てる
発達障害で理解力に課題がある子どもにとって、自己肯定感を育むことは何より重要です。「できない」ことに注目するのではなく、「できた」ことを認め、褒めることから始めてください。
例えば「今日は5分も集中できたね」「昨日より1問多く解けたね」といった小さな成長を見逃さず、具体的に褒めることで、お子さんは自信を持てるようになります。また、お子さんの興味や強みを活かす機会を作ることも大切です。
得意なことで成功体験を積むことで、苦手なことにも挑戦する勇気が生まれます。
聞く力に課題があるお子さんへの「効果的な対応策」
聞く力に課題があるお子さんは、実は「聞きたくても聞けない」状態であることが多いです。聞く力に課題があるお子さんへの対応は、環境整備と伝え方の工夫で大きく改善できます。
ここでは、実践的な対応策をご紹介します。
聞けていないように見える背景を理解して「改善につなげる」工夫
- 聴覚処理、注意持続、ワーキングメモリ、感覚過敏などが複合的に影響
- どのような状況で聞けなくなるのかパターンを観察
- 特徴を把握することで効果的な対応策が見えてくる
お子さんが聞けていないように見える背景には、様々な要因があります。聴覚処理の困難、注意の持続困難、ワーキングメモリの課題、感覚過敏などが複合的に影響しています。
まず、お子さんがどのような状況で聞けなくなるのかを観察し、パターンを見つけることから始めてください。
例えば、騒がしい環境では聞けないが静かな場所なら聞ける、長い説明は難しいが短い指示なら理解できるといった特徴を把握することで、効果的な対応策が見えてきます。
聞きやすい環境づくりと「視覚的なサポート」の実践方法
- 扇風機や時計の音、過度な掲示物など刺激を減らす
- 話す前に名前を呼んで注意を引き、ゆっくりはっきり話す
- 3コマ漫画形式、ピクトグラム、付箋キーワードなどで視覚化
聞きやすい環境づくりは、物理的な環境と伝え方の両面から行います。
物理的には、扇風機や時計のカチカチ音、過度な掲示物など、余計な音や視覚刺激を減らし、お子さんが集中しやすい環境を整えます。
伝え方では、話す前に名前を呼んで注意を引く、アイコンタクトを取る、ゆっくりはっきり話す、重要なポイントは繰り返すといった工夫が有効です。
視覚的サポートとして、要点を3コマ漫画形式で示す、ピクトグラムを活用する、付箋にキーワードを書いて貼るなどの方法を併用することで、理解度が格段に向上します。
お子さんの特性に合わせた「伝わりやすいコミュニケーション」のポイント
- 視覚優位、聴覚優位、体感覚優位などお子さんの得意な感覚を活かす
- 質問は選択式にし、答えやすい形で聞く
- 待つ時間を十分に取り、お子さんのペースに合わせる
発達障害で理解力に課題がある子どもとのコミュニケーションは、その子の特性に合わせることが成功の鍵です。
例えば、視覚優位の子には絵や写真を使う、聴覚優位の子にはリズムや歌を使う、体感覚優位の子には実際に体を動かしながら説明するなど、お子さんの得意な感覚を活かしてください。
また、質問は選択式にする、答えやすい形で聞く、待つ時間を十分に取るなど、お子さんが答えやすい工夫も大切です。家庭教師のランナーの先生たちは、こうした個別のコミュニケーション方法を習得しており、お子さんに最適な方法で指導します。
発達障害で理解力に課題がある子どもについて「大切なポイント」のまとめ
- ・「理解力がない」のではなく「理解の仕方が違う」ことを理解する
- ・視覚的支援、要点整理、成功体験の積み重ねで理解は着実に進む
- ・家庭・学校・専門機関が連携し、長期的視点でサポートすることが重要
発達障害で理解力に課題がある子どもへの支援は、決して難しいものではありません。大切なのは、お子さんの特性を理解し、その子に合った方法を見つけることです。
「理解力がない」のではなく「理解の仕方が違う」ということを忘れずに、お子さんの可能性を信じて支援を続けてください。
今回ご紹介した支援方法は、すべて今日から実践できるものばかりです。視覚的な支援、要点を整理した指示、成功体験の積み重ね、これらを継続することで、お子さんの理解は着実に進みます。
また、聞く力に課題があるお子さんについても、環境整備と伝え方の工夫で改善が期待できることを覚えておいてください。
学校との連携も欠かせません。担任の先生やコーディネーターと協力し、家庭と学校で一貫した支援を行うことで、お子さんは安心して学習に取り組めるようになります。必要に応じて専門機関への相談も検討し、お子さんに最適な支援体制を整えていきましょう。
そして、個別指導の重要性も忘れてはいけません。家庭教師のランナーをはじめとする各サービスは、発達障害のお子さんへの理解と支援経験が豊富です。
特にランナーは、発達障害コミュニケーション指導者が在籍し、お子さんの特性を深く理解した上で、最適な先生をマッチングしてくれます。各社それぞれの特徴を比較し、お子さんに合ったサービスを選ぶことが大切です。
最後に、親御さん自身の心のケアも大切にしてください。
一人で抱え込まず、支援者や同じ悩みを持つ保護者との交流を通じて、心の支えを得てください。お子さんの小さな成長を喜び、長期的な視点で見守ることで、道は必ず開けます。
発達障害は「個性」であり、適切な支援があれば、お子さんは自分らしく成長できる未来が待っています。なお、本記事は情報提供を目的としており、医療的な診断や治療に代わるものではありません。