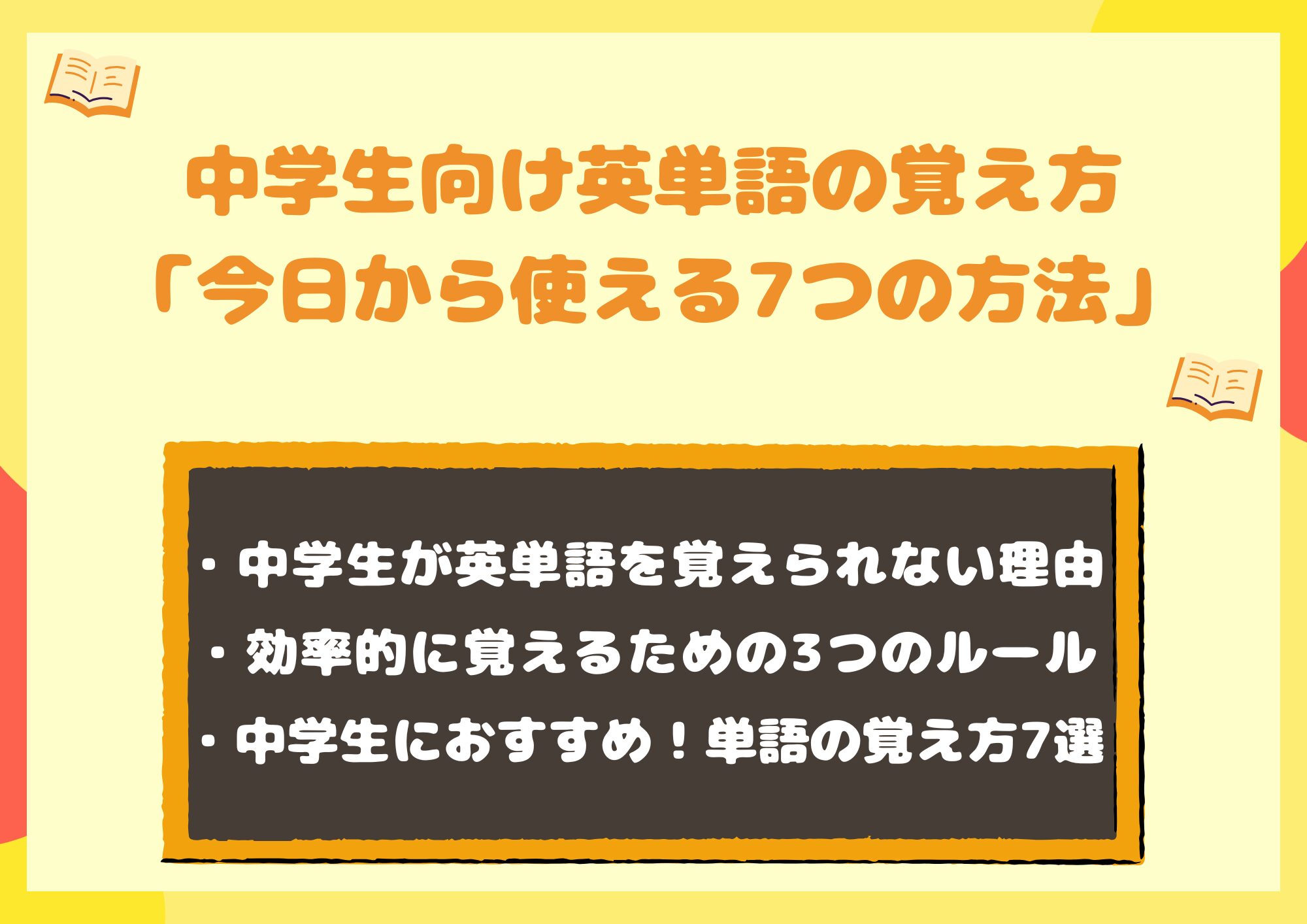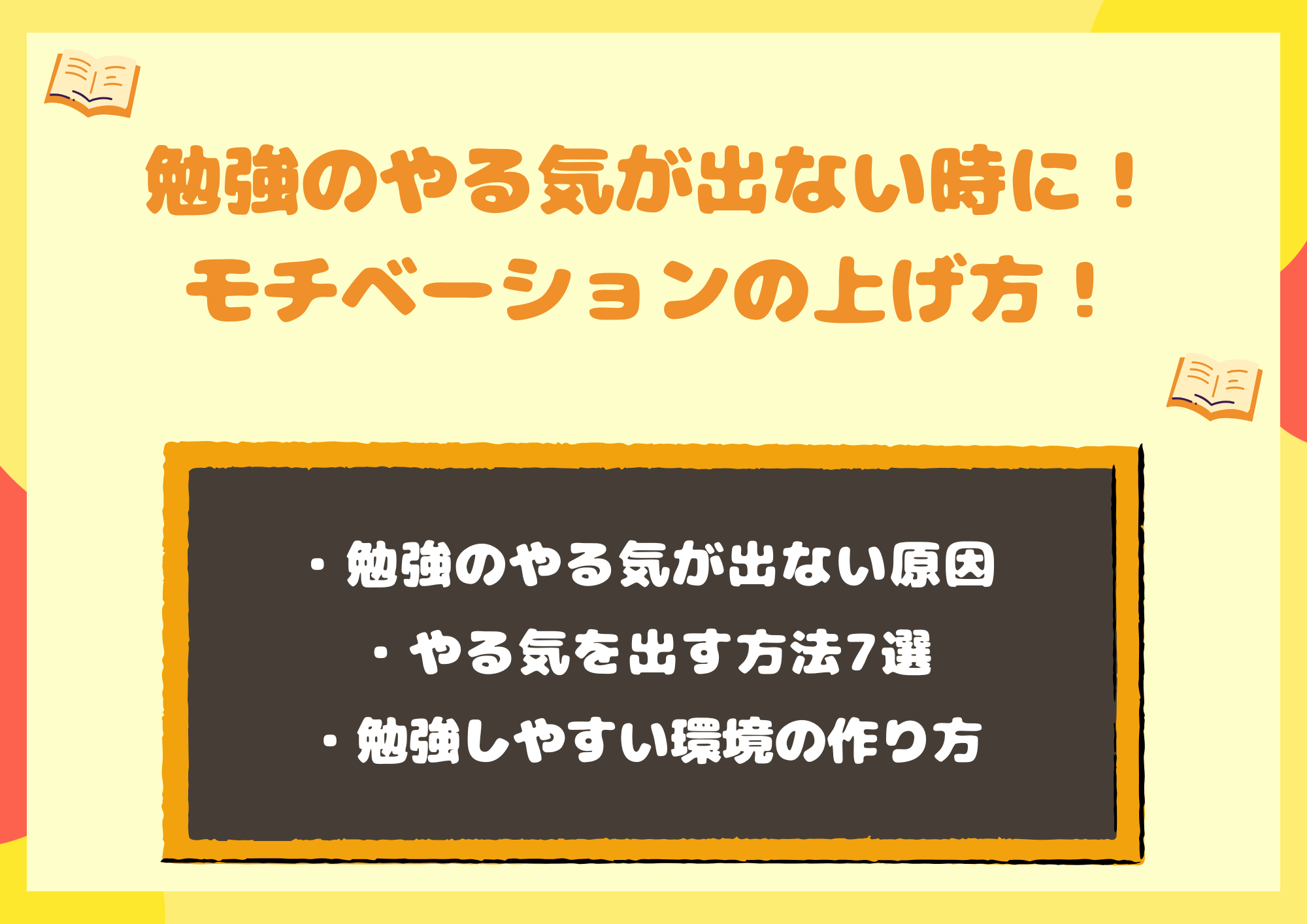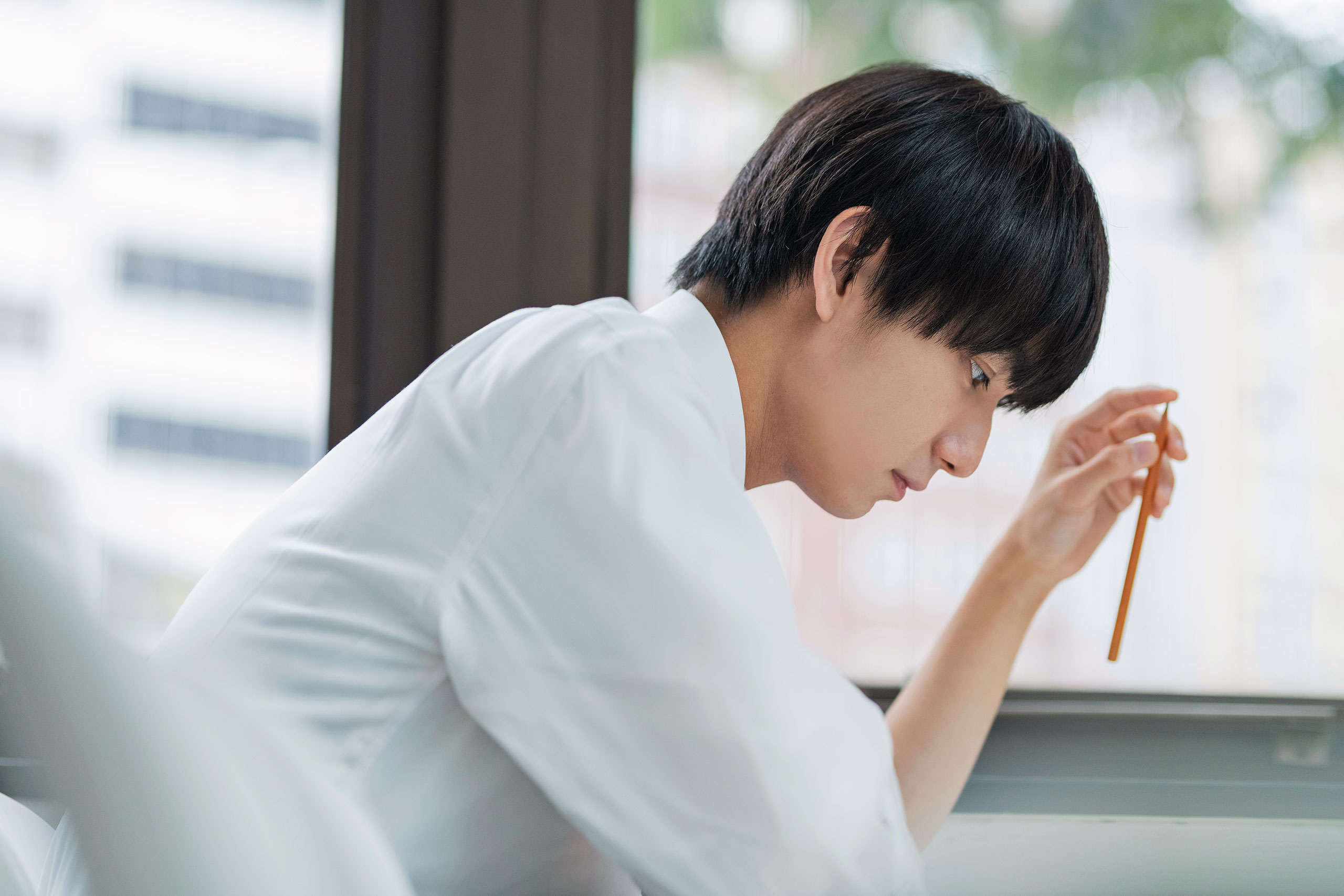- 勉強法
実力テストとは?3万人指導のプロが教える中3向け勉強法と対策
2025.10.28
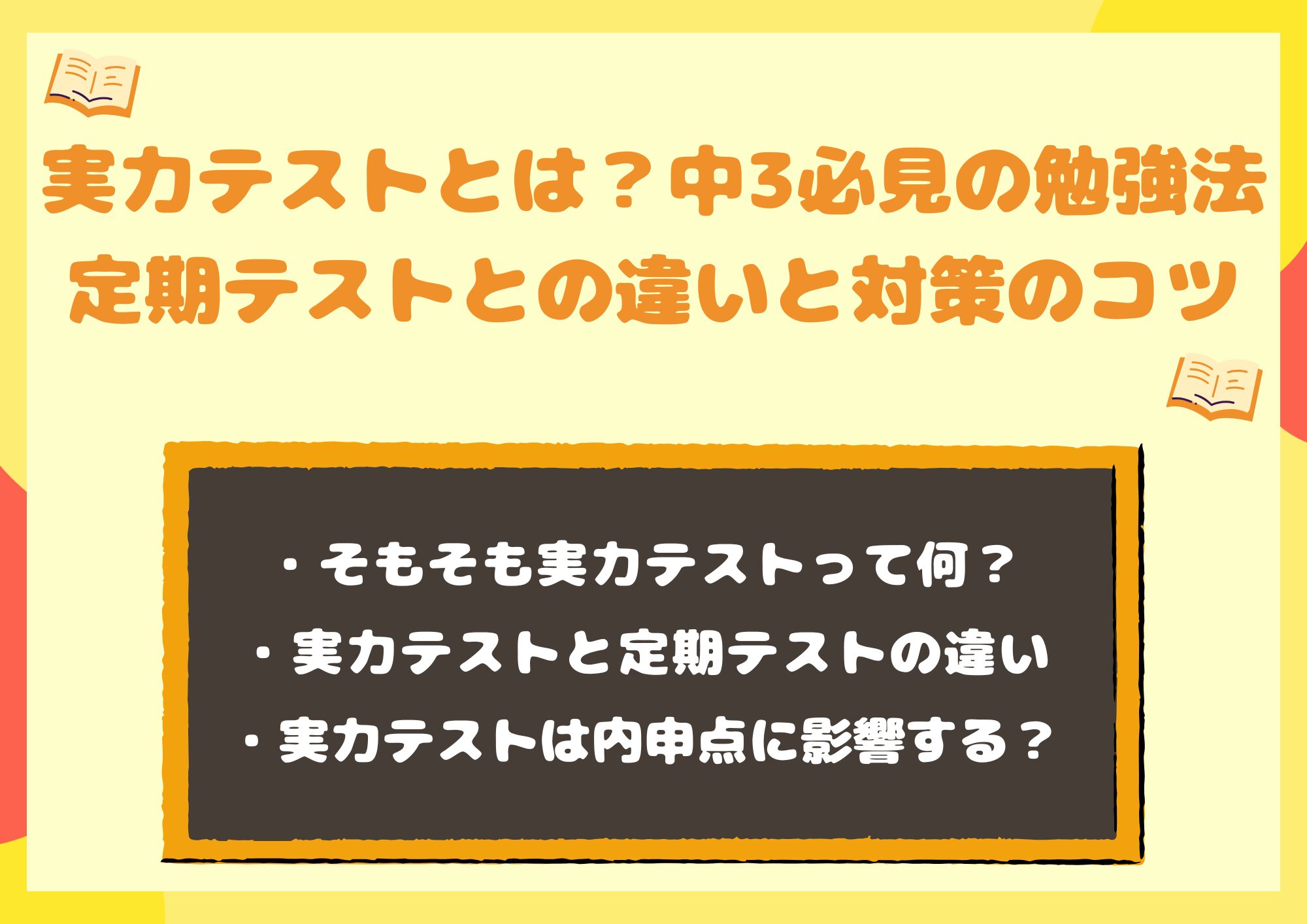
実力テストが近づくと、「範囲が広すぎて何から手をつけていいか分からない」と悩むお子さんは多いですよね。
私たちランナーは30,034人のお子さんを指導してきましたが、勉強が苦手な子でも正しいやり方を知れば、実力テストの点数は必ず伸びます。この記事では、実力テストの基本から効果的な勉強法まで徹底解説します。
志望校合格への第一歩を、一緒に踏み出しましょう。
目次
そもそも実力テストって何?中学生が知っておくべき基本
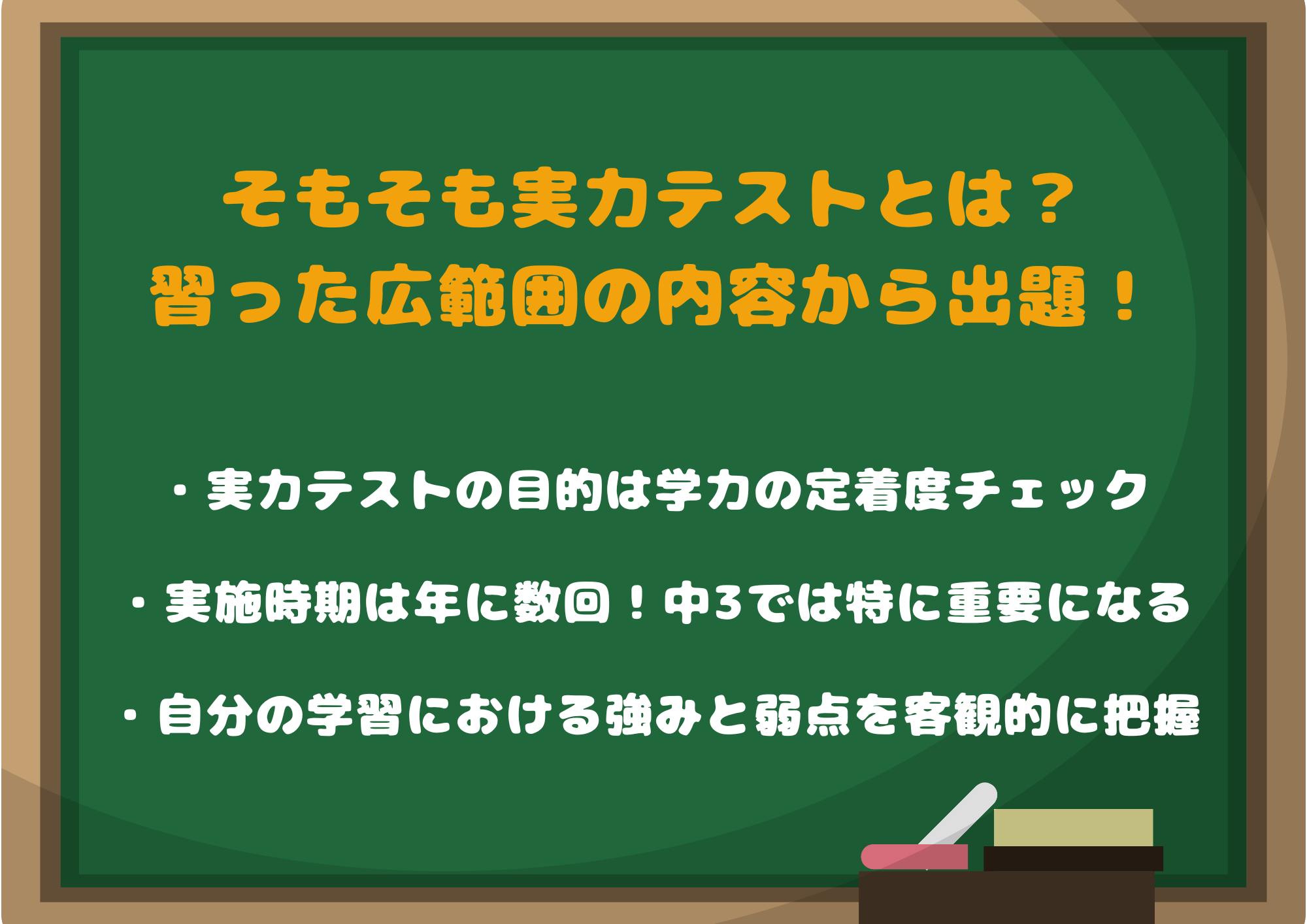
- 実力テストは中学で習った全範囲から出題される累積型の試験
- 定期テストと異なり応用問題の比率が高く思考力が求められる
- 中3の秋から冬の実力テストは志望校決定に大きく影響する
実力テストとは、これまでに学習した内容全体の定着度を測るための試験です。
定期テストとは異なり、中学生活で習った広範囲の内容から出題されるのが特徴なんです。
実力テストの目的は学力の定着度チェック
- 累積的な学力を診断し強みと弱点を可視化する
- 具体的な課題を明らかにして効果的な復習計画につなげる
実力テストの本来の目的は、生徒一人ひとりの累積的な学力を診断することにあります。
たとえば英語の現在完了形は理解できているけれど進行形が曖昧、といった具体的な課題を可視化できるんです。つまり実力テストは、自分の学習における強みと弱点を客観的に把握するための重要なツールなんですね。
この診断結果をもとに効果的な復習計画を立てることで、着実に学力を伸ばしていくことができます。
実施時期は年に数回|中3では特に重要になる
- 年に数回、学期ごとまたは定期的に実施される
- 中3の11月・12月のテストは三者面談での志望校決定に直結する
実力テストは多くの中学校で年に数回実施されています。
実施の頻度や時期は学校によって異なりますが、一般的には学期ごと、あるいは定期的に行われるケースが多いです。特に中学3年生になると、実力テストの重要性が格段に高まります。
中3の秋から冬にかけて実施される実力テストの結果は、三者面談での志望校決定に大きな影響を与えるからです。そのため中3の実力テストは、単なる学力チェックではなく、受験戦略を左右する極めて重要な試験と言えるでしょう。
実力テストと定期テストの違いを徹底比較
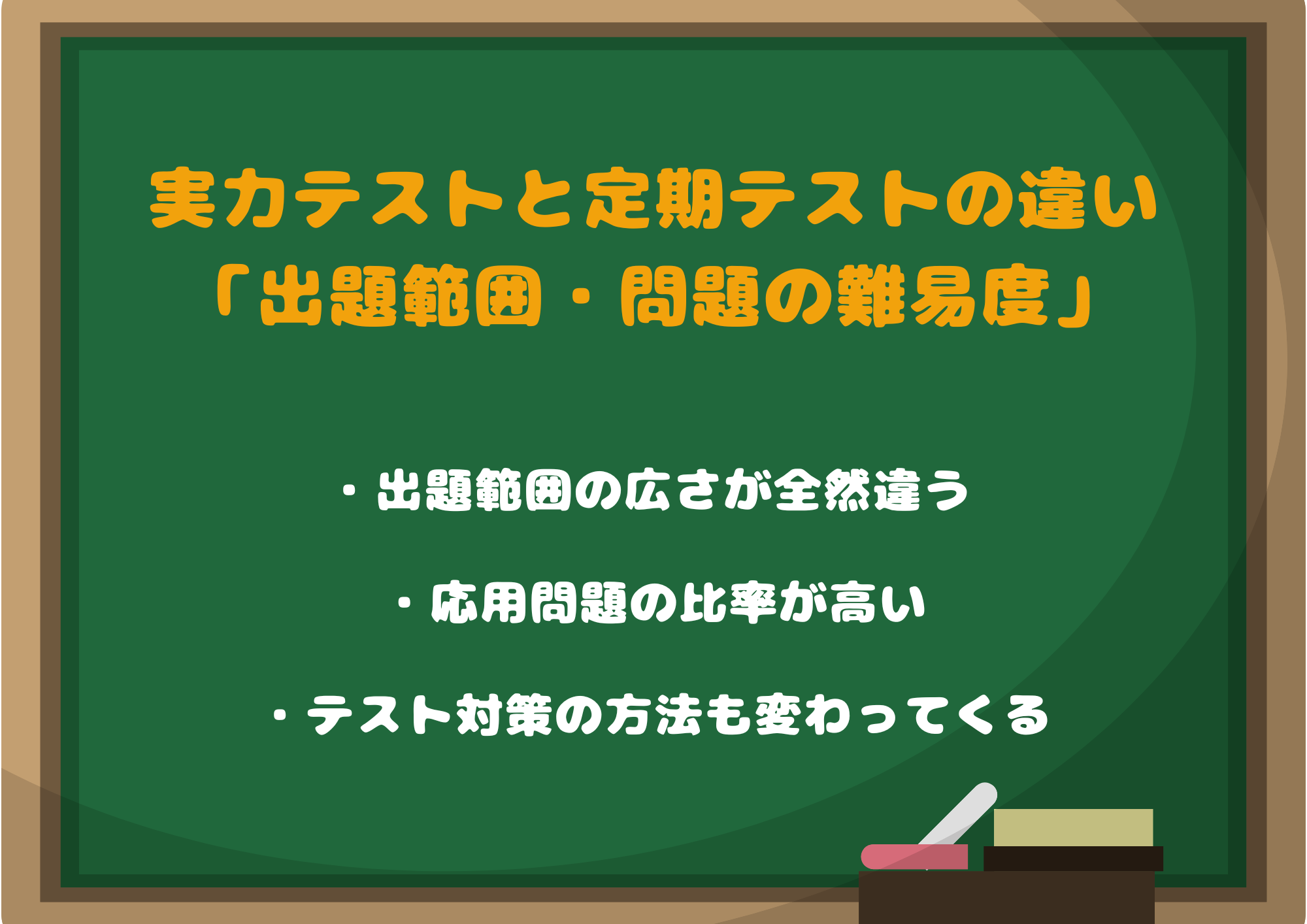
- 出題範囲:実力テストは全学習範囲、定期テストは限定的な範囲
- 問題形式:実力テストは応用問題が多く、定期テストは基本問題中心
- 対策方法:実力テストは長期的な復習、定期テストは短期集中の暗記
実力テストと定期テストは、同じ「テスト」という名前がついていても、その性質は大きく異なります。
この違いを理解することが、効果的な対策への第一歩になるんです。
出題範囲の広さが全然違う
- 定期テストは直近1ヶ月程度の限定範囲から出題
- 実力テストは中学入学後から現在までの全範囲が対象
最も大きな違いは、出題範囲の広さです。
定期テストは直近の数週間から1ヶ月程度で学習した限定的な範囲から出題されます。一方、実力テストは中学入学後から現在までに学習した全範囲が対象となる累積型の試験なんです。
中3の秋に実施される実力テストでは、約2年半分の学習内容すべてが出題範囲になります。この範囲の広さが、実力テストを難しく感じさせる最大の要因と言えるでしょう。
問題の難易度|応用問題が多い実力テスト
- 定期テストは基本的な知識問題が中心
- 実力テストは応用問題の比率が高く思考力を試す問題が多い
問題の難易度と形式にも明確な違いがあります。
定期テストは授業で扱った内容の理解度を確認することが主な目的なので、基本的な知識問題が中心です。一方で実力テストは、単なる知識の暗記だけでは対応できない応用問題の比率が高いんです。
複数の単元の知識を組み合わせて解く問題や、思考力・判断力を試す初見の問題も多く出題されます。このような問題構成は高校入試本番の出題傾向と非常に似ているため、実力テストは入試のシミュレーションとしても機能するんですね。
テスト対策の方法も変わってくる
- 定期テストは短期集中的な暗記や反復演習が効果的
- 実力テストは長期的かつ体系的な学習が必要
出題範囲と難易度が異なるため、テスト対策の方法も大きく変わってきます。
定期テストでは短期集中的な暗記や反復演習が効果的ですが、実力テストではこのような付け焼き刃的な勉強法は通用しません。必要なのは、長期的かつ体系的な学習です。
中1や中2の内容から基礎を固め直し、単元ごとのつながりを理解しながら知識を積み上げていく必要があります。つまり実力テストで高得点を取るには、日頃からコツコツと基礎を固め、定期的に復習する習慣が何より大切だということですね。
実力テストは内申点に影響する?志望校との関係
- 内申点への直接的な影響はほとんどない
- 志望校選びでは教員が進路指導の重要判断材料として活用する
実力テストと内申点の関係については、多くの生徒や保護者の方が気にするポイントです。
ここでは、その実態を正確に理解しましょう。
直接的な影響はほとんどない
- 実力テストの点数は内申点に直接反映されない
- 内申点は授業態度や提出物、定期テストで評価される
結論から言うと、ほとんどの中学校では実力テストの点数が内申点に直接反映されることはありません。
内申点は授業態度や提出物、定期テストの成績といった学校内の活動に基づいて評価されます。ですから、実力テストで思うような点数が取れなかったとしても、通知表の成績が直接下がるわけではありません。
この点は多くの方が誤解しやすいポイントなので、しっかり理解しておきましょう。
でも志望校選びには超重要な判断材料
- 教員は進路指導で実力テストの結果を最重要データとして活用
- 志望校の妥当性判断や合格可能性の予測に直結する
直接的な影響はなくても、間接的な影響は極めて大きいんです。
教員は進路指導を行う際、実力テストの結果を最重要データの一つとして活用します。実力テストは「入試本番でどれくらいの点数が取れそうか」を予測する最も信頼性の高い指標なんです。
特に中3の11月から12月に実施される実力テストは、三者面談での最終的な志望校決定に決定的な影響を与えます。つまり実力テストは、内申点には影響しないものの、志望校選択という受験の核心部分で重要な役割を果たしているんですね。
中3で実力テストが「やばい」と感じたら?
- 冷静に現状を分析し具体的な課題を明確にする
- 保護者は否定的な言動を避け支援的な声かけを心がける
実力テストで思うような結果が出ず、「やばい」と感じる瞬間は誰にでもあります。
そんなとき、どう対処すればいいのでしょうか。
まずは冷静に現状を把握しよう
- 感情的にならず客観的に結果を分析する
- どの科目や単元が弱いのか具体的な課題を特定する
点数が低かったとき、最初に感じるのは焦りや不安です。
しかしここで感情的になるのではなく、まずは冷静に現状を分析することが大切なんです。実力テストの結果は、お子さんの学力における「今の位置」を教えてくれる貴重な情報です。
どの科目が特に弱いのか、どの単元でつまずいているのか。こうした具体的な課題を明確にすることが、改善への第一歩になります。「やばい」と感じたときこそ、感情に流されず客観的に立ち位置を確認し、今からできる具体的な対策を考えましょう。
保護者はどう声をかければいい?
- 否定的な言葉や過度なプレッシャーは避ける
- 努力を認め気持ちに共感し前向きな声かけをする
保護者の方にとっても、お子さんの成績が振るわなかったときの対応は悩ましいものですよね。
ここで最も避けたいのは、否定的な言葉や過度なプレッシャーをかけることです。私たちランナーには発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフが在籍していますが、その視点からお伝えすると、「なぜ勉強しなかったの?」といった非難や他の子との比較は、お子さんの自尊心を傷つけ、学習意欲を低下させてしまいます。
まずはお子さんの努力を認める言葉から始めましょう。「よく頑張ったね」と努力を労い、「悔しいよね」と気持ちに共感することで、お子さんは心を開きやすくなります。
その上で「これで苦手なところがはっきりしたね」と前向きに捉え直す声かけをすることが効果的です。お子さんへの声かけに悩んでいる方は、「中学生のやる気を出させる方法」の記事も参考にしてみてくださいね。
実力テストの効果的な勉強法|今からでも間に合う!
- 過去の定期テストを解き直して知識の抜け漏れを特定
- 苦手な単元を集中的に復習して弱点を克服
- 長期的な学習計画を立てて着実に学力を積み上げる
実力テストで点数を上げるには、戦略的なアプローチが必要です。
ここでは、効果が実証されている具体的な勉強法を紹介します。勉強が苦手なお子さんでも、正しいやり方で取り組めば必ず成果は出ます。
「中学生の勉強法」の記事もあわせて参考にしてみてください。
過去の定期テストを解き直そう
- 中1・中2の定期テストは重要事項が凝縮された良質な問題集
- 3段階の反復学習で知識の抜け漏れを効率的に解消
実力テスト対策として最も推奨される方法が、過去の定期テストを徹底的に解き直すことです。
特に中1・中2の定期テストは、基礎的な重要事項が凝縮された良質な問題集と言えます。具体的な方法としては、3段階の反復学習が効果的です。
1周目ですべての問題を解いて間違えた箇所に印をつけ、2周目では印をつけた問題のみを解き直します。そして3周目で、完全に理解できるまで苦手な問題を潰していくんです。この体系的なアプローチにより、平均点を30点以上アップさせたケースも珍しくありません。
苦手な単元を集中的に復習
- 最も点数の低い苦手科目に絞って集中的に取り組む
- 基礎を固めた後に応用問題にも挑戦する
実力テストの結果から自分の弱点が明確になったら、そこを集中的に復習することが重要です。
全教科を満遍なく勉強するよりも、最も点数の低い苦手科目や苦手単元に絞って取り組む方が、短期間で成果が出やすいんです。たとえば数学の一次関数でつまずいているなら、その単元の基本問題を教科書や問題集で徹底的に解きます。
基礎が固まったら応用問題にも挑戦してみましょう。苦手を克服することは全体の底上げにつながります。
長期的な学習計画を立てることが大事
- 数週間から数ヶ月単位の長期的な計画を立てる
- 月1回程度の模試で進捗を確認し計画を柔軟に見直す
実力テストで成果を出すには、計画的な学習が不可欠です。
テスト直前に慌てて詰め込むのではなく、数週間から数ヶ月単位の長期的な視点で計画を立てましょう。たとえばテスト前の4週間を「分析と基礎固め」「弱点強化」「実践演習」「総仕上げ」といったフェーズに分けるのが効果的です。
こうした体系的な計画立案と実行管理は、モチベーションの維持にもつながります。高校受験に向けた学習時間の目安については、「高校受験の勉強時間」の記事も参考にしてみてくださいね。
実力テストに出やすい問題とは?教科別の対策
- 英語:長文読解、重要文法事項、リスニング、英作文
- 数学:計算問題、関数と図形の融合問題、文章題
- 国語:読解力、漢字・語彙、古文・漢文、作文
- 理科・社会:基礎知識、実験考察、グラフ・表の読み取り
実力テストには、教科ごとに出題されやすい典型的な問題パターンがあります。
ここでは教科別に、重点的に対策すべき内容を解説します。
英語で出やすいのはこんな問題
- 長文読解問題が大きな配点を占める
- 現在完了形、不定詞、関係代名詞などの重要文法事項が頻出
英語の実力テストでは、長文読解問題が大きな配点を占めます。
物語文や説明文、会話文など様々な形式の長文が出題され、内容把握や要旨を問う問題が中心です。また文法問題では現在完了形や不定詞、関係代名詞といった重要文法事項が繰り返し出題されます。
対策としては、教科書の本文を繰り返し音読し、重要構文を暗記することが効果的です。
数学は計算問題と応用問題がカギ
- 基本計算問題は確実に得点すべき
- 関数と図形の融合問題は難易度が高く差がつきやすい
数学の実力テストは、大きく計算問題と応用問題に分かれます。
計算問題では、正負の数や文字式、方程式、連立方程式、平方根といった基本計算が必ず出題されます。これらは確実に得点すべき問題なので、ミスなく素早く解けるまで反復練習しましょう。
応用問題では、関数のグラフを読み取る問題や図形の証明問題が頻出です。特に関数と図形の融合問題は難易度が高く、差がつきやすいポイントです。
国語は読解力が試される
- 論説文、小説、随筆文など多様な文章の読解力が求められる
- 漢字の読み書きや語彙問題も確実に得点すべき
国語の実力テストでは、読解力が最も重視されます。
論説文や小説、随筆文など多様なジャンルの文章が出題され、内容理解や表現技法、筆者の意図を問う問題が中心となります。文章全体の構成を把握し、段落ごとの要点を整理しながら読み進める力が求められるんです。
また漢字の読み書きや語彙問題も確実に得点すべきポイントです。
理科・社会は基礎知識の定着度チェック
- 理科:全分野から幅広く出題、実験考察やグラフ読み取り問題も頻出
- 社会:地理・歴史・公民から総合的に出題、用語の背景理解が重要
理科の実力テストでは、生物・化学・物理・地学の全分野から幅広く出題されます。
用語や法則を問う知識問題に加えて、実験結果を考察する問題やグラフ・表を読み取る問題も頻出です。社会では、地理・歴史・公民の各分野から総合的に出題されます。
用語を単に暗記するだけでなく、背景や関連性を理解しておくことが高得点への鍵です。理科・社会ともに、教科書の図表や資料を活用して視覚的に整理することが効果的な対策となります。
実力テストで点数が上がらない原因と解決策
- 基礎力が足りていない
- 勉強時間が絶対的に不足している
- 勉強のやり方が間違っている
私たちランナーは30,034人のお子さんを指導してきましたが、実力テストで伸び悩む子には共通点があります。
努力しているのに点数が伸びない場合、その原因を正確に特定することが改善への近道です。
基礎力が足りてないかも
- 土台が不安定なまま応用問題に取り組んでも解けない
- 教科書の基本問題や過去の定期テストで確認する
点数が上がらない最も一般的な原因は、基礎力の不足です。
応用問題を解こうとしても、土台となる基礎知識が不安定だと正解にたどり着けません。たとえば数学で連立方程式の応用問題が解けないのは、そもそも一次方程式の計算力が不十分だからかもしれません。
基礎力不足を見極めるには、教科書の基本問題や過去の定期テストを解き直してみることです。焦らず一歩ずつ、土台を固めることから始めましょう。
勉強時間は確保できてる?
- 実力テストは定期テストより多くの学習時間が必要
- 具体的な目標時間を設定し実際に確保できているか記録する
単純に、勉強時間そのものが不足している可能性もあります。
実力テストは広範囲から出題されるため、定期テストよりも多くの学習時間が必要です。部活や習い事で忙しくても、朝の時間や通学時間、休日を活用して学習時間を確保する工夫が求められます。
たとえば平日は最低2時間、休日は5時間といった具体的な目標時間を設定してみましょう。
勉強のやり方が間違っている可能性
- 「分かったつもり」で演習を怠っていないか
- 間違えた問題を放置せず原因を分析する
勉強時間は確保しているのに成果が出ない場合、勉強の方法そのものに問題があるかもしれません。
よくあるのが、「分かったつもり」で演習を怠るケースです。教科書を読んだり解説を聞いたりするだけで満足し、実際に自分の手で問題を解く練習が不足していると、テストでは解けません。
また間違えた問題をそのまま放置し、原因を分析しないのも非効率です。もし独学で限界を感じたら、先生や塾の力を借りて勉強法を見直すことも検討しましょう。
成績が伸び悩んでいる方は、「成績が上がらない中学生の原因と対策」の記事も参考にしてみてください。私たちランナーでは、お子さん一人ひとりに合った勉強のやり方から丁寧に指導しています。「中学生コース」の詳細もぜひご覧ください。
中3向け|実力テスト過去問の効果的な活用法
- 過去問で出題形式や難易度を体感できる
- 学校の先生や書店、インターネットで入手可能
- 本番と同じ時間制限で解き間違いを徹底分析する
過去問は、実力テスト対策において最も効果的なツールの一つです。
ここでは、過去問を最大限に活用する方法を解説します。受験勉強の進め方に悩んでいる方は、「中学生の受験勉強は何から始める?」の記事もあわせてご覧ください。
過去問を解くメリットって?
- 実際の出題形式や難易度を体感できる
- 間違いの分析を通じて知識の穴を埋められる
過去問を解く最大のメリットは、実際の出題形式や難易度を体感できることです。
どんな問題が出やすいのか、時間配分はどうすべきか、自分がどの分野で苦戦するのかといった貴重な情報が得られます。また本番と同じ形式で練習することで、テストへの不安が軽減され、本番でも落ち着いて実力を発揮できるようになるんです。
過去問は、自分の弱点を映し出す鏡であり、改善への具体的な道しるべなんですね。
過去問はどうやって手に入れる?
- 学校の先生に過去の実力テストのコピーをもらう
- 書店で都道府県別の公立高校入試過去問題集を購入
- インターネット上の無料データベースを活用
過去問を手に入れる方法はいくつかあります。
まず最も手軽なのは、学校の先生にお願いして過去の実力テストのコピーをもらうことです。多くの学校では、希望する生徒に過去問を提供してくれます。
また書店では都道府県別の公立高校入試過去問題集が販売されています。実力テストは入試問題に準じた形式で作られることが多いため、これらも有効な練習材料になります。
過去問を使った効率的な勉強法
- 本番と同じ時間制限で解く
- 間違いの原因を分析し類似問題で理解を定着させる
- 複数年分を解いて頻出パターンを把握する
過去問を解くだけでは、十分な効果は得られません。
まず、本番と同じ時間制限で過去問を解いてみましょう。時計を見ながら実際のテスト形式を再現することで、時間配分の感覚が養われます。
解き終わったら丸つけをし、間違えた問題には印をつけます。ここで重要なのは、なぜ間違えたのかを分析することです。知識不足なのか、計算ミスなのか、問題文の読み違いなのか、原因を明確にしましょう。
そして間違えた問題の類似問題を教科書や問題集で探し、理解できるまで解き直します。複数年分の過去問を解くことで頻出パターンが見えてきます。
実力テスト対策におすすめの学習サービス3選
- 家庭教師のランナー:勉強が苦手な子専門、1コマ30分900円
- オンライン家庭教師Wam:リーズナブルで質が高い
- 家庭教師のトライ:業界最大手の安心感
実力テスト対策を効果的に進めるには、質の高い学習サービスの活用も有効な選択肢です。
ここでは、特におすすめの3つのサービスを紹介します。
家庭教師のランナー|勉強が苦手な子専門で安心

- 創業21年、講師数国内最大級の14万人
- 小中学生1コマ30分900円、兄弟2人目以降半額以下
- 発達障害や不登校の子どもにも対応
- 2024年第一志望合格率97.5%
家庭教師のランナーは、創業21年の実績を持つ「勉強が苦手な小中高生専門」の家庭教師サービスです。
最大の特徴は、一人ひとりの個性に合わせたオーダーメイド指導で、勉強に苦手意識を持つお子さんに「わかる楽しさ」を感じてもらう指導理念を持っています。講師数は国内最大級の14万人を誇り、累計指導実績は30,034人、2024年の第一志望合格率は97.5%という確かな実績があります。
料金は小中学生は1コマ30分あたり900円と、塾の約半額でマンツーマン指導が受けられます。兄弟や友達と2人で同時に受けると2人目以降の月々の料金が半額以下になる独自のシステムも魅力です。
オンライン指導にも対応しており、全国どこからでも受講可能です。また高額テキスト販売が一切なく、月謝だけで指導を受けられるのも安心ポイントです。発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフも在籍しているため、様々な学習ニーズに対応できます。
オンライン家庭教師Wam|リーズナブルで質が高い

- 独自開発の専用システムで効率的なマンツーマン授業
- 東大など有名大学の現役学生・院生が講師
- 小学生40分×月4回が月4,900円から
オンライン家庭教師Wamは、学習塾WAMが運営するオンライン専業のサービスです。
独自開発の専用システムを用いた効率的なマンツーマン授業が特徴で、対面同等の質の高い指導を実現しています。講師は東京大学など有名大学の現役大学生・院生が中心です。
料金は小学生コース40分×月4回が月4,900円からと格安です。入会金や各種費用がかかります。
家庭教師のトライ|業界最大手の安心感

- 30年以上の実績、登録教師33万人以上
- 専任の教育プランナーによるきめ細かいサポート
- オリコン顧客満足度調査第1位
家庭教師のトライは、30年以上の実績を持つ業界最大手のサービスです。
全国33万人以上の登録教師から相性の良い教師を選べる圧倒的な人材ネットワークが最大の強みです。料金は入会金11,000円と授業料・交通費のみです。
オンライン指導にも完全対応しており、大手ならではの安心感と充実したサポート体制が魅力です。
実力テストの対策まとめ|志望校合格に向けて
- ・実力テストは中学生活全範囲から出題される累積型の試験で志望校決定に直結する
- ・過去の定期テストを解き直し苦手単元を集中復習する長期的な学習計画が重要
- ・保護者は子どもを批判せず共感し支援するパートナーとしての姿勢が求められる
- ・勉強が苦手なお子さんでも正しいやり方で取り組めば必ず成果は出る
ここまで、実力テストの基本的な仕組みから効果的な勉強法、おすすめの学習サービスまで詳しく解説してきました。
実力テストは、これまでの学習の蓄積全体を映し出す重要な診断ツールです。定期テストとは出題範囲も難易度も大きく異なり、短期的な詰め込みではなく長期的かつ体系的な学習が求められます。
効果的な対策としては、過去の定期テストを徹底的に解き直し、苦手単元を集中的に復習し、長期的な学習計画を立てることが重要です。点数が伸び悩む場合は、基礎力不足や勉強時間の不足、方法の誤りなど、原因を正確に特定して改善することが必要です。
2024年、ランナーで実力テスト対策をしたお子さんの第一志望合格率は97.5%でした。勉強が苦手なお子さんでも、正しいやり方で取り組めば必ず成果は出ます。
私たちランナーでは、90分の無料体験レッスンを実施しています。お子さんに合った勉強のやり方を一緒に見つけていきませんか?無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にお試しください。