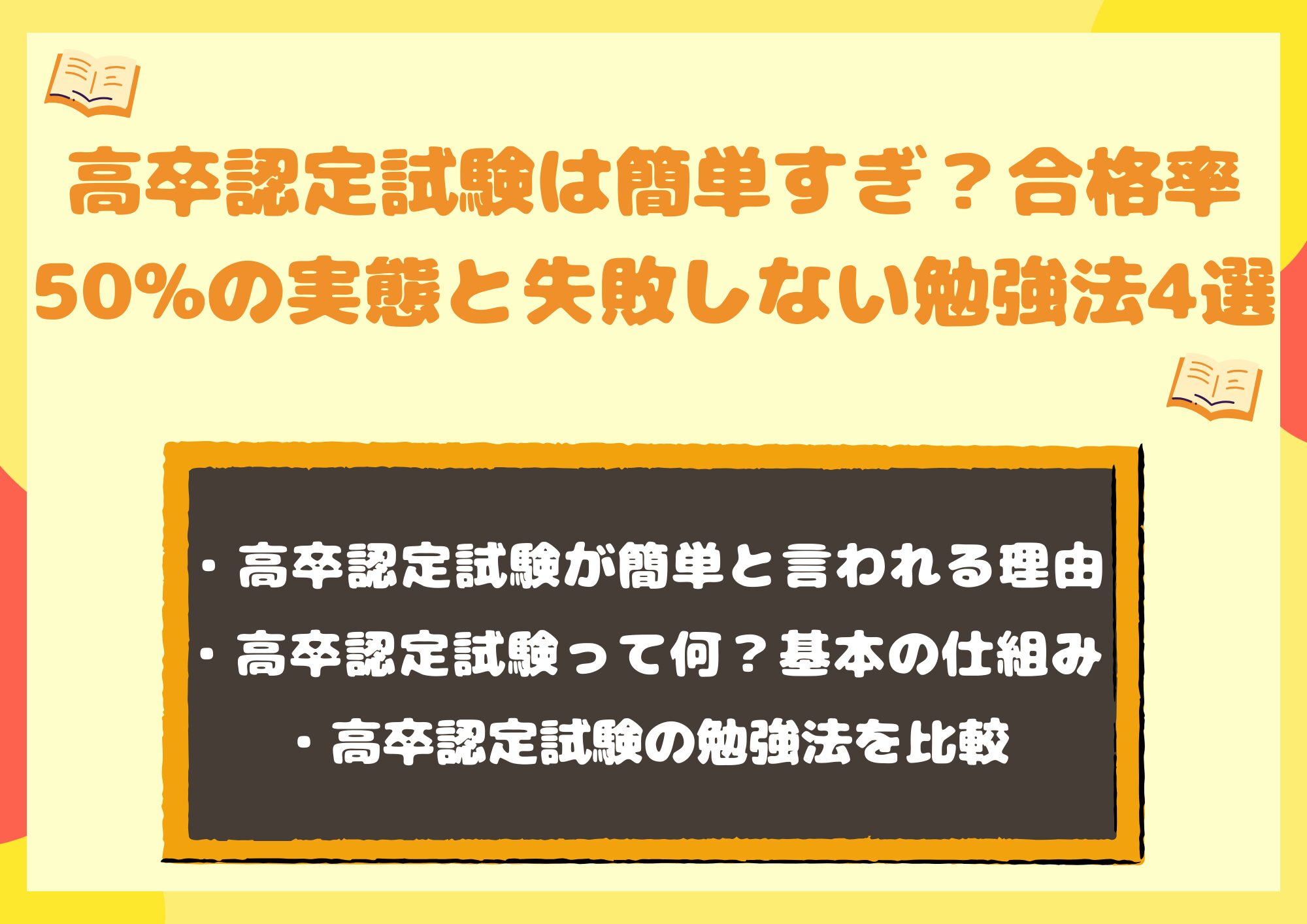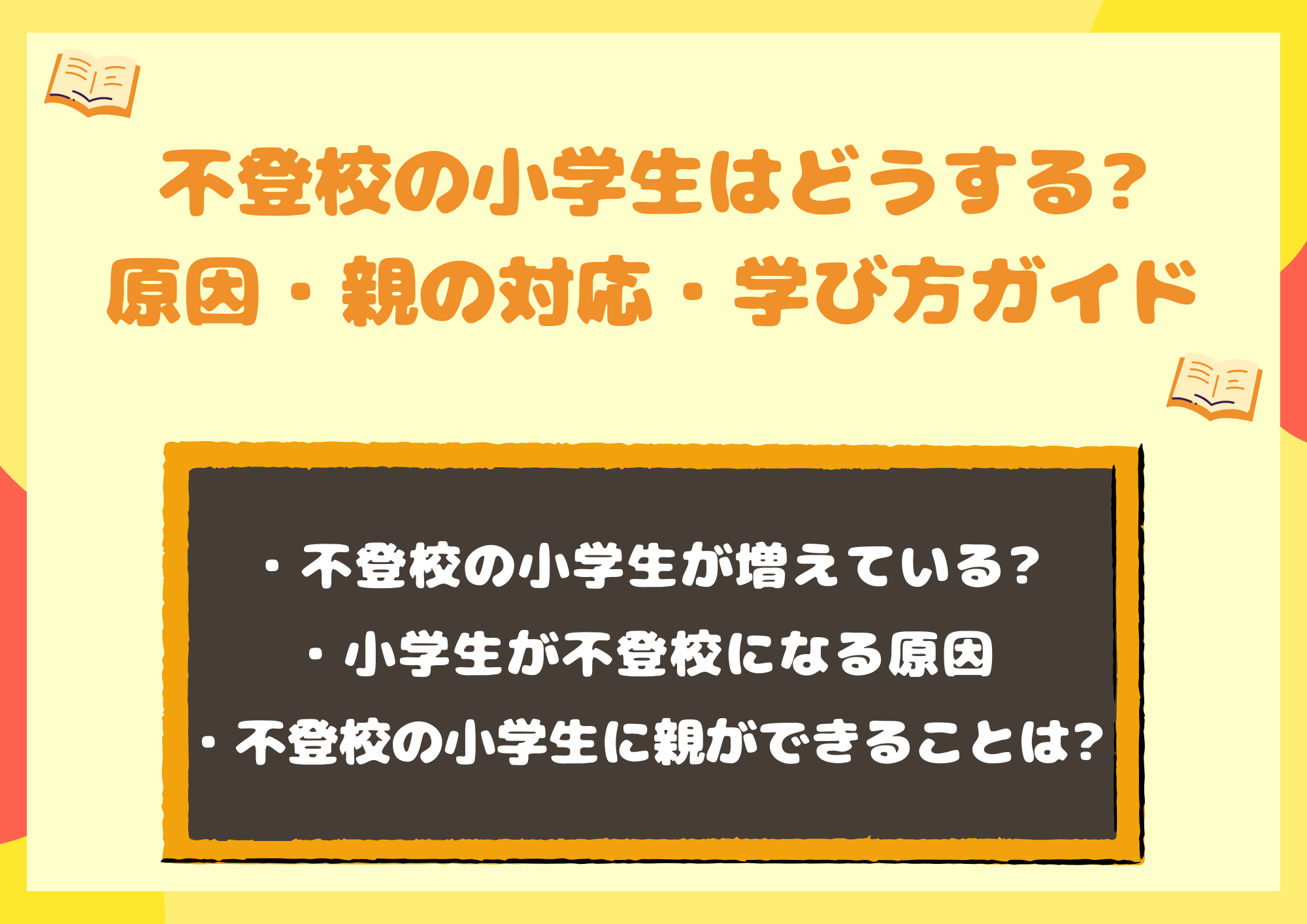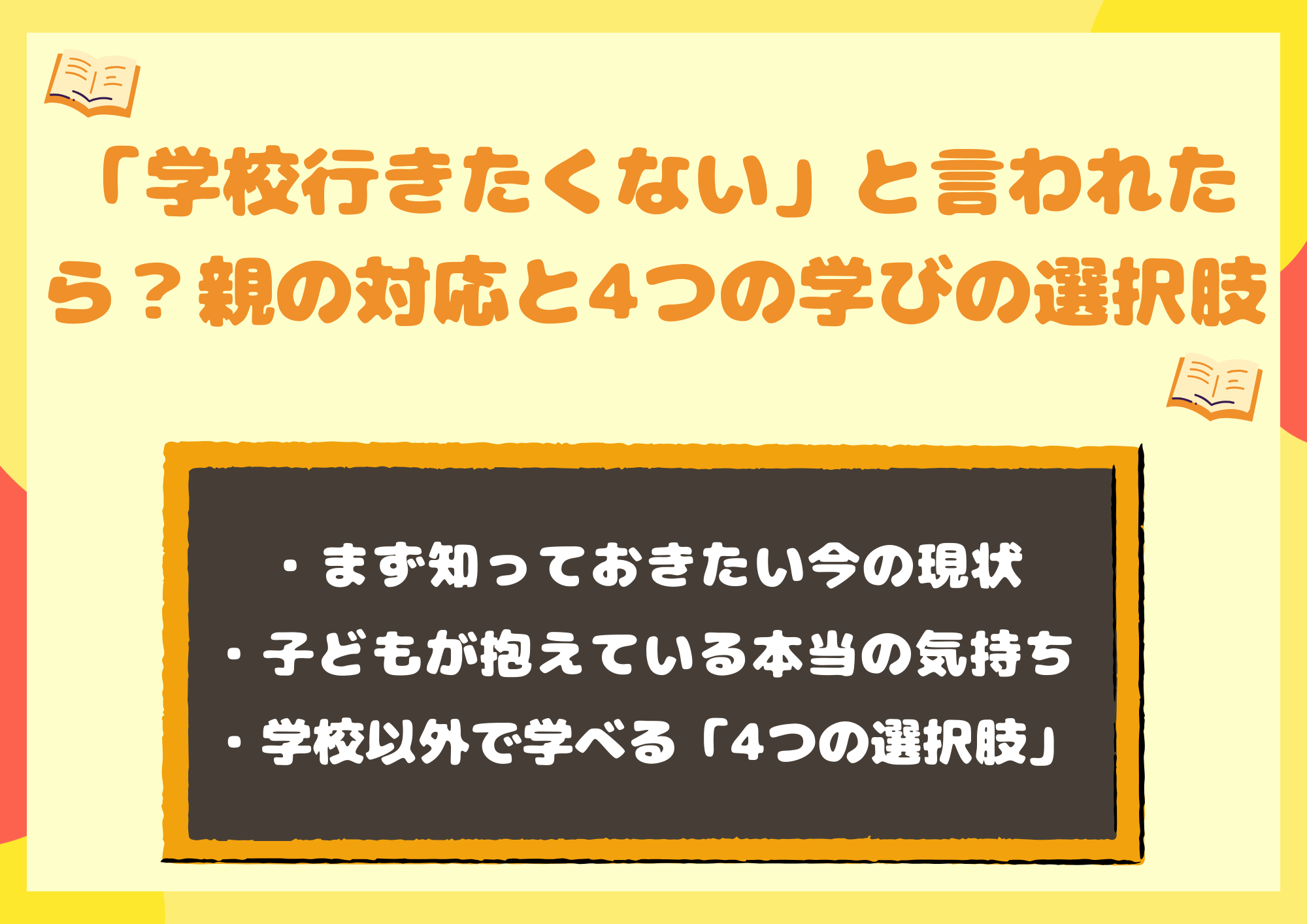- 不登校向けの家庭教師
不登校の原因が母親にある?悩む母親が今知っておきたい対応策
2025.08.14

「子どもが不登校になったとき、『母親である自分が原因なのではないか』と自分を責めてしまう方が少なくありません。
周囲の言葉やSNS上の情報に傷つきやすく、自責や孤独感に押しつぶされそうになることもあります。
しかし、不登校の背景は非常に多様であり、家庭以外にも学校や社会、本人の性格などさまざまな要因が複雑に絡み合っています。
この記事では、母親が原因と感じやすい社会的背景や、実際にどのように向き合えばよいか、さらに頼りになる家庭教師サービスについても詳しく解説します。
ご自身を過度に責めず、一歩ずつ前向きになれるためのヒントをお届けします。
目次
- 不登校の原因が母親にあると感じる時の本当の理由とは
- 不登校で母親が原因かもしれないと悩む時に知っておきたいチェックポイント
- 不登校が母親の接し方や育て方に関係している場合の具体例
- 不登校で悩む母親自身が自分を責めすぎないためにできること
- 不登校の母親ができる子どもへの正しい対応方法と実践例
- 不登校の子どもに効果的なサポートを受けられるおすすめ家庭教師サービス
- 家庭教師のランナー|不登校や発達障がい対応カウンセラーによる安心サポート
- 家庭教師のトライ|専門プランナーによる家庭ごとのきめ細やかな対応
- 学研の家庭教師|大手ならではの信頼と幅広い講師層で不登校にも対応
- 家庭教師のサクシード|上場企業の安心感と不登校支援実績
- 家庭教師ファースト|料金の安さと手厚いフォローで不登校家庭もサポート
- 家庭教師ジャンプ|正社員プロ講師による発達障がい・不登校特化指導
- オンライン家庭教師Wam|全国どこでも不登校対応のマンツーマンサポート
- 家庭教師のデスクスタイル|西日本全域対応の不登校サポートと学習習慣化
- 家庭教師のノーバス|個別指導塾併設で受験から不登校サポートまで
- オンライン家庭教師メガスタ|専門指導による全国対応のオンラインサポート
- 家庭教師サービス以外で利用できる不登校・母親の相談窓口と支援団体
- 不登校と母親の関係でよくある質問と回答まとめ
- 不登校の原因が母親かもしれないと悩む方へまとめ
不登校の原因が母親にあると感じる時の本当の理由とは
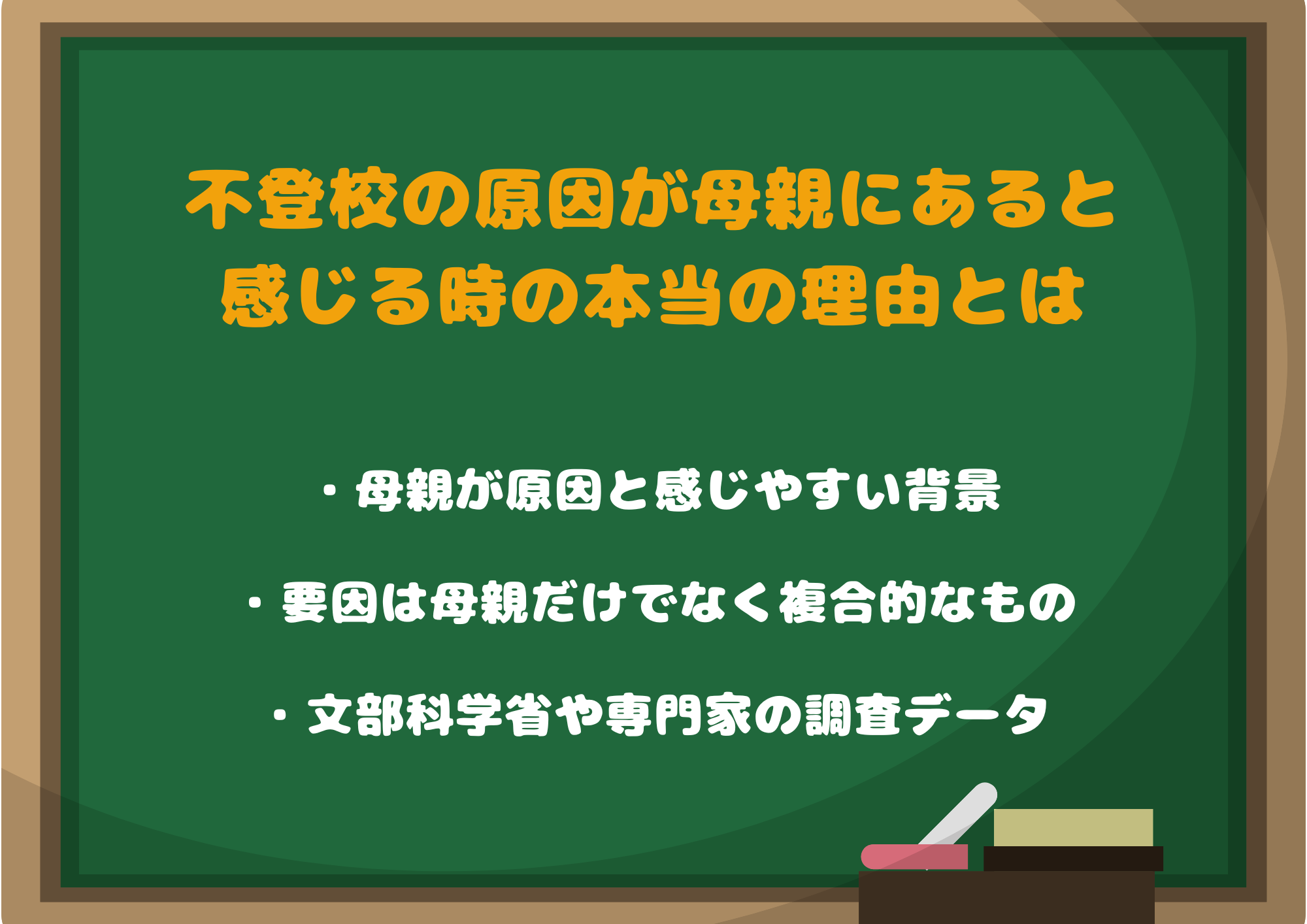
お子さまが不登校になった時、多くの母親は「自分の育て方が悪かったのでは」と深く悩みます。
これは、日本社会に根強く残る、母親神話や、子育ての責任が母親に偏りやすい風潮の影響を受けています。
SNSやメディアでも「親のせい」とされやすく、ますます自分を責めてしまいがちな環境です。
しかし、実際には不登校の要因は複雑であり、決して母親だけに責任があるものではありません。
不登校の本質を見誤らないためにも、まずは冷静に現状を見つめ直すことが大切です。
母親が原因と感じやすい背景や社会的なイメージ
- 日本特有の家庭観や母親神話が背景にある
- SNSやメディア情報により自責感が増大しやすい
- 「理想的な母親像」と現実のギャップで孤立感が強まる
母親が「自分が原因」と感じてしまう背景には、日本特有の家庭観や子育て観が強く影響しています。
家庭の問題が「母親の責任」とされがちな社会的風潮や、学校や周囲からの「家庭環境が影響している」という言葉が、母親の自責を深めることがあります。
また、SNSやテレビで発信される極端な事例や意見も、自責感を大きくする要因となります。
「理想的な母親像」が強調され、現実とのギャップに苦しむ方も少なくありません。
さらに、家庭の事情を外部に知られたくない気持ちや、恥ずかしさから孤立感が強まる場合もあります。
共働き世帯や多様な家族形態が増えていますが、依然として固定観念が根強いのも事実です。
こうした社会的イメージに流されず、客観的な事実に目を向けることが重要です。
「自分を責めるばかりでつらい」「他の家庭はもっと上手くできているように思う」など、ひとりで悩まずに相談できる環境をつくることも大切です。
不登校の主な要因は母親だけで決まらない複合的なもの
- 学校環境や友人関係・本人の気質など多様な要因が複合
- 母親一人に責任を負わせるのは間違い
- 広い視野で状況を整理することが重要
不登校の要因は、家庭だけでなく学校環境や友人関係、本人の気質や体調など、様々な要素が重なって生じます。
子どもの発達段階や思春期特有の不安・ストレスも影響します。
「学校でのいじめ」「先生との相性」「授業の難しさ」「クラスでの孤立感」など、学校生活にも多くの壁があります。
さらに、SNSやネットの普及により、人間関係のトラブルや情報過多が不登校の要因になるケースも増えています。
家庭内でも父親や兄弟との関係、経済的な状況、家庭固有の事情が複雑に絡み合っています。
「母親だけが悪い」「母親のせい」と単純に考えるのは危険です。
原因を一つに決めつけず、広い視野で状況を整理していくことが重要です。
「母親として何か間違ったのか」と悩んだ時も、他の多くの要因が同時に影響していることを理解することが、冷静な対応につながります。
文部科学省や専門家の調査データからみる家庭の影響
- 「家庭要因のみ」で不登校となる割合は一部に過ぎない
- 家族全体の関わり方が影響する
- 専門家や第三者の介入で解決する例も多い
文部科学省の調査によれば、不登校の要因として「家庭要因のみ」が占める割合は全体の一部に過ぎず、「本人要因」「学校要因」との複合的な影響が多いことが分かっています。
専門家も「家庭環境だけで不登校になるわけではない」と指摘し、現代の不登校は多因子的に発生する傾向にあるとされています。
家庭要因には「親子関係」「家庭内の雰囲気」「経済状況」などが含まれますが、母親だけの責任ではありません。
父親や祖父母など、家族全体の関わり方も影響します。
また、家庭以外の第三者や専門家が介入することで、子どもが安心感を得て学校復帰につながるケースも多いことが報告されています。
家庭だけで抱え込まず、周囲や専門家の力を借りることが大切です。
こうした事実を知ることで、母親が一人で自分を責め続ける必要はないと理解できます。
現実を正しく受け止め、できる対応策を考えていく姿勢が大切です。
不登校で母親が原因かもしれないと悩む時に知っておきたいチェックポイント
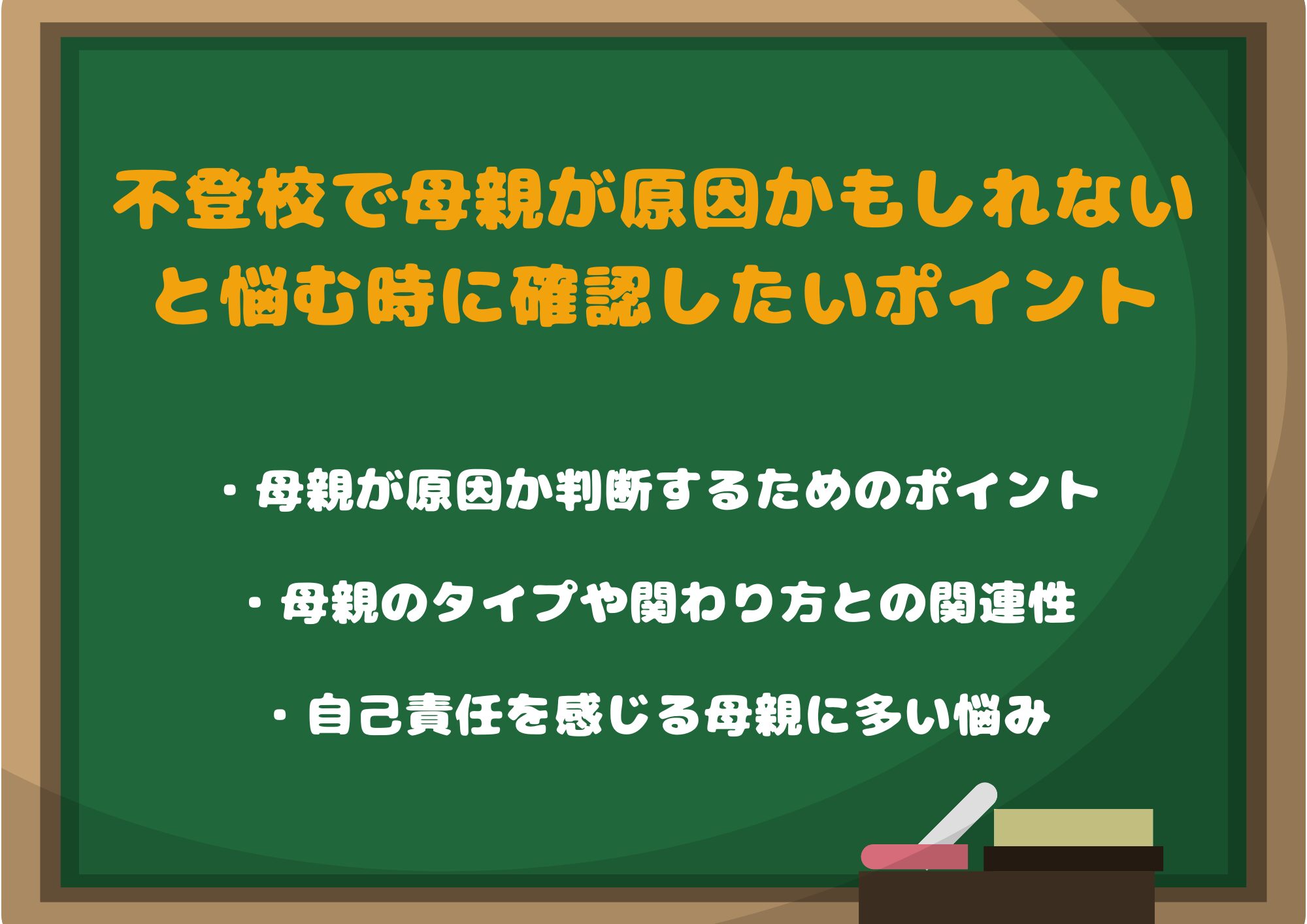
不登校になったとき、「もしかしたら自分の言動や接し方が原因では」と苦しむ母親も多いでしょう。
しかし、自己判断で悩み続けるのではなく、冷静に現状を見つめるためのチェックポイントを知ることが大切です。
日常生活や子どもとの関わりでどんなサインがあったか、どのような場面で子どもの心に影響を与えていたかを具体的に振り返ることで、改善のヒントや気づきを得ることもできます。
「自分のせい」と決めつける前に、客観的な視点で状況を整理しましょう。
母親が不登校の原因かどうか判断するためのポイント
- 子どもの様子や行動パターンを具体的に観察する
- 母親の言動や接し方が影響していないか振り返る
- 専門機関や第三者の意見を参考にする
まずは子どもの様子や行動パターンを具体的に観察しましょう。
「登校を嫌がるようになったきっかけ」「家庭内での変化やトラブル」「母親と子どもの関係の変化」など、過去から現在までの流れを振り返ります。
また、「母親の言動に対する子どもの反応」「日常的な会話や接し方にプレッシャーやストレスがなかったか」も重要な視点です。
専門機関やスクールカウンセラーに相談し、第三者の意見を取り入れることで、より客観的に現状を把握できます。
「家庭以外の場所で変化があった」「きっかけが学校や友人関係だった」という場合は、母親だけに責任を感じず、広い環境に目を向けてください。
自己判断をしすぎず、専門家や家族と一緒に状況を整理していくことが大切です。
ひとりで抱え込まず、必要なサポートを受けながら状況を冷静に見直すことが大切です。
母親のタイプや関わり方と不登校の関連性
- 母親の性格や日常の関わり方が子どもに影響する場合がある
- 子どもの個性や家庭の状況によって影響の度合いは異なる
- 関わり方を見直すことでより良い親子関係に近づく
母親の性格や日常の関わり方は、子どもの情緒や自己肯定感に影響することがあります。
たとえば「厳格で完璧主義なタイプ」「常に子どもを心配しすぎてしまうタイプ」「干渉が強く自立を妨げやすいタイプ」など、親子関係にはさまざまなスタイルが存在します。
これらがプレッシャーや自己表現の制限につながる場合も指摘されています。
一方で、子どもの個性や家庭の状況によって、同じ接し方でも影響の度合いは異なります。
母親が「こうすべき」と思い込みすぎて、無意識に子どもの本音に寄り添えなくなってしまうことも少なくありません。
家族全体のコミュニケーションや、父親やきょうだいとの関係性も、子どもの安定に関わっています。
「自分のタイプだからダメだった」と決めつけず、子どものサインを見逃さずに、必要に応じて関わり方を見直すことが、より良い親子関係の鍵です。
完璧な親でなくても大丈夫です。
柔軟に自分を変えていく姿勢が、子どもに安心を与えます。
自己責任を感じる母親に多い悩みと心理的な負担
- 自分のせいだと責任を感じやすい
- 過去の家庭環境や経験が影響する場合も
- 孤独を和らげる行動が負担軽減の近道
不登校の子どもを持つ母親は、「自分のせいだ」と強い責任感に苦しみがちです。
周囲からの「しつけが悪い」「甘やかしすぎ」などの声や、家族の無理解な言葉によって孤独や無力感を感じることも少なくありません。
「他のお母さんはできているのに自分はダメだ」と自分を責めてしまう現実もあります。
また、母親自身が子ども時代に厳しい環境で育ったり、家庭環境に課題があった場合、その影響が無意識に子育てにも現れやすいともいわれます。
母親のストレスや不安が子どもに伝わりやすいことも、悪循環の一因です。
「誰かと悩みを分かち合う」「専門家に相談する」など、孤独を和らげる行動が心理的な負担を軽減する近道です。
自分を責めすぎず、気持ちを言葉にして吐き出すことが、心の健康を守る第一歩です。
不登校が母親の接し方や育て方に関係している場合の具体例
不登校の背景には、家庭での接し方や育て方が影響しているケースもありますが、それが全ての原因ではありません。
ここでは「過干渉」「過保護」「期待・プレッシャー」「母親のストレス」「厳しすぎるしつけ」「コミュニケーション不足」など、どのような関わり方が子どもの不安や自信喪失につながるか、具体的に解説します。
自分の行動を振り返り、より良い関わり方を考える参考にしてください。
過干渉や過保護な育て方と子どもの心への影響
- 過干渉や過保護は自立心や自己決定力の育成を妨げる
- 親への依存心や自信喪失につながりやすい
- 失敗も成長の一部として見守ることが大切
母親が子どもの全てを管理しすぎたり、先回りして問題を解決しようとし過ぎると、子どもは「自分で考える機会」や「自分の意見を伝える経験」が減ります。
その結果、自己決定力や自信が育ちにくく、壁にぶつかった時に乗り越える力が不足しがちです。
また、過保護な対応が続くと、「自分でやるより親に頼るほうが楽」と感じ、徐々に自立心を失いやすくなります。
「困難に直面した時に逃げてしまう」など、不登校として表れることもあります。
「助けすぎることが必ずしも愛情ではない」と気づき、子どもが自分で考え選ぶ経験を重ねさせることが大切です。
失敗も成長の一部として見守る姿勢が、子どもの回復力や自己肯定感を高めます。
母親の期待やプレッシャーが与えるストレス
- 過度な期待や「もっと頑張りなさい」はプレッシャーになる
- 理想に応えられない自分を否定しやすくなる
- ありのままを受け入れることで安心につながる
「勉強で良い成績を取ってほしい」「将来はこうなってほしい」といった母親の期待は、時に子どもにとって大きなストレス源になります。
無意識のうちに「もっと頑張りなさい」「なぜできないの?」と声をかけることで、子どもは自分に自信を持てず、失敗を恐れて行動できなくなることもあります。
過度な期待は、「母親の理想に応えられない自分はダメだ」と思い込む原因になり、不登校や無気力、自己否定につながることがあります。
子どもが自分のペースで成長することを認め、過度な期待やプレッシャーから解放してあげることが大切です。
子どものありのままを受け入れることで、心の安心につながります。
応援する気持ちは大切ですが、「あなたらしくいて大丈夫」と伝えることが最大のサポートになります。
母親のストレスや気分の不安定さが子どもに与える影響
- 母親のストレスや気分の浮き沈みは子どもに伝わりやすい
- 家庭の雰囲気がピリピリすると子どもが不安になる
- 母親自身の心の安定が子どもの安心につながる
母親が日常的にストレスを抱えたり、気分の浮き沈みが激しい状態が続くと、その雰囲気は子どもにも伝わりやすくなります。
家の中がピリピリした空気に包まれると、子どもは「自分が悪いのか」「お母さんに迷惑をかけている」と感じてしまいます。
「今日は機嫌が悪いから話しかけないほうがいい」と思わせてしまうと、子どもは家庭で安心して過ごせなくなり、心の拠り所を失うこともあります。
母親自身の心の安定が、子どもの安心感にも直結します。
無理をせず、自分のストレスに気づき、ケアを心がけることで親子ともに余裕が生まれます。
厳しすぎるしつけやコミュニケーション不足の問題点
- 厳しすぎるしつけは本音を隠させる原因になる
- コミュニケーション不足は「理解されていない」と感じさせやすい
- お互いが本音で話せる家庭環境を意識する
家庭内で厳しいしつけや規律を重視しすぎると、子どもは自由な発言や感情表現ができなくなります。
失敗を厳しく叱られると、萎縮して本音を隠すようになり、心を閉ざしやすくなります。
それが積み重なることで、不登校や拒否反応として現れる場合もあります。
また、忙しさや生活リズムの乱れから、母親と子どものコミュニケーションが不足すると、子どもは「理解されていない」「自分は大切にされていない」と感じやすくなります。
日々の何気ない会話やスキンシップが、子どもの心の支えになります。
「厳しさ」と「愛情」は両立できますが、まずは子どもの気持ちに耳を傾ける姿勢が欠かせません。
完璧を目指すより、お互いが本音で話せる家庭環境を意識しましょう。
不登校で悩む母親自身が自分を責めすぎないためにできること
お子さまの不登校をきっかけに、「自分が全て悪い」と思い込んで苦しんでいる方へ。
知っておいてほしいのは、どんな家庭にも起こり得ることであり、決して母親一人の責任ではないということです。
自分を責め続けることは、解決を遠ざけるだけでなく、親子の心の健康を損なう原因にもなります。
今この瞬間から、母親自身の心のケアを始めてください。
不登校の原因は母親だけではないと知る重要性
- 不登校は多くの要因が複雑に絡み合って生じる
- 家庭要因のみで不登校になる子はごく一部
- 正しい情報をもとに「できること」に集中する
子どもの不登校は、多くの要因が複雑に絡み合って生じるものです。
学校の環境や友人関係、本人の気質や体調、社会全体の変化など、家庭以外にもさまざまな影響があります。
文部科学省の調査でも「家庭要因のみ」で不登校になる子はごく一部であることが明らかになっています。
自分の接し方や家庭のあり方を見直すことは大切ですが、「全て自分の責任」と抱え込んでしまうと、解決の糸口が見えなくなってしまいます。
他の家庭でも同じ悩みを抱えている母親は多く、決して自分だけが特別ではありません。
不登校の原因は一人のせいではなく、複数の要因が重なっているという現実を知ることで、自分を追い詰めずに状況を見直せます。
周囲の声や思い込みに振り回されず、正しい情報を元に「できること」に集中しましょう。
母親の自己肯定感を回復させる考え方
- 「私はダメな母親だ」と思い込む必要はない
- 過去の自分を否定せず、今できることに目を向ける
- 「今日できたこと」を認めて自分を褒める
「私はダメな母親だ」と思い込む必要はありません。
どんなに努力しても、子育ては思い通りにならないことの方が多いものです。
大切なのは「過去の自分」を否定せず、「今できること」「これからの変化」に目を向けることです。
日々の小さな工夫や子どもへの声かけ、家族との時間を大切にすることが、母親自身の自己肯定感を高める近道となります。
完璧を目指すより、「今日できたこと」を認め、自分を褒めてあげることが回復への第一歩です。
母親が自分を大切にすることで、子どもにも前向きな気持ちが伝わります。
子どものために頑張る自分自身も、しっかりいたわってあげてください。
家族や第三者への相談が心の負担を軽くする理由
- 家族や信頼できる第三者に悩みを話すことで心が軽くなる
- 専門家や経験者のサポートで新たな視点や解決策が得られる
- 相談することで思考が整理され、安心につながる
ひとりで全てを抱え込まず、夫や家族、信頼できる友人や第三者に悩みを話すことで、心の負担は大きく軽くなります。
特に同じ悩みを経験した人や専門家のサポートを受けることで、具体的な解決策や新たな視点が得られることも多いです。
相談することで思考が整理され、「気持ちを分かってもらえた」という安心を得られます。
母親が心に余裕を持つことは、家庭全体の雰囲気にも良い影響を与えます。
相談は弱さではなく、前向きな一歩です。
悩みを口に出すことで、次の行動に踏み出せます。
不登校の母親ができる子どもへの正しい対応方法と実践例
お子さまが不登校のとき、母親としてできることはたくさんあります。
無理に登校を促すよりも、子どもの気持ちに寄り添い、家庭を安全な居場所にすることが大切です。
ここでは、子どもの心を支える声かけやサポート方法、母親自身のストレスケア、家族全体で支える体制づくりまで、実践的な対応策を紹介します。
「何もできていない」と思い込まず、一歩ずつできることから始めましょう。
子どもの気持ちを受け止める声掛けやサポート方法
- 理由を問い詰めたり無理に登校を促すのは逆効果
- 「つらいね」「今は休んでも大丈夫」と気持ちに寄り添う
- 存在自体を認め、安心できる家庭の雰囲気を大切に
子どもが学校に行けないと感じている時は、無理に理由を問い詰めたり、焦って登校を促す声かけは逆効果となる場合があります。
「つらい気持ちがあるんだね」「今は休んでも大丈夫」と、子どもの感情を受け止める言葉を意識しましょう。
「学校に行けない自分はダメだ」と思い込まないように、子どもの存在自体を認めてあげることが大切です。
話したくない時は無理に聞き出さず、安心できる家庭の雰囲気を心がけてください。
「あなたの味方だよ」と伝えることが、子どもの心の回復につながります。
子どものペースを大切にし、少しずつ前向きな気持ちを育てていきましょう。
母親自身のストレスケアやリラックス方法
- 母親が心身ともに疲れ切らないよう工夫を
- 自分の時間や趣味、リラックスできる活動を意識する
- 信頼できる人との会話やカウンセリングも有効
母親が心身ともに疲れ切ってしまうと、子どものサポートにも限界が出てきます。
自分のための時間をつくったり、趣味やリラックスできる活動を意識して取り入れることも大切です。
信頼できる友人との会話やカウンセラーとの対話も効果的です。
自分自身のストレスを上手にケアすることで、親子の関係を良好に保つことができます。
母親が笑顔でいることが、家庭の雰囲気を明るくします。
「自分を大切にすること=子どもを大切にすること」と捉え、無理をしすぎないように心がけてください。
家庭内の雰囲気づくりや日常会話のポイント
- 否定や比較を避けて、ありのままを受け入れる雰囲気を大切に
- プレッシャーを感じさせない会話を意識する
- 小さな楽しみやスキンシップを共有する
家庭が子どもにとって安心できる場所になるよう、否定や比較を避けて、ありのままを受け入れる雰囲気を大切にしましょう。
日常会話では「どうしてできないの?」ではなく、「今日はどんなことがあった?」など、プレッシャーを感じさせない問いかけを心がけてください。
「ごはんが美味しいね」「一緒にテレビを観よう」など、小さな楽しみを共有することも効果的です。
子どもが心を開きやすくなるよう、日々の会話やスキンシップを意識してみてください。
家庭内の明るい雰囲気が、子どもの安心と自信を取り戻すきっかけになります。
焦らず、毎日を大切に過ごしていくことが大切です。
夫や家族との協力で子どもを支える体制づくり
- 母親ひとりで悩みを抱え込まない
- 家族全体で役割分担や話し合いを持つ
- 家族の協力体制が子どもの安心材料になる
母親ひとりで悩みを抱え込まず、夫やきょうだい、祖父母など家族全体で協力し合うことも大切です。
家族が仲良く話す姿を子どもに見せたり、一緒に悩みを共有することで、子どもに「一人じゃない」と感じさせることができます。
夫や家族と役割分担を決めたり、話し合いの場を持つことで、母親自身の負担も軽減されます。
家族全体でサポート体制を整えることで、子どもが安心して自分のペースで回復することができます。
家族の協力体制が、子どもにとって最大の安心材料です。
支え合いながら、前向きな家庭環境を一緒につくっていきましょう。
不登校の子どもに効果的なサポートを受けられるおすすめ家庭教師サービス
不登校のお子さまが学習の遅れを感じたり、家庭でのサポートだけでは限界があるときは、専門の家庭教師サービスの利用がとても有効です。
家庭教師は、お子さま一人ひとりの性格や状況に合わせて寄り添い、学習への自信や「できた!」という実感を育むことができます。
ここでは、不登校・発達障がい・学習の遅れに対応できる家庭教師サービスを厳選してご紹介します。
信頼できる第三者と一緒に歩むことで、お子さまにも前向きな変化が生まれます。
家庭教師のランナー|不登校や発達障がい対応カウンセラーによる安心サポート

- 20年以上の実績を持つ全国規模の家庭教師グループ
- 専門カウンセラー在籍、オーダーメイド指導が強み
- 月謝制・オンライン対応・細やかな本部フォロー
「家庭教師のランナー」は、運営会社であるマインズ株式会社(本社:大阪府大阪市、設立2004年)が展開する全国規模の家庭教師グループです。
20年以上の実績を持ち、不登校や発達障がいのお子さまに特化した専門カウンセラーが在籍しています。
お子さま一人ひとりに合わせたオーダーメイド指導で、「反抗的」「無気力」など難しいケースにも、その子に合う方法で丁寧に対応しています。
月謝制を採用し、月謝の目安は60分×月4回で8,800円(税込)~(2025年7月現在)。
兄弟同時指導やオンラインでの全国対応、LINEでの質問受付、定期的な本部スタッフのフォローや特別カリキュラムなど、きめ細やかなサポートも充実しています。
利用者の口コミで高評価が多く、特に「どんな状態でも子どもに合わせて支えてくれる」といった声が目立ちます。
お子さまの個性を尊重した学習支援で、保護者からも信頼されています。
勉強が苦手なお子さまも、まずは無料体験で「できる!」を実感してみてください。
家庭教師のトライ|専門プランナーによる家庭ごとのきめ細やかな対応

- 登録講師数33万人、最大手の家庭教師サービス
- 専任プランナーが相性の良い教師を選定
- オンライン指導も充実、幅広いニーズに対応
全国最大手の「家庭教師のトライ」は、登録講師数33万人(2024年3月時点)を誇り、相性の良い教師を専任プランナーが選定します。
ご家庭ごとに最適なプランを提案し、マンツーマンのオーダーメイド指導で、不登校や学習の遅れにも柔軟に対応します。
トライ式学習法を取り入れ、お子さま一人ひとりの理解度や目標に合わせたカリキュラムが組めます。
オンライン指導にも強く、自宅で安心してプロの指導を受けることが可能です。
講師交代は無料(※交通費等は別途必要な場合あり)。
30年以上にわたる受験データや豊富な実績も心強いポイントです。
受験から不登校のサポートまで、幅広いニーズに対応できるサービスです。
保護者と連携しながら、お子さまの将来に向けて着実にサポートしていきます。
学研の家庭教師|大手ならではの信頼と幅広い講師層で不登校にも対応

- 学研グループ運営、登録講師10万人超
- 幅広い講師層・訪問とオンライン両方に対応
- 中学・高校・大学受験まで幅広く対応
「学研の家庭教師」は、教育大手の学研グループが運営し、登録講師10万人超(2025年7月時点・公式発表)を有します。
大学生からプロ講師まで幅広い層が在籍し、オンライン・訪問どちらにも対応。
不登校や学習の遅れにも柔軟に対応できるのが強みです。
発達支援研修カリキュラムの導入など、旧タートルスタディスタッフのノウハウも継承しています。
中学・高校・大学受験対策まで豊富な指導実績を持ち、保護者の相談にも親身に対応します。
大手ならではのサポート体制で、初めての家庭教師利用でも安心感があります。
信頼できる教師との出会いで、子どもの学習意欲を引き出せる環境を整えましょう。
家庭教師のサクシード|上場企業の安心感と不登校支援実績

- 上場企業が運営、13万人以上の講師が登録
- 体験授業や講師指名制で相性を重視できる
- 柔軟な学習計画提案と手厚いサポート
「家庭教師のサクシード」は、上場企業が運営し、2023年8月時点で13万人以上の講師が登録しています。
学生から社会人まで厳選された講師が在籍し、不登校や発達障がいの支援にも豊富な実績を持っています。
講師指名制や体験授業など、子どもとの相性を重視できるシステムも特徴です。
主要コースは入会金不要で、教材費も必要最低限。
オンライン・対面どちらにも対応し、柔軟な学習計画の提案や科目対応も好評です。
担当スタッフと講師が連携し、子どもの変化を見守りながら前向きな学習習慣をサポートします。
初めての家庭教師でも安心して利用できる環境が整っています。
家庭教師ファースト|料金の安さと手厚いフォローで不登校家庭もサポート

- 最安プランで月4回11,000円(税込)から利用可能
- 体験授業後そのまま本契約へ移行できて安心
- 担当教師と本部スタッフの連携で手厚いフォロー
「家庭教師ファースト」は、最安プランでは60分×月4回で11,000円(税込/エリアや交通費により変動あり)から利用できる良心的な料金設定と、体験授業の手厚さで人気です。
無料体験後、そのまま担当講師が本契約に移行できるため、子どもも安心して学習を続けられます。
全国対応のオンライン指導も利用できます。
低価格でも指導の質が高く、受験対策から不登校支援まで充実したフォローが魅力です。
担当教師と本部スタッフが連携し、保護者の相談にも親身に対応します。
「費用を抑えながらもサポートを受けたい」ご家庭におすすめのサービスです。
初めての方も気軽に申し込みができるので、不登校の家庭にも選ばれています。
家庭教師ジャンプ|正社員プロ講師による発達障がい・不登校特化指導

- 全員正社員プロ講師による高品質な指導
- 発達障がい・不登校特化の個別対応と家族支援
- WISC検査など特性をふまえたカリキュラム
「家庭教師ジャンプ」は、全員正社員プロ講師による安定した質の高い指導を提供しています。
不登校や発達障がいなど、特別な配慮が必要なご家庭を対象にしたサポート体制が整っています。
WISC検査など特性をふまえた個別対応や、家族全体を支援する仕組みも充実しています。
初回訪問やカウンセリングからスタートできるため、家庭外との接点が持ちにくいお子さまでも安心して学習を始められます。
経験豊富なプロ講師による個別指導で、学びの自信を育てていきます。
特別なニーズを持つご家庭にも、心強い味方となるサービスです。
オンライン家庭教師Wam|全国どこでも不登校対応のマンツーマンサポート

- 全国対応のオンライン個別指導
- 小学生コースは40分×月4回4,900円~、中学生5,400円~
- 24時間オンラインで保護者相談も対応
「オンライン家庭教師Wam」は、独自開発のオンラインシステムで全国どこからでも高品質な個別指導を受けられます。
小学生コースは40分×週1回/月4回で4,900円(税込)から、中学生は5,400円(税込)から利用できる明確な料金体系です。
難関大学を含む大学生講師が中心となり、学習の遅れや不登校へのサポートも丁寧です。
生活リズムや予定に合わせて柔軟に授業が設定でき、保護者の相談も24時間オンラインで受け付けています。
手ごろな価格と充実したサポートが魅力で、不登校や学習の遅れに悩むご家庭をしっかり支えます。
全国どこでも気軽に始められるのも大きなメリットです。
家庭教師のデスクスタイル|西日本全域対応の不登校サポートと学習習慣化

- 西日本エリアで25年以上の実績
- 1コマ30分単位で指導、2人目以降無料制度あり
- オンライン・宿題計画サポートも充実
「家庭教師のデスクスタイル」は、西日本エリアで25年以上の実績を持つ家庭教師センターです。
1コマ30分単位で指導が受けられ、2人目以降は無料となる制度もあります。
勉強が苦手・不登校でやる気が出ないお子さまにも、一人ひとりのペースに合わせたサポートを提供します。
毎日の宿題計画や、オンライン指導にも対応しており、
「子どもが自分から勉強する習慣がついた」と多くのご家庭で好評です。
リーズナブルな月謝で始めやすく、保護者の負担も軽減できます。
家庭教師のノーバス|個別指導塾併設で受験から不登校サポートまで

- 個別指導塾併設で受験・不登校両対応
- 地域密着の情報とノウハウでサポート
- シンプルな料金体系も安心
「家庭教師のノーバス」は、関東・東海エリアを中心に個別指導塾を併設した家庭教師センターです。
受験対策、学習の遅れ、不登校サポートまで幅広く対応し、地域密着の情報と長年のノウハウを活かした指導を行っています。
講師と本部スタッフのダブル体制で、お子さまの状況に応じたきめ細かなフォローが特徴です。
塾と家庭教師の両方を活用したい方や、幅広く相談したい方にも適したサービスです。
市販教材を利用したシンプルな料金体系も安心ポイントです。
オンライン家庭教師メガスタ|専門指導による全国対応のオンラインサポート

- 全国4万人以上の講師が登録する大手オンライン家庭教師
- 難関受験~不登校・学習遅れまで幅広いプラン
- AI学習計画サポートや海外在住にも対応
「オンライン家庭教師メガスタ」は、全国4万人以上の講師が登録する大手オンライン家庭教師サービスです。
難関受験から不登校・学習の遅れまで、さまざまな状況に応じた専門プランが用意されています。
プロ講師や難関大学出身の講師による個別指導、AIによる学習計画サポートなども利用可能です。
訪問型より割安な料金体系で、海外在住のご家庭にも対応。
「オンラインでも成果が出る」と評判の高いサービスです。
どんな状況でも安心して利用できる体制が整っています。
家庭教師サービス以外で利用できる不登校・母親の相談窓口と支援団体
不登校や家庭の悩みは、家庭教師サービスだけでなく、専門機関やピアサポートなど多様な相談窓口を活用することで、より安心して解決策を探すことができます。
悩みを共有できる場所があるだけでも、心の負担は大きく軽くなります。
ひとりで抱え込まず、早めの相談や情報収集が前向きな行動につながります。
学校・自治体の教育相談室やスクールカウンセラー
- 学校や自治体の教育相談室を活用できる
- 専門家に学校生活や家庭の悩みを相談可能
- 学校と連携した対策や復帰支援も受けられる
お子さまが通う学校には、教育相談室やスクールカウンセラーが配置されていることが多く、学校生活に関する悩みや家庭内の問題について専門家に相談できます。
自治体の教育委員会でも「教育相談窓口」を設けており、電話や面談で気軽に相談することが可能です。
学校側と連携して対策を検討したり、在宅学習や復帰支援も受けられる場合があります。
学校や自治体の窓口を積極的に活用することで、家庭だけでは解決が難しい問題も早期対応しやすくなります。
「誰に何を相談したらいいかわからない」という場合も、まずは学校に問い合わせてみるのが一歩です。
不登校親の会や保護者向けサポートグループ
- 同じ悩みを持つ親同士で情報や気持ちを分かち合える
- 定期的な集まりやオンラインミーティングも多い
- 「自分だけじゃない」と感じられる心の支えになる
全国各地で開催されている「不登校親の会」や保護者向けのサポートグループは、同じ悩みを抱える親同士が集まり、気持ちを分かち合ったり情報交換できる場所です。
経験者ならではのアドバイスや温かい交流が、孤独感をやわらげてくれます。
定期的な集まりやオンラインミーティング、SNSコミュニティなど様々な活動形態があり、ご家庭の状況に合わせて参加方法を選ぶことができます。
「自分だけじゃない」と感じることが、気持ちの支えとなります。
勇気を出して一歩踏み出し、同じ悩みを共有できる仲間を見つけてください。
地域の子ども・家庭相談センターや専門クリニック
- 自治体運営の相談センターや児童精神科・心療内科を活用
- 専門家による心理・医療サポートが受けられる
- 早めの相談で心身両面のケアができる
市区町村が運営する「子ども・家庭相談センター」や、児童精神科・心療内科などの専門クリニックでは、不登校や親子関係の悩みに対して、専門家のカウンセリングや医療サポートを受けることができます。
心理面だけでなく、身体的な健康状態や発達チェックなど幅広い支援も提供しています。
早めの相談で、深刻化する前に適切なケアを受けられるのが大きなメリットです。
医療や福祉の専門家と連携し、家庭全体で支援を受けることが心の安定にもつながります。
子どもの様子が長引く場合や、対応に迷うときは、ためらわず専門機関を利用しましょう。
民間カウンセリング・ピアサポートサービス
- 民間のカウンセラーやピアサポートも選択肢
- 家庭のニーズに合った相談・共感が得られる
- 相談自体が前向きな行動となる
公的機関だけでなく、民間のカウンセリングルームやピアサポートサービスも増えています。
心理カウンセラーや経験豊富なスタッフによる個別相談・電話・オンライン相談など、家庭のニーズに合ったサポートが受けられます。
第三者の立場からアドバイスを受けたり、同じ経験をした人から共感を得ることで、気持ちが軽くなり、前向きな行動につなげやすくなります。
「話すことで気づく自分の気持ち」や「寄り添い合える安心感」が得られます。
相談すること自体が大きな一歩です。
気軽に利用できる窓口を探してみてください。
不登校と母親の関係でよくある質問と回答まとめ
不登校と母親の関係について、よく寄せられる疑問や悩みをQ&A形式でまとめました。
専門家の見解や経験者の声も交えながら、わかりやすくお答えします。
「ひとりで悩まない」「どんな不安も相談してOK」という気持ちを大切にしましょう。
「不登校は母親のせい?」に専門家はどう答えるか
- 専門家は「一人の責任ではない」と明言
- 家庭だけでなく複数の要因が重なっている
- 必要以上に自分を責めず広い視点で対策を考える
多くの専門家は、「不登校を一人の責任にすることはできない」と明言しています。
不登校は学校環境や本人の性格・体調・社会的要因など、様々な要素が影響して起こるものです。
文部科学省の調査でも、家庭だけでなく複数の要因が重なった結果として不登校になることが分かっています。
「母親だけが原因」という考えは間違いです。
必要以上に自分を責めず、広い視点で原因や対策を考えていきましょう。
母親のメンタルが不登校に影響すると言われた時の対応
- 母親が完璧である必要はない
- 無理せず第三者に相談や休息をとることも大切
- 母親自身も助けを求めてよい
「お母さんが元気がないと子どもも不安になる」と言われることがありますが、完璧である必要はありません。
母親が疲れている時や落ち込んでいる時は、無理に明るくふるまうよりも、家族や友人、第三者に相談して自分の気持ちを整えることが大切です。
子どもは「お母さんが自分のために努力してくれている」と感じられれば安心します。
母親自身も助けを求めてよいという意識が、結果的に家族全体を支える力となります。
ひとりで頑張りすぎず、つらい時は休息やサポートを受け入れてください。
父親や家族の役割はどう考えるべきか
- 母親だけで抱え込まず、家族全体で協力を
- 役割分担やお互いの気持ちの理解が大切
- 家族みんなで支える姿勢が子どもの回復を助ける
不登校への対応は母親だけで抱え込まず、父親や家族全体で協力することが重要です。
家族で役割分担したり、お互いの気持ちを理解し合うことで、子どもへのサポートがより効果的になります。
家族みんなが「味方だよ」という姿勢で見守ることで、子どもは自分のペースで回復しやすくなります。
父親や祖父母も積極的に関わり、家族みんなで支える体制が理想です。
家族全体で前向きな雰囲気づくりを心がけてください。
不登校の原因が母親かもしれないと悩む方へまとめ
- ・不登校は学校や社会、家庭、本人のさまざまな要因が複雑に絡む
- ・「母親だけが原因」と決めつける必要はない
- ・子どもの気持ちに寄り添い、家族や第三者と一緒に支えることが大切
- ・母親自身も自分を大切にし、悩みは周囲に相談する
- ・小さな一歩から始めていけば、新しい未来へ歩き出せる
不登校の背景には、家庭だけでなく学校や社会、本人の個性など多くの要因が複雑に絡み合っています。
「母親だけが原因」と決めつけて自分を責める必要はありません。
大切なのは、お子さまの気持ちに寄り添い、家族みんなで支え合いながら回復への道筋を一緒に探していくことです。
学校や第三者機関、信頼できる家庭教師サービスなどを活用すれば、親子だけで抱え込まず、前向きな一歩を踏み出すことができます。
母親自身も「自分を大切にする」ことを忘れないでください。
悩みを誰かに話すことで気持ちが整理され、新たなヒントや安心が得られます。
あなたとお子さまは、必ず新しい未来に向かって歩き出せます。
「できること」から一つずつ始めていくことで、小さな変化が大きな自信へと変わっていきます。
ご家庭が再び笑顔で満たされるよう、この記事が少しでも力になれば幸いです。