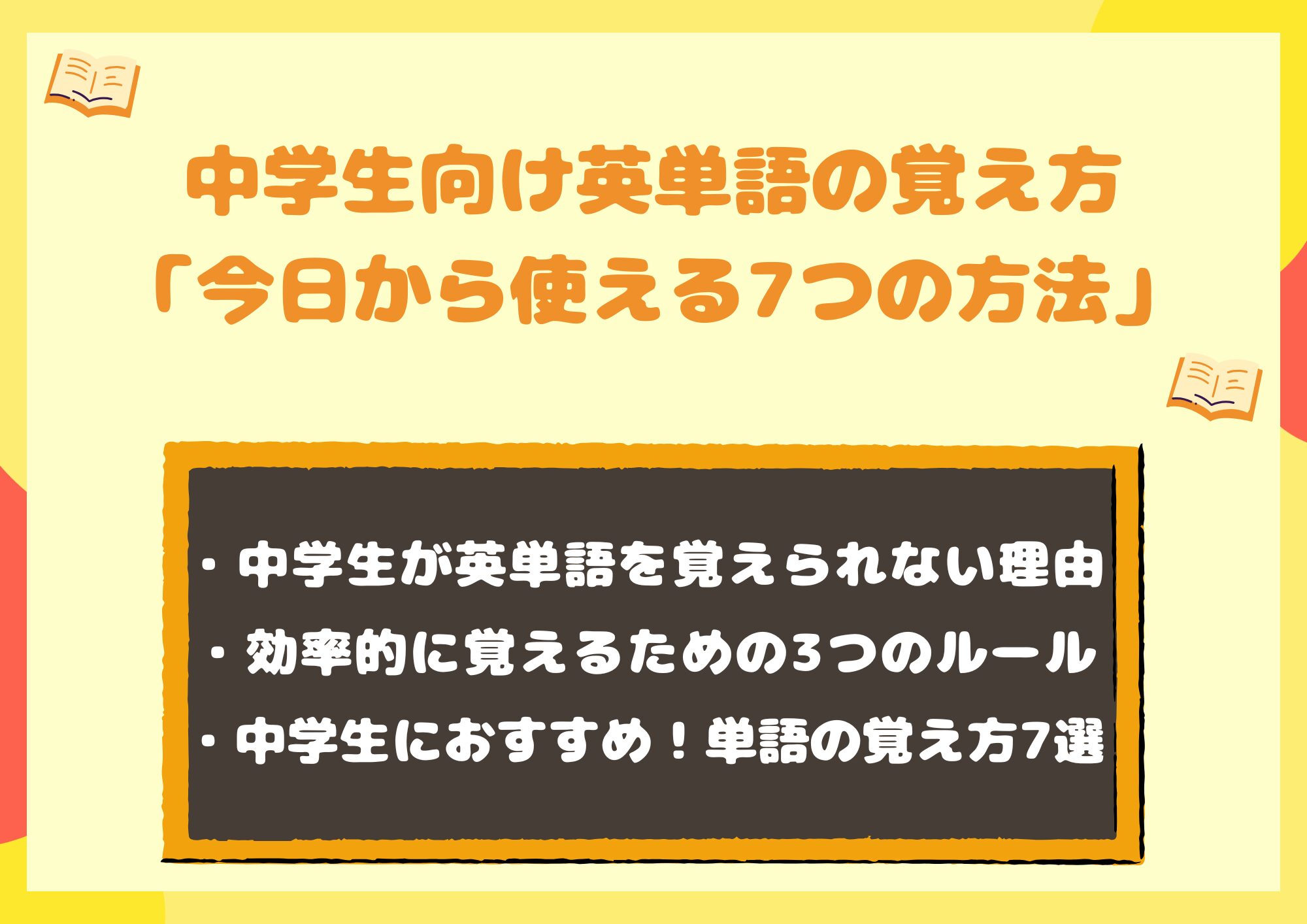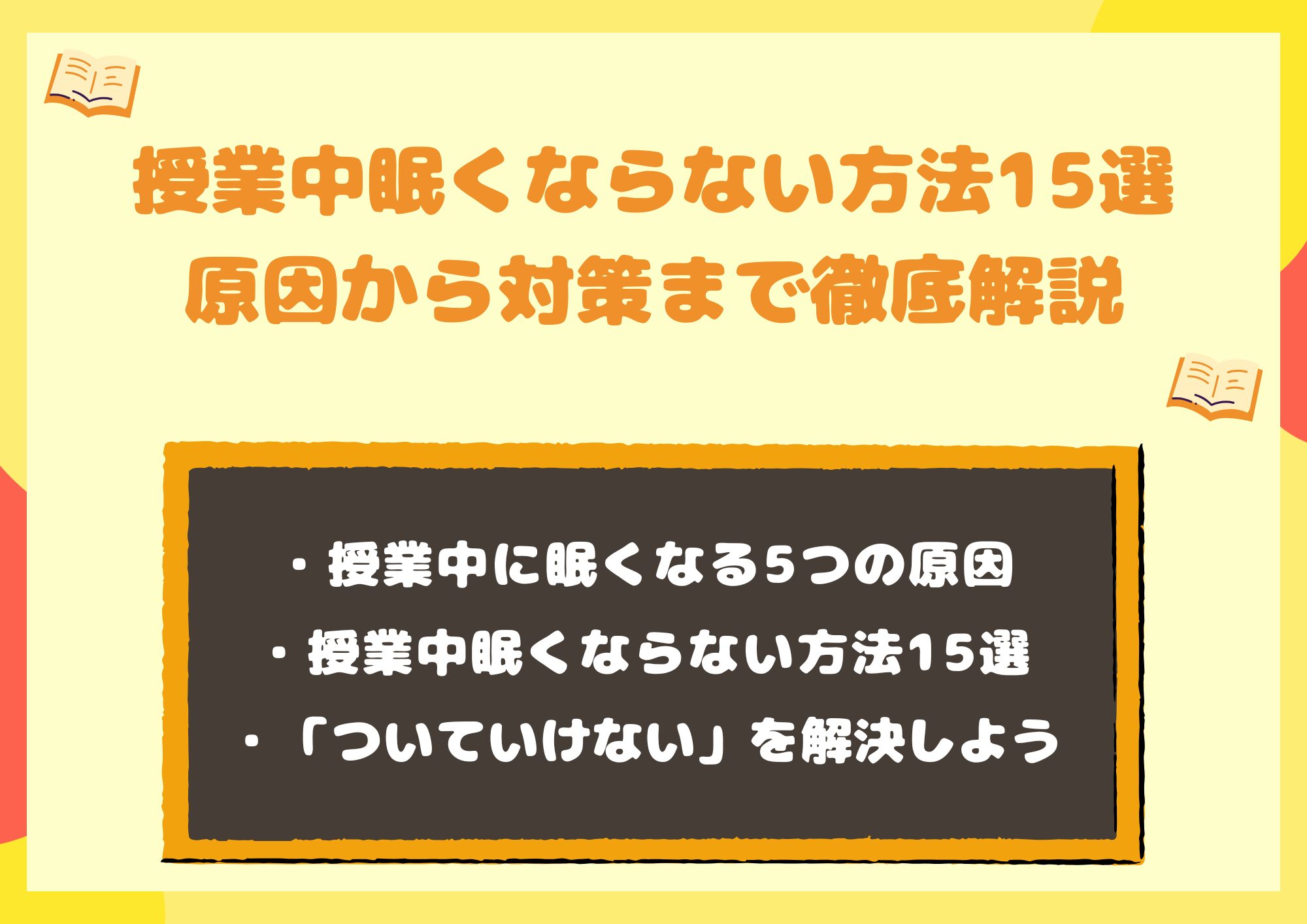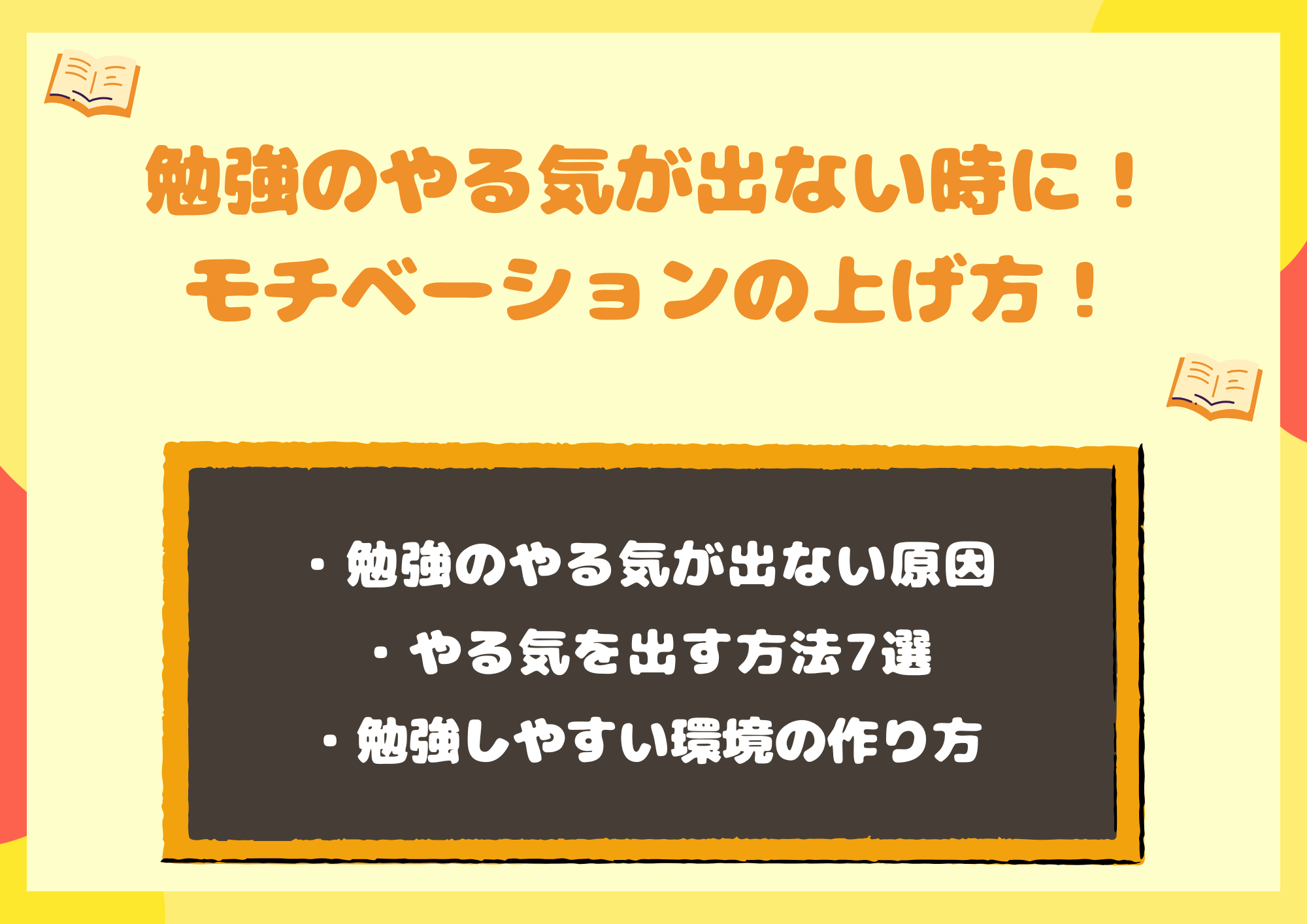- 勉強法
自主学習ネタ|小3〜中1まで学年別・教科別おすすめテーマ集
2025.10.28
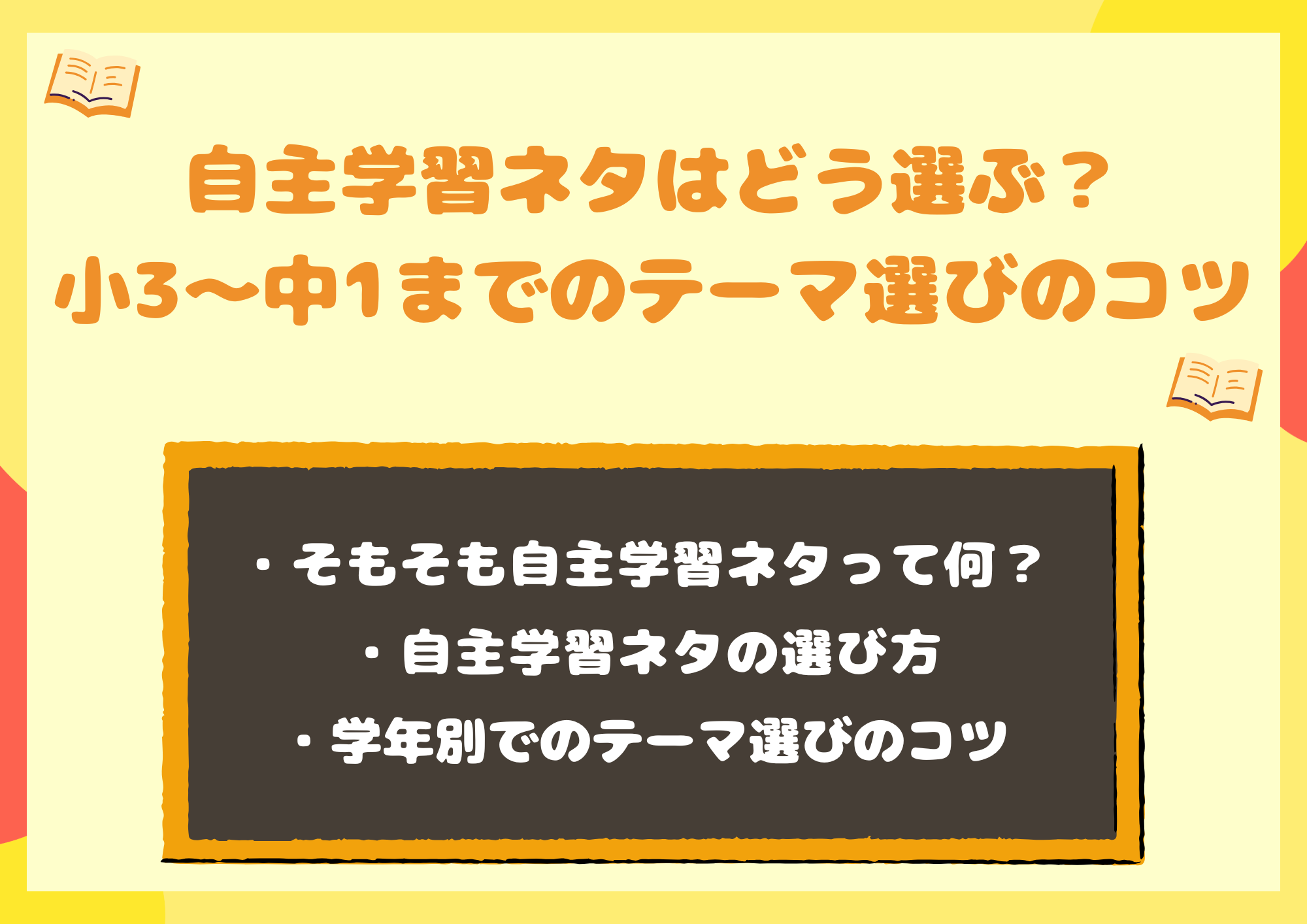
「自主学習って何を書けばいいの?」と、お子さんが毎日のように悩んでいる姿を見たことはありませんか。
宿題とは違って自分でテーマを決める自主学習は、子どもの主体性を育てる大切な学びの時間です。でも、毎日ネタを考えるのは大人でも大変ですよね。
この記事では、小学3年生から中学1年生まで、学年別におすすめの自主学習ネタをたっぷりご紹介します。小学生向けの記事が多い中、中学1年生までカバーしているので、幅広い学年のお子さんに役立てていただけますよ。
テーマ選びのコツや続けるための工夫もお伝えしますので、お子さんが「これやってみたい!」と思えるアイデアがきっと見つかります。
目次
そもそも自主学習ネタって何?宿題とは違うの?
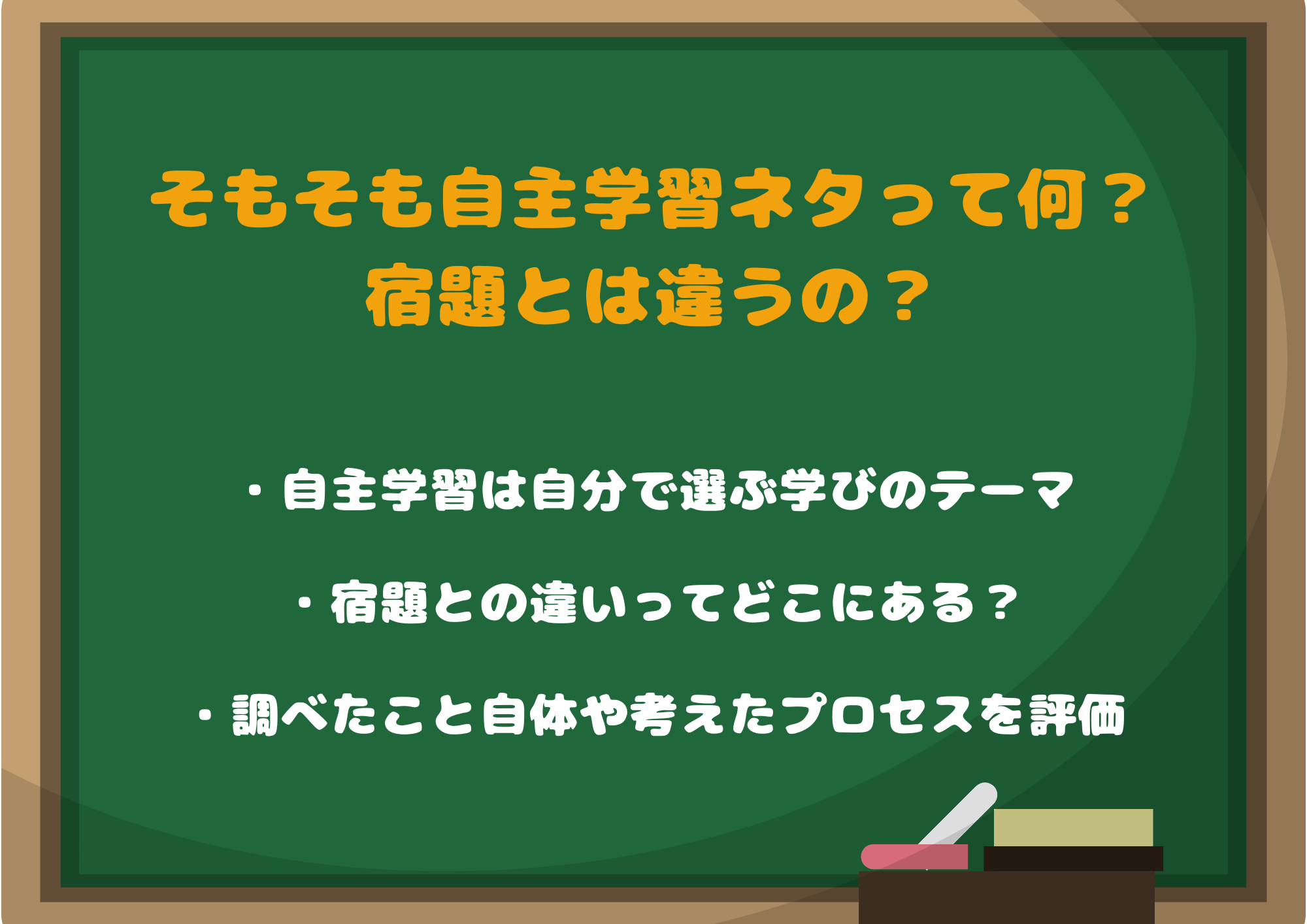
- 自主学習は自分でテーマを選ぶ学習活動
- 宿題との違いは「自分で決める」という主体性
自主学習という言葉はよく耳にしますが、普段の宿題とどう違うのか、はっきりしないという方も多いかもしれません。
実は、自主学習には子どもの成長にとって大切な意味があるんです。ここでは、自主学習の基本的な考え方と宿題との違いを見ていきましょう。
自主学習は自分で選ぶ学びのテーマ
- 興味や関心に基づいてテーマを選ぶ
- 「自分で選ぶ」プロセスが主体性を育てる
自主学習とは、子ども自身が興味や関心に基づいて学習テーマを選び、自分のペースで取り組む学習活動のことです。
先生から「このページをやりなさい」と指定されるのではなく、「今日は何を勉強しようかな」と自分で考えて決めるところから始まります。好きな昆虫について調べる、算数の苦手な単元を復習する、ニュースで気になった出来事を掘り下げるなど、テーマは自由です。
この「自分で選ぶ」というプロセスが、子どもの主体性や考える力を育てる大切なポイントになります。
宿題との違いってどこにある?
- 宿題は全員同じ、自主学習は一人ひとり違う
- 探究のプロセスそのものが評価される
宿題は先生が授業内容の定着を目的として出す課題で、全員が同じ内容に取り組むことが多いですよね。
一方、自主学習は一人ひとりが違うテーマで学ぶため、クラスメイトと同じである必要はありません。宿題が「やらなければならないもの」であるのに対し、自主学習は「自分がやりたいと思ったもの」という違いがあります。
また、調べたこと自体や考えたプロセスが評価されるのも特徴です。答えが一つではない探究型の学びができるのが自主学習の魅力と言えるでしょう。
自主学習ネタの選び方|迷ったときのヒント
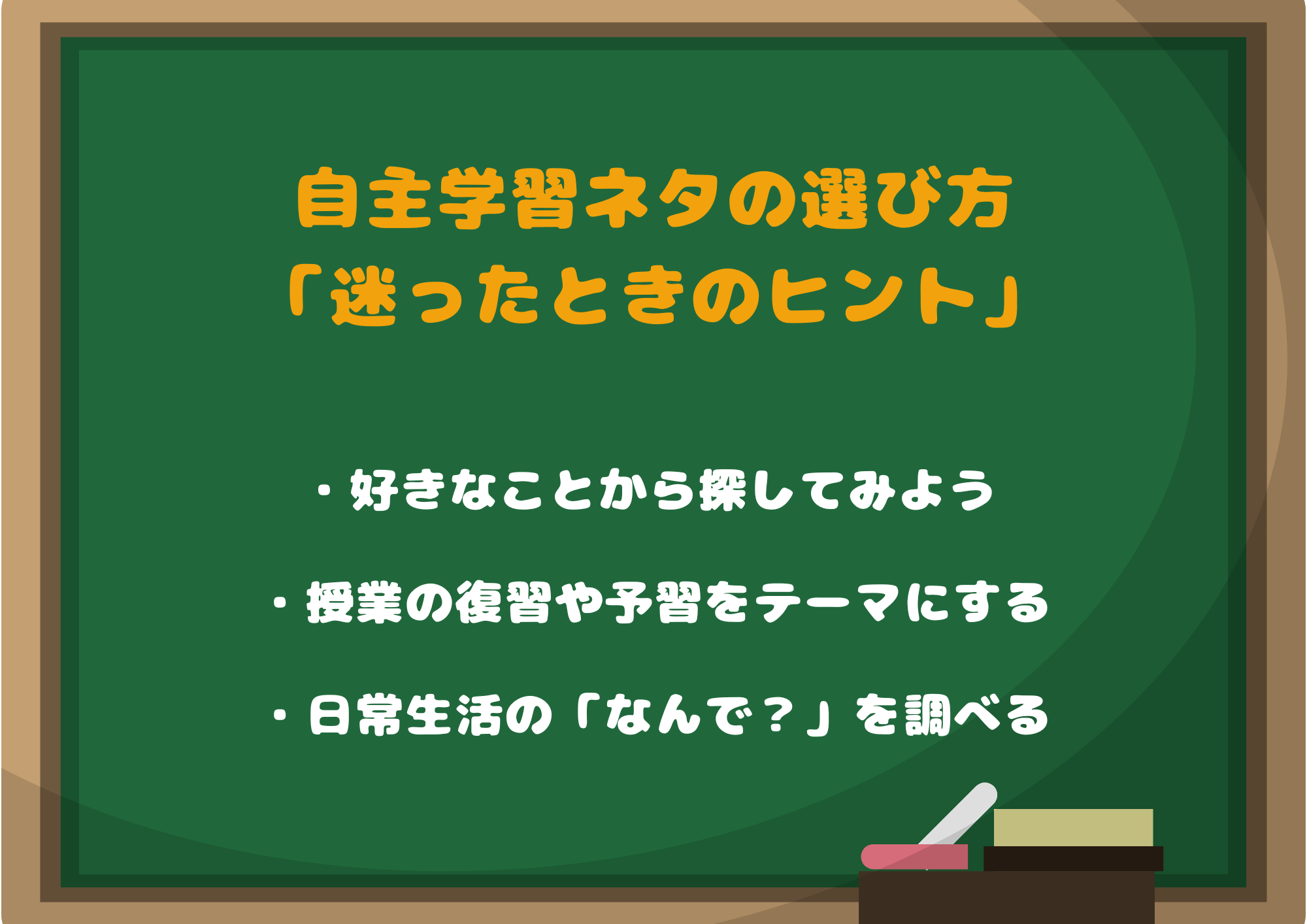
- 好きなこと・授業内容・日常の疑問から探す
- ワクワク系とバッチリ系のバランスが大切
「自由に選んでいい」と言われると、かえって何を選べばいいか分からなくなってしまうこともありますよね。
ここでは、自主学習のテーマを見つけるための具体的なヒントをご紹介します。お子さんと一緒に考えてみてください。
好きなことから探してみよう
- 興味のあることなら続けやすい
- 趣味や習い事に関連したテーマがおすすめ
一番続けやすいのは、やはり自分が好きなことや興味のあることをテーマにすることです。
恐竜が好きなら恐竜の種類や特徴を調べる、サッカーが好きならルールや有名選手について学ぶといった具合です。趣味や習い事に関連したテーマなら、すでに知識があるので調べるのも楽しくなります。
好きなことだからこそ、もっと深く知りたいという気持ちが自然に湧いてくるんです。
授業の復習や予習をテーマにする
- 授業内容の復習で理解が深まる
- テスト対策にも効果的
学校の授業で習ったことを自主学習で復習すると、理解がさらに深まります。
授業で「もっと知りたい」と思ったことを掘り下げたり、次の単元を先取りして予習したりするのも効果的です。特にテストの前には、苦手な単元を自主学習でしっかり練習すると成績アップにつながります。
授業内容と結びついているため、先生からも評価されやすいメリットもあります。
日常生活の「なんで?」を調べる
- 日常の疑問は素晴らしい学習ネタになる
- 観察力や疑問を持つ力が育つ
日常の中で感じた疑問や「なんでだろう?」という気持ちは、自主学習の素晴らしいネタになります。
「なぜ空は青いの?」「冬になると静電気が起きるのはなぜ?」といった身近な不思議を調べてみましょう。自分の生活と結びついた学びは、「勉強」という感覚が薄れて自然に探究できます。
観察力や疑問を持つ力も同時に育つため、一石二鳥の効果があります。
ワクワク系とバッチリ系のバランスを意識しよう
- ワクワク系:趣味や好奇心から生まれるテーマ
- バッチリ系:教科の力を伸ばすテーマ
- 両方をバランスよく取り入れると効果的
自主学習のテーマには、大きく分けて「ワクワク系」と「バッチリ系」の2つのタイプがあります。
ワクワク系は趣味や好奇心から生まれるテーマです。好きなスポーツのルールを調べる、ニュースで気になった話題を深掘りする、物語を創作するといった活動が当てはまります。楽しみながら取り組めるので、学ぶ意欲が自然に高まります。
バッチリ系は教科の力をしっかり伸ばすテーマです。授業の復習、計算練習、漢字の書き取り、間違い直しノートの作成などが該当します。学業成績の向上に直結するのが特徴です。
どちらか一方だけに偏るのではなく、両方をバランスよく取り入れると学習効果が高まります。今週はワクワク系で好きなことを深掘りし、来週はバッチリ系で算数の復習をするという具合に、交互に取り組んでみてください。
小学3年生向けの自主学習ネタ|簡単で楽しいテーマ集
- 「楽しい」「できた」という達成感を大切に
- 取り組みやすいテーマから始めよう
小学3年生は、自主学習を始めたばかりという子も多い時期です。
まずは「楽しい」「できた」という達成感を味わえる、取り組みやすいテーマから始めることが大切です。私たちランナーの小学生コースでも、お子さんの興味に合わせたテーマ選びをサポートしています。
国語|漢字や言葉遊びで楽しく学ぶ
- 漢字を使った短文作りやしりとり
- 辞書で面白い言葉を集める
3年生では新しい漢字をたくさん習うので、漢字練習は定番のテーマになります。
ただ書くだけでなく、習った漢字を使って短い文を作ったり、しりとりや言葉集めをしたりすると楽しくなります。好きな物語の感想を書く、詩を作ってみるといった創作活動もおすすめです。
辞書で見つけた面白い言葉を集めるのも、語彙力が自然に増えていきます。
算数|計算練習や図形の工作
- 九九の定着や時計の読み方
- 折り紙で図形を作る工作
3年生の算数では、かけ算の九九の定着や時計の読み方などが重要なテーマです。
計算ドリルを自主学習ノートに解いて丸つけまでするのは、基礎力をつける王道の方法と言えます。図形の勉強なら、折り紙で三角形や四角形を作ったり、身の回りの図形を探して描いたりするのも楽しいですよ。
理科|身近な生き物や植物の観察
- 昆虫や植物の観察とスケッチ
- 天気の変化や影の長さを記録
3年生の理科では、昆虫や植物の観察が中心になります。
庭や公園で見つけた生き物をスケッチして特徴を書き込む、育てている植物の成長を記録するといったテーマが取り組みやすいです。天気の変化を毎日記録する、影の長さを測って太陽の動きを調べるのも立派な観察になります。
社会|地域のお店や施設を調べる
- 近所のお店を地図にまとめる
- 地域の特産品や有名な場所を調べる
3年生の社会では、自分たちの住む地域について学びます。
近所のスーパーやコンビニがどこにあるか地図にまとめる、図書館や公民館の役割を調べるといったテーマが身近です。自分が住む町の特産品や有名な場所を調べると、地元への愛着も深まるでしょう。
工作・絵|好きなものを作ったり描いたり
- 好きなキャラクターを描く
- 作ったものについて説明を書く
勉強という形にこだわらず、好きなものを自由に表現するのも立派な自主学習です。
好きなキャラクターを描く、折り紙で作品を作る、段ボールで工作するといった活動は創造力を育てます。作ったものについて「どうやって作ったか」「工夫した点」を文章で説明すると、表現力も同時に磨かれます。
小学4年生向けの自主学習ネタ|ちょっと深掘りできるテーマ
- 調べ学習の幅が広がる時期
- 深く考えたり詳しく調べたりする力がつく
4年生になると、学習内容が少しずつ難しくなり、調べ学習の幅も広がります。
3年生のときよりも深く考えたり、詳しく調べたりする力がついてくる時期です。ここでは、4年生らしい探究心を活かせるテーマをご紹介します。
国語|慣用句やことわざを集めてみよう
- 慣用句やことわざを集めて意味を調べる
- 気に入った表現を使って文章を作る
4年生では慣用句やことわざを習うので、それらを集めて意味を調べるのは効果的な学習になります。
「犬も歩けば棒に当たる」「猫の手も借りたい」など、動物が出てくることわざを集めるといったテーマ設定も楽しいです。気に入った慣用句を使って短い文章を作ったり、イラストを添えたりすると記憶に残りやすくなります。
算数|図形や単位換算の練習
- 面積の計算や角度の測定
- 単位換算の問題を自分で作る
4年生の算数では、面積の計算や角度の測定など、図形の学習が本格的になります。
身の回りにある長方形や正方形の面積を実際に測って計算する、角度を分度器で測る練習をするのは実践的です。単位換算(kmとm、LとmLなど)の問題を自分で作って解くのも、理解が深まる方法です。
理科|月の満ち欠けや星座を調べる
- 月の形を記録して満ち欠けの周期を調べる
- 季節の星座を探して観察する
4年生の理科では、月や星といった天体の学習が始まります。
夜空を観察して月の形を記録し、満ち欠けの周期を調べるのは継続的な観察テーマとして最適です。季節の星座について調べて、実際に見つけられるか挑戦してみるのも楽しい体験になります。
社会|都道府県の特産品マップを作る
- 日本地図に各都道府県の特産品を書き込む
- ゴミ処理や水道の仕組みを調べる
4年生の社会では、都道府県の名前や位置を学びます。
日本地図を書いて、各都道府県の特産品やグルメを調べて書き込むと、楽しみながら地理が覚えられます。ゴミの処理方法や水道の仕組みなど、暮らしを支える仕組みを調べるのも社会科らしい探究になります。
趣味・特技|好きなことを深く調べる
- 好きなスポーツのルールを詳しくまとめる
- 料理のレシピをまとめる
4年生くらいになると、自分の趣味や特技について深く調べる力がついてきます。
好きなスポーツのルールを詳しくまとめる、好きな歌手やアーティストについて調べるといったテーマは意欲的に取り組めます。ゲームが好きならそのゲームの歴史を調べるのも立派な学習です。
小学5年生向けの自主学習ネタ|探究心を育てるテーマ
- 「なぜそうなるのか」を考える力を伸ばす
- 自分の意見をまとめる練習も
5年生は高学年として、より深い思考力や応用力が求められる時期です。
単に知識を覚えるだけでなく、「なぜそうなるのか」を考えたり、自分の意見をまとめたりする力を伸ばすチャンスなんです。ここでは、探究心を刺激するテーマをご紹介します。
国語|作文や物語創作に挑戦
- 読んだ本の感想をしっかり書く
- 新聞記事を要約して意見を加える
5年生になると、文章を書く力がかなり成長します。
読んだ本の感想をしっかり書く、架空の物語を創作する、「もし〇〇だったら」というテーマで作文するのは表現力を磨く良い練習です。敬語の使い方を整理する、文章の構成を意識してまとめる練習も効果的です。
算数|図形の面積や体積を実際に測ってみる
- 三角形や台形の面積を計算する
- 速さや割合の文章題を図や表でまとめる
5年生の算数では、三角形や台形の面積、立体の体積などを学びます。
教科書の公式を覚えるだけでなく、実際に身の回りのものを測って計算してみると理解が深まります。速さや割合といった文章題の解き方を、図や表を使って分かりやすくまとめるのも力がつく方法です。
理科|実験の記録や仮説を立てる
- 実験を詳しく記録して考察する
- 仮説を立てて家でできる実験をする
5年生の理科では、実験や観察をもとに考察する力が求められます。
学校で行った実験を自主学習ノートに詳しく記録し、「なぜそうなったか」を自分なりに考えて書くと学びが深まります。「もし条件を変えたらどうなるか」という仮説を立てて、家でできる簡単な実験をしてみるのも科学的思考が育ちます。
社会|歴史上の人物を調べて年表作成
- 興味のある歴史上の人物を調べる
- 調べたことを年表形式でまとめる
5年生の社会では、日本の歴史を学び始めます。
興味のある歴史上の人物(織田信長、卑弥呼、聖徳太子など)を選んで、その生涯や功績を調べるのは定番のテーマです。調べたことを年表形式でまとめると、時代の流れが視覚的に分かりやすくなります。
英語|好きな洋楽の歌詞を和訳してみる
- 好きな洋楽の歌詞を和訳する
- 身の回りの英単語を集めて単語帳を作る
5年生から英語が教科として本格的に始まります。
教科書の単語や表現を繰り返し書いて練習するのは基本ですが、好きな洋楽の歌詞を和訳してみるのは楽しい応用です。身の回りの英単語を集めてイラスト付きの単語帳を作る、簡単な英文日記を書いてみるといった工夫も続けやすいです。
小学6年生向けの自主学習ネタ|中学への準備にもなるテーマ
- 小学校の集大成と中学準備を両立
- 総まとめしながら先を見据える
6年生は小学校の集大成であり、中学進学を控えた大切な時期です。
これまで学んだことの総まとめをしつつ、中学での学習にもつながる内容に取り組むと効果的です。ここでは、小学校の仕上げと中学準備の両方に役立つテーマをご紹介します。
国語|読書感想文や要約の練習
- 読書感想文をじっくり書く
- 新聞記事を読んで要点をまとめる
6年生の国語では、長い文章を読み取り、要約したり自分の考えをまとめたりする力が重要になります。
読書感想文をじっくり書く、新聞記事を読んで要点を短くまとめる練習は中学でも役立つスキルです。四字熟語や故事成語を集めて使い方を確認すると、語彙の幅が広がり表現力も豊かになります。
算数|比や速さの文章題を解く
- 比や速さの文章題を繰り返し解く
- 小学校で習った計算を総復習する
6年生の算数では、比や速さ、場合の数など、中学数学につながる重要な単元を学びます。
これらの文章題は苦手な子も多いため、自主学習で繰り返し解く練習をすると理解が深まります。小学校で習った計算(分数、小数、割合など)を総復習するのも、中学に向けた土台作りになります。
理科|電気や磁石の仕組みを調べる
- 電池と豆電球の回路を図でまとめる
- 人体の仕組みを図鑑で調べる
6年生の理科では、電気の働きや磁石の性質など、物理分野の学習が増えます。
電池と豆電球を使った回路を図でまとめる、磁石の極と力の関係を実験してまとめるといったテーマは探究的です。身近な科学現象(虹の仕組み、音の伝わり方など)を調べると、理科への興味がさらに深まるでしょう。
社会|日本の歴史や政治の仕組み
- 日本の歴史を時代ごとに整理して年表を作る
- 国会の仕組みや選挙制度について調べる
6年生の社会では、歴史の総復習と政治の仕組みについて学びます。
日本の歴史を時代ごとに整理して年表を作る、歴史的な出来事の原因と結果を考察するのは理解を深める良い方法です。国会の仕組みや選挙制度について調べる、憲法の三大原則をまとめるといったテーマは中学の公民につながります。
SDGs|地域の課題と結びつけて考える
- 17の目標から興味のあるものを選んで調べる
- 自分にできることを考えて実践する
近年注目されているSDGs(持続可能な開発目標)は、6年生が取り組むのにふさわしいテーマです。
17の目標の中から興味のあるものを選び、その内容と重要性を調べてまとめることができます。自分の住む地域の環境問題やゴミ問題を調べて、SDGsの目標と結びつけて考えると探究が深まります。
中学1年生向けの自主学習ネタ|部活と両立できるテーマ
- 短時間でも効率よく学習できるテーマを選ぶ
- 定期テスト対策にもなる内容を意識
中学1年生になると、部活動や定期テストが始まり、生活リズムが大きく変わります。
忙しい中でも効率よく学習できるテーマを選ぶことが大切です。小学生向けの記事が多い中、この記事では中学1年生まで対応していますので、ぜひ参考にしてください。
国語|古典の音読や文法の復習
- 古典文を繰り返し音読する
- 文法事項を整理する
中学の国語では、古典(古文・漢文)が新しく加わります。
教科書の古典文を繰り返し音読して、現代語訳と照らし合わせる練習は基礎固めに効果的です。文法事項(動詞の活用、助詞、助動詞など)をまとめて整理するのも力がつきます。
漢字の練習や語彙を増やす取り組みは、定期テストの得点アップに直結します。
数学|方程式の解き方パターン整理
- 方程式の解き方をパターン別に整理する
- 間違えた問題を集めた「ミスノート」を作る
中1の数学では、文字式や方程式といった新しい概念を学びます。
方程式の解き方を問題のパターン別に整理してまとめると、テスト前の見直しに便利です。計算ミスをしやすいポイントを書き出す、間違えた問題を集めた「ミスノート」を作るのも実践的な学習法になります。
「中学生の勉強方法とサポート」の記事も参考にしてみてください。
理科|実験レポートの書き方を練習
- 目的・方法・結果・考察の形式でまとめる
- 元素記号や化学式を覚える
中学の理科では、実験とその考察が重要になります。
授業で行った実験を自主学習ノートに詳しく記録し、目的・方法・結果・考察という形式でまとめる練習をすると力がつきます。元素記号や化学式を覚える、生物の分類を整理するといった基礎的な暗記も継続して取り組みたい内容です。
社会|地理や歴史の用語まとめ
- 世界の国々を地図にまとめる
- 重要な用語を整理してまとめる
中1の社会では、地理分野を中心に学習します。
世界の国々の位置や気候、産業などを地図にまとめる、重要な用語を整理してまとめるのは定期テスト対策として効果的です。時事問題にも目を向け、ニュースで取り上げられた出来事を調べてまとめるのも社会への関心を深める良い習慣です。
英語|教科書の本文を暗唱してみる
- 教科書の本文を繰り返し音読して暗唱する
- 新出単語を例文とともにまとめる
中学の英語では、文法事項が増え、長い文章も読むようになります。
教科書の本文を繰り返し音読して暗唱できるまで練習すると、文法も単語も自然に身につきます。新出単語を例文とともにまとめる、英作文の練習をするといった取り組みも力になります。
私たちランナーの中学生コースでは、部活と勉強の両立もサポートしています。「中学生の家庭学習」の記事もぜひご覧ください。
自主学習ノートのまとめ方|見やすく楽しいノート作り
- 見出しや日付で整理する
- 色分けは3色まで、自分の言葉でまとめる
せっかく調べたり考えたりしても、ノートがごちゃごちゃしていると後で見返したときに分かりにくいですよね。
自主学習ノートを見やすく、そして楽しく作るコツをご紹介します。
見出しや日付で整理しよう
- 日付とテーマの見出しを必ず書く
- ページ番号を振ると整理しやすい
ノートの各ページには、必ず日付とテーマの見出しを書きましょう。
これがあるだけで、後から見返したときに「いつ、何を学んだか」がすぐに分かります。見出しは少し大きめの字で、色を変えたり下線を引いたりすると目立って探しやすくなります。
ページ番号を振っておくと、さらに整理しやすくなり、目次を作ることもできるんです。
色分けは3色までがおすすめ
- 使う色は3色程度に絞る
- それぞれの色に役割を決めておく
カラフルなノートは楽しいですが、色を使いすぎるとかえって見にくくなってしまいます。
使う色は3色程度に絞り、それぞれの色に役割を決めておくと効果的です。たとえば、赤は重要なキーワード、青は説明や補足、緑は自分の考えや疑問といった具合です。
色のルールを決めておくと、復習するときにポイントがパッと目に入ります。
図やイラストで分かりやすく
- 図や表、イラストを使うと分かりやすい
- 視覚的な情報は記憶に残りやすい
文章だけでなく、図や表、イラストを使うとノートがぐっと分かりやすくなります。
関係性を示すなら矢印や図、情報を比較するなら表が適しています。絵が得意でなくても、簡単なイラストや記号を添えるだけで記憶に残りやすくなります。
視覚的な情報は脳に強く印象づけられるため、学習効果を高める強力な武器になります。
自分の言葉でまとめるのが大事
- 教科書をそのまま写すのではなく自分の言葉で
- 自分のコメントを加えると理解が深まる
教科書や参考書をそのまま写すのではなく、自分の言葉で言い換えてまとめることが最も重要です。
情報を自分なりに理解して再構成するプロセスこそが、本当の学びにつながります。「つまり〇〇ということ」「これは△△と似ている」といった自分のコメントを加えると、理解が深まります。
自主学習を続けるコツって?モチベーションの保ち方
- 時間と場所を決めて習慣化する
- 小さな目標と変化で飽きない工夫を
自主学習を始めたものの、だんだん飽きてきたり面倒になったりすることは誰にでもあります。
続けるためには、ちょっとした工夫やコツが必要です。お子さんがなかなか勉強に向かえないときは、「子どもが勉強しない」の記事も参考にしてみてください。
学習時間と場所を決めておく
- 毎日同じ時間に自主学習をすると習慣になる
- 集中を妨げるものは見えないところに
「今日はいつやろうかな」と毎日考えていると、結局やらないで終わってしまうことがあります。
夕食後の30分、お風呂の前の20分など、毎日同じ時間に自主学習をすると習慣になりやすいです。学習する場所も決めておくと、「この机に座ったら勉強モード」と脳が切り替わるようになります。
スマホやゲームなど、集中を妨げるものは見えないところに置いておくことも大切です。
小さな目標を設定して達成感を味わう
- 「毎日1ページ」など小さな目標を設定する
- 達成したらシールやチェックで「見える化」
「毎日1ページ」「1週間で3テーマ」といった小さな目標を設定すると、達成感が得やすくなります。
大きな目標だけだと遠すぎて挫折しやすいため、小さなステップに分けるのがコツです。達成したらカレンダーにシールを貼る、チェックリストに印をつけるといった「見える化」も効果的です。
テーマに変化をつけて飽きない工夫
- テーマにバリエーションをつける
- ワクワク系とバッチリ系を交互に
毎日同じような内容ばかりだと、どうしても飽きてしまいます。
今日は算数、明日は好きなことの調べ学習、次は理科の観察というように、テーマにバリエーションをつけましょう。ワクワク系とバッチリ系を交互に取り入れると、楽しさと学力向上の両方が手に入ります。
保護者や先生からの声かけが励みに
- 具体的に褒めてもらえると励みになる
- 努力や工夫したプロセスを認めてもらう
一人で黙々と続けるのは、大人でも難しいものです。
保護者や先生が「よく調べたね」「この図は分かりやすいね」と具体的に褒めてくれると、大きな励みになります。結果だけでなく、努力や工夫したプロセスを認めてもらえると、やる気がさらに高まります。
自主学習をサポートしてくれる家庭教師って?
- 一人ひとりに合わせた指導が魅力
- テーマ選びから丁寧にサポート
自主学習がなかなか続かない、テーマ選びが毎日大変…そんなお悩みには、専門家のサポートが力になることもあります。
特に、テーマ選びに悩んだり、学習方法が分からなかったりするときは、家庭教師のサポートがあると心強いです。勉強が苦手なお子さんへのアプローチについては「勉強が嫌いな子」の記事もご覧ください。
家庭教師が自主学習に役立つ理由
- 学力や性格に合わせた指導ができる
- ノートのまとめ方や調べ方のコツを教えてくれる
家庭教師は、子ども一人ひとりの学力や性格に合わせた指導をしてくれます。
自主学習のテーマ選びで迷っているときに、その子の興味や学習状況に応じた提案をしてくれるんです。また、ノートのまとめ方や調べ方のコツを教えてくれるため、自主学習の質が格段に上がります。
テーマ選びから一緒に考えてくれる
- 興味を引き出して学習テーマに結びつける
- テスト対策に直結するテーマを提案
「何をしたらいいか分からない」という悩みは、自主学習で最もよくある壁です。
家庭教師は、子どもとの対話を通じて興味のあることを引き出し、それを学習テーマに結びつけてくれます。苦手な単元を克服するための効果的な復習方法を一緒に考えたり、テスト対策に直結するテーマを提案したりもします。
自主学習サポートにおすすめの家庭教師サービス3選
- お子さんやご家庭の状況に合ったサービスを選ぶ
- それぞれの特徴を比較して検討
自主学習を効果的にサポートしてくれる家庭教師サービスは数多くありますが、ここでは特におすすめの3つをご紹介します。
家庭教師のランナー|勉強が苦手な子専門で安心

- 30,034人の指導実績、2024年第一志望合格率97.5%
- 小・中学生1コマ30分900円とリーズナブル
- 発達障害コミュニケーション指導者の資格保有者在籍
私たち家庭教師のランナーは、創業21年の実績を持つ、勉強が苦手な小中高生専門の家庭教師グループです。
これまで30,034人のお子さんを指導してきた私たちランナーは、一人ひとりの個性に合わせたオーダーメイド指導を行っています。2024年の第一志望合格率は97.5%という高い実績を誇ります。
料金は小・中学生で1コマ30分900円と非常にリーズナブルで、週1回60分なら月12,000~15,000円程度から利用可能です。兄弟や友達と2人同時に受けると、2人目以降の月々の料金が半額以下になるユニークな制度もあります。
発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフも在籍しており、お子さん一人ひとりに寄り添ったサポートが可能です。オンライン指導にも対応しており、全国どこからでも受講できます。
「わかる楽しさ」を感じてもらうことを大切にしており、自主学習のテーマ選びから丁寧にサポートしています。無料体験後の無理な勧誘は一切ありませんので、まずはお気軽にお試しください。
家庭教師ファースト|低価格で質の高い指導

- 小・中学生なら週1回60分で月約10,000円
- 入会金無料で気軽に始められる
- 実際に担当となる先生で無料体験できる
家庭教師ファーストは、全国展開する準大手の家庭教師センターです。
小・中学生なら週1回60分で月約10,000円、高校生でも月11,000円~と良心的な料金設定が魅力です。入会金も無料なので、気軽に始められます。
実際に担当となる先生で無料体験を行い、そのまま正式契約できるためミスマッチが少ないのが特徴です。オンライン指導にも対応しています。
学研の家庭教師|大手の安心感とノウハウ

- 教育大手「学研グループ」が運営
- 約12万人の教師が登録
- 大手の安心感とノウハウが充実
学研の家庭教師は、教育大手「学研グループ」が運営する家庭教師派遣サービスです。
約12万人の教師が登録されており、厳選された大学生からプロ講師まで幅広い人材から最適な教師を紹介してくれます。目安として指導料は1時間3,190円~で、週1回60分なら月約12,760円~利用できます。
高額教材の販売は行っていないため安心です。大手企業が培ったノウハウで、サポート体制が充実しています。
自主学習ネタについてまとめ
- ・自主学習は子どもが自分で考え、自分で学ぶ力を育てる学習活動
- ・好きなこと・授業内容・日常の疑問からテーマを探す
- ・ワクワク系とバッチリ系をバランスよく取り入れる
- ・ノートは見出しや色分けで整理し、自分の言葉でまとめる
- ・時間と場所を決める、小さな目標を設定することで継続できる
ここまで、小学3年生から中学1年生までの自主学習ネタを学年別にご紹介してきました。
自主学習は、子どもが自分で考え、自分で学ぶ力を育てる大切な学習活動です。宿題とは違い、テーマを自由に選べるからこそ、興味や好奇心を活かした深い学びができるんです。
テーマ選びのコツは、好きなことから探す、授業内容と結びつける、日常の疑問を調べるといった方法がありました。ワクワク系とバッチリ系をバランスよく取り入れることで、楽しさと学力向上の両方を実現できます。
続けるためには、学習時間と場所を決める、小さな目標を設定する、テーマに変化をつけるといった工夫が効果的です。もしテーマ選びや学習方法に悩んだら、家庭教師のサポートを受けるのも一つの方法ですね。
自主学習を通じて、お子さんが「自ら学ぶ楽しさ」を発見し、生涯にわたって学び続ける力を身につけていくことを願っています。