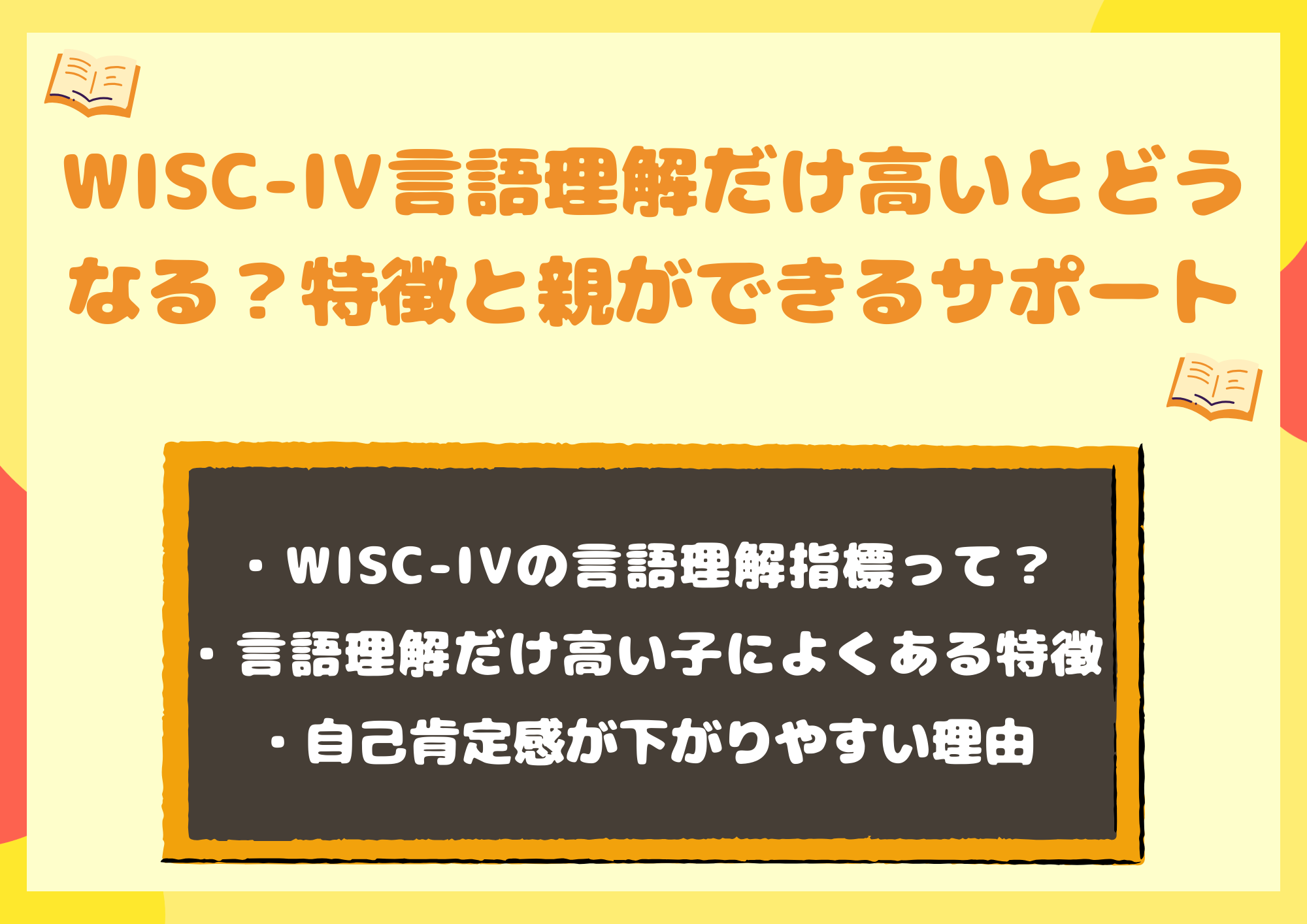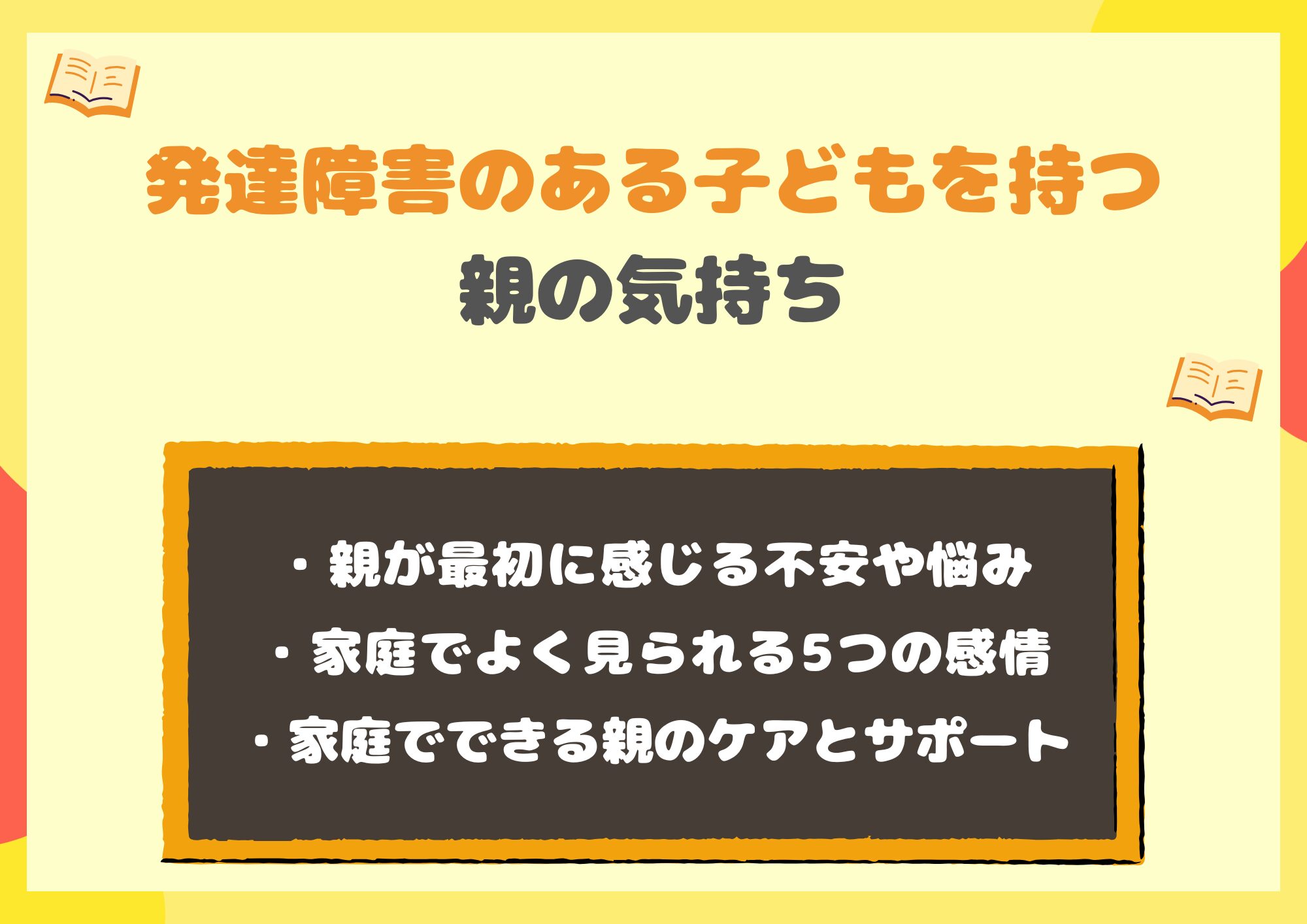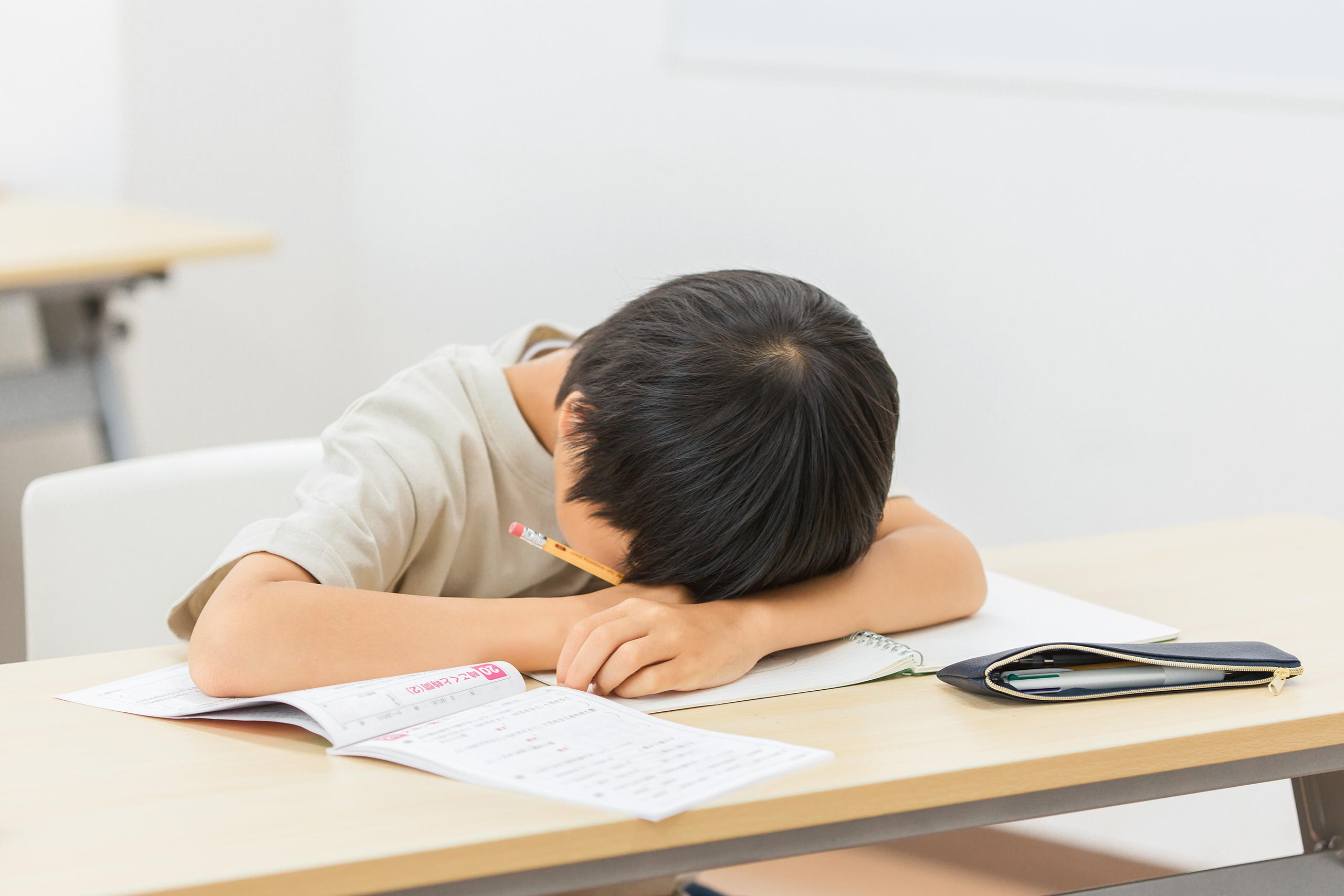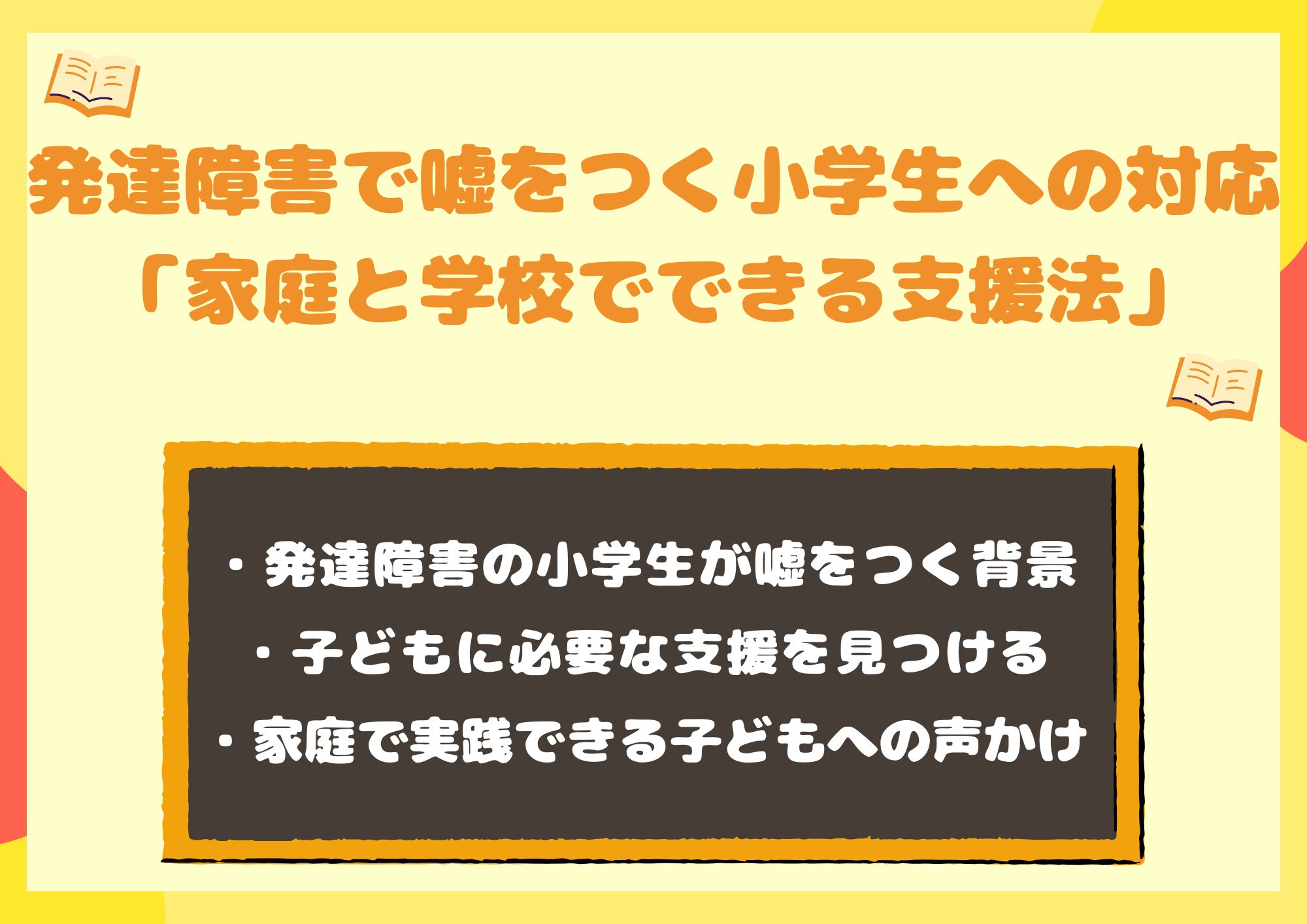- 発達障害向けの家庭教師
母子分離不安と発達障害の関係|原因と家庭でできる5つの対応法
2025.11.12
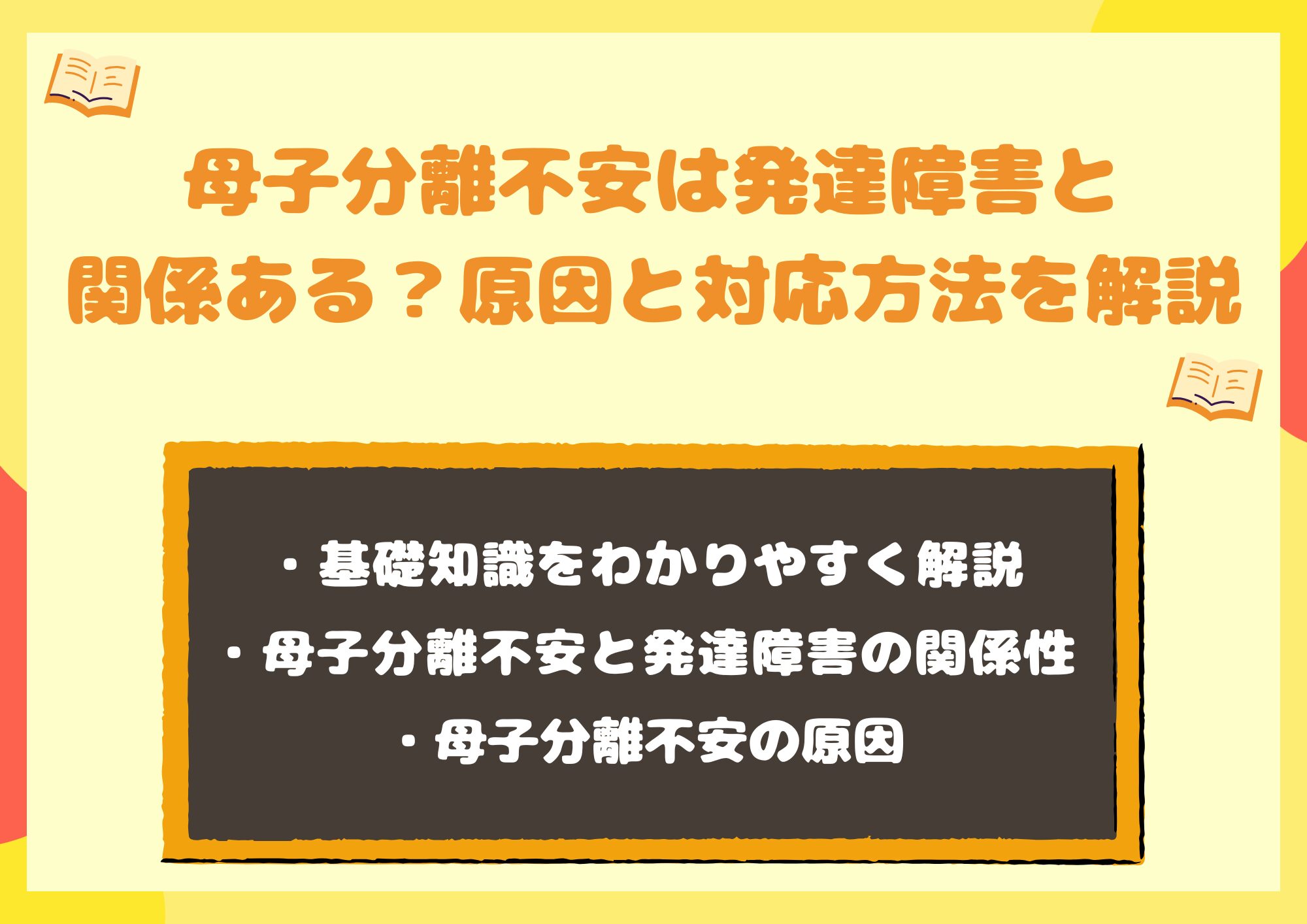
お子様が幼稚園や学校に行く時、泣き叫んで離れようとしない姿を見るのは、親として本当につらいものです。
「いつまで続くんだろう」「他の子は平気なのに、うちの子だけ」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
実はこの母子分離不安、発達障害と関係している場合があります。環境の変化への強い不安や感覚過敏といった特性が、分離不安を引き起こしている可能性があるんです。
でも安心してください。適切な理解と対応があれば、お子様も保護者の方も楽になる方法はたくさんあります。この記事では、母子分離不安と発達障害の関係から、家庭でできる対応方法、専門的な支援まで詳しくご紹介します。
目次
母子分離不安って何?基礎知識をわかりやすく解説
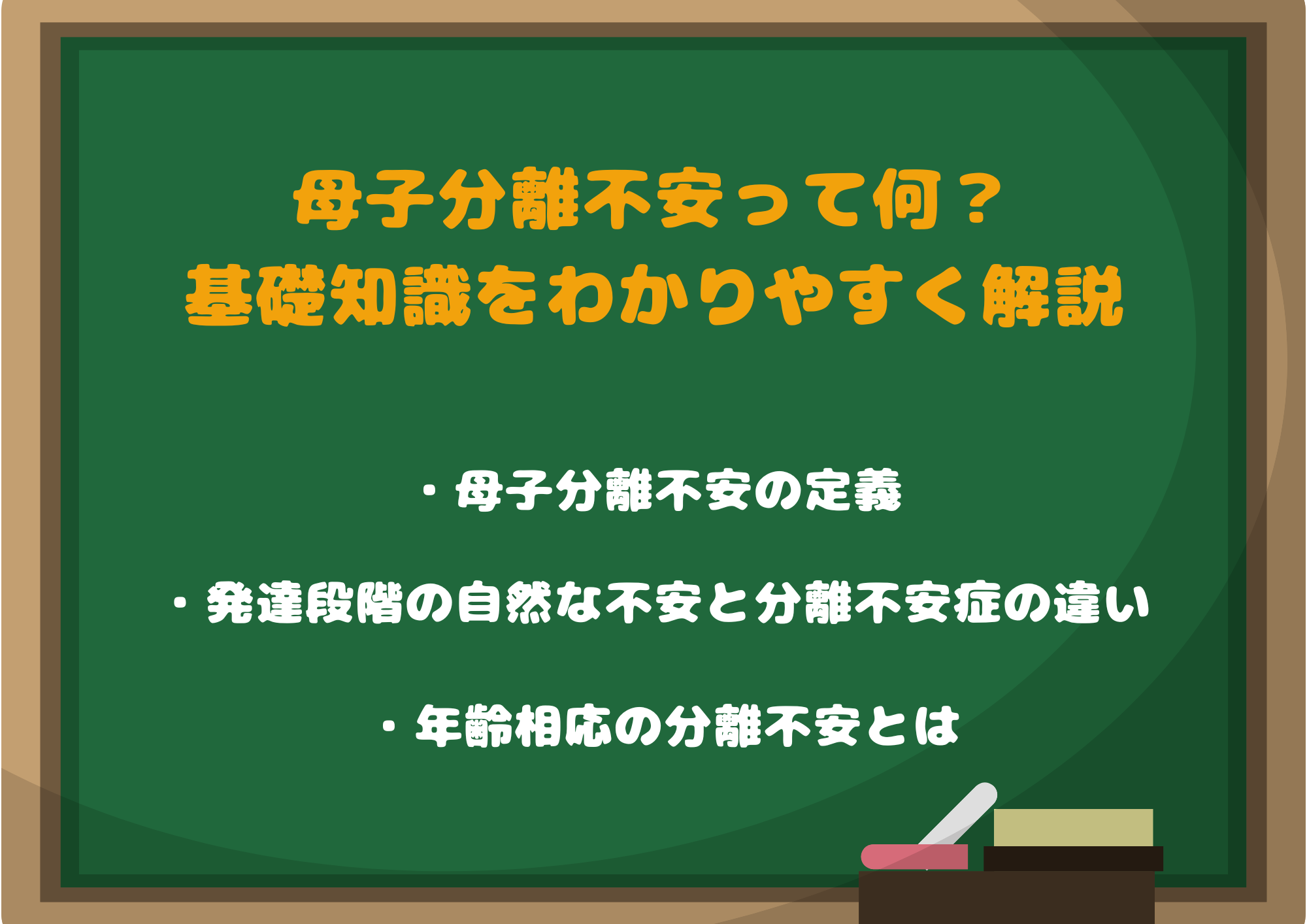
- 母子分離不安の定義と症状について理解できます
- 発達段階の自然な不安と分離不安症の違いがわかります
- 年齢に応じた分離不安の特徴を知ることができます
母子分離不安とは、親と離れることに強い不安を感じる状態のことです。
お子様が泣いたり、しがみついたりする姿は、多くの保護者の方が経験されています。まずはこの不安について、正しく理解することから始めましょう。
母子分離不安の定義|親と離れることへの強い不安
- 親と離れる場面で過度な不安を示す状態
- 身体症状として現れることもある
- 強さや続く期間によって対応が変わる
母子分離不安は、親と離れる場面で過度な不安を示す状態を指します。
具体的には、保育園や幼稚園の送り迎えで激しく泣く、親の姿が見えないとパニックになる、家でも親の後を追い続けるといった行動が見られます。
この不安は、お子様にとって親が「安全基地」であることの表れでもあるんです。ただし、その強さや続く期間によって、発達段階の自然な反応なのか、専門的な対応が必要なのかが変わってきます。
発達段階の自然な不安と分離不安症の違い
- 自然な分離不安と医学的な「分離不安症」は異なる
- 分離不安症は4週間以上続く強い不安が特徴
- 日常生活への影響の大きさがポイント
すべての母子分離不安が問題というわけではありません。
発達の過程で自然に見られるものと、医学的な支援が必要なものがあるんです。生後8ヶ月頃から始まる人見知りや、2〜3歳の「ママじゃなきゃイヤ」という時期は、多くのお子様が経験する発達上の自然な反応です。
一方で「分離不安症」という医学的な診断名もあります。これは発達段階から見て明らかに不相応な強い不安が、4週間以上続いている状態です。
不安の強さ、続いている期間、日常生活への影響の大きさがポイントになります。判断が難しい場合は、児童精神科や発達障害者支援センターに相談することをおすすめします。
何歳まで続く?年齢相応の分離不安とは
- 生後8ヶ月頃の人見知りは知的発達の証拠
- 1歳半頃にピークを迎え、徐々に落ち着く
- 4歳を過ぎても強い不安が続く場合は相談が必要
年齢によって、分離不安の現れ方は変わってきます。
生後8ヶ月頃に始まる人見知りは、親以外の人を認識できるようになった証拠です。これは知的発達の表れなので、むしろ喜ばしいことなんですね。1歳半頃にピークを迎え、その後は徐々に落ち着いていくのが一般的です。
2〜3歳になると「ママがいい」「パパじゃダメ」といった特定の人へのこだわりが強くなることもあります。多くの場合、3歳を過ぎると少しずつ親から離れて遊べる時間が増えていきます。
ただし、4歳を過ぎても強い分離不安が続く場合や、入園・入学をきっかけに突然悪化した場合は、何か別の要因が隠れている可能性があります。
母子分離不安と発達障害の関係性
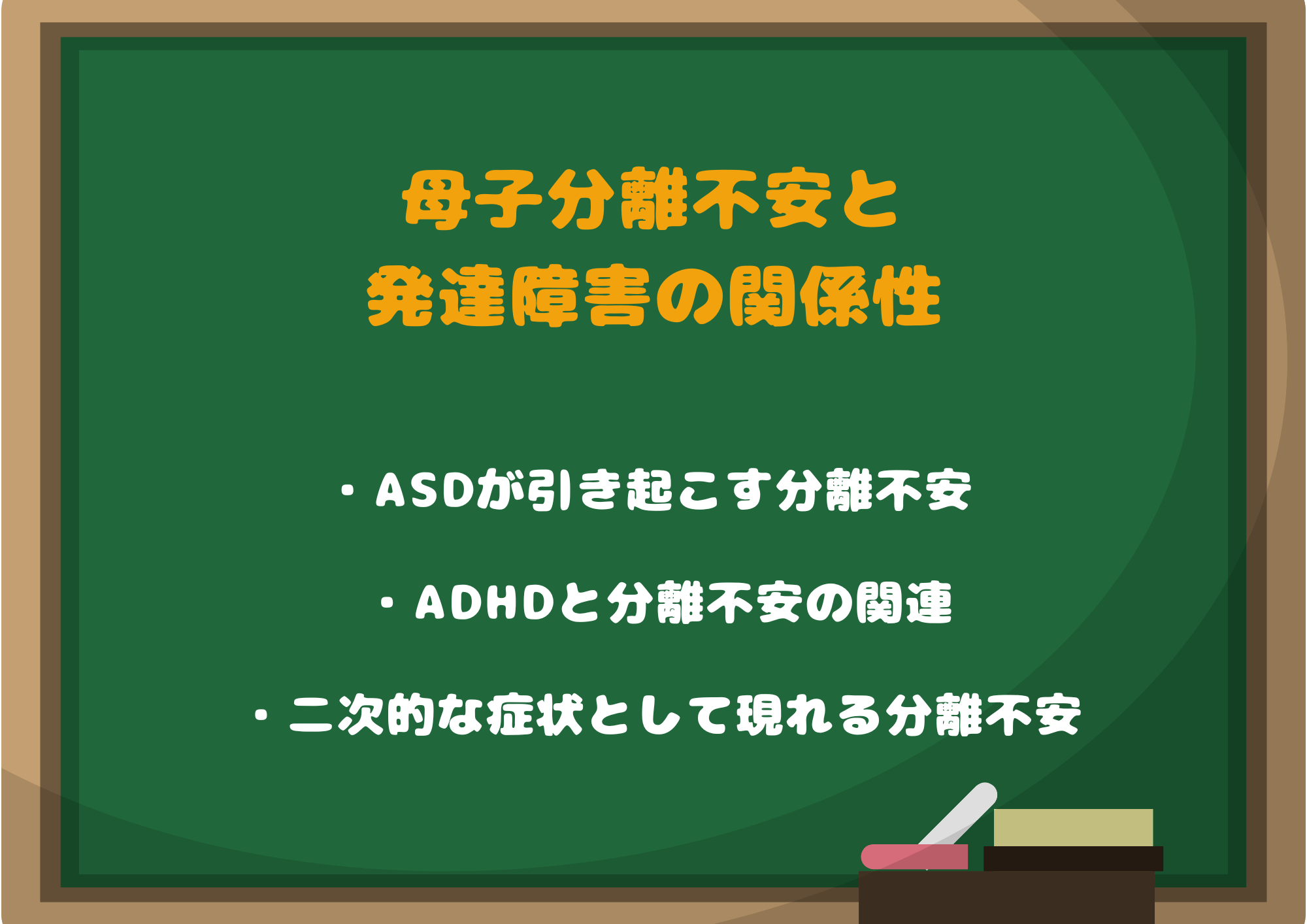
- ASD(自閉症スペクトラム)が引き起こす分離不安
- ADHD(注意欠陥多動性障害)と分離不安の関連
- 二次的な症状として現れる分離不安
母子分離不安の背景に、発達障害の特性が関係している場合があります。
特にASD(自閉症スペクトラム)やADHD(注意欠陥多動性障害)の特性が、環境の変化や集団生活への不安を強めることがあるんです。発達障害の特性を正しく理解したい方は「子供の発達障害を理解する|特徴から支援まで親の完全ガイド」も参考になります。
ASD(自閉症スペクトラム)が引き起こす分離不安
- 変化への強い不安|いつもと違うことが怖い
- 感覚過敏が原因|学校が苦痛な場所になる可能性
ASDの特性を持つお子様は、独特の理由で親と離れることに強い抵抗を示すことがあります。
それは単に「親と離れたくない」というよりも、新しい環境や予測できない状況そのものへの不安が大きいんです。いつもと違うことが起こると、どう対処していいかわからず、パニックになってしまうことがあります。
ASDのお子様の多くは「いつもと同じ」であることに強い安心感を持っています。入園や入学、クラス替え、担任の先生の変更といった環境の変化は、定型発達のお子様以上に大きなストレスになるんです。
また、特定の感覚に過敏な方もいます。教室の騒音、蛍光灯のまぶしさ、給食の匂い、体操服のタグのチクチク感。こうした刺激が耐え難い苦痛になることがあります。この場合、お子様が拒否しているのは「親との分離」ではなく「学校という不快な場所」そのものかもしれません。
ADHD(注意欠陥多動性障害)と分離不安の関連
- 集中が続かない|新しい環境での困難
- 衝動性と不安|感情のコントロールが難しい
ADHDの特性を持つお子様も、新しい環境への適応に困難を抱えることがあります。
集中力の維持や衝動のコントロールといった課題が、集団生活での不安を強めているんです。その結果、唯一安心できる親のそばから離れられなくなることがあります。
ADHDのお子様は、注意を一つのことに向け続けることが苦手な傾向があります。授業中に先生の話を最後まで聞けない、忘れ物が多い、周りの刺激にすぐ気を取られる。こうした困難が積み重なると、学校が「うまくいかない場所」「怒られる場所」になってしまうんです。
また、思ったことをすぐ口に出してしまう、順番を待てないといった衝動性は、友達とのトラブルにつながることがあります。対人関係での失敗経験が積み重なると、親のそばにいれば守ってもらえるという安心感を求めるようになります。
二次的な症状として現れる分離不安
- 発達障害の特性によって適応が難しくなる
- 困難が積み重なると園や学校が「怖い場所」に
- 背景にある困難への対応が重要
発達障害そのものが直接的に分離不安を引き起こすわけではありません。
多くの場合、発達障害の特性によって園や学校での適応が難しくなり、その結果として分離不安が現れることがあるんです。
感覚過敏で教室が苦痛な場所になっている、集団行動のルールが理解できず叱られることが多い、友達とのコミュニケーションがうまくいかない。こうした困難が積み重なると、園や学校が「怖い場所」になってしまいます。
この場合、分離不安そのものを治療するのではなく、背景にある困難に対応することが重要になります。
母子分離不安の原因|なぜうちの子だけ?
- 環境の変化がきっかけとなる場合が多い
- 発達の特性による不安の増幅
- 家庭環境やトラウマ体験の影響
母子分離不安の原因は一つではありません。
環境の変化、発達の特性、家庭環境、過去の経験など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。「うちの子だけ」と感じるかもしれませんが、実は多くの保護者の方が同じ悩みを抱えているんです。
環境の変化がきっかけ|入園・入学が引き金に
- 入園や入学といったライフイベントが引き金に
- 新しい環境は予測できない要素だらけ
- 引っ越しや家族構成の変化も要因に
母子分離不安が顕在化する最も多いきっかけが、環境の大きな変化です。
保育園や幼稚園への入園、小学校への入学といったライフイベントは、お子様にとって予測できない要素だらけの大冒険なんですね。新しい場所、知らない先生や友達、初めてのルール。こうした変化が一度に押し寄せると、どんなお子様でも不安を感じます。
特に発達障害の特性があるお子様は、変化への適応により多くのエネルギーを必要とします。引っ越しや家族構成の変化なども、分離不安を引き起こすきっかけになることがあります。
発達の特性による不安の増幅
- ASDでは不確実性が恐怖の対象に
- ADHDでは失敗経験が積み重なりやすい
発達障害の特性は、環境の変化への不安を何倍にも増幅させることがあります。
ASDの特性がある場合、「いつもと違う」状況そのものが強い恐怖の対象になります。見通しが立たない、予測できない、どうしていいかわからない。こうした不確実性が、パニックレベルの不安を引き起こすんです。
ADHDの特性がある場合は、新しい環境での失敗経験が積み重なりやすい傾向があります。注意散漫で先生の指示を聞き逃す、衝動的な行動でトラブルになる。こうした経験が「学校は怖い場所」という認識を強めます。
家庭環境や親子関係の影響
- 親の不安が子どもに伝わることがある
- 保護者自身のケアも大切
家庭環境も、母子分離不安に影響を与える要因の一つです。
ただし、これは「保護者の育て方が悪い」という意味ではありません。親子の関係性や家庭内の状況が、お子様の不安の強さに関係することがあるという理解が大切です。
例えば、親自身が不安を強く感じている場合、その不安がお子様に伝わることがあります。また、過度に心配しすぎる対応が、お子様の「一人では無理」という思い込みを強化してしまうこともあるんです。
発達障害のお子様を持つ親御さんの気持ちについては「発達障害のある子どもを持つ親の気持ち|最初に感じる不安や悩みとは」でも詳しく解説しています。
トラウマ体験|過去の離別経験が影響することも
- 入院や迷子の経験が影響する場合がある
- 家族の死別や離婚も要因に
過去に親と離れた際の怖い経験が、トラウマとして残っていることがあります。
例えば、入院で親と離れた、預け先で怖い思いをした、迷子になって不安だったといった経験です。こうした記憶が、親と離れること自体への強い恐怖となって現れることがあるんです。
また、家族の死別や離婚といった大きな喪失体験も、分離不安を引き起こす要因になります。
年齢別の特徴と症状|いつから気をつけるべき?
- 乳幼児期の自然な不安について理解できる
- 登園しぶり・登校しぶりのサインがわかる
- 不登校へ発展するリスクを知ることができる
母子分離不安の現れ方は、年齢によって大きく変わってきます。
乳幼児期の自然な反応から、就学後の登校しぶりまで、それぞれの時期の特徴を理解することが大切です。お子様の年齢に合わせた対応を考えていきましょう。
0歳〜3歳|発達段階の自然な不安
- 生後8ヶ月頃から人見知りが始まる
- 1歳半頃にピークを迎える
- 2〜3歳で徐々に落ち着くのが一般的
0歳から3歳の時期は、ほとんどのお子様が何らかの分離不安を示します。
これは発達の過程で自然に見られる反応なので、過度に心配する必要はありません。むしろ、親子の愛着関係がしっかり形成されている証拠でもあるんです。
生後8ヶ月頃になると、多くの赤ちゃんが人見知りを始めます。これは「親」と「それ以外の人」を区別できるようになった証拠で、認知発達の重要なステップなんです。
1歳半頃に分離不安はピークを迎え、その後徐々に落ち着いていくのが一般的です。2〜3歳になると、親がいなくても少しずつ安心して遊べる時間が増えていきます。
3歳〜小学校入学|登園しぶりのサイン
- 入園という環境変化がきっかけになることが多い
- 毎朝泣き叫ぶ行動が見られることがある
- 身体症状として現れる場合も
幼稚園や保育園に通い始める3〜6歳の時期は、新しい環境への適応が求められます。
この時期の分離不安は、入園という大きな環境変化がきっかけになることが多いんです。多くの場合、数週間から数ヶ月で慣れていきますが、中には長引くお子様もいます。
朝になると「行きたくない」と泣き叫ぶ、園の前で固まってしまうといった行動が見られます。これは単なるわがままではなく、新しい環境への不安の表れなんです。
また、不安が身体症状として現れることもあります。「お腹が痛い」「頭が痛い」といった訴えが、登園前になると繰り返し現れるんです。これは仮病ではなく、心理的な不安が身体の症状として表れる「心身症」の一種です。
小学校低学年|登校しぶりと学習の遅れ
- 小学校入学は大きな環境変化
- 朝の体調不良が繰り返される場合は要注意
- 授業についていけない不安が影響することも
小学校入学は、お子様にとって環境の大きな変化です。
幼稚園や保育園とは違い、時間割に沿った授業、宿題、テストといった新しい要素が加わります。この変化が、分離不安を再燃させたり、悪化させたりすることがあるんです。
小学生になると、不安の表現がより具体的になります。「学校に行きたくない」と直接的に訴える、朝になると必ず体調不良を訴える、学校の準備をしたがらない。こうしたサインが続く場合は、学校での何らかの困難が背景にあることが多いんです。
発達障害の特性があると、授業の内容を理解することが難しい場合があります。「できない自分」を見せたくないという気持ちが、登校しぶりにつながることもあります。
小学生のお子様の学習サポートについては「小学生コース」で詳しくご紹介しています。
小学校高学年以降|不登校へのリスク
- 分離不安が続くと不登校のリスクが高まる
- 学習内容の難化や友達関係の複雑化が影響
- 早めに専門的な支援を受けることが重要
小学校高学年になっても分離不安が続く場合、不登校へと発展するリスクが高まります。
この時期は学習内容も難しくなり、友達関係も複雑になる時期です。発達障害の特性による困難が積み重なると、「学校に行けない」状態が固定化してしまうことがあります。
この段階では、早めに専門的な支援を受けることが重要になります。児童精神科や発達障害者支援センターに相談し、適切なサポート体制を整えることをおすすめします。
発達障害のお子様が勉強しない理由と対策については「発達障害の中学生が勉強しない理由とその対策をタイプ別に解説」も参考になります。不登校のお子様へのサポートは「不登校の家庭教師サポート」をご覧ください。
登校しぶり・不登校を防ぐために今できること
- 早期の対応が不登校予防につながる
- 学習面のサポートで自信を取り戻せる
- 家庭教師なら自宅で安心して学習できる
分離不安を放置すると、登校しぶりから不登校へと発展するリスクがあります。
「学校=怖い場所」「学校=できない場所」という認識が固定化する前に、早めの対応が大切です。特に学習面でつまずきがあると、学校への苦手意識が強まりやすいので、家庭でのサポートが重要になります。
家庭教師なら、自宅という安心できる環境で、お子様のペースに合わせた学習が可能です。集団が苦手でも、1対1なら落ち着いて取り組めるお子様も多いんです。
学習面での「できた!」という成功体験が、お子様の自信につながります。自信がつくと、新しい環境への挑戦にも前向きになれるんです。
不登校になりやすい家庭の特徴と対策については「不登校になりやすい家庭の特徴と対策!家庭環境を見直し子どもの学びと心を支える方法」も参考になります。
家庭でできる対応方法|まずは親ができること
- 子どもの不安を受け止める方法を学べる
- 段階的に離れる練習の進め方がわかる
- 安心できる環境づくりのポイントを理解できる
専門的な支援を受ける前に、あるいは並行して、家庭でできる対応方法があります。
保護者の方の接し方や環境づくりが、お子様の不安を和らげる大きな力になるんです。焦らず、お子様のペースに合わせて取り組んでいきましょう。
子どもの不安を受け止めよう|否定しないことが第一歩
- 不安を訴えたときはまず共感することが大切
- 否定的な言葉は不安を強めてしまう
- 受け止めながらも前向きなメッセージを伝える
お子様が不安を訴えたとき、まずはその気持ちを受け止めることが何より大切です。
「そんなの平気でしょ」「みんなできてるよ」といった否定的な言葉は、お子様の不安をさらに強めてしまうことがあります。「怖いんだね」「不安なんだね」と、まずは気持ちに共感することから始めましょう。
受け止めてもらえたという安心感が、不安を和らげる第一歩になります。ただし、過保護になりすぎないバランスも大切です。不安を受け止めながらも、「でも大丈夫だよ」「一緒に頑張ろう」という前向きなメッセージも伝えていきましょう。
保護者の方が「あんしんサポートサービス」を活用すれば、専門スタッフに育児の悩みを相談することもできます。詳しくは「あんしんサポートサービス」をご覧ください。
段階的に離れる練習|焦らず少しずつ
- 短時間から始めて徐々に慣らしていく
- 「必ず戻ってくる」という信頼感を育てる
- 視覚的な情報で見通しを立てると効果的
いきなり長時間の分離を強いるのではなく、短い時間から徐々に慣らしていく方法が効果的です。
無理に引き離すと、かえって不安が強まり、逆効果になることがあります。お子様のペースを尊重しながら、少しずつステップアップしていきましょう。
まずは家の中で、視界から離れる練習から始めてみましょう。「ちょっと洗濯物を取ってくるね、5分で戻るよ」と具体的に伝え、必ず約束通りに戻ってきます。これを繰り返すことで、「ママは必ず戻ってくる」という信頼感が育ちます。
特にASDの特性があるお子様には、視覚的な情報が効果的です。タイマーを使って「この音が鳴ったら戻ってくる」と具体的に示しましょう。予測ができると、不安が和らぐんです。
安心できる環境づくり|家庭が安全基地に
- 予測可能な生活リズムを作る
- お守りアイテムを持たせると効果的
- 家庭が安全基地になることが大切
家庭がお子様にとって安心できる「安全基地」になることが、とても重要です。
外の世界で不安や緊張を感じても、家に帰れば安心できるという場所があることで、お子様は少しずつチャレンジする勇気を持てるようになります。
毎日のルーティンを一定に保つことで、お子様は安心感を得られます。起きる時間、食事の時間、寝る時間を決め、できるだけ同じパターンで過ごすようにしましょう。予測できる生活リズムは、特に発達障害のお子様にとって心の安定につながります。
また、お気に入りのぬいぐるみやハンカチなど、お子様が安心できるアイテムを持たせる方法も効果的です。園や学校に持っていけるものを、お子様と一緒に選んでみましょう。
過保護に注意|適切な距離感って?
- 過保護になりすぎると自信が育ちにくくなる
- 少しずつできることを増やすサポートが理想的
- わからないときは専門家に相談
お子様の不安を受け止めることは大切ですが、過保護になりすぎないバランスも重要です。
親が先回りしてすべてを解決してしまうと、お子様は「自分一人では何もできない」という思い込みを強めてしまうことがあります。少しずつ、お子様が自分でできることを増やしていくサポートが理想的です。
失敗しても大丈夫、という経験を積み重ねることで、お子様の自信が育っていきます。適切な距離感がわからないときは、カウンセラーや療育の専門家にアドバイスを求めることも有効です。
今からできる一歩|まずは無料体験で相性を確認
- 家庭での対応と専門的サポートの併用が効果的
- 自宅で受けられる無料体験ならお子様の負担も少ない
- 発達障害の指導経験が豊富なスタッフが在籍
家庭での対応と専門的なサポートを併用することで、より効果的にお子様を支えることができます。
「でも、うちの子は人見知りが激しくて…」「新しい人に会うのが苦手で…」という心配をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。そんなお子様にこそ、自宅で受けられる家庭教師という選択肢があります。
家庭教師のランナーでは、無料体験レッスンを実施しています。自宅という安心できる環境で、親御さんのそばにいながら受けられるので、お子様の負担も少ないんです。
発達障がいコミュニケーション指導者を取得したスタッフが在籍しており、お子様の特性に合わせた対応が可能です。「うちの子に合うかな?」と不安な方も、まずは無料体験で相性を確認してみませんか。
無料体験の流れについては「初回指導までの流れ」をご覧ください。
専門的な支援とサポート体制
- 医療機関での診断とアセスメントについて学べる
- 療育サービスの活用方法がわかる
- 学校での支援や家庭教師の活用法を理解できる
家庭での対応だけでは難しい場合、専門的な支援を受けることが大切です。
医療、福祉、教育、そして民間のサービスまで、さまざまな支援の選択肢があります。お子様の状況に合わせて、最適なサポート体制を整えていきましょう。
医療機関での診断とアセスメント
- 児童精神科で専門的な評価を受けられる
- 診断があると支援を受けやすくなる
- WISC検査でお子様の特性を把握できる
専門的な支援の第一歩は、医療機関での診断とアセスメントです。
お子様の状態を正しく理解することで、適切な支援方法が見えてきます。診断を受けることに不安を感じる方もいるかもしれませんが、これは支援を受けるためのスタートラインなんです。
児童精神科では、お子様の発達や行動について専門的な評価を受けられます。診断を受けることで、福祉サービスを利用するための受給者証が取得できたり、学校での合理的配慮を依頼する際の参考資料になったりします。
診断は「レッテル貼り」ではなく、適切な支援につながる大切なステップです。
WISC検査は、お子様の認知能力を詳しく調べる発達検査の一つです。この結果をもとに、お子様に合った学習方法や支援の方向性を考えることができるんです。WISC-IVの結果の見方については「WISC-IV知能検査の結果の見方|数値の意味と子どもへの活かし方をわかりやすく解説」で詳しく解説しています。
療育サービス|児童発達支援と放課後等デイサービス
- SSTで社会性を身につけることができる
- 受給者証があれば負担軽減制度を利用できる
- 専門スタッフによるサポートを受けられる
療育サービスは、発達に課題のあるお子様の成長をサポートする福祉サービスです。
社会性や生活スキルを身につけるための専門的なプログラムが用意されています。利用するには受給者証が必要ですが、所得に応じた負担軽減制度もあるんです。
SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、社会生活に必要なスキルを体系的に学ぶトレーニングです。あいさつの仕方、友達への声のかけ方、気持ちの伝え方など、ロールプレイやゲームを通じて、楽しみながらスキルを身につけられます。
受給者証は、市区町村の福祉窓口に申請し、医師の診断書や発達検査の結果を提出します。手続きには時間がかかることがあるので、早めに相談を始めることをおすすめします。
学校での支援|通級による指導と合理的配慮
- 通級による指導で個別の支援を受けられる
- 障害者差別解消法に基づき合理的配慮を依頼できる
- 学校との対話を通じて配慮内容を決めていく
学校内でも、お子様の特性に合わせたさまざまな支援を受けることができます。
通常の学級に在籍しながら、個別の支援を受ける仕組みが整っているんです。保護者から学校に働きかけることで、お子様に必要な配慮を得ることができます。
通級による指導は、通常の学級に在籍しながら、一部の時間に障害に応じた特別の指導を受ける仕組みです。お子様の困難に合わせて、社会性のトレーニングや学習面でのサポートが受けられます。
合理的配慮の提供は、障害者差別解消法に基づき、学校でも必要に応じて行われます。座席の位置、指示の出し方、試験時間の延長など、お子様の特性に応じた配慮を依頼してみましょう。
母子分離不安のお子様に家庭教師が効果的な理由
- 自宅という安心できる環境で学習できる
- 親のそばにいながら指導を受けられる
- 1対1なので集団が苦手でも取り組める
母子分離不安のあるお子様にとって、家庭教師は特に相性の良い学習サポートです。
なぜなら、自宅という最も安心できる環境で、親御さんのそばにいながら学習できるからです。集団が苦手なお子様でも、1対1のマンツーマン指導なら落ち着いて取り組めることが多いんです。
学校や塾では「親と離れる」「新しい環境に行く」「知らない人がいる」といった複数のハードルを同時に越えなければなりません。でも家庭教師なら、分離不安を悪化させることなく、学習サポートを受けることができます。
また、お子様の特性やペースに合わせたオーダーメイドの指導が可能なので、「できた!」という成功体験を積み重ねやすいのも大きなメリットです。
発達障害のお子様に最適な家庭教師の選び方については「発達障害の子どもに最適な家庭教師の選び方とおすすめサービス徹底比較」も参考になります。
家庭教師のランナー|発達障害の子どもに寄り添う指導

- 創業21年・30,034人の指導実績
- 発達障がいコミュニケーション指導者取得スタッフ在籍
- 2024年第一志望合格率97.5%
- 1コマ30分900円からのシンプルな料金体系
家庭教師のランナーは、発達障害のお子様の指導に特化した家庭教師サービスです。
創業21年、30,034人の指導実績があり、勉強が苦手なお子様専門のサポートを行っています。2024年の第一志望合格率は97.5%。自宅という安心できる環境で、マンツーマンの指導が受けられるんです。
ランナーには、発達障がいコミュニケーション指導者を取得したスタッフが在籍しています。お子様の特性を理解した上で、一人ひとりに合わせたオーダーメイドの指導を行います。反抗的・無気力な状態でも、「わかる楽しさ」を感じてもらえるよう工夫された指導が魅力です。
料金は、1コマ(30分)小中学生900円・高校生1000円というシンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。実際には月々15,000円から25,000円ほどで受講されているご家庭が多いです。
発達障害のお子様へのサポートについて詳しくは「発達障害の家庭教師サポート」をご覧ください。
学校・園との連携と相談窓口
- 子どもの特性を共有する方法を学べる
- 定期的な情報共有の重要性がわかる
- 相談できる窓口を知ることができる
お子様の成長には、家庭と学校・園との連携が欠かせません。
特に発達障害のお子様の場合、学校側にお子様の特性を正しく理解してもらい、適切な配慮を得ることが重要です。また、一人で抱え込まずに相談できる窓口を知っておくことも大切です。
子どもの特性を共有しよう|具体的な配慮を依頼
- 具体的な困難を説明することが大切
- 個別の指導計画を文書化しておくと安心
- 座席位置や指示の出し方など具体的に依頼
学校や園の先生に、お子様の特性を具体的に伝えることが第一歩です。
「発達障害があります」だけでは、どんな配慮が必要なのか先生に伝わりません。「大きな音が苦手です」「急な予定変更が不安になります」など、具体的な困難を説明しましょう。
個別の指導計画は、お子様に必要な配慮や指導方法を文書化したものです。担任の先生が変わっても、この計画があれば支援内容を引き継ぐことができます。年度の初めに、学校と相談しながら作成することをおすすめします。
定期的な情報共有|連絡帳や面談を活用
- 日々の連絡帳で様子を共有する
- 定期的な面談で詳しい情報交換ができる
- 些細なことでも早めに相談する関係を築く
日々の連絡帳や定期的な面談を通じて、お子様の様子を共有することが大切です。
家庭でうまくいった対応方法を学校に伝えたり、学校での様子を教えてもらったりすることで、一貫した支援ができます。些細なことでも気になることがあれば、早めに相談する関係を築いておきましょう。
問題が大きくなる前に対応できることも多いんです。
相談できる窓口|一人で抱え込まないで
- 発達障害者支援センター|公的な総合相談窓口
- 児童相談所|18歳未満の子どもの総合相談
- スクールカウンセラー|学校内で気軽に相談
母子分離不安や発達障害の悩みは、一人で抱え込まずに相談することが大切です。
発達障害者支援センター
各都道府県・指定都市に設置されている公的な相談窓口です。医療、福祉、教育にわたる総合的な相談に対応しています。相談は無料で、プライバシーもしっかり守られます。
児童相談所
18歳未満のお子様に関するあらゆる相談に対応する公的機関です。子育て等の相談は、児童相談所相談専用ダイヤル「0120-189-783」を利用できます。
スクールカウンセラー
多くの学校には、臨床心理士などの専門資格を持つカウンセラーが配置されています。保護者だけでの相談も可能なので、気軽に利用してみましょう。
よくある質問と誤解|知っておきたいこと
- 愛情不足が原因ではない
- 自然に治るとは限らない
- 厳しく突き放すのは逆効果
- 診断はレッテル貼りではない
母子分離不安や発達障害について、多くの保護者の方が同じような疑問や誤解を持っています。
ここでは、よくある質問に答えながら、正しい理解を深めていきましょう。
愛情不足が原因?親の育て方のせいなの?
- 育て方の問題ではなく特性と環境のミスマッチ
- 罪悪感を持つ必要はない
- 専門家のサポートを受けることが大切
お子様の強い分離不安を見ると、「自分の育て方が悪かったのでは」と自分を責めてしまう方が多くいます。
でも、そのように自分を責める必要は全くありません。母子分離不安の多くは、環境の変化や発達の特性が関係しており、育て方の問題ではないんです。
分離不安が強いお子様の多くは、環境の変化への適応が難しい特性を持っています。入園や入学といった大きな環境変化、集団生活のルールの複雑さ、感覚過敏による不快感。こうした要因が重なって、不安が強く現れているんです。
罪悪感を持つことは、かえって家庭内の緊張を高め、悪循環を生むことがあります。専門家のサポートを受けながら、お子様に合った対応を一緒に考えていきましょう。
いつまで続くの?自然に治るもの?
- 程度によって経過は異なる
- 専門的な支援が必要なケースもある
- 早期の適切な対応が鍵
分離不安の経過は、お子様によって大きく異なります。
年齢相応の分離不安であれば、時間とともに自然に落ち着いていくことが多いです。しかし、4歳を過ぎても強い不安が続く場合や、日常生活に大きな支障が出ている場合は、専門的な支援が必要になります。
分離不安を放置すると、登校しぶりから不登校へと発展するリスクがあります。早めに専門家に相談し、適切な対応を始めることが重要です。
厳しく突き放すべき?我慢させた方がいい?
- 無理な分離は逆効果になることが多い
- トラウマ体験になる可能性がある
- 段階的な支援と環境調整が正解
「甘やかしているから不安が強いのでは」と考え、厳しく突き放そうとする方もいます。
でもこの対応は、多くの場合逆効果になってしまうんです。お子様が強い不安を示しているのに、無理やり引き離して我慢させると、トラウマ体験になる可能性があります。
適切な対応は、短時間から徐々に慣らしていく段階的なアプローチです。同時に、お子様が不安を感じている原因を取り除く環境調整も重要です。
診断を受けるとレッテル貼りになる?
- 診断は適切な支援を受けるための重要なステップ
- 受給者証の取得や合理的配慮の参考資料になる
- お子様の特性を正しく理解することが大切
発達障害の診断を受けることへの抵抗感を持つ方は少なくありません。
「診断を受けるとレッテルを貼られて、子どもの将来が不利になるのでは」という不安ですね。でも実際には、診断は不利益ではなく、むしろ適切な支援を受けるための重要なステップなんです。
診断名があることで、療育サービスを利用するための受給者証が取得できます。また、学校で合理的配慮を依頼する際の参考資料にもなります。
お子様の特性を正しく理解し、その特性に合わせた環境を整えることで、お子様は本来の力を発揮できるようになります。
母子分離不安と発達障害についてまとめ
- ・母子分離不安の背景には発達障害の特性が関係していることがある
- ・変化への強い不安や感覚過敏といった特性が分離不安として現れる
- ・保護者の育て方の問題ではなく環境とのミスマッチが原因
- ・専門家に相談しお子様の特性を正しく理解することが大切
- ・家庭教師なら自宅で親のそばにいながら学習サポートを受けられる
お子様の母子分離不安の背景には、発達障害の特性が関係していることがあります。
変化への強い不安や感覚過敏といった特性が、環境の変化をきっかけに分離不安として現れるんです。でも、これは決して保護者の育て方の問題ではありません。
適切な理解と支援があれば、お子様も保護者の方も楽になる道はたくさんあります。まずは専門家に相談し、お子様の特性を正しく理解することから始めましょう。
発達障害者支援センターや児童相談所相談専用ダイヤル(0120-189-783)での相談、療育サービスの利用、学校での合理的配慮の依頼など、活用できる支援は多岐にわたります。
また、家庭教師のランナーでは、発達障害のお子様に寄り添った指導を行っています。自宅という安心できる環境で、親御さんのそばにいながら学習できるので、母子分離不安のあるお子様にも安心です。
発達障がいコミュニケーション指導者を取得したスタッフが在籍しており、お子様の特性に合わせたオーダーメイドの指導が可能です。公的支援と民間サービスを組み合わせて、お子様に最適な支援体制を整えていきましょう。
一人で抱え込まず、周囲の力を借りながら、お子様の成長を見守っていってくださいね。