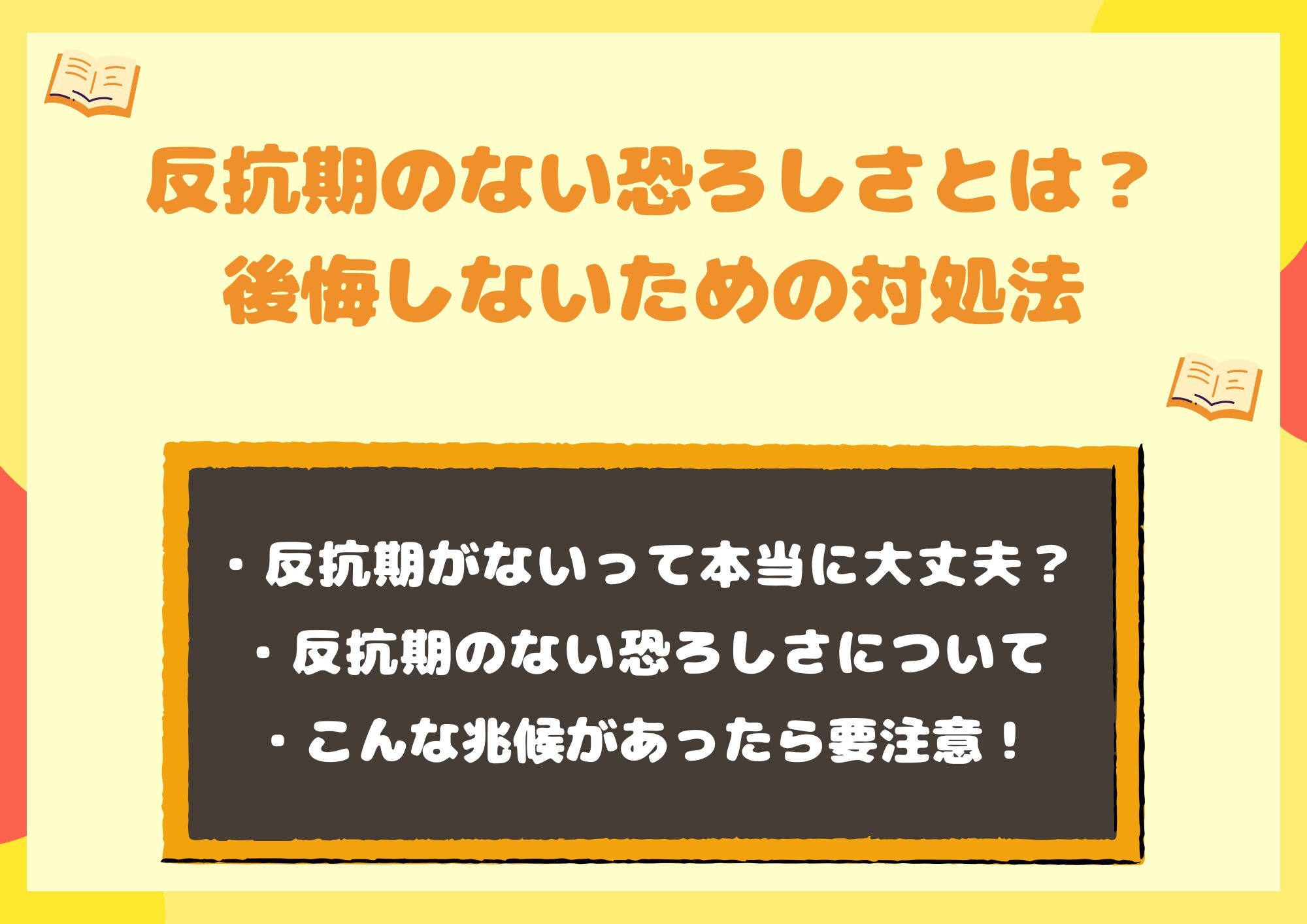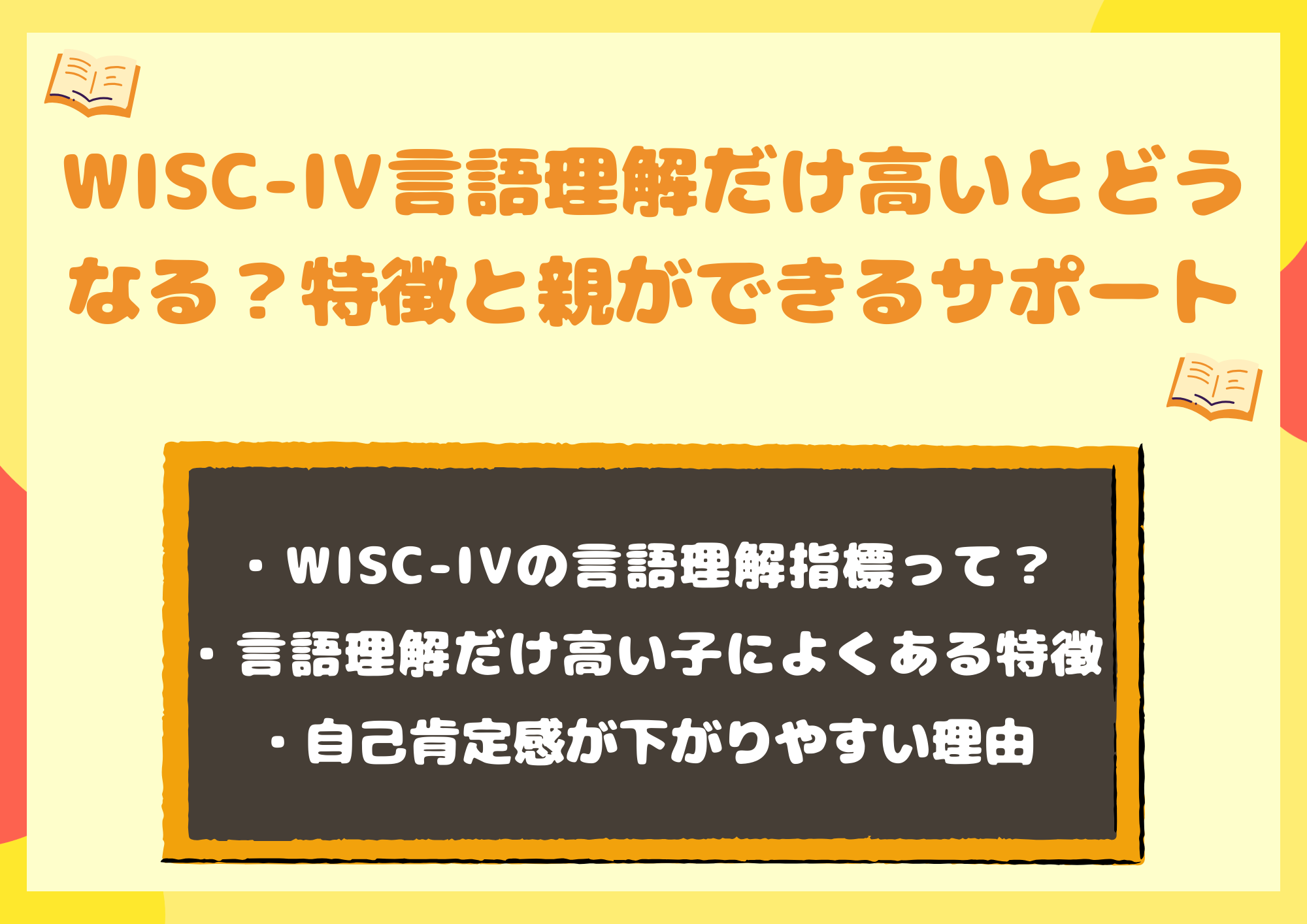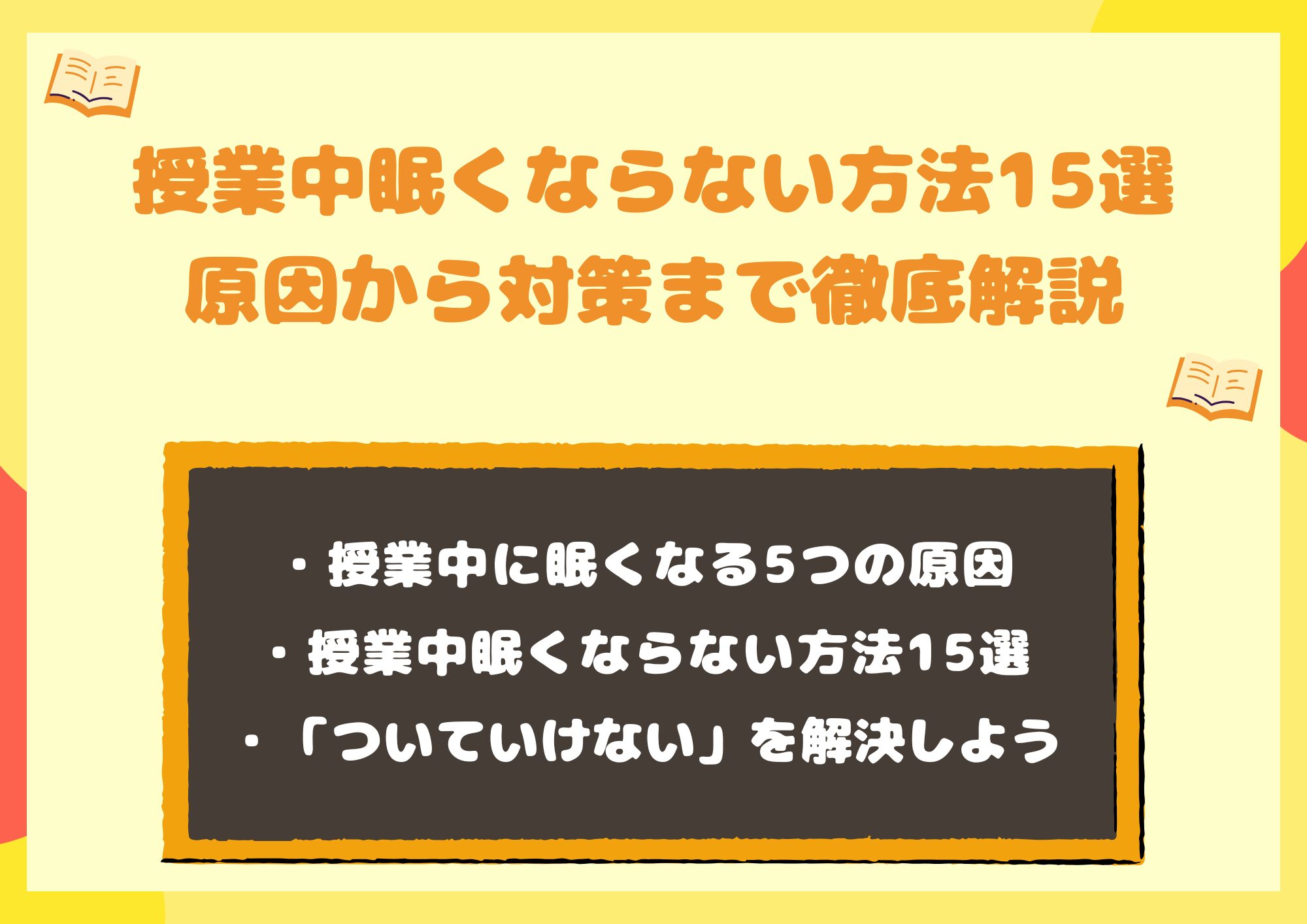- 中
中学生の受験生の勉強時間はどれくらい?成功するために親ができるサポートもご紹介
2025.01.29

受験を控える中学生にとって、勉強時間の確保とその効果的な活用は非常に重要です。特に、時期ごとに適切な学習量を見極めながら取り組むことが、志望校合格への近道となります。
この記事では、受験生が意識すべき勉強時間の目安や効率的な学習法について詳しく解説します。受験対策を進める上での参考にしてください。
目次
中学生の受験生の勉強時間は1日平均してどれくらい必要?
- 平日は学校の授業後に2~3時間の勉強時間を確保するのが理想。
- 休日は4~6時間を目安に、午前中は基礎学習、午後は応用問題や過去問を取り組むと効果的。
- 無理なく継続できる勉強時間を設定し、スケジュールを計画的に立てることが重要。
受験生にとって、1日の勉強時間をどれくらい確保すればよいのかを知ることは重要です。ただ長時間勉強するだけではなく、時期に応じた適切な勉強時間を設定し、効率的に学習を進めることが成功の鍵となります。ここでは、平日と休日それぞれの理想的な勉強時間の目安について解説します。
夏休みまでの勉強時間:平日1.5~2時間、休日3~4時間
夏休みまでの時期は、部活動や学校行事が忙しいため、勉強時間を確保しにくい傾向があります。しかし、基礎固めを進めるためにも、平日は最低1.5時間、休日は3時間以上を目安に取り組むことが理想的です。
特に主要3教科(国語・数学・英語)をバランスよく学習する習慣をつけましょう。
夏休み中の勉強時間:平日・休日問わず5~6時間
夏休みは受験生にとって最大の学習期間です。1日のスケジュールをしっかり組み、午前中に2~3時間、午後に2時間、夜に1~2時間の勉強を行うことで、効率よく学力を向上させることができます。
また、夏休み中は過去問や模擬試験に取り組むなど、実戦的な学習を取り入れると効果的です。
夏休み明けから12月までの勉強時間:平日2~3時間、休日4~5時間
夏休みが終わると、学校の授業や行事が本格的に始まります。この時期は、学校で習う新しい内容の復習と、受験範囲の総復習を並行して行う必要があります。
平日は放課後に2時間を目安に復習を行い、休日は1日を通して4時間以上を確保することを目指しましょう。
冬休み中の勉強時間:平日・休日問わず6~8時間
冬休みは受験直前の追い込み時期です。この期間では、苦手分野の克服に集中することが重要です。午前中に3時間、午後に3時間、夜に2時間といった形で1日の勉強スケジュールを組むと効率的です。
特に重要なポイントは、過去問や模擬試験を繰り返して受験本番に慣れることです。
1月以降(受験直前)の勉強時間:平日3~4時間、休日7~8時間
1月以降は最終調整の期間です。過去問の解き直しや、これまでの間違いを復習することで得点力を高めます。平日は登校後の夕方から3~4時間、休日は午前中3時間、午後3時間、夜1~2時間を目安に学習を進めましょう。
また、この時期は体調管理にも注意が必要です。
中学生の受験生の勉強時間は平日と休日1日平均してどれくらい必要?

受験生にとって、平日と休日の勉強時間の確保は重要です。平日は学校の授業があるため、1日あたり平均して2~3時間の学習が理想的です。放課後や夕食後を利用して、学校の復習や受験対策に取り組むと良いでしょう。
一方、休日はまとまった時間を確保できるため、4~6時間を目安に取り組むことをおすすめします。午前中は基礎力を固め、午後は応用問題や過去問に挑戦するなど、時間帯ごとに学習内容を分けることで効率が上がります。
受験生の中学生が勉強時間を確保するための方法を5つ解説

受験生にとって、限られた時間をどう効率的に使うかが重要です。しかし、部活や学校行事の合間に勉強時間を確保するのは簡単ではありません。そこで、日常生活の中で無理なく学習時間を増やすための具体的な方法を5つご紹介します。
小さな工夫を積み重ねることで、受験勉強の成果を最大限に引き出しましょう。
1.睡眠時間をしっかり確保する
勉強時間を増やすために睡眠時間を削ると、かえって集中力や記憶力が低下し、学習効率が悪くなります。受験生にとっても、1日6~8時間の睡眠を確保することが大切です。
睡眠不足にならないよう、夜更かしを避け、決まった時間に就寝する習慣を身につけましょう。
2.スケジュールを立てて実行する
1日の学習スケジュールを立てることで、どの教科をどの時間に取り組むかを明確にできます。例えば、放課後の1時間を学校の復習に、夜の2時間を受験対策に充てるなど、細かく計画を立てると効率的です。
また、スケジュールを実行するために無理のない計画を心がけることも重要です。
3.勉強しやすい環境を整える
集中して勉強するためには、環境づくりが欠かせません。机の上を整理整頓し、勉強に不要なものを片付けましょう。また、テレビやスマホなどの誘惑を遠ざけ、静かで落ち着いた場所を選ぶことも大切です。
自分にとって最適な環境を整えることで、学習効率が大きく向上します。
4.移動中など隙間時間も有効活用
通学中や待ち時間を上手に活用することで、勉強時間を増やせます。例えば、単語カードを使った暗記や、音声教材を活用したリスニング練習などが効果的です。こうした短時間の積み重ねが、受験期の大きな成果につながります。
5.家庭教師を利用する
受験期に効率よく学習を進めるためには、家庭教師の利用がおすすめです。特に、個人契約ではなく、質が担保された家庭教師会社を選ぶことが重要です。個人契約の場合、指導の質が保証されていないため、期待する成果が得られないこともあります。また、塾では個別指導が高額で、グループ指導では成績が伸び悩むケースも少なくありません。
一方、家庭教師会社では指導方法が徹底されており、安心して任せられます。個別指導により、生徒さんの弱点に的確にアプローチできるため、成績アップが期待できます。さらに、塾よりも費用を抑えられる場合が多いのも魅力です。
ランナーの家庭教師は、特に勉強が苦手なお子さんに寄り添った指導に定評があります。独自の教材を活用し、一人ひとりの学習状況に合わせた効果的な指導を行うため、受験期に非常におすすめの選択肢です。
受験生の中学生が成功するために親ができるサポートをご紹介

受験期はお子さんにとって大きなプレッシャーがかかる時期です。この時期に保護者がどのようにサポートするかによって、学習意欲や成果が大きく変わることがあります。
以下では、受験を乗り越えるために保護者ができる具体的なサポート方法をご紹介します。
今後の進路について親子で一緒に考える
お子さんの将来を見据え、進路について一緒に考えることは重要です。具体的な目標を共有することで、受験への意欲が高まります。また、定期的に話し合う場を設けることで、お子さんの考えや気持ちを確認しながら進路を見直すこともできます。
保護者として過度に押し付けるのではなく、お子さんの意見を尊重しながらサポートしていきましょう。
食事や日常の体調管理に気をつける
健康は受験を乗り越えるための土台となります。栄養バランスの取れた食事を心がけることで、集中力や学習効率が向上します。また、十分な睡眠を確保することも重要です。受験期は体調を崩しやすいため、風邪予防や適度な運動を取り入れた生活習慣を整えましょう。
特に試験直前には、ストレス軽減のためにリラックスできる時間を作ることも大切です。
勉強や成績などの悩みを聞いてあげる
受験期には勉強や成績に関する悩みが出てくることがあります。保護者がその悩みに耳を傾けることで、お子さんの不安を軽減することができます。ただし、アドバイスを押し付けるのではなく、まずはお子さんの気持ちに寄り添う姿勢が大切です。
悩みを共有することで安心感を与え、前向きに取り組む力を引き出しましょう。
中学生の受験生の勉強時間についてまとめ
勉強時間のまとめ
- •平日は学校後に2~3時間を確保するのが理想。
- •休日は4~6時間を目安に、午前と午後でメリハリをつける。
- •時期に応じた学習計画を立て、無理なく継続することが大切。
受験を控える中学生にとって、勉強時間の確保や毎日の積み重ねが合格への重要なポイントです。
特に、夏休みや冬休みといった長期休暇を有効活用し、基礎固めや実戦的な学習を進めることが成功の鍵となります。
コツコツと取り組み、目標に向かって頑張りましょう。
この記事の監修者
マインズ株式会社
本部
大島 あずさ
教育現場を志していたところ、家庭教師という仕事に出会い、「1対1での指導の素晴らしさ」に惹かれ、気がつけば10年になっています。勉強が苦手な子にももちろんですが、「理解することの楽しさ」を一人でも多くのお子さんに伝えるために日々努力しています。
# 経歴
家庭教師歴10年。家庭教師として仕事をしながら教師へのサポート業務も行いつつ、マインズ株式会社に入社。現在はマインズ株式会社本部に所属し、コンテンツ作成やサービス向上のためのコンテンツ制作に勤しんでいる。
# 得意領域
- 学習支援コンテンツ制作
- 勉強が苦手な子へのアプローチ