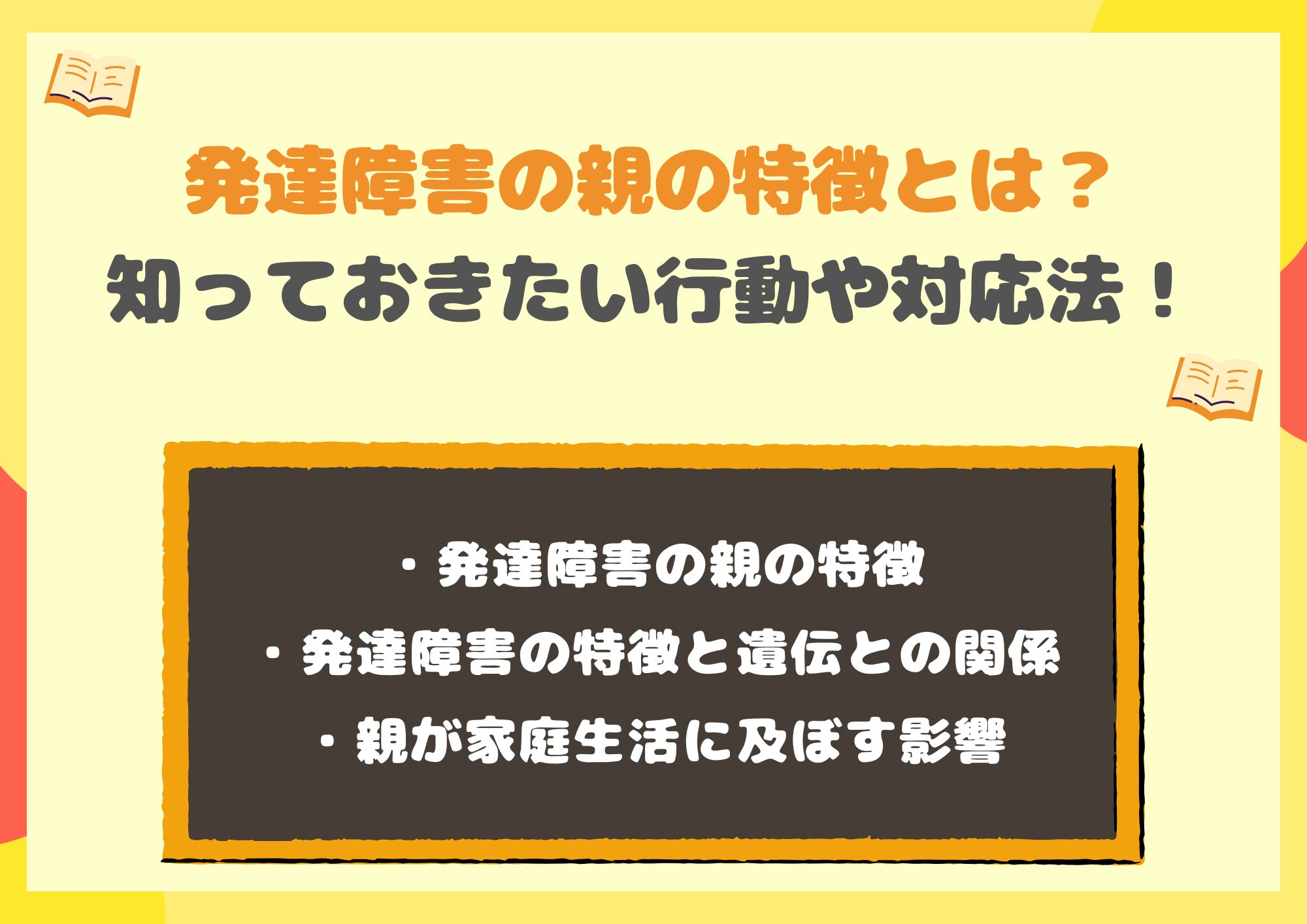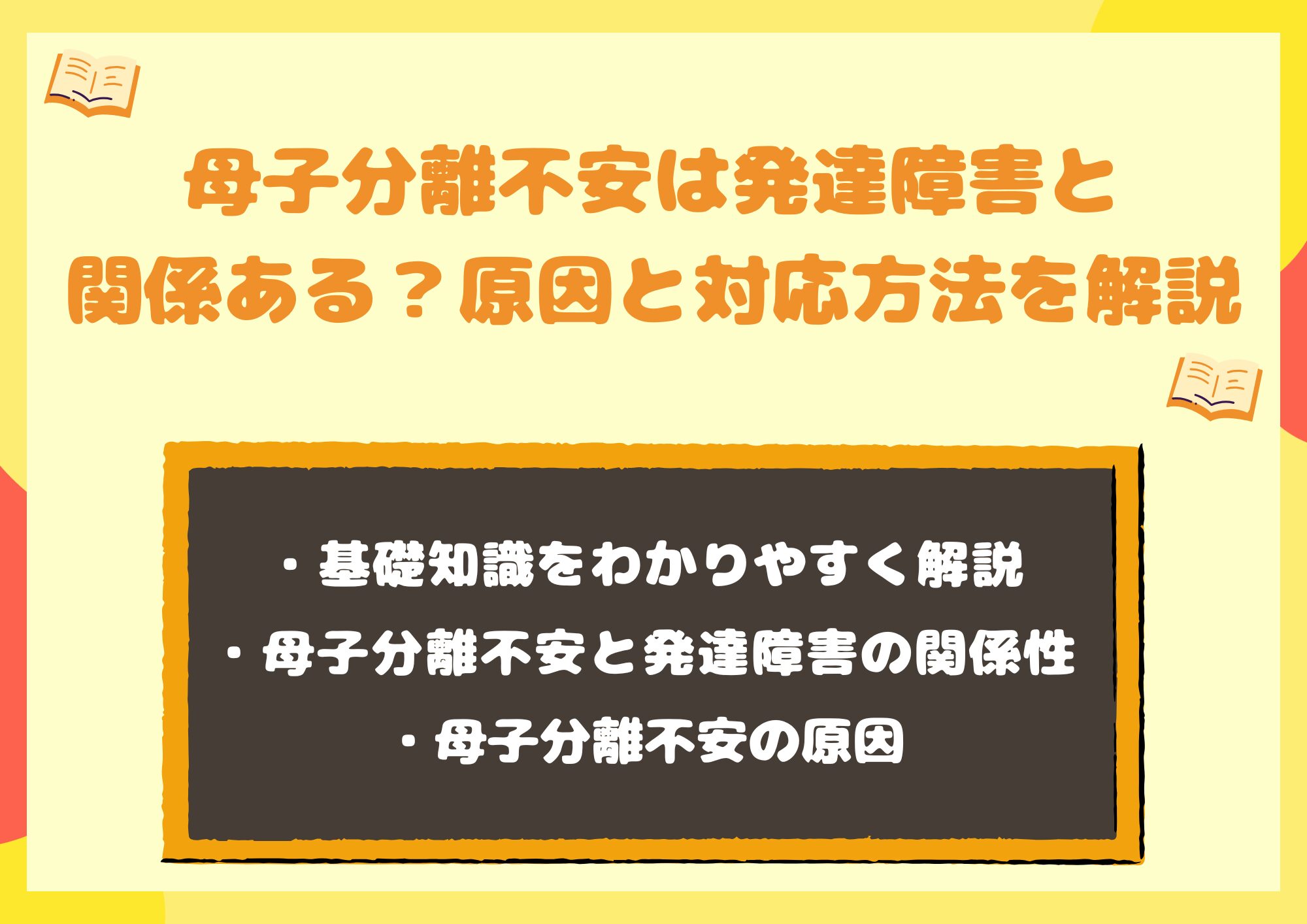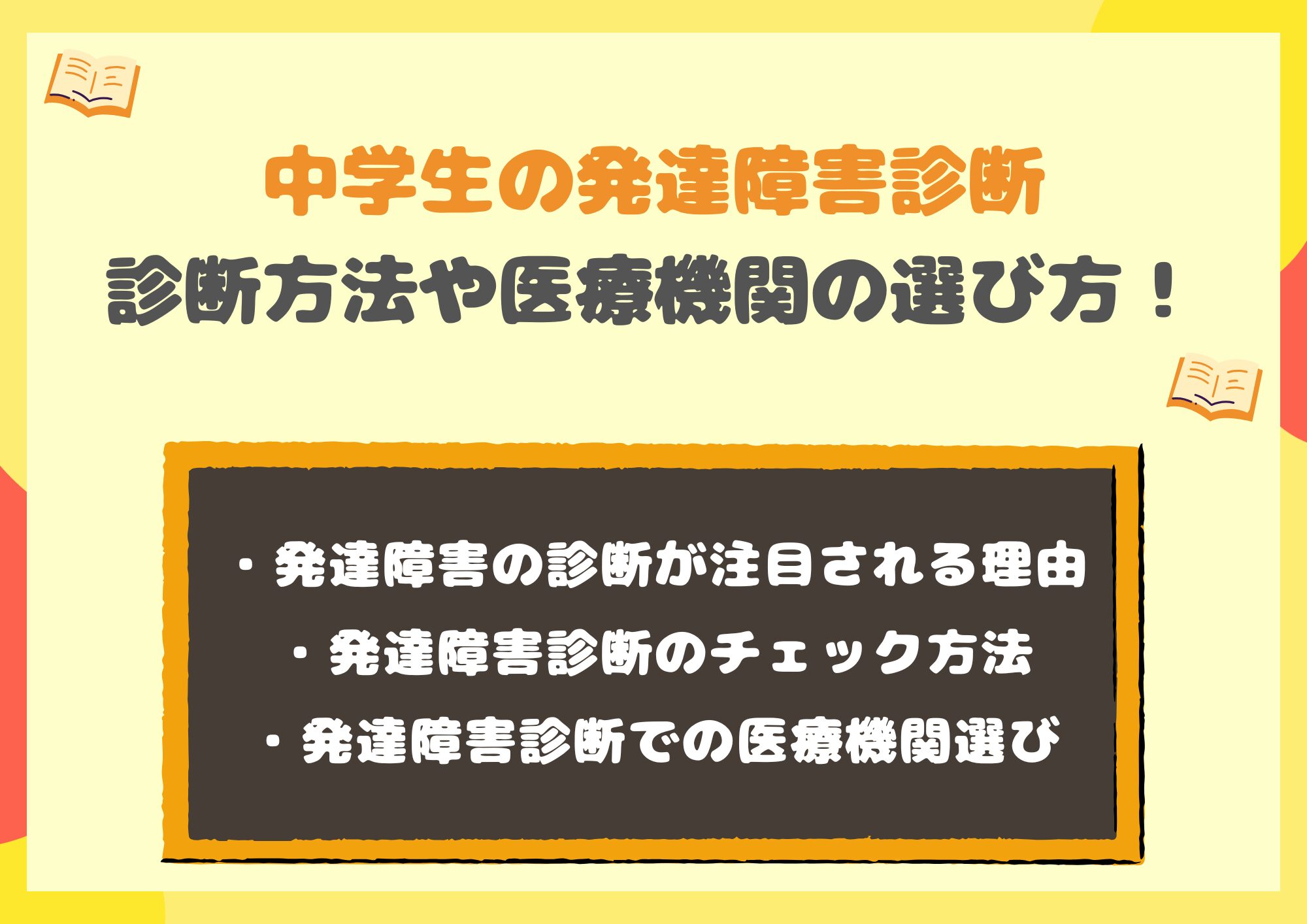- 発達障害向けの家庭教師
親の言うことを聞かない発達障害のある子どもへの対応と家庭教師活用法
2025.08.14

発達障害のあるお子さんが「親の言うことを聞かない」と悩むご家庭は増えています。
なぜ保護者の指示やお願いが伝わりにくいのか、背景や理由を深く理解することは、お子さんへの適切なサポートを始める大きな一歩です。
本記事では、発達障害のある子どもの特性や家庭での対応のコツ、避けたいNG対応、さらに家庭教師サービスを活用した支援例まで、実践的で信頼できる情報を網羅的に紹介します。
親子のコミュニケーションを円滑にし、お子さんの自己肯定感を育てながら、家庭でできる工夫や専門家の力を上手に活用する方法を具体的に解説します。
本記事を通じて、お子さんへの不安をやわらげ、保護者自身も安心して前向きに進めるヒントを得ていただけます。
目次
親の言うことを聞かない発達障害のあるお子さんの悩みが増えている背景
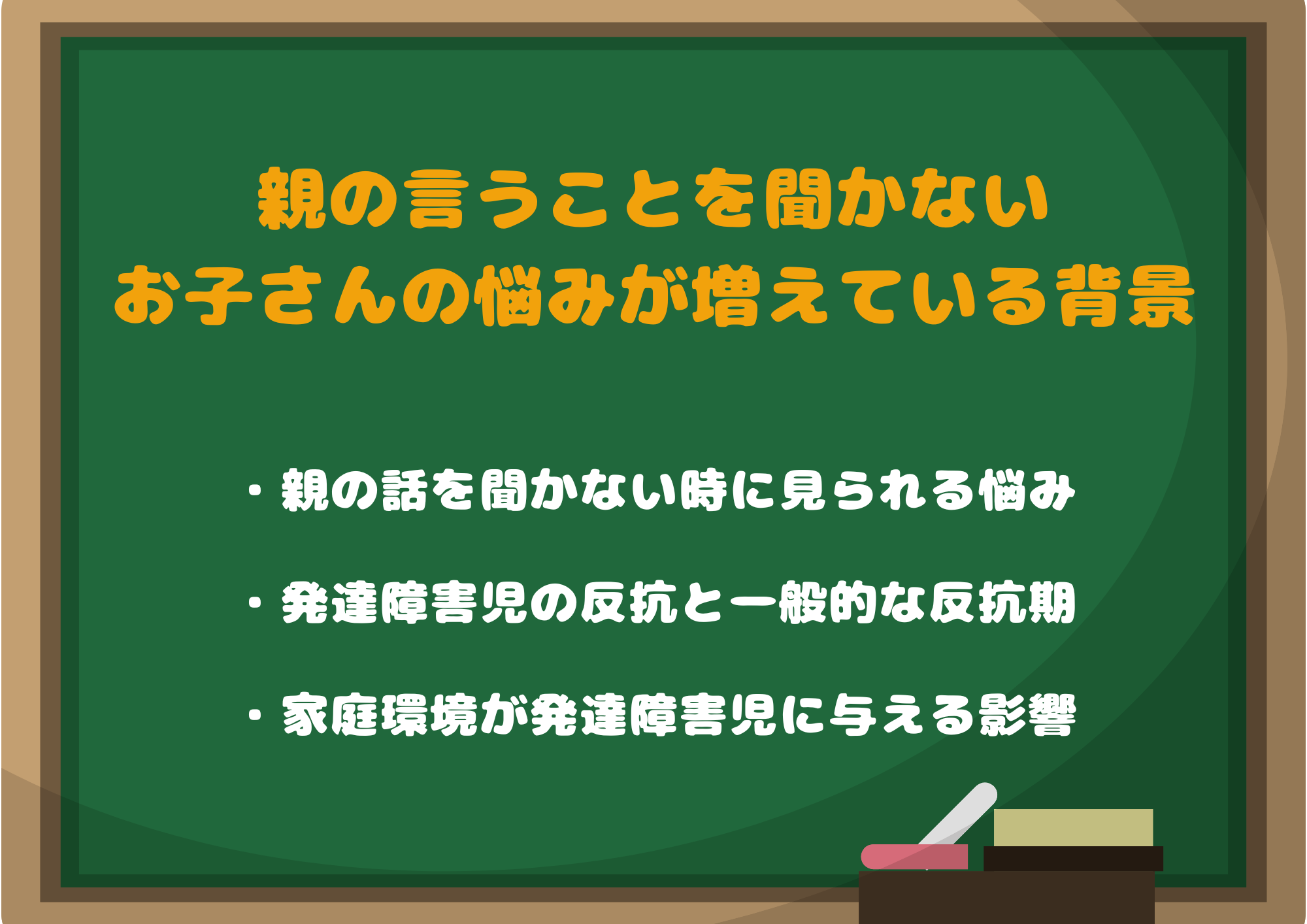
近年、「親の言うことを聞かない」発達障害のあるお子さんについての相談が増えています。
学校や地域社会の理解が進みつつあるものの、家庭内での具体的な接し方に悩む保護者は少なくありません。
お子さんの成長を支えたいのに、うまく伝わらず苛立ちや孤独感を抱えるご家庭が多いのが現状です。
保護者自身が「私の育て方が悪いのか」と自責しがちですが、発達障害の特性は育て方や愛情の有無とは関係ありません。
「なぜ言うことを聞かないのか」ではなく、「どのような支援や工夫で成長できるか」という視点が大切です。
発達障害のあるお子さんが親の話に反応しにくいのは、決してわがままや甘えではありません。
脳の働きや感覚の特性が関係しており、この理解が親子関係を良好に保つ土台となります。
まずは、お子さんの特性や行動を冷静に観察し、「できていない」より「どうしたら伝わるか」に目を向けることが大切です。
発達障害のある子が親の話を聞かない時に見られる悩みと課題
- 親の指示が伝わらず、声掛けに反応しない悩みが多い
- 日常生活のルールや勉強習慣で困り感が強く出る
- 自己肯定感の低下や悪循環に注意が必要
発達障害のあるお子さんが親の指示を聞かない場合、保護者は「声掛けがまったく届かない」「何度言っても反応しない」「やるべきことをやってくれない」など多くの悩みを抱えます。
特に日常生活のルールや支度、勉強の習慣づけなど基本的な場面で困り感が強く現れます。
こうした場合、「発達障害かもしれない」と悩み始め、焦りや不安が強くなることも珍しくありません。
学校や周囲からの指摘で、はじめて専門的な支援や相談の必要性を感じるご家庭も多いです。
また、指示が通らない状況が続くと親子ともにストレスがたまり、叱責や口論が増えてしまうリスクも高まります。
お子さんの自己肯定感が下がり、「どうせできない」「親に認められない」と感じる悪循環に陥ることもあります。
こうした状況を改善するには、お子さんの特性に合った伝え方や環境づくりが欠かせません。
無理に「普通」に合わせようとせず、一人ひとりの得意や興味を見つけて伸ばす姿勢が重要です。
不安な時は一人で抱え込まず、家族や専門家、同じ悩みを持つ保護者のコミュニティとつながることで気持ちも軽くなります。
多くのご家庭で同じような悩みがあるので、孤立せず一歩ずつ支援を活用しましょう。
発達障害児の反抗と一般的な反抗期との違い
- 発達障害の反抗は脳機能の特性やコミュニケーション困難が原因
- 一般的な反抗期とは背景や対応方法が異なる
- 信頼関係を損なわない対応が重要
発達障害のあるお子さんが親の言うことを聞かない時、その行動を「反抗期」と混同しやすいですが、本質は異なります。
一般的な反抗期は成長過程で自立心が強くなることで一時的に指示を拒否したり反発したりしますが、意思疎通や状況判断は基本的にできます。
一方、発達障害のある場合は自分の意思や気持ちをうまく言葉で伝えられなかったり、親の指示自体が理解しづらいなど「脳機能の特性」が関係しています。
感覚過敏や注意力の偏りが原因で、決して「反抗したいから」ではないことが多いです。
また、「ダメ」と言われることで余計に混乱し、反発が強まることもあります。
発達障害児の「反抗」は、周囲の状況や他人の意図が読み取りにくい、予想外の変化に対応しにくいといった困難さが背景にあるのが特徴です。
そのため、親子間の信頼関係を損なわないためにも、「反抗」ではなく「困りごと」と捉え直し、理解を深めることが重要です。
叱る・押し付けるよりも、どうすれば気持ちや意図が伝わるかを一緒に模索していく姿勢が大切です。
家庭環境や親子のコミュニケーションが発達障害児の行動に与える影響
- 家庭内の雰囲気や保護者のストレスが子どもの安定に影響
- 一貫性と安心できる環境が重要
- 保護者自身のメンタルケアも不可欠
家庭環境や親子間のコミュニケーションスタイルは、発達障害のあるお子さんの行動に大きな影響を与えます。
家庭内が落ち着いているとお子さんは安心して過ごせますが、保護者のイライラや不安が強いと、お子さんも不安定になりやすい傾向があります。
発達障害のあるお子さんは、言葉以外の雰囲気や態度に敏感な一方で、保護者の指示の意図がうまく理解できず混乱することも珍しくありません。
また、きょうだい関係や家族全体のルールづくりも、行動パターンに影響します。
一貫性があり安心できる環境づくりがポイントです。
「言うことを聞かない」の背景には、保護者自身の疲れやストレスが大きく関わっている場合もあります。
そのため、保護者自身の心身の健康やメンタルケアも、お子さんの安定した成長のためには不可欠です。
時には「完璧な親」を目指さず、周囲のサポートを頼る勇気も大切です。
親の声掛けが届きにくい発達障害のあるお子さんに見られる特徴や主なタイプ
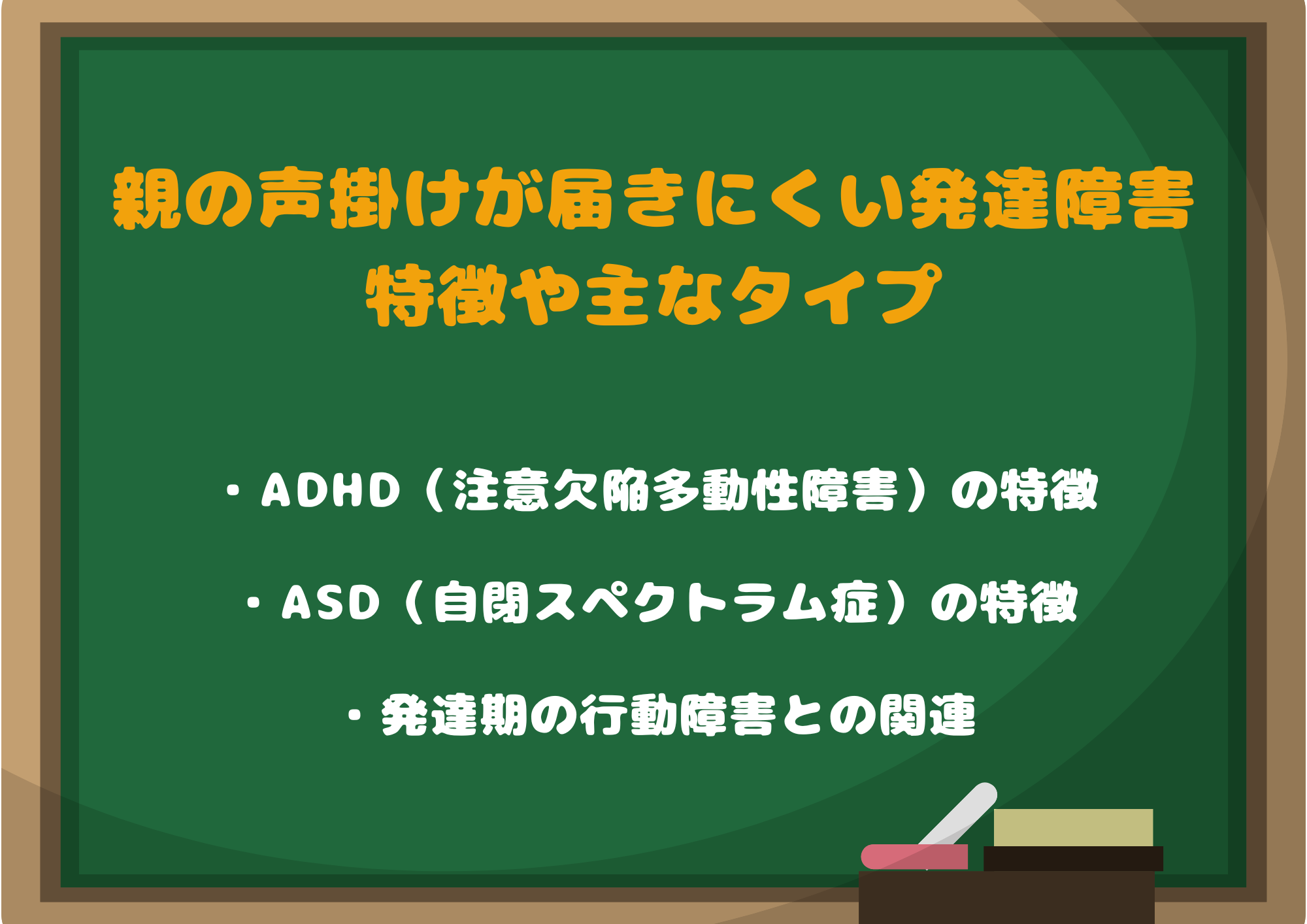
発達障害のあるお子さんが保護者の声掛けに反応しにくい背景には、さまざまなタイプや特性が関わっています。
主なタイプとしてはADHD(注意欠陥多動性障害)、ASD(自閉スペクトラム症)、発達期の行動障害(例:反抗挑戦性障害/ODD)などが挙げられます。
それぞれの特性を知ることで、お子さんに合った接し方が見つけやすくなります。
まずはどのような傾向があるか、詳しく見ていきましょう。
お子さんが「どうしてできないの?」と責められることなく、個性を大切にし強みを伸ばしていくことが重要です。
ADHD(注意欠陥多動性障害)による「言うことを聞かない」傾向の特徴
- 指示への注意の持続が難しく衝動的な行動が目立つ
- 言葉での説明より視覚サポートや短いフレーズが効果的
- できたことを認める声掛けや環境設定が重要
ADHDのあるお子さんは、「親の言うことを聞かない」と見られやすい傾向が顕著です。
これは指示に注意を向け続けることが難しい、思いついたらすぐ行動してしまう衝動性(impulsivity)、静かにじっとしていられない多動性(hyperactivity)が組み合わさるためです。
保護者が「何度も同じことを注意しても伝わらない」と感じるのは、忘れやすさや集中力の持続が苦手な特性によるものです。
また、言葉での指示だけでは理解が難しく、視覚的なサポートや短いフレーズで伝える工夫が必要です。
ADHDのお子さんは興味があることには高い集中を見せる一方、苦手なことや退屈な作業には注意を向けにくい傾向があります。
そのため、怒るよりも「何ができたか」を認める声かけや、行動がしやすい環境設定が重要です。
「だらしない」「ふざけている」と決めつけず、特性に合わせた伝え方とサポートを心がけましょう。
保護者が特性を理解し接し方を工夫するだけでも、親子関係が大きく変わります。
ASD(自閉スペクトラム症)による親の言葉が伝わりにくいケースの特徴
- あいまいな表現や抽象的な指示が伝わりにくい
- 予定変更や急な指示で混乱しやすい
- 具体的で一貫性のある伝え方が有効
ASD(自閉スペクトラム症)の場合、「親の言葉が伝わりにくい」「言うことを聞かない」と感じる特徴があります。
これは、暗黙の了解やあいまいな表現の理解が難しく、相手の気持ちや意図を読み取るのが苦手な特性が関係しています。
例えば「ちゃんと片付けてね」と言われても、何をどう片付けるのか具体的な指示がなければ動きにくいです。
より伝わる例として「机の上の鉛筆と教科書を引き出しにしまってね」と具体的に伝えることで理解しやすくなります。
また、予定の変更や急な指示に強いストレスを感じ、急かされるとパニックになる場合もあります。
ASDのお子さんには、「具体的で一貫性のある伝え方」「手順を見える化するサポート」が特に有効です。
安心して取り組める環境を整え、ルールや流れを分かりやすく伝えることがポイントです。
発達期の行動障害(例:反抗挑戦性障害/ODD)との関連
- 大人の指示やルールに反発しやすい
- 否定や叱責で行動がエスカレートしやすい
- 安心できる雰囲気や認めるコミュニケーションが重要
ADHDやASD以外にも、発達期の行動障害(例:反抗挑戦性障害/ODD)が関連する場合があります。
ODDはDSM-5で「行動障害」に分類され、「怒り・易刺激性・挑発行動が6か月以上持続する状態」と医学的に説明されています。
大人の指示やルールに反発しやすく、時に意図的に反抗するように見える態度が続きます。
ただし、根本には「理解されない」「認められない」といった心理的な葛藤が隠れていることが多いです。
ODDのお子さんは、否定や叱責を受けることで反抗的な行動がエスカレートしやすい傾向があります。
ADHDやASDと重なって現れることも多く、複数の特性が絡み合う場合もあります。
「どうしてうまくいかないのか」と悩む前に、お子さんが安心して話せる雰囲気や、できたことを認めるコミュニケーションを意識しましょう。
適切な理解と支援があれば、自己肯定感を回復し、前向きな行動も増えていきます。
発達障害のある子どもが指示やお願いに反応しにくい主な理由
発達障害のあるお子さんが「親の指示やお願いに反応しにくい」と感じる背景には、さまざまな要因があります。
単なる「わがまま」や「怠け」ではなく、脳機能や感覚、発達特性によるものです。
保護者が困り感に気づき、適切なアプローチを知ることが親子関係をより良くする第一歩となります。
ここでは主な理由と、早期理解・支援の重要性について解説します。
「なぜ伝わらないのか」を冷静に分析し、お子さんに合った声掛けや環境づくりに役立てましょう。
行動面や感覚面での発達障害特性が影響する例
- 感覚過敏・鈍麻により指示が伝わりにくい場合がある
- 成長とともに困りごとや得意が変化する
- 具体的な声掛けや環境調整で行動しやすくなる
発達障害のあるお子さんは、行動面や感覚面で独自の特性を持っています。
聴覚や視覚の感覚過敏・鈍麻があると、普通の声掛けがうまく伝わらなかったり、指示内容が頭に残りにくいことがあります。
ADHDの「注意の切り替えが苦手」「集中が続かない」といった特性も、指示に反応しない原因となります。
ASDの場合、あいまいな表現や状況判断が必要な場面で特に混乱しやすく、結果として動けなくなることも少なくありません。
これらの特性は成長とともに変化することもあり、その時々の困りごとや得意な部分を丁寧に観察することが大切です。
保護者が「こうあるべき」という先入観を捨て、具体的な声掛けや環境調整を行うことで、お子さんが安心して行動できるようになります。
脳機能の特性から考える親子コミュニケーションの難しさ
- 発達障害は脳機能の違いによるもの
- 優しい声掛けでも伝わらない場合がある
- 脳特性を理解したアプローチが信頼関係維持の鍵
発達障害は「脳機能の違い」によるものと医学的に説明されています。
例えばADHDは脳内の情報伝達物質のバランスが関係し、注意や行動のコントロールが難しくなります。
ASDでは社会的な合図や相手の意図を読み取る神経ネットワークの働きに特徴があります。
このような脳の働きによる違いは、単なる「性格の問題」ではありません。
保護者がどれだけ優しく伝えても、脳の機能的な特性で伝わらないことがあるのです。
しかし、正しく理解し受け止めることでお子さんは安心し、「自分は悪くない」と感じることができます。
保護者も「どうして伝わらないの?」というストレスから解放され、落ち着いて接することができます。
脳機能の特性に基づいたアプローチを意識することが、親子の信頼関係を守る近道です。
二次障害リスクと早期理解・支援の重要性
- 誤解や厳しい叱責で自己肯定感が低下しやすい
- 不安・抑うつ・二次障害のリスクがある
- 早期の気づきと専門サポートの活用が重要
発達障害の困り感に気づかず、「怠け」「わがまま」「反抗」と誤解して厳しく叱り続けると、自己肯定感を失いやすくなります。
その結果、不安や抑うつ、引きこもりや暴力など「二次障害」に発展するリスクが高まります。
「なんでできないんだろう」「自分はダメな子なんだ」と感じることで、ますます保護者の言葉が届かなくなる悪循環が生まれます。
そのため、早期に「発達特性があるかもしれない」と気づき、専門機関や家庭教師サービスなどの支援を利用することが重要です。
専門的なアドバイスや外部サポートを受けることで、保護者も安心し、お子さんと余裕を持って向き合えます。
「お子さんの味方」でいるために、早めの支援を積極的に活用しましょう。
家庭でできる発達障害児の対応方法と効果的な工夫
発達障害のあるお子さんには、家庭での小さな工夫や環境調整が大きな安心と自信につながります。
ポイントは「分かりやすく・見通しを持てること」と、「できた」を積み重ねられる仕組みづくりです。
無理に叱ったり、普通に合わせたりするよりも、少しのコツで日々がぐっとラクになります。
ここでは家庭で取り組める具体的な対応例や声掛け、肯定的な関わり方を紹介します。
親子で笑顔が増える工夫を、今日から始めてみましょう。
家の中で取り組める環境調整や視覚支援の工夫
- 「見てわかる」リストやタイマー活用が効果的
- 色分けやマークで持ち物・場所を区別
- 急な予定変更は事前予告で不安を軽減
発達障害のあるお子さんは、環境の変化や刺激に敏感だったり、見通しの立たない状況に不安を感じやすい傾向があります。
そのため、家の中では「何を・どこで・どうすればよいか」がひと目でわかる環境づくりが効果的です。
たとえば、やるべきことをリスト化して壁に貼る、タイマーで時間を可視化する、色分けやマークで持ち物や場所を区別するなど視覚的なサポートが有効です。
また、片付けやすい収納、静かに落ち着けるスペース、急な予定変更を事前に知らせるなどの配慮の積み重ねが大切です。
「見てわかる仕組み」を取り入れることで、親子のストレスが大幅に軽減します。
伝わりやすい声掛けやコミュニケーションのポイント
- 短く具体的に一度にひとつだけ伝える
- 「何を・どのくらい・いつまで」かを明確に
- できたことはすぐ認め、肯定的な言葉を意識
発達障害のあるお子さんには、「どう伝えるか」がとても重要です。
長く複雑な指示や抽象的な言い方は伝わりにくいため、短く・具体的に・一度にひとつずつ伝えることを意識しましょう。
「ちゃんと勉強して」よりも「今から10分間、漢字を書こうね」のように行動内容と時間を明確にするのがポイントです。
できたことをすぐに認めてあげることで、「分かってもらえた」とお子さんも安心感を得られます。
否定よりも肯定の言葉を増やし、「これなら自分にもできる」と思える声掛けを意識しましょう。
伝え方を工夫することで、親子のコミュニケーションがぐっとスムーズになります。
ほめ方・肯定的な関わりで伸ばす自己肯定感
- 結果だけでなく努力や過程もほめる
- 具体的な場面を取り上げて声掛け
- 肯定的な関わりで自信を育てる
発達障害のあるお子さんは、日常の中で失敗体験が重なりやすく、自己肯定感が下がりがちです。
だからこそ、「できたこと」「がんばったこと」を見つけて積極的にほめることが、自己肯定感を育てる鍵となります。
ほめるときは結果だけでなく、努力や過程も一緒に認めるのがコツです。
たとえば「最後まで机に座れたね」「今日は忘れ物を減らせたね」と、具体的な場面を取り上げて声をかけましょう。
肯定的な関わりを意識することで、お子さんは少しずつ自信を持てるようになります。
シンプルなルールづくりと行動習慣化のすすめ
- 家庭内のルールはできるだけシンプルに
- 繰り返し伝えて習慣化をサポート
- 「ルールが守れる仕組み」づくりを意識
発達障害のあるお子さんは、「複雑なルール」や「状況によって変わる決まり」が苦手な傾向があります。
そのため、家庭ではできるだけシンプルで分かりやすいルールを設定し、繰り返し伝えてあげることが効果的です。
「帰宅したら手を洗う」「寝る前にランドセルを準備する」など、一つひとつの行動を絵や文字で見える化し、習慣化できるようにサポートしましょう。
一度に多くを求めず、小さな約束を守れたら積極的にほめて、できることを少しずつ増やすと達成感を味わいやすくなります。
「ルールを守る」よりも「ルールが守れる仕組みづくり」を意識することで、保護者もお子さんもストレスを減らせます。
シンプルな決まりと行動の積み重ねが、日常生活をスムーズにし自信の土台となります。
実践しやすい声掛け・接し方の具体例
- 「具体的・短く・ひとつずつ」が基本
- できたことをすぐその場で認める
- 失敗時も寄り添いながら励ます
発達障害のあるお子さんに響く声掛けは、「具体的で短く」「ひとつずつ」「できたことをすぐ認める」ことです。
たとえば「今から10分だけお片付けしよう」「机の上の本を本棚に戻そう」といった、すぐに行動できる内容で伝えるのがポイントです。
「〇〇できて偉かったね」「さっきのやり方良かったよ」と結果や行動をその場で伝えることで、達成感や自信に繋がります。
失敗やできなかった時は叱るのではなく、「次はどうしたらできるか一緒に考えよう」と寄り添う姿勢が大切です。
保護者が「できた!」に注目することで、お子さん自身も前向きにチャレンジしやすくなります。
ちょっとした声掛けの工夫が、親子の関係性を大きく変える力となります。
発達障害のある子どもと接する上で避けたいNG対応
どんなに愛情を持って接していても、発達障害の特性を理解せずに関わると、お子さんがさらに不安定になったり、親子の信頼関係が揺らいだりすることがあります。
ここでは「ついやってしまいがちなNG対応」と、その理由や注意点を解説します。
大切なのは「ダメな親」と自分を責めることではなく、気づいたその時から対応を変えていくことです。
親子で成長できるコミュニケーションを意識し、安心して相談できる環境を整えましょう。
お子さんの良い変化を信じて、一緒に前を向いて進んでいきましょう。
つい叱ってしまいがちな場面で気をつけたいポイント
- 大きな声で叱る・繰り返し注意は逆効果になりやすい
- 人格否定にならないように注意
- できなかった時は一緒に解決策を考える
発達障害のあるお子さんは、ルールや順序が理解しづらかったり、注意がそれやすかったりと「保護者が期待する行動」が難しい場合がよくあります。
そんなとき、保護者はついイライラして大きな声で叱ったり、何度も同じことを注意しがちですが、これは逆効果になることが多いです。
叱られ続けることで自己肯定感が下がり、「やる気がなくなる」「無力感を感じる」といった悪循環につながります。
「ダメなことはダメ」と伝えるのは必要ですが、強い否定や人格否定にならないよう注意しましょう。
できなかったことを責めるより、「どうしたらできるか」を一緒に考える姿勢が大切です。
叱る回数より、認める回数を増やすことで、お子さんは徐々に前向きに変化します。
親子の信頼関係を保つために注意したい対応
- 「できないこと」より「できたこと」に目を向ける
- 失敗時も「どうすればできるか」を一緒に考える
- 保護者が感情的になりすぎないことが大切
親子の信頼関係は、お子さんの心の安定や自己肯定感の発達に非常に重要です。
そのためには「できないこと」ばかり指摘せず、「できたこと」に目を向けてコミュニケーションを取ることが欠かせません。
約束を守れなかった時も「あなたはダメ」と決めつけるのではなく、「どうすればできるようになるかな」と一緒に考えたり、できた時はすぐに認めることを意識しましょう。
保護者が感情的になりすぎると、お子さんは「どうせ何をしても無駄」と感じやすくなります。
気持ちを落ち着けて、「親は味方」と思ってもらえる関係性を保つことが大切です。
信頼関係は「できた!」の積み重ねと、保護者の一貫した愛情によって築かれます。
大人自身が守るべき約束と一貫性の大切さ
- 大人の都合でルールを変えない
- 保護者も決めた約束は必ず守る
- 一貫した対応が安心感・信頼構築の基本
発達障害のあるお子さんは、約束やルールの一貫性がないと混乱しやすくなります。
「昨日は良かったのに今日はダメ」「お父さんとお母さんで言うことが違う」といった状況では、どちらを信じて良いのか分からなくなってしまいます。
保護者自身が決めたルールを守り、大人の都合で変えないことが重要です。
また、「○○したら一緒に遊ぼうね」「終わったらおやつにしよう」といった約束も、必ず守るよう心がけましょう。
大人が約束を守る姿を見せることで、お子さんも安心して日々の生活に取り組めます。
一貫した対応と約束を守る姿勢が、信頼構築の基本となります。
発達障害や指示が通りにくい子どもにおすすめの家庭教師サービス
発達障害のあるお子さんや「親の指示が伝わりにくい」と感じるご家庭では、家庭教師サービスの活用が大きな支えになります。
マンツーマンで個々の特性や困りごとに合わせた指導が受けられるため、自己肯定感の向上や学習習慣の定着にもつながります。
ここでは、発達障害やコミュニケーションが苦手なお子さんにも適した、信頼できる家庭教師サービスを厳選して紹介します。
プロの力を借りて、お子さんの「できる!」を増やしましょう。
家庭教師のランナーが発達障害やコミュニケーションが苦手な子に選ばれる理由

- 発達障害・不登校など多様なニーズに特化
- オーダーメイドの指導プランを提案
- 心理的ケアや学習習慣づくりもサポート
- オンライン指導やICTツールの活用も可能
- 月謝制・入会金・管理費あり。高額テキスト販売なし
「家庭教師のランナー」は、発達障害や学習の遅れ、不登校など多様なニーズに対応した家庭教師サービスです。
お子さんの特性や状況に応じて、最適な指導プランをオーダーメイドで提案しています。
「勉強が苦手」「やる気が続かない」「集団になじめない」といった中学生にも、コミュニケーションを大切にした指導で自信や学習意欲の向上を目指します。
定期テスト対策や課題管理、受験準備まで幅広くサポート。
発達障害や不登校に詳しい専門スタッフが在籍し、心理的なケアや家庭での学習習慣づくりも相談できます。
オンライン指導にも対応(対応地域は要確認)し、ZoomやLINEなどのICTツールを活用した質問サポートも利用できます。
一人ひとりに合わせた指導で、保護者とともに安心して学習環境を整えられる点が大きな強みです。
指導内容やサポート範囲、料金体系の詳細は無料体験でご確認ください。
家庭教師のトライによる個別サポートの特徴

- 全国33万人超の講師から最適な先生を選べる
- 専任プランナーによる家庭と教師の橋渡し
- 発達障害・コミュニケーションが苦手な子にも柔軟対応
- オンライン指導・講師交代無料・厳しい採用基準
- 月謝制・入会金・管理費あり。高額テキスト販売なし
家庭教師のトライは、全国33万人超の講師から相性の合う教師を選べる大手サービスです。
専任の教育プランナーが家庭と教師をつなぎ、きめ細やかな学習計画や相談対応を実施しています。
発達障害を持つお子さんにも、マンツーマンの「トライ式学習法」で特性や理解度に合わせたカリキュラムを提案します。
オンライン指導にも対応し、全国どこでも自宅でプロの指導が受けられるため、集団授業が苦手なお子さんやご家庭にも最適です。
厳しい採用基準や講師交代無料制度も安心材料です。
月謝制で高額教材の販売はなく、入会金・管理費(月額)は発生します。
一人ひとりの課題やペースに柔軟に合わせた学びを実現できます。
詳細な料金やサポート範囲は公式サイトまたは無料相談にてご確認ください。
学研の家庭教師が発達障害を持つお子さんに合うポイント

- 大手教育グループの安心と長年のノウハウ
- 厳選講師&オンライン指導対応
- 進路・生活面のサポートも充実
- 月謝制・入会金・管理費あり。高額テキスト販売なし
学研の家庭教師は、大手教育グループならではの安心感と長年のノウハウが強みです。
厳選された大学生からプロ講師まで幅広い講師陣が在籍し、お子さんの状況や学年に合わせて最適な先生を紹介します。
発達障害や学習の遅れ、不登校などにも理解があり、個々に合わせたサポートが可能です。
オンライン指導にも積極的で、通塾が難しいご家庭でも「いつもの先生」と安心して学べます。
「学研」ブランドの信頼と、教師と本部スタッフの密な連携による進路相談・生活面サポートも人気の理由です。
料金体系は月謝制で、高額な教材販売はなく、入会金・管理費が必要です。
お子さんの特性や課題をしっかり理解し、長期的な視点で成長を支えます。
詳細は公式サイトや相談窓口でご確認ください。
家庭教師サクシードで実現する安心の学習サポート

- 東証グロース上場の信頼とコスパの高さ
- 体験授業の先生がそのまま担当
- 柔軟な学習計画&複数科目対応
- 教材費・入会金ゼロ。月謝制
家庭教師サクシードは、東証グロース上場・株式会社サクシード(証券コード9256)が運営する安心感とコストパフォーマンスの高さが特長です。
学生から社会人まで13万人超の厳選講師がマンツーマンで丁寧な指導を行います。
体験授業を担当した先生がそのまま正式担当となるので、お子さんがリラックスして学べると好評です。
発達障害のお子さんにも柔軟な学習計画とコミュニケーションを大切にした対応を重視しています。
教材費や入会金ゼロで始めやすく、1回の授業で複数科目に対応できるなど、ご家庭のニーズに寄り添った運営です。
担当教師と本部スタッフがダブルで学習をサポートし、急な不安や困りごとにも迅速に対応できます。
お子さんとご家庭の安心と満足を両立できる家庭教師サービスです。
サポート内容や詳細は公式サイトでご確認ください。
家庭教師ファーストの柔軟な対応が発達障害のお子さんにもおすすめな理由

- 低価格で全国展開・幅広い講師陣
- 無料体験後にそのまま契約もOK
- 発達障害・不登校のお子さんにも柔軟対応
- フォロー体制や入会後のサポートも充実
- 月謝制で入会金・管理費あり。高額教材販売なし
家庭教師ファーストは、低価格で質の高い指導を全国展開する準大手サービスです。
学生から社会人まで幅広い講師が在籍し、目的やお子さんの個性に合わせて最適な先生を紹介できます。
無料体験授業を経てそのまま契約できるため、初めて家庭教師を利用するご家庭でもミスマッチが起こりにくいのが特長です。
発達障害や不登校のお子さんにも対応しやすいカリキュラムやフォロー体制が整っており、長期的な学習も安心して続けられます。
2025年最新料金例では、小学生補習コース(60分×月4回)が9,240円など、リーズナブルな料金も魅力です。
テスト対策から受験、不登校支援まで幅広くサポートし、入会後の丁寧なフォローも保護者から高い評価を得ています。
一人ひとりの状況に柔軟に寄り添う姿勢が、発達障害のお子さんにも最適です。
サービスの詳細は公式サイトや無料相談でご確認ください。
ノーバスによる発達障害の子へのきめ細やかな指導

- 老舗ならではの講師の質と安心感
- 個別指導塾ノウハウのきめ細やかなサポート
- 教材販売なし・既存教材活用
- 教務スタッフと講師のダブルサポート体制
- 月謝制・入会金・管理費あり
家庭教師のノーバスは、老舗の安心感と講師の質に定評がある大手サービスです。
プロ家庭教師から大学生まで幅広い講師が在籍し、個別指導塾のノウハウを活かしたきめ細やかな学習サポートを実現しています。
発達障害や不登校のお子さんにも、無理のない範囲から丁寧に指導を進めることで、自己肯定感を高めながら学習できます。
教材販売がなく、既存教材や手持ち教材を活用できるシンプルな料金体系ですが、初期登録費や月額サポート費(例:月額管理費3,300円、入会金など)が別途必要です。
教務スタッフによるダブルサポート体制もあり、保護者の不安や悩みにもスムーズに対応しています。
お子さんのペースを大切にした指導で、無理なくステップアップできます。
サービス内容や詳細は公式サイトにてご確認ください。
あすなろの家庭教師が親しみやすい理由と発達障害のサポート体制
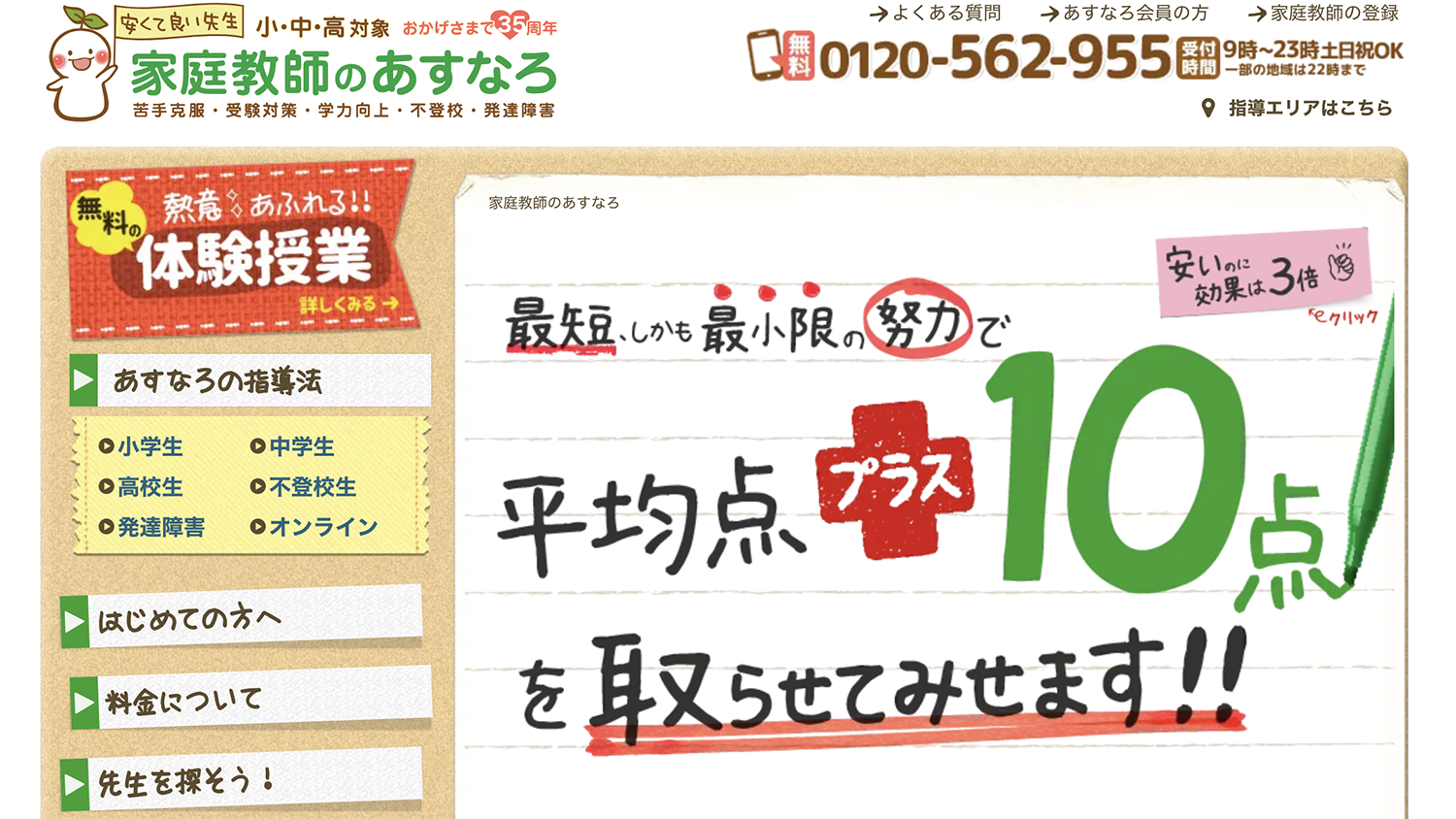
- 勉強が苦手な子専門で親身な指導
- 若い大学生講師が多く、子どもが心を開きやすい
- LINE無料サポート・全国ネットワーク
- 「できた体験」を積み重ねる指導が得意
- 月謝制・入会金・管理費あり。高額教材販売なし
家庭教師のあすなろは、「勉強が苦手な子専門」を掲げ、発達障害や学習遅滞、不登校など多様な子どもたちに親身な指導を行っています。
大学生中心の若い先生が多く、年齢が近いため子どもが自然に心を開きやすい点も大きな魅力です。
LINEでの無料サポートや全国ネットワークによる経験豊富な教師の紹介があり、地方でも安心して利用できます。
発達障害のお子さんには「できた体験」を積み重ねる指導スタイルが自信の回復につながり、親子とも無理なく学習が続けられます。
保護者へのフォロー体制も手厚く、「困ったときにすぐ相談できる」安心感も人気です。
勉強が苦手・発達障害のお子さんに“寄り添う力”が光る家庭教師サービスです。
サポート内容の詳細は公式サイトや無料相談でご確認ください。
学参による発達障害児へのプロ指導のメリット

- プロ家庭教師専門センターならではの安心感
- 発達検査や特性に応じた柔軟な指導法
- 無料体験・複数講師提案で相性確認可能
- 月謝制・入会金・管理費あり。教材販売なし
学参は、創業40年以上の歴史を持つプロ家庭教師専門の紹介センターです。
登録講師はすべて指導経験者で厳選されており、発達障害や不登校にも深い理解をもつ教師を選べます。
発達検査や特性に応じた柔軟な指導法を用意し、学力だけでなくコミュニケーション面や生活リズムにも対応可能です。
オンライン・訪問の両方に対応し、遠方でも質の高いプロ指導を受けられます。
希望に合わせて講師を複数提案してもらえ、無料体験授業でお子さんとの相性も確認できます。
経験豊富なプロ講師による“寄り添う”指導で、苦手意識や自信喪失の改善に最適です。
サービス内容の詳細は公式サイト等でご確認ください。
合格王のマンツーマン指導が発達障害児に向いている理由

- 厳選された指導経験豊富な教師が担当
- 担任+教務スタッフの二重サポート体制
- 「できた!」体験を重視したコーチング型指導
- 講師交代無料・個別カリキュラム対応
- 月謝制・入会金・管理費あり。教材販売なし
合格王は「合格」に徹底フォーカスしたマンツーマン指導と手厚い教務サポートが魅力です。
採用基準が厳しく、指導経験豊富な教師のみを採用し、発達障害のお子さんにも一人ひとりに合わせたカリキュラムを提供します。
担任教師+教務スタッフの二重サポート体制で、保護者も安心して相談や学習管理を任せられます。
生徒の「できた!」体験を重視したコーチング型指導が、自己肯定感の向上にもつながります。
講師交代も無料で対応し、お子さんに合った教師が見つかるまで徹底サポートしてくれます。
苦手や不安が強い発達障害のお子さんでも“できる自信”を積み重ねられる家庭教師サービスです。
詳細は公式サイトや相談窓口でご確認ください。
ジャンプの家庭教師が特別なニーズに強い理由

- 正社員プロ教師100%の専門センター
- 検査結果や特性に応じたカリキュラム設計
- 本部と現場の連携による安心サポート
- 初回家庭訪問で丁寧なヒアリング
- 月謝制・入会金・管理費あり。教材販売なし
ジャンプの家庭教師は、発達障害や学習障害、不登校など特別なニーズに対応する正社員プロ教師100%の専門センターです。
全教師が正社員で独自研修を受けた経験豊富なプロのみで、指導品質が安定しています。
WISCなどの検査結果や特性に合わせたカリキュラムで、自己肯定感を育てる指導を重視しています。
初回の家庭訪問では本部スタッフが同席し、保護者の悩みやお子さんの困りごとを丁寧にヒアリングします。
本部と現場が連携したサポートで、多くのご家庭から「頼れる存在」として信頼されています。
訪問中心ですが、状況に応じてオンラインでの相談や指導導入も可能です。
発達障害や二次障害リスクが高いお子さんにも最適な“安心と専門性”を提供します。
公式サイトや無料相談で詳細をご確認ください。
発達障害児と家庭教師を併用したサポート成功事例
家庭教師サービスの活用により、「親の言うことを聞かない」と悩んでいたご家庭にも明るい変化が生まれています。
ここでは実際に家庭教師を利用して自己肯定感ややる気が向上した成功例、ご家庭のリアルな声を紹介します。
専門家と一緒に「できた!」体験を増やし、家庭全体が前向きになるサポート事例です。
家庭教師を活用して自己肯定感ややる気を高めた実例
- 「できた!」を積み重ねて自信回復
- 保護者も余裕を持って接する変化が生まれる
- 視覚支援や短時間集中学習が効果的
小学校2年生・男児の例では、学校や家庭で指示が通らず叱られてばかりでしたが、「家庭教師のランナー」でマンツーマン指導を開始。
先生が“できた!”を見つけてすぐに褒めてくれるので、本人も自信を持てるようになり、家庭での声掛けにも徐々に反応できるようになりました。
ADHD傾向が強く忘れ物や注意散漫が目立っていた中学1年生も、家庭教師サクシードの担当講師による視覚支援や短時間集中学習の導入で、「自分でもやればできる」と思えるようになりました。
保護者も「子どもにイライラせずに接する余裕ができた」と変化を実感しています。
このように、専門家のサポートと家庭の工夫を組み合わせることで、自己肯定感ややる気が大きく高まる事例が多くあります。
「わかる」体験が増えたことで変化した家庭の声
- 「できない」が「できた!」に変わる成功体験
- 親子の気持ちも前向きに変化
- 家庭内の緊張・不安が軽減
「何度言っても聞いてくれない」「勉強が手につかない」と悩んでいたご家庭が、家庭教師のノーバスを利用したことで「分からなかった問題が分かるようになった!」というお子さんの声が出るようになりました。
学研の家庭教師では、指導前は「自分は勉強ができない」と自信を失っていたお子さんが、担当教師と一緒に課題を分解し一つずつ取り組むことで、「やればできる!」と前向きな気持ちを持てるようになった体験談も多いです。
どのご家庭も、「家庭教師を利用して、親子ともに気持ちが軽くなった」と感じています。
専門家に頼ることで、家庭内の緊張や不安が減り、親子の笑顔が増えるという変化が現れています。
発達障害のある子どもの進路・就学・将来を見据えたサポートのコツ
発達障害のあるお子さんにとって、進路や将来に関する不安は保護者にとっても大きな悩みの一つです。
小学校・中学校のうちは「今」の困りごとへの対応が中心になりがちですが、長い目でどのように成長を支え、社会に羽ばたく準備をしていくか考えることが大切です。
ここでは進路選択や就学準備、将来を見据えたサポートのコツを具体的に紹介します。
お子さんの「好き」や「得意」を活かせる環境を整え、親子で明るい未来を描きましょう。
長期的な視点で考える支援のポイント
- 短期的な問題解決だけでなく長期的な成長も重視
- 「できること」が増えていく変化に注目
- 特性や興味を活かせる柔軟な進路選択が大切
発達障害のあるお子さんの成長を支えるには、短期的な問題解決だけでなく、数年先を見据えた支援が欠かせません。
「今できていないこと」を責めるのではなく、「少しずつできることが増えている」という変化に注目し、自己肯定感を育てていくことが重要です。
進路については、無理に一般的な道を選ばせるのではなく、お子さんの興味や得意分野、安心して学べる環境を優先しましょう。
たとえば、特別支援学級や通級指導、放課後等デイサービスの利用など、柔軟な選択肢を前向きに検討することがポイントです。
学習や生活でつまずいた時には「何が苦手か」「どうすれば取り組みやすいか」を一緒に考え、必要に応じて家庭教師や外部サービスの力を借りるのも効果的です。
“できた”経験を積み重ねていくことが、長期的な成長と安定につながります。
専門機関や相談窓口と家庭教師サービスを上手に活用する方法
- 専門機関・相談窓口と連携して正しい診断や支援策を得る
- 家庭教師も併用し個別の学習・メンタルサポートを活用
- 「早めの相談」「外部サポートの活用」で安心感UP
発達障害のあるお子さんの将来を考えるうえで、専門機関や相談窓口の活用はとても心強い存在です。
児童精神科や発達障害者支援センター、スクールカウンセラーなどに相談することで、正しい診断や具体的な支援策、進路情報を得ることができます。
家庭教師サービスも併用することで、学校や家庭だけでは補えない個別の学習支援やメンタルケアを受けられます。
困ったときは一人で抱え込まず、「早めの相談」「外部サポートの活用」を意識しましょう。
たとえば、学校や福祉機関と家庭教師担当者が連携を取ることで、よりきめ細かな支援が可能です。
情報共有やアドバイスを受けることで、保護者も気持ちに余裕を持てるようになります。
専門機関と家庭教師を両立させることで、お子さんの「今」と「将来」の両方をバランスよく支援できます。
発達障害の子どもへの理解とサポートについてまとめ
- ・発達障害の子どもの「言うことを聞かない」は性格やしつけの問題ではない
- ・シンプルなルール・環境調整・肯定的な声掛けが有効
- ・専門家や家庭教師と連携し「できる自信」を積み重ねていく
- ・長期的な視点で進路や将来の支援も重要
- ・保護者は一人で抱え込まず、外部サポートを活用
発達障害のあるお子さんの「親の言うことを聞かない」行動は、性格やしつけの問題ではなく、脳の特性や感覚の違いによるものです。
そのため、保護者は「どうしてできないのか」と責めるより、「どうすれば伝わるか」「どうしたら自信を持てるか」という視点で日々接することが大切です。
家庭では、シンプルなルールや環境調整、肯定的な声掛けを心がけましょう。
できないことではなく、「できたこと」を積み重ねる関わり方が、自己肯定感を自然に育てます。
また、つい感情的に叱ってしまったり対応に迷った時は、専門家や家庭教師など第三者のサポートを上手に利用してください。
家庭教師サービスは、お子さんの特性や学習スタイルに合わせて柔軟な支援を提供し、「できる自信」を育む心強い味方です。
長期的な目線で進路や将来を考え、専門機関・学校・家庭教師の連携により、親子で安心して歩んでいくことができます。
一人で抱え込まず、「あなたの子育ては大丈夫」と自分自身にも声をかけてあげてください。
どんな困りごとも、一緒に乗り越えていけるサポート体制が必ずあります。
まずは小さな一歩から、親子で「できる!」を増やしていきましょう。