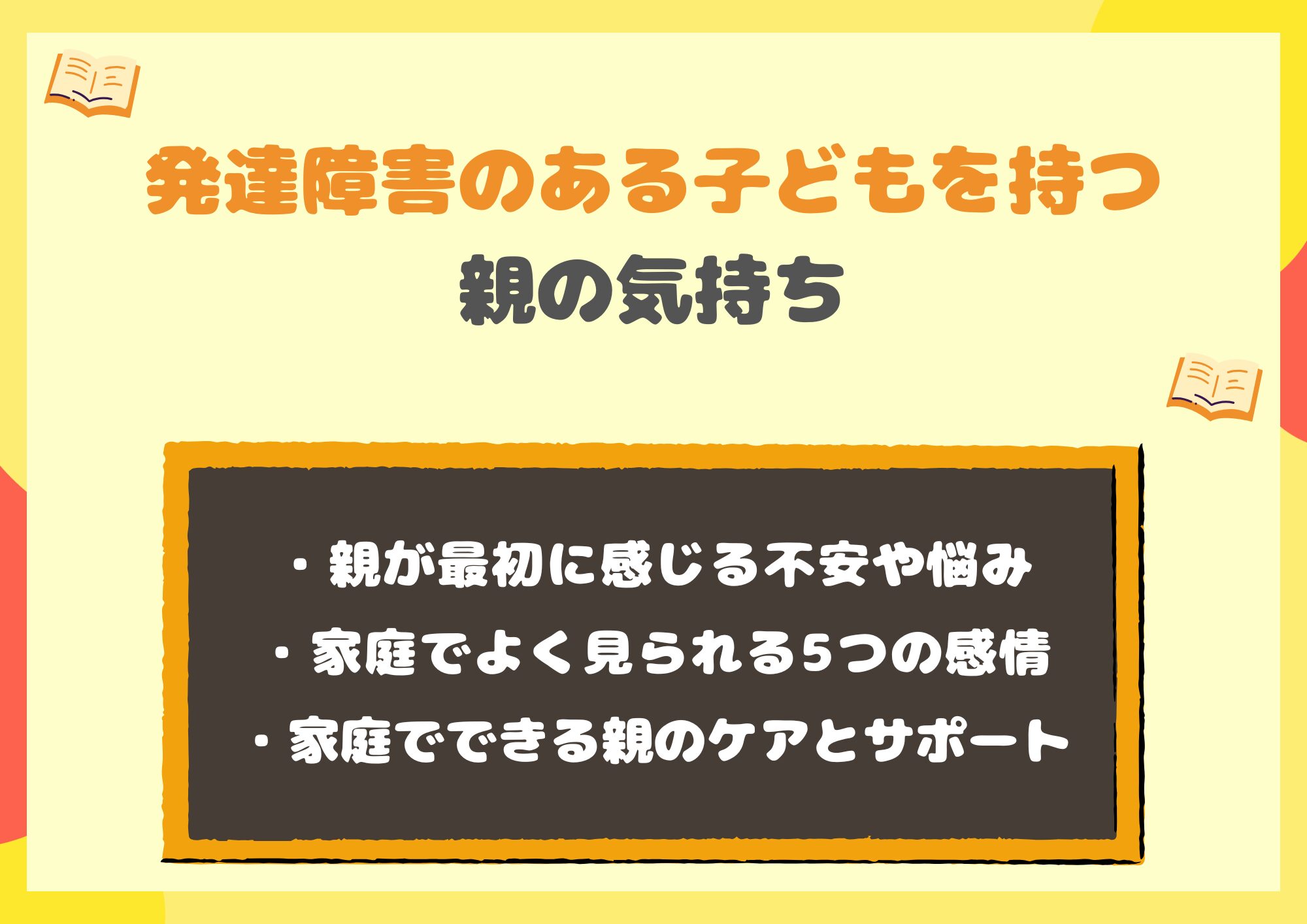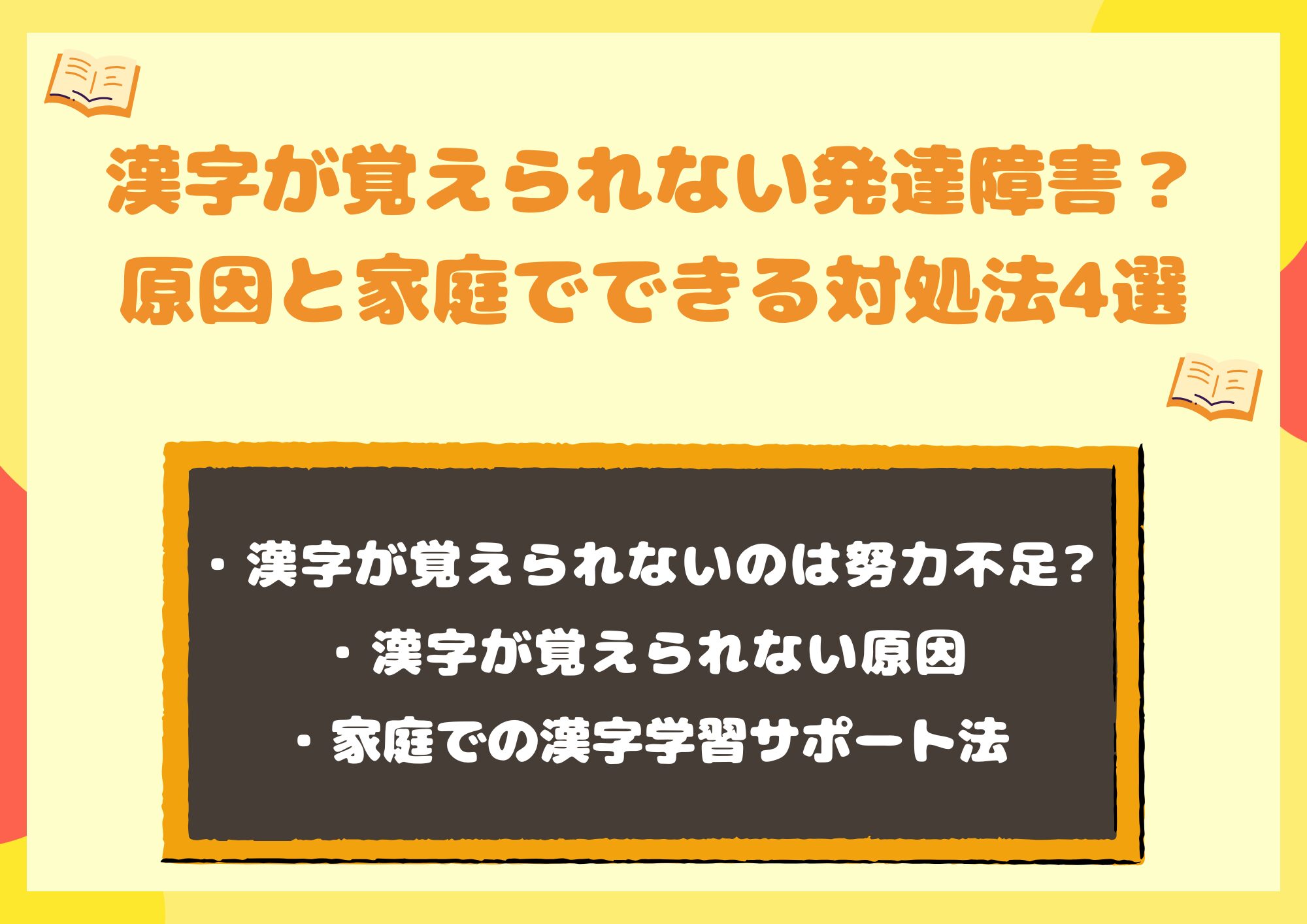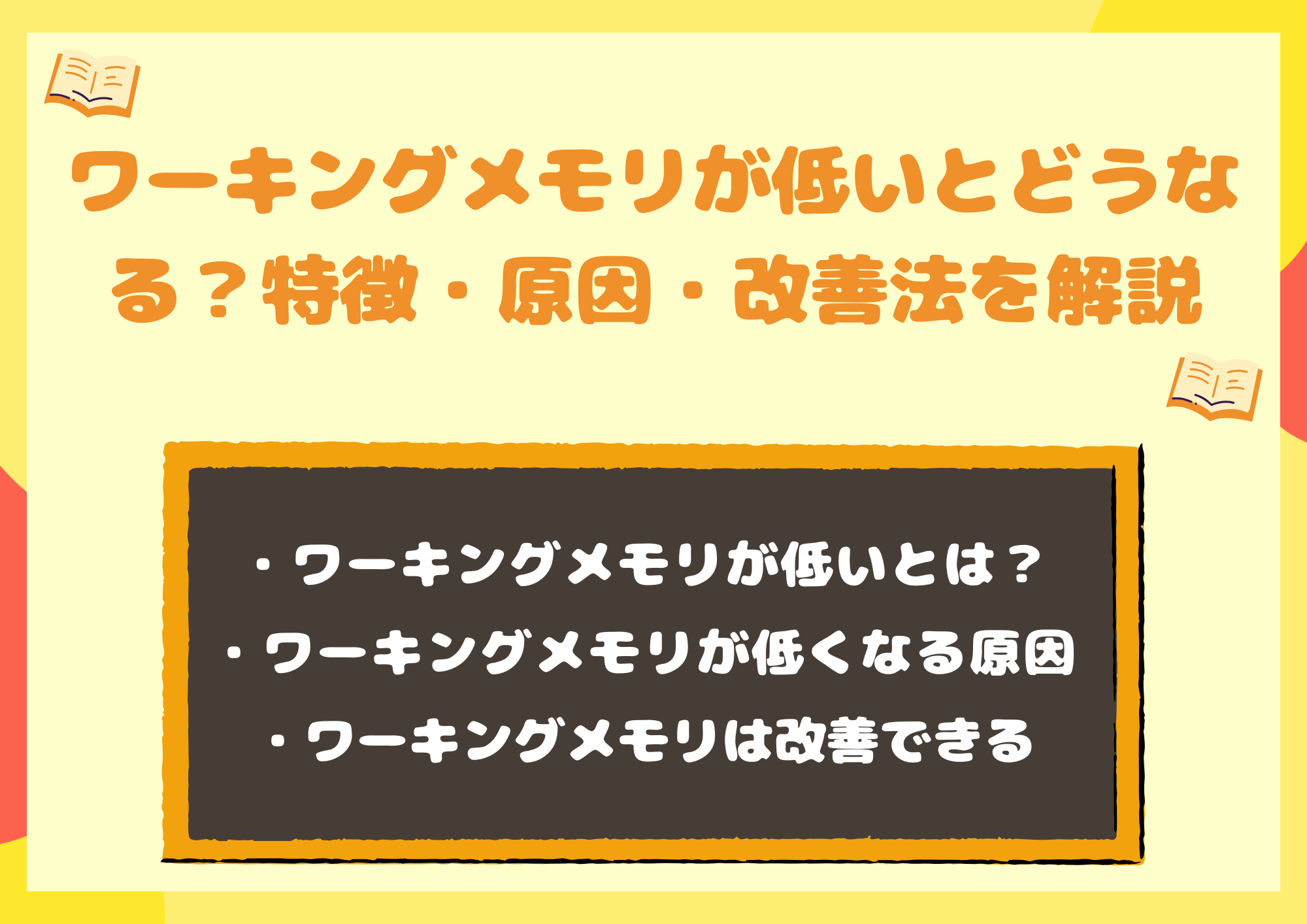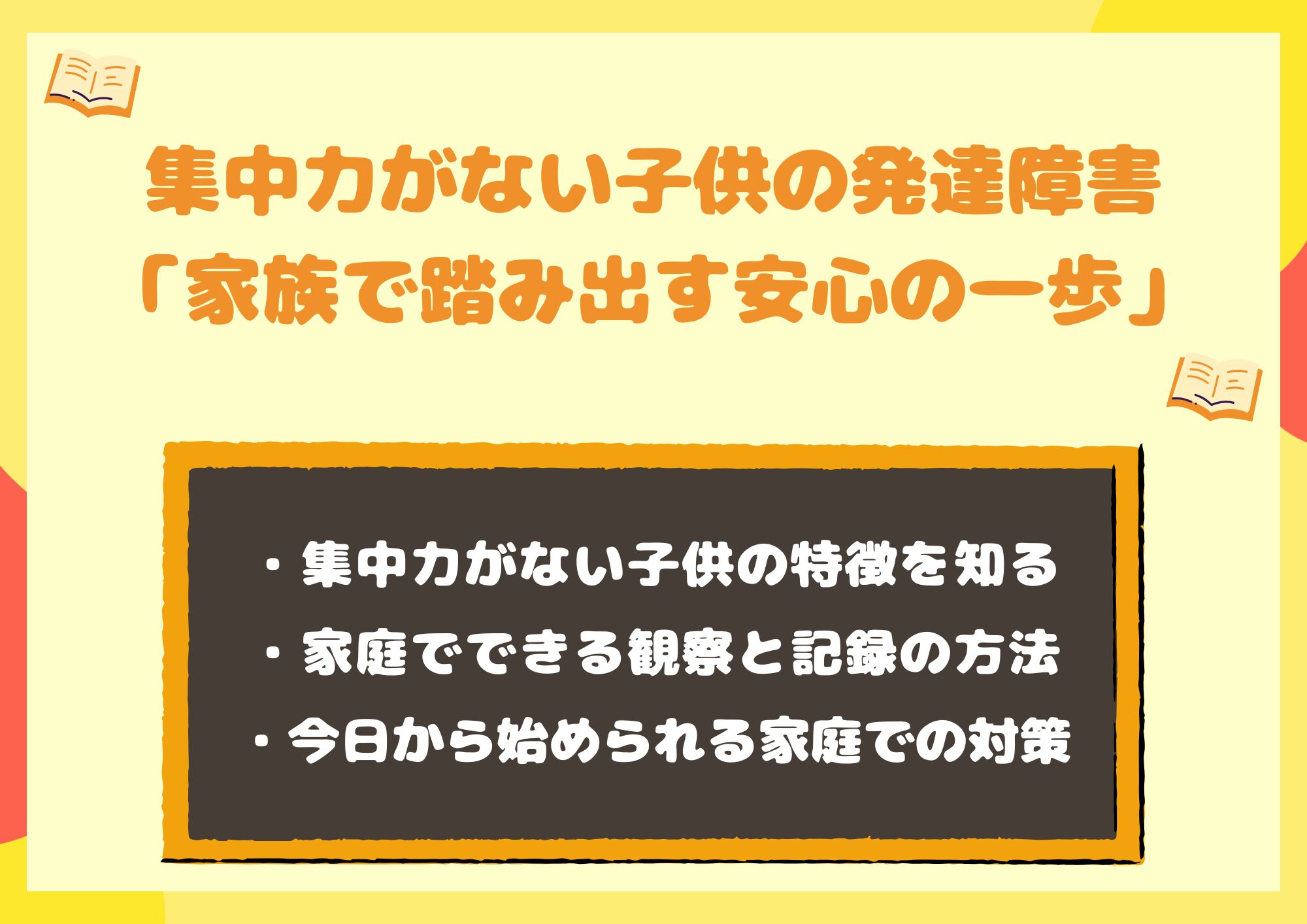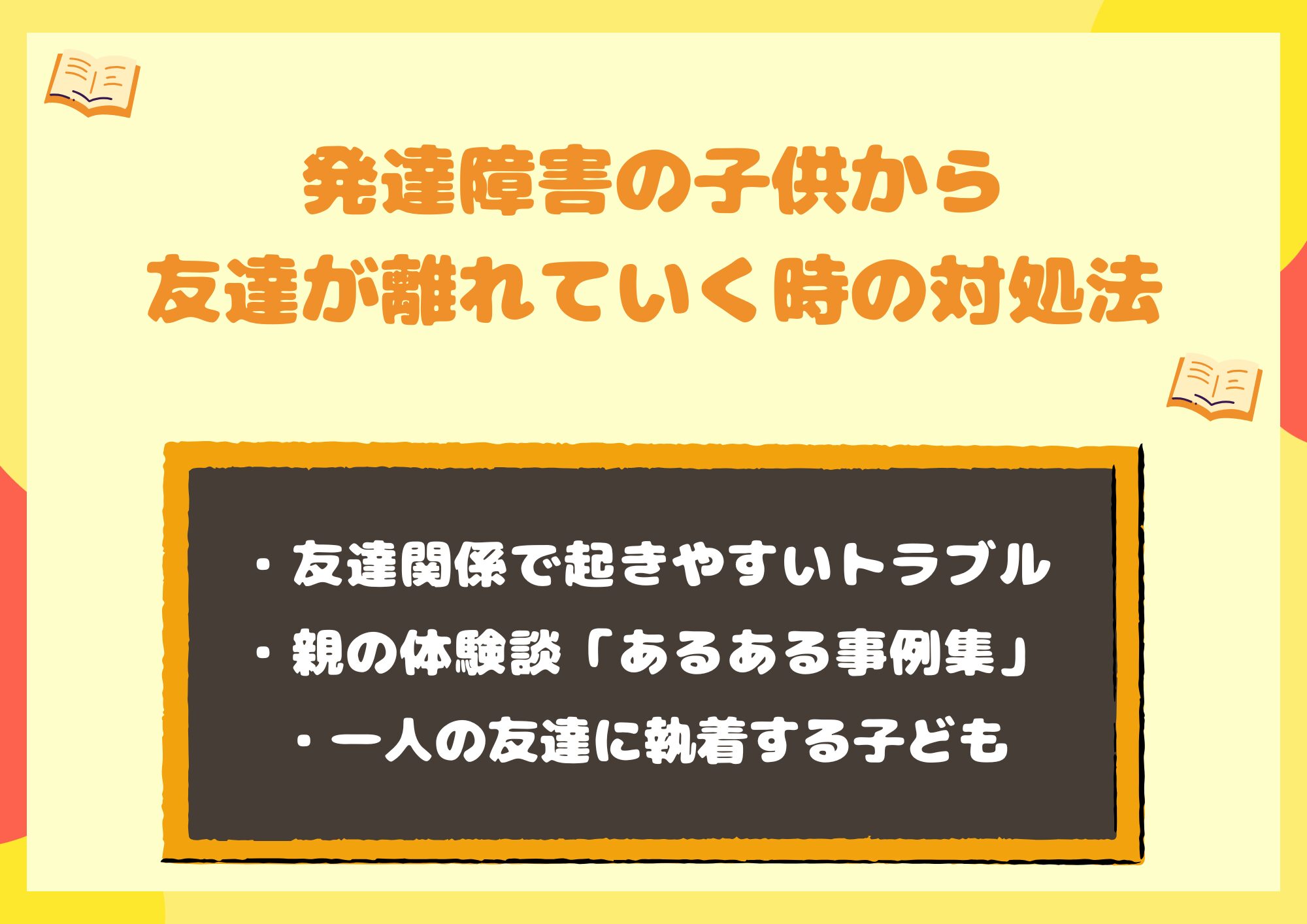- 発達障害向けの家庭教師
子どもの万引きと発達障害|親ができる初動対応と再発防止策
2025.09.30

子どもの万引きが発覚した瞬間、多くの親御さんは強い動揺と罪悪感に襲われます。
「まさかうちの子が」という驚きとともに、発達障害の特性が関係しているのではないかという不安も頭をよぎることでしょう。
実は、注意欠如・多動症(ADHD)や自閉スペクトラム症(ASD)などの発達障害を持つ子どもの万引き行動には、衝動性や実行機能の困難さといった特性が影響している場合があります。
しかし、これは発達障害と万引きに直接的な因果関係があるという話ではなく、個々の特性への理解と支援により改善が期待できる課題です。
本記事では、万引きが発覚した際の冷静な初動対応から、発達特性に配慮した再発防止策、そして適切な相談先まで、具体的かつ実践的な情報をお伝えします。
お子さまの行動の背景を理解し、家族で前向きに取り組むための道筋を一緒に見つけていきましょう。
目次
子どもの万引きが発覚した時の初動対応を確認する
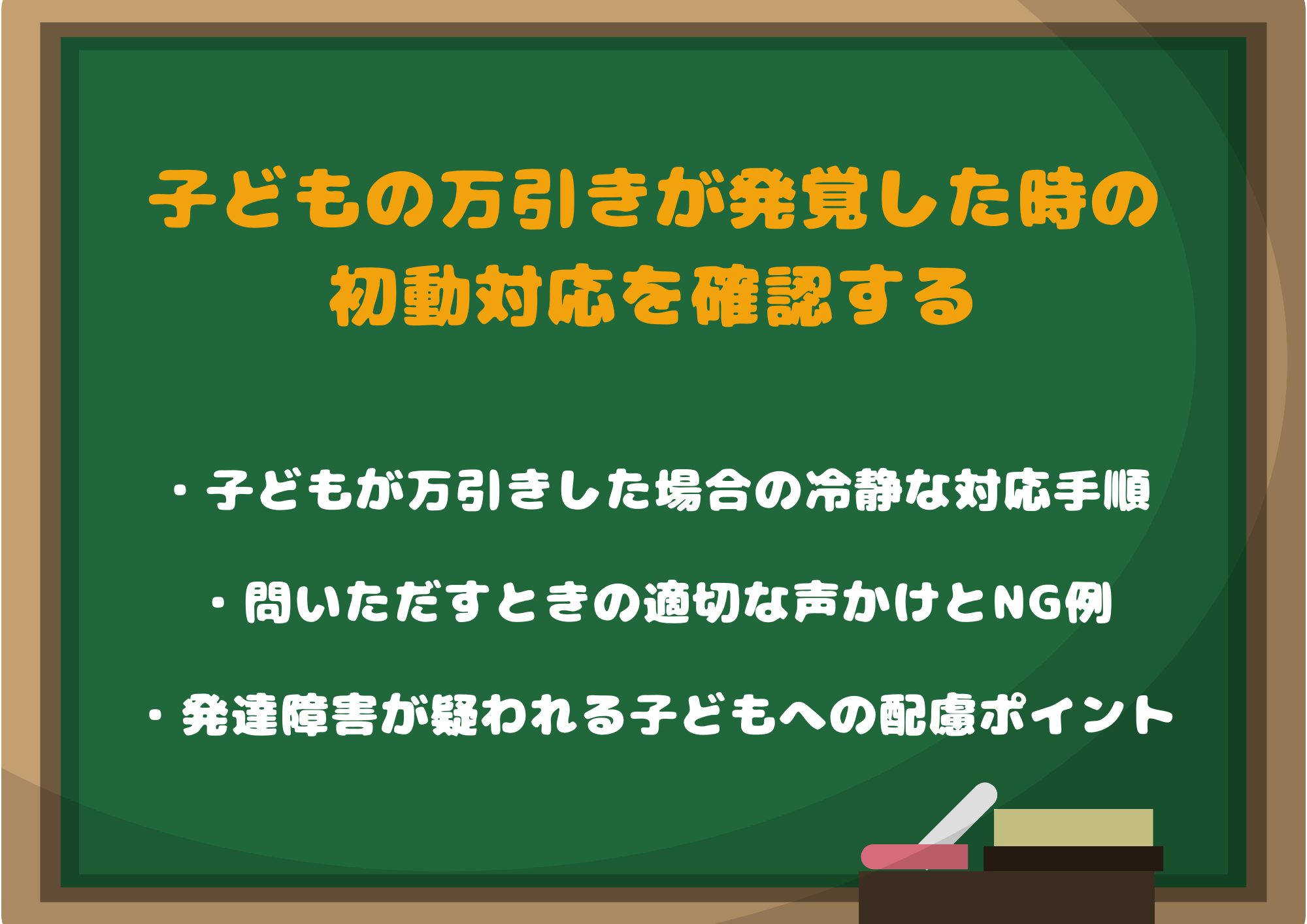
万引きが発覚した際、親として早期に適切な対応をすることが大切です。
感情的になってしまいがちですが、冷静な対応こそが子どもの将来を守り、再発防止につながる第一歩となります。
ここでは、具体的な対応手順を詳しく解説していきます。
子どもが万引きした場合の冷静な対応手順
- まず深呼吸をして冷静さを取り戻し、感情を整理する時間を取る
- 事実確認として、いつ・どこで・何を・どのような状況で万引きしたのかを整理
- 子どもの安全確保と精神状態を確認し、落ち着いた環境で話を聞く準備を整える
万引きが発覚したら、まず深呼吸をして冷静さを取り戻すことが大切です。
最初にすべきは事実確認で、いつ・どこで・何を・どのような状況で万引きしたのかを整理します。店舗からの連絡であれば、担当者の名前と連絡先を控え、返却や弁償についての具体的な手続きを確認しましょう。
子どもと話す前に、親自身が感情を整理する時間を5分でも取ることが、その後の対応を大きく左右します。
次に、子どもの安全確保と精神状態の確認を行い、落ち着いた環境で話を聞く準備を整えます。この時点では、叱責や長時間の説教は避け、まず事実関係の確認に専念することが重要です。
子どもに万引きを問いただすときの適切な声かけとNG例
- 「何があったのか、ゆっくり聞かせてくれる?」などオープンな質問から始める
- 感情的な言葉は避け、協力的な姿勢を示して子どもが本音を話しやすい環境を作る
- 「警察に突き出すよ」などの脅しは逆効果となり信頼関係を損なう
子どもへの声かけは、今後の親子関係と再発防止の成否を左右する重要な場面です。
適切な声かけの例として「何があったのか、ゆっくり聞かせてくれる?」「困ったことがあったの?」といった、オープンな質問から始めることをおすすめします。
子どもが話しやすい雰囲気を作り、否定や批判を避けながら事実を確認していきましょう。
一方、NGな声かけとして「どうしてこんなことしたの!」「恥ずかしくないの?」といった感情的な言葉は、子どもを追い詰め、嘘や否認を誘発する可能性があります。
「あなたの気持ちも聞きたいから、一緒に考えよう」という協力的な姿勢を示すことで、子どもは本音を話しやすくなります。
また、「警察に突き出すよ」「もう信用できない」といった脅しや絶望的な言葉も避けるべきです。脅しは逆効果となり、信頼関係を損なう可能性があります。
発達障害が疑われる子どもへの配慮ポイント
- ADHD傾向の子どもは衝動性、ASD傾向の子どもはルール理解の困難さがある場合がある
- 短い言葉で具体的に伝え、視覚的な支援(イラストや図)を活用する
- 感情的な表現より事実ベースの説明が効果的で、段階的に理解を促す
発達障害の特性がある子どもの場合、通常とは異なる配慮が必要になります。
注意欠如・多動症(ADHD)傾向のある子どもは、衝動性から「欲しい」と思った瞬間に手が出てしまう可能性があり、自閉スペクトラム症(ASD)傾向の子どもは、社会的ルールの理解が不十分な場合があります。
これらは悪意ではなく、特性による困難さの表れである場合があります。対応時は、短い言葉で具体的に伝え、視覚的な支援(イラストや図)を活用すると理解しやすくなります。
感情的な表現よりも、「お店の物を勝手に持って帰ることはルール違反」という事実ベースの説明が効果的です。
また、一度にたくさんの情報を伝えるのではなく、段階的に理解を促していくことも大切です。
学校や店舗への謝罪・連絡方法
- 店舗への謝罪は速やかに誠実に行い、訪問時は親子で伺う
- 学校への連絡は担任教諭またはスクールカウンセラーに事実を伝える
- 家庭と学校で連携する前向きな姿勢を示すことで協力を得やすくなる
店舗への謝罪は、速やかに誠実に行うことが基本です。
電話での初回連絡では「この度は大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません」という謝罪から始め、訪問日時の調整と返却・弁償の方法を確認します。
訪問時は親子で伺い、子ども自身にも謝罪の機会を与えることで、行動の重大性を理解させます。
学校への連絡は、担任教諭またはスクールカウンセラーに事実を伝え、今後の支援について相談します。「家庭と学校で連携して子どもを支援したい」という前向きな姿勢を示すことで、学校側も協力的になりやすいです。
メールで連絡する場合は、事実関係を簡潔にまとめ、面談の希望日時を複数提示すると良いでしょう。
子どもの万引きと発達障害の関係を解説|盗み癖やルールが守れない背景
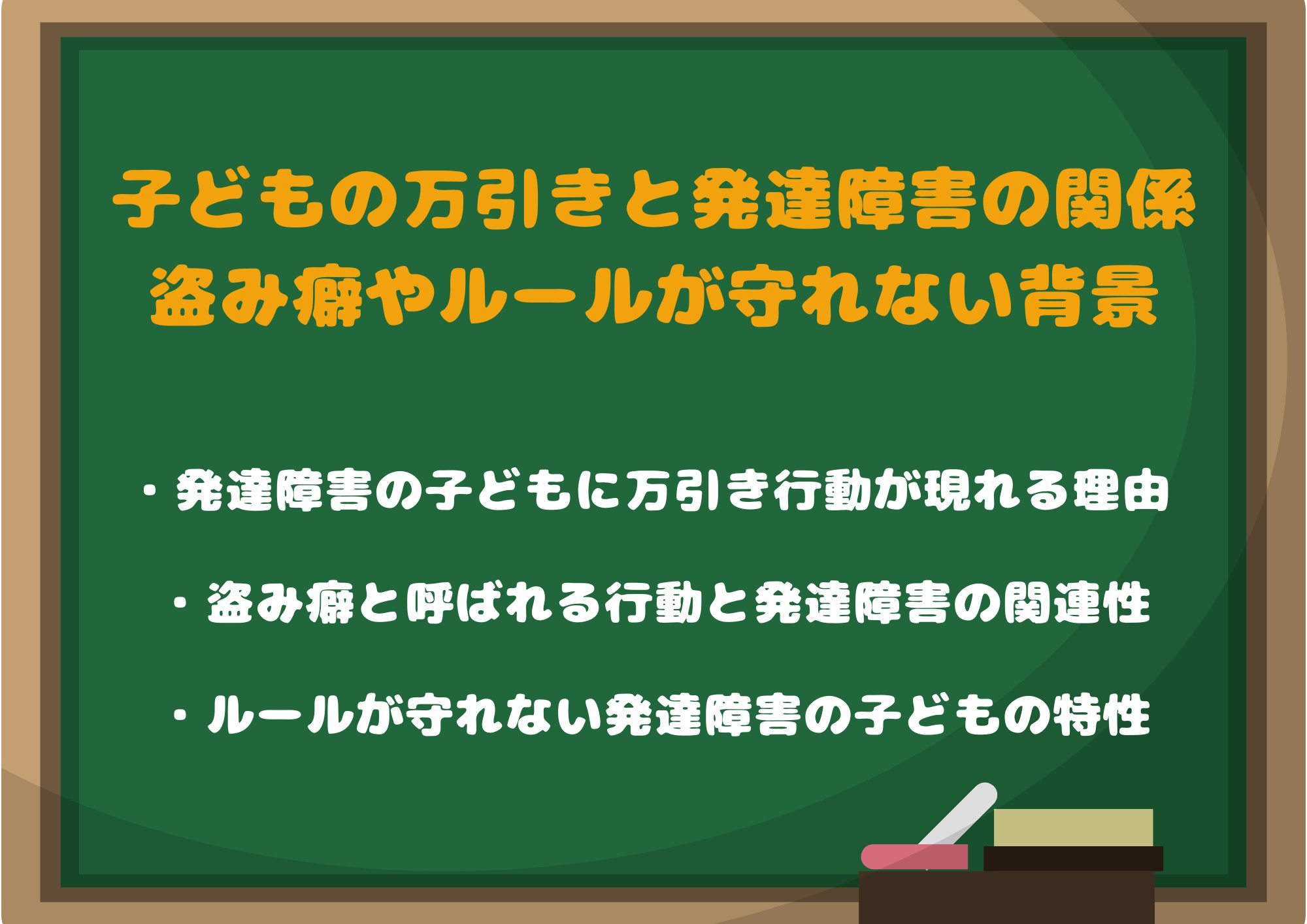
万引き行動と発達障害の関係は複雑で、すべての発達障害児が万引きをするわけではありません。
しかし、発達特性による困難さが、結果として万引き行動につながる場合があることが指摘されています。
ここでは、その背景にある認知や実行機能の特性を理解し、適切な支援につなげるための知識を深めていきましょう。
発達障害の子どもに万引き行動が現れる理由と特徴
- ADHD特性による衝動性の高さから行動を抑制できないケースがある
- 実行機能の困難さにより「お金を払う」という手順を忘れることがある
- ASD特性では社会的ルールの暗黙の了解が理解しにくい場合がある
発達障害を持つ子どもの万引き行動には、いくつかの特徴的なパターンがあります。
まず、ADHD特性による衝動性の高さから、「欲しい」と思った瞬間に行動を抑制できないケースがあります。また、実行機能の困難さにより、「お金を払う」という手順を忘れてしまったり、順番を守ることが難しい場合もあります。
これらの行動は意図的ではなく、脳の機能的な特性の影響が関与する場合があると考えられています。
ASD特性のある子どもの場合、社会的ルールの暗黙の了解が理解しにくく、「お店の物は勝手に持って帰ってはいけない」という当たり前のルールが身についていないこともあります。
一部の当事者では、特定の触感や見た目の物に強く惹かれることも影響している場合があります。
盗み癖と呼ばれる行動と発達障害の関連性について
- 「盗み癖」は俗称であり専門用語ではないため慎重に扱う必要がある
- 認知機能や衝動制御の困難さに起因することが多いとされる
- 環境調整や視覚的支援により多くのケースで改善が見込める
「盗み癖」という言葉は俗称であり、専門用語ではないことに注意が必要です。
この言葉は繰り返される万引き行動を指して使われることがありますが、発達障害の文脈では慎重に扱う必要があります。
発達特性による万引き行動は、性格や道徳心の問題ではなく、認知機能や衝動制御の困難さに起因することが多いとされています。
例えば、ワーキングメモリの弱さから、「これはお金を払わなければいけない」という情報を保持できない場合があります。また、報酬系の特性により、即座に得られる満足感を優先してしまう傾向も関係している可能性があります。
重要なのは、ラベルを貼るのではなく、行動の背景にある機能的な困難さを理解し、適切な支援策を講じることです。
環境調整や視覚的支援により、多くのケースで改善が見込めます。
ルールが守れない発達障害の子どもにみられる特性
- 実行機能の困難さにより計画・実行・行動抑制に課題がある
- 注意の持続が困難でルールそのものを覚えていられないことがある
- 適切な環境調整と支援により改善が期待できる
発達障害の子どもがルールを守れない背景には、複数の認知的特性が関わっています。
実行機能の困難さにより、計画を立てて実行する、結果を予測する、行動を抑制するといった能力に課題がある場合があります。また、注意の持続が困難で、ルールそのものを覚えていられないこともあります。
時間の概念が曖昧で、「今」の欲求と「後で起こる結果」を結びつけて考えることが苦手な子どももいます。
こうした特性は、適切な環境調整と支援により、改善が期待できます。
視覚的な手がかりやリマインダー、スモールステップでの練習などが効果的な支援方法となります。
親が「しつけ」や「性格」と混同しやすいポイント
- 何度注意しても同じ失敗を繰り返すのは記憶の定着や般化の困難さによるもの
- 叱られてもヘラヘラしているのは感情調整の困難さの可能性がある
- 環境や方法を変えて試すことで特性による困難さかを見極められる
発達特性による行動を「しつけ不足」や「性格の問題」と誤解してしまうケースは少なくありません。
例えば、何度注意しても同じ失敗を繰り返す姿を見て、「反省していない」「わざとやっている」と感じてしまうことがあります。しかし、これは記憶の定着や般化の困難さによるもので、悪意ではない場合がほとんどです。
また、叱られてもヘラヘラしている様子から「反省の色が見えない」と思われがちですが、これは感情調整の困難さや、ストレス対処としての防衛反応の可能性があります。
「できない」のか「やらない」のかを見極めるには、環境や方法を変えて試してみることが大切です。
支援により改善が見られれば、それは特性による困難さだったと理解できます。
再発防止のために家庭でできること|4週間実践プラン
万引きの再発を防ぐには、具体的で実行可能な計画が必要です。
ここでは、4週間で段階的に取り組める実践プランをご紹介します。毎週の目標を設定し、小さな成功体験を積み重ねることで、子どもの行動改善と自信回復を同時に進めていきましょう。
なお、以下の例は一般的な方法であり、お子さまの年齢や特性、ご家庭の方針により調整が必要です。
家庭内での環境調整と持ち物管理の工夫
- お金やカードの管理を明確にし、子どもが自由に持ち出せない環境を作る
- 買い物前に買うものリストを作成し、予算を決めて必要な金額だけを持たせる
- 視覚的に分かりやすいお小遣い帳や買い物メモを活用する
環境調整は再発防止の第一歩となる重要な取り組みです。
まず、お金やカードの管理を明確にし、子どもが自由に持ち出せない環境を作ります。財布は決まった場所に保管し、必要な時だけ親の管理下で使用するルールを設定しましょう。
買い物に行く際は、事前に買うものリストを作成し、予算を決めて必要な金額だけを持たせます。
視覚的に分かりやすいお小遣い帳や買い物メモを活用することで、子どもも金銭管理の感覚を身につけやすくなります。
また、欲しいものは「ほしいものリスト」に書き出し、計画的に購入する習慣をつけることも効果的です。
子どもと一緒に作る行動契約やごほうび設定の方法
- 守るべきルールを3つ程度に絞り、具体的で達成可能な目標を設定する
- 達成できたらシールやポイントを付与し、一定数で活動や体験型のごほうびと交換
- 契約書は子どもと一緒に装飾し、見やすい場所に貼ってモチベーションを維持
行動契約は、子どもと一緒に作ることで効果が高まります。
まず、守るべきルールを3つ程度に絞り、具体的で達成可能な目標を設定します。例えば「お店では手に取った物を必ず棚に戻す」「買い物カゴに入れる前に親に確認する」などです。
達成できたらシールやポイントを付与し、一定数貯まったら好きな活動や小さなごほうびと交換できるシステムを作ります。
ごほうびは物質的なものより、「一緒に好きなゲームをする」「特別なおやつの時間」など、体験型のものが望ましいとされています。
契約書は子どもと一緒に装飾したり、見やすい場所に貼ったりして、モチベーションを維持しましょう。ただし、ご家庭の教育方針に合わせて内容は調整してください。
発達障害の子どもに効果的な声かけ例と習慣づくり
- 買い物前には具体的な予告をし、店内では良い行動をその場で褒める
- うまくいかなかった時も前向きな提案で成功体験につなげる
- 毎日「今日できたこと」を3つ挙げる習慣で自己肯定感を高める
発達障害の子どもへの声かけは、タイミングと内容が重要です。
買い物前には「今日はお菓子を1つ買います。レジでお金を払ってから持って帰ります。」と、具体的な予告をします。店内では「上手にカゴに入れられたね!」「ちゃんと確認してくれてありがとう!」など、良い行動をその場で褒めることが大切です。
うまくいかなかった時も「次はこうしてみよう」と前向きな提案をし、成功体験につなげていきます。
毎日同じ時間に「今日できたこと」を3つ挙げる習慣をつけることで、自己肯定感も高まります。寝る前の振り返りタイムを設け、親子でその日の良かった点を共有することもおすすめです。
週ごとの振り返りと行動の記録テンプレ活用
- ABC観察記録を活用し、問題行動のパターンと効果的な対応を記録
- 週ごとに環境調整、買い物練習、自己管理強化、計画立案と段階的に進める
- 記録は「○△×」の3段階評価でも効果があり、小さな進歩も評価する
週ごとの振り返りは、進歩を確認し、次の目標を設定する大切な機会です。
ABC観察記録(A:きっかけ、B:行動、C:結果)を活用し、どんな状況で問題行動が起きやすいか、どんな対応が効果的だったかを記録します。
1週目は環境調整と基本ルールの確認、2週目は買い物練習、3週目は自己管理の強化、4週目は振り返りと今後の計画立案という流れで進めます。
記録は詳細でなくても、「○△×」の3段階評価(行動が起きなかった・軽減した・再発した)でも効果があります。
大切なのは継続することと、小さな進歩も見逃さずに評価することです。
月末には、子どもと一緒に「がんばり賞」を決めて、達成感を味わえるようにしましょう。
子どもの気持ちに寄り添うコミュニケーションとケア方法
万引きをした子どもの心には、罪悪感や恥ずかしさ、不安など複雑な感情が渦巻いています。
この感情に適切に寄り添うことが、再発防止と健全な成長の鍵となります。
ここでは、子どもの気持ちを受け止め、信頼関係を再構築するための具体的な方法をお伝えします。
万引きした子どもの感情を受け止める言葉かけ
- 感情に焦点を当てた質問で子どもが気持ちを話しやすい環境を作る
- 「誰でも間違いをすることはあるよ」と一緒に解決方法を考える姿勢を示す
- 「今回のことから何か学べることはある?」と成長の機会に変える
子どもの感情を受け止める第一歩は、共感的な言葉かけから始まります。
「怖かったね」「どんな気持ちだった?」といった、感情に焦点を当てた質問をすることで、子どもは自分の気持ちを話しやすくなります。
責めるのではなく、「誰でも間違いをすることはあるよ。」「一緒に解決方法を考えよう。」という姿勢を示すことが大切です。
「あなたがダメな人だからではない。今回はやり方の問題だった。」という言葉は、子どもの自尊心を守りながら行動の修正を促せます。
また、「今回のことから何か学べることはある?」と問いかけることで、今回の出来事を手順の見直しと練習計画づくりに活かすことができます。
恥ずかしさや嘘・否認への対応スクリプト
- 嘘や否認の背景には強い恥の感情や恐怖があることを理解する
- 「本当のことを話しても怒らない」と安心感を与えることから始める
- 嘘を追及するより真実を話した時に評価することで正直な対話を促進
子どもが嘘をついたり、事実を否認したりする場合の対応は慎重に行う必要があります。
まず、嘘や否認の背景には強い恥の感情や恐怖があることを理解しましょう。「本当のことを話しても怒らないから、ゆっくり教えて。」と安心感を与えることから始めます。
それでも否認が続く場合は、「今は話したくないのね。準備ができたら教えてね。」と、時間を置くことも効果的です。
嘘を追及するよりも、「正直に話してくれてありがとう!」と真実を話したときに評価することで、今後の正直な対話を促進できます。
決して「嘘つき」というレッテルを貼らず、行動と人格を分けて対応することが重要です。
家族の罪悪感や孤立感を軽減する工夫
- 同じ悩みを持つ家族は多く、適切な支援を受ければ改善の道がある
- 家族会議を開き全員で協力する姿勢を示し、問題を家族の絆を深める機会に変える
- 兄弟にも個別の時間を設け、家族全体でサポートし合える環境を作る
万引き問題は、家族全体に影響を与え、親も強い罪悪感や孤立感を抱えることがあります。
まず大切なのは、「あなただけの問題ではない」と認識することです。同じ悩みを持つ家族は多く、適切な支援を受ければ改善の道があります。
家族会議を開き、全員で協力して取り組む姿勢を示すことで、問題を家族の絆を深める機会に変えられます。
「完璧な親なんていない」と自分を許し、必要な時は専門家の支援を求めることも大切な選択です。
兄弟がいる場合は、それぞれの気持ちを聞く時間を設け、家族全体でサポートし合える環境を作りましょう。
特性別|発達障害の種類ごとに考えたい支援とヒント
発達障害といっても、ADHDやASD、学習障害など、その特性は多様です。
それぞれの特性に応じた支援方法を理解することで、より効果的な対応が可能になります。
ここでは、特性別の具体的な支援方法とヒントをご紹介します。
ADHDの子どもに多い衝動性と対処方法
- 「今すぐ欲しい」という強い欲求には事前の準備と環境調整が重要
- 買い物前にリストを作成し、店内では役割を与えて注意を適切に向ける
- 深呼吸や手を握るなどの代替行動を教えて自己制御力を高める
注意欠如・多動症(ADHD)の子どもの衝動性は、「今すぐ欲しい」という強い欲求として現れることがあります。
この特性に対しては、事前の準備と環境調整が特に重要です。買い物前に「今日買うものリスト」を作成し、それ以外は「次回リスト」に書き込むルールを設定します。
店内では、カゴを持たせて役割を与えることで、注意を適切な行動に向けることができます。
「待つ練習」として、欲しいものを見つけたら10数えてから判断する習慣をつけることも効果的とされていますが、お子さまの年齢や特性により適否が異なります。
また、衝動的な行動の前兆を見つけたら、深呼吸や手をギュッと握るなどの代替行動を教え、練習することで自己制御力を高められる場合があります。
ASD(自閉スペクトラム症)傾向の子どもに有効な対応
- 明確で具体的なルール提示と買い物手順の視覚化が効果的
- ソーシャルストーリーで買い物の流れを物語形式で理解させる
- 予測可能性を高める工夫や事前の視覚スケジュールを活用する
自閉スペクトラム症(ASD)傾向のある子どもには、明確で具体的なルール提示が必要です。
「お店のものは買わないと持って帰れない」という抽象的な説明より、「商品→カゴ→レジ→お金→レシート→持ち帰り」という手順を視覚化して示すことが効果的です。
ソーシャルストーリー(短い物語で手順を学ぶ支援手法)を作成し、買い物の流れを物語形式で理解させる方法もあります。
感覚刺激への配慮も重要で、混雑した店舗を避ける、イヤーマフを使用するなどの工夫が必要な場合があります。
予測可能性を高めるため、いつも同じ店舗、同じルートで買い物をすることで安心感を与えられる場合がありますが、ルーティン化が難しい家庭では事前の視覚スケジュールで代替することも可能です。
変更がある場合は事前に十分な説明をし、心の準備をする時間を設けましょう。
グレーゾーンや診断前後の子どもに家庭でできる支援
- 診断の有無に関わらず、困りごとがある子どもには適切な支援が必要
- 子どもの得意・不得意を観察し、困難さが生じる場面を把握する
- 学校や地域の相談窓口は診断前でも相談や支援を受けることができる
診断の有無に関わらず、困りごとがある子どもには適切な支援が必要です。
グレーゾーンの子どもは、一見普通に見えるため周囲の理解を得にくく、本人も混乱しやすい状況にあります。
まずは、子どもの得意・不得意を観察し、どんな場面で困難さが生じるかを把握しましょう。診断を急ぐよりも、今できる環境調整や支援を始めることが大切です。
「診断がなくても、困っていることへの支援は受けられる」という事実を知ることで、親の焦りも軽減される傾向があります。
学校や地域の相談窓口では、診断前でも相談や支援を受けることができるので、積極的に活用していきましょう。
発達障害の子どもを支える家庭教師サービス「学習と成長を伴走」
発達障害や学習の困難を抱える子どもにとって、個別のサポートは大きな力になります。
家庭教師サービスは、一人ひとりの特性に合わせた指導で、学習面だけでなく生活面でもサポートを提供できます。ここでは、発達障害の子どもに対応できる主要な家庭教師サービスをご紹介します。
サービスの選定にあたっては、サポート範囲、料金の透明性、専門性などを比較検討することをおすすめします。
家庭教師のランナー|発達障害や不登校の子どもも安心のサポート体制

- 「勉強が苦手な子専門」として発達障害や不登校の子どもへの支援に注力
- 発達支援に関する研修を受けたスタッフが家庭と講師をつなぐサポート
- オンライン指導とLINEでの質問対応サービスで授業がない日も安心
私たち家庭教師のランナーは、「勉強が苦手な子専門」として発達障害や不登校の子どもへの支援に特に力を入れています。
発達支援に関する研修を受けたスタッフが在籍し、専門的な知識を持ったスタッフが家庭と講師をつなぐサポートを行います。多数の講師から、お子さまの特性に合った先生を見つけやすい体制を整えています。
料金は、1コマ(30分)小中学生900円・高校生1000円というシンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。
オンライン指導にも対応しており、LINEでの質問対応サービスもあるため、授業がない日でも安心してサポートを受けられます。
家庭教師のトライ|オーダーメイド指導と家庭への寄り添い

- 多数の登録教師から最適な先生を選べる業界大手サービス
- 専任の教育プランナーが発達特性に配慮したカリキュラムを作成
- トライ式学習法を発達障害の子どもの特性に合わせてカスタマイズ
業界大手の家庭教師のトライは、多数の登録教師から最適な先生を選べるサービスです。
専任の教育プランナーが家庭と教師の間に入り、発達特性に配慮したオーダーメイドカリキュラムを作成します。トライ式学習法という独自メソッドは、発達障害の子どもの特性に合わせてカスタマイズ可能とされています。
教師交代は条件により可能とのことで、詳細は問い合わせが必要です。
長年の実績による豊富なノウハウで、学習面だけでなく生活面のアドバイスも受けられるとされています。
学研の家庭教師|発達障害サポート実績と家庭学習支援

- 教育大手の学研グループ運営で発達障害児への支援実績あり
- 発達支援の研修を受けた教師を優先的に派遣できる体制
- 視覚的に分かりやすい教材を使用した指導が可能
教育大手の学研グループが運営する家庭教師サービスは、発達障害児への支援実績があるとされています。
登録教師の中から、発達支援の研修を受けた教師を優先的に派遣できる体制が整っているとのことです。学研の教材開発ノウハウを活かし、視覚的に分かりやすい教材を使用した指導も可能とされています。
大手企業運営による安心感と、教育のプロフェッショナルによるサポートが特徴とされています。
オンライン指導にも対応し、全国どこからでも専門的な支援を受けられるサービスです。
家庭教師のサクシード|上場企業運営の安心感と提案力

- 上場企業運営で多数の教師が在籍するサービス
- 発達障害の子どもへの指導経験がある教師を優先的にマッチング
- 体験授業を担当した先生がそのまま正式担当になる講師指名制
上場企業が運営する家庭教師のサクシードは、多数の教師が在籍しているとされています。
発達障害の子どもへの指導経験がある教師を優先的にマッチングし、体験授業を担当した先生がそのまま正式担当になる「講師指名制」で、子どもの不安を軽減するとのことです。
料金は指導内容や地域により異なるため、詳細は問い合わせが必要です。教務スタッフによる学習計画のサポートも提供され、家庭の負担軽減が期待できます。
オンライン指導も選択でき、対面と同様のサポートを受けられるサービスです。
家庭教師ファースト|低価格で幅広い子どもの学習サポート

- 価格を抑えたプランも用意されているサービス
- 発達障害や不登校支援の専門コースあり
- 担当教師自身が体験指導を行うためリラックスして授業に臨める
家庭教師ファーストは、価格を抑えたプランも用意されているサービスです。
発達障害や不登校支援の専門コースもあり、料金は学年や地域、指導内容により異なります。実際に担当となる先生で無料体験ができるため、子どもとの相性を事前に確認できます。
担当教師自身が体験指導を行うため、子どもも最初からリラックスして授業に臨めるとされています。
手持ち教材での指導も可能で、追加費用を抑えながらサポートを受けられるサービスです。
家庭教師のノーバス|長期運営で蓄積した運営ノウハウ

- 関東・東海エリアで長期運営により豊富な指導実績
- 発達障害の子どもへの対応経験が豊富な教師が多数在籍
- 教師と学習プランナーのダブル体制でサポート
関東・東海エリアで展開する家庭教師のノーバスは、長期運営により豊富な指導実績があるとされています。
発達障害の子どもへの対応経験が豊富な教師が多数在籍し、個別指導塾も運営しているため、多様な学習支援のノウハウを持っています。
教師と学習プランナーのダブル体制で、きめ細やかなサポートを提供するサービスです。長期運営で蓄積された地域密着の情報網で、学校との連携もスムーズに行えます。
オンライン指導サービスも利用でき、遠方からでも指導を受けられます。
家庭教師のあすなろ|親しみやすい先生による学習フォロー
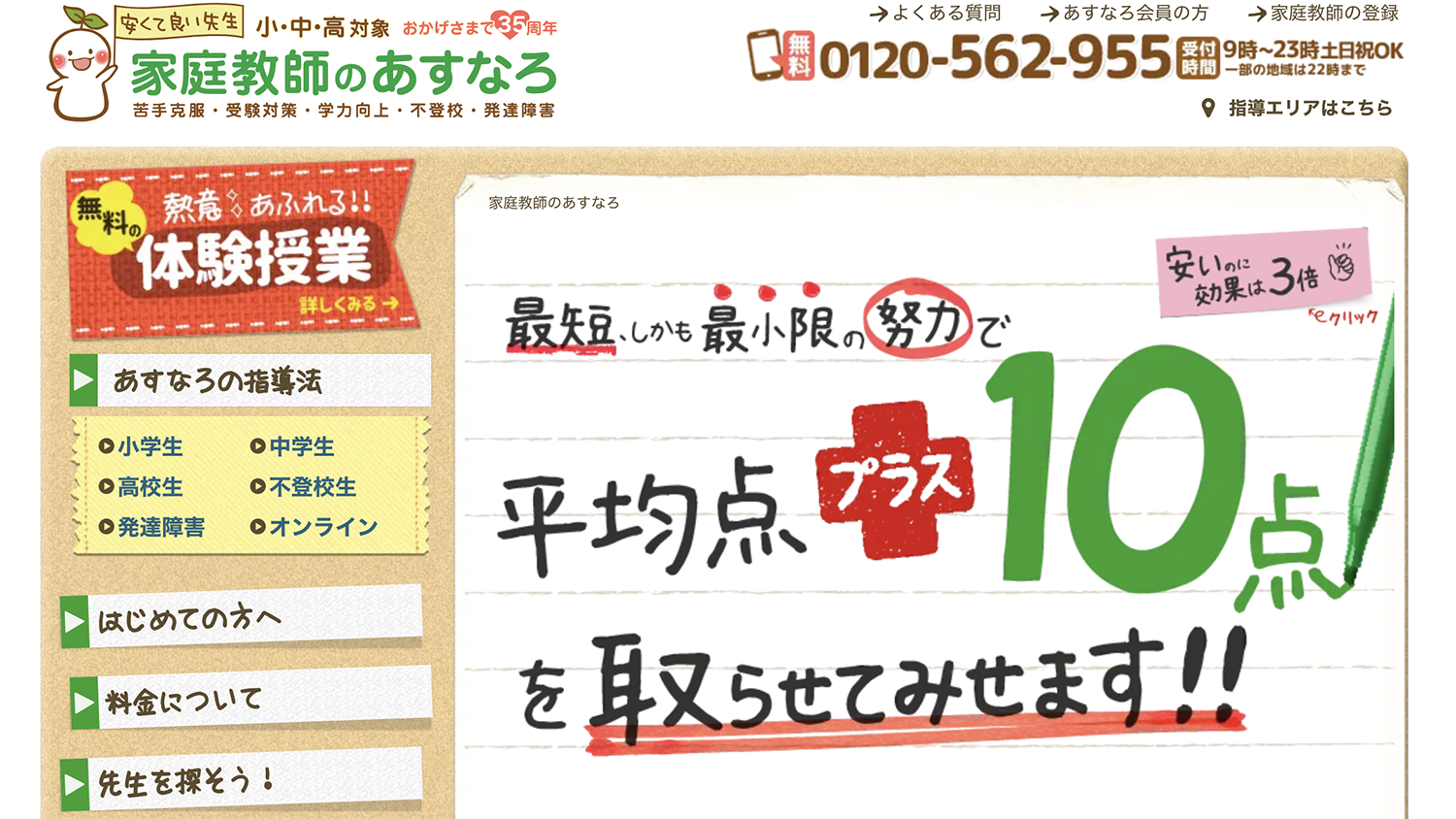
- 「勉強が苦手な子専門」で大学生中心の親近感ある指導
- 長年の運営実績と発達障害対応ノウハウを蓄積
- LINEを使った質問対応サービスで授業がない日も質問可能
「勉強が苦手な子専門」を掲げる家庭教師のあすなろは、大学生中心の若い先生による親近感のある指導が特徴とされています。
長年の運営実績があり、発達障害の子どもへの対応ノウハウも蓄積されているとのことです。LINEを使った質問対応サービスで、授業がない日でも質問できる環境を整えているとされています。
料金は指導内容や地域により異なり、親しみやすい指導で子どものやる気を引き出します。
基礎固めに重点を置いた指導方針で、つまずきを放置しない仕組みが整っているサービスです。
家庭教師学参|プロ家庭教師による個別支援の強み

- 長年の指導実績を持つプロ家庭教師による専門的支援
- 講師選択制度により無料体験授業で相性を確認してから契約
- 部活や習い事に合わせて授業回数や時間を柔軟に調整可能
長年の指導実績を持つ家庭教師学参は、プロ家庭教師による専門的な支援が強みとされています。
指導経験者による講師陣で、発達障害の子どもへの対応経験も豊富とのことです。講師選択制度により、無料体験授業で相性を確認してから正式契約できます。
部活や習い事に合わせて授業回数や時間を調整でき、子どもの負担を軽減できます。
教務担当によるフォローも提供され、学習計画から進路相談まで総合的なサポートを受けられるサービスです。
オンライン家庭教師Wam|自宅から発達障害サポートを受ける

- オンライン専門で独自開発の専用システムで効率的な個別指導
- 発達障害の子どもに配慮した視覚的な教材提示と双方向システム
- 移動時間ゼロで体力的・精神的負担を軽減しながら指導を受けられる
オンライン専門の家庭教師Wamは、独自開発の専用システムで効率的な個別指導を実現しているとされています。
発達障害の子どもに配慮した視覚的な教材提示や、双方向のやり取りに最適化されたシステムで、対面同等の指導を提供するとのことです。
料金は学年や指導内容により異なり、詳細は問い合わせが必要です。移動時間ゼロで、子どもの体力的・精神的負担を軽減しながら指導を受けられます。
多様な講師が在籍し、全国どこからでも指導を受けられるオンラインサービスです。
オンライン家庭教師トウコベ|東大生講師の学習支援
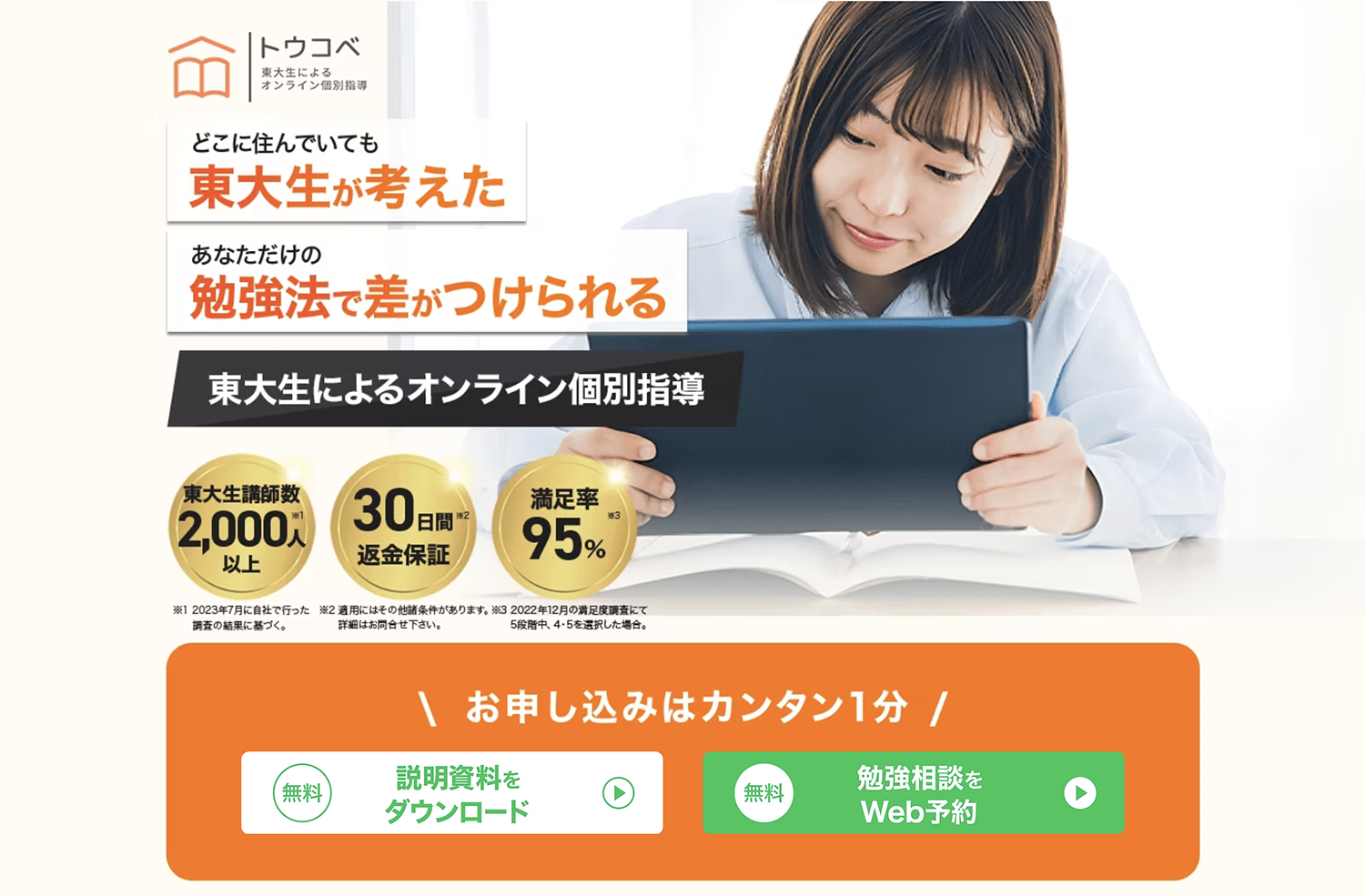
- 東京大学の現役東大生による個別指導を受けられるサービス
- 東大生講師から発達特性に理解のある先生を選べる
- 返金保証制度があり利用者の満足度が高いと評価
東京大学の現役東大生による個別指導を受けられるトウコベは、学習支援を提供するサービスです。
東大生講師から、発達特性に理解のある先生を選べるとされています。利用者の満足度が高いと評価されているサービスです。
東大生ならではの学習方法や経験を活かした指導で、子どもの可能性を引き出すサービスです。
オンライン家庭教師マナリンク|プロ講師と直接マッチングできる安心感
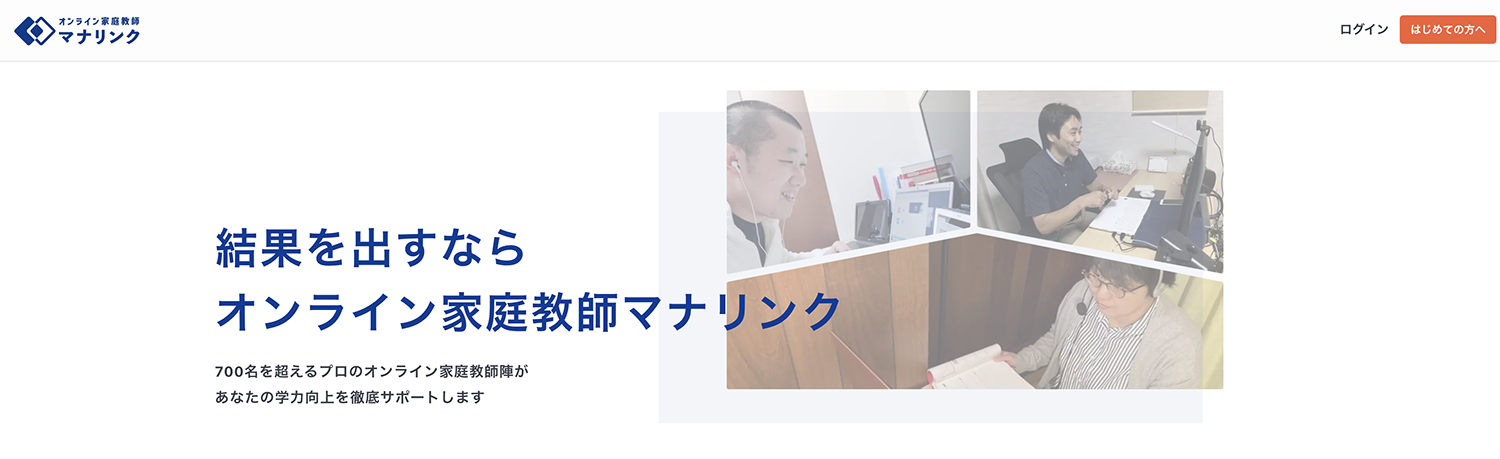
- 主に社会人プロ講師が登録する発達障害支援の専門性が高いサービス
- サイト上で講師のプロフィールや指導動画を見て自分で先生を選べる
- 料金体系は講師により異なり必要な時に必要な分だけ受講できる
主に社会人プロ講師が登録するマナリンクは、発達障害支援の専門性が高いサービスです。
サイト上で講師のプロフィールや指導動画を見て、自分で先生を選べるシステムが特徴です。元教員や発達支援の資格を持つ講師も多数在籍し、専門的な支援を受けられます。
料金体系は講師により異なり、必要な時に必要な分だけ受講できる柔軟性があり、専用アプリでの質問対応も可能で、授業外でもサポートを受けられるサービスです。
子どもの万引きと発達障害の相談先ナビ|学校・医療・地域サポートを活用する
万引き問題や発達障害の対応には、家庭だけでなく専門機関との連携が不可欠です。
適切な相談先を知り、効果的に活用することで、子どもへの支援の質が大きく向上します。
ここでは、主要な相談先とその活用方法について詳しく解説します。なお、自治体や学校により対応は異なるため、詳細は各機関にお問い合わせください。
学校(担任・特別支援コーディネーター)への相談方法と準備
- 担任教諭に連絡を取り面談時間を設定して相談する
- 経緯のメモ、観察記録、診断書(あれば)を持参する
- 特別支援教育コーディネーターへは担任を通じて依頼すると円滑
学校への相談は、子どもの支援を考える上で重要なステップの一つです。
まず担任教諭に連絡を取り、面談の時間を設定します。その際、「子どもの困りごとについて相談したい」という形で申し込むと、学校側も準備をして対応してくれます。
面談時には、これまでの経緯をまとめたメモ、観察記録、医療機関の診断書(あれば)を持参しましょう。
特別支援教育コーディネーターへの相談を希望する場合は、担任を通じて依頼すると円滑に進みます。
学校での様子と家庭での様子を共有し、一貫した支援方針を立てることが大切です。
スクールカウンセラーや医療機関での支援の受け方
- スクールカウンセラーは担任または養護教諭を通じて予約可能
- 医療機関の受診は小児科、児童精神科、発達外来などが選択肢
- 初診時は医療機関の指示に従い必要な持ち物を準備する
スクールカウンセラーは、心理の専門家として子どもと家族をサポートしてくれます。
多くの学校で定期的な相談日が設けられており、担任または養護教諭を通じて予約できます。初回相談では、現在の困りごとと希望する支援内容を明確に伝えることが重要です。
医療機関を受診する場合は、小児科、児童精神科、発達外来などが選択肢となりますが、まずは医療機関の指示に従ってください。
初診時は、医療機関から指定された持ち物を準備し、母子手帳や成績表、行動観察記録なども持参すると状況を把握しやすくなる場合があります。
診断を急がず、まずは相談から始めることも可能です。
地域の子育て・発達相談窓口の探し方
- 市区町村の子育て支援課、保健センター、児童相談所が主な窓口
- 発達支援センターや療育センターで発達検査や療育プログラムを提供
- 子育て世代包括支援センターでワンストップ相談が可能な場合も
地域には様々な相談窓口があり、多くは無料で利用できますが、費用は自治体により異なります。
市区町村の子育て支援課、保健センター、児童相談所などが主な窓口となります。「発達支援センター」「療育センター」といった専門機関もあり、発達検査や療育プログラムを提供しています。
窓口の探し方として、市役所のホームページで「子育て支援」「発達相談」で検索する、または電話で問い合わせる方法があります。
多くの自治体で「子育て世代包括支援センター」が設置され、ワンストップで相談できる体制が整っている場合があります。
親の会や当事者団体の情報も、地域の福祉課で入手できます。
子どもの万引きと発達障害に関するよくある質問(FAQ)
子どもの万引きと発達障害について、多くの親御さんから寄せられる質問をまとめました。
「もし再発したらどうすればいいの?」「兄弟にはどう説明したらいい?」など、実際に直面して初めて気づく悩みは少なくありません。
SNS時代特有の新たなリスクや、罰の効果についての誤解など、現代の子育て環境ならではの疑問もあります。
ここでは、特に相談の多い5つの質問について、具体的で実践的な回答をご紹介します。同じ悩みを抱える方々の参考になれば幸いです。
万引きが再発してしまった場合の対応は?
- 前回の対応を振り返り効果的だった点と不足点を冷静に分析する
- 専門機関への相談を検討し、より専門的な支援を受ける
- 行動記録を詳細に取りパターンを分析して予防策を立てる
万引きが再発した場合でも、諦める必要はありません。
まず、前回の対応を振り返り、何が効果的で何が不足していたかを冷静に分析します。再発は、前回の対策が十分に機能しなかったサインとして分析することが大切です。
専門機関への相談を検討し、より専門的な支援を受けることで、新たな解決策が見つかる場合があります。
行動記録を詳細に取り、パターンを分析することで、より効果的な予防策を立てられます。
家族だけで抱え込まず、学校や医療機関と連携を強化することも重要です。
兄弟姉妹への説明や接し方のコツは?
- 年齢に応じた説明で幼い兄弟には簡単な言葉で伝える
- 家族みんなで協力する姿勢を示し全員で支え合う
- 兄弟にも個別の時間を設け「あなたも大切」と伝え続ける
兄弟姉妹への説明は、年齢に応じて適切に行う必要があります。
幼い兄弟には「お兄ちゃん(お姉ちゃん)は今、お約束を守る練習をしているの」という簡単な説明で十分です。
年齢が上の兄弟には、発達の特性について年齢に応じた説明をし、「家族みんなで協力しよう」という姿勢を示します。
兄弟にも個別の時間を設け、「あなたも大切」というメッセージを伝え続けることが重要です。兄弟が感じる不公平感や不満も受け止め、家族全体のバランスを保つよう心がけましょう。
SNSやインターネットでの情報拡散リスクについて
- 家族や関係者にSNSへの投稿を控えるよう依頼する
- 学校にも情報管理について相談しプライバシー保護を徹底
- 子ども自身にもSNSでの情報発信リスクを年齢に応じて説明
現代では、子どもの万引き情報がSNSで拡散されるリスクがあります。
まず、家族や関係者に対して、SNSへの投稿を控えるよう依頼することが大切です。学校にも情報管理について相談し、プライバシー保護を徹底してもらいましょう。
万が一情報が拡散された場合は、弁護士や専門窓口への相談を検討することをおすすめします。
子ども自身にも、SNSでの情報発信のリスクについて、年齢に応じた説明をすることが必要です。デジタルタトゥーとして残る可能性があることを理解させ、慎重な行動を促しましょう。
罰やペナルティで子どもの行動は変わるのか?
- 罰だけでは発達障害の子どもの行動改善は期待できない
- 良い行動を強化する「正の強化」アプローチが効果的
- 小さな成功体験を積み重ねることで望ましい行動が増える
罰やペナルティだけでは、発達障害の子どもの行動改善は多くのケースで期待できません。
発達特性による行動は、意図的ではないことが多く、罰を与えても根本的な解決にはなりません。むしろ、自己肯定感を下げ、問題行動を悪化させる可能性があります。
効果的とされるのは、良い行動を強化する「正の強化」アプローチです。
できたことを褒め、小さな成功体験を積み重ねることで、望ましい行動が増えていく傾向があります。
必要な場合は、自然な結果(買い物に連れて行かないなど)を体験させることは有効ですが、過度な罰は避けるべきです。
診断前でも支援や相談は受けられる?
- 発達障害の診断がなくても多くの支援や相談を受けることができる
- 学校では困りごとがあれば合理的配慮を求められ診断書は必須でない
- 「困っている」ことが支援を受ける理由として十分
発達障害の診断がなくても、多くの支援や相談を受けることができます。
学校では、困りごとがあれば合理的配慮を求めることができ、診断書は必須ではありません。地域の発達相談窓口や子育て支援センターも、診断の有無に関わらず相談を受け付けています。
民間の療育機関やカウンセリングも、多くが診断前から利用可能です。
「困っている」ことが支援を受ける理由として十分であり、診断を急ぐ必要はありません。まずは相談から始め、必要に応じて診断を検討するという流れで問題ありません。
子どもの万引きと発達障害についてまとめ
- ・万引き行動には発達特性が影響している可能性があるが、適切な支援により改善が期待できる
- ・初動対応では冷静さを保ち、子どもの感情を受け止めながら事実確認を行う
- ・環境調整と行動支援の両面からアプローチし、4週間プランで段階的に改善を図る
- ・家庭教師などの個別指導サービスで発達特性に配慮した学習支援を受けられる
- ・学校・医療機関・地域の相談窓口など様々な支援機関と連携することが重要
子どもの万引きと発達障害の関係について、初動対応から再発防止、そして適切な支援方法まで詳しく解説してきました。
万引き行動の背景には、ADHDの衝動性やASDのルール理解の困難さなど、発達特性による要因が隠れている可能性があります。
しかし、これは発達障害が万引きの直接的な原因というわけではなく、適切な理解と支援により改善が期待できる課題です。
なお、発達障害と万引きを短絡的に結びつけることは避け、個々の特性と状況を丁寧に理解することが重要です。
初動対応では、冷静さを保ち、子どもの感情を受け止めながら事実確認を行うことが重要です。店舗や学校への誠実な対応と並行して、子どもへの共感的な声かけを心がけましょう。
今回の出来事を手順の見直しと練習計画づくりに活かし、家族全体で前向きに取り組む姿勢が、子どもの自己肯定感を守り、再発防止につながります。
再発防止には、環境調整と行動支援の両面からアプローチすることが効果的です。
買い物リストの作成、視覚的支援の活用、行動契約によるポジティブな強化など、具体的な方法を4週間プランとして実践していきましょう。週ごとの振り返りと記録により、子どもの進歩を確認し、必要に応じて支援方法を調整することも大切です。
個別指導サービスは、発達特性に配慮した学習支援を提供し、子どもの成功体験を増やす重要な役割を果たします。
専門的な知識を持つ講師による個別対応で、学習面だけでなく生活面でのサポートも期待できます。各サービスには特色があるため、お子さまの特性やご家庭のニーズに合わせて選択することをおすすめします。
最後に、この問題は家族だけで解決する必要はないということを強調したいです。
学校、医療機関、地域の相談窓口など、様々な支援機関があなたの味方です。診断の有無に関わらず、困っていることがあれば遠慮なく相談してください。
子どもの特性を理解し、適切な支援を続けることで、より良い方向を目指せるはずです。
支援を継続することで、行動の安定化が段階的に見込めることを信じて、一歩ずつ前に進んでいきましょう。