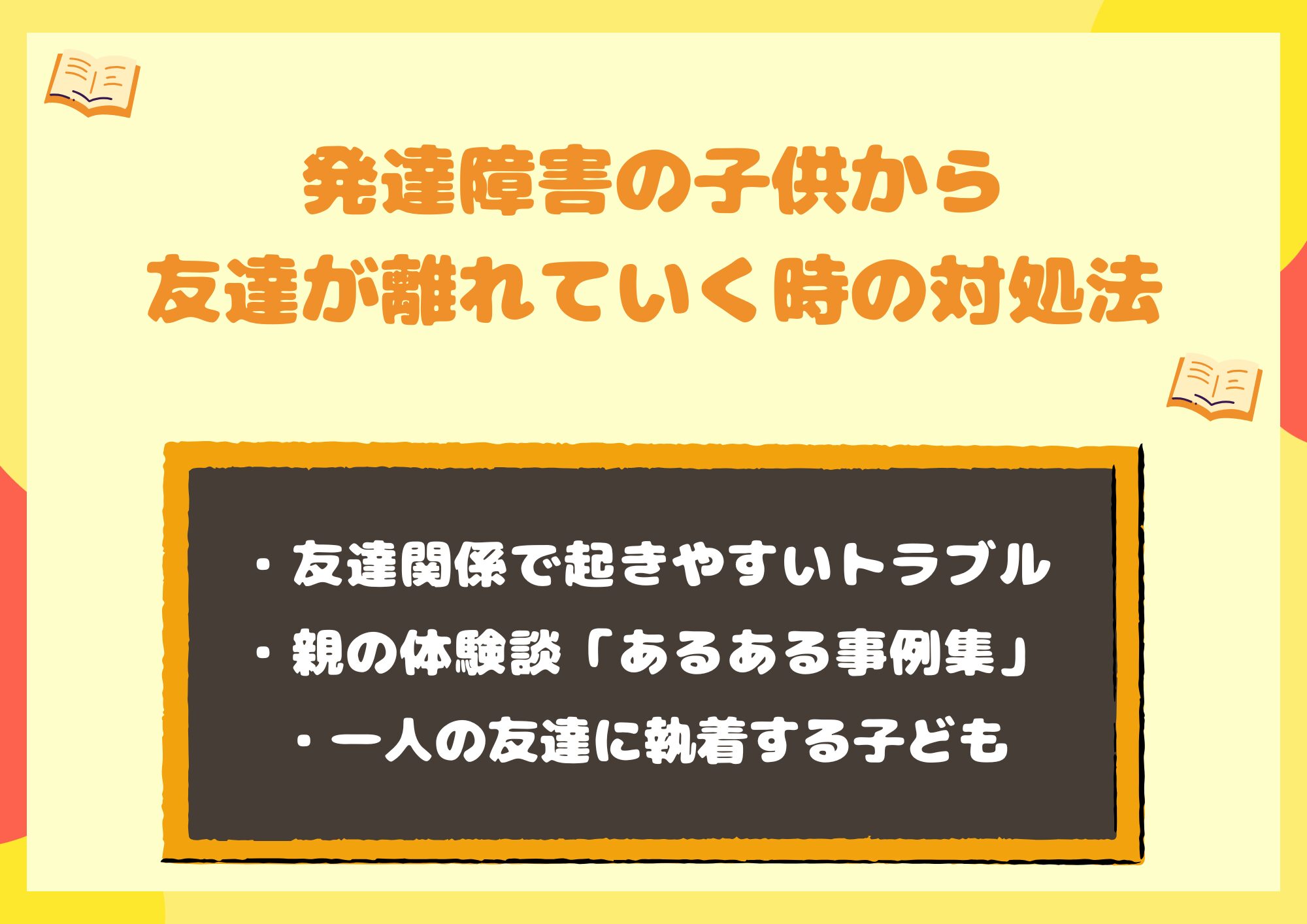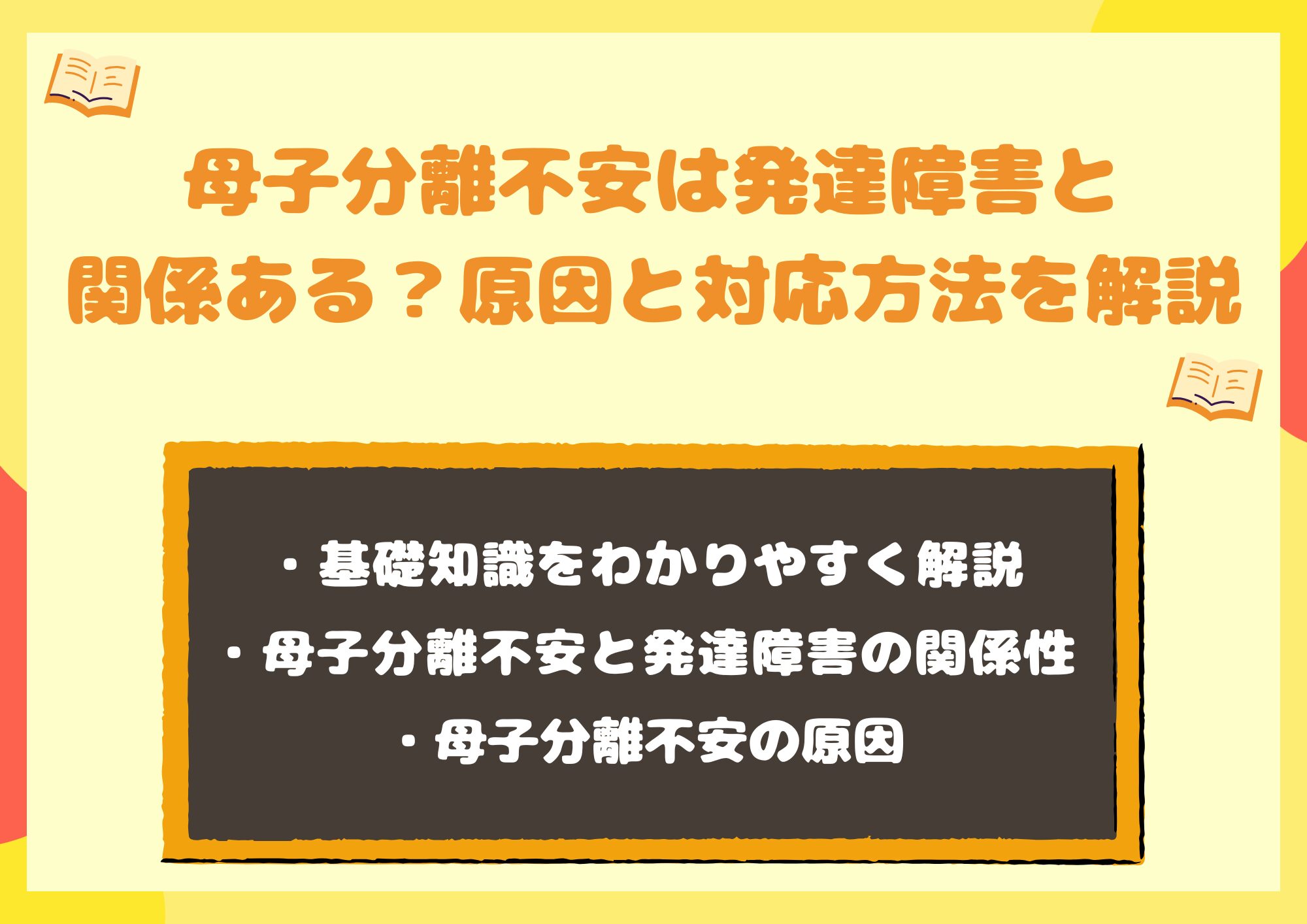- 発達障害向けの家庭教師
発達障害で嘘をつく小学生への対応|家庭と学校でできる支援法
2025.09.30
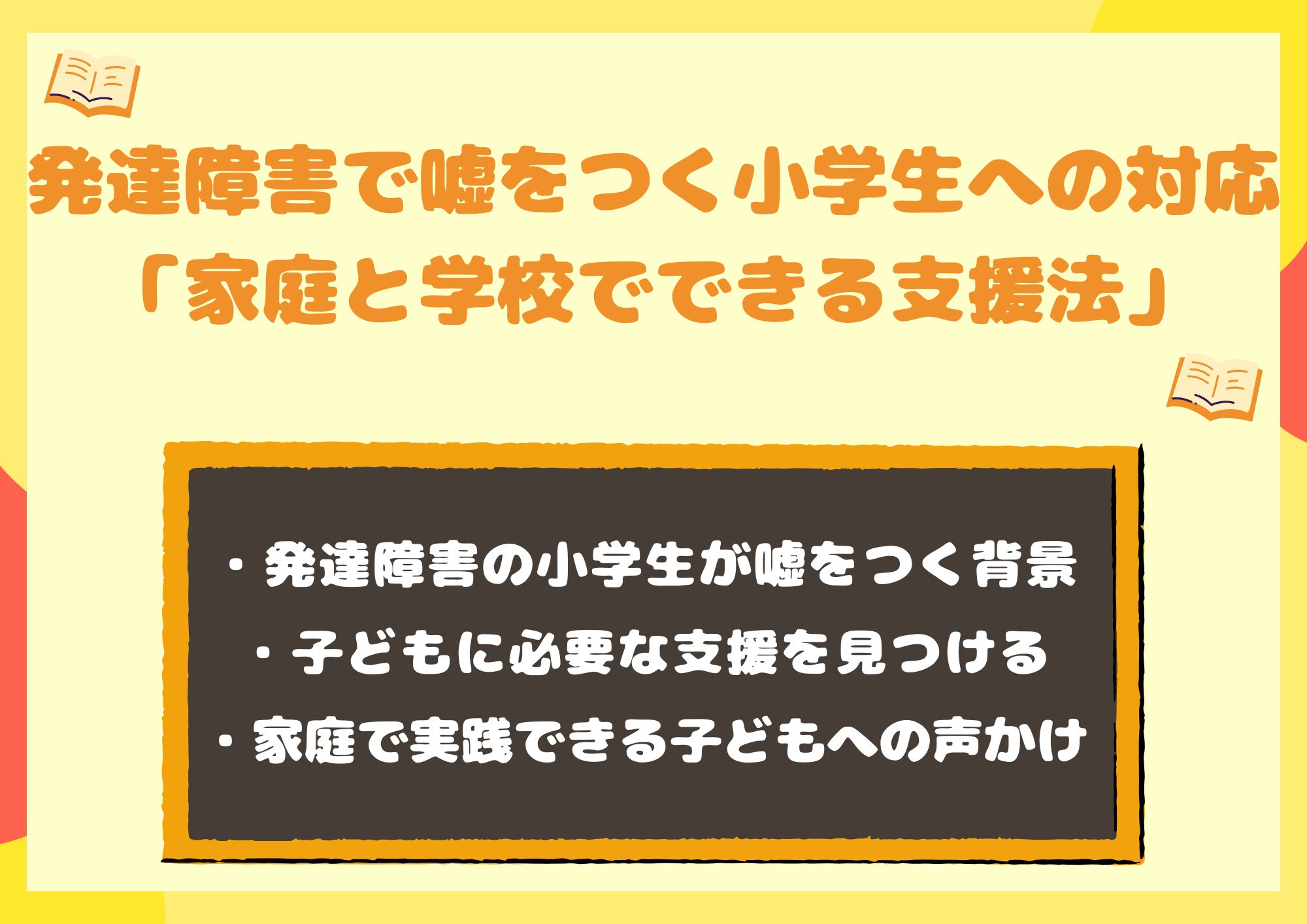
小学生のお子様がうそをついたり、返事をしない様子に戸惑いを感じていませんか。
発達障害の特性がある子どもたちにとって、これらの行動は「困っているサイン」であることが多く、叱るよりも環境を整えることで改善につながります。話に割り込む行動も含めて、お子様の気持ちを理解し、適切な支援方法を見つけることが大切です。
この記事では、発達障害のある小学生が示す様々な行動の背景を解説し、家庭や学校でできる具体的な対応方法、さらには専門的なサポートを提供する家庭教師サービスまで、包括的にご紹介します。
ランナーの無料体験はこちら!目次
発達障害のある小学生がうそをつく背景と「安心できる環境づくり」
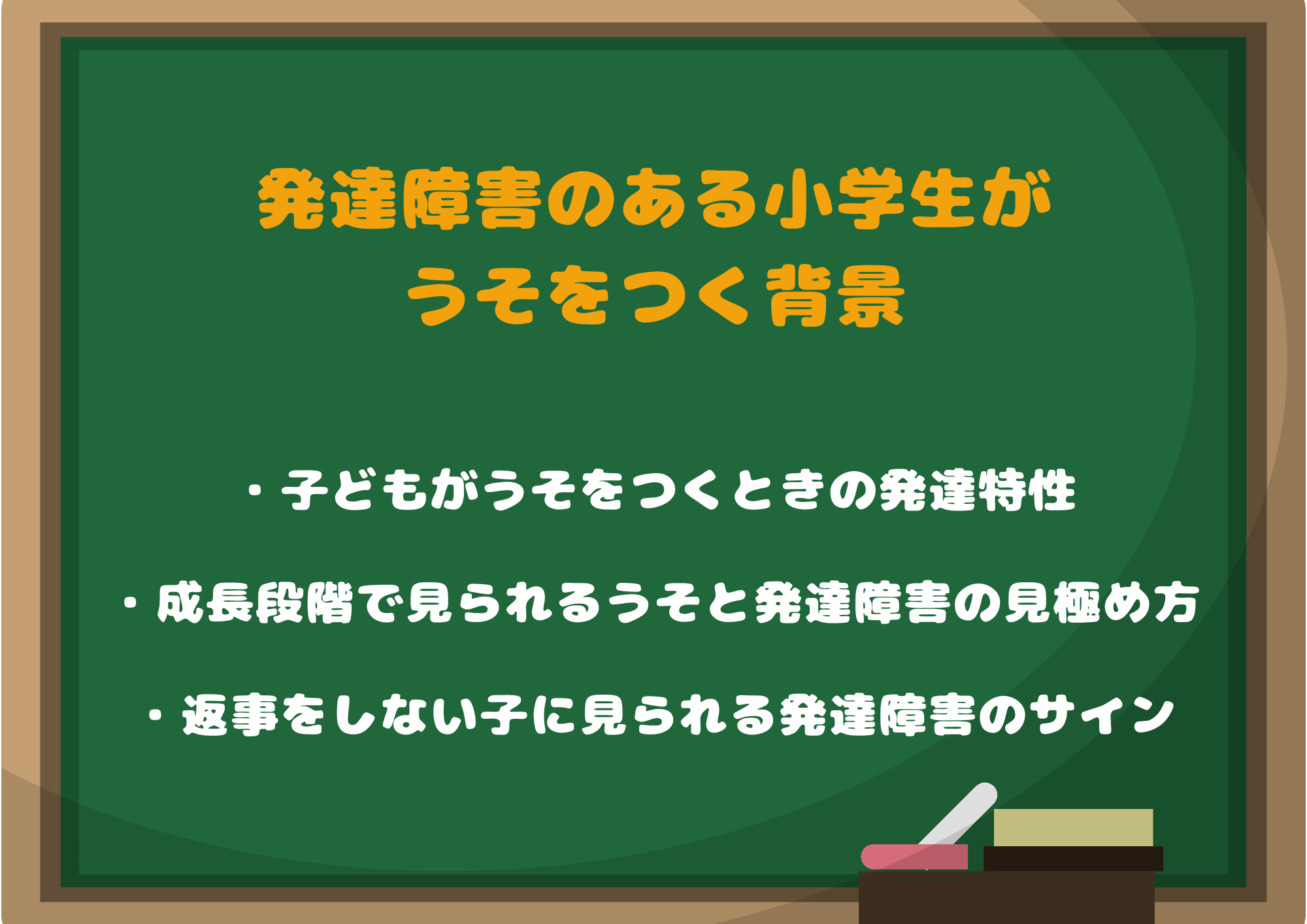
発達障害のある子どもがうそをつく行動には、実は深い理由があります。
小学生の時期は、自己認識が発達し始める大切な時期ですが、発達障害のある子どもたちは、情報処理や感情のコントロールに困難を抱えることがあり、結果として自己防衛的な応答になる場合があるのです。
これは決して「悪い子」なのではなく、その子なりの適応方法なのだと理解することが、支援の第一歩となります。
子どもがうそをつくときの発達特性と理解のポイント
- うそには「回避」「自己防衛」「記憶のズレ」「相手を喜ばせたい」の4つの機能がある
- ADHD特性では物をなくしやすく「知らない」と言いがち
- ASD特性では想像と記憶が混同されることがある
発達障害のある小学生がうそをつく背景には、主に4つの機能があります。
まず、課題や叱責から逃れたいという「回避」の機能です。宿題を「やった」と言ってしまうのは、できなかった自分を責められたくない気持ちの表れです。
次に、失敗を隠したいという「自己防衛」の機能があります。注意欠如・多動症(ADHD)の特性で物をなくしやすい子どもは、「知らない」と言うことで、その場をしのごうとします。
また、時間感覚や記憶のズレから生じるうそもあります。自閉スペクトラム症(ASD)の特性がある子どもの一部では、想像と記憶が混同されることがあります。
最後に、相手を喜ばせたいという思いから、事実と異なることを言ってしまうケースもあります。これらの特性を理解することで、お子様への接し方が変わってきます。
成長段階で見られるうそと発達障害の見極め方
- 同じパターンのうそを繰り返すのが特徴
- 特定の場面(宿題・片付け・友達関係)に集中する
- 頻度と生活への影響度を観察して見極める
小学生の時期には、発達障害の有無に関わらず、想像力の発達に伴ってうそをつくことがあります。しかし、発達障害が背景にある場合、その頻度や内容に特徴が見られます。
例えば、同じパターンのうそを繰り返す、状況に合わないうそをつく、うそをついたことを覚えていないなどの特徴があります。また、うそをつく場面が特定の状況(宿題、片付け、友達関係など)に集中している場合は、その場面で特に困難を感じている可能性があります。
成長に伴う一時的なうそなのか、支援が必要なサインなのかを見極めるには、頻度と生活への影響度を観察することが大切です。
週に何回起きるか、学校生活や家庭生活にどの程度影響しているかを記録してみましょう。
返事をしない子どもに見られる発達障害のサイン
- 聴覚過敏により複数の音を同時に処理できない
- 過集中状態では周囲の刺激に気づきにくい
- 情報処理に時間がかかっているサインである
返事をしない子どもの行動には、聴覚過敏や情報処理の特性が関係していることがあります。
発達障害のある小学生は、複数の音が同時に聞こえると、どれに注目すべきか分からなくなることがあります。
また、何かに集中しているときは、過集中(特定の対象に注意が強く向いた状態)により、周囲の刺激に気づきにくくなることがあります。
さらに、聞こえてはいるものの、返事をするタイミングが分からない、何と答えていいか分からないという場合もあります。これは無視をしているのではなく、情報処理に時間がかかっているサインです。
選択的緘黙の可能性も考えられますが、気になる場合は専門機関に相談することをおすすめします。
話に割り込む行動から分かる小学生の困りごと
- ADHDの衝動性により思いついたことをすぐ言いたくなる
- 会話のルールやタイミングを学習途中である
- 社会的スキルの習得に時間がかかっている
発達障害のある子どもが話に割り込む行動には、衝動性のコントロールの難しさが表れています。
ADHDの特性がある小学生は、思いついたことをすぐに言わないと忘れてしまうという不安から、相手の話を遮ってしまうことがあります。
また、会話のルールやタイミングを学習途中であることが多く、いつ話していいのか分からないという困難を抱える子どももいます。ASDの特性がある場合は、自分の興味のある話題になると、相手の反応を読み取れずに一方的に話し続けてしまうこともあります。
これらは「マナーが悪い」のではなく、社会的なスキルの習得に時間がかかっているということを理解し、練習の機会を作ることが大切です。
返事をしない・話に割り込む子どもの行動から「必要な支援を見つける」
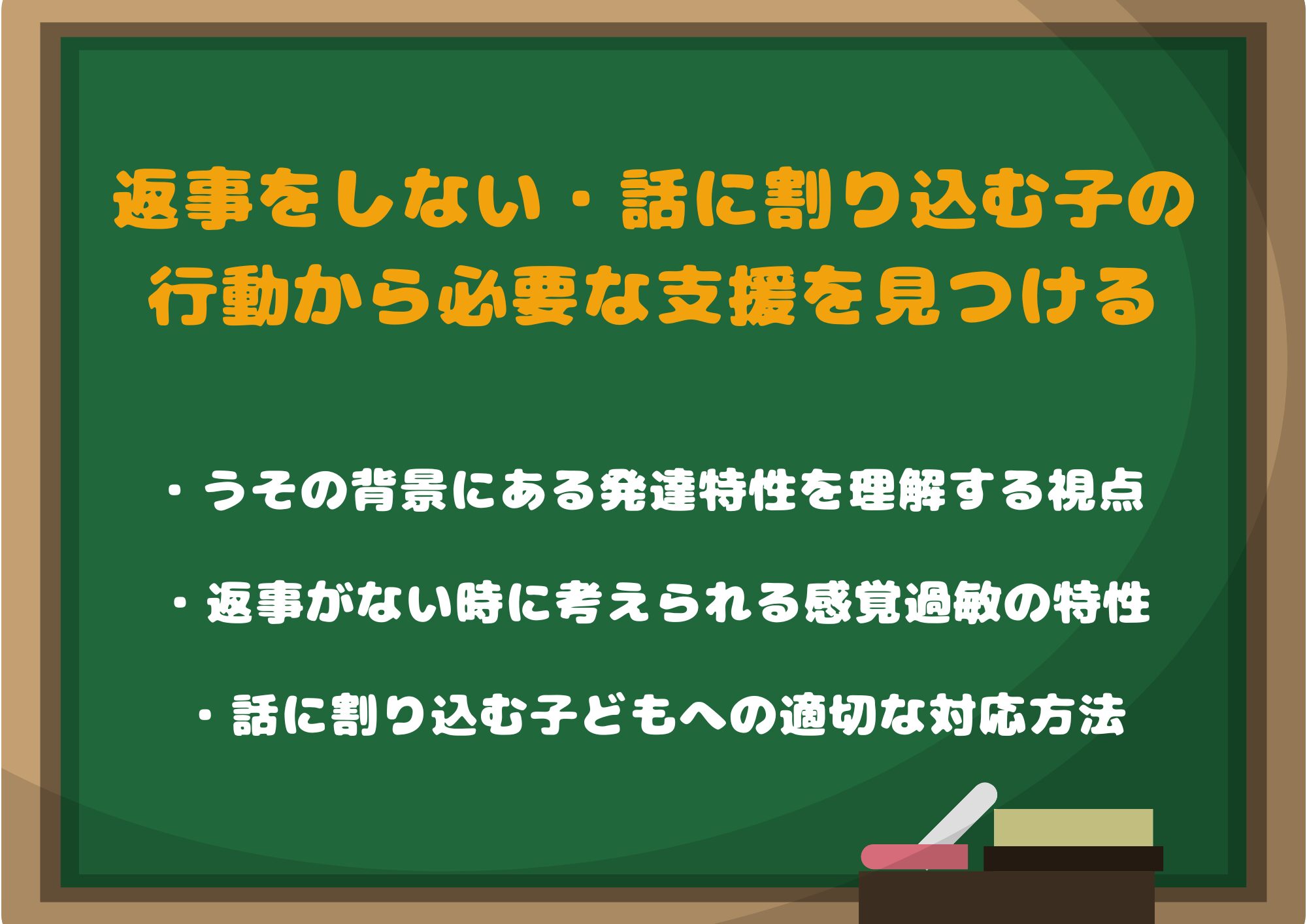
子どもたちの行動一つ一つには、理由があります。
返事をしない、話に割り込むといった行動も、その子なりの困りごとのサインです。
発達障害の特性を理解し、適切な支援方法を見つけることで、子どもたちは安心して自分を表現できるようになります。大切なのは、行動を「問題」として捉えるのではなく、「何に困っているのか」という視点で見ることです。
うその背景にある発達特性を理解する視点
- ABC分析で行動の前後を分析すると効果的
- ワーキング・メモリーの弱さが影響している
- 視覚的な支援ツールを使う工夫が必要
うそをつく行動を分析するときは、ABC分析(先行事象・行動・結果)を使うと効果的です。
例えば、宿題についてうそをつく場合、先行事象として「宿題の指示が理解できなかった」「やり方が分からなかった」という困りごとがあり、行動として「やった」とうそをつき、結果として「その場は叱られずに済む」という流れがあります。
この分析により、問題はうそそのものではなく、宿題への取り組み方にあることが分かります。
発達障害のある小学生は、ワーキング・メモリーの弱さから指示を覚えられなかったり、実行機能の困難さから計画的に取り組めなかったりすることがあります。これらの特性を理解し、視覚的な支援ツールを使うなどの工夫が必要です。
返事がない時に考えられる感覚過敏や集中の特性
- 聴覚過敏で複数の音が同じ大きさで聞こえる
- 触覚過敏により服の感触で集中できない
- 視界に入る位置から別の感覚でアプローチする
返事をしない子どもの背景には、様々な感覚処理の特性が隠れています。
聴覚過敏がある場合、エアコンの音、時計の音、外の車の音など、複数の音が同じ大きさで聞こえてしまい、人の声を選択的に聞き取ることが困難になります。また、触覚過敏があると、服の感触が気になって集中できないこともあります。
過集中の状態では、目の前のことに全神経を集中させているため、周囲の刺激に気づきにくくなることがあります。
このような状態の子どもに対しては、まず視界に入る位置に移動し、本人の同意がある場合に限り、肩を軽くタッチするなど、別の感覚を使ってアプローチすることが有効です。
返事を待つ時間も、通常の3秒ではなく、個人差を考慮して10秒程度まで延ばしてみましょう。
話に割り込む子どもへの適切な対応方法
- 「待つ」スキルを視覚的に教える
- 具体的なルールを決めて練習する
- 成功体験を積み重ねて褒める
話に割り込む子どもへの対応は、まず「待つ」スキルを視覚的に教えることから始めます。
「話したいことがあるときは手を挙げる」「相手が話し終わるまで5つ数える」など、具体的なルールを決めて練習します。
タイマーを使って「1分間聞く練習」をゲーム感覚で行うのも効果的です。また、子どもが話に割り込んでしまったときは、「今は〇〇さんの話を聞く時間だよ」と優しく伝え、「あなたの話は次に聞くから待っててね」と約束することで、安心して待てるようになります。
成功したときは必ず褒めて、「待てた」という成功体験を積み重ねていきましょう。
小学生のうそのパターンとその背景にある気持ち
- 願望型・防衛型・混乱型の3つのパターンがある
- 「認められたい」「怒られたくない」という気持ちが背景にある
- うそを責めずに気持ちを受け止めることが大切
発達障害のある小学生のうそには、いくつかの典型的なパターンがあります。
「願望型のうそ」では、「友達がたくさんいる」「テストで100点を取った」など、こうありたいという願望を現実として話してしまいます。「防衛型のうそ」では、失敗や困難を隠すために「忘れ物はしていない」「宿題はもう終わった」と言います。
「混乱型のうそ」では、記憶が曖昧で、事実と想像が混ざってしまいます。これらのうその背景には、「認められたい」「怒られたくない」「期待に応えたい」という切実な気持ちがあります。
子どものうそを責めるのではなく、その気持ちを受け止めることが大切です。
家庭で実践できる子どもへの声かけと「小さな変化を積み重ねる工夫」
発達障害のある小学生への対応は、日々の小さな工夫の積み重ねが大切です。
うそをつく、返事をしない、話に割り込むといった行動に対して、叱責ではなく、環境調整と適切な声かけで対応することで、子どもは安心して成長できます。
家庭でできる具体的な方法を実践し、「できた!」という成功体験を少しずつ増やしていくことが、子どもの自信につながります。
うそを責めずに子どもの気持ちを受け止める声かけ例
- 気持ちを代弁して理解を示す
- 一緒に解決方法を考える提案をする
- 正直に話せたときは必ず褒める
子どもがうそをついたときの声かけは、責めるのではなく、気持ちを理解することから始めます。
「宿題やった」とうそをついた場合は、「宿題のこと、心配だったんだね」と気持ちを代弁し、「一緒にやってみようか」と提案します。
「友達と遊んだ」という願望型のうそには、「友達と遊びたかったんだね」と共感を示し、「今度一緒に遊ぶ約束をしてみる?」と現実的な目標を設定します。
大切なのは、うそを指摘する前に、その背景にある気持ちを理解し、受け止めることです。「本当のことを話してくれてありがとう」と、正直に話せたときは必ず褒めることで、真実を話しても安全だという環境を作ります。
返事をしない子どもへの効果的な接し方と配慮点
- 視界に入る位置からアイコンタクトを取る
- 指示は短く具体的に一つずつ伝える
- 個人差を考慮して10秒程度待つ
返事をしない子どもには、まず環境と伝え方を工夫することが大切です。
呼びかける前に、子どもの視界に入る位置に移動し、アイコンタクトを取ってから話しかけます。「〇〇ちゃん」と名前を呼び、3秒待ち、反応がなければ本人の同意がある場合に限り肩を軽くタッチして、もう一度名前を呼びます。
指示は短く、一度に一つだけ伝え、「ご飯だよ」ではなく「手を洗ってきてね」と具体的に伝えます。聴覚過敏がある場合は、静かな環境で話しかけ、声のトーンを落とすことも効果的です。
返事がなくても、個人差を考慮して10秒程度は待ち、処理する時間を与えることが重要です。
話に割り込む場合の家庭での対応と練習方法
- 砂時計やタイマーで「待つ」を見える化する
- 「お話ゲーム」で会話のルールを練習する
- 成功したら必ず褒めて価値を理解させる
「待つ」を見える化する視覚支援ツール
話に割り込む子どもには、「待つ」ことを視覚的に理解できるツールが効果的です。
砂時計やタイムタイマーを使って、「この砂が全部落ちるまで待つ」という具体的な目標を設定します。
また、「話したいカード」を作り、話したいときはカードを持って待つというルールにすることで、気持ちをコントロールしやすくなります。
会話のルールを楽しく練習する方法
家族で「お話ゲーム」をして、会話のルールを練習しましょう。
「ボールを持っている人だけが話せる」というルールで、実際にボールを回しながら話す練習をします。最初は30秒ずつ、慣れてきたら1分ずつに延ばしていきます。
成功したら「よく待てたね!」と褒めることで、待つことの価値を理解できるようになります。
これらの練習を楽しみながら続けることで、子どもは自然に会話のルールを身につけていきます。
視覚支援ツールやチェックリストの活用例
- 朝の準備チェックリストで一つずつ確認
- タイムタイマーで残り時間を視覚化
- ルーティン表で見通しを持たせる
発達障害のある小学生には、視覚的な支援が非常に効果的です。
朝の準備チェックリストを作り、「歯磨き」「着替え」「カバンの準備」など、一つずつチェックできるようにします。
宿題管理表では、科目ごとに「やること」「終わったこと」を色分けして管理します。タイムタイマーで残り時間を視覚化し、「あと5分で片付け」という予告を分かりやすくします。
ルーティン表を作って、毎日の流れを視覚化することで、見通しが持てて不安が減ります。これらのツールを使うことで、子どもは自分で管理する力を少しずつ身につけていきます。
学校との連携で作る「子どもが安心して過ごせる環境」
発達障害のある小学生が学校で安心して過ごすためには、家庭と学校の連携が欠かせません。
うそをつく、返事をしない、話に割り込むといった行動について、学校での様子と家庭での様子を共有し、一貫した対応をすることで、子どもは混乱することなく成長できます。
先生との協力体制を築くことで、子どもにとって最適な学習環境を整えることができます。
担任の先生に伝えたい家庭での様子と困りごと
- 問題行動と効果的な対応をセットで伝える
- 具体的な配慮方法をお願いする
- 家庭での取り組みを共有して連携する
担任の先生には、具体的な事実と対応方法を簡潔に伝えることが大切です。
「宿題についてうそをつくことがあります。家では、宿題を小分けにして、一つ終わるごとに褒めることで改善が見られました」というように、問題行動と効果的だった対応をセットで伝えます。
返事をしない場合は、「呼びかけてから10秒程度待っていただけると返事ができることが多いです(個人差があるため目安です)」と具体的な配慮をお願いします。
話に割り込む傾向がある場合は、「手を挙げるルールを家で練習しています」と家庭での取り組みを共有し、学校でも同じルールで対応してもらえるよう相談します。
特別支援学級・通級指導教室・スクールカウンセラーの活用方法
- 特別支援学級では少人数で個別配慮を受けられる
- 通級指導教室で週に数時間個別学習が可能
- スクールカウンセラーは保護者の相談にも対応
学校には様々な支援体制があり、子どもの特性に応じて活用できます。
特別支援学級では、少人数で個別の配慮を受けながら学習できます。
通級指導教室では、週に数時間、コミュニケーションスキルや学習の基礎を個別に学べます。スクールカウンセラーは、子どもだけでなく保護者の相談にも応じてくれます。
これらの支援を受けるには、まず担任の先生に相談し、必要に応じて教育相談や発達検査を受けることになります。早めに相談することで、子どもに合った支援を受けられる可能性が高まります。
連絡帳や面談で共有したいポイント
- 日々の小さな変化や成功体験を記録
- 困りごとには家庭での対応も併せて伝える
- 定期的な情報交換で多角的にサポート
連絡帳では、日々の小さな変化や成功体験を共有することが重要です。
「今日は自分から宿題を見せてくれました」「10秒待つと返事ができました」など、ポジティブな変化を中心に記録します。
困りごとを相談する際は、「〜で困っています。〜を試してみます」という形で、家庭での対応も併せて伝えます。
面談では、事前に伝えたいことをメモにまとめ、優先順位をつけて話します。学校での様子を聞き、家庭での様子と照らし合わせて、共通の対応方針を決めていきます。
定期的な情報交換により、子どもの成長を多角的にサポートできます。
専門機関への相談を検討する「タイミングと選び方」
発達障害が疑われる場合、専門機関への相談を検討することも大切です。
うそをつく、返事をしない、話に割り込むといった行動が日常生活に大きな影響を与えている場合は、早めの相談が子どもの将来にプラスになります。
相談することは決して「レッテルを貼る」ことではなく、子どもの特性を理解し、より良い支援を受けるための第一歩です。
うそや返事をしない行動が続く時の相談の目安
- 2週間以上改善が見られない場合
- 学習や友人関係に明らかな影響がある場合
- 早期相談で二次的な困難の予防につながる
専門機関への相談を検討する目安として、以下のような状況があります。
行動が週に何度も繰り返され、2週間以上改善が見られない場合、学習や友人関係に明らかな影響が出ている場合、子ども自身が強い不安や自己否定感を抱いている場合などです。
また、家庭での対応に限界を感じたり、学校から相談を勧められたりした場合も、相談のタイミングです。早期に相談することで、適切な支援を受けられ、二次的な困難の予防につながる場合があります。
迷ったら、まず相談してみることが大切です。専門家は、発達障害の診断だけでなく、子育ての悩みにも寄り添ってくれます。
地域の相談先と活用のポイント
- 市町村の発達相談センターで無料相談が可能
- 民間療育施設では個別・小集団プログラムあり
- かかりつけ医から適切な紹介先を教えてもらう
地域には様々な相談窓口があり、それぞれ特徴があります。
市町村の発達相談センターでは、無料で発達検査や相談を受けられます。児童相談所では、より専門的な支援が必要な場合の相談に応じています。
教育センターでは、学校生活に関する相談ができます。民間の療育施設では、個別や小集団での療育プログラムを受けられます。
医療機関の発達外来では、診断や投薬治療も含めた総合的な支援を受けられます。まずは、かかりつけの小児科医に相談し、適切な紹介先を教えてもらうのも良い方法です。
発達外来・専門医を選ぶときの確認事項
- 待機期間と発達検査の実施有無を確認
- 療育プログラムや学校連携体制をチェック
- 成長記録や学校情報を持参してスムーズな診察を
発達外来や専門医を選ぶ際は、いくつかの確認事項があります。まず、待機期間を確認し、初診まで何か月待つのかを把握します。
発達検査の実施有無と、検査結果の説明方法も重要です。療育プログラムの有無や、学校との連携体制についても確認しましょう。
また、セカンドオピニオンを求めることも可能です。医師との相性も大切なので、子どもが安心して受診できる環境かどうかを見極めます。
初診時は、これまでの成長記録や学校からの情報をまとめて持参すると、スムーズな診察につながります。
発達障害のある小学生を支える「家庭教師サービスの特徴と選び方」
発達障害のある小学生にとって、個別対応ができる家庭教師は非常に有効な学習支援となります。
うそをつく、返事をしない、話に割り込むといった特性がある子どもも、マンツーマンの環境では安心して学習に取り組めます。
それぞれの家庭教師サービスには特色があり、お子様の特性やご家庭の状況に合わせて選ぶことができます。
家庭教師のランナー「不登校や発達障害への専門的サポート」

- 発達障害コミュニケーション指導者が在籍
- お子様の特性に合わせた最適な先生をマッチング
- オンライン指導で柔軟な対応が可能
私たち家庭教師のランナーは、創業20年の実績を持ち、発達障害や不登校のお子様への支援に特に力を入れています。
発達障害コミュニケーション指導者が在籍し、専門的な知識を持ったスタッフが、お子様一人ひとりの特性を理解した上で、最適な先生をマッチングします。
カウンセリングでは、お子様の特性や困りごとを詳しくお聞きし、妥協することなく相性の良い先生を探します。
料金は、1コマ(30分)小中学生900円・高校生1000円というシンプルで分かりやすい料金体系を採用しています。オンライン指導にも対応しており、お子様の希望に応じて柔軟な対応が可能です。
定期的にスタッフがご家庭の様子を伺い、小さな悩みにも親身に対応させていただきます。
ランナーの無料体験はこちら!家庭教師のトライ「個別対応で子どものペースに合わせた指導」

- 業界最大手の豊富な教師陣
- 専任教育プランナーによるサポート体制
- トライ式学習法で発達特性に応じた指導
家庭教師のトライは、業界最大手として多数の登録教師から、発達障害のある小学生に対応できる経験豊富な教師を選定します。
完全マンツーマン指導により、返事をしない子どもにも根気強く対応し、その子のペースに合わせた学習を進めます。
専任の教育プランナーが、ご家庭と教師の間に立ち、きめ細かなサポートを提供します。
トライ式学習法では、発達特性に応じた学習方法を提案し、視覚的な教材や具体的な説明で理解を深めます。相性が合わない場合は教師交代が可能で、お子様に最適な環境を整えます。
学研の家庭教師「小学生の困りごとに寄り添う指導体制」

- 教育大手の学研グループが運営
- 特別支援教育の知識を持つ教師を紹介
- 視覚的に分かりやすい教材での指導
学研の家庭教師は、教育大手の学研グループが運営しており、発達障害のある小学生への指導経験が豊富です。
話に割り込む子どもへの対応経験がある教師や、特別支援教育の知識を持つ教師を紹介できます。学研の教材開発ノウハウを活かし、視覚的に分かりやすい教材を使った指導が特徴です。
オンライン指導では、画面共有機能を使って、集中力を保ちやすい環境を作ります。保護者への定期的な報告により、お子様の成長を共有し、家庭での対応についてもアドバイスを提供します。
家庭教師ファースト「マンツーマンで安心できる学習環境」

- 実際の担当教師で体験授業を実施
- 不登校支援コースでコミュニケーション能力もサポート
- 手持ち教材での指導も可能
家庭教師ファーストは、実際に担当する先生で体験授業を行うため、発達障害のある小学生も安心して学習を始められます。
料金は地域・コースにより異なりますので、詳細は公式サイトでご確認ください。不登校支援コースもあり、学習だけでなく、コミュニケーション能力の向上もサポートします。
手持ちの教材を使った指導も可能なため、お子様に馴染みのある教材で学習を進められます。オンライン指導でも、対面と同様の質の高い指導を受けられます。
家庭教師のサクシード「話に割り込む子どもへの配慮あるサポート」

- 上場企業運営の安心感
- 1回の授業で複数科目の指導が可能
- 体験授業の先生がそのまま正式担当に
家庭教師のサクシードは、上場企業が運営する安心感と、充実した教師陣による手厚いサポートが特徴です。
料金は地域・コースにより異なりますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。
教務スタッフによる学習計画のサポートにより、発達障害のある小学生でも無理なく学習を継続できます。1回の授業で複数科目を指導できるため、集中力が続きにくいお子様にも柔軟に対応します。
体験授業を担当した先生がそのまま正式担当になるシステムで、安心して学習をスタートできます。
家庭教師のノーバス「返事をしない子どもへの支援実績と特徴」

- 関東・東海地方で展開する大手センター
- 教師と学習プランナーのダブル体制
- 特別支援教育の専門知識を持つ教師も在籍
家庭教師のノーバスは、関東・東海地方で展開する大手家庭教師センターで、発達障害児への支援実績が豊富です。
教師と学習プランナーのダブル体制により、学習面と生活面の両方をサポートします。個別指導塾も運営しているため、豊富な指導ノウハウがあります。
プロ家庭教師コースでは、特別支援教育の専門知識を持つ教師による指導も受けられます。オンライン指導サービスも提供しており、全国どこからでも質の高い指導を受けることができます。
家庭教師のあすなろ「家庭の悩みに寄り添うサービス内容」
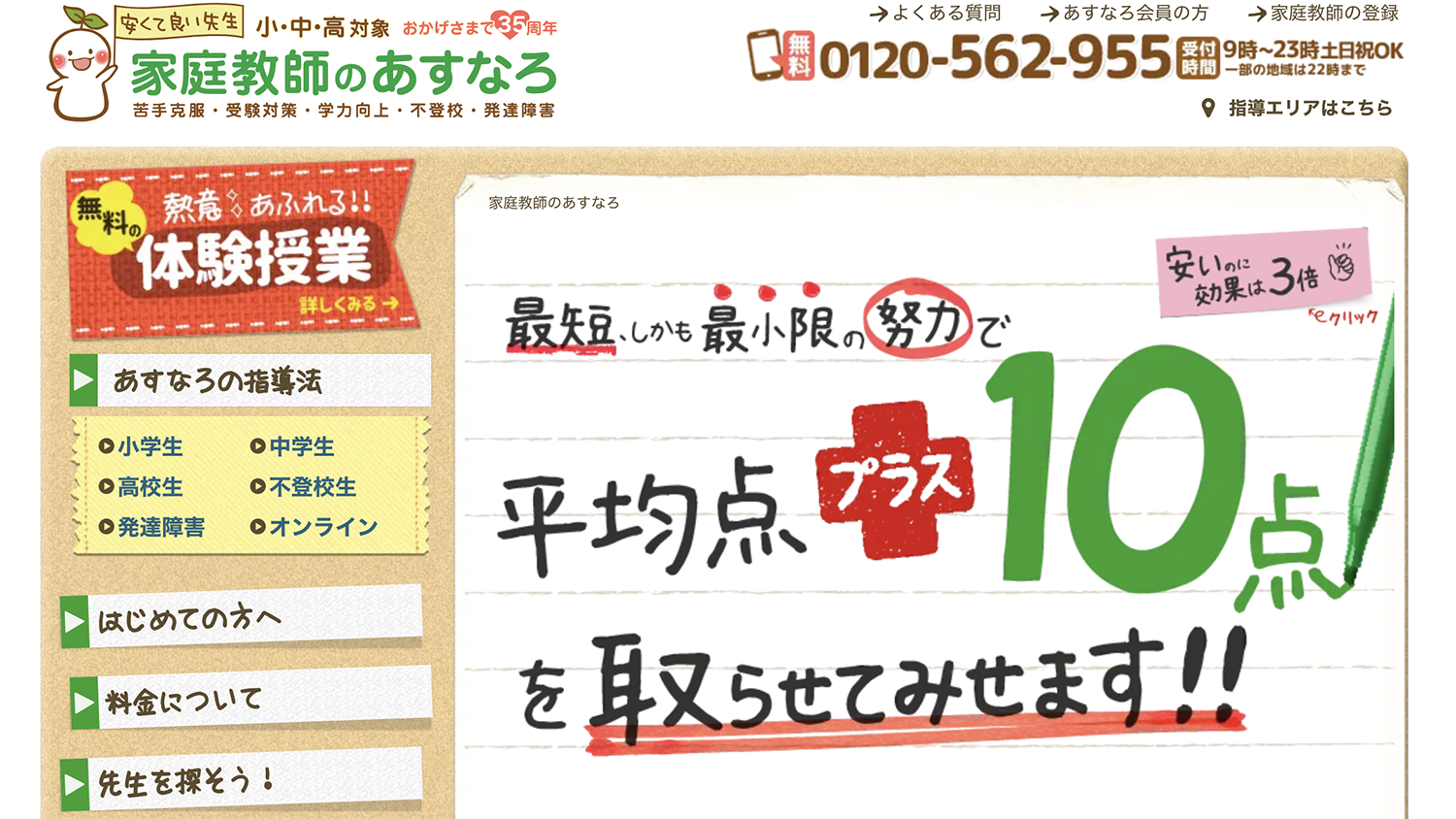
- 勉強が苦手な子専門の長年の実績
- 大学生中心の親しみやすい先生
- LINEでの質問対応サービスあり
家庭教師のあすなろは、「勉強が苦手な子専門」として長年の実績があり、発達障害のある小学生の指導にも慣れています。
大学生中心の若い先生が、お兄さん・お姉さんのような親しみやすい関係を築きます。料金は地域・コースにより異なりますので、詳細は公式サイトでご確認ください。
LINEでの質問対応サービスにより、授業がない日でもサポートを受けられます。基礎固めに重点を置いた指導により、学習の土台をしっかりと作ります。
家庭教師 学参「発達障害のある子ども向けの専門的な指導」

- プロ家庭教師専門の紹介センター
- 無料体験授業で相性を確認
- 授業回数の調整が柔軟に可能
家庭教師学参は、長年の指導実績を持つプロ家庭教師専門の紹介センターです。
全員が指導経験者である講師陣は、発達障害のある小学生への対応にも精通しています。
無料体験授業で相性を確認してから契約できるため、話に割り込む子どもや返事をしない子どもも、安心できる先生と出会えます。
部活や習い事に合わせて授業回数を調整できる柔軟性があり、発達障害のある子どもの体調や気分に応じた対応も可能です。教務担当によるフォローアップも充実しています。
オンライン家庭教師Wam「全国対応で柔軟な学習サポート」

- 独自開発の専用システムで集中しやすい環境
- 全国どこからでも受講可能
- チャット機能でコミュニケーションサポート
オンライン家庭教師Wamは、独自開発の専用システムにより、発達障害のある小学生でも集中しやすい学習環境を提供します。
料金は地域・プラン・キャンペーンにより異なりますので、最新情報は公式サイトでご確認ください。有名大学生による指導により、質の高い学習が可能です。
画面上での双方向やり取りがスムーズで、返事をしない子どもでも、チャット機能などを使ってコミュニケーションを取れます。全国どこからでも受講可能で、移動時間がないため、お子様の負担も軽減されます。
今日から使える観察記録と「子どもに伝わる声かけ集」
発達障害のある小学生への対応は、日々の観察と適切な声かけが重要です。
うそをつく、返事をしない、話に割り込むといった行動を記録し、パターンを見つけることで、より効果的な対応ができます。
また、その場面に応じた声かけを準備しておくことで、落ち着いて対応できるようになります。
家庭で使える行動観察チェックリストの作り方
- 時間帯・場所・相手・状況・行動・結果を記録
- 1週間続けることでパターンが見える
- 時間帯別の配慮で適切な支援につながる
行動観察チェックリストは、お子様の行動パターンを理解するための重要なツールです。まず、記録する項目を決めます。
「いつ(時間帯)」「どこで(場所)」「誰と(相手)」「何をしていた時(状況)」「どんな行動(うそ・返事なし・割り込み)」「その後どうなったか(結果)」を記録します。
1週間続けると、パターンが見えてきます。例えば、「夕方の宿題時間にうそが多い」「朝は返事をしない」などの傾向が分かれば、その時間帯に特別な配慮をすることができます。
記録を続けることで、お子様の困りごとがより明確になり、適切な支援につながります。
場面別の声かけ例「うそ・返事なし・話に割り込む時」
- うそには気持ちの代弁から始める
- 返事がない時は方法を広げて対応
- 話に割り込んだら見通しを示す
うそをついた時の声かけ例
うそをついた時は、まず深呼吸をして落ち着いてから対応します。
「本当のことを話すのが怖かったんだね」と気持ちを代弁し、「一緒に解決方法を考えよう」と提案します。
「次からは、困ったときは『分からない』『難しい』って言ってもいいんだよ」と、代替の表現を教えます。
返事をしない時の声かけ例
返事がない時は、「聞こえているけど、返事するのが難しいのかな?」と理解を示します。
「手を挙げてくれるだけでもいいよ」「うなずいてくれるだけでもいいよ」と、返事の方法を広げます。返事ができた時は、「返事してくれてありがとう」と必ず伝えます。
話に割り込んだ時の声かけ例
話に割り込んだ時は、「話したいことがあるんだね」と気持ちを受け止めます。
「今は〇〇さんの話を聞く時間だから、もう少し待ってね」と優しく伝え、「あと1分で君の番だよ」と見通しを示します。
待てた時は、「よく待てたね!今度は君の話を聞くよ」と約束を守ります。
これらの声かけを繰り返すことで、子どもは安心して適切な行動を身につけていきます。
よくある質問と専門的なアドバイス
発達障害のある小学生を育てる保護者の方々から、よく寄せられる質問と、それに対する専門的なアドバイスをご紹介します。
うそをつく、返事をしない、話に割り込むといった行動への対応に悩む声は多く、同じ悩みを持つ方々の参考になれば幸いです。
保護者の悩みに対する具体的な対応例
- うそは困っているサインとして理解する
- 返事の形は様々でアイコンタクトも立派な返事
- 学校と連携して一貫した対応を心がける
「毎日うそをつかれて、信頼関係が崩れそうです」という悩みには、うそは信頼を裏切る行為ではなく、困っているサインだと理解することが大切です。うそをつかなくても安全だと感じられる環境を作り、小さな正直さも褒めることで、少しずつ改善していきます。
「返事をしないので、無視されているように感じます」という悩みには、返事の形は様々で、アイコンタクトやうなずきも立派な返事だと認識を変えることが重要です。
「授業中に話に割り込んで、先生から注意を受けます」という悩みには、学校と連携して、手を挙げるルールの徹底や、発言カードの活用などを提案します。家庭での練習を学校でも実践できるよう、一貫した対応を心がけましょう。
子どもの成長に伴う変化と将来への見通し
- 適切な支援により必ず成長する
- 中学生では自己理解が深まり対処法を身につける
- 特性を強みに変えて活躍する可能性がある
発達障害のある子どもも、適切な支援により成長します。
小学生の時期に見られるうそや返事をしない行動も、理解と対応により改善していきます。
中学生になると、自己理解が深まり、自分の特性を理解した上で対処法を身につけられるようになります。話に割り込む行動も、社会的スキルの習得により、適切なタイミングで発言できるようになります。
大切なのは、今できないことを悲観するのではなく、小さな成長を認め、褒めることです。将来的には、特性を強みに変えて活躍する大人に成長する可能性は十分にあります。
早期の適切な支援が、お子様の可能性を最大限に引き出します。
まとめ「子どもの気持ちに寄り添いながら支援を続けるために」
- ・うそ・返事をしない・話に割り込むは困っているサイン
- ・発達特性を理解して環境を整えることが大切
- ・家庭・学校・専門機関の連携で適切な支援を
- ・家庭教師サービスで個別対応の学習支援が可能
- ・小さな成功体験を積み重ねて自信を育てる
発達障害のある小学生が示すうそをつく、返事をしない、話に割り込むといった行動は、その子なりの適応方法であり、困っているサインです。
これらの行動を「問題」として捉えるのではなく、背景にある発達特性や気持ちを理解することから、本当の支援が始まります。お子様の特性を理解し、環境を整え、適切な声かけをすることで、良い変化が生まれやすくなります。
家庭での小さな工夫、学校との連携、必要に応じた専門機関への相談、そして個別対応ができる家庭教師の活用など、様々な支援方法があります。
家庭教師のランナーをはじめとする各サービスは、発達障害のあるお子様一人ひとりの特性に合わせた指導を提供しています。マンツーマンの環境では、お子様のペースに合わせて、じっくりと向き合うことができます。
私たちは、お子様の「できた!」という成功体験を大切にし、自信を育てるお手伝いをさせていただきます。
子育てに正解はありません。試行錯誤しながら、お子様に合った方法を見つけていくことが大切です。
一人で悩まず、周りのサポートを上手に活用しながら、お子様の成長を見守っていきましょう。今日から始められる小さな一歩が、お子様の明るい未来につながることを信じて、一緒に歩んでいきましょう。
ランナーの無料体験はこちら!