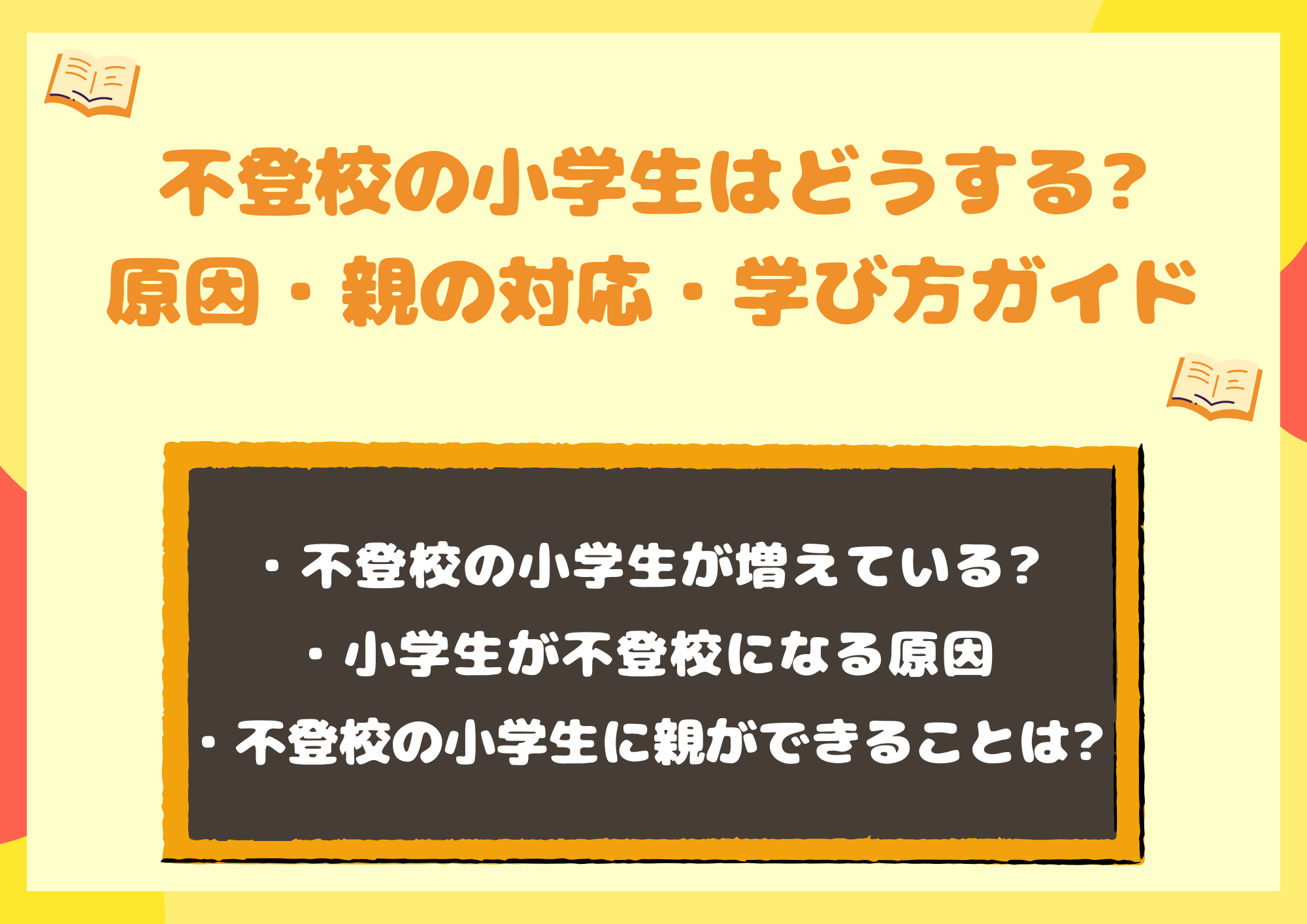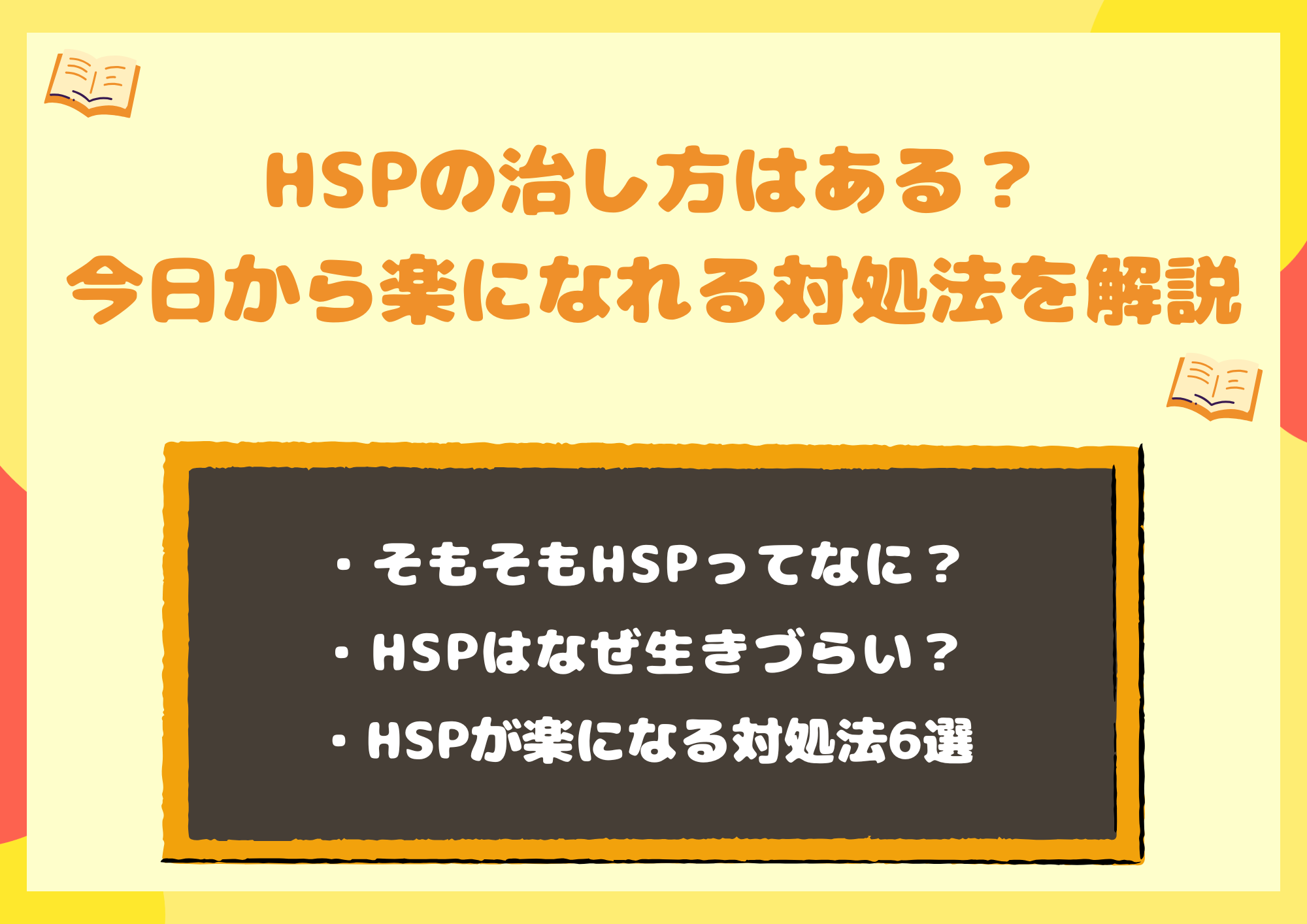- 不登校向けの家庭教師
不登校は甘え!という誤解と本当の原因を解説|対処法からおすすめ家庭教師まで全て紹介
2025.08.14

「子どもが学校に行けないのは甘えなのか?」という疑問に悩むご家庭は決して少なくありません。
不登校の子どもを持つ保護者は、「甘え」と言われることで自責や混乱を感じることがありますが、現代の不登校は単純な理由だけで生じるものではありません。
精神的なプレッシャーや人間関係、発達特性、家庭環境など複数の背景が複雑に絡み合っています。
この記事では、「不登校=甘え」という誤解を解き、子どもが直面する本当の理由や、保護者ができる対処法、そしてサポートに役立つ家庭教師サービスまで幅広く紹介します。
お子さまとご家庭が少しでも前向きな一歩を踏み出せるよう、正しい理解と実践的なヒントをお伝えします。
目次
「不登校は甘え!」という誤解とその本当の理由
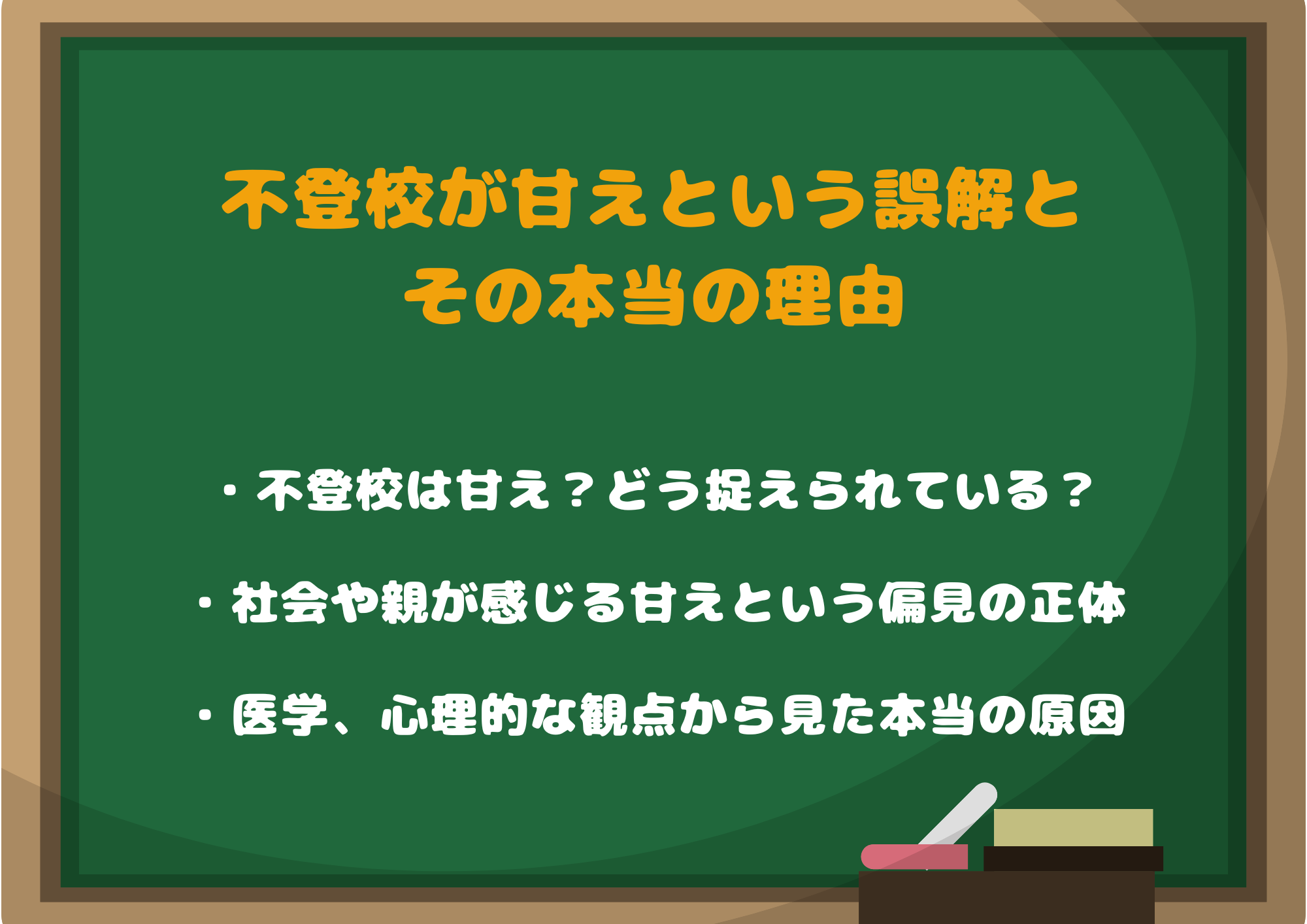
子どもが不登校になると、保護者や周囲の人は「これは甘えなのでは」と考えることがあります。
SNSなどでも「不登校=甘え」「親が甘やかしている」などの意見が目につきますが、実際の背景は多岐にわたります。
ここでは「甘え」という言葉がどう使われているのかと、本質的な理由を掘り下げていきます。
「不登校は甘え?」どう捉えられているのか?
- 家庭内で「うちの子は甘えているのでは」と不安が生じやすい
- 社会的には努力不足や怠けと結びつけられがち
- 「甘え」と決めつけることで本当のSOSを見逃すリスクがある
不登校の問題が起きると、家庭内で「うちの子は甘えているのでは」といった不安が生まれがちです。
親戚や知人から「もっと厳しくすべき」「甘やかしすぎだ」と指摘されることも多く、社会的には不登校を努力不足や怠けと結びつける見方が根強く残っています。
このような考え方は、お子さまや家族をさらに追い詰める一因となることがあります。
不登校は「甘え」や「わがまま」だけが原因で起こるわけではありません。
むしろ、本人は心身の不調やさまざまな環境要因に苦しみ、助けを必要としていることが多いのです。
周囲が「甘え」と決めつけてしまうと、本当の気持ちやSOSサインを見逃してしまうリスクがあります。
子どもの気持ちを正しく理解するには、一度「甘え」という先入観を脇に置いて、寄り添う姿勢が大切です。
保護者の不安も自然なものですが、一人で抱え込まず、専門機関や支援者の力を借りることも有効です。
社会や親が感じる「不登校は甘え」という偏見の正体
- 「学校へ行くのが当然」という社会的価値観が偏見を生みやすい
- 親や社会の不安や戸惑いが「甘え」というレッテルに反映される
- 本質的な問題を見失わない視点が大切
日本では「学校へ行くのが当然」という価値観が根強く、不登校の子どもに「甘えている」「しつけ不足」といった偏見が生まれやすい背景があります。
保護者も、周囲からの視線や意見に心を痛めることが多いものです。
「甘え」というレッテルには、親や社会の不安や戸惑いも反映されています。
不登校を「甘え」と決めつけてしまうと、本来向き合うべき問題の本質を見失いがちです。
子どもたちが抱えているストレスや心の葛藤は、大人が想像している以上に深刻な場合があります。
現代の不登校は、友人関係の不和やいじめ、家庭内トラブル、発達障害、精神的な課題などが複雑に関係しています。
決めつけを捨てて、「今子どもはどんな気持ちなのか」を一緒に考えることが、保護者にできる大切な一歩です。
社会の価値観も見直されつつある今、柔軟な見方が求められています。
医学的・心理的な観点から見た不登校の本当の原因
- 医学的にはうつや起立性調節障害、発達障害が関与することも多い
- 心理的にはいじめやストレス、自己肯定感の低下などが複雑に絡む
- 多面的な理解と専門的な支援が重要
文部科学省や日本小児精神医学会の調査によると、不登校の背景には「甘え」だけでは説明できない要因が多く存在します。
医学的には、うつ状態や起立性調節障害、自律神経の乱れ、発達障害(ASD・ADHD・LDなど)が関係していることも報告されています。
また、心理的には、いじめや人間関係の悩み、過度なストレス、自己肯定感の低下なども複雑に絡み合っています。
これらは子ども自身の意思だけで解決できる問題ではなく、「甘え」と一括りにするのは適切ではありません。
不登校の原因は多面的であり、正確な理解と支援が重要です。
子どもの苦しさや不安を見逃さず、医学的・心理的な視点で原因を探り、必要に応じて専門家の力を借りることも選択肢です。
「怠け」や「わがまま」と決めつけず、一人ひとりに合ったサポートを考えましょう。
不登校が「甘え」とされるケースの特徴とタイプ
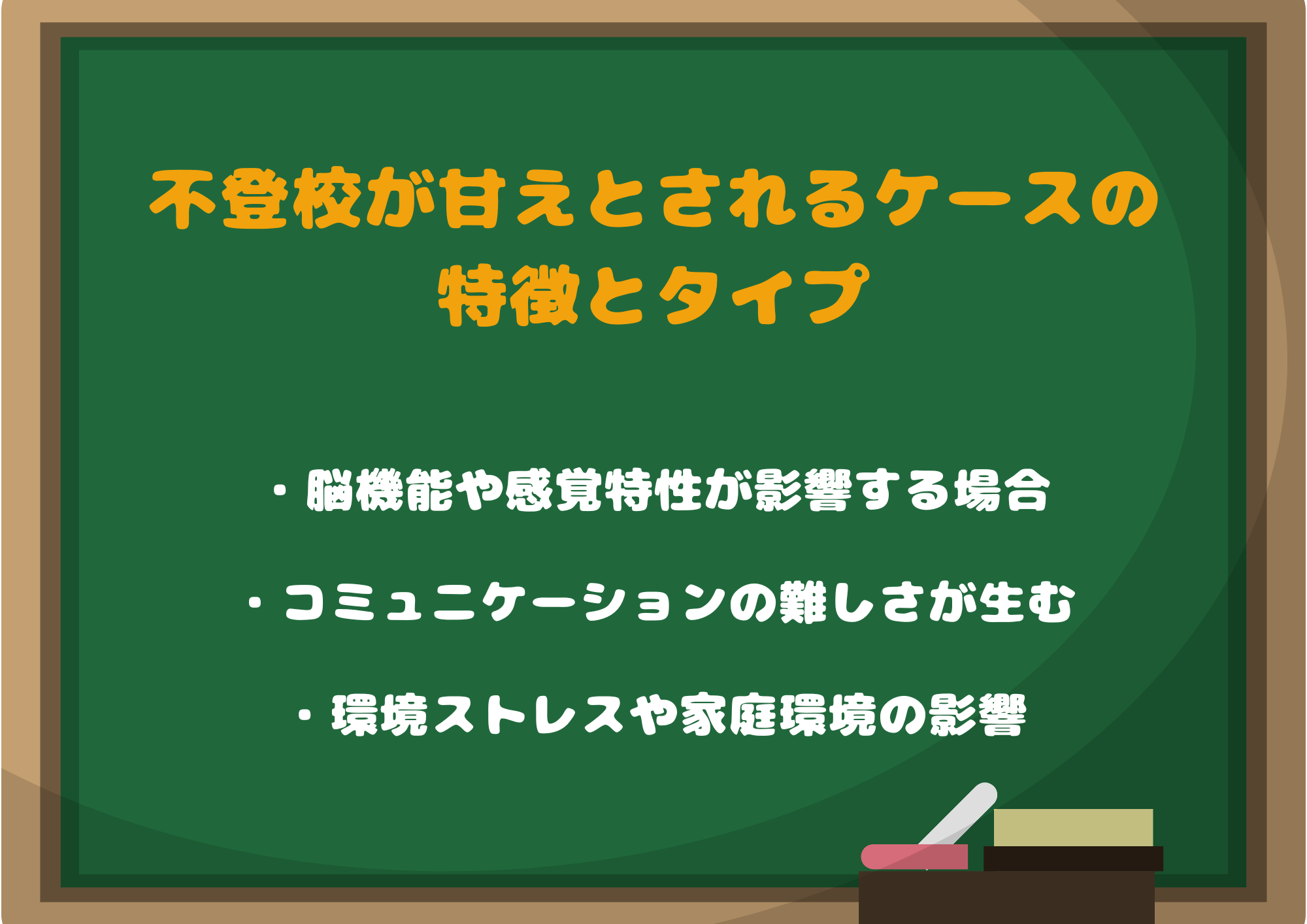
不登校が「甘え」とみなされやすいケースには共通した特徴があります。
たとえば、親への強い依存や、家庭で過剰なサポートを受けている状態では、外部から「甘えている」と判断されやすい傾向があります。
ですが、そうした行動にも個々の理由があります。
「甘え依存型」と呼ばれるタイプの行動や家庭環境の影響を具体的に紹介し、保護者としてどのように関わるべきかを考えていきましょう。
不登校の子どもが家庭に強く依存するのは、「外の世界が不安」「家だけが安心できる」と感じているからです。
また、過保護や過干渉、逆に無関心といった極端な家庭環境も影響します。
家庭の中でだけ安心感を求め、登校意欲が薄れるケースが多く見られます。
この場合も「甘え」で片付けることはできません。
子どもから発せられるSOSや、家庭でのコミュニケーションを見直すことがポイントです。
不登校の「甘え依存型タイプ」の子どもに見られる特徴
- 家庭内では元気だが外では不安や緊張が強い
- 登校直前に体調不良を訴える、親から離れたがらない傾向
- 強い依存の背景には子どもの不安が隠れている
「甘え依存型」とされる子どもは、家庭内では元気でも外では緊張や不安を強く感じやすい傾向があります。
登校や習い事の直前になると体調不良を訴える、朝起きられなくなる、親から離れたがらない、という行動が目立ちます。
また、何かを決めるときは親の同意を必要としたり、気を引くために無意識にトラブルを起こす場合もあります。
このタイプの背景には、子どもの不安や家庭での安心感への強い期待が隠れています。
一見わがままのように見えても、本人なりの必死のサインであることが多いのです。
保護者は「依存しすぎかも」と自責するのではなく、まずは子どもの気持ちを受け止めることから始めてください。
専門家や家庭教師サービスの利用も有効な選択肢となります。
家庭内で過度な依存がある場合のサインとは
- 親から離れるのを極端に嫌がる、家でだけ元気になる
- 体調不良やトラブルの頻発、常に親の顔色をうかがう
- 依存の背景には深い不安や緊張がある
家庭内で過度な依存が見られる場合、登校が困難になるだけでなく日常生活にもサインが表れます。
たとえば、親から離れるのを極端に嫌がる、家では元気でも外では無気力になる、自己主張せず常に親の顔色をうかがうなどがその例です。
朝になると体調不良を訴えることが増えたり、家庭内トラブルが絶えない場合も依存が強いと考えられます。
周囲からは「甘え」と見られがちですが、子どもは家庭に安心を求めている状態です。
依存の背後には子どもの深い不安や緊張が隠れています。
保護者は無理に突き放そうとせず、安心できる環境づくりを優先しましょう。
手を貸しすぎない程度の距離感を保ちつつ、子どもの自立を少しずつ促していくのが大切です。
必要に応じて、外部支援や相談サービスの活用も視野に入れましょう。
親子関係や家庭環境が与える影響
- 過干渉や過保護、無関心、親同士の不仲が影響する
- 信頼関係や家庭の安心感が回復の大きな力となる
- 家庭教師サービスの活用も有効な選択肢
不登校には親子関係や家庭環境が大きく関係します。
過干渉・過保護や逆に無関心、コミュニケーション不足、親同士の不仲、兄弟間での比較や期待などが影響する場合もあります。
このような環境は、子どもが外の社会に向かうエネルギーを育てにくくします。
一方で、家庭が安定し信頼関係が築かれていれば、子どもは徐々に外の世界にも目を向けやすくなります。
親子の信頼関係や家庭の安心感は、不登校を乗り越える大きな力となります。
家庭内の雰囲気や関わり方を見直し、自己肯定感を高めてあげることが大切です。
困難なときこそ「家族で考え、支え合う」姿勢が回復への足がかりになります。
家庭教師サービスなども活用し、親子で安心して取り組める環境づくりを目指しましょう。
不登校の子どもの行動が「甘え」に見える背景と子どもの心理
不登校の子どもの行動が「甘え」に見える時、その裏にはさまざまな葛藤や理由が隠れています。
本人も学校に行きたい気持ちはあるものの、それをうまく言葉にできず、保護者に説明できないまま苦しさを抱えることも多いです。
「明日こそは行く」と決意しても登校できなかった時、周囲から「甘え」と見られることもありますが、そこには言葉にできないつらさがあります。
この章では、子どもの内面に寄り添い、行動の背景にある「助けてほしい」という気持ちに気づくポイントを解説します。
まずは、子どもの気持ちを否定せず、丁寧に受け止めてあげることが大切です。
子どもが「行きたいのに行けない」葛藤を感じているとき、自分を責める気持ちが強くなりがちです。
「朝になると体が動かない」「みんなについていける自信がない」などの思いに押しつぶされることもあります。
保護者は、「甘え」と捉える前に、子どもの中のSOSを見逃さないよう意識しましょう。
学校へ行けない子どもが感じている本当の苦しさ
- 「学校へ行きたい」と「行けない」の間で葛藤している
- 体調不良や罪悪感など、心身にさまざまな症状が現れる
- 子どものSOSは真剣な助けを求める声
不登校の子どもは、外から見ると「怠けている」ように見えるかもしれません。
ですが実際には、「学校へ行きたい」という思いと「どうしても行けない」という現実の間で葛藤し、強い罪悪感や苦しさを抱えています。
朝になると頭痛や腹痛、不安感など、体の症状として現れることも珍しくありません。
「今日も行けなかった」と自分を責め、ますます自己肯定感が下がってしまうこともあります。
子どもが発するSOSは「甘え」ではなく、真剣な助けを求める声です。
こうした苦しさを理解し、「つらかったね」と共感の言葉をかけてあげてください。
周囲が「がんばれ」と叱咤するだけでは、子どもは孤立を深めてしまいます。
本音を安心して話せる環境を整えることが、再出発の力になります。
「甘え」と「SOSサイン」はどう違うのか
- 「甘え」と見える行動は実はSOSである場合が多い
- 体調不良や感情の不安定さもSOSの一つのサイン
- 安心して「助けて」と言える環境づくりが重要
「甘え」と見なされる行動の多くは、実は「助けてほしい」というSOSサインである場合が多いです。
学校へ行きたくないと正直に言えず、体調不良を装ったり、感情が不安定になったりするのも、子どもなりのSOSの表現です。
これを「甘え」と片付けてしまうと、子どもはさらに心を閉ざしてしまいます。
逆に、SOSに気づいてもらえたと感じると、少しずつ自分の気持ちを話せるようになります。
「甘え」と「SOSサイン」は見た目は似ていても、まったく意味が異なります。
安心して「助けて」と言える環境づくりが、子どもの自信と一歩を支えます。
まずは子どもの言動をしっかり受け止めてください。
子どもの自己肯定感の低下と将来への不安
- 長期化すると自己否定や将来不安が強くなりやすい
- 小さな「できた」を積み重ねることが大切
- 保護者が一緒に前進する気持ちで伴走する
不登校が長期化すると、「自分はダメな人間だ」「将来もこのままだったらどうしよう」といった自己否定感や不安が強まることがあります。
保護者が「甘え」と責めてしまうと、子どもはさらに自信を失い、前向きな行動が難しくなります。
自己肯定感を取り戻すには、小さな「できた」を見つけ、積み重ねることが欠かせません。
学校以外の居場所や、家庭教師サービス、趣味や習い事などを通じて、「自分にもできる」「成長できる」体験を用意しましょう。
保護者も共に不安に向き合い、伴走する気持ちで一歩一歩前進することが大切です。
不登校の「甘え」と向き合う保護者のための対応法
お子さまの不登校が「甘え」と感じられることがあっても、その感情を否定する必要はありません。
実際に行動する際には、「甘え」と決めつけず、子どもの心に寄り添う姿勢が大切です。
無理に登校を促すと、子どもが孤立したり自己否定感を強めたりすることもあります。
この章では、家庭でできる関わり方や、親自身が気持ちを保つための具体的な方法について解説します。
お子さまの変化を温かく見守りながら、家庭全体が少しずつ前進できるヒントをまとめました。
保護者自身が「自分のせいだ」と思い詰めてしまうのはよくあることです。
ですが、まずはお子さまの気持ちを受け止めることから始めてみてください。
教育相談センターや家庭教師サービスなど、家庭外のサポートを利用すれば、家族だけで抱え込まずに済みます。
不登校からの回復には時間がかかりますが、焦らず一歩ずつ進めることが大切です。
不登校が「甘え」と決めつけないために大切なこと
- 「甘え」とレッテルを貼らずに本当の気持ちを探る
- 家庭は子どもが自分らしくいられる場所にする
- 家庭教師や教育相談センターの利用も有効
お子さまが不登校になったとき、まず心がけてほしいのは「甘え」というレッテルを貼らないことです。
「今日も学校に行かなかった」「やる気がない」と感じた時も、その裏側にある本当の気持ちや理由を探ることを意識しましょう。
子どもは大人以上に自分でコントロールできない不安やプレッシャーと戦っています。
家庭は、子どもが自分らしくいられる最も大切な場所です。
不登校の子どもには「味方がいる」と実感できることが何よりの力となります。
「大丈夫だよ」「つらかったね」と気持ちを受け止めてあげてください。
どうしても難しい時は、家庭教師サービスや教育相談センターなど第三者の手を借りて、家族の負担を減らすことも選択肢です。
お子さまのペースで、安心できる環境を一緒に探していきましょう。
家庭で実践できる子どもとの関わり方
- 子どもの気持ちや行動を認めることが大切
- 日常の声かけや褒めることが信頼関係を育てる
- 家庭教師など外部サポートの活用も効果的
家庭でのコミュニケーションは、不登校からの回復に大きな影響を与えます。
「学校に行くことがすべて」という固定観念を外し、子どもの気持ちや行動を認めることが大切です。
毎朝「おはよう」と声をかける、好きな話題で話す、できたことをきちんと褒めるなど、日常のやりとりが信頼関係を育てます。
子どもは「分かってくれる大人」がいることで、徐々に安心と自信を持てるようになります。
家庭の中だけでは難しいことも多いため、「家庭教師」など外部サポートの力を活用するのもおすすめです。
たとえば家庭教師のランナーのように、不登校や学習が苦手なお子さま向けの個別指導を受けられるサービスもあります。
お子さまが少しでも「できた」「楽しい」と思える体験を増やすことが、再び社会とつながるきっかけとなります。
親自身のメンタルケアとストレス軽減法
- 悩みを一人で抱え込まないことが大切
- 外部相談先やリラックスできる時間を持つ
- 親の心のケアが子どもの安心感にもつながる
お子さまの不登校が続くと、保護者も精神的・肉体的に疲れやすくなります。
「自分が悪いのかも」「どうしたらいいのかわからない」と悩むのは当然のことです。
大切なのは、悩みを一人で抱え込まないこと。
家族や信頼できる友人、カウンセラー、家庭教師サービスなど、外部の相談先を積極的に活用しましょう。
親自身の心のケアは、子どもの安心感にもつながります。
一人でリラックスできる時間を作る、体調管理を心がける、趣味や運動で気分転換を図るなど、日々自分を大切にすることも忘れずに。
また、専門家など第三者に相談することで、新しい気づきが得られることもあります。
前向きな気持ちでいることが、家庭の空気を明るくし、お子さまにも安心をもたらします。
不登校の子どもに悩む家庭が知っておきたい支援先
不登校の子どもと向き合う上では、家庭だけで悩みを抱えず、必要に応じて専門の支援を受けることも大切です。
特に学習や生活リズムのサポートには家庭教師サービスが役立ちますが、サービスごとに特徴やサポート内容が異なるため、ご家庭やお子さまの状況に合わせて選ぶことがポイントとなります。
ここでは、代表的な家庭教師サービスのサポート内容と、それぞれの特徴を紹介します。
家庭教師のランナーによる不登校対応サポート

- 20年以上の実績と勉強が苦手な子・不登校専門サポート
- 専門カウンセラーや発達障害指導者が在籍
- 柔軟なオーダーメイド指導と全国対応・オンライン可
家庭教師のランナーは、20年以上にわたって勉強が苦手なお子さまや不登校のご家庭をサポートしてきた家庭教師グループです。
不登校や「甘え」とみなされがちな状態でも、専門カウンセラーや発達障害コミュニケーション指導者が在籍し、一人ひとりに合わせた個別指導を行っています。
挫折経験や自己肯定感の低下、登校への不安などに寄り添い、わかりやすさと小さな達成を積み重ねていくオリジナルのサポート体制が強みです。
全国の主要エリアをカバーし、オンラインにも対応しています。
家庭教師のランナーは、不登校や「甘え」に悩むご家庭にも、オーダーメイドで柔軟なサポートを提供しています。
講師の選定や初期カウンセリング、目標設定、定期的な振り返りなど、段階を踏んでフォローアップを実施しています。
兄弟同時指導や急な予定変更への柔軟な対応など、ご家庭のニーズに応じた提案も可能です。
家庭教師のトライの不登校サポート体制

- 全国規模のネットワークと豊富な講師陣
- 生活習慣や心理的サポート・カウンセラー在籍
- オンラインやマンツーマン個別カリキュラムが充実
家庭教師のトライは、全国規模のネットワークと豊富な講師陣が特長です。
不登校や登校しぶりのお子さまには、学習指導だけでなく生活習慣や心理的なサポートも提供しており、主要拠点には教育支援カウンセラーも在籍しています。
マンツーマンのカリキュラムやオンライン指導も充実しており、通学が難しい場合でも自宅で学びやすい環境が整っています。
「トライ式学習法」による個別の学習プランで、つまずきや課題を明確にし、一歩ずつ自信を積み重ねていきます。
家庭教師のトライは、不登校や「甘え」と感じる悩みにも柔軟なアプローチで応えてくれます。
相性が合わない場合の教師交代も無料で対応可能。受験対策や進路相談まで幅広くフォローします。
学研の家庭教師による不登校対応の取り組み

- 大手教育グループならではの安心感と実績
- 自信回復から始める基礎学習とペース調整
- オンライン指導・進路相談や学習相談も柔軟対応
学研の家庭教師は、大手教育グループならではの安心感と、きめ細かなサポート力が特長です。
不登校の子どもには、まず自信を回復するための基礎学習からスタートし、本人のペースに合わせて徐々に学力を引き上げていきます。
オンライン指導にも対応しており、外出が難しい場合でも安心して利用できます。
旧タートルスタディスタッフのノウハウを活かし、中学受験から大学受験まで幅広く対応。
学研の家庭教師は、ご家庭と教師が連携し、不登校のお子さまを丁寧にサポートします。
進路や学習プランの相談も柔軟で、復学や将来の不安に寄り添いながら支援しています。高額教材の販売はなく、料金も明確です。
家庭教師のサクシードの不登校と甘えに特化した指導

- 東証グロース上場企業が運営・13万人超の講師陣
- 不登校・甘え対応も担当教師と教務スタッフが連携
- 教材費・入会金無料、科目やスケジュール調整も柔軟
家庭教師のサクシードは、東証グロース上場(2021年12月22日)の企業が運営しており、13万人以上の講師陣による質の高いマンツーマン指導を実現しています。
不登校や「甘え」と見なされやすい状態にも対応し、担当教師と教務スタッフが連携して学習計画を提案します。
科目やスケジュールは柔軟に調整でき、オンライン指導も可能です。
教材費や入会金が無料で、交通費のみが別途必要となります。
サクシードは、ご家庭と密に連携しながら、無理なく進める学習環境づくりに注力しています。
小さな達成感を積み重ねるサポートが好評で、専門家とともにお子さまの自信を育てていけます。
家庭教師ファーストの不登校支援サービス

- 全国対応・低価格と高品質な指導
- 無料体験で講師とマッチング、同一講師の継続指導
- 生活リズムや学習習慣の回復もサポート
家庭教師ファーストは、全国対応の低価格と高品質な指導で人気のサービスです。
不登校のお子さまにも、無料体験で実際の講師と出会い、そのまま契約できる仕組みを提供しています。
基本的に同一講師が継続担当しますが、地域によっては変更となる場合もあります。
オンライン指導でも丁寧なサポートが受けられ、生活リズムや学習習慣の回復にも配慮しています。
家庭教師ファーストは、親しみやすい指導と明瞭な料金設定で、ご家庭の不安に寄り添います。
受験や学校復帰など、それぞれの目標に合わせたプラン提案が可能です。
家庭教師のあすなろの「勉強が苦手な子」支援と不登校サポート
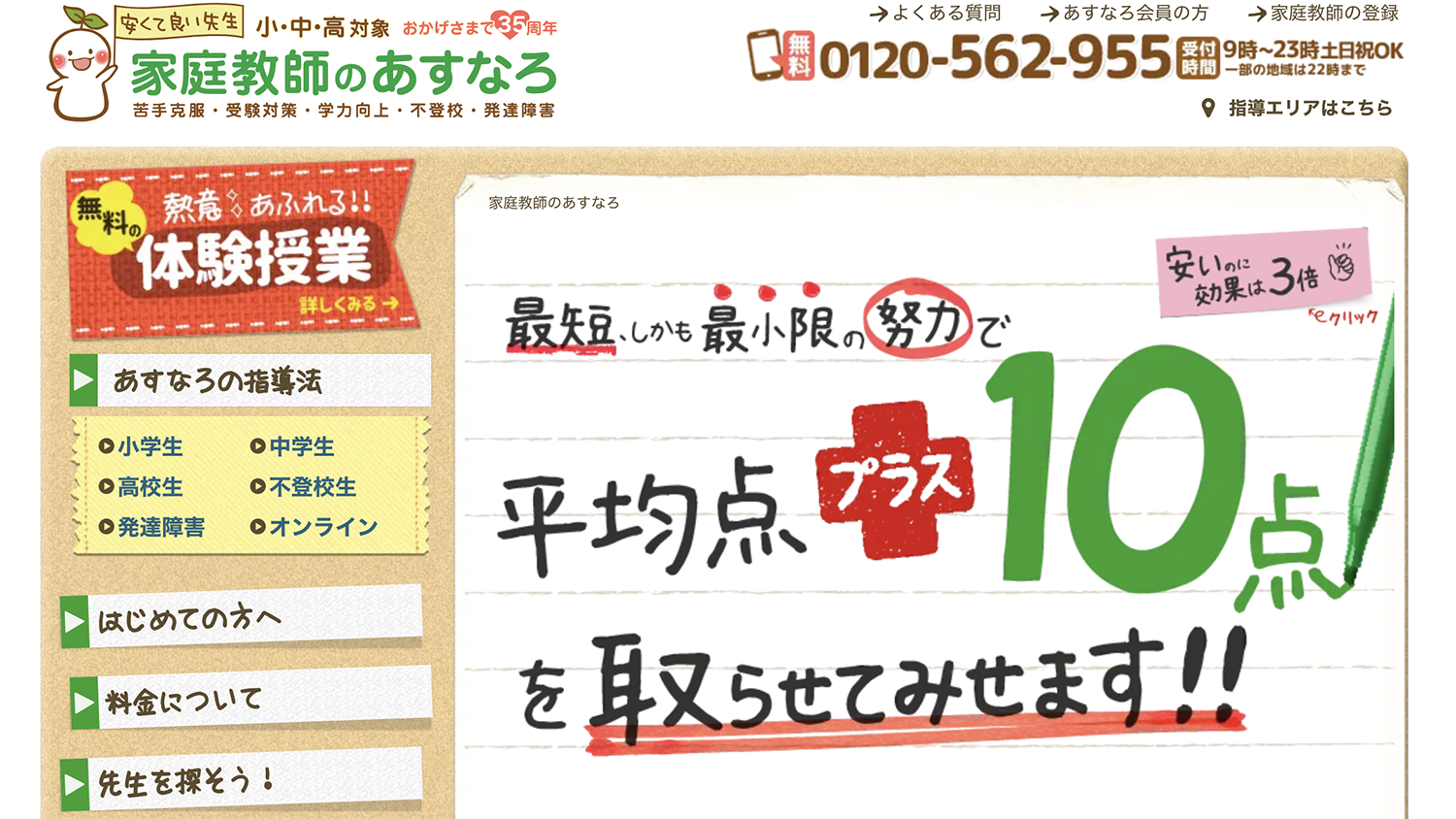
- 勉強が苦手な子専門で全国サポート
- LINE質問サポートなど授業外フォローも充実
- 完全オンライン・低価格で自己肯定感の支援も重視
家庭教師のあすなろは、「勉強が苦手な子専門」として、全国のご家庭をサポートしています。
大学生を中心とした若い講師陣が、子どものやる気や自信を引き出す独自の指導を行っています。
LINEを使った無料の質問サポート「お悩みお助け隊」など、授業外のフォローも充実しています。
「甘え」と見られがちな状態にも丁寧に寄り添い、小さな成功体験を積み重ねる仕組みを整えています。
あすなろは、学力向上だけでなく、自己肯定感のサポートも大切にしています。
完全オンライン対応で、どんな地域でも利用可能です。月謝も低価格で、保護者の負担を和らげます。
家庭教師ジャンプの発達障害・不登校専門の対応

- 発達障害や不登校の専門サポートに特化
- WISC等の検査や特性を踏まえたオーダーメイド指導
- 本部スタッフや教務担当と連携し家庭全体を支援
家庭教師ジャンプは、発達障害や不登校の子どもへの専門サポートを行うサービスです。
専任プロ教師中心(契約形態は複数)で、WISCなどの検査結果や特性を踏まえたオーダーメイド指導を実施しています。
事前のカウンセリングや無料体験を通じて、お子さまに最適なアプローチを提案。
不登校や「甘え」と受け止められがちな行動の背後にある課題も丁寧にサポートします。
本部スタッフや教務担当が連携し、家庭全体を支える体制が評価されています。
ジャンプは、「最後の砦」として、ご家庭やお子さまに専門的なフォローを提供します。
訪問指導を中心にしつつ、オンライン指導にも対応しています。
家庭教師ゴーイングの発達障害・不登校向けオンライン指導

- 発達障害・不登校対応のオンライン家庭教師専門
- 現役東大生や難関大講師多数在籍、全国利用可
- 専用ホワイトボードや進捗管理など学習サポートが充実
家庭教師ゴーイングは、発達障害や不登校に対応したオンライン専門の家庭教師サービスです。
首都圏を中心に、現役東大生や難関大学の講師が多数在籍し、幅広いニーズに対応しています。
オンライン専用ホワイトボードを活用し、自宅で効率よく個別指導が受けられます。
採用は指導経験者のみ。長期的なフォローや学習プランの進捗管理、進路相談、保護者向けサポートも充実しています。
ゴーイングは、オンラインに特化した高品質な指導で、不登校や学習に悩むお子さまをサポートします。
全国どこでも利用可能なので、通学が困難な場合にもおすすめです。
オンライン家庭教師Wamの全国対応・不登校専門オンライン指導

- 全国どこでも難関大学在籍講師による個別指導
- 双方向オンラインシステムで分かりやすい授業
- 生活・学習リズムに合わせて柔軟サポート
オンライン家庭教師Wamは、全国どこでも難関大学在籍の講師による個別指導を提供しています。
独自のオンラインシステムと双方向コミュニケーションにより、わかりやすい授業を実現。
無理なく始められる低価格プランや、生活・学習リズムに合わせた柔軟なサポートが特長です。
部活動や家庭の予定に合わせてスケジュール調整が可能。保護者との相談体制も整っています。
Wamは、オンラインでも丁寧なサポートで、不登校からの一歩を着実に後押しします。
学習習慣が身についていない場合や、復学のきっかけが欲しいご家庭にも適しています。
オンライン家庭教師メガスタの最先端オンライン不登校サポート

- 約4万人の講師ネットワークとAI活用の最先端システム
- 進捗管理・個別設計で自宅学習でも「できる」を実感
- 難関大出身講師や海外在住も含む幅広い指導体制
オンライン家庭教師メガスタは、約40,000人の講師ネットワークを持ち、AIを活用した類題のレコメンド機能や進捗管理システムを採用しています。
全国および海外からも高品質なオンライン指導が受けられ、画面上での板書共有やリアルタイムコミュニケーションにより自宅学習でも「できる」「分かる」実感を得やすい仕組みです。
お子さま一人ひとりの状況に合わせて、学習の習慣づけから自己肯定感の回復まで幅広くサポートします。
難関大学出身者や経験豊富な講師陣が在籍し、保護者との相談体制も充実。
「とりあえず家で何か始めたい」という状態からでも柔軟にスタートできます。
メガスタは、最先端の仕組みと経験豊かな講師陣で、不登校や学習に不安があるお子さまを個別に支援します。
進度や教材もすべて個別設計。まずはオンライン体験授業から気軽に始められます。
不登校が「甘え」と見られるよう事についてまとめ
- ・不登校は「甘え」と一括りにできない複雑な要因が背景にある
- ・医学的・心理的・家庭環境・社会的価値観が絡み合う現代の不登校
- ・「甘え」と決めつけず子どものSOSやサインに向き合うことが大切
- ・保護者も一人で抱え込まず、専門家や家庭教師サービスなど支援先を活用
- ・家庭内コミュニケーションや自己肯定感の育成も回復の大きなポイント
- ・ご家庭ごとの状況に合ったサポートや選択肢を見つけて前向きな一歩を
不登校が「甘え」と見なされやすい現実の中で、子どもや保護者は日々さまざまな葛藤や苦しさと向き合っています。
しかし実際には、医学的・心理的な要因や家庭環境、社会的な価値観など、さまざまな背景が絡み合っているのが現代の不登校の実情です。
「甘え」と決めつけず、一人ひとりの気持ちやサインにしっかり向き合うことが回復の大きな一歩です。
子どもの声に丁寧に耳を傾け、保護者も専門家や支援先と連携しながら、焦らず前向きに進んでいきましょう。
家庭教師サービスをはじめ、さまざまな支援の選択肢を活用することで、新しい道や選択肢が見つかることもあります。
家庭内でのコミュニケーションや自己肯定感の育成、外部サポートの活用によって、ご家庭もお子さまも少しずつ希望を取り戻すことができます。
今、不登校や「甘え」で悩むご家庭にこそ、あきらめずに一歩を踏み出してほしいと願っています。
困った時には無理をせず、信頼できる支援先を頼ることも大切です。