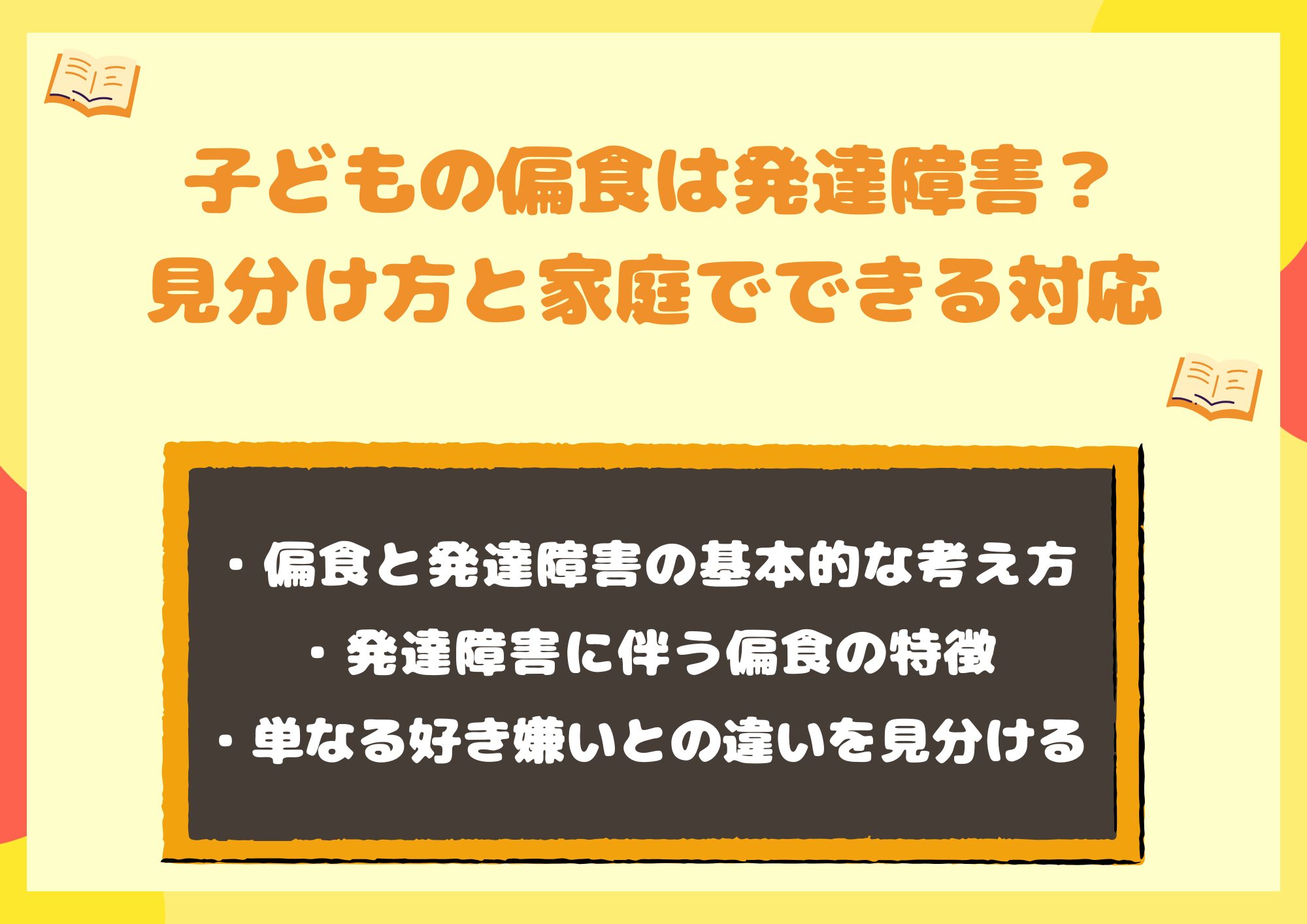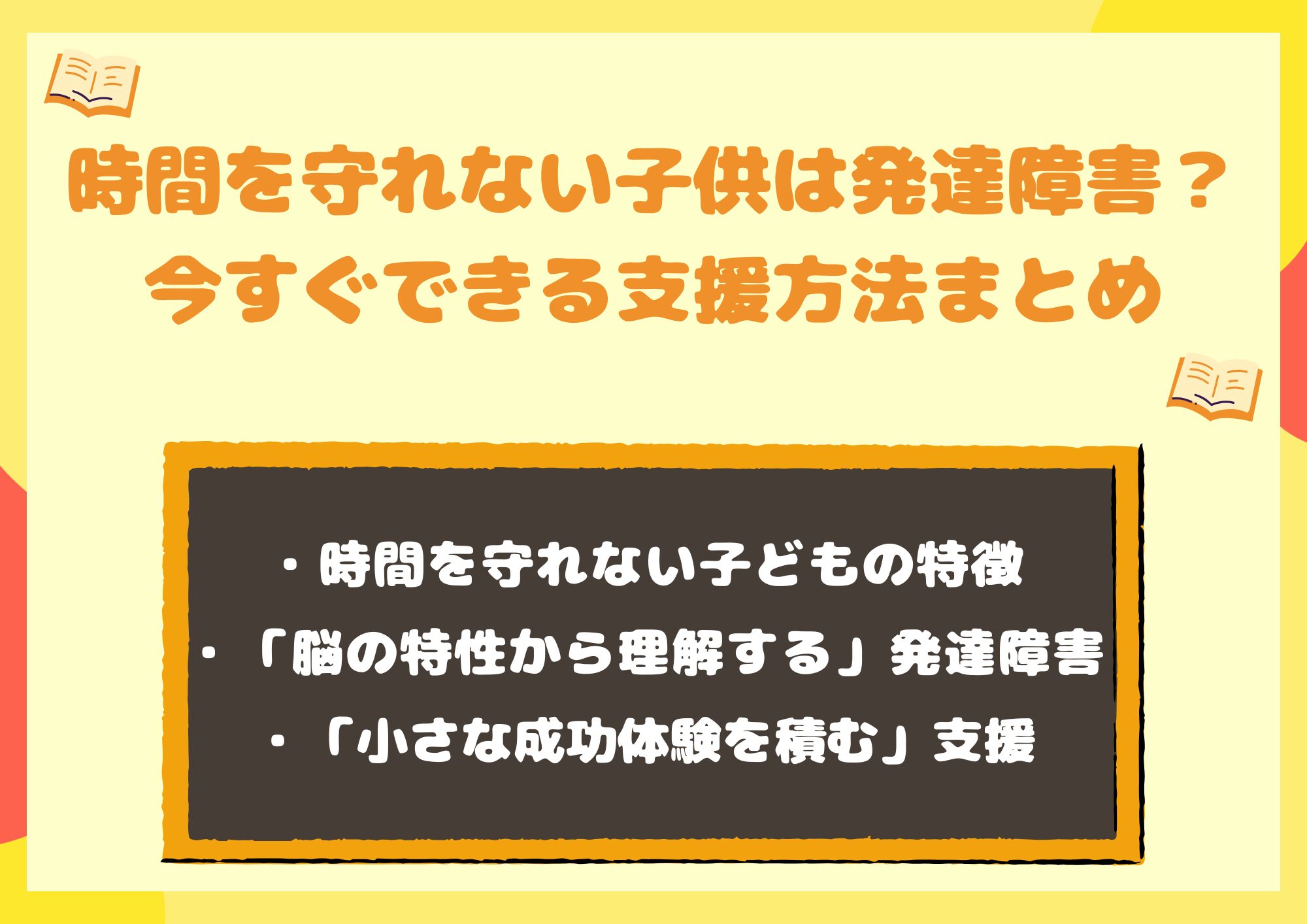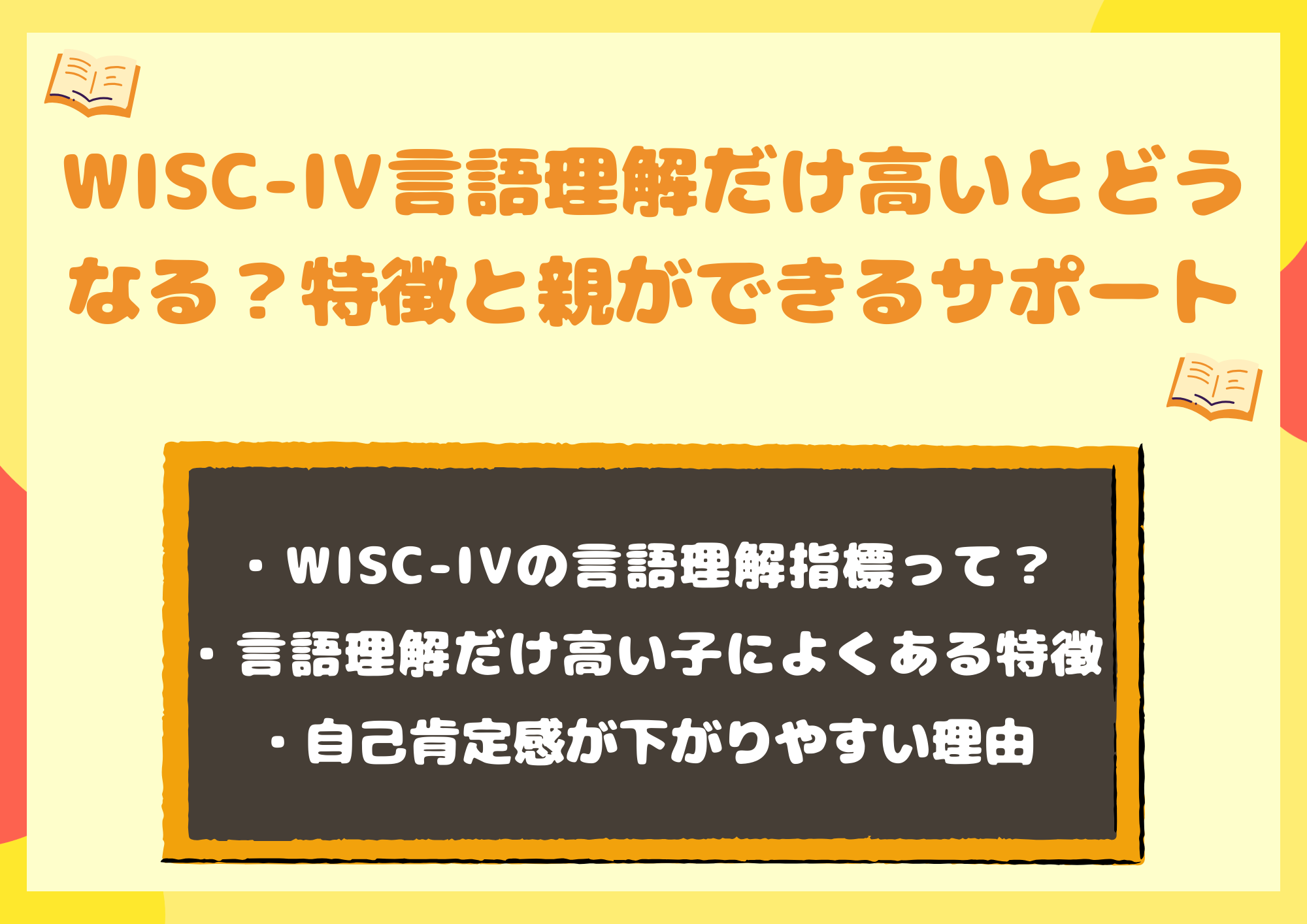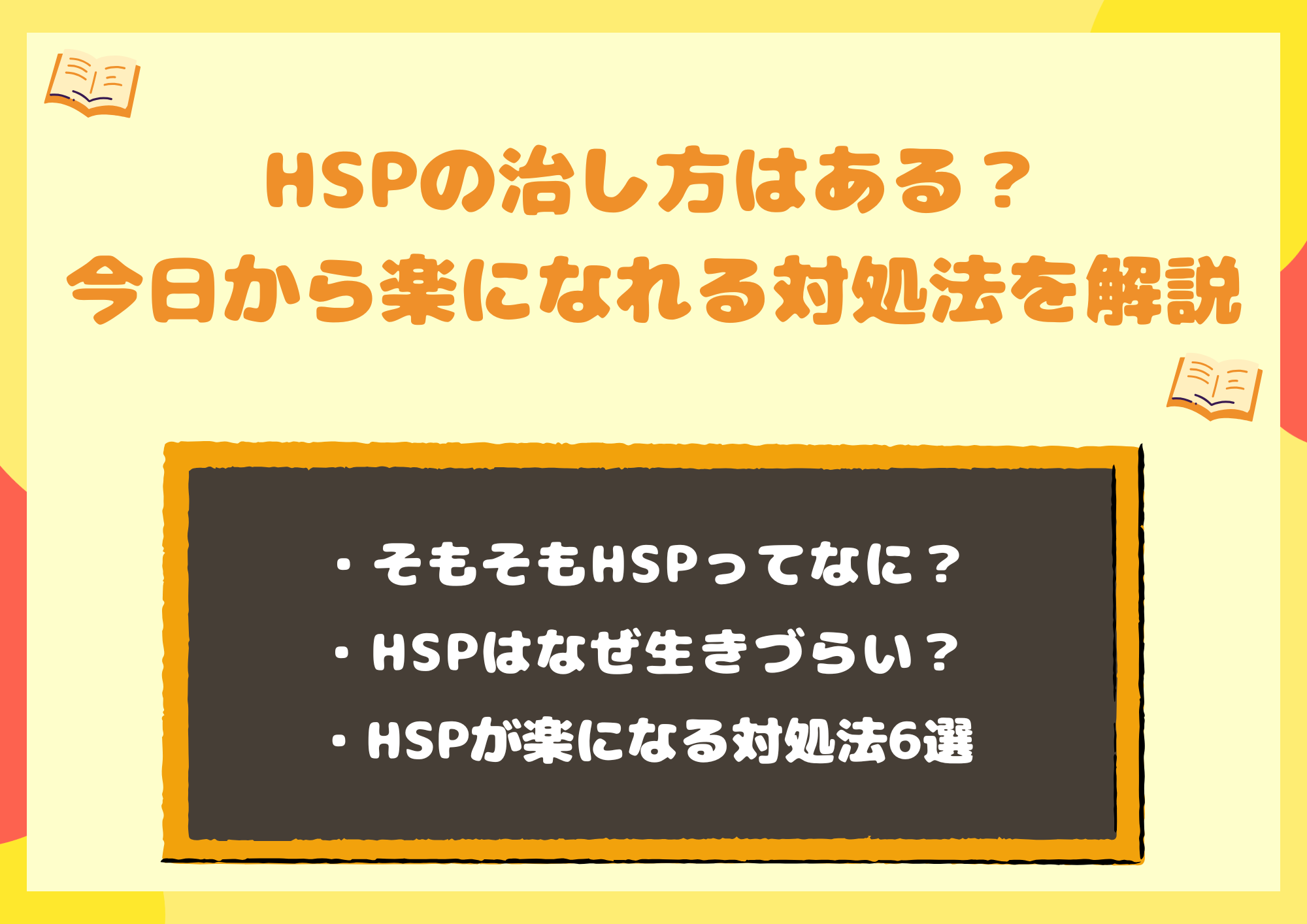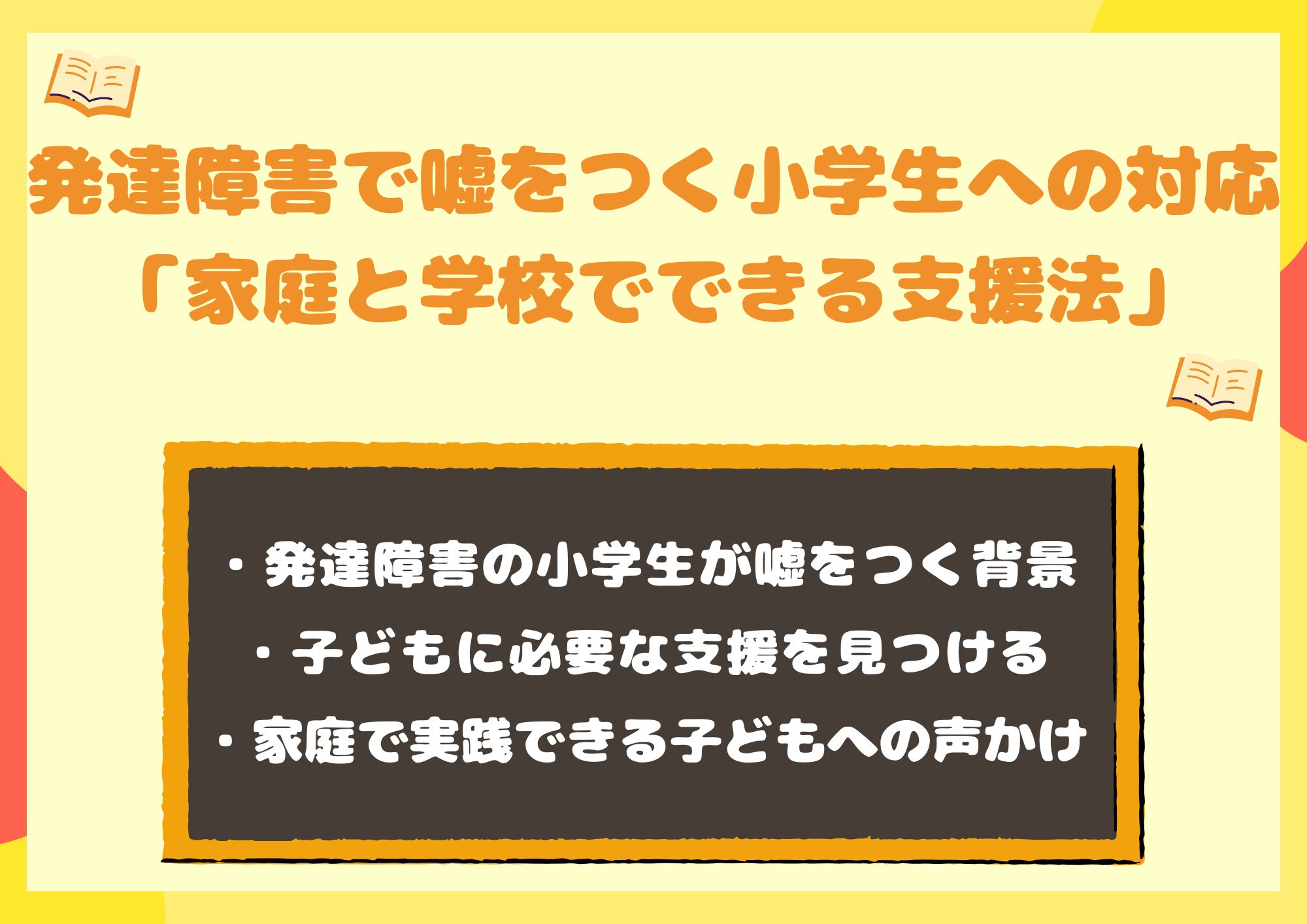- 発達障害向けの家庭教師
集中力がない子供の発達障害を理解する「家族で踏み出す安心の一歩」
2025.09.25
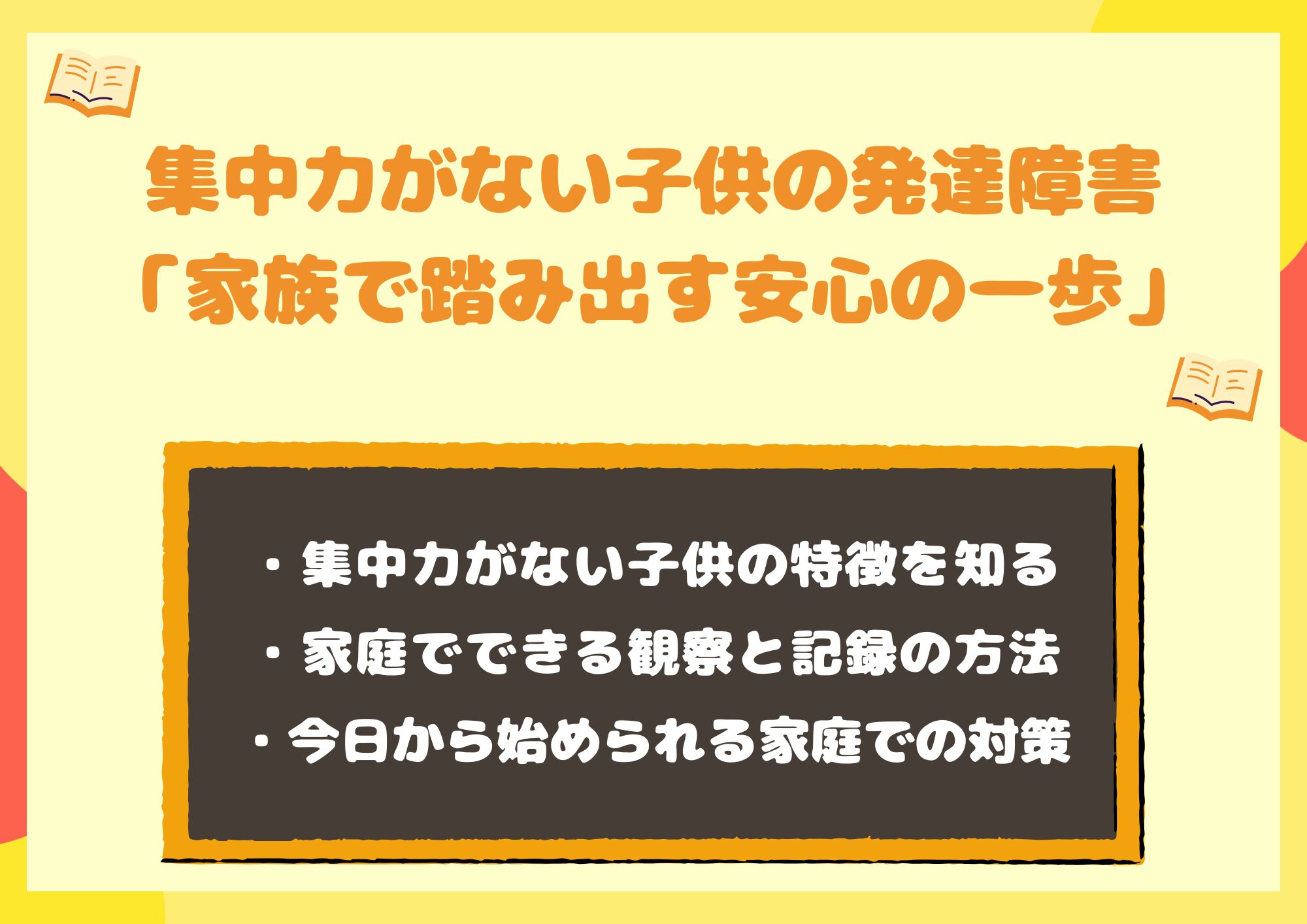
お子さんが授業中に席を立ってしまったり、宿題に集中できなかったりすることで悩んでいませんか。
「うちの子、もしかして発達障害なのかな」という不安を抱えながら、どこに相談すればいいのか、家庭で何ができるのか分からずに一人で抱え込んでいる親御さんは少なくありません。
発達障害による集中力の問題は、適切な理解と対応によって改善が期待できます。
この記事では、集中力がない子供の発達障害について、今日から実践できる具体的な対策と、家族みんなで取り組める支援方法をお伝えします。診断の有無に関わらず、お子さんの「今の困りごと」を軽くする方法は多くあります。
一緒に、お子さんの可能性を信じて、小さな一歩から始めていきましょう。
ランナーの無料体験はこちら!目次
発達障害で集中力がない子供の特徴を知る「まず理解から始めよう」
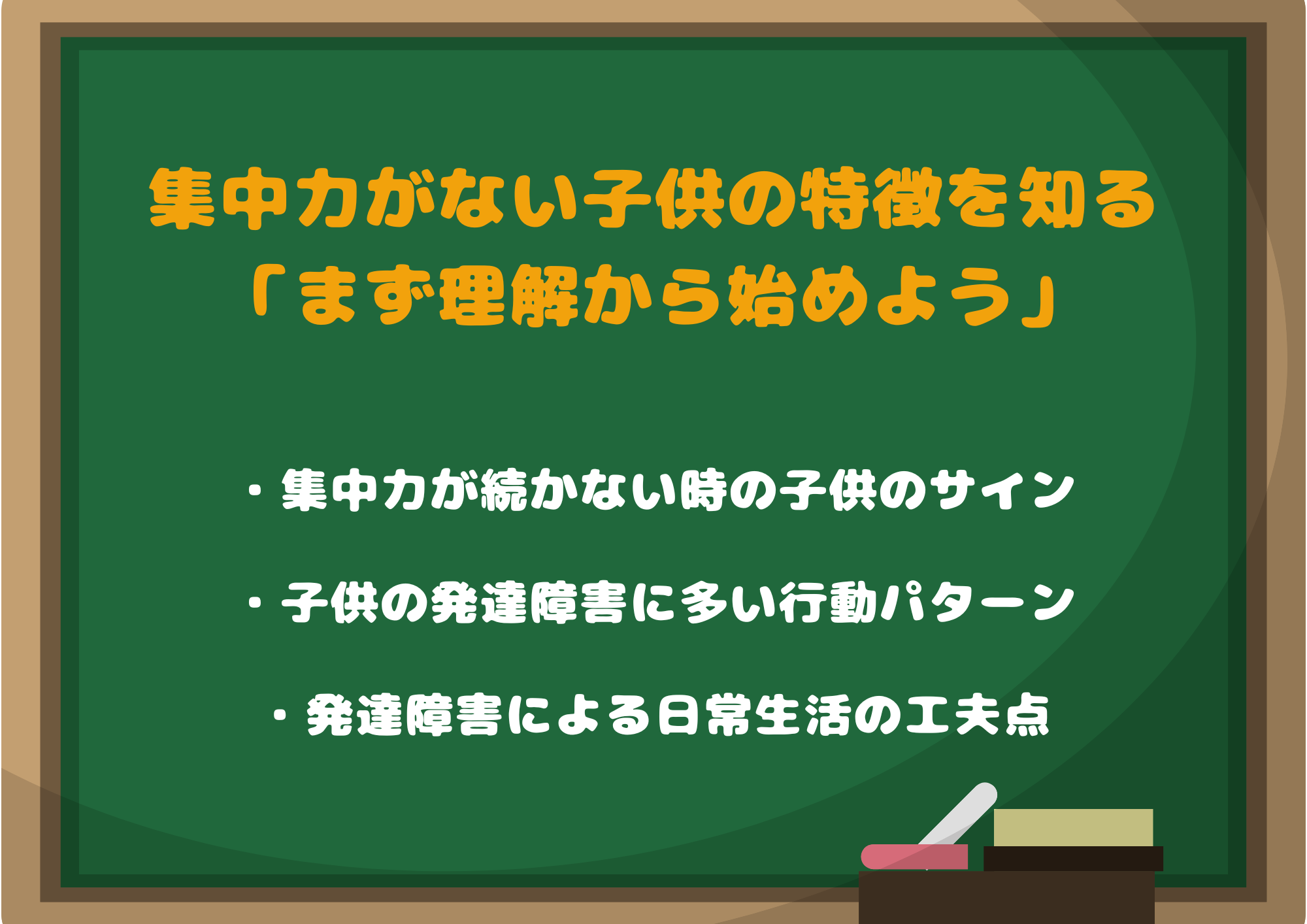
発達障害による集中力の問題は、お子さんの「わがまま」や「やる気のなさ」ではありません。脳の特性によるもので、適切な理解と対応があれば、お子さんは本来持っている力を発揮できるようになることが多いです。
まずは、集中力がない子供に見られる特徴を知ることで、お子さんの行動の背景にある理由が見えてきます。
「なぜうちの子はこうなの?」という疑問が、「こういう特性があるから、こう対応すればいいんだ」という理解に変わることで、親子の関係も改善していくことが期待できます。
集中力が続かない時に見られる子供のサイン
- 授業中のボーッとした様子や課題の未完了は努力不足ではなく脳の特性による
- 「過集中」という特性で興味のあることには何時間でも集中できる場合がある
- 忘れ物の多さや時間管理の苦手さも集中力の問題と関連している
集中力が続かない子供には、いくつかの共通したサインがあります。
授業中にボーッとしている、話を聞いていないように見える、課題を最後までやり遂げられない、忘れ物が多い、時間の管理が苦手などの特徴が見られます。これらは本人の努力不足ではなく、注意の切替や感覚処理の特性が背景にある場合が多いです。
また、興味のあることには過度に集中する「過集中」という特徴も一部の子供に見られることがあります。
好きなゲームや本には何時間でも没頭できるのに、宿題には5分も集中できないというギャップに、親御さんは戸惑うことも多いでしょう。これも発達障害の特性として一部の人に見られるもので、興味の有無によって集中力に大きな差が生じることがあります。
落ち着きがない子供の発達障害に多い行動パターン
- 体のどこかが常に動いている「多動性」は脳を活性化させるための行動
- 順番を待てない、思いついたことをすぐ口に出す「衝動性」も特徴の一つ
- 適切な環境調整と対応により症状の軽減・適応が進むことが期待できる
落ち着きがない子供の発達障害では、じっとしていることが苦手で、常に体のどこかが動いている状態が見られます。椅子に座っていても足をブラブラさせたり、鉛筆や消しゴムをいじったり、席を立って歩き回ったりすることがあります。
これは「多動性」と呼ばれる特性で、体を動かすことで脳が活性化し、逆に集中力を保とうとしている場合もあります。
また、順番を待てない、人の話を最後まで聞けない、思いついたことをすぐに口に出してしまうなどの「衝動性」も見られることがあります。これらの行動は、周囲から「落ち着きがない」「しつけがなっていない」と誤解されやすく、お子さん自身も叱られることが多くなりがちです。
しかし、これらは脳の特性によるもので、適切な環境調整と対応により、軽減・適応が進むことがあります。
走り回る子供の発達障害による日常生活の工夫点
- 感覚刺激を求める「感覚探求」の特性から動き回る行動が生まれる
- 計画的な運動機会の確保で授業中の落ち着きが改善することがある
- 「走ってもいい時間」と「静かにする時間」のメリハリをつけることが大切
走り回る子供の発達障害では、エネルギーが有り余っているように見え、常に動き回っている状態が特徴的です。家の中でも外でも、歩くより走ることが多く、高いところに登ったり、危険な遊びをしたりすることもあります。
このような行動は、感覚刺激を求める「感覚探求」の特性から来ている場合があり、体を動かすことで脳が必要とする刺激を得ようとしているのです。
日常生活では、安全に体を動かせる時間と場所を確保することが大切です。朝の登校前に軽い運動をする、休み時間は外で思いきり遊ぶ、放課後はスポーツ活動に参加するなど、計画的に運動の機会を作ることで、授業中の落ち着きが改善することがあります。
また、家庭では「走ってもいい時間」と「静かにする時間」のメリハリをつけ、視覚的なタイマーなどを使って切り替えの練習をすることも効果的です。
家庭でできる観察と記録の方法「小さな変化に気づくために」
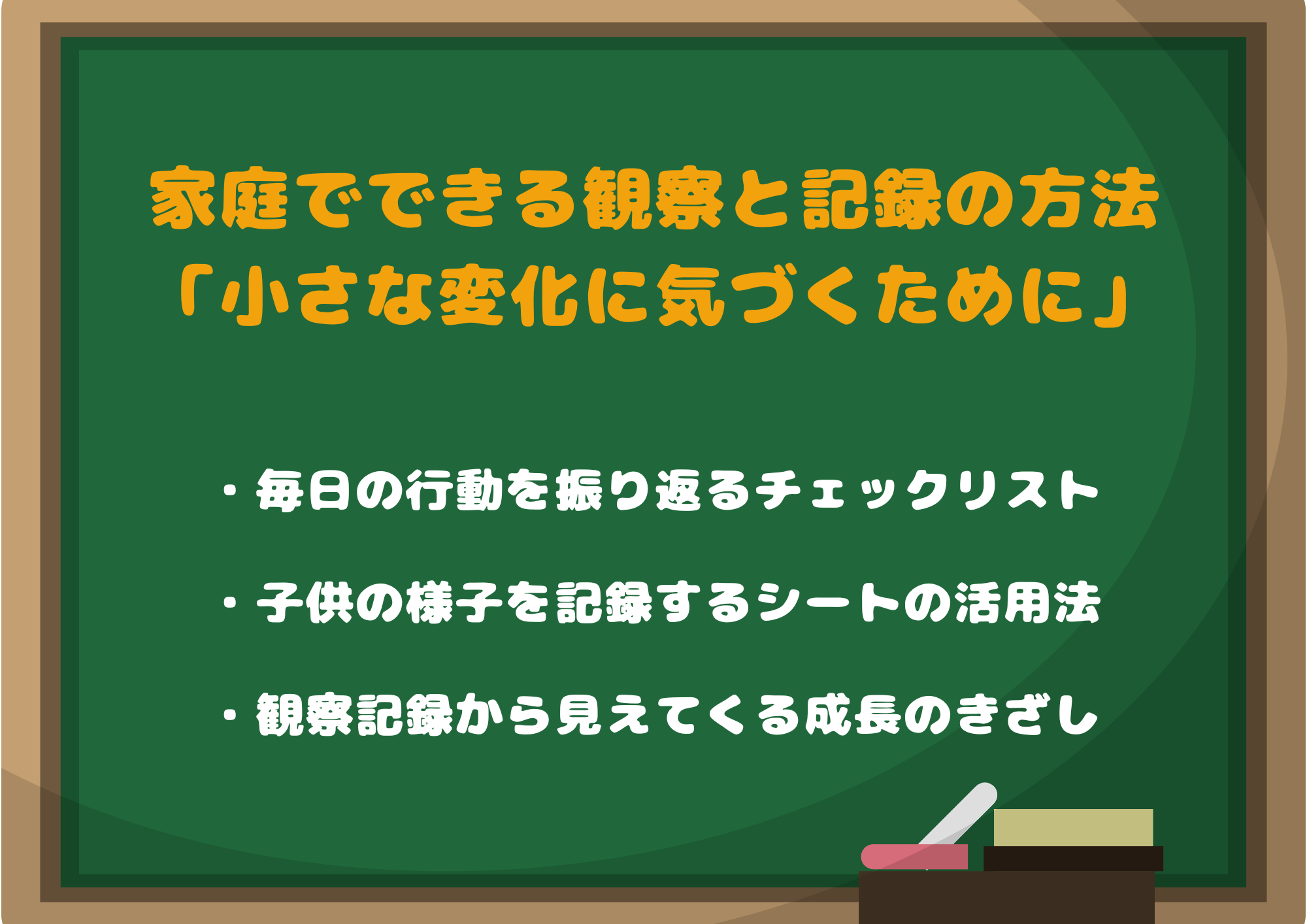
お子さんの行動を客観的に観察し記録することは、発達障害の特性を理解し、効果的な対策を見つけるための第一歩です。
「いつも落ち着かない」という漠然とした印象ではなく、具体的にいつ、どこで、どんな状況で困った行動が起きやすいのかを把握することで、対応方法が見えてきます。
観察と記録は難しく考える必要はありません。日常の中で気づいたことをメモする程度から始めて、徐々に詳しく記録していけば大丈夫です。
毎日の行動を振り返るための簡単チェックリスト
- 主要な活動を3段階評価することで問題が起きやすい時間帯を特定できる
- 最低5~7日分の連続記録で行動パターンの傾向が見えてくる
- 記録の目的は「うまくいく条件探し」で細かさより継続を優先する
毎日の行動チェックリストは、お子さんの一日の流れを把握し、問題が起きやすい時間帯や状況を特定するのに役立ちます。
朝起きてから寝るまでの主要な活動(起床、朝食、登校準備、学校、宿題、入浴、就寝など)について、「スムーズにできた」「少し困った」「とても困った」の3段階で評価します。
最低5~7日分の連続記録で傾向抽出ができます。
例えば、「月曜日の朝は特に準備に時間がかかる」「宿題は夕食前より後の方が集中できる」などの傾向が分かれば、それに合わせた対策を立てることができます。記録の目的は”問題の特定”ではなく”うまくいく条件探し”。細かさより継続を優先しましょう。
子供の様子を記録するシートの活用法
- ABC記録(先行事象・行動・結果)で行動の前後関係を明確にする
- 短い文章やキーワードでの記録でも十分効果がある
- 良い行動も記録することで成功パターンが見つかる
ABC記録(先行事象・行動・結果)のフレームワークを使った記録シートでは、困った行動が起きた時の状況を詳しく記録します。
「いつ(時間)」「どこで(場所)」「何をしていた時(状況)」「どんな行動(具体的な様子)」「その後どうなった(結果)」を記入することで、行動の前後関係が明確になります。
例えば、「算数の授業中に席を立つことが多い」という記録から、「算数が苦手で不安を感じている」「問題が分からなくて助けを求めている」などの理由が推測できます。
記録は短い文章やキーワードで構いません。スマートフォンのメモ機能を使えば、その場ですぐに記録できます。
また、良い行動も同じように記録することで、「どんな時にうまくいくのか」という成功パターンも見つけることができます。
観察記録から見えてくる成長のきざし
- 日々見過ごしがちな小さな成長も記録により実感できる
- 記録を学校の先生や専門家と共有することで効果的な支援を受けられる
- 「できるようになったこと」に注目することで前向きな気持ちになれる
継続的な観察記録は、お子さんの小さな成長や変化に気づくための貴重な資料となります。日々の生活では見過ごしがちな「5分座っていられるようになった」「忘れ物が週3回から1回に減った」などの進歩も、記録を振り返ることで実感できます。
これらの小さな成長の積み重ねが、お子さんの自信につながり、さらなる成長を促します。
また、記録を学校の先生や専門家と共有することで、より具体的で効果的な支援を受けることができます。「できないこと」ではなく「できるようになったこと」に注目することで、親子ともに前向きな気持ちで取り組めるようになります。
記録は単なるデータではなく、お子さんの成長の証であり、家族の希望の光となるのです。
今日から始められる家庭での対策「できることから少しずつ」
発達障害による集中力の問題は、家庭での工夫次第で改善することが期待できます。特別な道具や高額な費用は必須ではありません。
日常生活の中でできる小さな工夫の積み重ねが、お子さんの生活を楽にし、家族全体の笑顔を増やしていきます。大切なのは、完璧を求めずに「今日できることから始める」という姿勢です。
一つずつ試してみて、お子さんに合う方法を見つけていきましょう。
声かけと環境を整えるための具体的な工夫
- 否定的な言葉より肯定的で具体的な指示が効果的
- 学習スペースの視覚的刺激を減らし集中しやすい環境を作る
- タイマーで見通しを持たせることで集中力を保ちやすくなる
効果的な声かけは、お子さんの行動を変える大きな力になります。「ダメ」「やめなさい」という否定的な言葉ではなく、「○○しよう」という肯定的で具体的な指示が効果的です。
例えば、「走らないで」ではなく「歩こうね」、「うるさい」ではなく「小さい声で話そう」と伝えることで、お子さんは何をすればいいのか明確に理解できます。
環境面では、学習スペースから余計な物を片付け、視覚的な刺激を減らすことが重要です。机の上には今使う物だけを置き、壁の掲示物も最小限にします。
また、聴覚遮蔽(イヤーマフ等)や視覚遮蔽(パーテーション等)を使って、刺激をコントロールすることも効果的です。タイマーを使って「あと5分で終わり」という見通しを持たせることで、集中力を保ちやすくなります。
生活リズムと習慣づくりのステップ
- 規則正しい生活リズムが心の安定をもたらす基盤となる
- 視覚的なスケジュール表で達成感を味わえる工夫をする
- 段階的なアプローチで一つずつ目標を達成していく
規則正しい生活リズムは、発達障害のお子さんにとって心の安定をもたらす重要な基盤となります。毎日同じ時間に起床・就寝することから始め、朝食・夕食の時間も固定していきます。
急に全てを変えるのではなく、まずは「朝7時に起きる」という一つの目標から始めて、できたら次のステップに進むという段階的なアプローチが成功の鍵です。
習慣づくりには、視覚的なスケジュール表が役立ちます。一日の流れを絵や写真で示し、終わった活動にはシールを貼るなど、達成感を味わえる工夫をします。
また、「朝の準備リスト」「寝る前のルーティン」などをイラスト付きで作成し、お子さんが自分でチェックできるようにすることで、自立心も育ちます。
安全に発散できる活動と切り替えのコツ
- 計画的に体を動かす時間を設けることでエネルギーを発散できる
- お手伝いを通じて建設的にエネルギーを使う方法もある
- 活動の切り替えには「予告」が効果的で心の準備ができる
体を動かすことが好きな発達障害のお子さんには、安全に発散できる活動の時間を計画的に設けることが大切です。トランポリン、バランスボール、室内用ジャングルジムなどを活用すれば、天候に関係なく体を動かせます。
また、お手伝いを通じて体を動かすこともできます。掃除機をかける、洗濯物を運ぶ、買い物の荷物を持つなど、日常の活動を「お仕事」として任せることで、エネルギーを建設的に発散できます。
活動の切り替えには、「予告」が効果的です。「あと10分で片付けの時間だよ」「5分後に宿題を始めるよ」と事前に伝えることで、心の準備ができます。
切り替えが上手にできた時は、すぐに褒めることで、次回への意欲につながります。
学校との連携で作る支援体制「一緒に考える環境づくり」
お子さんの発達障害による困りごとは、家庭だけでなく学校でも起きています。学校と家庭が同じ方向を向いて支援することで、お子さんは安心して学校生活を送ることができます。
先生との連携は難しそうに感じるかもしれませんが、お子さんのために一緒に考えてくれる味方を増やすという気持ちで、少しずつ関係を築いていきましょう。大切なのは、批判や要求ではなく、「一緒に考えていただけませんか」という協力的な姿勢で臨むことです。
担任の先生に伝えたいポイントのまとめ方
- 具体的な困りごとを数値や状況を含めて明確に伝える
- 家庭で効果があった対応方法を共有して学校でも取り入れやすくする
- 資料は箇条書きでA4用紙1枚程度にまとめると効果的
担任の先生に伝える際は、具体的で分かりやすい情報をまとめることが重要です。「集中力がない」という抽象的な表現ではなく、「10分以上座っていることが難しい」「音に敏感で、隣のクラスの声が聞こえると集中が切れる」など、具体的な困りごとを伝えます。
また、家庭で効果があった対応方法も共有します。「タイマーを使って時間を区切ると集中しやすい」「聴覚遮蔽を使うと落ち着く」など、実際に試して良かった方法を伝えることで、学校でも取り入れやすくなります。
先生も多くの生徒を見ているため、具体的な情報があることで、お子さんへの理解と対応がスムーズになります。資料は箇条書きでA4用紙1枚程度にまとめ、面談の際に渡すと効果的です。
配慮をお願いする時の伝え方と文例
- 困りごとと具体的な配慮内容を明確に伝える
- 学校の運営・安全配慮の観点から調整が必要な場合もある
- 相談ベースで提案し協力をお願いする姿勢が大切
合理的配慮をお願いする際は、お子さんの困りごとと、それに対する具体的な配慮内容を明確に伝えることが大切です。ただし、学校の運営・安全配慮の観点から調整が必要な場合もあることを理解しておきましょう。
例えば、「授業中に立ち歩いてしまう時は、廊下を少し歩いて戻ることを許可していただけないでしょうか」「テストの時は、別室や仕切りのある席で受けさせていただくことは可能でしょうか」など、相談ベースで提案します。
文例としては、「いつもお世話になっております。○○の集中力の維持が難しいことについて、ご相談があります。
家庭では5分ごとに小休憩を入れることで、課題に取り組めるようになってきました。学校でも可能な範囲で、授業中に立ち上がって体を動かす時間を作っていただくことは可能でしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、一緒に○○のためにできることを考えていただけませんでしょうか」といった、協力をお願いする姿勢で伝えると良いでしょう。
学校生活で取り入れたい支援のアイデア
- 座席配置を工夫することで集中しやすい環境を作る
- 視覚的支援や課題の調整など学習面での配慮が効果的
- 環境調整はお子さんが本来の力を発揮するための支援
学校生活では、様々な支援の工夫を取り入れることができます。座席の配置では、窓際や廊下側ではなく、先生の近くや刺激の少ない場所を選んでもらうことで、集中しやすくなります。
また、クッションやバランスディスクを椅子に置くことで、体を動かしながらも着席を保つことができます。
学習面では、プリントを小分けにする、課題の量を調整する、口頭での指示に加えて板書や絵カードを使うなどの視覚的支援が効果的です。休み時間には、図書室や保健室など静かに過ごせる場所の確保も重要です。
これらの支援は「特別扱い」ではなく、お子さんが本来の力を発揮するための「環境調整」です。クラスの他の子供たちにも、「みんなそれぞれ得意不得意がある」という多様性の理解を促すことで、お互いを認め合える学級づくりにつながります。
相談先と支援サービスの選び方「安心して頼れる場所を見つける」
発達障害の疑いがある場合、一人で悩まずに専門機関に相談することが大切です。相談先は複数あり、それぞれに特徴があります。
まずは身近な相談窓口から始めて、必要に応じて専門的な支援につなげていくという段階的なアプローチがおすすめです。相談することは決して「負け」ではなく、お子さんと家族の未来をより良くするための積極的な一歩です。
自治体や医療機関の相談窓口について
- 市区町村の子育て支援センターや保健センターで無料相談が可能
- 医療機関は地域によって待機が発生する場合があり早めの予約が必要
- 療育センターでは診断の有無に関わらず支援を受けられる場合がある
最初の相談先として、市区町村の子育て支援センターや保健センターがあります。これらの窓口では、発達相談や育児相談を無料で受けることができ、必要に応じて専門機関への紹介もしてもらえます。
保健師や心理士が対応してくれるため、医療機関に行く前の相談先として気軽に利用できます。
医療機関では、小児科、児童精神科、小児神経科などが発達障害の診断や治療を行っています。地域によっては待機が発生する場合があるため、早めの予約が必要です。
診断を急ぐよりも、まずは困りごとへの対処法を学び、実践することが大切です。また、療育センターや児童発達支援センターでは、診断の有無に関わらず支援を受けられる場合がありますが、支援の可否・要件は自治体や事業所により異なるため、事前に確認が必要です。
受給者証や利用者負担などの給付制度についても、自治体窓口で詳細を確認しましょう。
専門相談を選ぶ時の確認ポイント
- 相談員の資格や経験、発達障害の専門知識を確認する
- 相談方法は対面だけでなく電話やオンラインも選択肢に
- 家族全体へのサポート体制があるかも重要な視点
専門相談を選ぶ際は、いくつかの確認ポイントがあります。まず、相談員の資格や経験を確認し、発達障害に関する専門知識があるかを確かめます。
また、相談の頻度や期間、費用についても事前に確認しておくことが大切です。公的機関は無料または低額ですが、待機期間が長いことがあります。
相談方法も重要なポイントです。対面相談だけでなく、電話やオンラインでの相談が可能かどうかも確認しましょう。
お子さんの特性によっては、慣れない場所での相談が難しい場合もあるため、家庭訪問や学校訪問が可能な機関を選ぶことも検討できます。また、家族全体へのサポートがあるかどうかも大切な視点です。
初回相談から支援開始までの流れを知る
- 生育歴や困りごとを伝えるため母子手帳や記録を持参する
- 検査結果を基に療育プログラムなどの支援計画が立てられる
- 支援は成長に合わせて柔軟に見直していくもの
初回相談では、お子さんの生育歴や現在の困りごとについて詳しく聞かれます。母子手帳や園・学校からの連絡帳、行動記録などを持参すると、具体的な情報を伝えやすくなります。
相談員は、お子さんの行動観察や発達検査を行い、支援の必要性や方向性を判断します。
検査結果を基に、支援計画が立てられます。この計画には、療育プログラムへの参加、定期的な相談、学校との連携などが含まれます。
支援は一度始めたら変更できないものではなく、お子さんの成長に合わせて柔軟に見直していくものです。支援開始後も、定期的な評価と計画の見直しを行いながら、お子さんに最適な支援を継続していきます。
長期的なサポート計画の立て方「家族みんなで成長を支える」
発達障害のお子さんへの支援は、短期間で完結するものではありません。お子さんの成長に合わせて、支援内容も変化していく必要があります。
長期的な視点でサポート計画を立て、家族全員で協力していくことで、お子さんの可能性を最大限に引き出すことができます。計画は柔軟に変更できるものとして捉え、小さな成功を積み重ねていくことが重要です。
目標設定と振り返りで見つける小さな成功
- 達成可能な小さな目標から始めて段階的にステップアップする
- 定期的な振り返りで小さな成功を見つけて認める
- 振り返りは成長を確認する前向きな時間として活用する
目標設定は、お子さんの現在の力に合わせて、少し頑張れば達成できるレベルから始めます。例えば、「宿題を最後までやり遂げる」という大きな目標ではなく、「算数のプリント1問を解く」という小さな目標から始めます。
達成できたら、「2問解く」「5分間集中する」と少しずつステップアップしていきます。
定期的な振り返りでは、できたことを具体的に褒めることが大切です。「今週は3日も宿題ができたね」「給食の準備が早くなったね」など、小さな成功を見つけて認めることで、お子さんの自信につながります。
振り返りは批判の場ではなく、成長を確認し、次の目標を一緒に考える前向きな時間にしましょう。
家族と学校が連携するためのコミュニケーション
- 連絡帳や定期面談で情報交換を密にする
- 家族全員で発達障害の知識と対応方法を共有する
- 家族会議で役割分担や対処法を話し合う
家族と学校の連携を深めるには、定期的な情報交換が欠かせません。連絡帳を活用して日々の様子を共有したり、月1回程度の面談を設定したりすることで、お互いの取り組みを確認できます。
家庭での成功体験を学校に伝え、学校での工夫を家庭でも取り入れることで、一貫した支援が可能になります。
きょうだいや祖父母など、家族全員の理解と協力も重要です。発達障害について正しい知識を共有し、対応方法を統一することで、お子さんは安心して過ごすことができます。
家族会議を開いて、それぞれの役割分担を決めたり、困った時の対処法を話し合ったりすることも効果的です。
成長に合わせた支援の見直しタイミング
- 学年やクラス替えなど環境変化時が見直しの良いタイミング
- お子さん本人の意見も取り入れて主体的な取り組みにつなげる
- 見直しは「より良い方法を見つける」前向きなプロセス
支援の見直しは、お子さんの成長や環境の変化に合わせて行います。学年が上がる時、クラス替えの時、長期休暇の前後などは、支援内容を見直す良いタイミングです。
また、お子さんの興味関心の変化や、新たに獲得したスキルに応じて、支援方法を調整することも大切です。
見直しの際は、これまでの記録を振り返り、何が効果的だったか、何を改善すべきかを分析します。お子さん本人の意見も聞きながら、「もっとこうしてほしい」「これは続けたい」という要望を取り入れることで、主体的な取り組みにつながります。
支援の見直しは「今までのやり方が間違っていた」ということではなく、「より良い方法を見つける」ための前向きなプロセスです。
発達障害に関する多くの誤解や偏見「正しい理解で前に進む」
発達障害に関しては、多くの誤解や偏見がまだ残っています。「しつけの問題」「甘やかしすぎ」などの間違った認識は、お子さんと家族を苦しめ、適切な支援を遅らせる原因になります。
正しい知識を持つことで、お子さんへの理解が深まり、効果的な支援につながります。ここでは、よくある誤解について分かりやすく解説します。
叱ることで改善するのか?「適切な対応方法」
- 叱責のみでは改善につながりにくく逆効果となる場合がある
- 叱るのではなく「教える」ことが適切な対応
- 具体的にすぐ褒めることで望ましい行動が定着しやすくなる
「厳しく叱れば治る」という考えは、発達障害への大きな誤解です。発達障害は脳の特性によるもので、叱責のみでは改善につながりにくく、逆効果となる場合があります。
むしろ、過度な叱責は、お子さんの自己肯定感を下げ、二次的な問題(不安、うつ、反抗的行動など)を引き起こす可能性があります。
適切な対応は、叱るのではなく「教える」ことです。できない理由を理解し、できる方法を一緒に考え、スモールステップで練習していくことが大切です。
「なぜできないの」ではなく「どうしたらできるかな」という視点で接することで、お子さんは安心して挑戦できるようになります。褒める時は具体的に、すぐに褒めることで、望ましい行動が定着しやすくなります。
診断がなくても支援は受けられるのか?
- 市区町村の相談窓口は診断の有無に関わらず利用可能
- 支援の可否や要件は自治体によって異なるため確認が必要
- 「グレーゾーン」のお子さんも適切な支援を受ける権利がある
診断がなくても、多くの支援を受けることは可能です。市区町村の子育て支援センターや教育相談は、診断の有無に関わらず利用できます。
学校でも、診断がなくても個別の配慮や支援を受けることができる場合があります。大切なのは、お子さんの困りごとを具体的に伝え、必要な支援を求めることです。
療育や児童発達支援も、市区町村の判断により、医師の診断書がなくても利用できる場合があります。ただし、支援の可否や要件は自治体によって異なるため、詳細は各自治体の窓口で確認することが必要です。
「グレーゾーン」と呼ばれる、診断基準を満たさないけれど支援が必要な状態のお子さんも、適切な支援を受ける権利があります。診断を待つ間にも、できることから始めていくことが、お子さんの成長にとって重要です。
家庭のしつけが原因という誤解について
- 発達障害は親の育て方やしつけが原因ではなく医学的に証明されている
- 生まれつきの脳の特性で遺伝的要因などが複雑に関わっている
- 大切なのは過去を責めるのではなく今からできることに目を向けること
発達障害は、親の育て方やしつけが原因ではありません。これは医学的に証明されている事実です。
発達障害は生まれつきの脳の特性であり、遺伝的要因や胎児期の環境要因などが複雑に関わっていると考えられています。親御さんが自分を責める必要は全くありません。
しかし、周囲からの「しつけがなっていない」という視線や言葉に傷つくことも多いでしょう。そんな時は、信頼できる専門家や同じ悩みを持つ親の会などで話を聞いてもらうことで、心の負担を軽くできます。
大切なのは、過去を振り返って自分を責めることではなく、今からできることに目を向けることです。お子さんにとって最も必要なのは、ありのままを受け入れてくれる家族の存在なのです。
学習支援サービスの比較と選び方「子供に合った環境を探す」
発達障害のお子さんの学習支援では、一人ひとりの特性に合わせた個別指導が効果的です。集団塾では集中が難しいお子さんも、家庭教師なら自分のペースで学習を進めることができます。
ここでは、発達障害のお子さんに対応している主要な家庭教師サービスを比較し、それぞれの特徴をご紹介します。オンライン指導にも対応しているサービスが多く、送迎の負担なく質の高い指導を受けることができます。
家庭教師のランナーが提供する個別対応の特徴

- 創業20年以上の実績と約14万人の講師数でお子さんに合った先生を見つけやすい
- 発達障害コミュニケーション指導者が在籍し専門的なマッチングを実施
- 高額なテキスト販売なしでオンライン指導にも対応
私たち家庭教師のランナーは、創業20年以上の実績を持ち、「勉強が苦手な小中高生専門」として、発達障害のお子さんへの指導に特に力を入れています。
講師数は約14万人なので、お子さんの特性に合った先生を見つけやすいのが大きな強みです。
発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフが在籍・監修体制を整えており、お子さん一人ひとりの特性を理解した上で、最適な先生をマッチングします。
料金はプラン・地域等で変動しますが、兄弟同時指導の割引制度もご用意しています。高額なテキスト販売は一切なく、安心して続けることができます。
オンライン指導にも対応しており、不登校のお子さんでも自宅で安心して学習できる環境を提供しています。
ランナーの無料体験はこちら!家庭教師のトライによる学習サポート体制

- 業界最大手で全国33万人以上の登録教師から最適な先生を選べる
- 独自の「トライ式学習法」で個別対応を提供
- 30年以上の実績で発達障害のお子さんの進学サポートにも強い
家庭教師のトライは業界最大手として、全国33万人以上の登録教師から最適な先生を選ぶことができます。
専任の教育プランナーが家庭と教師をつなぐサポートを行い、発達障害のお子さんに対しても、独自の「トライ式学習法」を活用した個別対応を提供しています。
完全マンツーマン指導により、お子さんのペースに合わせた学習が可能です。料金は学年・地域・担当ランク・回数で変動する見積制となっています。
オンライン指導システム「トライオンライン」も充実しており、全国どこからでも質の高い指導を受けることができます。30年以上の指導実績と豊富な受験情報の蓄積により、発達障害のお子さんの進学サポートにも強みを持っています。
学研の家庭教師が持つ指導ノウハウ

- 教育大手の学研グループが運営する安心感のあるサービス
- 約12万人の登録教師から発達障害への理解がある先生を選定
- 大手企業ならではの研修体制で教師の質が高く保たれている
学研の家庭教師は、教育大手の学研グループが運営する安心感のあるサービスです。
約12万人の登録教師の中から、発達障害への理解がある先生を選定し、お子さんの学年や目的に応じた指導を提供しています。大手企業ならではの研修体制により、教師の質が高く保たれているのが特徴です。
料金はコース・学年により変動しますので、最新料金は公式サイトでご確認ください。指定教材の有無はコースによって異なりますので、詳細は申込時にご確認ください。
オンライン指導にも対応し、訪問と同じ質のサポートを全国で提供しています。
家庭教師のサクシードで受けられるサポート内容

- 上場企業運営で13万人以上の教師が在籍
- 体験授業担当の先生がそのまま正式担当になる「講師指名制」
- 担当教師と教務スタッフのダブルサポート体制
家庭教師のサクシードは上場企業が運営する安心感のあるサービスで、13万人以上の教師が在籍しています。
発達障害のお子さんへの指導経験が豊富な教師も多く、体験授業を担当した先生がそのまま正式担当になる「講師指名制」により、お子さんとの相性を確認してから本格的な指導を始められます。
料金設定は学年やコースによって異なり、入会金は原則無料の掲載があります。最新の適用条件は公式サイトでご確認ください。
担当教師と教務スタッフによるダブルサポート体制で、きめ細かな学習計画のフォローを受けることができます。
家庭教師ファーストが大切にする指導方針

- 実際に担当となる先生で無料体験ができる
- 発達障害や不登校のお子さんへの支援コースが充実
- 営業スタッフではなく担当教師自身が体験指導を行う
家庭教師ファーストは、実際に担当となる先生で無料体験を行うことができ、お子さんとの相性を確認してから契約できるのが大きな特徴です。
発達障害や不登校のお子さんへの支援コースも充実しており、一人ひとりの特性に合わせた丁寧な指導を行っています。
小学生のベースプラン例で月1万円前後からの水準がありますが、学年・コースで変動します。入会金の有無や手持ちの教材での指導可否は、最新情報を公式サイトでご確認ください。
営業スタッフではなく担当教師自身が体験指導を行うため、お子さんが最初からリラックスして授業に臨めます。オンライン指導にも対応し、全国どこからでも同じサービスを受けることができます。
家庭教師のノーバスによる個別指導の特徴

- 関東・東海地方を中心に展開する老舗の家庭教師センター
- 教師と学習プランナーのダブル体制できめ細かなサポート
- オンライン指導サービス「Netty」も関連サービスとして展開
家庭教師のノーバスは、関東・東海地方を中心に展開する老舗の家庭教師センターです。個別指導塾も運営しているため、豊富な指導ノウハウと受験情報を持っています。
発達障害のお子さんへの対応経験も豊富で、教師と学習プランナーのダブル体制できめ細かなサポートを提供しています。料金は地域・学年により前後しますが、目安として週1回90分授業で月25,000~30,000円程度です。
プロ家庭教師コースも他社より比較的安価で利用できます。オンライン指導サービス「Netty(ネッティー)」も関連サービスとして展開しており、訪問と同様の質の高い指導を全国で受けることができます。
不要な教材販売がなく、シンプルな料金体系で安心して利用できます。
家庭教師のあすなろが実践する寄り添い型指導
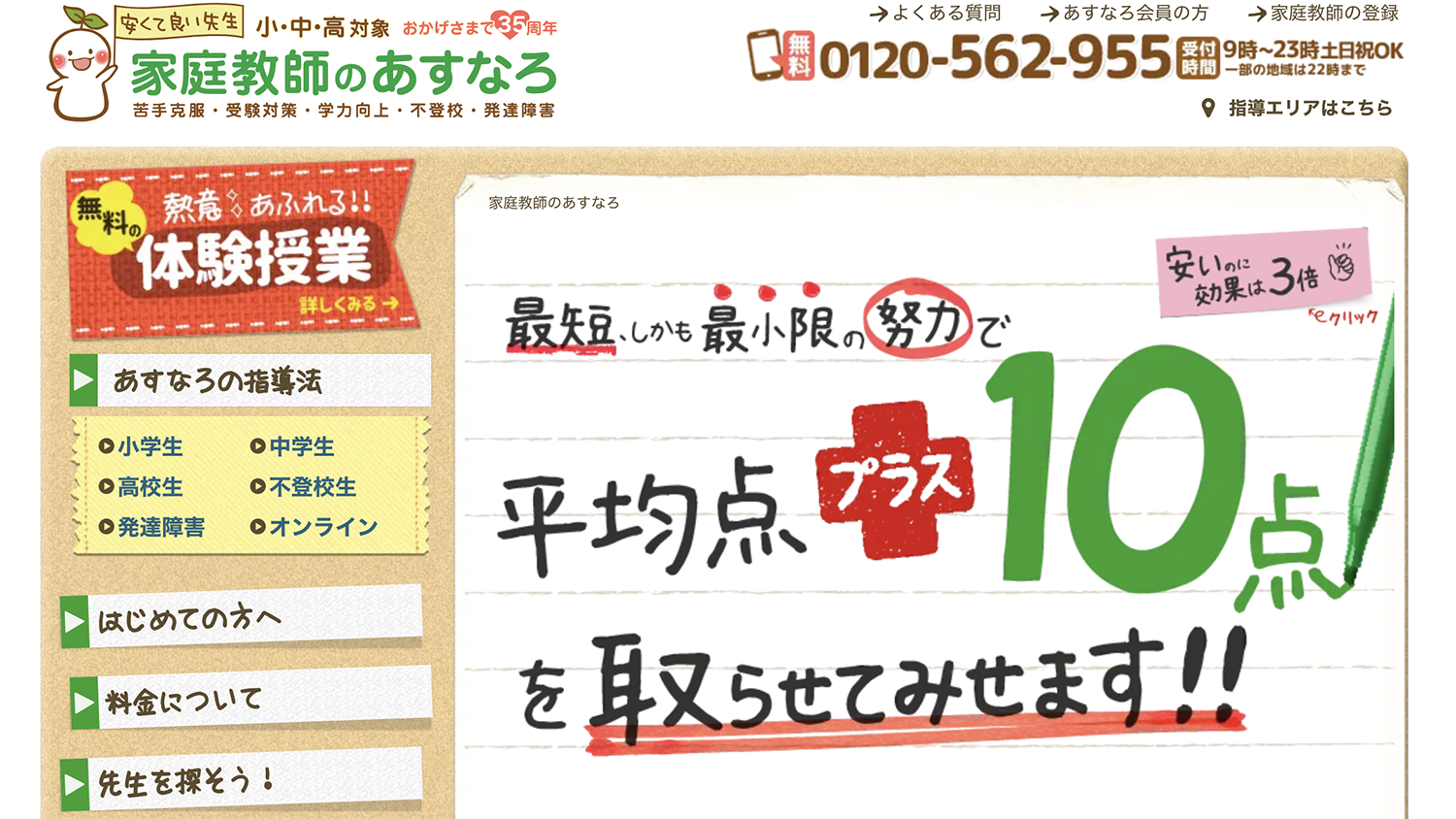
- 「勉強が苦手な子専門」で35年以上の実績
- 大学生中心の若い先生で親近感を持って接することができる
- LINEを使った「お悩みお助け隊」で授業のない日も質問可能
家庭教師のあすなろは「勉強が苦手な子専門」を掲げ、35年以上の実績を持つサービスです。大学生中心の若い先生が多く、お子さんとの年齢が近いため、親近感を持って接することができます。
発達障害のお子さんに対しても、一人ひとりのペースに合わせた優しい指導を心がけています。料金は月約1.5万~2.5万円が多い価格帯となっています。
LINEを使った「お悩みお助け隊」サービスでは、授業のない日でも質問ができ、つまずきを放置しない仕組みが整っています。オンライン指導にも対応し、全国どこからでも同じ料金でサービスを受けることができます。
家庭教師学参が提供する専門的な指導内容

- 40年以上の指導実績を持つプロ家庭教師専門サービス
- 講師選択制度で希望条件に合った教師を複数提案
- 部活や習い事で忙しい時期は授業回数を柔軟に調整可能
家庭教師学参は、40年以上の指導実績を持つプロ家庭教師専門のサービスです。登録講師は全員が指導経験者で、発達障害のお子さんへの対応経験も豊富です。
講師選択制度により、希望条件に合った教師を複数提案してもらい、無料体験授業で相性を確認してから契約できます。授業料は教師ランク・方式で変動し、1時間4,400円からの設定例があります。
初期費用・諸経費の有無は最新案内でご確認ください。部活や習い事で忙しい時期は授業回数を柔軟に調整でき、お子さんのペースに合わせた指導が可能です。
オンライン指導「学参オンライン」も提供しており、全国どこからでも質の高いプロ講師の指導を受けることができます。
オンライン家庭教師Wamで実現する柔軟な学習

- 独自開発の専用システムで効率的なオンライン指導
- 東京大学など有名大学の現役学生が講師として在籍
- オンライン専業で移動時間ゼロ、部活や習い事で忙しくても対応可能
オンライン家庭教師Wamは、独自開発の専用システムを使った効率的なオンライン指導が特徴です。板書共有や双方向のやり取りに最適化されたシステムにより、発達障害のお子さんでも集中しやすい環境で学習できます。
東京大学など有名大学の現役学生が講師として在籍しています。
料金は小学生40分×月4回で月4,900円から、中学生は月7,600円から、高校生は月9,200円からとなっていますが、学年・コース・地域で変動があります。最新の料金は公式サイトでご確認ください。
オンライン専業のため、移動時間ゼロで効率的に学習でき、部活や習い事で忙しいお子さんにも最適です。
オンライン家庭教師トウコベの東大生による指導
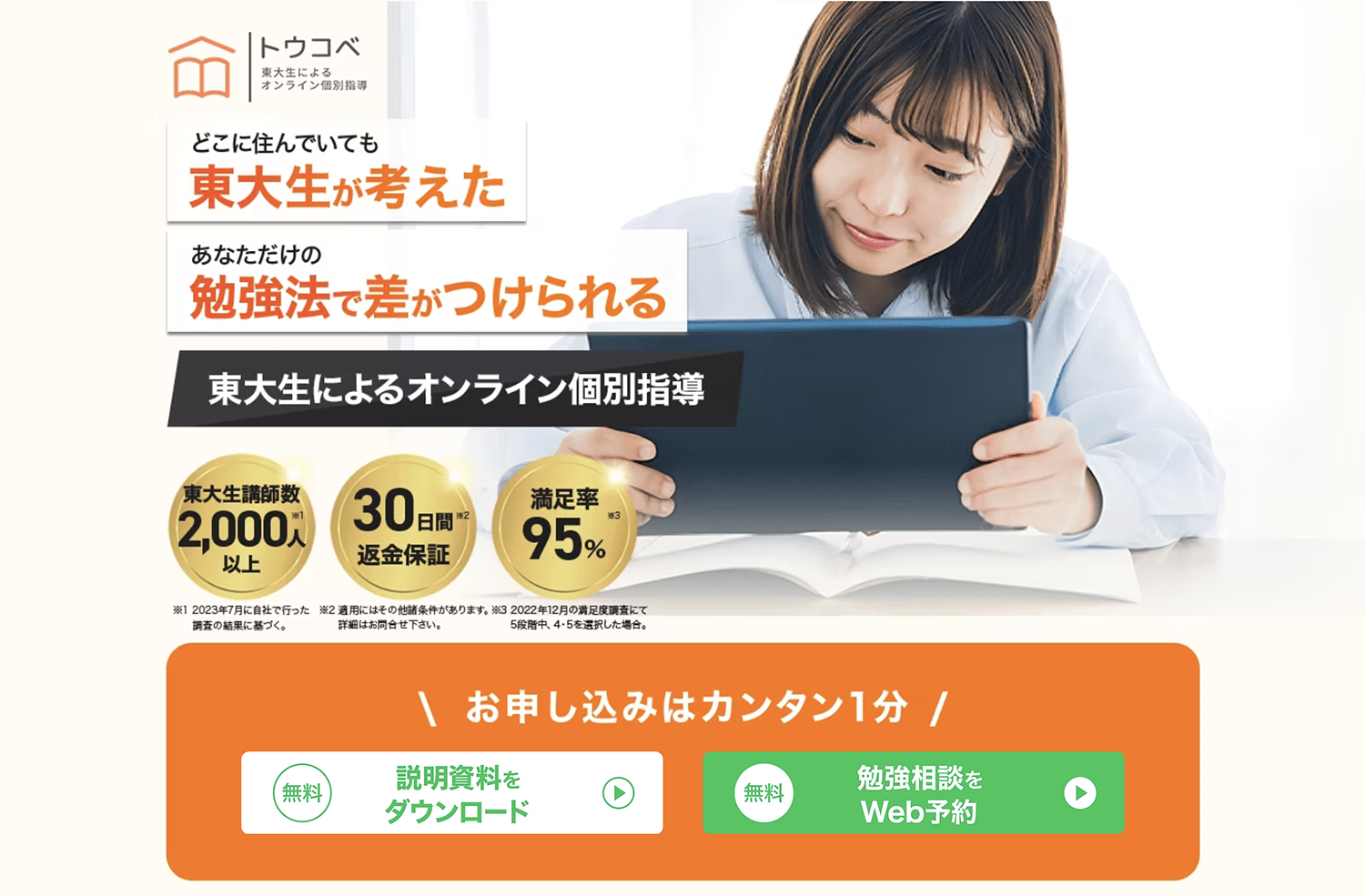
- 東京大学の現役東大生講師による個別指導サービス
- 1,500名以上の東大生が登録し満足度95%以上の評価
- 30日間返金保証付きで安心して試すことができる
オンライン家庭教師トウコベは、東京大学の現役東大生講師による個別指導サービスです。自社公表の実績として、1,500名以上の東大生が登録しており、満足度95%以上という評価を得ています。
発達障害のお子さんに対しても、東大生ならではの論理的で分かりやすい指導により、学習への興味を引き出します。料金は講師・プランにより幅広く設定されており、詳細は公式サイトでご確認ください。
30日間返金保証が付いているため、安心して試すことができます。オンライン特化のサービスで、日本全国および海外からでも東大生の指導を受けることができます。
講師交代も自由で、お子さんに最適な先生を見つけることができます。
オンライン家庭教師マナリンクのプロ講師による指導
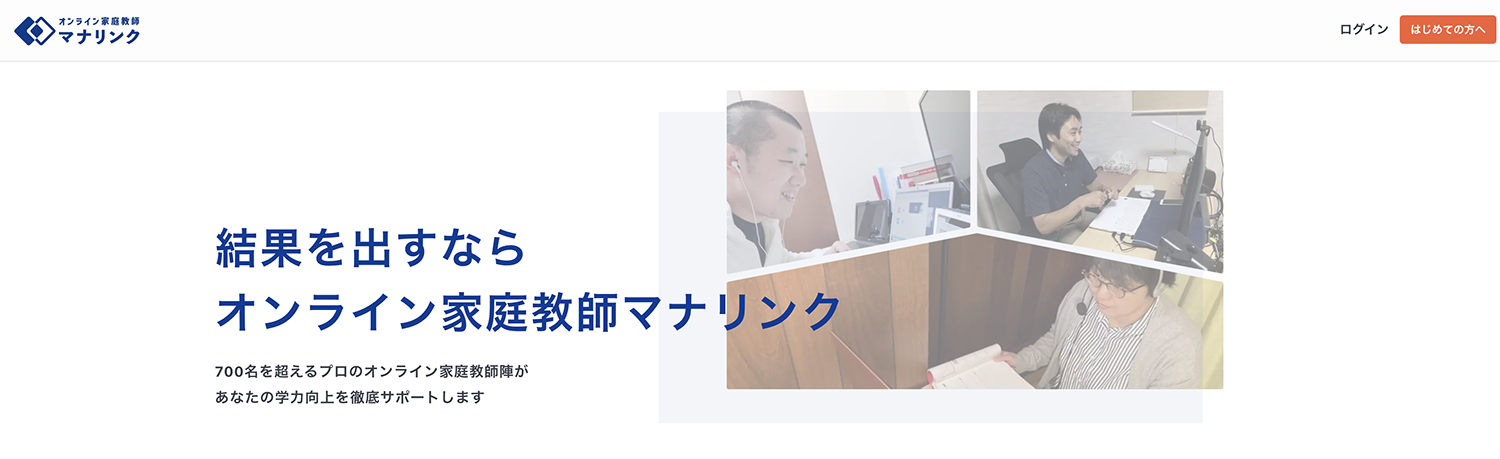
- 100%社会人のプロ講師のみが登録するマッチングプラットフォーム
- サイト上で講師のプロフィールや動画を見比べて選べる
- 専用アプリで講師と直接やり取りができきめ細かなサポート
オンライン家庭教師マナリンクは、100%社会人のプロ講師のみが登録するマッチングプラットフォームです。塾講師や教員、有資格者など経験豊富な先生が揃っており、発達障害のお子さんへの専門的な指導も可能です。
サイト上で講師のプロフィールや動画を見比べて、自分に合った先生を選ぶことができます。
入会金が必要ですが、月会費は原則不要です。講師ごとに料金が設定されており、大きく変動します。
専用アプリで講師と直接やり取りができ、きめ細かなサポートを受けることができます。短期集中での利用も可能で、お子さんのニーズに合わせた使い方ができます。
集中力がない子供の発達障害についてのまとめ
- ・発達障害による集中力の問題は適切な理解と対応で改善が期待できる
- ・家庭でできる工夫と学校との連携で支援の輪を作ることが大切
- ・診断の有無に関わらず今できることから始めることが重要
- ・親御さんが一人で抱え込まず様々な支援を活用することが必要
- ・小さな成功を積み重ね、お子さんの可能性を信じて前進する
集中力がない子供の発達障害について、ここまで様々な視点から理解を深め、具体的な対策をお伝えしてきました。
発達障害は決して「治す」ものではなく、お子さんの特性として理解し、適切な支援によってその子らしく成長していくためのものです。
診断の有無に関わらず、今お子さんが困っていることに対して、できることから始めていくことが何より大切です。
家庭での小さな工夫、学校との連携、専門機関への相談、そして適切な学習支援サービスの活用など、様々な支援の輪を作ることで、お子さんは安心して成長できる環境を得ることができます。
親御さんが一人で抱え込む必要はありません。家族、学校、専門家、そして家庭教師など、たくさんの味方と一緒に、お子さんの成長を支えていけばいいのです。
時には思うように進まない日もあるでしょう。しかし、小さな成功を積み重ね、お子さんの「できた!」という笑顔を見つけていくことで、前に進むことができます。
お子さんの可能性を信じ、家族みんなで寄り添いながら、一歩ずつ歩んでいきましょう。今日から始められる小さな一歩が、お子さんと家族の明るい未来につながることを心から願っています。
ランナーの無料体験はこちら!