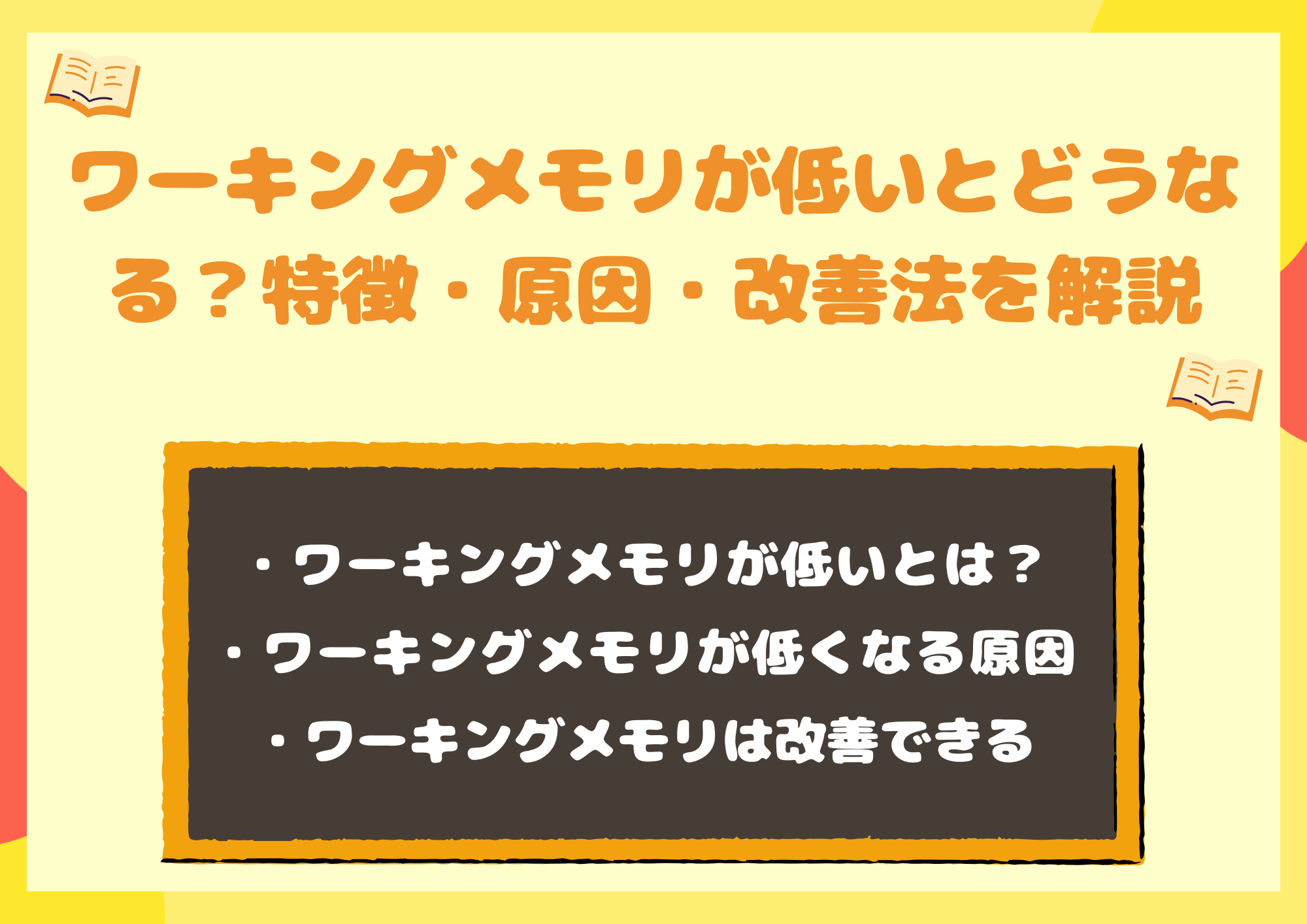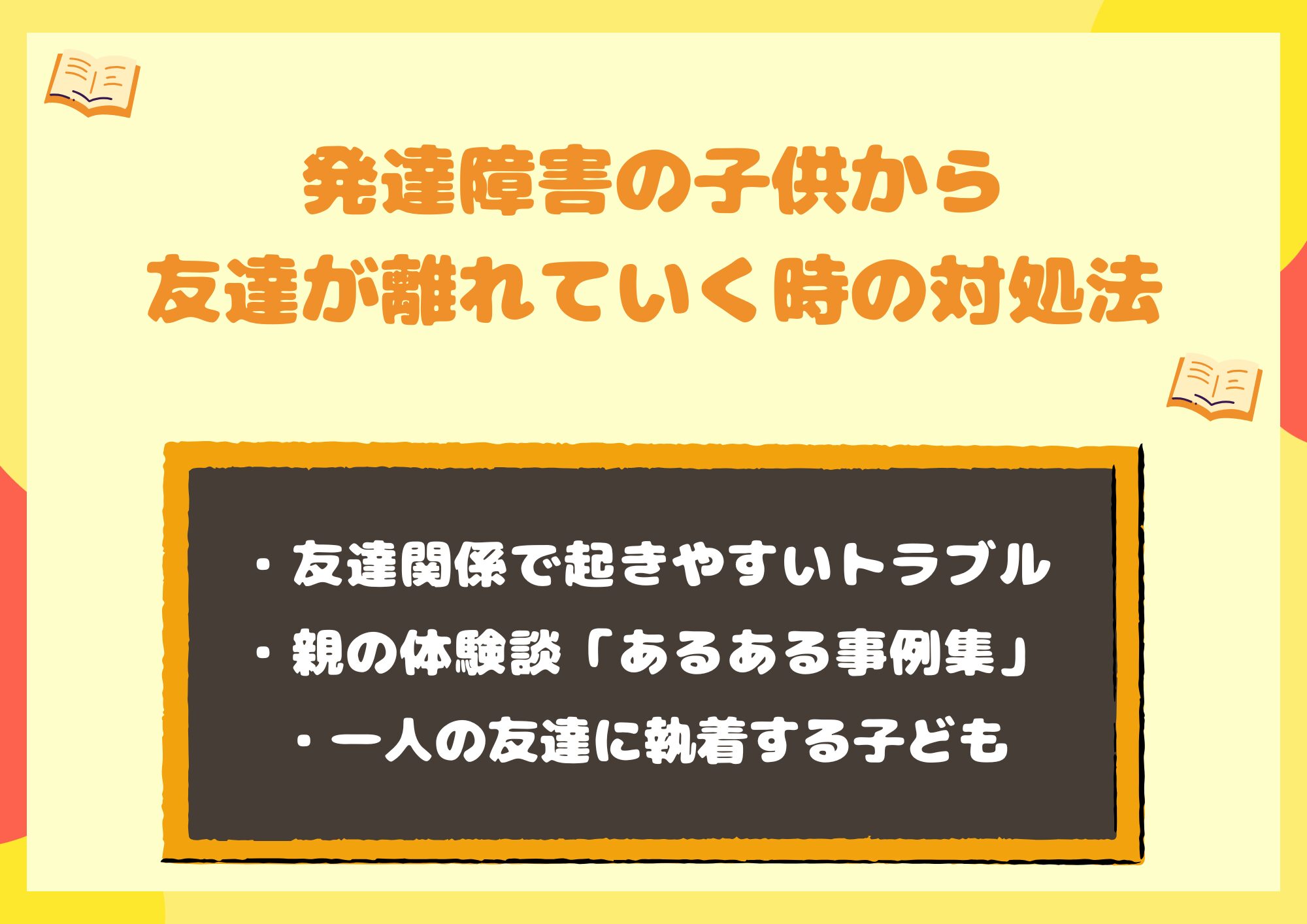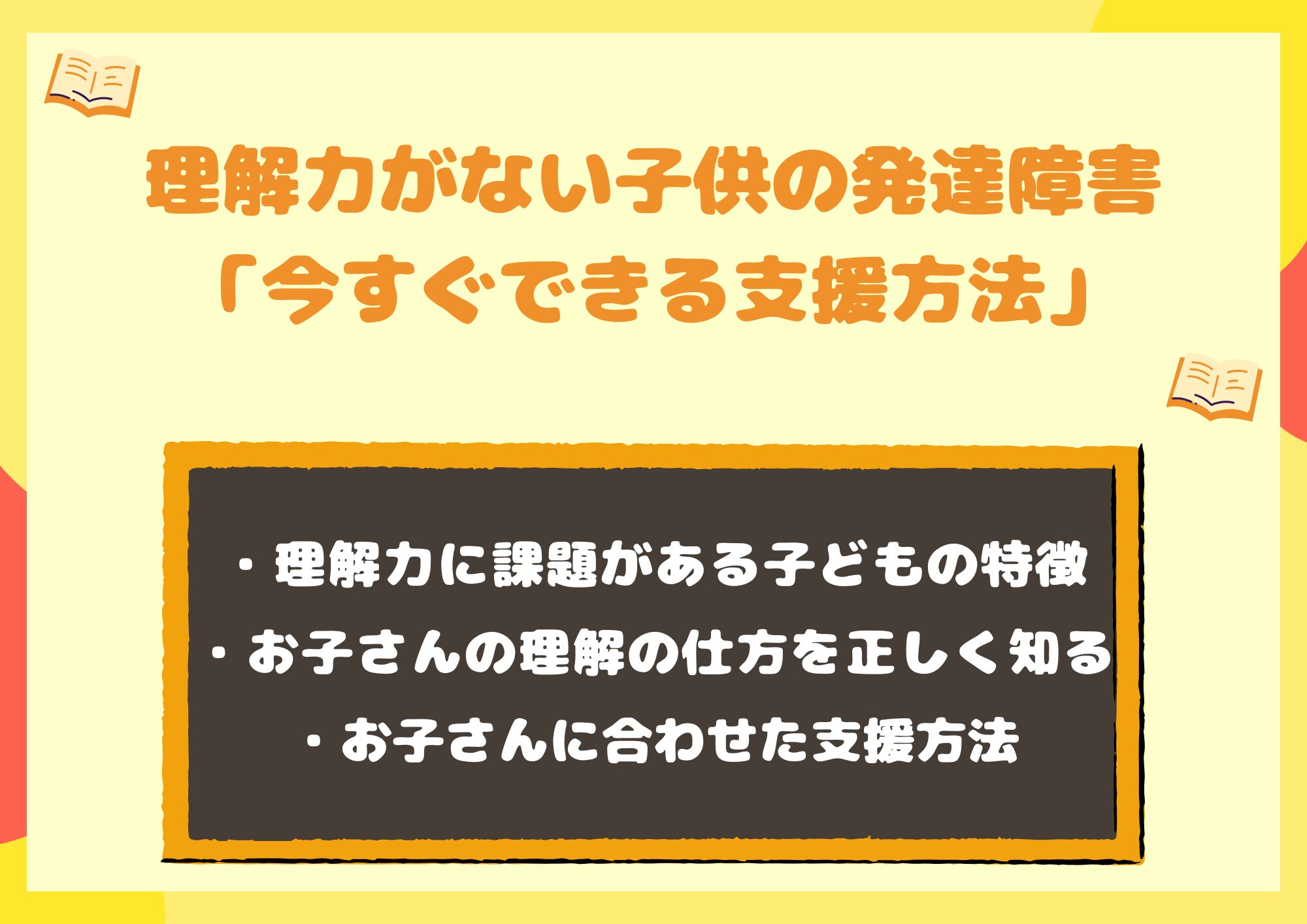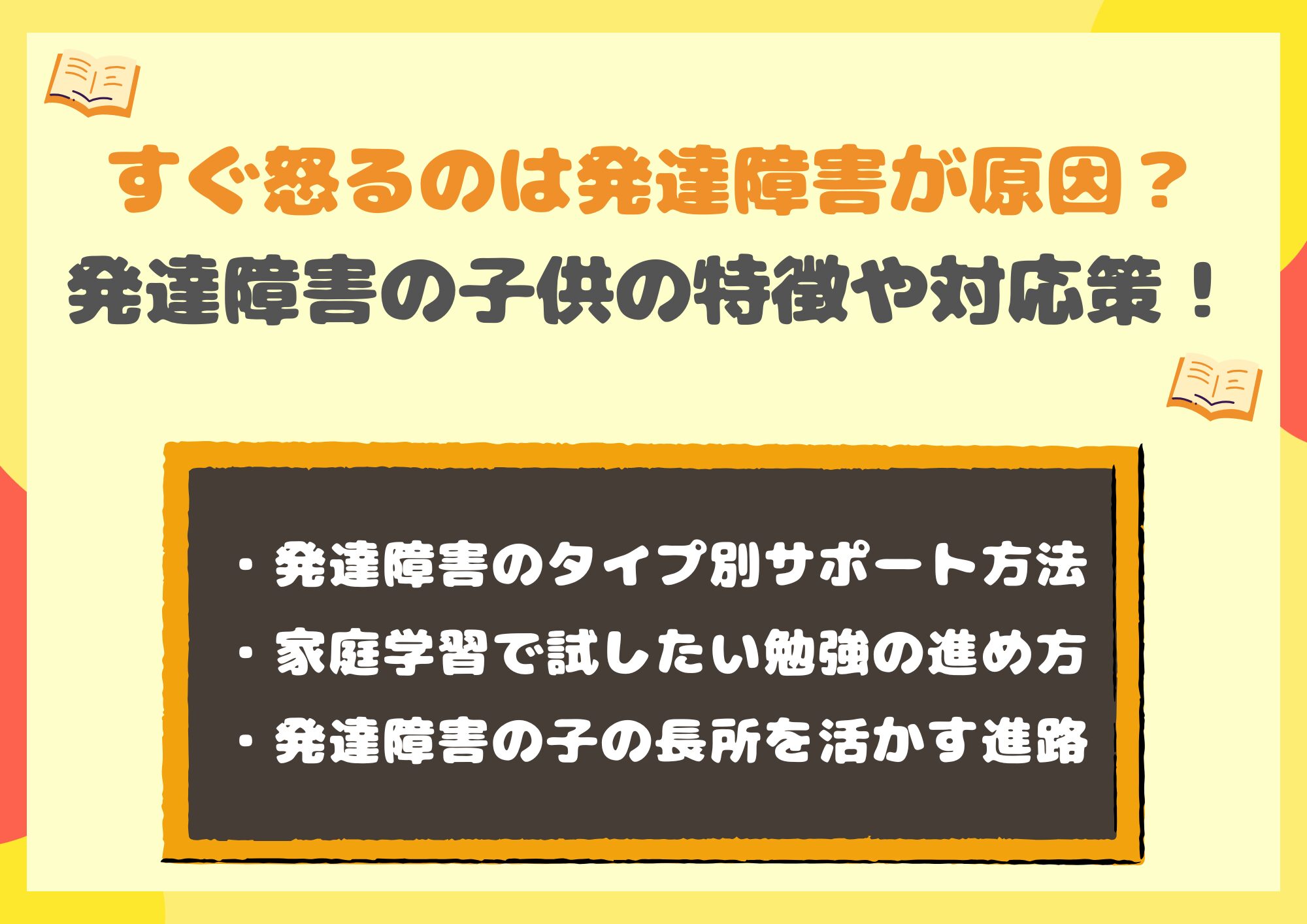- 発達障害向けの家庭教師
中学生の発達障害診断と支援の実態|信頼できる病院・チェック方法・家庭教師活用
2025.08.14
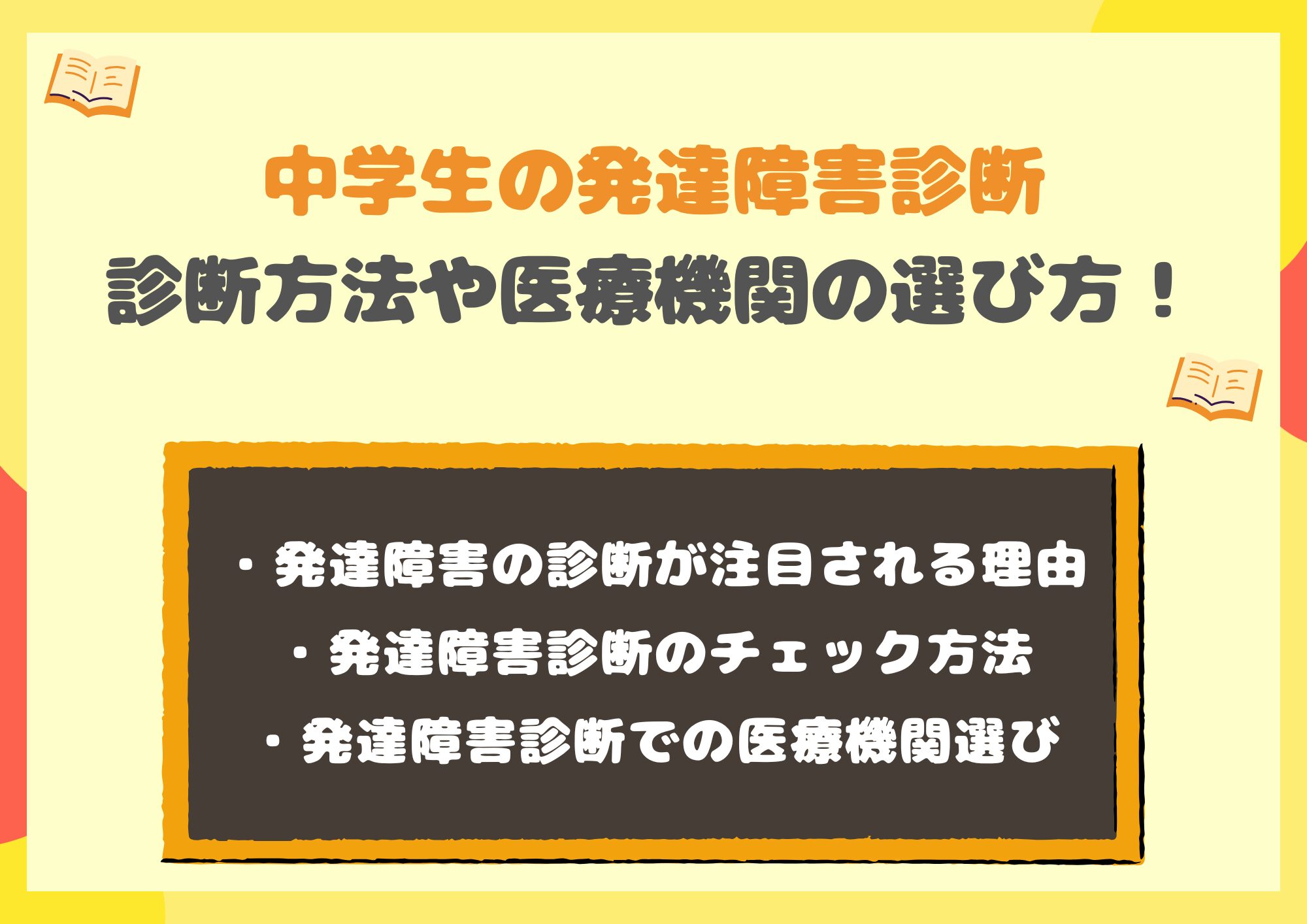
中学生になると学習や人間関係が複雑になり、小学生時代には見えにくかった発達障害の特性が表面化しやすくなります。
授業への適応や友人関係の変化、部活動での課題など、思春期特有の悩みが増える中、保護者の「対応方法が分からない」「診断や支援の選択肢が多くて迷う」といった声も多く聞かれます。
本記事では中学生の発達障害診断を検討する保護者に向けて、診断方法や医療機関の選び方、家庭でできる観察ポイント、学習サポートの具体例まで、最新の情報を分かりやすくまとめています。
東京都の主要な専門機関リストやセルフチェックリスト、家庭教師サービスなど、信頼できるデータとともにお伝えします。
目次
中学生で発達障害の診断が注目される理由と保護者の悩み

ここ数年、発達障害の診断や支援への関心が社会全体で高まっています。
とくに中学生期は、それまで見過ごされていた特性が目立ちやすく、保護者の「このままでよいのか」という不安も強くなりがちです。
進路選択や人間関係など多くの変化が重なる時期に、適切な診断とサポートを受けることで子どもの可能性は大きく広がります。
この章では、発達障害の診断が中学生期に増える背景と、実際の保護者の悩みについて説明します。
発達障害の診断が中学生期に増える背景とは
- 学習内容や生活環境が複雑化し、特性が顕在化しやすい。
- 協調性や自己管理力が求められる場面が増加。
- 学校から特性を指摘されるケースが増えている。
- 早期の診断・支援で二次障害予防につながる。
学習内容や集団生活が複雑になることで、発達障害の特性がより分かりやすく表れます。
小学生の頃は「個性」と受け取られやすかった言動も、中学校では「協調性がない」「注意力が散漫」など否定的に評価される場面が増えます。
教科ごとに異なる対応が求められ、ノート管理や課題提出、教科切り替えなど高い自己管理力が必要となるため、「遅れ」や「苦手さ」が浮き彫りになりやすくなります。
部活動や委員会活動への参加が増え、対人トラブルも起こりやすくなる点も特徴です。
中学生は診断の必要性に気付きやすい大事なタイミングです。
学校側から発達特性を指摘され、戸惑う保護者も少なくありません。
早めに適切な支援につなげることで、不登校や自信喪失などの二次障害予防にもつながります。
厚生労働省等の調査でも中学生以降に診断を受けるケースが増えており、「診断はサポートの第一歩」と捉えられる傾向が強まっています。
まずは正しい情報を得て、冷静に選択肢を検討することが重要です。
中学生の発達障害でよくある保護者の困りごと
- 具体的な接し方・対応策が分からない。
- 診断・相談先の選び方に迷う。
- 自己肯定感の低下や成績・友人関係の悩みが多い。
- 共働きで受診や相談の時間確保も課題。
保護者が特に悩みやすいのは、学校や家庭での「具体的な接し方」です。
「どこで診断を受ければよい?」「成績低下の原因は何か?」といった疑問や、「学校生活や家庭学習への対応」「友人とのトラブル」「自己肯定感の低下」など多岐にわたる問題に直面します。
選択肢が多い一方で、信頼できる情報を見極めるのが難しいのも現状です。
共働き家庭では受診や相談の時間確保も課題となります。
「子どもの自己肯定感を損なわず、前向きなサポートをしたい」と考える保護者が増えています。
課題を一つずつ整理し、具体的なアクションへ進める情報をこの後ご案内します。
学校生活や成績低下・部活動で目立つ発達特性のサイン
- 授業態度や成績、部活動で特性が表れやすい。
- ADHDやASDなどの傾向が行動に現れる。
- 行動記録をまとめ、相談の準備を進めることが大切。
中学生の発達障害は授業態度や成績、部活動で表れることが多いです。
「授業に集中できない」「課題提出を忘れやすい」「友人との約束が守れない」などの行動は特性のサインである可能性があります。
成績の急激な変化や部活動でのトラブルも、発達障害に関連していることがあります。
ADHD傾向では「注意力散漫」「忘れ物が多い」、ASD傾向なら「空気を読むのが苦手」「変化に対応できない」などがよく見られる特長です。
「行動の背景を理解し、子どもを責めずに支える姿勢」が、二次障害の防止や自己肯定感維持のカギです。
家庭と学校で協力し、成績や行動記録をまとめて医療機関への相談準備を進めましょう。
中学生の発達障害診断の基礎知識と主なチェック方法

発達障害の診断を受けるには、主な障害の種類や検査、セルフチェックの方法を知ることが大切です。
診断は「できる・できない」の判定だけでなく、本人の強みや課題を客観的に理解し、最適な支援につなげるためのものです。
ここでは主要な発達障害の種類、診断の流れと検査、自宅でできるセルフチェック、代表的な発達検査の内容を説明します。
事前に基礎知識を持つことで、医療機関や学校との連携もスムーズに進みます。
中学生で多い発達障害の種類と特徴(ADHD・ASD・LD等)
- ADHD・ASD・LDが中学生で多い代表的な発達障害。
- 特性は外見で分かりづらいが、学習・行動面に現れる。
- 複数特性の重なりや個人差が大きい。
- 支援は「できない」ではなく、特性に合わせた配慮が大切。
中学生によく見られる発達障害には、ADHD(注意欠如・多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、LD(学習障害)などがあります。
ADHDは「集中が続かない」「ミスや忘れ物が多い」「落ち着きがない」などが特徴です。
ASDは「集団での会話が苦手」「急な変更への対応が難しい」「特定分野への強いこだわり」など、社会性や柔軟性の課題が中心です。
LDは「読み書き」や「計算」など特定分野だけに強い苦手さが出る点が特徴で、知的発達はおおむね問題ありません。
これらの特性は外見では分かりづらく、複数の特性が重なるケースも多いため、家庭や学校での観察が重要となります。
「発達障害は“できない”のレッテルではなく、特性に合わせた支援が必要な子どもである」という理解が第一歩です。
診断と支援は、本人の可能性を広げる前向きなプロセスとして活用しましょう。
中学生の発達障害診断に使われる主な検査とフロー
- 問診・行動観察・知能検査(WISC-Vなど)を組み合わせて診断。
- 診断は支援のスタートライン。
- 結果説明まで数週間~3か月かかる場合が多い。
- 事前準備で安心して臨める。
発達障害の診断は、複数回の問診や検査を組み合わせて行います。
医療機関ではまず問診・面談があり、家庭や学校での行動観察、成績や生活歴も重要な判断材料です。
次に知能検査として、「WISC-V」(ウィスク・ファイブ:2018年より日本国内で導入)が多く使われ、中学生向けの行動評価には「Conners 3」「ADHD-RS」などが活用されます。
「WAIS-IV」は16歳以上の高校生や大人が対象です。中学生の検査では通常使用しませんが、高校進学後の評価で用いられることがあります。
心理士による発達検査や、学校・家庭からのヒアリングシートも診断に役立ちます。
検査結果をもとに児童精神科医や臨床心理士が総合的に判断し、診断後は説明や診断書発行、学校との情報共有につながります。
診断はゴールではなく、今後の支援や環境調整のスタートラインです。
検査は数時間かかる場合もあり、予約から結果説明までは数週間〜3か月程度を見込んでおきましょう。
事前に流れや準備を確認しておくと、安心して臨むことができます。
自宅でできる中学生向け発達障害セルフチェックリスト
- 家庭でセルフチェックを実施し、行動を客観的に把握。
- 本人と保護者が一緒に取り組むことで気づきにつながる。
- 複数当てはまる場合は早めに専門相談を。
- セルフチェックは診断の代わりではない。
「発達障害かもしれない」と感じた場合、家庭でセルフチェックを行うことが第一歩です。
「学校の持ち物準備が苦手」「口頭指示をすぐ忘れる」「人との距離感がつかめずトラブルが起きやすい」「予定変更に動揺しやすい」など、日常の行動を書き出してみましょう。
保護者と本人が一緒にチェックシートを使うことで、気づきや自己理解につながります。
インターネット上では「発達障害チェックリスト(中学生向け)」が公開され、無料で利用できます。
ただし、セルフチェックは診断ではなく、専門機関への相談につなげるための目安です。
気になる点が複数当てはまる場合は、医療機関や学校カウンセラーへ早めに相談することで二次障害予防に役立ちます。
不安を一人で抱えず、信頼できる専門家と連携して進めましょう。
WISC-VやWAIS-IVなど中学生対象の発達検査の内容と特徴
- WISC-Vは中学生の発達検査で最も多く使われる。
- 5つの指標で強み・苦手を多面的に評価。
- 検査は標準得点で結果が示される。
- 不明点は担当医や心理士に質問し、理解を深める。
中学生の発達障害診断で多く使われるのは「WISC-V」(2018年より日本版運用)です。
WISC-Vは言語理解・知覚推理・ワーキングメモリー・処理速度・視空間認知という5つの指標から多面的に評価します。
実施時間は約65〜80分程度で、臨床心理士などの専門スタッフが実施します。
検査結果では「標準得点(平均100、SD15)」で強み・苦手が客観的に示され、学習面の課題把握や支援計画に役立ちます。
「WAIS-IV」は16歳以上が対象で、高校生や大人向けの知能検査です。中学生の診断には原則用いませんが、15歳後半の進路選択時などに実施されることもあります。
検査結果は標準得点で評価し、個々の特徴や必要な支援方針の検討資料として活用しましょう。
分かりにくい場合は担当医や心理士に遠慮なく質問し、理解を深めてください。
中学生の発達障害診断を受けるための医療機関の選び方
診断を検討する際、どの医療機関を選べばよいか悩む保護者が多くいます。
児童精神科や発達障害外来、臨床心理士のいる相談機関など、専門性のある施設を選ぶことが大切です。
また、診断までの流れや費用、自治体による医療費助成制度についても事前に調べておくと安心です。
この章では東京都の主な診断機関リスト、受診予約から検査までの流れ、助成制度のポイントをまとめます。
東京都で発達障害診断ができる主な病院と専門機関一覧
- 国立成育医療研究センターなど信頼できる大規模専門病院。
- 区市町村の発達障害者支援センターも利用可能。
- 児童精神科医や臨床心理士がチームでサポート。
- 予約のしやすさや通いやすさも選択の基準。
東京都内には発達障害の診断に対応した専門病院・クリニックが多くあります。
主な例として、国立成育医療研究センター、東京都立小児総合医療センター、東京大学医学部附属病院 こころの発達診療部、順天堂大学医学部附属順天堂医院 小児・思春期精神医学講座、昭和大学附属烏山病院(児童・思春期精神科)などが挙げられます。
また区市町村の発達障害者支援センターや、児童精神科を備えた総合病院も利用できます。
各病院では児童精神科医や臨床心理士が連携し、問診や発達検査、家族面談など総合的な支援を行っています。
予約のしやすさや専門分野、通いやすさも病院選びの重要なポイントです。
最新情報は自治体や発達障害者支援センターの公式サイトを参照してください。
診断予約から検査結果までの流れと必要な準備
- 予約は電話・Webで受付が一般的。
- 初診では問診票・家族面談・行動観察が中心。
- WISC-Vなどの知能検査やヒアリングシートが必要な場合も。
- 診断前に行動記録や成績推移の資料を整理。
- 質問リストを作成しておくと安心。
受診までの流れは、電話やWebで予約後、初診で問診票の記入・家族面談・行動観察などが行われます。
必要に応じてWISC-Vなどの知能検査や心理検査、学校や家庭からのヒアリングシート提出が求められることもあります。
検査結果は数週間〜3か月程度待つケースが多いです。
結果説明時には今後の支援方針も案内されます。
事前準備として「家庭での行動記録」「成績推移」「学校での困りごとリスト」をまとめておくとスムーズです。
本人の同意や気持ちの確認も忘れずに行いましょう。
「分からない点は初診予約時に看護師や受付へ確認」することで安心して診断を受けられます。
質問リストの作成もおすすめです。
発達障害診断にかかる費用と自治体の助成制度
- 診断・検査費用は1万~2万円台(保険適用時)、知能検査は保険適用外が多い。
- 知能検査は1回1万~5万円程度かかる場合も。
- 自治体によって医療費助成制度あり。
- 費用負担に不安がある場合は福祉課・支援センターに相談を。
診断にかかる費用は医療機関や検査内容によって異なります。
健康保険が適用される場合は3割負担となり、初診・再診・各種検査を合わせ1万〜2万円台が一般的です。
知能検査(WISC-Vなど)は多くの場合保険適用外となり、1回あたり1万〜5万円程度かかることがあります。
自治体の医療費助成制度(名称・条件は地域により異なる)が利用できる場合もあり、年齢や世帯状況によって自己負担が軽減されることもあります。
診断書の発行には別途数千円の費用が必要なケースもあります。
経済的な負担を感じた場合は、自治体の福祉課や発達障害者支援センターに相談し、最新情報を確認しましょう。
制度の詳細や申請方法は必ず自治体窓口で確認してください。
診断前に家庭で準備したい中学生の行動観察と記録ポイント
医療機関で診断を受ける前に、家庭や学校での行動記録を整理しておくことで診断の精度が高まります。
「どの場面で困りごとが多いか」「家と学校で違いがあるか」など、保護者や先生が感じることを具体的にまとめておきましょう。
担任や養護教諭・スクールカウンセラーとも情報共有し、診断時の参考資料を揃えることが大切です。
この章では記録のつけ方や学校連携のコツ、診断時に役立つ資料例を紹介します。
家庭でできる行動記録の付け方と学校連携のコツ
- 「いつ」「どこで」「何が起きたか」「どう対応したか」を簡単に記録。
- 行動記録は診断・支援計画に重要。
- スマホのメモやアプリ活用もOK。
- 学校との連携で客観的なサポートが可能に。
行動記録は「いつ」「どこで」「どんな状況で」「何が起きたか」「どう対応したか」を毎日簡単に記録するのが基本です。
例として「朝の支度に時間がかかる」「友人とのトラブルがあった日」「宿題に手がつけられなかった」など、具体的な出来事を時系列で記載します。
この記録は診断や支援計画作成の重要な参考資料となります。
担任やカウンセラーと共有することで、客観的なサポート計画が立てやすくなります。
続けることで「どの場面で困るか」「うまくいった支援策」なども分かり、今後の支援に活用できます。
記録が苦手な場合はスマホのメモやカレンダーアプリで短文でも継続することが大切です。
家庭の状況に合わせ、無理なく記録と連携を進めてください。
担任・養護教諭・スクールカウンセラーへの相談の進め方
- まずは担任に困りごとを相談し、学校の様子を確認。
- 担任が難しい場合は養護教諭やスクールカウンセラーにも連絡可能。
- 保護者面談や教育相談日も積極的に活用。
- 行動記録や困りごとリストを持参して相談を具体的に。
- 一人で抱えず、学校や専門職と協力することが大切。
「誰に相談したらよいか分からない」と感じる保護者も多いですが、まずは担任の先生に「最近このような困りごとがある」と伝え、学校での様子を聞いてみましょう。
担任への相談が難しい場合は、養護教諭やスクールカウンセラーへの直接連絡も有効です。
学校によっては「教育相談日」や「保護者面談日」が設けられているので、こうした機会も活用しましょう。
相談時は行動記録や困りごとリストを持参することで、具体的な話し合いができます。
一人で悩まず、他の保護者や専門職と協力してサポート体制を整えることが大切です。
一人で抱え込まず、気軽に相談できる環境づくりが中学生支援には不可欠です。
学校との連携はお子さんの将来にとって重要な一歩となります。
診断時に持参したい成績推移や行動記録の具体例
- 成績表やテストの点数推移、生活記録表が診断の精度向上に役立つ。
- 家庭でまとめた行動記録や学校からの連絡帳も有効。
- 「どの科目が苦手か」「どんな場面でつまずきやすいか」など客観的データを整理。
- 必要な資料は医療機関に事前確認を。
- 資料は完璧でなくてOK。できる範囲で少しずつ集めることが大切。
医療機関での診断時には「過去1年程度の成績表」「テストの点数推移」「生活記録表」などを持参すると、診断の精度が上がります。
家庭でまとめた行動記録や学校からの連絡帳コピー、本人の生活リズムや困った時の様子を書いたメモも有効です。
「どの科目が苦手か」「どんな場面でつまずきやすいか」「どのような支援が効果的だったか」などの客観的なデータが診断や今後の支援に直結します。
医師や心理士はこうした資料をもとに、お子さんに合ったサポート方法を提案してくれます。
資料は完璧でなくて構いません。できる範囲で少しずつ集めて整理し、診断時に活用しましょう。
迷った時は事前に医療機関へ「必要な資料」について確認してみてください。
中学生の発達障害診断結果の読み取り方と今後の学校対応
発達障害の診断を受けた後、保護者が「診断書の内容の見方」や「学校や進路選択への活かし方」で悩むケースが多いです。
大切なのは「できる・できない」にとらわれず、診断結果を活用し、お子さんに合った支援策や学習環境を整えていくことです。
ここでは診断書の読み取りポイント、学校との連携方法、進路選択への活かし方を紹介します。
診断書・検査結果から読み取る中学生の特性理解ポイント
- 診断書・検査結果に示された特性を具体的に確認。
- WISC-Vなどの得点で強み・課題が可視化される。
- 分からない部分は必ず質問・確認することが大切。
- 必要に応じてセカンドオピニオンも検討可能。
- 診断結果は今後の支援の“地図”になる。
診断書や検査結果には「ADHD傾向」「ASDの特性」「ワーキングメモリーに課題がある」などの表現が並ぶことがあります。
分からない部分は主治医や心理士にその場で質問し、「どこが得意でどこが苦手か」「どんな支援が必要か」を具体的に確認してください。
WISC-Vなどの検査結果では、「言語理解」「処理速度」など分野ごとの強みや課題が標準得点(平均100、SD15)で示され、得意不得意が可視化されます。
学校用の診断書には、配慮事項(テスト時の時間延長や座席配慮など)が記載される場合もあります。
診断結果はお子さんの特性を「見える化」し、効果的な支援やサポートにつなげる“地図”です。
説明に納得できない場合は、セカンドオピニオンを検討するのも方法のひとつです。
個別教育支援計画(IEP)を活用した学校との連携方法
- 診断結果をもとにIEP(個別教育支援計画)を作成。
- 保護者・本人も話し合いに参加し、希望や困りごとを伝える。
- 「授業中の配慮」「課題提出期限延長」など具体的支援を明確化。
- 定期的に計画の見直しが必要。
- IEPの活用で家庭と学校が同じ目標を持てる。
診断結果をもとに、学校では「個別教育支援計画(IEP)」が作成されることがあります。
IEPはお子さん一人ひとりの特性や目標に合わせて、学校・家庭・専門機関が協力し支援内容を明確にするプランです。
作成時は保護者や本人も話し合いに参加し、希望や困りごとを伝えてください。
IEPには「授業中の配慮」「課題の提出期限延長」「休み時間の過ごし方」など具体的な支援が盛り込まれます。
進捗や新たな課題が生じた場合は、定期的に計画を見直しましょう。
IEPの活用で、学校と家庭が“同じ目標”でサポートできる体制を作ることができます。
診断書や検査結果は分かりやすくまとめて学校側と共有しましょう。
中学生の発達障害診断結果を進路・高校選びに活かすコツ
- 進路・高校選びは苦手を補う支援が受けられる環境も重視。
- 通級指導教室や特別支援学級、通信制高校など多様な選択肢。
- 学校説明会や見学時に支援体制を確認する。
- 担任やカウンセラーと進路相談を進める。
- 支援センターや外部機関も活用可能。
診断結果をもとにした進路・高校選びは、多くの家庭にとって大きなテーマです。
「苦手を補う支援」がある高校や、「個別配慮」が受けやすい環境を選ぶことが重要です。
例えば通級指導教室や特別支援学級設置校、学習サポートが充実した通信制高校なども選択肢になります。
学校説明会や見学時に「発達障害の生徒への支援体制」や「卒業生の進路実績」なども直接質問してみましょう。
進路相談では、担任や進路指導教員、カウンセラーと連携し、お子さんの特性や希望を丁寧に伝えることが大切です。
診断結果を前向きに活かし、“自分らしく学べる進路”を選べるよう親子で話し合いましょう。
判断が難しい時は発達障害者支援センターなど外部機関も活用してください。
中学生の発達障害診断後に使える支援制度と学習サポート
診断後は学校や地域にさまざまな支援制度が用意されています。
通級指導教室や特別支援学級、放課後等デイサービスなど、本人の課題や目標に合わせて選択できます。
またICTやアプリなどのデジタルツールや、家庭教師による個別サポートも有効です。
ここでは主な支援制度や学習サポートの特徴・選び方についてまとめます。
通級指導教室や特別支援学級など学校内支援制度
- 通級指導教室は苦手分野を個別に補う制度。
- 特別支援学級は少人数で手厚いサポート。
- 全国の中学校設置率は約30%(文科省調査)。
- 利用希望の場合は診断書や検査結果の申請が必要。
- 定期的な面談や支援内容の見直しも重要。
通級指導教室は、通常学級に在籍しつつ苦手分野(コミュニケーション・学習スキルなど)を個別に補う支援制度です。
曜日や教科が限定される場合が多いので、学校と相談しながら利用計画を立てましょう。
特別支援学級は、より手厚いサポートが必要な生徒向けに少人数で学べるクラスです。
中学校の設置率は全国平均で約30%(文科省2023調査)となっており、校種や地域により対応状況が異なります。
利用希望の場合は担任やカウンセラーに相談し、診断書や検査結果をもとに申請手続きを進めてください。
学校内の支援制度を利用することで、苦手のサポートと得意分野の伸長が両立できます。
利用開始後も定期的な面談や支援内容の見直しが重要です。
放課後等デイサービスの選び方と活用事例
- 放課後等デイサービスは生活・学習・社会性の支援が受けられる福祉サービス。
- 利用には障害児通所支援受給者証の申請が必要。
- 学習型・運動療育型などサービス内容は多様。
- 見学・体験利用で本人に合うか確認が重要。
- 口コミや福祉窓口も活用して選択。
放課後等デイサービスは、発達障害のある子どもが放課後や休日に生活・学習・社会性の支援を受けられる福祉サービスです。
利用には障害児通所支援受給者証が必要で、市区町村の福祉窓口で申請します。
2024年の厚生労働省ガイドラインでは、放課後等デイサービスは「生活能力向上」「学習支援」「社会適応」などの目的別に多様なプログラム提供が求められています。
学習支援型、運動療育型、社会性・自立型などサービス内容は様々なので、事前に見学や体験利用で本人に合うか確認することが重要です。
口コミや自治体の紹介も活用し、目的や将来目標に合わせて選択しましょう。
放課後等デイサービスを活用することで、社会性や自己肯定感の向上につながる事例も多数あります。
迷う場合は福祉窓口や相談支援専門員へご相談ください。
ICTやアプリなど中学生の発達障害に役立つ学習ツール
- ICTツールやアプリは学習・生活管理に有効。
- 「Classiホーム」「スタディプランナー」など国内でも普及。
- やることリスト・時間管理アプリ・読み書き補助アプリも活用可能。
- 視覚的にスケジュール管理やリマインドができる。
- 選定に迷ったら学校や家庭教師に相談。
ICTツールやアプリの活用は、発達障害のある中学生の学習や生活管理にとても効果的です。
国内でよく使われている例として、「Classiホーム」や「スタディプランナー」などが挙げられます。
「やることリスト」や「時間管理アプリ」「計算・読み書き補助アプリ」などを使うことで、課題管理や学習習慣づくり、忘れ物防止にも役立ちます。
タブレットやPCの活用で視覚的にスケジュールを管理したり、宿題提出のリマインドもできます。
学校や家庭教師と連携し、最適なツールを選んで学習の自立を支援しましょう。
デジタルツールの導入で本人のストレスを減らし、学びの幅を広げることができます。
導入や選定に迷う場合は、学校のICT担当や家庭教師サービスのサポートにも相談してみてください。
家庭学習の悩みに寄り添う中学生の発達障害対応型家庭教師サービス
発達障害のある中学生は、集団授業よりも一人ひとりに合わせた個別対応が効果的なことが多いです。
家庭教師サービスを活用することで、学習の遅れや不登校、やる気の低下など幅広い課題に柔軟に対応できます。
ここでは「家庭教師のランナー」をはじめとした、信頼できる家庭教師サービスの特長を比較し紹介します。
発達障害や不登校にも特化|家庭教師のランナーの特徴と強み

- 発達障害・不登校など多様なニーズに特化。
- オーダーメイドの指導プランを提案。
- 心理的ケアや学習習慣づくりもサポート。
- オンライン指導やICTツールの活用も可能。
- 月謝制・入会金・管理費あり。高額テキスト販売なし。
「家庭教師のランナー」は、発達障害や学習の遅れ、不登校など多様なニーズに対応した家庭教師サービスです。
お子さんの特性や状況に応じて、最適な指導プランをオーダーメイドで提案しています。
「勉強が苦手」「やる気が続かない」「集団になじめない」といった中学生にも、コミュニケーションを大切にした指導で自信や学習意欲の向上を目指します。
定期テスト対策や課題管理、受験準備まで幅広くサポート。
発達障害や不登校に詳しい専門スタッフが在籍し、心理的なケアや家庭での学習習慣づくりも相談できます。
オンライン指導にも対応し、ZoomやLINEなどのICTツールを活用した質問サポートも利用できます。
一人ひとりに合わせた指導で、保護者とともに安心して学習環境を整えられる点が大きな強みです。
指導内容やサポート範囲、料金体系の詳細は公式サイトや無料相談でご確認ください。
大手安心|家庭教師のトライの発達障害中学生向けサポート

- 大手家庭教師サービスで全国対応。
- 専任教育プランナーが家庭と教師をつなぐ。
- 個々の学力や特性に合わせて柔軟に指導。
- 反復学習や苦手克服プログラムも充実。
- オンライン指導や教師交代サポートも無料。
家庭教師のトライは、全国に多くの登録教師を持つ大手サービスです。
専任教育プランナーが家庭と教師をつなぎ、相性や特性を重視したマンツーマン指導を実施しています。
発達障害のある中学生にも、個々の学力や目標に応じてカリキュラムを柔軟に作成。
「トライ式学習法」による反復学習や苦手克服プログラムも評価されています。
オンライン指導は専用システムを利用し、自宅でも高品質な授業が受けられます。
教師交代が無料でできるサポート体制も強みです。
信頼と安心のサポートで、発達障害があるご家庭にも高い満足度が評価されています。
料金やコース内容は地域や学年によって異なるため、無料相談や体験授業を積極的に活用してください。
教育大手|学研の家庭教師の発達障害対応と事例

- 教育グループならではの安心感と多様な講師陣。
- 特性や学年・目標に合わせた厳選教師を紹介。
- オンライン指導も対応、首都圏を中心に広いエリア。
- 保護者・教師・本部が連携して進路や生活面もサポート。
- 個別の課題に寄り添った指導で自信を育む。
学研の家庭教師は、教育グループならではの安心感と多様な講師陣が特長です。
発達障害の特性や学年・目標に合わせて、厳選された教師を紹介します。
首都圏を中心に広いエリアで対応し、オンライン指導も利用可能です。
学習障害や注意欠如など、個別の課題に応じたカリキュラムで自信を育みます。
保護者・教師・本部が連携したフォロー体制で、進路や生活面の相談も可能です。
教育の専門家が“親子二人三脚”で寄り添い、長期的な成長を支援します。
初めての方でも安心して利用を始められます。
上場企業運営|家庭教師のサクシードの発達障害サポート体制

- 上場企業が運営する全国対応の家庭教師サービス。
- 小学生から高校生まで幅広く対応可能。
- 月謝制・明朗な料金体系、入会金や教材費不要。
- オンライン・訪問指導どちらも対応。
- 保護者・生徒の相談にも丁寧に対応。
家庭教師のサクシードは上場企業が運営する全国対応の家庭教師サービスです。
発達障害のある中学生向けに柔軟なカリキュラムを設計し、小学生から高校生まで対応可能。
月謝制・明朗な料金体系で、入会金や教材費は不要です。
オンライン・訪問指導どちらにも対応し、複数科目の同時指導も可能。
教務スタッフと担当教師が連携し、保護者や生徒の相談にも丁寧に対応しています。
上場企業ならではの安心感とコストパフォーマンスの高さで、継続しやすいサポートを実現しています。
まずは体験授業から利用を始めてみてください。
専門正社員指導|家庭教師ジャンプの発達障害対応の特長

- 発達障害や不登校専門で正社員教師のみを派遣。
- 検査結果や特性に基づいた個別指導。
- 社会性や自己肯定感の向上にも注力。
- 初回家庭訪問やオンライン体験指導も実施。
- 学校や福祉機関とも連携を強化。
家庭教師ジャンプは、発達障害や不登校の生徒専門で正社員教師のみを派遣するサービスです。
WISC等の検査結果や特性をもとに個別に指導し、社会性や自己肯定感の向上にも注力しています。
初回の家庭訪問やオンライン体験指導も用意されており、保護者の不安にも丁寧に寄り添います。
首都圏・静岡・群馬・埼玉など幅広く対応し、学校や福祉機関とも連携を強化しています。
発達障害に真摯に向き合い、長期的なサポートを求めるご家庭に適したサービスです。
担当教師と本部が連携し、きめ細やかな支援を続けます。
リーズナブル|家庭教師ファーストの発達障害中学生サポート

- 全国対応・低価格の家庭教師サービス。
- 入会金なし・手持ち教材対応・無料体験あり。
- 発達障害や学習障害にも多数の指導実績。
- オンライン・訪問どちらも選択可能。
- 定期フォローや保護者相談も充実。
家庭教師ファーストは全国対応の低価格サービスとして知られています。
担当教師による無料体験、入会金なし、手持ち教材への対応が可能です。
発達障害や学習障害、不登校の生徒にも多くの指導実績があり、個別カリキュラムで柔軟に対応しています。
オンライン・訪問指導の両方で「分からない」を丁寧にフォロー。
本部スタッフによる定期フォローや保護者相談も充実しています。
リーズナブルな料金と手厚いサポートが、長期的な家庭学習を支えます。
まずは無料体験でサービスの雰囲気を確認してみましょう。
地域密着|家庭教師のノーバスの中学生発達障害対応

- 関東・東海地方中心の地域密着型サービス。
- 経験豊富な教師と個別指導塾のノウハウ。
- 市販教材・手持ち教材で柔軟対応。
- 本部と担当教師の二重サポート体制。
- 地域の安心感が高評価。
家庭教師のノーバスは、関東や東海地方で地域密着型の指導を展開しています。
指導経験豊富な教師陣と、個別指導塾で培ったノウハウを活かし、発達障害・学習障害の生徒にも適切な指導法を提供します。
市販教材や手持ち教材を使い、学習状況に合わせてカリキュラムを調整可能。
本部と担当教師が二重でサポートし、定期面談や学習プランの見直しも細やかです。
難関校受験や定期テスト対策にも対応し、「地域の安心感」が高く評価されています。
地域に根差したサポートと情報で、一人ひとりに寄り添う指導が実現できます。
相談は最寄りの教務拠点から可能です。
勉強が苦手な子専門|家庭教師のあすなろの発達障害サポート
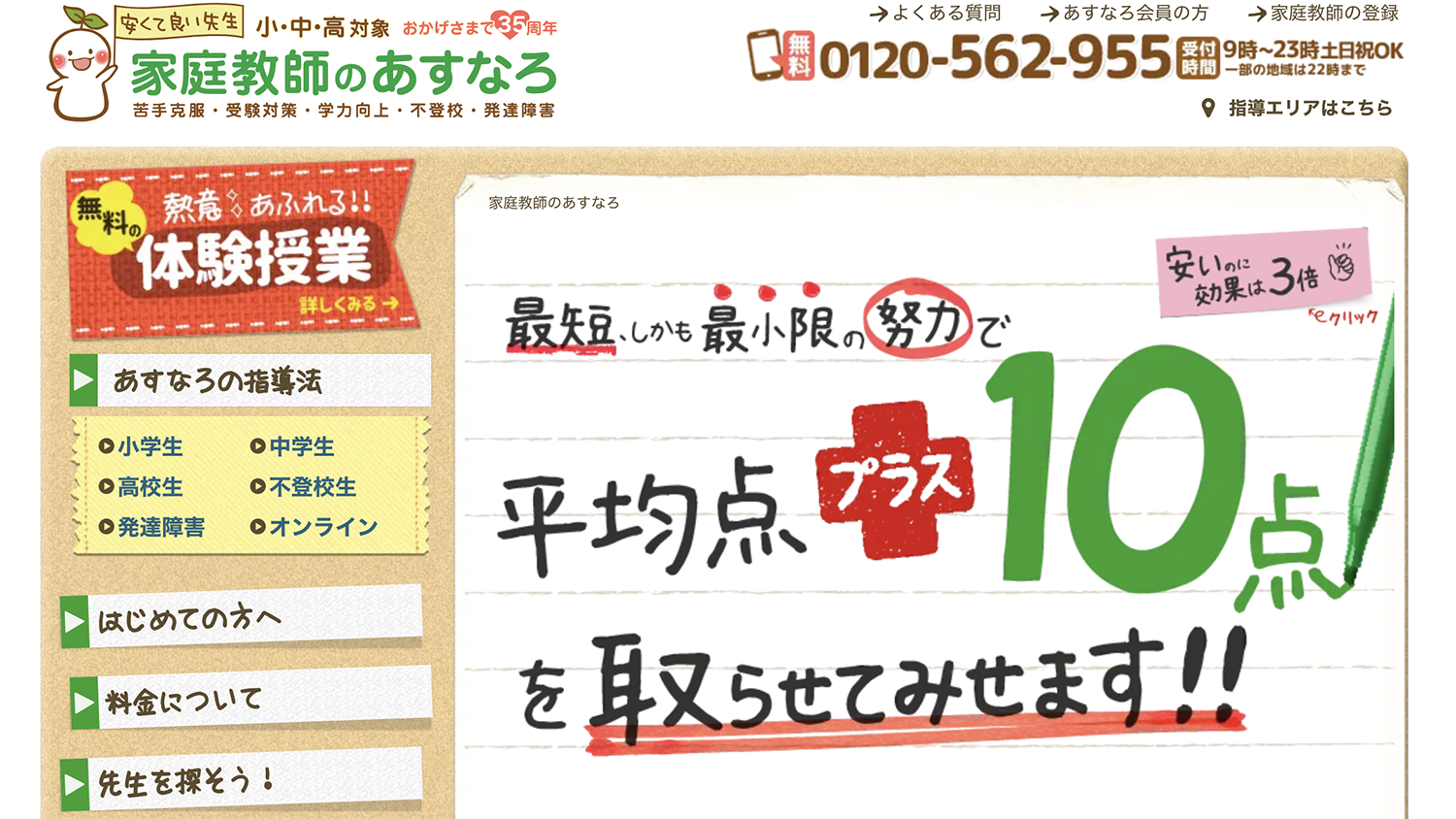
- 「勉強が苦手な子専門」を掲げたリーズナブルなサービス。
- 大学生教師中心で親しみやすい指導。
- LINEでの質問サポートや無料体験授業。
- 地方でもオンラインで全国同一水準のサポート。
- 「分からない」をすぐ解決できる体制。
家庭教師のあすなろは「勉強が苦手な子専門」を掲げたリーズナブルなサービスです。
若い大学生教師が中心で、発達障害や学習障害の子どもにも親しみやすい指導を行います。
LINEでの質問サポートや無料体験授業、保護者サポートも充実。
地方でもオンラインで同じ水準のサービスを受けることができます。
「分からない」をその場で解決し、やる気アップを目指せる体制が整っています。
無料体験から安心してスタートできます。
プロ教師専門|家庭教師 学参の発達障害中学生対応力

- プロ家庭教師専門で40年以上の実績。
- 難関校受験から発達障害・不登校まで幅広く対応。
- 授業回数や内容の調整、進路相談も柔軟。
- 全国500か所以上の教室とオンライン指導。
- 無料相談で疑問や不安を解消。
家庭教師 学参は、プロ家庭教師専門の紹介センターとして40年以上の実績があります。
指導経験豊富なプロが、難関校受験から発達障害・不登校対応まで幅広くサポート。
授業回数や内容の調整、進路や学習相談など柔軟なフォローが特徴です。
全国500か所の教室やオンライン指導も利用でき、多様なニーズに対応しています。
プロならではの指導力と柔軟な対応で、一人ひとりの個性や課題に向き合う学習支援が可能です。
まずは無料相談で疑問や不安を解消してみてください。
診断後の中学生と家族のメンタルケア・相談窓口
発達障害の診断後は、本人だけでなく家族全体のメンタルケアがとても重要です。
「なぜうちの子だけが」と自責や孤立感に悩む保護者も多いため、カウンセリングや保護者同士のピアサポートを積極的に活用しましょう。
思春期の子どもとどう向き合うか悩んだとき、専門機関や体験談の活用も大きな助けになります。
この章では家族の心のケアや代表的な相談窓口、体験談の活用方法を紹介します。
親の心理的負担を軽減するカウンセリング・ピアサポート活用
- 診断後は親の罪悪感や不安を抱きやすい。
- 自治体や学校のカウンセリング、NPO等の親の会を活用。
- 東京都発達障害者支援センター(TOSCA)など公的窓口も利用可能。
- ピアサポートで同じ経験の親と交流できる。
- 家族全体のメンタルケアも大切。
診断が出ると、親御さんは「自分のせいでは」と罪悪感や不安を抱きやすくなります。
そうした思いを一人で抱えず、自治体や学校のカウンセリング、NPO等の「親の会(ピアサポート)」を利用しましょう。
たとえば東京都発達障害者支援センター(TOSCA)などの公的窓口では、情報提供や専門家による相談も可能です。
同じ経験をした保護者同士で話すことで、「うちだけじゃない」と気持ちが和らぐことも多いです。
カウンセラーには具体的な支援策や家庭での対応のコツも相談できます。
家族のメンタルケアも大切な支援のひとつです。安心して相談できる場づくりを意識しましょう。
無理せず家族で前を向いて進めるよう、定期的にサポートを受けてください。
子どもの同意を得る思春期のコミュニケーション術
- 思春期は自立心・プライバシー意識が高まる。
- 本人の気持ち・同意を大切にした声かけが重要。
- 第三者を交えて話すのも有効。
- 共感と尊重を意識し、急がず信頼関係を築く。
- 子どものペースを大事にサポートを続ける。
思春期の中学生は自立心やプライバシー意識が強くなります。
診断や支援を進める際も、本人の気持ちや同意を大切にしましょう。
「こうしなさい」ではなく、「どう思う?」「一緒に考えよう」と声かけをし、決めつけや否定を避けることが大切です。
時には第三者(カウンセラーや信頼できる先生)を交えて話すことで、本人も自分の考えを言葉にしやすくなります。
思春期の子どもとの対話は“共感と尊重”が基本です。急がず、信頼関係をゆっくり築いていきましょう。
子どものペースを尊重し、サポートを続けてください。
同年代の保護者体験談やコミュニティ活用のすすめ
- 保護者の体験談やコミュニティで孤独感や不安を軽減。
- 自治体・支援センター・SNS等で保護者会やピアサポートを探す。
- リアルな声や実体験から“明日できるヒント”が得られる。
- オンラインサロンや相談イベントも増加中。
- 家庭や本人の状況に合わせて無理なく活用。
同じ悩みを抱える保護者の体験談やコミュニティは、孤独感の軽減や実践的なヒントが得られる場です。
自治体・支援センター・SNS・掲示板などで「発達障害 中学生 保護者会」や「ピアサポートグループ」などを探してみましょう。
リアルな声や実体験を知ることで「完璧じゃなくていい」と肩の力が抜けるきっかけにもなります。
オンラインのサロンや相談イベントも増えているので、無理のない範囲で参加してみてください。
体験談やコミュニティの力を借りて、“明日からできること”を一歩ずつ実践しましょう。
すべての情報を取り入れる必要はなく、ご家庭や本人の状況に合わせて活用するのがポイントです。
中学生の発達障害診断と支援まとめ
- 中学生期は発達障害の特性が明らかになりやすい時期。
- 診断は「支援につなげるためのパスポート」として活用。
- 診断の流れや医療機関の選び方、行動観察・家庭学習の工夫が重要。
- 診断後は学校・家庭・地域・専門家と連携し柔軟なサポートを。
- 家庭教師やICTツール、メンタルケアの場も成長支援の要素。
- 「一人で抱え込まない」ことが長期的な成長につながる。
中学生期は発達障害の特性が明らかになりやすい時期です。
適切な診断はレッテルではなく、「支援につなげるためのパスポート」となり、お子さんの可能性を広げます。
診断の流れや医療機関の選び方、家庭や学校での記録・観察の工夫、診断後の進路選択や家庭教師サービスの活用など、信頼できる情報と支援策を知ることが安心の第一歩です。
診断後は家族・学校・地域の専門家と連携し、個性や強みに合わせたサポートを柔軟に進めましょう。
家庭教師やICTツール、メンタルケアの場づくりも成長支援の大切な要素です。
「一人で抱え込まない」「親も子も前向きに相談できる場所を持つ」ことが長い目で見た成長につながります。
本記事が、ご家庭の不安や迷いを少しでも解消し、お子さんのよりよい未来への一歩となれば幸いです。
今できることから始めて、安心して次のステップを踏み出してください。