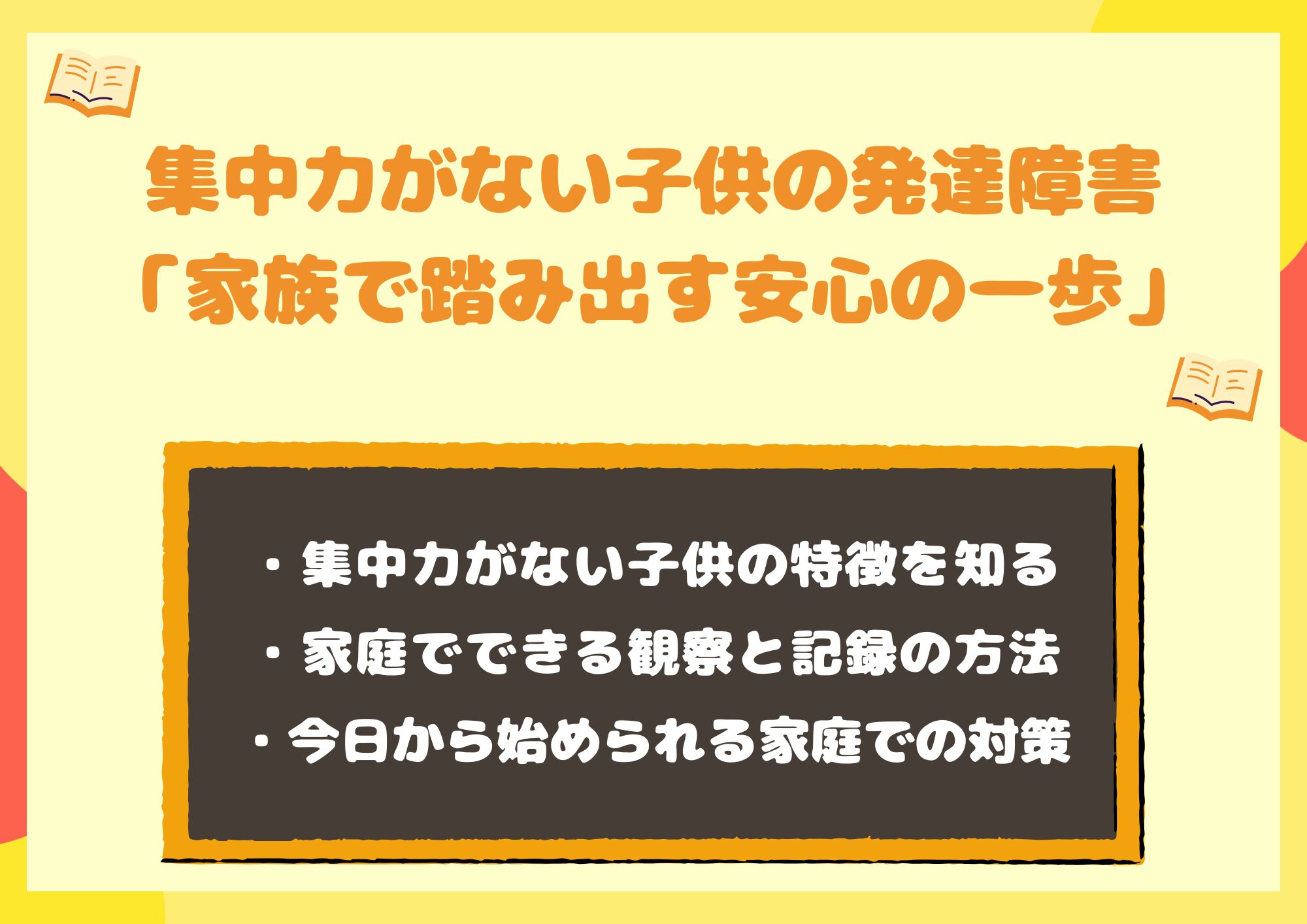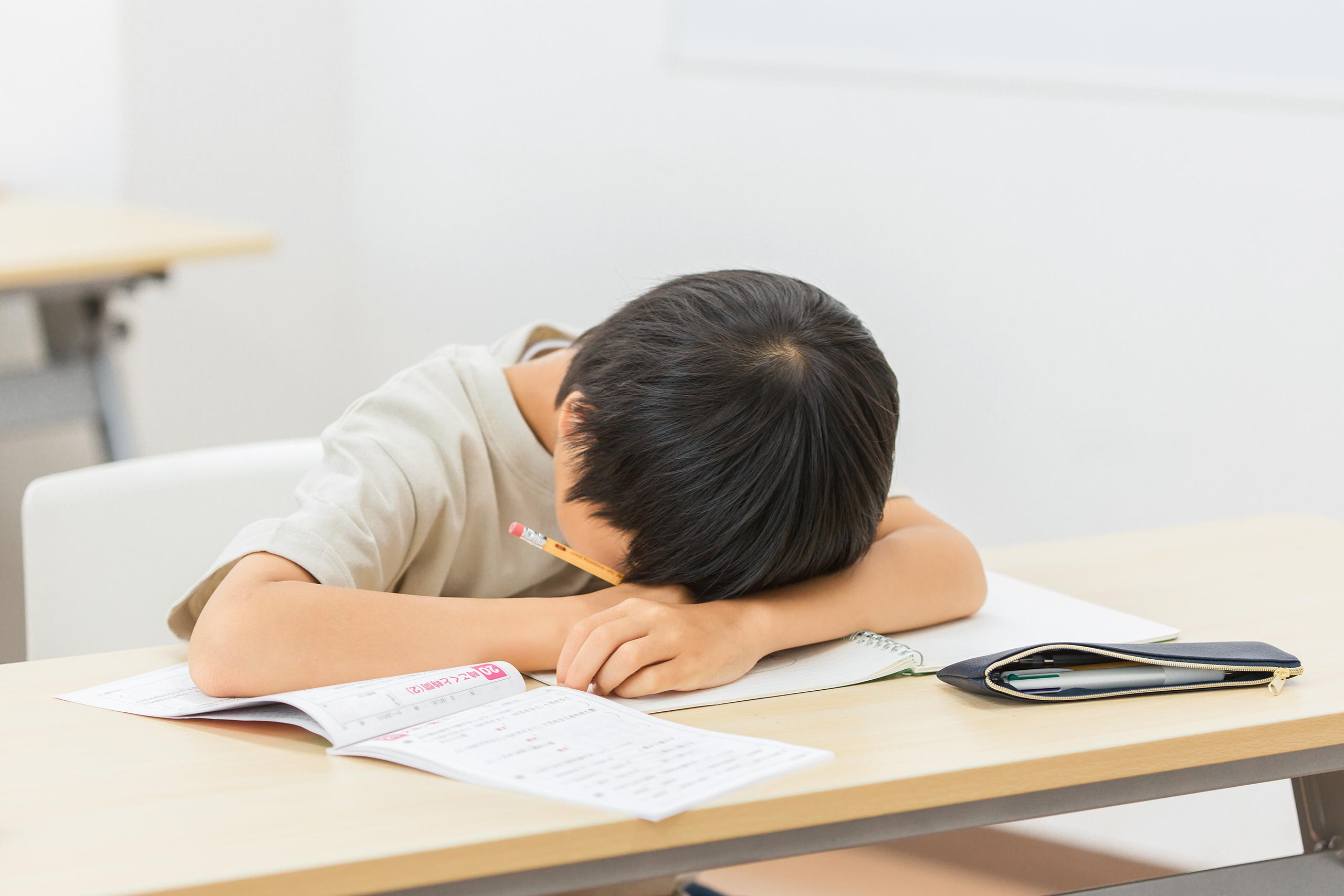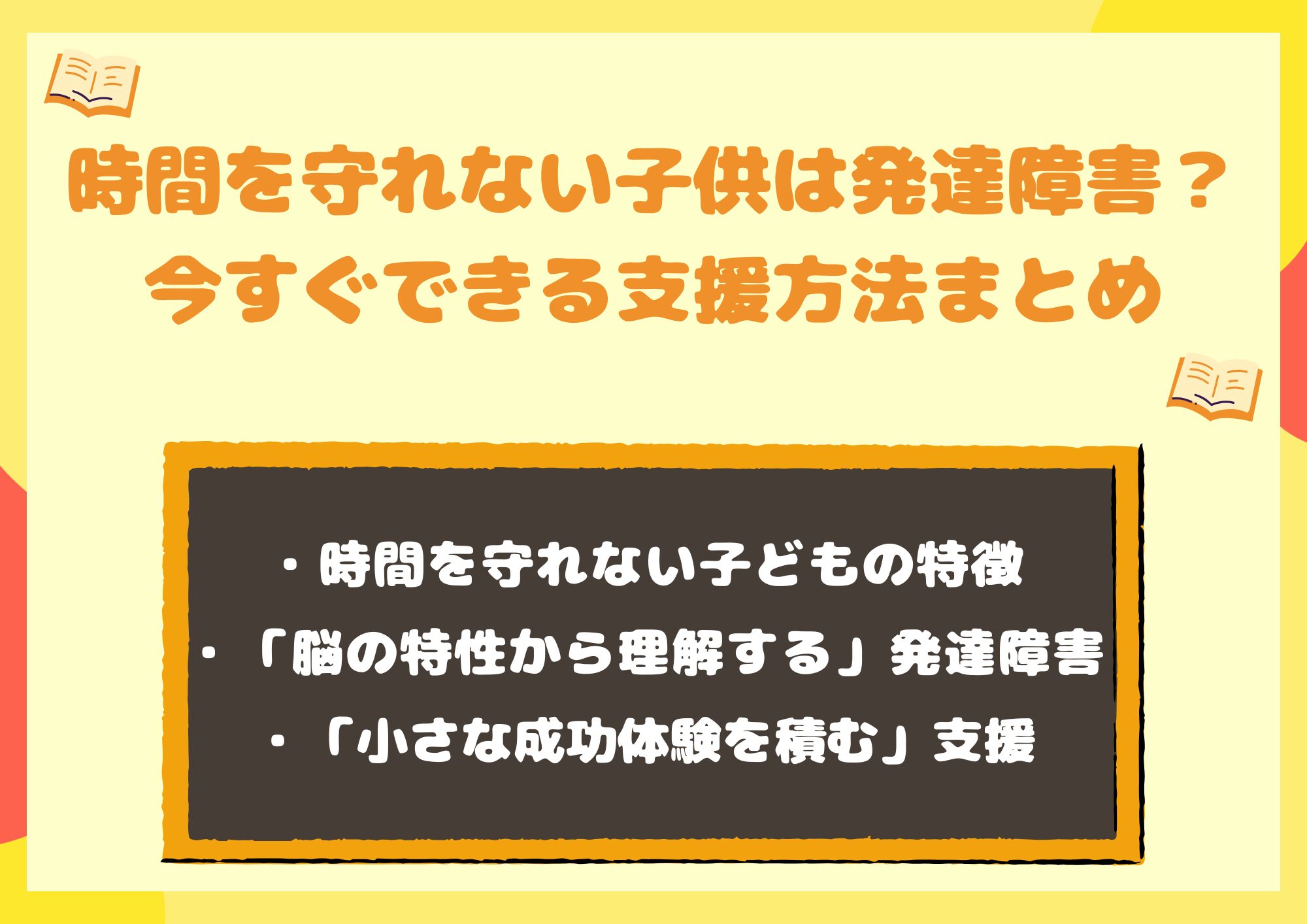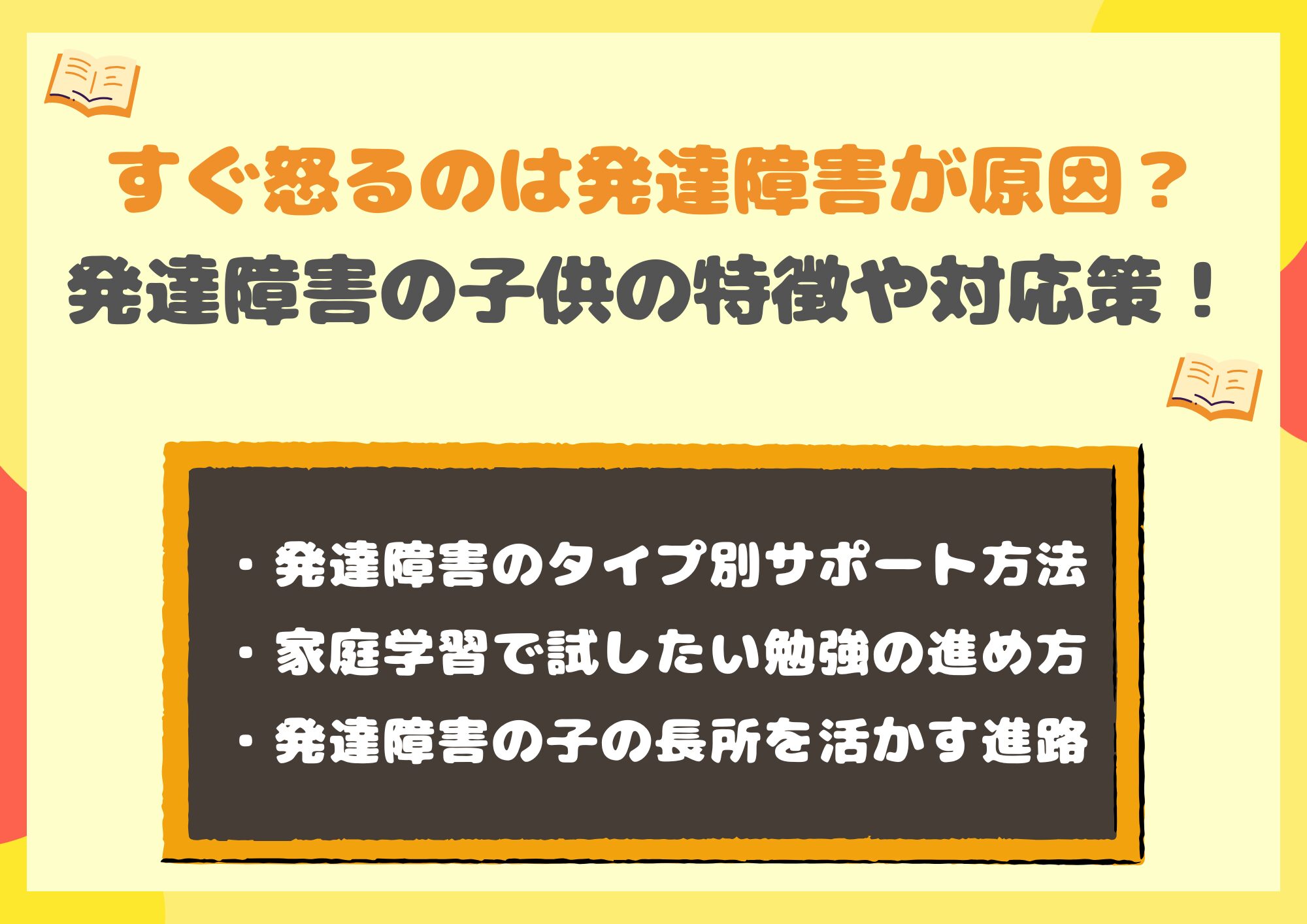- 発達障害向けの家庭教師
発達障害の子供が勉強についていけない時の親の対策と支援サービスを徹底解説
2025.07.18

発達障害の子供が学校の勉強についていけなくなった時、親はどのように向き合えばよいのでしょうか。
近年、発達障害のある子供が学習面でつまずくケースが増えており、「うちの子だけができないのでは」と悩む家庭も多くなっています。
学校や家庭で努力しても思うような成果が見えず、限界を感じてしまう親御さんも少なくありません。
しかし今では多様な支援策や専門サービスが整い、子供の特性を理解して寄り添うサポートが可能です。
子供の特性を理解し、適切な支援を受けることで「できるようになった!」という実感を得ることができます。
この記事では、発達障害の子供が勉強についていけない時に家庭でできる工夫や、家庭教師サービスを含めた具体的な支援策を徹底解説します。
ランナーの無料体験はこちら!目次
発達障害で勉強についていけない悩みが増える背景と現状
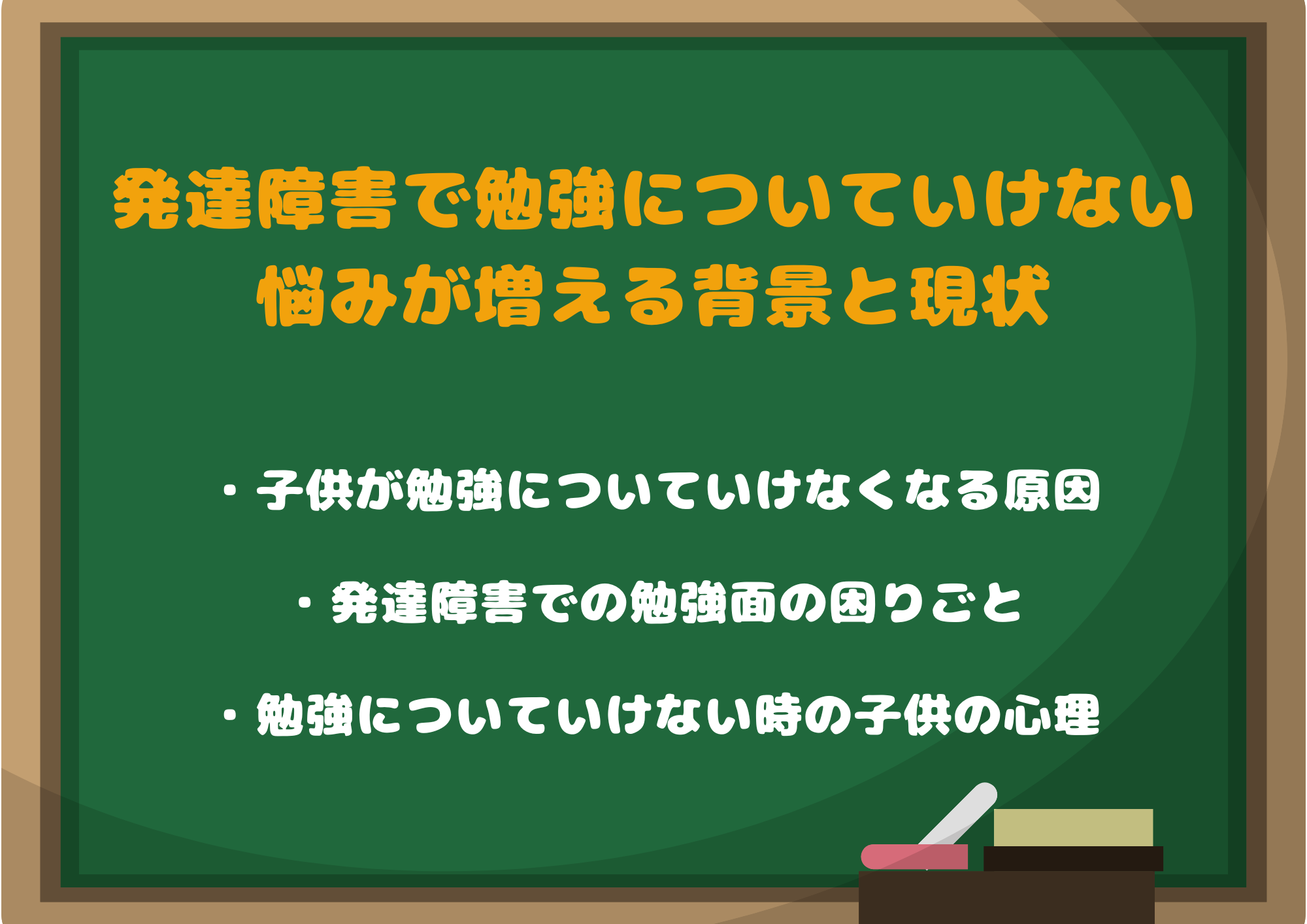
発達障害の子供が勉強についていけないと感じる家庭は年々増加傾向にあります。
文部科学省の2022年調査によると、通常学級に在籍する発達障害の可能性がある児童生徒は、担任等の回答による推計で全体の8.8%に上るとされています(正式な診断ではありません)。
従来よりも「特性への理解」や「サポート体制の充実」が求められていますが、まだ十分とは言えない状況です。
親や教師が努力しても結果が出ない、家庭学習が成り立たないといった悩みも深刻化しています。
学校と家庭だけで解決できず、社会全体で支えることが重要になっています。
子供が勉強についていけないのは「本人の努力不足」ではありません。
特性に合った支援を受けることで、着実に学びを進めることができます。
発達障害の子供が勉強についていけなくなる主な原因
- ASD・ADHD・LDなど特性による影響が大きい
- 集団生活や自己肯定感の低下で意欲が下がる
- 早期の特性理解と支援が重要
発達障害の子供が学習についていけなくなる背景にはさまざまな要因があります。
ASD(自閉スペクトラム症)は教科書の抽象的な説明が理解しにくい、ADHD(注意欠如・多動症)は集中力が持続せず課題に取り組みにくい、LD(学習障害)は読む・書く・計算など特定分野に強い苦手意識がある、など特性ごとの影響があります。
また、集団生活のストレスや自己肯定感の低下が学習意欲の減退につながるケースもあります。
「自分だけできない」と感じる気持ちが重なることで、さらに勉強から距離を置いてしまいます。
早めに特性を理解し、適切な対応をすることがとても大切です。
学校や家庭でよく見られる発達障害での勉強面の困りごと
- 板書が遅い・指示を覚えられない・忘れ物が多い
- 学習習慣が定着しにくい
- ストレスを溜めやすいので支援体制が重要
発達障害の子供が直面しやすい勉強面での困りごとには共通点があります。
例えば板書を写すのが極端に遅い、指示を一度に覚えられない、宿題や提出物を忘れやすいなど学習活動自体に難しさが出やすいです。
また、集団授業のスピードについていけなかったり学習習慣が定着しにくいことも多く、親子ともにストレスが溜まりやすくなります。
困りごとを責めず、特性に合わせた支援体制を整えることが最も大切です。
「勉強についていけない」と感じた時の子供と親の心理
- 子供は劣等感・無力感を抱きやすい
- 親も自分を責めがちで悪循環になる
- 少しの成長や努力に目を向けることが大切
子供は「自分だけできない」と感じて劣等感や無力感を抱きやすくなります。
小さなミスが続くことで自己肯定感を失い、やる気の低下や不登校の傾向につながる場合もあります。
親も「なぜできないのだろう」「教え方が悪いのか」と自分を責めてしまうことが多いです。
家庭内で緊張が高まり、親子の余裕がなくなる悪循環に陥りがちです。
焦るよりも、「頑張っていること」「少しでも前に進んだこと」に目を向けてあげましょう。
適切な支援や第三者のサポートを利用することで、親子の心の余裕を保てます。
発達障害のタイプ別|勉強についていけない時の特徴とサポート方法
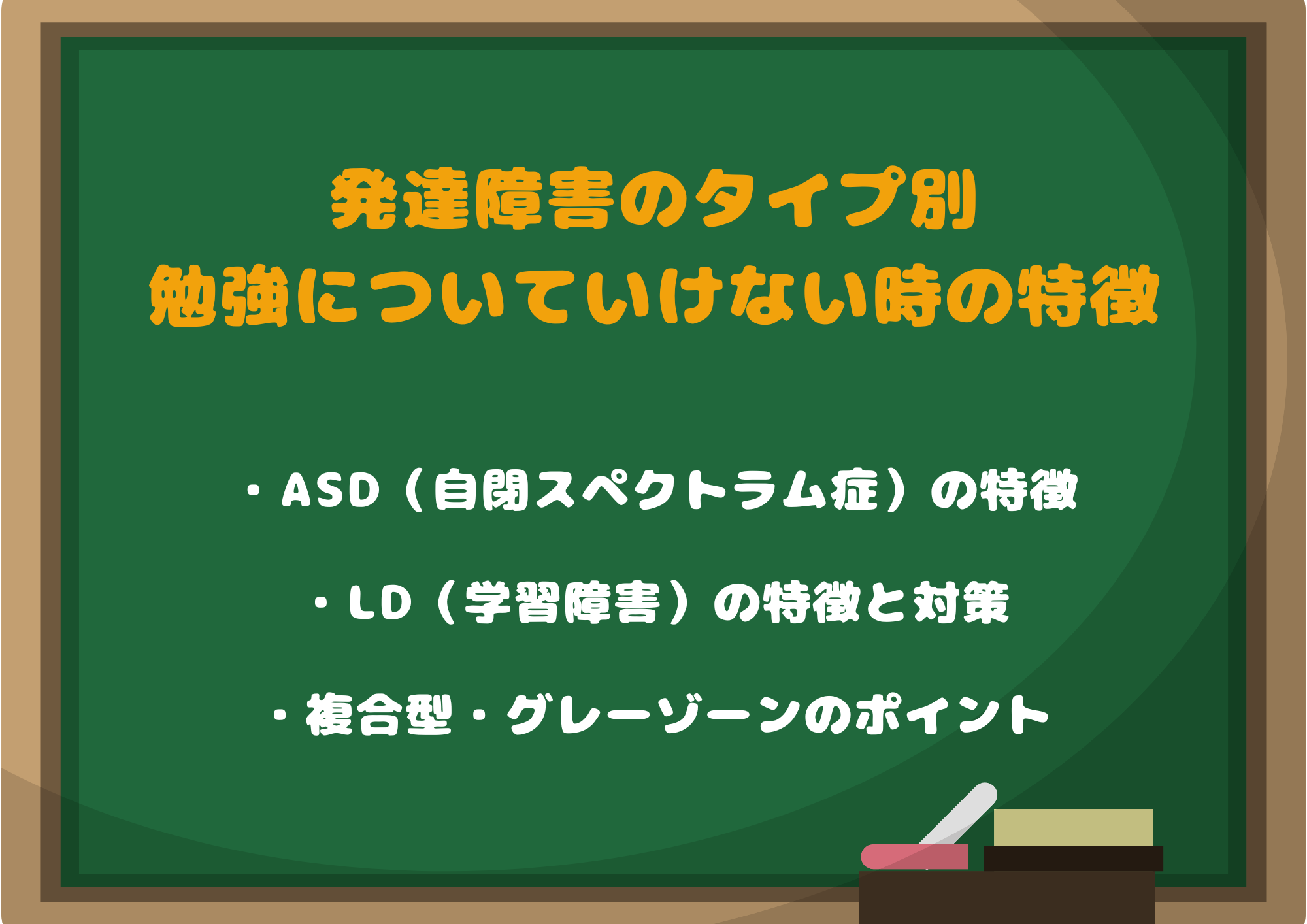
発達障害といっても、その特性や困りごとはさまざまです。
「うちの子のタイプは?」と迷う方も多いですが、タイプ別の特徴や対策を知ることでより具体的な支援方法が見つかります。
ASD、ADHD、LD、複合型やグレーゾーンなど、子供の特性に合わせて支援方法を選ぶことが大切です。
特性ごとに合った支援を行うことで、子供の「できる!」を引き出せます。
ASD(自閉スペクトラム症)の子供が勉強についていけない特徴と対策
- 予定変更や曖昧な指示が苦手
- 視覚的・具体的な教材や手順が有効
- 見通しの持てるスケジュールを意識
ASDの子供は急な予定変更が苦手、曖昧な指示が理解しづらい、興味のない教科に極端に取り組まないなど学習上の課題が目立ちます。
細部へのこだわりやマイルールが強く、集団授業に馴染みにくいことも多いです。
具体的かつ視覚的な教材を使い、ステップごとに分けて伝える工夫が効果的です。
得意なことを伸ばしつつ、苦手な場面は「できる手順」を明確にしてあげることが重要です。
予測できるスケジュールや見通しの持てる支援がASDの子供には適しています。
ADHD(注意欠如・多動症)の子供が勉強についていけない特徴と対策
- 注意が散りやすい・ミスが多い
- 短時間区切り・アクティビティ型学習が効果的
- ToDoリスト・タイマーの活用が有効
ADHDの子供は注意が散りやすい、ケアレスミスが多い、じっとしているのが苦手など集中力の維持が難しい傾向があります。
短時間ごとに区切って休憩を入れたり、身体を動かしながら学ぶアクティビティ型の学習方法が効果的です。
ToDoリストやタイマーを活用して進行を見える化することも有効です。
前向きな声かけとできたことを褒めてあげることが、自信につながります。
無理に長時間座らせず、「短く集中」「すぐフィードバック」を意識しましょう。
LD(学習障害)の子供が勉強についていけない特徴と対策
- 「読み書き」「計算」など分野ごとの苦手が顕著
- 支援ツールやICT教材でハードルを下げる
- 学校や専門機関と連携し合理的配慮も検討
LDの子供は「読み書き」「計算」など特定分野で苦手さが現れますが、他の領域では問題がない場合も多いです。
黒板の字を写せない、文章題が極端に苦手、など個別のつまずきポイントが顕著です。
「できること」と「苦手なこと」を明確に分け、不得意な分野には支援ツールやICT教材を使ってハードルを下げましょう。
苦手な部分を責めず、成功体験を積み重ねることが「できる」領域の拡大につながります。
必要に応じて学校や専門機関に相談し、合理的配慮も検討しましょう。
複合型・グレーゾーンの発達障害で勉強についていけない時のポイント
- 複数の特性が重なる困りごとが増加傾向
- 型にはめず無理しない環境づくりが重要
- 家庭・学校・外部支援の組み合わせが有効
ASDやADHD、LDの特性が複数現れる複合型や、診断に至らないグレーゾーンの子供も増えています。
一人ひとり異なる困りごとがあり、通常支援だけでは対応しきれない場合もあります。
型にはめず、親子ともに無理をしない環境づくりが大切です。
家庭・学校・外部支援をバランスよく組み合わせることが、子供の可能性を広げる第一歩です。
本人のペースを大切にし、少しずつ成功体験を積み上げましょう。
発達障害で勉強についていけない時に家庭でできる工夫と支援
発達障害の子供が学習につまずいた時、家庭での対応を工夫することで子供の自信や学習意欲を引き出せます。
学校の授業だけで十分な成果が出なくても、親のちょっとしたサポートや学習環境の見直しが大きな効果を生みます。
「うまくいかない」と悩んでいる方こそ、毎日の小さな変化を大切にしてください。
家族でできる具体的な工夫を積み重ねることが、子供の「できた!」という成功体験につながります。
家庭学習で試したい勉強の進め方・声かけの工夫
- 小さな目標設定・できたことを褒める
- 短く・順番に伝える声かけを意識
- ご褒美や休憩も効果的に使う
勉強についていけないと感じた時は、まず「できたこと」に注目して小さな目標を設定してあげましょう。
いきなり完璧を求めず、1日5分から始める、1問だけ解くなどハードルを下げることが大切です。
声かけも「なぜできないの?」ではなく、「今日ここまでできたね!」「前より速く終わったね」など、具体的に褒めることを意識しましょう。
指示や説明は短く、1つずつ順番に伝えると理解度が上がります。
「少しずつできた」を積み重ねることが、勉強の自信回復につながります。
ご褒美や休憩も取り入れて、楽しい家庭学習時間を目指してください。
家庭でできる学習環境の整え方と集中しやすい工夫
- 机の上を整理し、必要なものだけに
- 静かな場所・壁をシンプルに
- タイマーでメリハリ・集中が切れたら休憩
発達障害の子供は外部刺激に敏感なことが多いため、学習スペースの工夫が重要です。
机の上を片付けて必要なものだけを置く、壁をシンプルにする、静かな場所を選ぶなどの配慮が集中力維持に役立ちます。
タイマーを使って「この時間だけは勉強する」と区切ることでメリハリのある学習ができます。
集中が途切れた時は無理に続けさせず、休憩を入れることも大切です。
子供が「集中しやすい」環境づくりは、親ができる大切なサポートの一つです。
「やる気が出ない」「続かない」ときの発達障害の子供への接し方
- 無理強いせず気持ちを受け止める
- 好きなこと・得意なことに注目
- 子供の選択肢や成功体験を大切に
どんな子供でも「やる気が出ない」「勉強が続かない」時期がありますが、発達障害の子供は特にそうした傾向が強く出ることがあります。
無理にやらせようとすると反発しやすく、親子関係も悪化しがちです。
まずは子供の気持ちを受け止め、「どうしたらやる気が出る?」と一緒に考える時間を持ちましょう。
勉強以外の得意分野や好きなことを話題にし、自信回復のきっかけを作ることも有効です。
子供自身の選択肢や成功体験を大切にすることで、自然とやる気を引き出せます。
親が勉強を教える時に気をつけたいポイント
- 「早くできるように」と焦らない
- できたこと・努力した過程を認める
- ミスや忘れ物も一緒に対策を考える
親が子供に勉強を教えるとき、「早くできるように」とつい急いでしまいがちです。
しかし焦りやイライラは子供に伝わり、「勉強=叱られるもの」と感じさせてしまいます。
大事なのは「できたこと」や「努力した過程」をしっかり認めることです。
ミスや忘れ物があっても否定せず、「次はどうしたらうまくいくか」を一緒に考えるようにしましょう。
親の声かけ一つで、子供の学習意欲や自己肯定感は大きく変わります。
発達障害で勉強についていけない悩みを相談できる専門機関・窓口
家庭内だけで悩みを抱え込む必要はありません。
発達障害の学習サポートや親の心のケアには、専門機関や相談窓口を積極的に利用しましょう。
学校や自治体、福祉センター、NPO法人など、子供と家族に寄り添う支援が整いつつあります。
専門家や外部の支援を活用することで、親も子供も「一人じゃない」と感じられます。
学校や支援級・通級指導教室を活用する方法
- まずは学校の支援体制を確認
- 支援級や通級教室の活用で無理なく学習
- 家庭と学校の連携が重要
まずは通っている学校のサポート体制を確認しましょう。
支援級や通級指導教室は、発達障害の子供が無理なく学習を進めるための専門的な環境を提供しています。
担任や特別支援コーディネーターに相談することで、学習の配慮や個別計画を作ってもらえる場合もあります。
合理的配慮や加配もお願いできるため、家庭と学校の連携が大切です。
学校だけで解決しきれない場合は、外部機関と併用して支援の幅を広げましょう。
発達障害者支援センター・自治体の相談窓口の利用方法
- 都道府県・市町村に支援センターあり
- 無料で専門スタッフに相談できる
- 制度や手続きも丁寧に案内
各都道府県や市町村には「発達障害者支援センター」や「子育て相談窓口」が設けられています。
無料で専門スタッフに相談でき、必要に応じて医療・教育・福祉機関への橋渡しも行っています。
「相談してもいいのかな?」と迷う時こそ、早めの相談が安心につながります。
制度の利用や手続きも丁寧に案内してもらえるため、初めての方でも心配いりません。
困った時は一人で抱え込まず、専門窓口を頼りにしてください。
医療機関・心理士への相談のすすめ
- 発達検査やカウンセリングが受けられる
- 専門家による具体的な対応策の提案
- 必要に応じて薬物療法やペアレントトレーニングも
学習だけでなく、子供の行動や感情面が気になる場合は医療機関や臨床心理士に相談するのも有効です。
発達検査やカウンセリングを通して、本人や家族に合った具体的な対応策を提案してもらえます。
薬物療法やペアレントトレーニングなど、専門的な支援が必要な場合もあるため、医師や心理士との連携も考えましょう。
専門家のアドバイスを受けることで、安心して次の一歩を踏み出せます。
地域の子育て支援団体やNPOとの連携方法
- 親同士の交流会やイベントが多数
- オンラインコミュニティで情報交換
- 孤独や不安の解消に役立つ
各地域には発達障害や子育てをサポートする団体・NPOが増えています。
同じ悩みを持つ親同士の交流会や専門家によるワークショップ、学習支援イベントなども多数あります。
オンラインコミュニティやLINEグループで情報交換する家庭も多いです。
「自分だけじゃない」と感じられる場を持つことで、気持ちが楽になります。
地域の団体やNPOとつながることで、孤独や不安を解消できます。
発達障害の子供が勉強についていけない時に利用できる家庭教師・学習支援サービス
家庭や学校だけでは十分なサポートが難しい時は、家庭教師や学習支援サービスの活用も選択肢に入れてみてください。
発達障害の特性を理解した専門家が、一人ひとりに合わせて学習支援を行うことで、「勉強ができない」「ついていけない」という悩みの根本的な解決が期待できます。
オンライン指導や低料金プランも増えているので、家庭のニーズや子供の状況に合わせて最適なサービスを選ぶことが大切です。
家庭教師や学習支援のプロに頼ることで、子供の学習意欲や自信を大きく伸ばすことが可能です。
家庭教師のランナー|発達障害・勉強が苦手な子供専門の個別サポート

- 22年以上の実績、発達障害・不登校に特化
- 個性に寄り添うオーダーメイド指導
- リーズナブルな月謝・兄弟同時指導割引あり
家庭教師のランナーは、「勉強が苦手な小中高生専門」の家庭教師グループとして22年以上の実績があります。
発達障害や不登校、学習遅れの子供にも特化したカウンセラーや指導者が在籍し、「子供の個性に寄り添うオーダーメイド指導」を徹底しています。
リーズナブルな月謝のみで高額テキスト販売も一切なく、兄弟・友人同時指導で2人目以降は半額になるなど家計にも優しい仕組みです。
全国どこでもオンライン指導に対応しており、約14万人の講師から最適な先生を選べる安心感があります。
反抗的・無気力な子供にも「わかる楽しさ」を実感できる工夫が豊富で、家庭での学習習慣づけや定期テスト対策にも柔軟に対応しています。
発達障害や勉強嫌いのお子様でも、自信とやる気を育める指導力が最大の特長です。
無料体験のお申込みも可能で、初めて家庭教師を利用するご家庭にも最適です。
ランナーの無料体験はこちら!家庭教師のトライ|オーダーメイド指導と充実のフォロー体制

- 業界最大手・全国33万人以上の教師
- トライ式学習法による個別最適化指導
- 教育プランナーによる手厚い進捗・相談対応
家庭教師のトライは、全国33万人以上の登録教師と30年以上の実績を持つ業界最大手のサービスです。
特に発達障害のある子供向けに「トライ式学習法」を活用したマンツーマン指導が特長で、個々の特性や苦手に合わせてオーダーメイドの学習計画を作成します。
専任の教育プランナーが家庭と教師の橋渡しを行い、進捗管理や相談対応も徹底したサポート体制を整えています。
オンライン指導にも対応し、地域を問わず高品質な個別指導を受けられるのも魅力です。
相性が合わない場合は何度でも無料で教師交代が可能なため、安心して継続できます。
発達障害の特性に配慮した柔軟なサポートが充実している家庭教師サービスです。
学研の家庭教師|大手ならではの安心感と発達障害への対応力

- 大手教育グループの安心感とノウハウ
- 発達障害対応の研修済み講師が担当
- 全国主要エリアで柔軟に対応可能
学研の家庭教師は、大手教育グループの信頼とノウハウを活かしたサービスです。
厳選された12万人超の教師が在籍し、発達障害の子供には専門研修を受けた講師が担当します。
学校や家庭との連携を重視し、一人ひとりに合った教材や学習プランで着実な成績アップをサポートしています。
オンライン指導や全国主要エリアへの対応も可能で、柔軟なサポート体制が魅力です。
大手ならではの安心感と、長年蓄積された指導実績が高評価を得ています。
家庭教師ファースト|低料金と発達障害支援の両立が魅力

- 全国展開・リーズナブルな料金
- 発達障害・勉強苦手にも柔軟対応
- 対面・オンライン・教師指名も可能
家庭教師ファーストは、全国展開の大手センターでありながら、リーズナブルな料金と手厚いサポートを両立しています。
発達障害や勉強が苦手な子供にも柔軟に対応し、無料体験や担当教師の指名も可能です。
対面・オンライン両方に対応しており、創業1993年の株式会社エムズグラント(未上場)が運営しています。
営業スタッフではなく担当教師が体験指導を行うため、子供もリラックスして学習をスタートできます。
「低価格×質の高い指導」を求めるご家庭に特におすすめのサービスです。
オンライン家庭教師Wam|全国対応・低料金で発達障害にも強い

- オンライン専業で低料金を実現
- 発達障害・不登校向けのコース充実
- 好きな時間・場所でマンツーマン指導
オンライン家庭教師Wamは、オンライン指導専業ならではの低料金と、発達障害に特化した高品質な個別指導が特長です。
独自開発の指導システムを活用し、東大生など難関大の先生が全国どこからでもマンツーマンで指導します。
「対面と変わらない分かりやすさ」と「好きな時間・場所で学べる自由度」が好評です。
発達障害や不登校の子供向けのコースもあり、忙しい家庭や通塾が難しい場合にも安心して利用できます。
手軽に高品質な個別指導を受けたいご家庭にぴったりのオンラインサービスです。
プロ家庭教師のジャンプ|発達障害・不登校対応の正社員プロ教師制

- 全教師が正社員のプロ家庭教師
- 発達障害・不登校・WISC対応に強い
- 無料カウンセリング・学習計画提案が充実
プロ家庭教師のジャンプは、発達障害や不登校生に特化した、正社員のみのプロ家庭教師センターです。
全教師が社員として雇用されており、豊富な経験と専門性に裏打ちされた安定した指導が受けられます。
WISC等の検査結果や個々の特性に合わせた指導法の研究にも注力しており、家庭と密な連携を図ります。
オンラインや対面での無料カウンセリング、学習計画提案などサポート体制も万全です。
「最後の砦」として信頼される、特別なニーズに強い家庭教師サービスです。
発達障害で勉強についていけない悩みで親が疲れた時のセルフケアと支援
子供の学習サポートが思うように進まないと、親自身も「もう限界」と感じてしまうことがあります。
つい自分を責めたり、周囲の目が気になって孤立感を深めてしまうことも少なくありません。
ですが、親が疲れ切ってしまう前に、セルフケアや外部の支援を上手に利用することがとても大切です。
親自身の心の余裕が、子供の成長を後押しする力となります。
「うんざり」「限界」と感じた時に親がまずできること
- まず「疲れている自分」を認める
- 無理せずリフレッシュする時間をつくる
- パートナーや家族、友人に気持ちを打ち明ける
頑張っても状況が変わらない時、「自分だけがダメなんだ」と思い込んでしまいがちです。
しかし、同じように悩んでいる親御さんは大勢います。
まずは「疲れている自分」を認めてあげることが大切です。
無理をせず、家事や仕事を少し休んでリフレッシュする時間を作りましょう。
時にはパートナーや家族、友人に気持ちを打ち明けるだけでも、心がぐっと楽になります。
自分を責めずに「まずは休む」ことも、立派な子育てです。
家族や周囲の理解を得るための伝え方・相談のコツ
- 子供の特性や困りごとを率直に伝える
- 「どうしてほしいか」を具体的に共有
- 支援者のアドバイスを冷静に伝える
発達障害の子供を育てるうえで、家族や周囲の無理解が一番のストレスになることもあります。
理解を深めてもらうには、子供の特性や具体的な困りごとを率直に伝えることがポイントです。
「こんな時にどうしてほしいのか」を具体的に伝え、時には医師や支援者のアドバイスを共有しましょう。
感情的にならず冷静に伝えることで、相手も協力しやすくなります。
また、地域の支援団体やピアサポートの場で他の親御さんの体験談を聞くことも有効です。
周囲と協力し合うことで、家庭全体がより良いサポート体制に変わります。
親自身のストレスを軽減する支援サービス・コミュニティ
- 行政やNPO主催の親の会が全国に多数
- SNS・オンラインサロンで交流も活発
- 悩みを共有できる場がリセットに役立つ
全国には、発達障害の子供を育てる親向けの支援サービスやコミュニティが数多くあります。
行政やNPO主催の親の会、SNSを通じたオンラインサロン、カウンセリングサービスなども活用しましょう。
誰かに悩みを共有できるだけで気持ちが安らぎ、「また明日も頑張ろう」と思えるはずです。
定期的にリセットできる場所を持つことで、ストレスが溜まりにくくなります。
「自分も大切にする」ことが、親子の幸せのために最も大切です。
発達障害の子供が勉強についていけない時の将来と進路選択の考え方
勉強についていけない現状に悩んでも、子供には必ずその子なりの「得意」や「強み」があります。
視野を広げて進路や将来の選択肢を探ることで、本人の自信や希望を引き出すことができます。
「学力」だけでなく、「好きなこと」「続けてきたこと」にも目を向けてください。
一人ひとりの個性や成長を尊重する進路選択が、子供の人生を豊かにします。
勉強が苦手な発達障害の子供の長所を活かす進路事例
- 手先の器用さや集中力など強みを活かす
- IT・福祉・専門職など多様な選択肢
- 好きなこと・得意なことを伸ばせる環境へ
勉強だけがすべてではありません。
手先の器用さや集中力、優れた記憶力、独創的な発想、得意なスポーツや芸術など、発達障害の子供には多様な強みがあります。
福祉職やクリエイティブ職、IT系、専門職など、個性を活かせる仕事や学校の選択肢も広がっています。
本人の好きなこと・得意なことを伸ばす進路を、家庭・学校・支援者と一緒にじっくり検討していきましょう。
進路選びの主役は子供自身であることを大切にしてください。
将来の選択肢と「自信」をつけるための家庭・学校の連携
- 家庭と学校が協力し「できた」を喜ぶ
- 達成感の積み重ねで選択肢が広がる
- 職業体験・就労支援なども活用
自信を持てない子供には、家庭と学校が協力して「できたこと」を一緒に喜ぶ環境づくりが大切です。
小さな達成感の積み重ねが、将来の選択肢を広げるきっかけになります。
学校の進路指導や職業体験、地域の支援団体の就労支援なども積極的に活用しましょう。
進路に迷った時は第三者の意見や、同じ経験をした先輩たちの話を聞くのも良い刺激になります。
「できることは必ずある」と信じて、子供の背中をそっと押してあげてください。
発達障害の子供のキャリア形成を支える社会資源
- ハローワーク・就労移行・特例子会社など活用
- 地域企業・NPOと連携した支援体制が充実
- 卒業後の自立を社会全体でサポート
発達障害の子供の進路や就職をサポートする社会資源も年々充実しています。
ハローワークの障害者雇用支援や就労移行支援、職業訓練校、特例子会社、地域ジョブコーチ制度など、専門機関の活用も選択肢に入れてください。
NPOや地域企業との連携により、安心して働ける環境づくりも進んでいます。
「卒業後の自立が不安」という声もありますが、社会全体で支援の輪が広がっています。
社会資源を上手に活用して、子供の自立やキャリアを力強く応援しましょう。
発達障害で勉強についていけない悩みについてまとめ
- ・月額の相場は2万円から6万円程度。
- ・家庭教師の種類や契約内容によって料金が変わる。
- ・費用内訳や条件を事前に確認し、適切な教師を選ぶことが大切。
発達障害の子供が勉強についていけない時、親も子供も「どうしたらいいのか」と悩むことがあるでしょう。
しかし、困難を感じているのは決してあなただけではありません。
それぞれの子供に合ったサポートや環境づくり、外部機関や専門家の力を借りることで、親子の負担や不安は大きく軽減できます。
家庭教師サービスをはじめとする学習支援や、行政・学校・地域の制度を活用することで、子供は少しずつ「できること」を増やしていけます。
そして、何より大切なのは、親自身が自分を責めすぎず、「できていること」に目を向けることです。
子供も親も一人で悩まず、多様な支援とつながりを活用して「次の一歩」を踏み出しましょう。
子供の未来には無限の可能性が広がっています。
迷った時は、支援サービスや仲間の声を頼りに、一歩ずつ前進してください。
ランナーの無料体験はこちら!