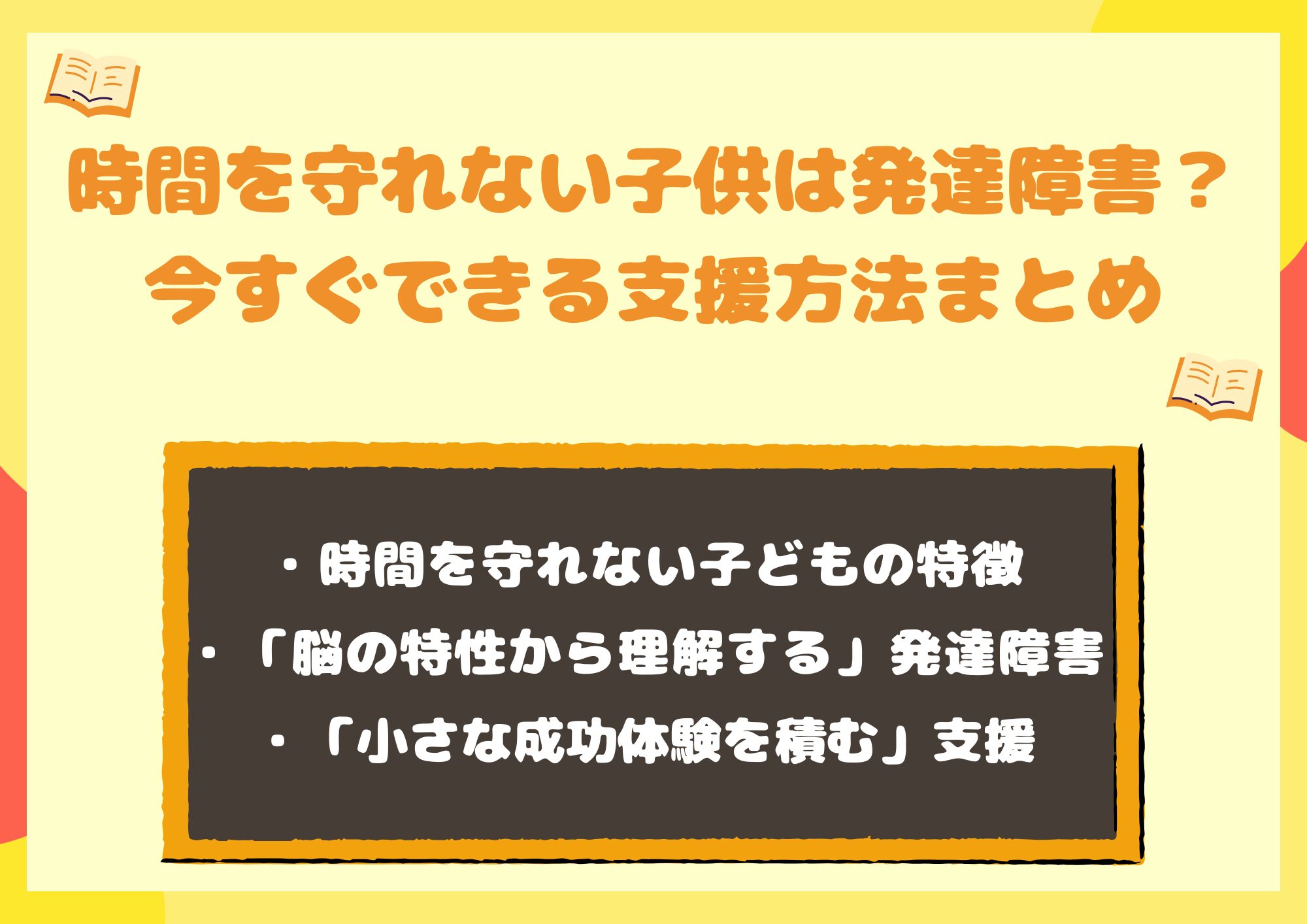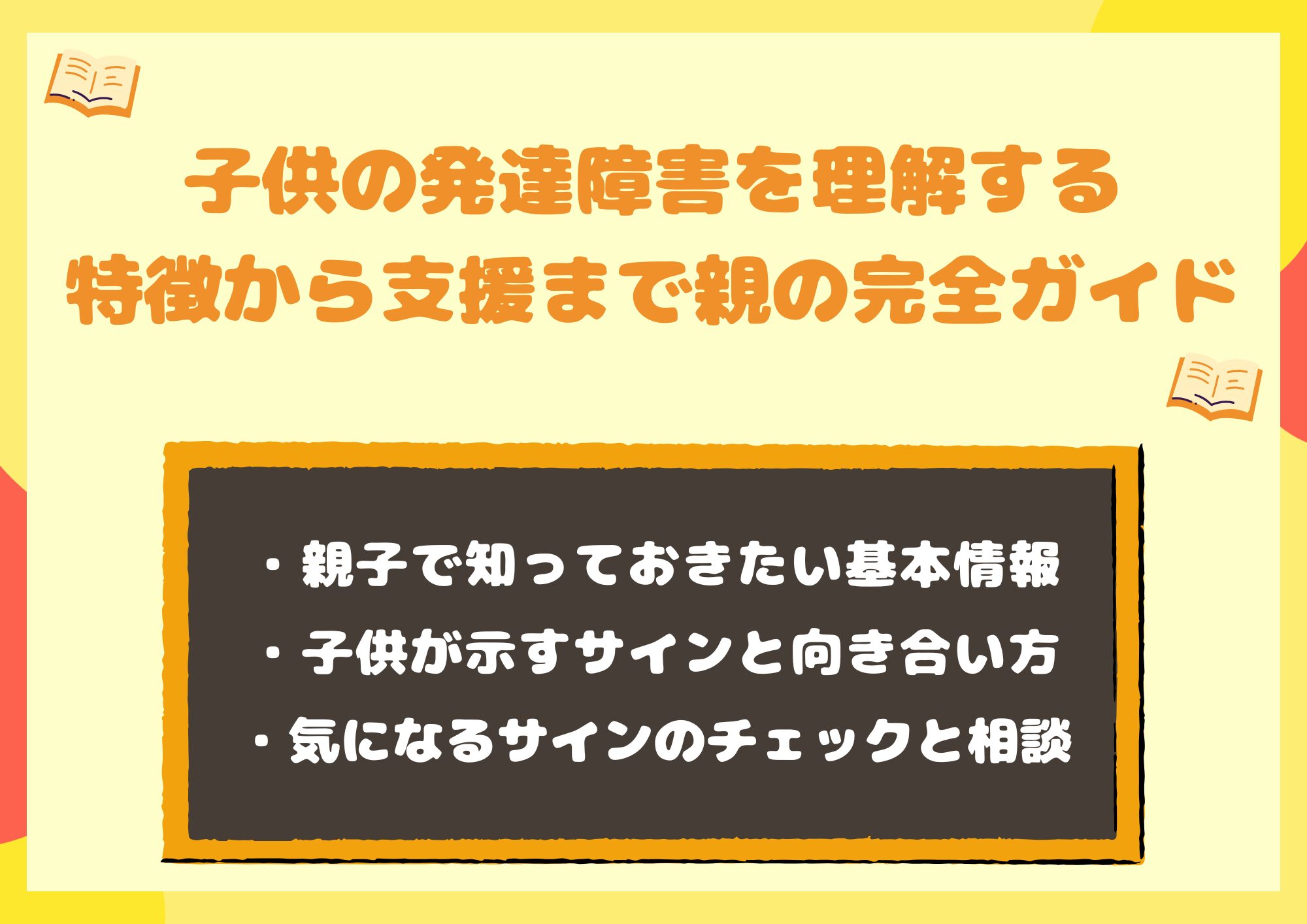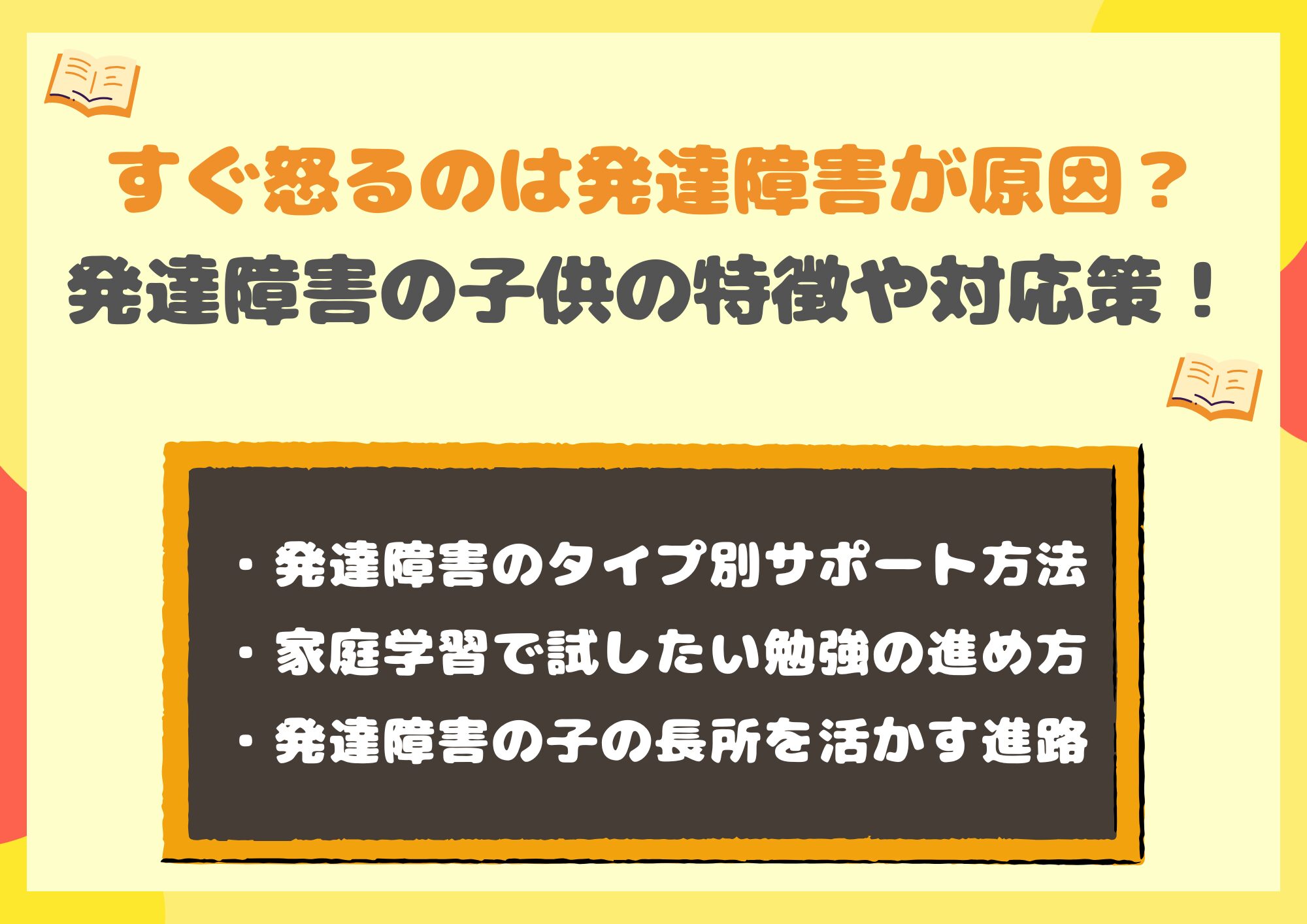- 発達障害向けの家庭教師
発達障害の子供から友達が離れていく時の対処法と改善ステップ!
2025.09.30
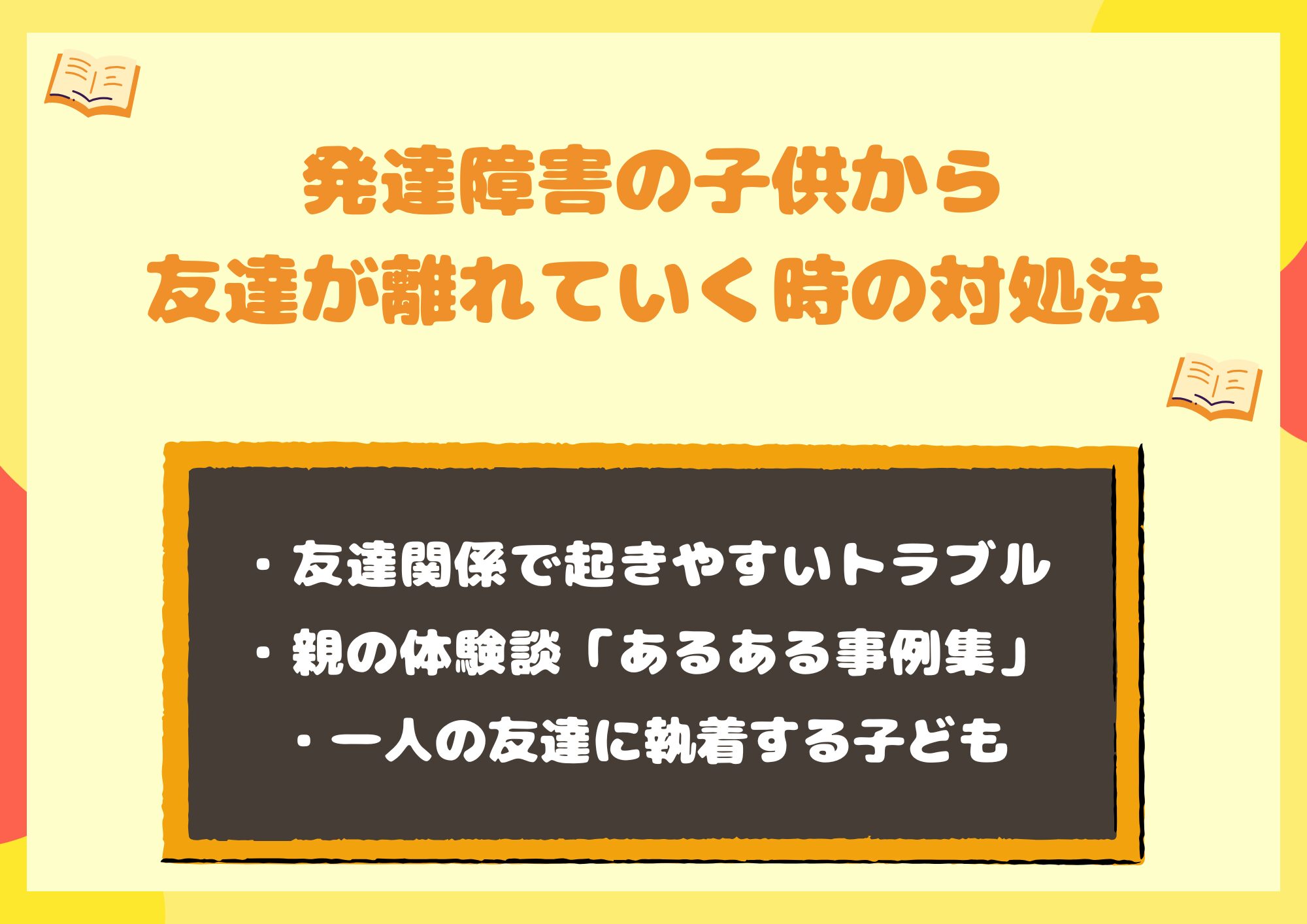
発達障害のある子どもが友達から距離を置かれてしまう。親として非常につらく感じる経験です。
「また一人で遊んでいる」「友達に避けられているみたい」という場面を目にするたび、心が痛むことでしょう。特に「距離が近すぎる」「一人の友達に執着してしまう」といった行動は、本人に悪気がないだけに対応に悩みます。
しかし、適切な支援と練習を積み重ねることで、友達関係が改善していく可能性が高まります。
この記事では、発達障害のある子どもが友達と良い関係を築くための具体的な方法をご紹介します。家庭でできる支援から学校との連携方法まで、今日から実践できる内容を詳しく解説していきます。
ランナーの無料体験はこちら!目次
発達障害がある子どもの友達関係で起きやすいトラブルの背景「親が知っておくと安心」
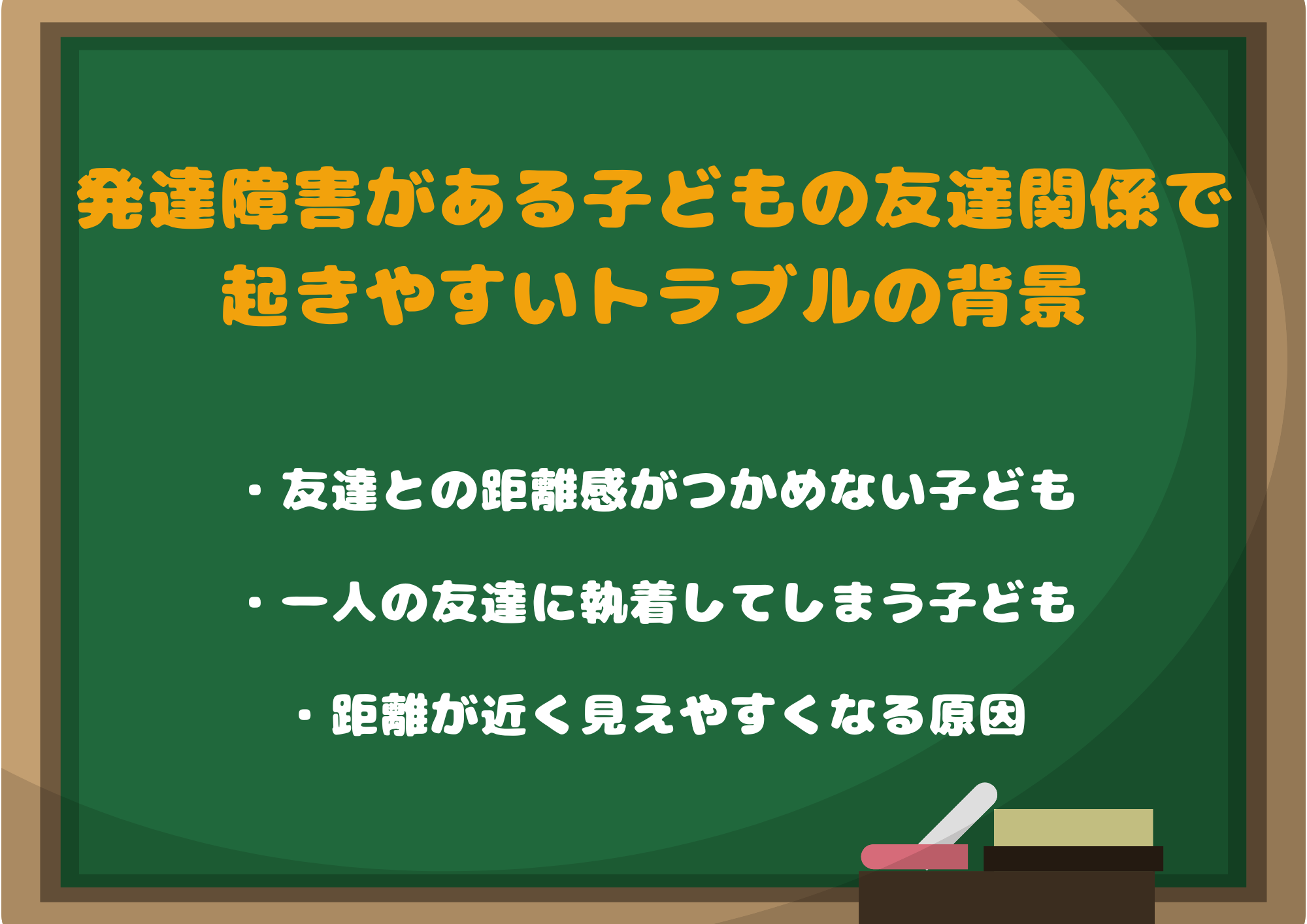
発達障害のある子どもが友達関係でつまずく背景には、脳や感覚処理の特性による情報処理の違いが一因となる場合があります。
これは決して「わがまま」や「性格の問題」ではなく、見えない部分での困難さが原因となっています。親御さんがこの背景を理解することで、子どもへの接し方が変わり、適切な支援につながります。
発達障害の特性を「困った行動」ではなく「支援が必要なサイン」として捉えることが、改善への第一歩です。
以下、具体的な特徴と原因を見ていきましょう。
友達との距離感がつかめない子どもに見られる特徴的な行動パターン
- 物理的・心理的な距離を測ることが苦手な場合がある
- 非言語的な合図(表情・視線・声の強弱)の読み取りが難しい
- 相手の心地よい距離を推測することが困難なことがある
発達障害のある子どもは、相手との物理的・心理的な距離を測ることが苦手な場合があります。
例えば、話すときに顔を近づけすぎたり、相手が嫌がっているサインに気づかなかったりします。これは視覚的な情報処理や、非言語的な合図(表情・視線・声の強弱など)の読み取りが難しいことが原因です。
また、自分の感覚と他者の感覚が違うことを理解しにくいため、相手の心地よい距離を推測することが難しい時があります。
急にハグをしたり、肩を組んだりする行動も、本人にとっては親しみの表現ですが、相手には「距離が近すぎる」と感じられてしまいます。こうした行動パターンを把握することで、具体的な練習方法が見えてきます。
一人の友達に執着してしまう子どもの発達障害における心理的な理由
- 不安の高さと変化への苦手さから強い執着が生じる
- 自閉スペクトラム症(ASD)の特性でルーティンを好む傾向
- 新しい友達作りへの不安や関係性の変化が苦手
一人の友達への強い執着は、不安の高さと変化への苦手さから生じることが多いです。
発達障害のある子どもにとって、人間関係は予測が難しく不安を感じやすいものです。そのため、一度安心できる関係を見つけると、その友達だけに頼ってしまいます。
また、自閉スペクトラム症(ASD)の特性がある子どもは、ルーティンや決まったパターンを好むため、「いつも同じ友達と遊ぶ」という行動が安心感をもたらします。
個人差がありますが、新しい友達を作ることへの不安や、関係性の変化を受け入れることの難しさも、執着を強める要因となっています。
この心理を理解することで、関係を尊重しつつ、徐々に関係の幅を広げる支援ができます。
距離が近く見えやすくなる原因と感覚処理の特性
- 感覚統合の課題が影響する場合がある
- 固有受容感覚(深部感覚)の特性により境界線が曖昧になりやすい
- 相手の嫌がるサインを読み取ることが難しい
発達障害のある子どもが距離感を適切に保てない背景には、感覚統合の課題が影響する場合があります。
固有受容感覚(深部感覚)などの感覚処理の特性により、自分と他者の境界線が曖昧になりやすいことがあります。また、触覚が鈍感な子どもは、強い刺激を求めて相手に近づきすぎてしまうこともあります。
脳の特性による感覚の違いを理解し、視覚的な支援や具体的なルールで補うことが効果的です。
さらに、相手の表情や声のトーンから「嫌がっている」というサインを読み取ることが難しいため、相手が離れようとするまで気づきにくい場合があります。
友達が離れていく発達障害のある子どもによくある場面と親の体験談
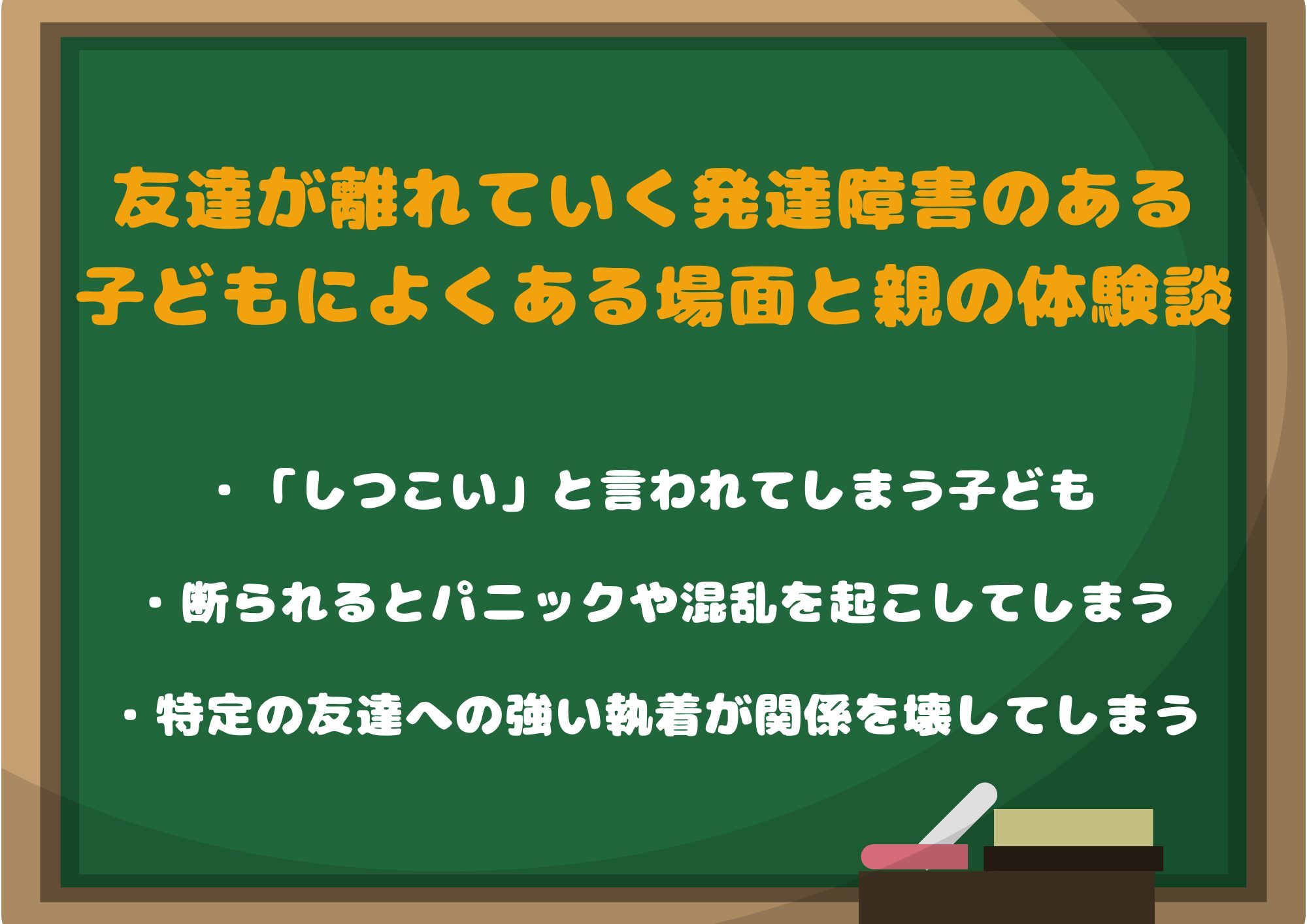
実際に多くの親御さんが経験している場面を共有することで、同様の悩みを抱える家庭が多いことを知る安心感を持っていただきたいです。
同じような悩みを抱える家庭は多く、それぞれが試行錯誤しながら改善への道を歩んでいます。以下の事例を参考に、お子さんの行動パターンを客観的に見つめ直してみましょう。
「しつこい」「ベタベタする」と言われてしまう子どもの具体的な行動例
- 同一話題の反復、会話への割り込みなどが見られる
- 特定の友達を過度に探索し、何度も誘い続ける
- 過度な身体接触で相手の負担感を生んでしまう
よくある行動として、以下のような例があります。①同一話題の反復、②会話への割り込み、③特定の友達の過度な探索、④過度な身体接触などです。
例えば、休み時間のたびに特定の友達を探し回り、「一緒に遊ぼう」と何度も誘い続ける姿が見られます。断られても「なんで?」「いつなら遊べる?」と質問を続け、相手を困らせてしまうこともあります。
また、身体的な接触も多く、手をつなぎたがる、腕を組む、後ろから抱きつくなどの行動が「過度な身体接触」と受け取られてしまいます。
これらの行動は愛情表現や不安の裏返しであることを理解しつつ、適切な表現方法を教えることが大切です。本人は友達と仲良くしたい一心での行動ですが、相手の負担感に配慮する練習を並行して行うことが重要です。
断られるとパニックや混乱を起こしてしまう場合の対処法
- 予想外の出来事への対応が苦手で強い混乱を示す
- 安全で静かな場所への移動と見守りが重要
- 事前の心の準備と代替案の用意が効果的
発達障害のある子どもは、予想外の出来事への対応が苦手なため、友達に断られると強い混乱を示すことがあります。
泣き出したり、怒ったり、その場から動けなくなったりするパニック状態は、本人にとっても辛い体験です。このような場合、まず安全で静かな場所に移動し、必要に応じて見守ることが重要です。
事前の対策として、「断られることもある」という心の準備をさせる練習が効果的です。
「もし断られたら、別の遊びをする」という代替案を複数の選択肢として用意しておき、視覚的にカードで示すと理解しやすくなります。また、深呼吸や数を数えるなどの落ち着く方法を普段から練習しておくことで、パニックの程度を軽減できます。
特定の友達への強い執着が関係を壊してしまうケースと予防策
- 執着が強すぎると相手が重荷に感じて距離を置く
- 複数の友達候補を作ることが重要
- ローテーション制やスケジュール表での管理が効果的
一人の友達に執着しすぎると、相手が重荷に感じて距離を置き始めることがあります。
実際に「〇〇ちゃんとしか遊びたくない」と言い続けた結果、その友達から避けられるようになったという体験談は少なくありません。執着が強まると、相手の選択を狭めてしまう行動(他の子と遊ぶのを妨げる等)も見られます。
予防策として、複数の友達候補を作ることが重要です。
「今日は〇〇ちゃん、明日は△△くん」というローテーション制を導入し、視覚的なスケジュール表で管理するのも取り入れやすい方法の一つです。また、一人遊びの時間も大切にし、友達に依存しない楽しみ方も身につけさせましょう。
一人の友達に執着する子どもへの家庭でできる支援方法「今日から始められる」
家庭での支援は、子どもが安心して練習できる環境を作ることから始まります。
学校では緊張してうまくできないことも、家族の場で練習すると心理的負担が軽くなる場合があります。以下の方法を参考に、お子さんのペースに合わせて少しずつ取り組んでみてください。
小さな達成経験を重ねることで、学校でも自然にできるようになっていきます。
距離感を視覚的に練習できるパーソナルスペースカードの作り方
- A4サイズの紙を4つに区切って相手別の距離を図示
- 色分け(緑・黄・赤)で距離感を視覚的に理解
- 毎日短時間の練習で徐々に定着(個人差あり)
パーソナルスペースカードは、相手との適切な距離を視覚的に理解するためのツールです。
A4サイズの紙を4つに区切り、それぞれ「家族」「友達」「先生」「知らない人」と書きます。各欄に、その相手との適切な距離を図で示し、「腕1本分」「机1つ分」など具体的な目安を記入します。
校内・屋外など状況別の例も追加すると効果的です。
カードには色分けも効果的で、緑(OK)、黄(注意)、赤(NG)で距離感を示すと理解しやすくなります。
実際に家族で練習する際は、床にテープで線を引いて距離を体感させましょう。毎日短時間の練習を継続すると徐々に定着しやすくなります(期間には個人差があります)。
執着を和らげる声かけのタイミングと具体的なフレーズ例
- 否定ではなく代替案を示すことがポイント
- 執着行動が始まる前の予防的な声かけが効果的
- 共感しながら社会のルールを教える
執着が見られたときの声かけは、否定ではなく代替案を示すことがポイントです。
「〇〇ちゃんばかりじゃダメ」ではなく、「〇〇ちゃんももしかしたら他の遊びがしたいかもしれないから、今日は△△をしてみよう」と提案します。タイミングは、執着行動が始まる前の予防的な声かけが効果的です。
朝の準備中に「今日は誰と遊ぶ?3人の名前を考えてみよう」と選択肢を広げる声かけをします。
また、「〇〇ちゃんが忙しそうだったら、一人で本を読むのもいいね」と、一人の時間も価値があることを伝えます。執着行動が出た後は、「気持ちはわかるけど、友達も選ぶ権利があるんだよ」と共感しながら社会のルールを教えていきます。
学校との連携で友達関係をサポートする際の相談ポイント
- 具体的な支援方法を連絡帳に記載して共有
- 子どもの支援シートを作成して面談で活用
- 月1回は定期的な情報交換の機会を作る
学校との連携では、具体的な支援方法を共有することが成功の鍵となります。
連絡帳に「対人距離の練習をしています。腕1本分の距離を意識できるよう支援いただけると助かります」と具体的に記載します。また、「3回ルール(誘いは3回まで)を家庭で練習中です」と伝えることで、学校でも同じ対応をしてもらえます。
面談では、子どもの支援シートを作成して持参すると効果的です。
「得意なこと」「苦手なこと」「パニック時の対応」を1枚にまとめ、担任と支援の方向性を共有しましょう。定期的な情報交換も大切で、月1回は子どもの様子を報告し合う機会を作ることをお勧めします。
発達障害で距離が近い子どもへの実践的なトレーニング「成功体験を積む方法」
距離感の改善には、具体的で繰り返し可能なトレーニングが不可欠です。
ここでご紹介する方法は、療育の現場で用いられることのある効果的なアプローチです。お子さんの理解度に合わせて、スモールステップで進めていきましょう。
小さな成功を褒めることで、自信とやる気が育ちます。
OK行動とNG行動を整理したリストの活用で適切な関わり方を身につける
- 具体的な行動を絵カードと文字で示す
- NG行動には必ず代替案をセットで教える
- 練習時の即時の称賛やフィードバックが効果的
OK行動リストの作成方法と使い方
OK行動リストは、友達との適切な関わり方を明確にする重要なツールです。
「挨拶をする」「名前を呼んでから話しかける」「順番を守る」など、具体的な行動を絵カードと文字で示します。このリストは子どもと一緒に作ることで、理解と納得が深まります。
NG行動への代替案の提示
NG行動には必ず代替案をセットで教えます。
「急に抱きつく→声をかけてハイタッチ」「何度も同じ話をする→3回までと決める」など、具体的な置き換え行動を示します。図やアイコンで示し、練習時には即時の称賛やフィードバックが効果的です。
「3回ルール」やタイマーを使った誘い方の練習で自己コントロール力を育てる
- 同じ相手への誘いを3回までに制限する方法
- 状況や相手により柔軟に調整することも大切
- タイマーで時間管理し会話のやり取りを身につける
3回ルールの導入手順
3回ルールは、同じ相手への誘いを3回までに制限する方法です。
指を使って数えながら誘い、3回断られたら「また今度ね」と言って他の活動に移ります。最初は親が一緒に数え、徐々に自分でカウントできるように練習します。
ただし、状況や相手により柔軟に調整することも大切です。
タイマーを活用した時間管理
タイマーは話す時間や遊ぶ時間を区切るのに有効です。
短時間(例:3〜5分)のタイマーをセットし、その間だけ好きな話をしていいというルールを作ります。タイマーが鳴ったら相手の話を聞く番、という交代制にすることで、会話のやり取りが身につきます。
断られた後の気持ちの切り替え方と次の行動リストの準備
- 感情メーターで感情を可視化して対処法を決める
- 断られた後の選択肢を3つ書いたカードを携帯
- 耐久性のあるカードでポケットサイズにする
感情の可視化と対処法
断られたときの感情を「感情メーター」で可視化します。
数値が高いときは深呼吸、中程度なら好きな歌を歌う、低いときはすぐ次の活動へ、というように対処法を決めておきます。感情に名前をつけることで、コントロールしやすくなります。
次の行動リストの携帯方法
断られた後の選択肢を3つ書いたカードを常に持たせます。
「本を読む」「絵を描く」「他の友達を探す」など、一人でもできる活動と他者との活動をバランスよく含めます。カードは耐久性のあるカードにして、ポケットに入るサイズにすると使いやすいです。
友達への執着を分散させる遊びの選択肢と興味の広げ方「関係の幅を増やす」
執着を減らすには、興味や楽しみの対象を増やすことが効果的です。
一つのことに集中しやすい発達障害の特性を活かしながら、少しずつ興味の幅を広げていきます。新しい活動への不安を減らし、「楽しそう」と思えるような導入が大切です。
以下の方法で、無理なく関係性の幅を広げていきましょう。
複数の遊びリストを作って執着対象を増やすアイディア集
- 運動系・創作系・ゲーム系に分類して作成
- 得意な要素を含む遊びから導入する
- 定期的に新しい遊びに挑戦して選択肢を増やす
遊びリストは、子どもの興味に応じて「運動系」「創作系」「ゲーム系」に分類して作成します。
各カテゴリーに5つずつ活動を入れ、写真や絵で視覚的に示します。例えば運動系なら「鬼ごっこ」「ドッジボール」「なわとび」など、一人でも複数でもできる活動を混ぜます。
新しい遊びを導入する際は、得意な要素を含めることがポイントです。
数字が好きな子なら点数制のゲーム、絵が好きな子なら創作要素のある遊びから始めます。定期的に新しい遊びに挑戦し、気に入ったものをリストに追加していくことで、自然に選択肢が増えていきます。
ソーシャルストーリーやロールプレイで友達付き合いを予習する方法
- 社会的な場面を物語形式で説明する
- 家族で実際の場面を演じて練習する
- 様々な反応を演じることで対応の幅を広げる
ソーシャルストーリーは、社会的な場面を物語形式で説明する方法です。
「友達が他の子と遊んでいるとき」という場面を、主人公の気持ちと適切な行動を含めて物語にします。「太郎くんは、花子ちゃんが別の友達と遊んでいるのを見ました。少し寂しかったけど、『また後でね』と言って、図書室で本を読みました」のような内容です。
ロールプレイでは、実際の場面を家族で演じて練習します。
親が友達役になり、様々な反応(快く受け入れる、断る、条件付きでOK)を演じることで、対応の幅が広がります。成功したら大げさに褒め、うまくいかないときも振り返りを行い、「もう一回やってみよう」と励まします。
小さな成功体験の積み重ねで自己肯定感を高めるステップ
- 成功体験をできるだけ細分化して設定
- 成功ノートで毎日1つできたことを記録
- 段階的な目標設定で達成感を共有
成功体験は、できるだけ細分化して設定します。
「友達と仲良く遊ぶ」という大きな目標ではなく、「挨拶ができた」「順番を守れた」という小さな成功を認めます。成功ノートを作り、毎日1つできたことを記録すると、進歩が見えやすくなります。
段階的な目標設定も重要で、最初は「5分間一緒に遊ぶ」から始めます。
それができたら10分、15分と延ばしていきます。一定回数成功したら(例:2〜3回)次のステップに進むという明確な基準を設けることで、子どもも親も達成感を共有できます。また、友達以外の場面(家族、先生)での成功も認めることで、全体的な自信につながります。
発達障害のある子どもの学習場面を支える家庭教師活用のポイント
発達障害のある子どもの友達関係の困りごとは、個別指導を通じて学習場面でのコミュニケーション練習の機会を設けることができます。
家庭教師サービスは、子どものペースに合わせた指導ができ、学習面での成功体験を通じて自信の形成を後押しできます。
発達障害に理解のある家庭教師を選ぶと、子どもの特性に配慮した指導につながります。
ここでは、地域またはオンラインで利用できる家庭教師サービスの特徴をご紹介します。
なお、学習支援で直接的な改善を保証するものではなく、対人トラブルが深刻な場合は学校・医療・福祉等の専門機関との連携が重要です。
家庭教師のランナー|発達障害の子どものコミュニケーションスキルを伸ばす個別指導の特徴

- 発達特性に関する研修・有資格スタッフによる社内支援体制
- 教材の強制販売は行わない運用
- オンライン指導にも対応
家庭教師のランナーでは、発達障害のある子どもへの指導体制を整えています。
発達障害コミュニケーション指導者の資格を持つスタッフが本部に在籍し、教師への研修・支援体制があります。
創業から20年以上、勉強が苦手な小中高生への指導実績があり、一人ひとりの個性に合わせたオーダーメイド指導を行っています。
講師選考から指導後のフォローまでの体制があり、子どもに合った教師を見つけやすい環境を整えています。オンライン指導にも対応しているため、対面での学習が苦手な子どもでも学習を継続しやすくなります。
ランナーの無料体験はこちら!家庭教師のトライ|発達障害の子どもの友達トラブルや対人関係サポートの取り組み

- 正社員の教育プランナーが担任として学習をサポート
- 理解の定着を狙う独自の学習メソッド
- トライのオンライン個別指導塾を利用可能
家庭教師のトライでは、登録教師約33万人から相性の良い教師を選べます。
正社員の教育プランナーが担任として家庭と教師をつなぎ、個別のカリキュラムで指導を行います。
完全マンツーマン指導で、理解の定着を狙う独自の学習メソッドを採用しています。創業から30年以上の実績があり、各都道府県の受験情報の蓄積があります。
教師との相性が合わない場合は、回数制限なし・無料で交代が可能です。トライのオンライン個別指導塾により、自宅で対面と同様の指導を受けることができます。
学研の家庭教師|発達障害の子どもに対応した友達との関わりを支援するサポート例

- 教育大手「学研グループ」が運営
- 約12万人の教師が登録
- 対面は地域限定、オンラインは全国対応
学研の家庭教師は、教育大手「学研グループ」が運営する家庭教師派遣サービスです。
大学生からプロ講師まで約12万人の教師が登録されており、お子様の学年・目的に応じて適した教師を紹介します。
対面指導は関東・東海・近畿などの地域で、オンライン指導は全国で対応しています。教師の採用・研修体制やサポートの仕組みが整っています。
中学受験から高校・大学受験まで幅広い入試対策の実績があります。オンライン指導では、自宅のPCやタブレットで全国どこからでも学研の教師による指導を受けることができます。
オンライン家庭教師マナリンク|発達障害の子ども向けの個別サポート内容
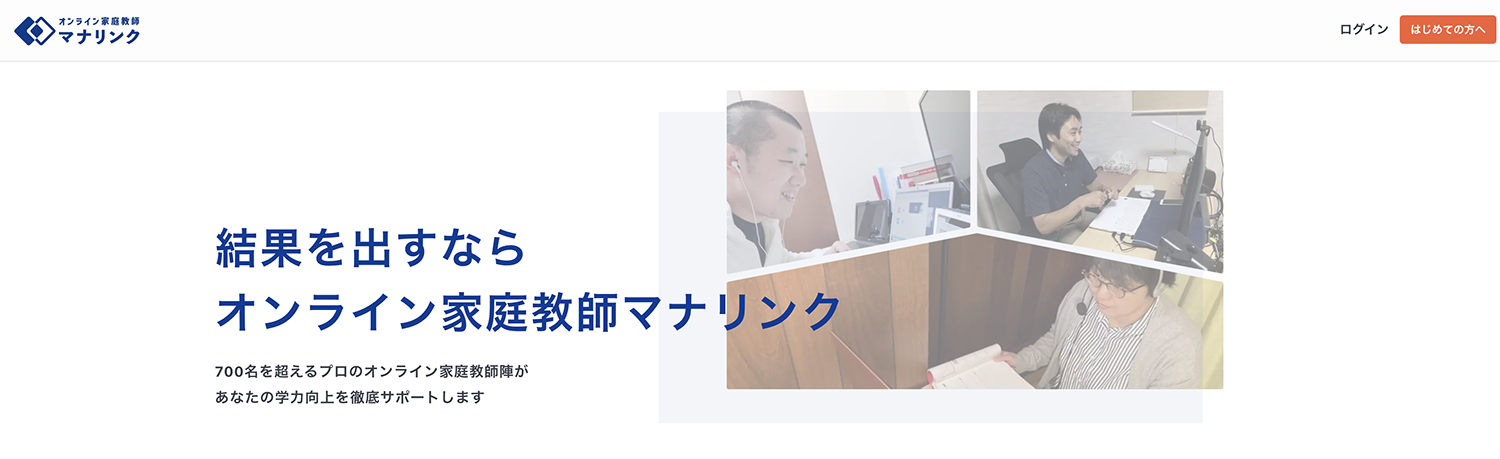
- 100%社会人の先生(塾講師や教員、有資格者など)
- 講師のプロフィール・動画・口コミを見比べて選択可能
- 専用アプリで相談・質問に対応
オンライン家庭教師マナリンクは、経験豊富なプロ講師のみが登録するマッチングプラットフォームです。
100%社会人の先生(塾講師や教員、有資格者など)が在籍しており、定期テストから受験対策まで幅広いニーズに対応します。
生徒と先生を直接つなぐ仕組みで、専用アプリ上で日程調整や質問対応ができます。サイト上で講師のプロフィール・動画・口コミを見比べて、自分に合ったプロ講師を指名できます。
講師とのやりとりは専用アプリで相談・質問ができ、個別のサポートを受けられます。初回に入会金19,800円(税込)が必要で、月額の基本料・管理費は不要、授業料を講師ごとに支払う方式です。
家庭教師のノーバス|発達障害の子どもの友達との距離感トレーニング支援

- グループで個別指導塾も運営
- 教師と学習プランナーのWサポート体制
- オンライン家庭教師ネッティーも提供
家庭教師のノーバスは、関東および東海に展開する家庭教師センターです。
大学生から社会人・プロ講師まで幅広い層の教師が在籍し、グループで個別指導塾も運営しているため受験情報や指導ノウハウの蓄積があります。
教師の指導力と本部スタッフによる「教師と学習プランナーのWサポート体制」で生徒を支えます。創業以来の指導実績から地域に根ざした受験情報があります。
オンライン家庭教師ネッティー(ノーバス運営)により、訪問と同様のサポートを受けることができます。高額教材のセット販売は行わず、手持ちの教材を活用した指導が可能です。
親のメンタルケアと専門機関との連携で孤立を防ぐ「一人で抱え込まない」
発達障害のある子どもを育てる親御さんは、周囲の理解を得られず孤独を感じることが多いです。
しかし、適切なサポートを受けることで、親子ともに前向きに歩んでいけます。自分を責めず、必要な支援を積極的に求めることが、結果的に子どものためにもなります。
罪悪感や焦りを和らげるセルフケアの方法と相談先リスト
- 発達障害は育て方の問題ではなく脳の特性
- 同じ悩みを持つ親の会への参加で心の負担軽減
- 定期的に自分の時間を作り趣味や休息に充てる
親の罪悪感は、「もっと早く気づいていれば」「私の育て方が悪かった」という思いから生まれます。
しかし、発達障害は育て方の問題ではなく、脳の特性によるものです。まず、この事実を受け入れ、自分を許すことから始めましょう。
セルフケアとして、同じ悩みを持つ親の会への参加をお勧めします。
各地に親の会があり、オンラインでの交流も増えています。経験を共有し、「うちもそうだった」という共感を得ることで、心の負担が軽減されることがあります。
また、定期的に自分の時間を作り、趣味や休息に充てることも大切です。
専門機関や支援団体とつながるメリットと連携のコツ
- 発達障害者支援センターなど様々な支援機関が利用可能
- 子どもの行動記録などを整理して伝えることが重要
- 医療・福祉・教育の各分野から総合的な支援を受ける
専門機関との連携は、客観的な視点と専門知識を得られる重要な機会です。
発達障害者支援センター、児童発達支援センター、教育相談所など、様々な支援機関があります。これらの機関では、子どもの特性評価や具体的な支援方法のアドバイスを受けられます。
連携のコツは、情報を整理して伝えることです。
子どもの行動記録、学校での様子、家庭での工夫などをメモにまとめて持参すると、的確なアドバイスを受けやすくなります。
また、状況に応じて複数の機関を併用されることもあり、医療、福祉、教育の各分野から総合的な支援を受けることで、より効果的な改善が期待できます。
発達障害のある子どもと友達関係についてのまとめ「希望を持って進む道筋」
- ・発達障害の特性による困難さは適切な理解と支援で改善が期待できる
- ・パーソナルスペースカードや3回ルールなどの具体的ツールを活用
- ・家庭・学校・専門機関との連携で総合的なサポートを受ける
- ・小さな達成経験を重ね、完璧を求めず一歩ずつ前進
- ・親のメンタルケアも重要で、同じ悩みを持つ仲間とつながる
発達障害のある子どもが友達から離れていく悩みは、適切な理解と支援によって改善が期待できます。
距離感がつかめない、一人の友達に執着してしまうといった行動は、脳の特性による困難さの表れであり、決して子どもの性格や親の育て方の問題ではありません。
この記事でご紹介した具体的な支援方法を、お子さんのペースに合わせて少しずつ実践してみてください。
パーソナルスペースカードや3回ルールなどのツールを使い、小さな達成経験を重ねることで、友達との適切な関わり方が身についていきます。大切なのは、完璧を求めず、一歩ずつ前進することです。
また、家庭だけで抱え込まず、学校や専門機関、家庭教師サービスなどの支援を積極的に活用しましょう。
特に私たち家庭教師のランナーのような発達障害に理解のあるサービスは、選択肢の一つになり得ます。親御さん自身のメンタルケアも忘れずに、同じ悩みを持つ仲間とつながることで、孤独感から解放されます。
友達関係の改善は一朝一夕にはいきませんが、適切な支援と愛情深い見守りがあれば、良い方向に向かう可能性が高まります。
今日できることから始めて、お子さんの笑顔が増える日々を目指していきましょう。
ランナーの無料体験はこちら!